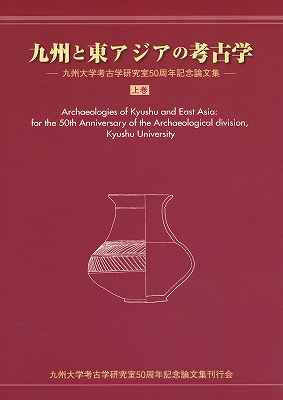|
|
《上 巻》【目 次】 □序―九州大学考古学研究室創立50年― □九州島嶼部における縄文土器の移動形態についての予察 ―五島列島出土縄文土器の岩石学的分析から―〔鐘ヶ江賢二〕 □弥生時代における木製農具の成立と東北アジアの磨製石器 〔宮本 一夫〕 □松菊里型住居の伝播とその背景〔端野晋平〕 □貯蔵穴の形態変遷を通してみた弥生時代集落の動向 ―三国丘陵遺跡群を題材として―〔杉本岳史〕 □韓国・勤島遺跡のアワビおこし〔武末純一〕 □甕棺製作におけるタタキ成形技法の意義 ―内面のアテ具痕についての新資料―〔橋口達也〕 □九州の弥生水田の立地と灌漑技術〔福田匡朗〕 □弥生時代墳墓出土土器からみる祭祀儀礼の変化〔高木暢亮〕 □弥生時代中期北部九州地域の区画墓の性格 ―浦江遺跡第5次調査区区画墓の意義を中心に―〔溝口孝司〕 □遣漢使節の道〔高倉洋彰〕 □九州大学筑紫地区出土巴形銅器鋳型の位置づけ ―巴形銅器の分類と製作技法の検討―〔田尻義了〕 □弥生時代抜歯風習の研究 ―北部九州・山口地方を中心として―〔舟橋京子〕 □弥生時代の生産と消費(覚) ―輝緑凝灰岩製石庖丁の場合を例に―〔中村修身〕 □中継地の形成 ―固城郡東外洞遺跡の検討を基に―〔寺井 誠〕 □弥生ガラスの考古学〔柳田康雄〕 □断体儀礼考〔田中良之〕 □三角縁盤龍鏡の系譜〔辻田淳一郎〕 □土器からみた古墳出現期の地域社会 ―山陰地方をケーススタディーとして―〔渡邊 誠〕 □装飾古墳における三角文の出現と展開 ―中・北部九州例を中心に―〔宇野愼敏〕 □西日本の島嶼部に立地する積石塚古墳の性格について 〔大西智和〕 □牛頸窯跡群と渡来人〔亀田修一〕 □北部九州における初期瓦生産と須恵器生産〔岡田裕之〕 □奈良県葛城市三ツ塚古墳群・古墓群の形成過程 ―古代氏族墓地の基礎的研究―〔小田裕樹〕 □陶(十瓶山)窯跡群における初期の瓦生産と讃岐国分寺瓦屋 〔渡部明夫〕 《下 巻》【目 次】━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □居住空間史としての大宰府条坊論〔中島恒次郎〕 □筑後国府の道路遺構〔神保公久〕 □古代住居の建替からみた居住集団 ―筑後川中流域の古代農村集落―〔小澤佳憲〕 □隅田八幡宮2号経塚出土小型海獣葡萄鏡について〔杉山 洋〕 □古琉球出土の元青花瓷の研究〔亀井明徳〕 □新安沈船に積載された金属工芸品 ―その性格と新安船の回航性をめぐって―〔久保智康〕 □中世日本の縁辺部における地域性 ―対馬・壱岐・五島・琉球の状況から―〔降矢哲男〕 □墨書宋人銘の書かれた経筒〔森井啓次〕 □首里城出土の鶴形水注 ―明代華南三彩陶の研究4―〔木村幾多郎〕 □緑釉耳付壷について〔東中川忠美〕 □薩摩焼窯神石塔小考〔渡辺芳郎〕 □福岡藩黒崎鋳銭場〔梅崎憲司〕 □狩猟採集社会の階層化について ―カナダ北西海岸民族誌モデルの再検討―〔石川 健〕 □考古学と社会学の交錯 ―和辻哲郎と「社会学的」考古学の成立をめぐって―〔山 泰幸〕 □欧米考古学における社会理論と北部九州の古墳時代研究 〔重藤輝行〕 □Old Hanziにおける甲骨文字符号化作業の問題点〔鈴木 敦〕 □宋明代の古鏡研究―青柳種信の参考にした漢籍―〔岡村秀典〕 □岡崎敬先生の先駆的イラン踏査 ―「岡崎フィールド・ノート」とその後の展開―〔大津忠彦〕 □中国先史時代の土製支脚〔今村佳子〕 □三里河遺跡大汶口文化墓葬について〔黄 建秋〕 □製作技術からみた戟国時代江漢地域出土青銅鼎 ―包山2号墓・天星観2号墓・望山1,2号墓出土青銅鼎の検討― 〔丹羽崇史〕 □中国初期王朝形成期中原地域における墓葬から見た社会の複雑化 に関する検討〔徳留大輔〕 □イスラエル ガリラヤ(キネレット)湖を中心とする漁撈活動の 歴史的 展開〔平川敬治〕 □オーストロネシア語族の研究から見た台湾と琉球の先史関係 〔陳 有貝〕 □ロシア共和国沿海州パルチザン区フロロフカ村シャイガ山城出土の 金代銅鏡について―金代東北流通史理解の一資料として―〔高橋学而〕 □フィジーにおける土器製作と製作具[中園 聡] |