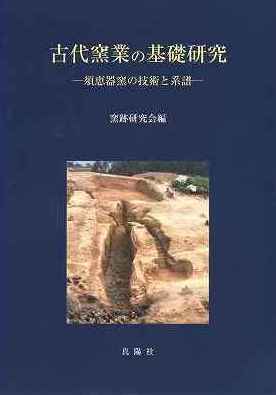|
|
【目 次】(〔 〕内は執筆者) 序 文〔森内秀造〕 論集作成における用語の統一について〔望月精司〕 第1部 総 論 第1章 窯からみた須恵器生産史〔藤原 学〕 第2章 須恵器窯の基本用語整理と構造分類 第1節 須恵器の窯式名称を巡って ―窖窯か登窯か―〔森内秀造〕 第2節 窯構造の分類〔森内秀造〕 第3節 窖窯構造をもつ須恵器窯跡の各部位構造とその 理解〔望月精司〕 <コラム>窯構造の判別方法〔浜中有紀〕 第2部 須恵器窯の技術 第1章 古代窯業技術の基礎ノート―窯焚き・築窯の経験 的知を読み解くために―〔余語琢磨〕 第2章 実験考古学から見た須恵器窯の築造と焼成2 ―実験考古学と民俗考古学―〔木立雅朗〕 第3章 遷りゆく窯―多面的な窯構造技術論と地域窯業の 多様性理解の試み―〔北野博司〕 第4章 須恵器窯の構築技術と補修技術 第1節 地下掘り抜き式窯〔望月精司〕 第2節 半地下天井架構式窯と地上窯体構築式窯の構築法 復元〔森内秀造〕 第3節 半地下天井架構式窯 ―関東・東北の事例から―〔利部 修〕 第3部 各地域の窯の様相 第 1章 古代須恵器生産における地域差とその意義 〔渥美賢吾〕 第 2章 伝来期の須恵器窯跡〔藤原 学〕 <コラム>初期須恵器窯跡から出土する軟質土器について 〔大坪州一郎〕 第 3章 九 州〔石木秀啓〕 第 4章 中国・四国〔池澤俊幸〕 第 5章 関 西〔牛谷好伸・浜中有紀〕 第 6章 陶 邑 窯 ―大阪府南部須恵器窯跡群の地域性―〔白石耕治〕 第 7章 東 海〔城ヶ谷和広〕 第 8章 甲 信 越〔山田真一〕 第 9章 北 陸〔望月精司〕 第10章 関 東〔渡辺 一〕 第11章 東 北〔菅原祥夫〕 第12章 溝付排煙口型窯の分布と系譜〔渥美賢吾〕 第13章 石組側壁窯の分布と系譜〔山田真一〕 第14章 下降傾斜燃焼部構造をもつ窯の分布と系譜 〔大橋(西田)由美子〕 第4部 窯業体制と生産組織 第1章 南比企窯と関東諸窯の生産史的検討 ―古代窯業生産の主体者像―〔渡辺 一〕 第2章 湖西窯産須恵器の流通〔後藤建一〕 第3章 北陸の古代土器生産と窯・工房・工人集落 〔望月精司・鹿島昌也〕 第4章 陶邑窯と畿内諸窯の検討〔千葉太朗〕 第5章 出雲・大井窯跡群の様相と生産体制試論 〔丹羽野裕・平石充〕 第6章 牛頸窯跡群の生産体制解明に向けて〔舟山良一〕 第7章 「陶部」・須恵器工人・家族〔岡田裕之〕 第8章 須恵器窯の構造と工人移動論〔菱田哲郎〕 第5部 窯跡研究の新視点 第1章 丹波・篠窯跡群の「小型窯」について ―窯構造をめぐる問題提起―〔木立雅朗〕 第2章 須恵器窯業の生態と社会―窯の分布論―〔北野博司〕 第3章 須恵器窯業での森林利用の一考察〔小林克也〕 第4章 須恵器大甕からみる古代の窯業生産 ―近畿地方を中心に―〔木村理恵〕 〈コラム〉須恵器大甕の容量〔和田達也〕 第5章 土器生産からみた特殊地域〔上村安生〕 ま と め 須恵器窯と技術、地域、社会〔菱田哲郎〕 付 録 移築や現地保存公開、復元実験している窯〔浜中有紀〕 窯跡研究会活動記録〔浜中有紀〕 執筆者名簿 あとがき〔舟山良一〕 |