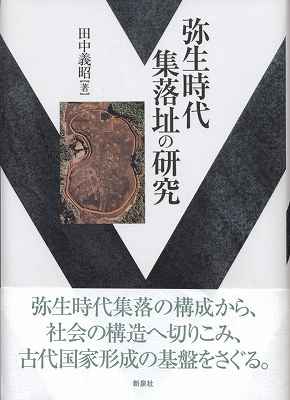|
|
●弥生時代集落の構成から、社会の構造へ切りこみ、古代国家形成 の基盤をさぐる。「南武蔵でおびただしい遺跡群の資料の検討から 導き出された拠点集落と周辺集落という類型、またそれらの結合形態 としての世帯共同体─農業共同体─政治的地域集団という地域社会 の重層構造が適応できることを示したことは、出雲地方の弥生時代 集落址研究に新たな地平を開くものと考えられる。さらに手工業生産、 鉄器流通のセンター、青銅器祭祀の祭祀権の掌握、大型首長墓の 造営等の諸属性が考えられる出雲の臨海性の拠点集落と、中国雲南 ・東南アジアの漢帝国周辺の「駅商国家」との比較を提言しているのも 注目される。」―甘粕 健(新潟大学名誉教授)「序文」より ●目次 序文 甘粕 健 第Ⅰ部 弥生時代集落址研究の目的と方法 第1章 弥生時代集落研究の道程 ―共生・協同の場とその動態を求めて 一 和島誠一に学ぶ 二 世帯共同体論と拠点集落の構想 三 古代出雲に政治的地域集団の具体像を見る 四 共同体論の今日的意義 第Ⅱ部 南関東における弥生時代集落址研究 第2章 南関東における農耕社会の成立をめぐる若干の問題 一 宮ノ台期における単位集落の構造と変遷 二 小地域における拠点と周辺 三 若干の考察 第3章 南関東における初期農耕集落の展開過程 一 分析の視点と方法 二 初期農耕集落の変遷過程 三 初期農耕集落の地域的展開 四 初期農耕集落展開の諸相 第Ⅲ部 出雲における弥生時代集落址研究 第4章 中海・宍道湖岸西部域における農耕社会の展開 一 歴史的舞台の形成 二 出雲平野における弥生集落群の展開 三 農業集団の構成とその性格 四 政治的広域集団 その成立と変遷 第5章 弥生時代拠点集落としての西川津遺跡 一 松江市西川津遺跡の概要 二 海崎地区と宮尾坪内地区 三 拠点集落としての西川津遺跡の検討課題 第Ⅳ部 弥生時代集落址研究の成果と課題 第6章 弥生時代拠点集落の再検討 一 神奈川県大塚遺跡とその周辺―拠点集落の諸様相(1) 二 島根県西川津遺跡―拠点集落の諸様相(2) 三 島根県四絡遺跡群―拠点集落の諸様相(3) 四 弥生時代拠点集落の特性 第7章 原史期集落の特性と類型 ―山陰地方の大規模集落遺跡を例として 一 原史期集落のモデル 二 山陰原史期拠点集落の諸例 三 大規模集落遺跡の類型的特徴 第Ⅴ部 生産・葬制・祭祀をめぐる問題 第8章 弥生時代以降の食料生産 一 水田農業の成立と展開 二 水田農業の諸画期 三 畑(畠)作と漁業の様相 四 食料生産における経営の二者 第9章 古代馬杷一試考 一 古代馬杷論小史 二 古代馬杷の実例 三 出土遺跡と馬杷の構造および年代・地域性 四 古代馬杷の意義 第10章 山陰地方における古代鉄生産の展開について 一 問題状況と課題認識 二 古代鉄生産関連遺跡の概要 三 古代鉄生産展開の諸段階 付 章1 銅鐸・銅剣・銅矛と古代出雲 一 荒神谷遺跡の構造と出土青銅器 二 青銅器の変遷と分布圏 三 荒神谷遺跡と出雲地方の弥生文化 付 章2 加茂岩倉遺跡の発見とその意義 一 加茂岩倉遺跡の構造と銅鐸の諸相 二 山陰地方の弥生青銅器と地域性 三 加茂岩倉・荒神谷両遺跡と古代出雲 参考文献/挿図等出典一覧 本書のなりたち 武井則道 |