|
|
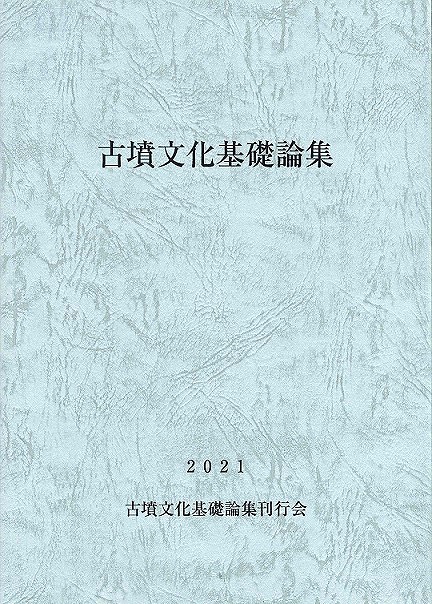
|
| 書籍番号 |
80853 |
| 書 名 |
古墳文化基礎論集 |
| シリーズ |
|
| データ |
B5 404頁 |
| ISBN/ISSN |
|
| 編 著 者 |
古墳文化基礎論集刊行会編集 |
| 出 版 年 |
2021年12月 |
| 出 版 者 |
古墳文化基礎論集刊行会 |
| 価 格 |
在庫切れ |
序 文
本書は、金属器および埴輪を中心とした古墳文化研究に関する
論文集である。
学史を紐解くと、金属器と埴輪の研究は主に1930年頃から進め
られ、現在の研究基盤を形成した古墳文化編年論の中核分野で
ある。その成果は古墳文化そのものを探究するための基礎に位置
づけられる基盤的論考として、現在でも繰り返し引用される重要
な研究が多い。また、本書に収められた各論文の執筆者は、近年
の当該分野における研究を牽引してきた中堅研究者を多数含んで
いる。これらの論文は、古墳文化の的確な先行研究を踏まえた
堅実な検証等が特色で、なかには将来的に古墳文化研究を推進
する論考もあると期待される。
一方で、各論文のテーマは執筆者の自由な創意や問題意識に
拠るため、体系性のある配置は行っていない。そこで、古墳文化
研究の大小テーマごとに収録する各論文を参照できるように項目
別の「参考・引用文献索引」を巻末に配置し、"逆引き事典"的な
機能をもたせたまとまりのある図書を目指した。
的確な引用はしばしば対象文献の学史的・学術的位置づけを
鮮明にする。ときに、書評や解題よりも雄弁であることは多くの
研究者が経験していることで、初学者にとっても最良の研究入門
の役割を果たすものであろう。
本書が、収録された各論文が挑んだテーマの分析と研究成果の
公開と共に、このような横断的・縦断的な視点で、学史を踏まえ
た古墳文化研究における各論文の位置づけと課題を浮かび上がら
せることができたとすれば望外である。
なお、このような構成と意図は、執筆者の一人で本論文集の
企画・編集の中心的役割を果たし、その最中に不治の病に倒れた
故阪口英毅さんとの打合時における本書のデザイン(構成)等の
意見を活かしたものである。本書をその霊前に捧げることをお許し
願いたい。
筆者を代表して 古谷 毅
……………………………………………………………………………
【目次】
「領域」が対峙する場所
─「下総型」埴輪と異系統埴輪の共存/対置─ ……犬木 努
朝倉地域西部の中期の埴輪工人
─ハケメの分析を中心に─ ………………井上義也
三角縁神獣鏡の成立
…………………………………………岩本 崇
古墳時代中期の北関東地域
─出入口・交通経路・鈴付馬具─
……………内山敏行
京築における鉄刀についての一考察─古墳時代における豊前
軍事組織解明に向けての基礎作業─
……………宇野愼敏
平城宮東院下層埴輪窯跡群の基礎的検討 …………………大澤正吾
小田原市天神山1号墳出土遺物の再検討
…………………太田雅晃
一須賀様式の単竜環頭と倭製双竜環頭
─二子塚古墳の双竜環頭は誰が作ったか─
……………大谷晃二
古墳時代の鶏 …………………………………………………賀来孝代
長野県大室古墳群大室谷支群168
号墳の埴輪
─積石塚古墳の埴輪とシナノの古墳時代中期─ ………風間栄一
小見真観寺古墳と柏木貨一郎
………………………………加藤一郎
東国における出現期の人物埴輪
……………………………加部二生
紀伊における家形埴輪(予察)
─紀伊風土記の丘万葉植物園出土資料の紹介─
………河内一浩
伝榛原町出土単鳳環頭大刀把頭をめぐる問題 ……………金 宇大
稲童15号墳出土方形板革綴短甲の再検討
…………………阪口英毅
播磨における竪穴式石槨の一様相
…………………………島田 拓
漁具副葬と海部
─島根県今浦横穴墓群の検討を中心に─
………………清水邦彦
頸甲に用いられた板金の板取り展開形状再論
……………杉井 健
石製模造品の研究視点について
─小林行雄の著述から─
…………………清喜裕二
鳥取県南部町・普段寺1号墳の合子形土器 ………………髙田健一
豊前豊後における埴輪の導入
………………………………田中裕介
円筒埴輪製作における「輪台技法」の再検討
─尾張・下原窯出土資料を手がかりにして─
…………辻川哲朗
古墳時代における双魚佩製作の
一様相─新出事例の分析を起点として─
………………土屋隆史
圭頭大刀の生産主体について
………………………………豊島直博
古墳副葬の石製祭器の意義
─大垣市矢道長塚古墳・昼飯大塚古墳・遊塚古墳からの解釈─
………中井正幸
東山窯成立に関わる系譜と編年の諸問題
…………………中里信之
古墳時代における甲冑副葬の意義
…………………………橋本達也
庄内川流域における渡来系集団の動静
─勝川遺跡(古墳群)から志段味古墳群へ─
…………早野浩二
「末期古墳」副葬矢の製作
…………………………………平林大樹
片流れ造り建物とその性格─踐祚大嘗祭式を敷衍して─ 穂積裕昌
九州における小札甲について
………………………………松﨑友理
博多遺跡群にみる古墳時代前期の鉄器生産の一様相
……水野敏典
飯塚市山王山古墳出土?形鏡板の再検討
─中国北朝系?轡馬装の影響をめぐって─
……………桃﨑祐輔
古墳の裾
………………………………………………………森下章司
挂甲武人埴輪を出土した前方後円墳の一例
─群馬県伊勢崎市安堀古墳表採の埴輪について─
……横澤真一
仕様と系列から後期型小札甲を考える …………………横須賀倫達
菅原東と新池
………………………………………………和田一之輔
金属器・埴輪研究の特質と展望(Ⅰ)
……………………古谷 毅
《文字化けを修正した目次は以下のURLからご覧いただけます(PDF)》
https://www.chugoku-shoten.com/mokuji/jmokuji/80853/80853.pdf
|
|