|
|
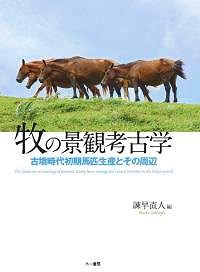
|
| 書籍番号 |
81421 |
| 書 名 |
牧の景観考古学 古墳時代初期馬匹生産とその周辺 |
| シリーズ |
|
| データ |
A4 379頁 (上製本) |
| ISBN/ISSN |
978-4864451642 |
| 編著者 |
諫早 直人編 |
| 出版年 |
2023年2月 |
| 出版者 |
六一書房 |
| 価 格 |
11,000円(税込) |
【内容紹介】
─────────────────────────────
四周を海に囲まれた日本列島に大量の家畜馬がもたらされ、定着
したのは古墳時代中期、およそ5世紀を前後する時期のことである。
以後、動力が機械化するまでの長い間、日本列島の歴史において、
馬はヒト・モノ・情報を運ぶ陸上最速の交通手段であり続けた。
その存在は、しばしば戦争の行方を左右し、農耕馬や駄馬として
人々の日常生活を助けることとなる。古墳時代は、その起点とな
った日本列島における畜力利用の開始期、導入期にあたる。
近年、発掘調査の蓄積とそれをふまえた馬そのもの(ウマ遺存体)
や馬具といった「モノ」の研究の急速な進展によって、文献史料に
は記されなかった日本列島における馬の本格的渡来(大量渡来)の
実態が明らかとなりつつある。しかしながら両者の研究からは、
いつ頃、どの地域で、どのような馬がどのように飼われ、どのよ
うに利用されたのか、それらの馬がどこから来たのかなどについ
ての手がかりは得られるが、馬がどのような場所で実際に飼われ
ていたのかや、牧はどこにあったのかといった具体的な「場」に
関する議論は、なかなか進んでいない。
日本列島で最初に営まれた牧はどのような景観だったのだろう
か。それはユーラシア大陸の牧や日本の古代以降の牧と、何が同
じで何が違ったのだろうか。
本書は、この素朴な問いの答えを求めて古代の馬研究会のメン
バーと進めてきた共同研究の成果を一書にまとめたものである。
主たるフィールドは、当時、河内湖北岸に位置した大阪府四條畷
市とその周辺。
第Ⅰ部では、文献史料にみえる「河内馬飼」によって営まれた
日本列島における最古の牧「河内の牧」があったと目されるこの
「場」に焦点をあてて、これまでも注目されてきたウマ遺存体や
馬具といった遺物だけでなく、遺構や遺跡空白地も含めた遺跡間
関係の動態を検討することで、馬を飼っていた集落やその周辺の
土地利用にまで議論を及ぼすことを試みた。第Ⅱ部では、異なる
フィールド、外からの視点で、河内湖北岸という「場」を相対化
するとともに、古墳時代牧研究に残された課題のあぶり出しを試
みた。
個々の論考が「景観」を真正面から論じているわけではないけ
れども、個々の論考で明らかとなった知見を紡ぎ合わせていくこ
とで、古墳時代初期牧景観の復元を目指した。我々の挑戦が成功
したかどうかは読者の判断に委ねるほかないが、本書を「牧の景
観考古学」と題した所以である。
─────────────────────────────
口絵
初夏の蔀屋北集落
(早川和子画)
晩冬の讃良の牧 (早川和子画)
さらら馬飼いの里 (佐野喜美画・栗山雅夫撮影)
蔀屋北遺跡遺構図
(宮崎泰史・松田篤作成)
蔀屋北遺跡周辺の地形と河内湖推定ライン
(井上智博作成)
目 次
総論
―牧の景観考古学事始め―……………………………諫早直人
1
1.古墳時代牧研究の現状と課題
1
2.河内の牧の考古学―研究のあゆみ 2
3.本書の構成
18
第Ⅰ部 河内湖北岸の初期馬匹生産とその周辺
河内平野北東部における弥生時代後期~古墳時代の地形変遷と
人間活動―放牧地の検討の前提として―
…………井上智博 27
1.はじめに―本稿の目的
27
2.河内平野北東部の地形形成過程
27
3.弥生時代後期から飛鳥時代における地形形成の背景
―降水量変動との関係
41
4.地形形成過程からみた古墳時代中・後期の生業システム研究
の課題 42
遺跡立地からみた放牧地
―讃良遺跡群の馬飼い―
……………………………實盛良彦 47
1.讃良遺跡群とは
47
2.讃良遺跡群の牧についての研究史
47
3.牧の要件と放牧地の認識 49
4.遺跡分布の様相と牧の範囲
51
5.遺跡分布から想定できる放牧地
52
6.まとめ―遺跡分布様相からみた讃良遺跡群馬飼い集団の組織53
蔀屋北遺跡と馬関連遺構について
………………宮崎泰史 61
1.はじめに
61
2.蔀屋北遺跡の馬 62
3.蔀屋北遺跡の馬関連遺構
62
4.おわりに 70
蔀屋北遺跡出土ウマ遺存体の新知見
…丸山真史・覚張隆史 73
1.はじめに
73
2.安定同位体比によって何がわかるか
73
3.蔀屋北遺跡から出土したウマ遺存体の概要と特徴
74
4.安定同位体比分析に用いた資料 74
5.安定同位体比測定の結果
77
6.ウマの飼育と管理に関する考察 80
7.まとめ
83
馬の医療と治療
―四條畷市奈良井遺跡出土結石の再発見― ………野島 稔
85
1.はじめに
85
2.「ベゾアール(結石)」シャルロット・デュマ展
85
3.奈良井遺跡の結石 87
4.結石について
90
5.まとめ 92
土器からみた河内湖北岸地域
………………… 中野 咲 95
1.はじめに
95
2.河内湖北岸の古墳時代中・後期土器の特質
―煮炊器を中心に
95
3.外来系土器について 99
4.おわりに―土器からみた河内湖北岸地域
110
蔀屋北遺跡で出土した製塩土器の意味 …………塚本浩司 117
1.はじめに
117
2.蔀屋北遺跡の製塩土器 117
3.日本列島での製塩の前提
118
4.コップ形製塩土器の用途 120
5.内陸の製塩の経済性
121
6.出土遺構 124
7.おわりに―焼塩とウマ
126
蔀屋北遺跡周辺の鍛冶とその特性 ………………真鍋成史 131
1.はじめに
131
2.蔀屋北遺跡周辺における金属製馬具生産について
131
3.大阪府・奈良県における金属製馬具出土鍛冶遺跡 139
4.考察
144
5.まとめ 146
仏教文化とその基盤からみた牧廃絶後の讃良地域 …新尺雅弘
151
1.はじめに 151
2.研究史と本論の視座
151
3.讃良地域における7世紀の仏教文化 153
4.讃良地域における仏教文化の基盤
162
5.おわりに 167
韓半島初期牧場に関する基礎的研究 …………李炫[女正]
173
1.研究の目的と課題 17
2.高麗・朝鮮時代における牧場研究の現況
174
3.高麗・朝鮮時代の牧場からみた韓半島初期の牧場 184
4.おわりに
191
第Ⅱ部 河内湖北岸の初期馬匹生産の歴史的意義を探る
同位体分析からみた馬の来歴と産地・消費地
―蔀屋北遺跡と東日本の比較―
………植月 学・丸山真史 195
1.はじめに
195
2.ウマ同位体分析の進展と問題の所在 195
3.東日本の馬生産地と消費地
196
4.おわりに 200
牧のある風景
―中国古代を手がかりに―
…………………………菊地大樹 203
1.はじめに 203
2.古典籍にみる牧
203
3.出土文字資料にみる牧 205
4.画像資料にみる牧
207
5.おわりに
207
古墳時代の牧,三国時代の牧
―朝鮮半島からのまなざし、朝鮮半島へのまなざし―
……………諫早直人 211
1.はじめに
211
2.朝鮮半島からのまなざし 212
3.朝鮮半島へのまなざし
213
4.おわりに
218
上毛野地域における馬の登場
―富岡市後賀中割遺跡7号墳の調査成果から―
…右島和夫 221
1.はじめに 221
2.後賀中割遺跡7号墳の基礎的検討
222
3.後賀中割遺跡の周辺の遺跡動向 225
4.5世紀における方墳とその意義
227
5.おわりに 230
ヤマト王権の馬匹生産戦略
―大和を起点に―
……………………………………青柳泰介 237
1.はじめに
237
2.大和の馬関連遺物の分布と変遷 237
3.手工業生産と馬
238
4.王権の馬匹生産戦略と「畿内」の南北差―王権による「畿内」
の構想と手工業生産拠点の配置 239
5.おわりに
241
淀川左岸の開発と5世紀の王権
―茨田堤を中心に― …………………………………菱田哲郎
243
1.はじめに 243
2.茨田堤の比定
243
3.遺跡からみた茨田堤の築堤時期 244
4.茨田屯倉と茨田郡域の開発
246
5.北河内の低地部と王権 247
6.おわりに
248
「河内の牧」研究の最新成果から …………… 千賀 久 253
1.はじめに
253
2.「河内の牧」・讃良遺跡群 253
3.「河内の牧」の馬飼集団
257
4.おわりに
259
附編 蔀屋北遺構の再検討
蔀屋北遺跡検出遺構の再検討
……………………… 青柳泰介・諫早直人・中野 咲・松田 篤
・宮崎泰史 261
1.はじめに 261
2.時期区分の提示
262
3.各時期の土器様相 269
4.蔀屋北遺跡検出遺構の再検討
278
5.おわりに
290
蔀屋北遺跡検出遺構一覧表
……………………… 青柳泰介・諫早直人・中野 咲・松田 篤
・宮崎泰史 293
総 括 ………………………………………………諫早直人
372
あとがき ……………………………………………………… 375
英文目次
……………………………………………………… 377
執筆者一覧
…………………………………………………… 379
コラム
さらら馬飼の里イラストを描いて
…………………佐野喜美 60
蔀屋北遺跡がみつかった頃
…………………………宮崎泰史 72
イラストは調査と絵のコラボレーション
…………野島 稔 94
馬を運んだ船 …………………………………………塚本浩司
130
蔀屋北遺跡の復元イラストを描く …………………早川和子
172
早川和子さんと復元画を描く(その1) ……………諫早直人
210
早川和子さんと復元画を描く(その2) ……………諫早直人
220
古代の馬研究会の活動について ……………………青柳泰介
252
|
|