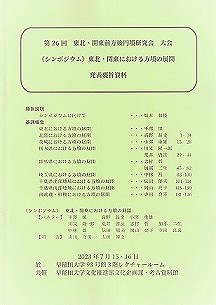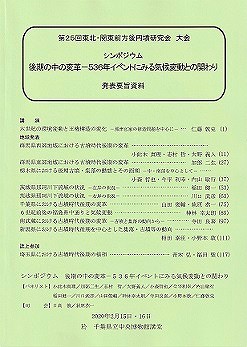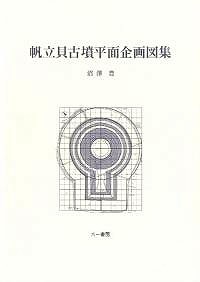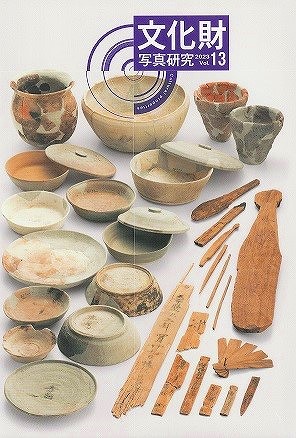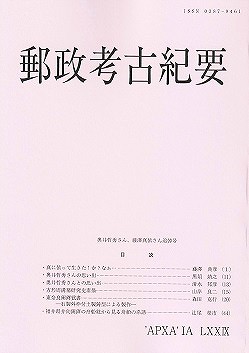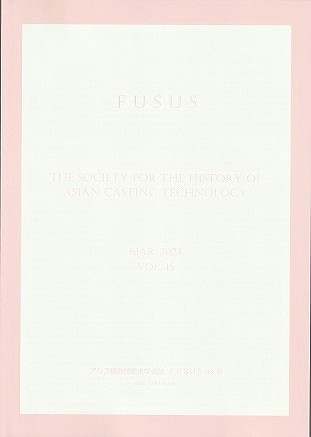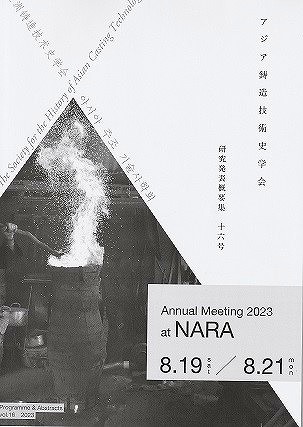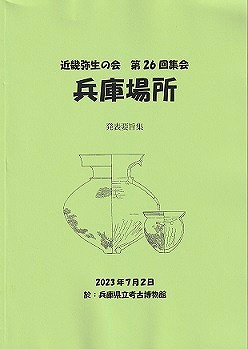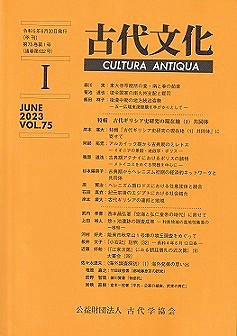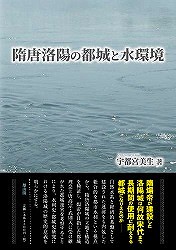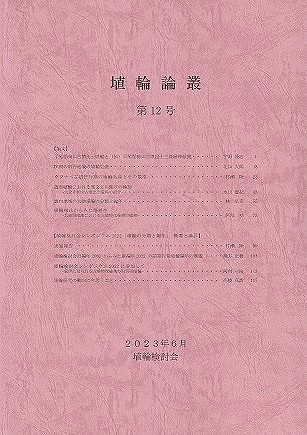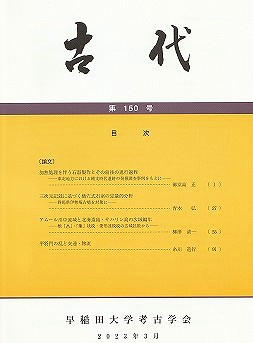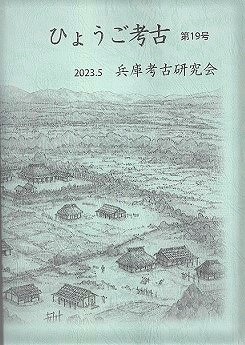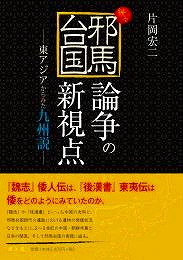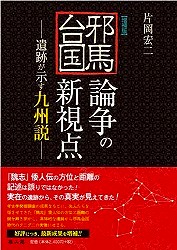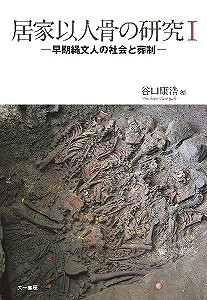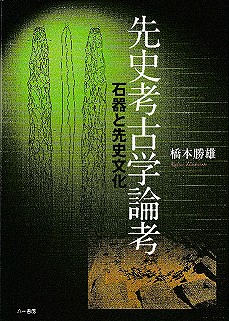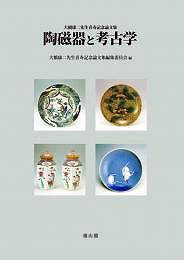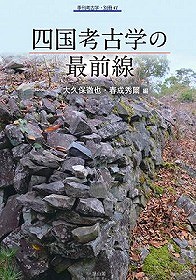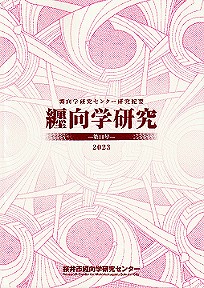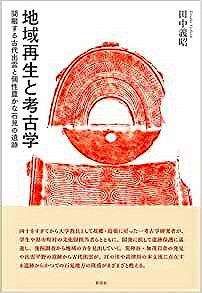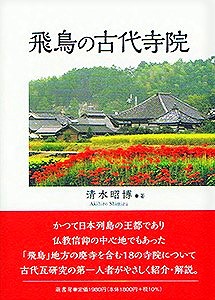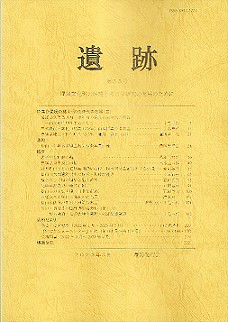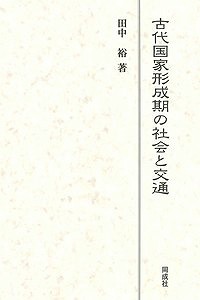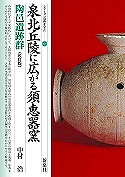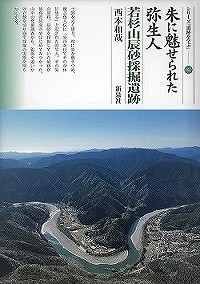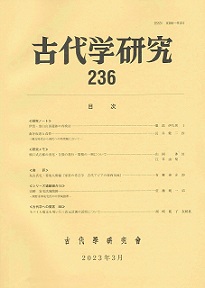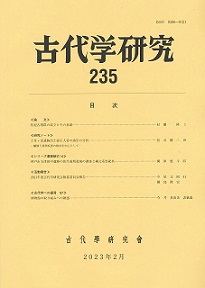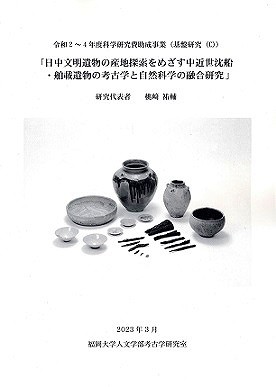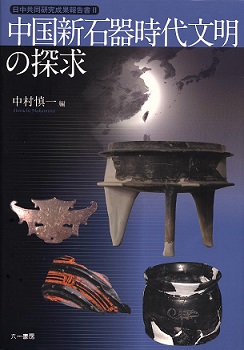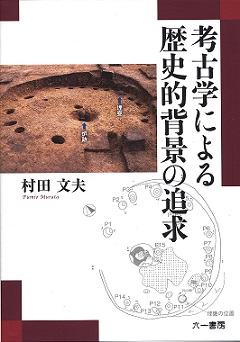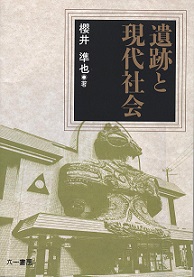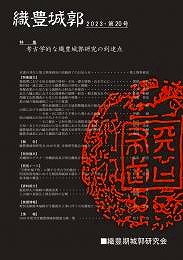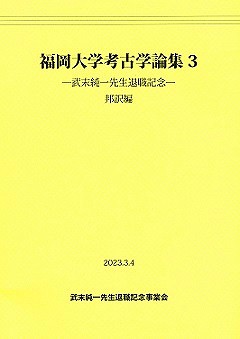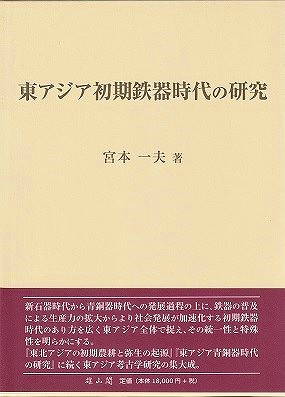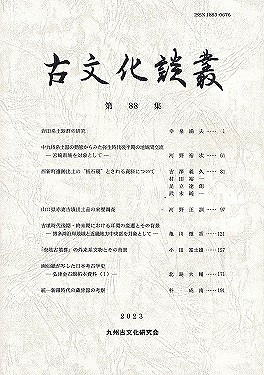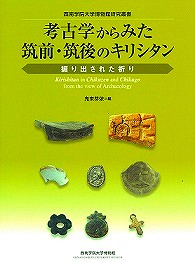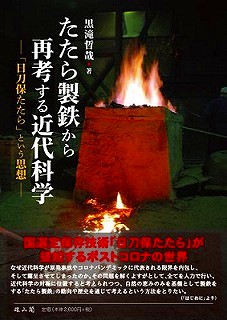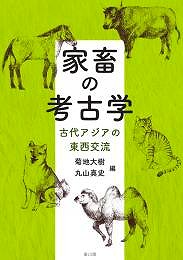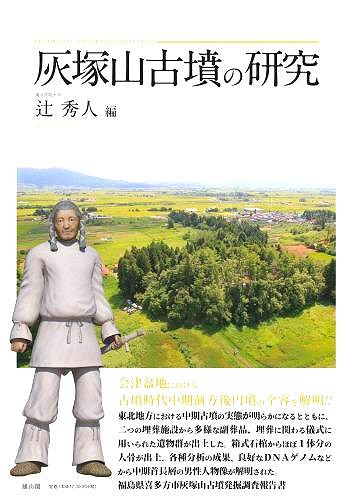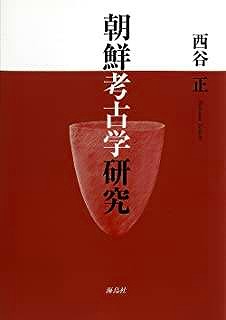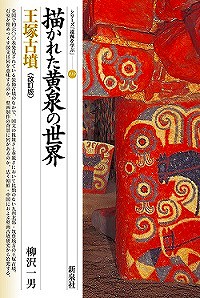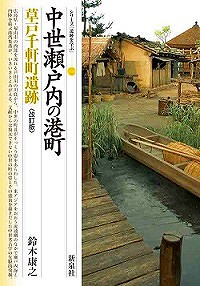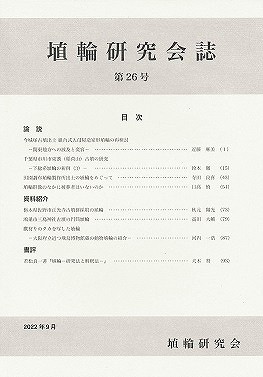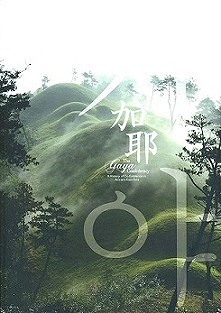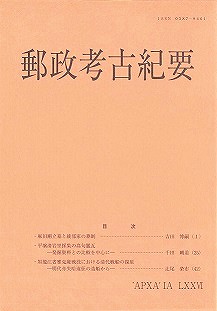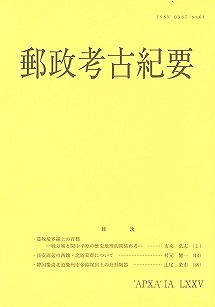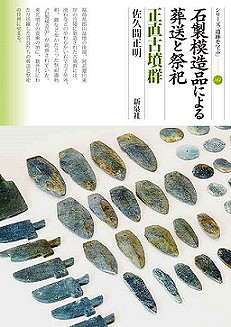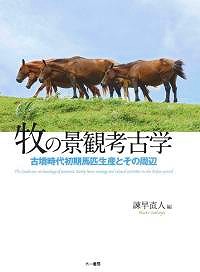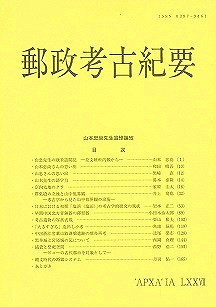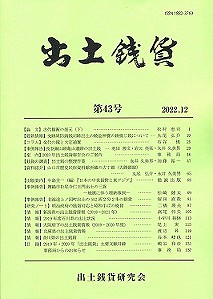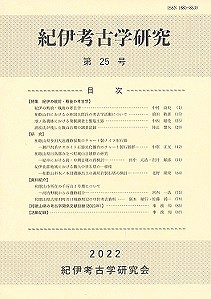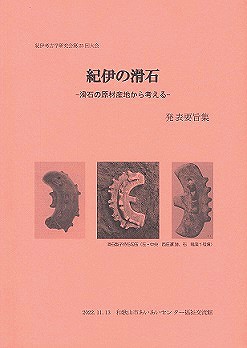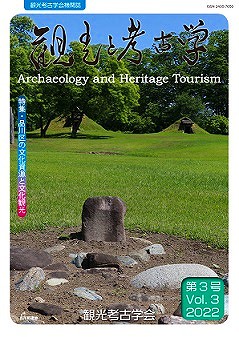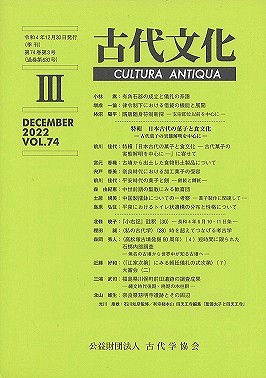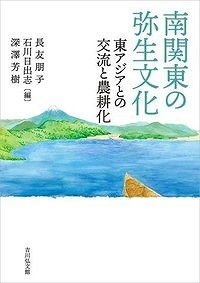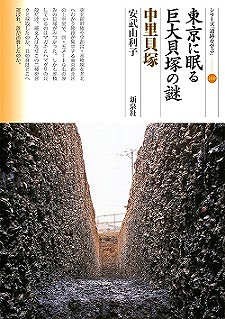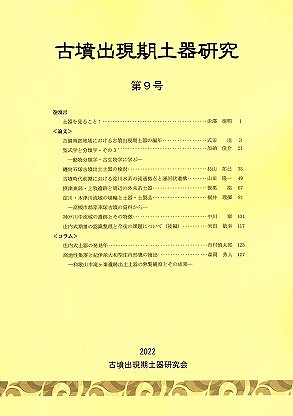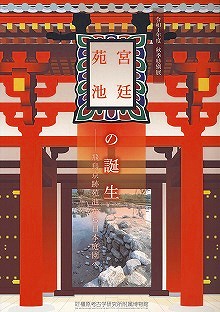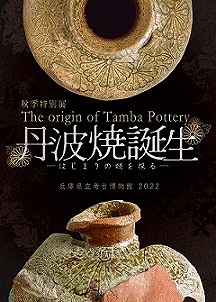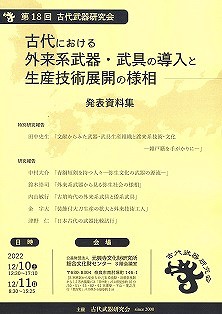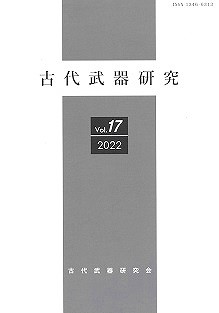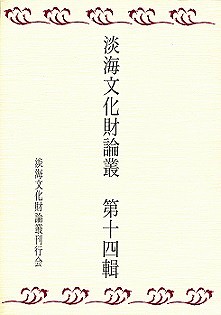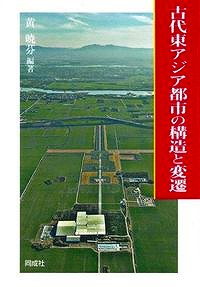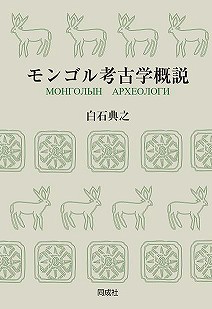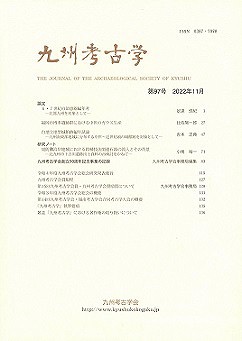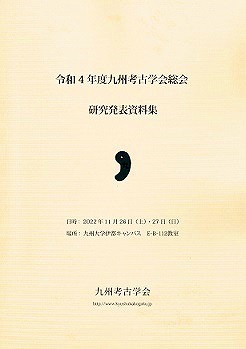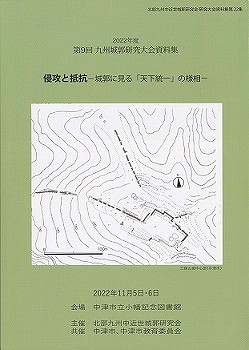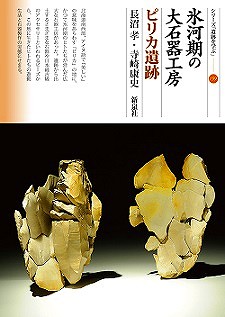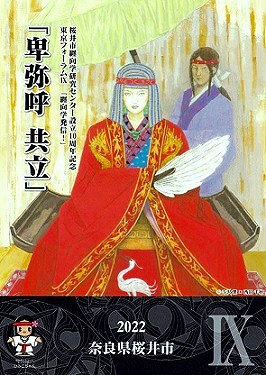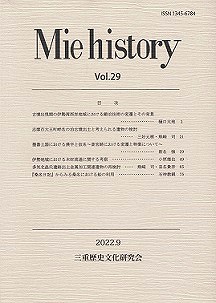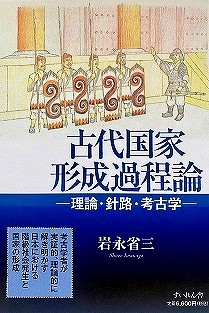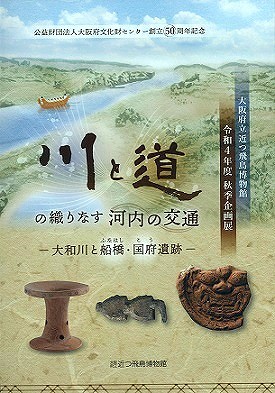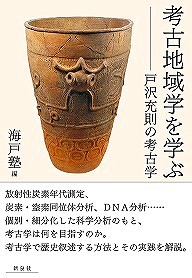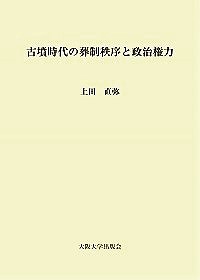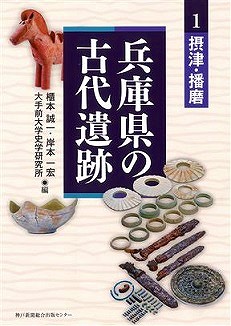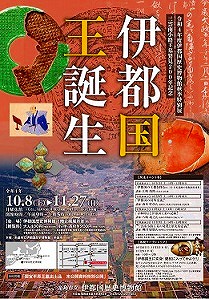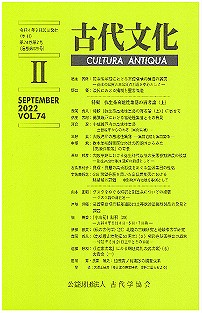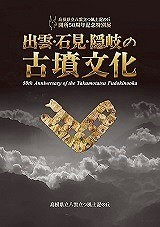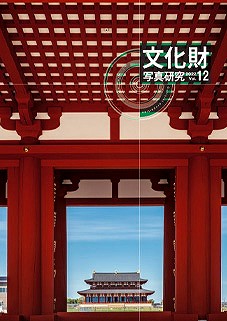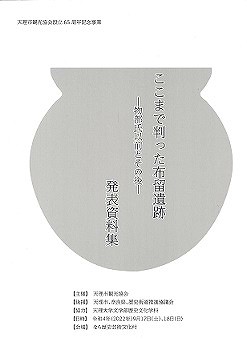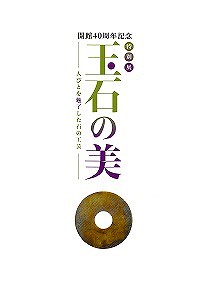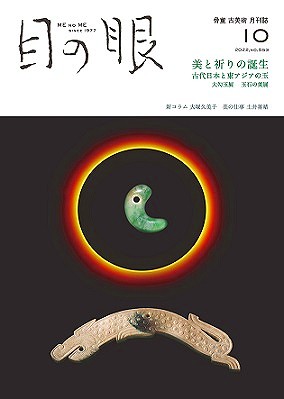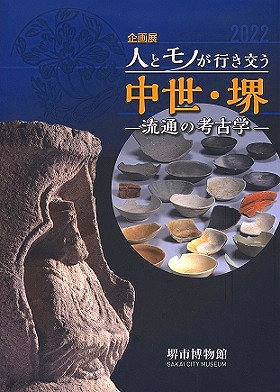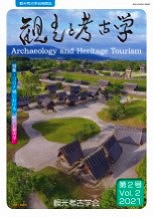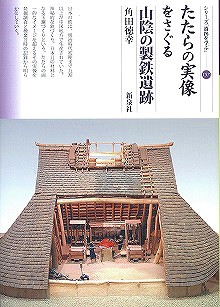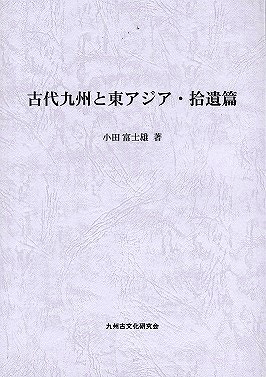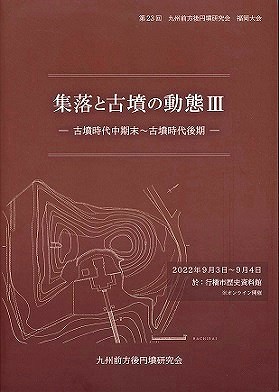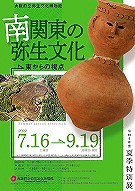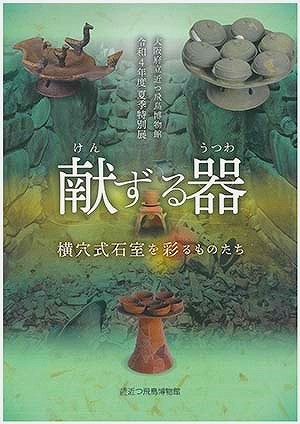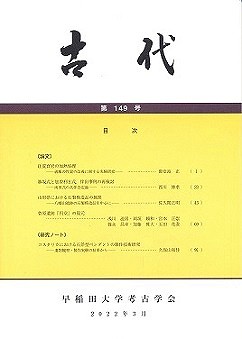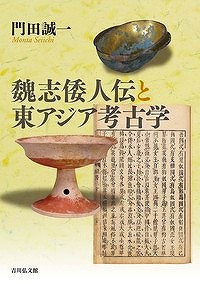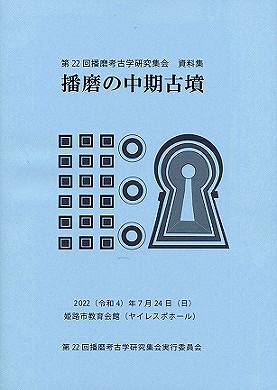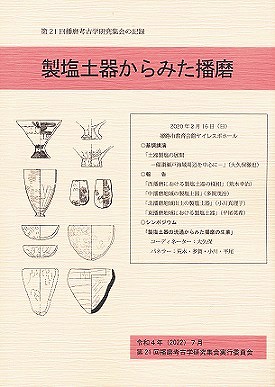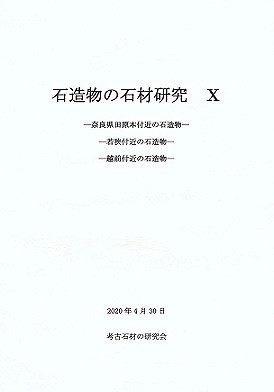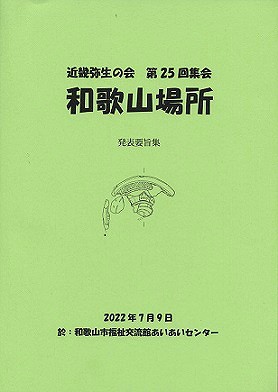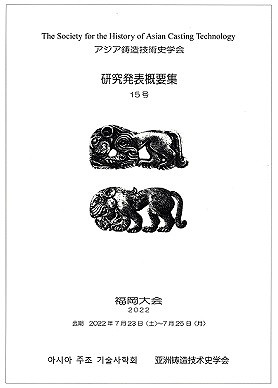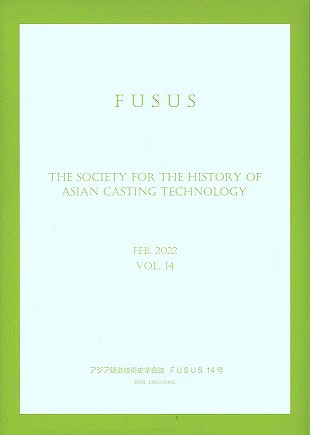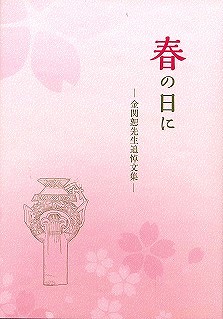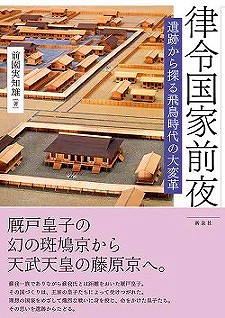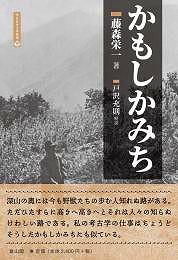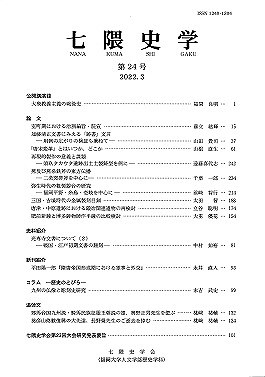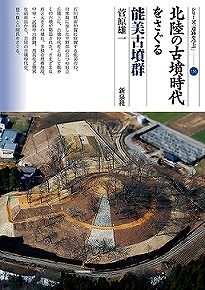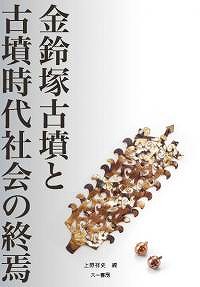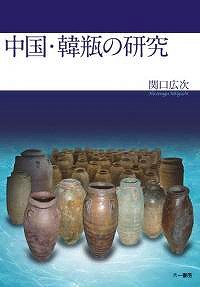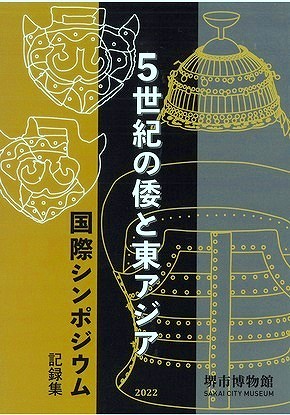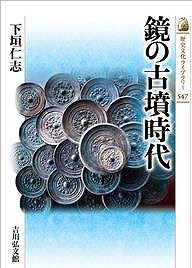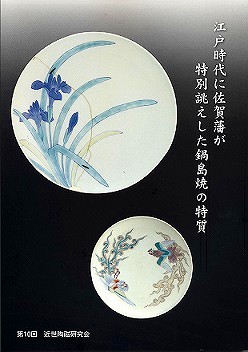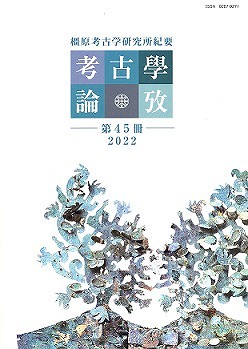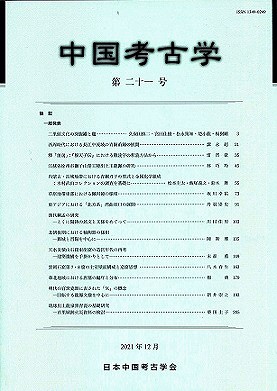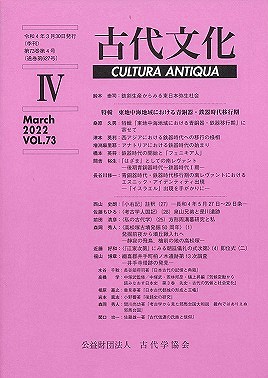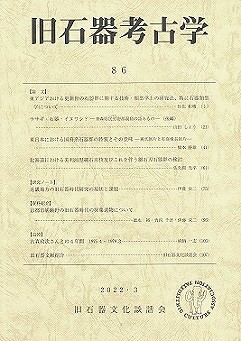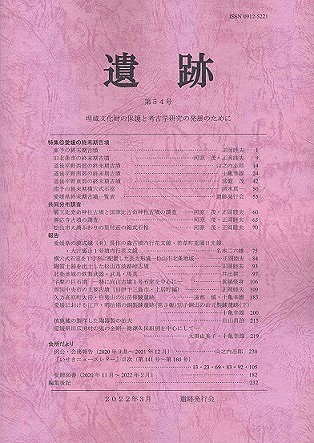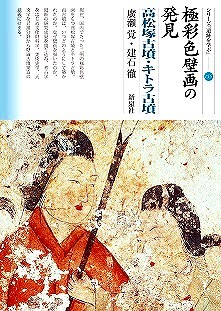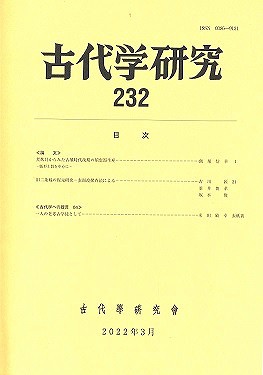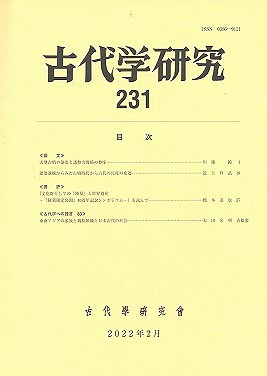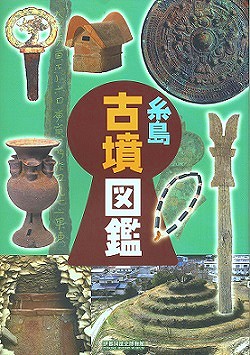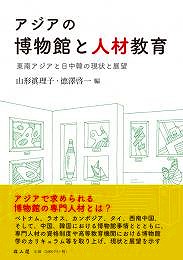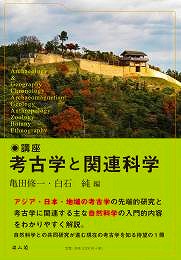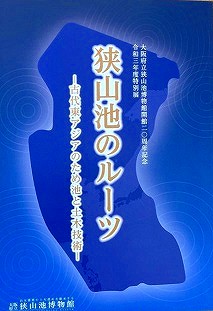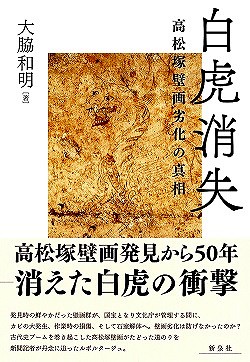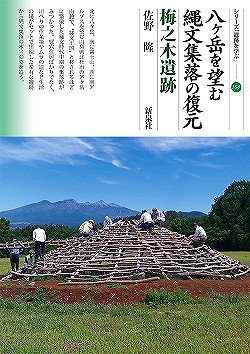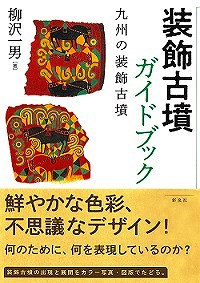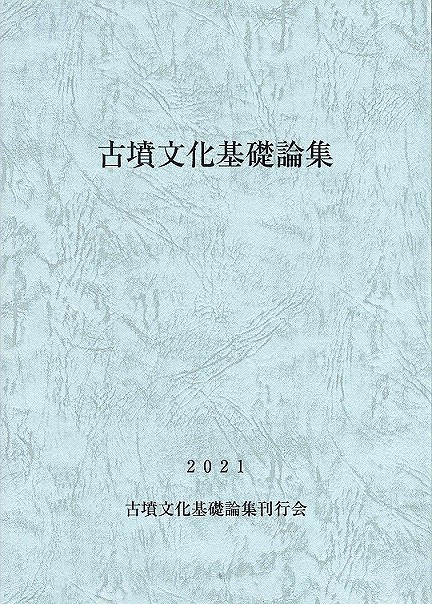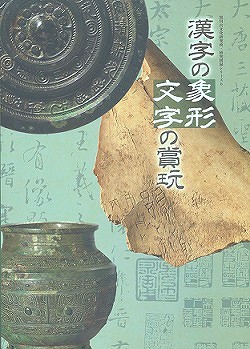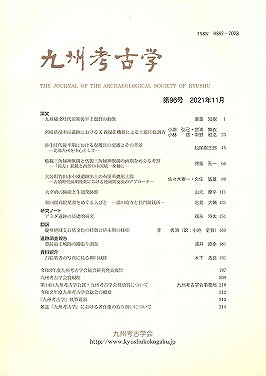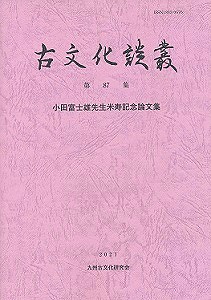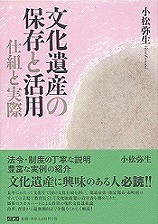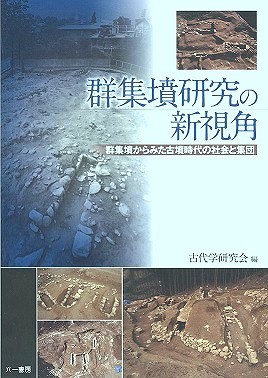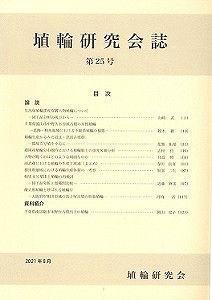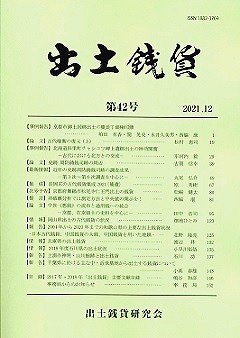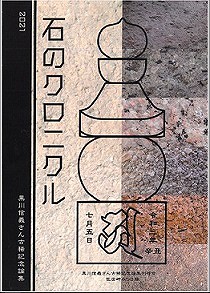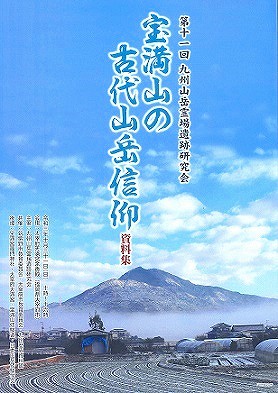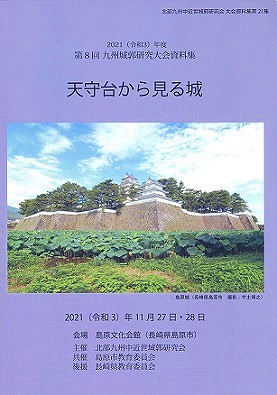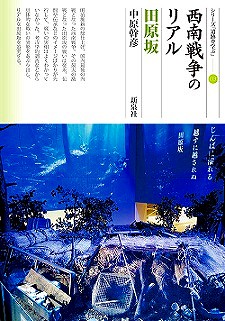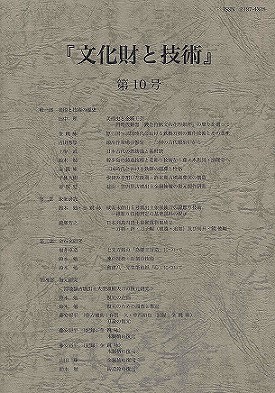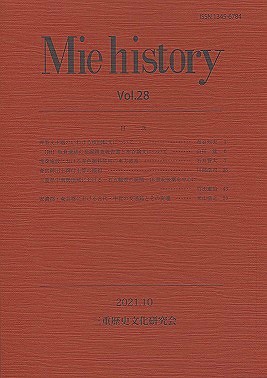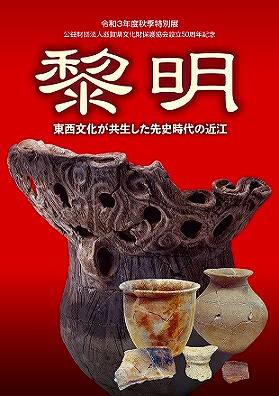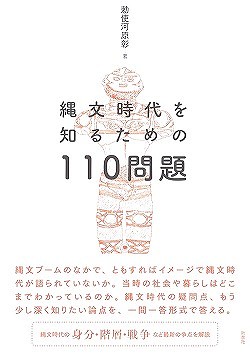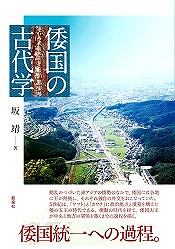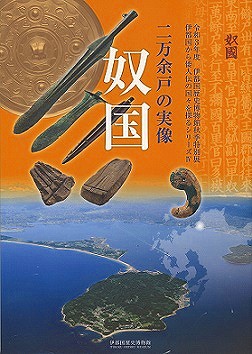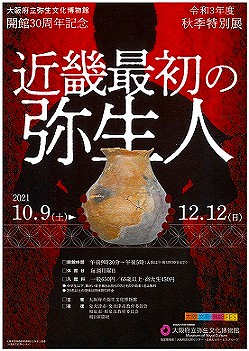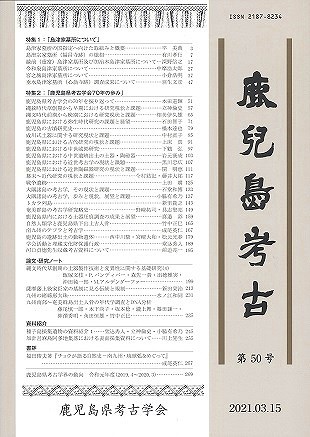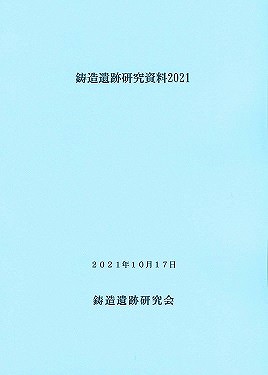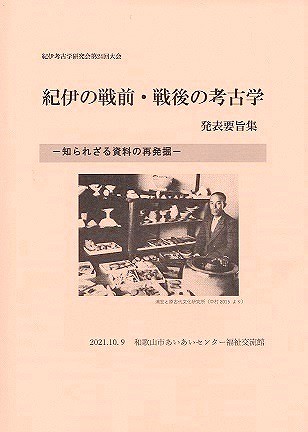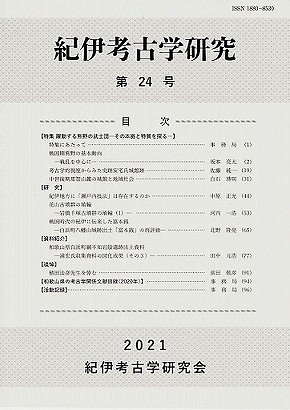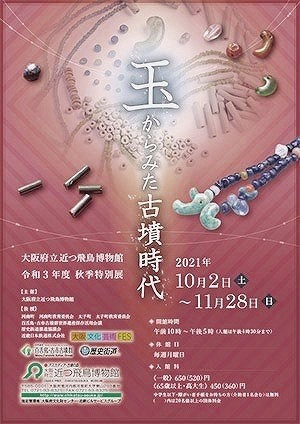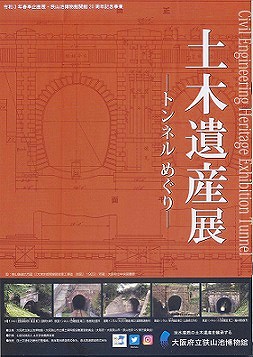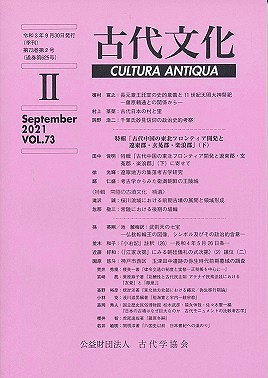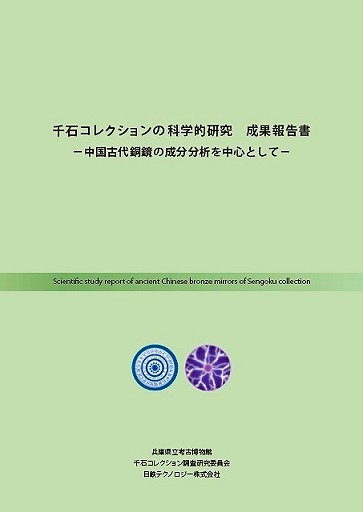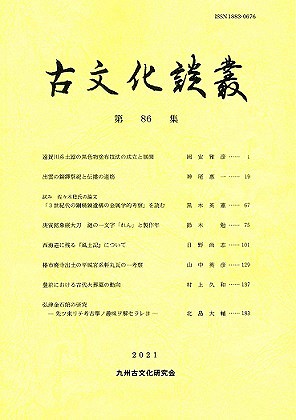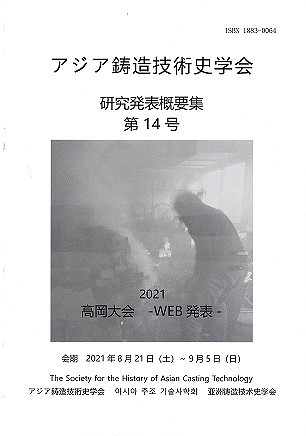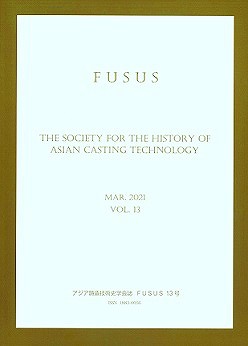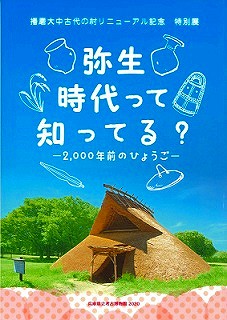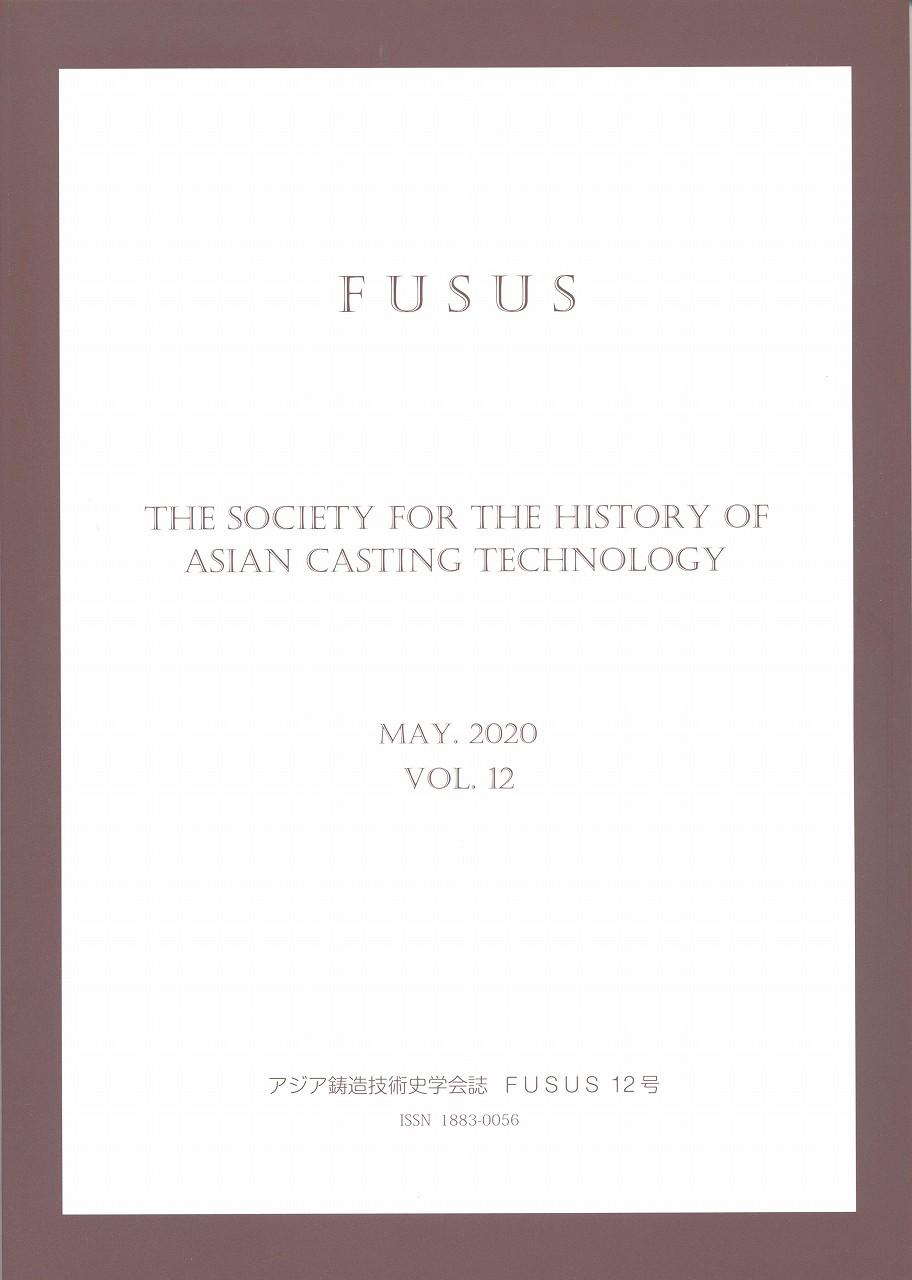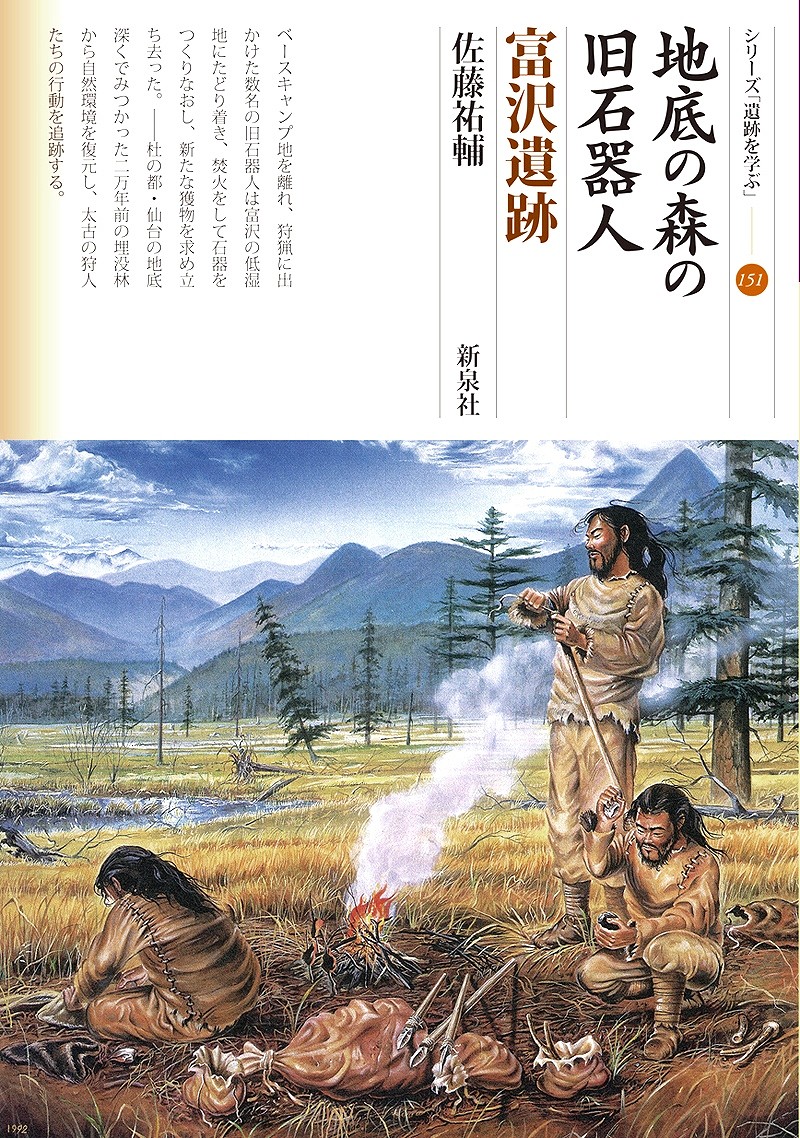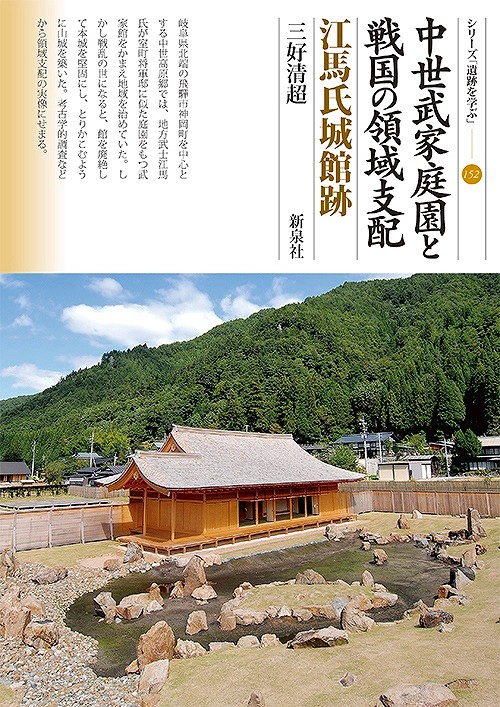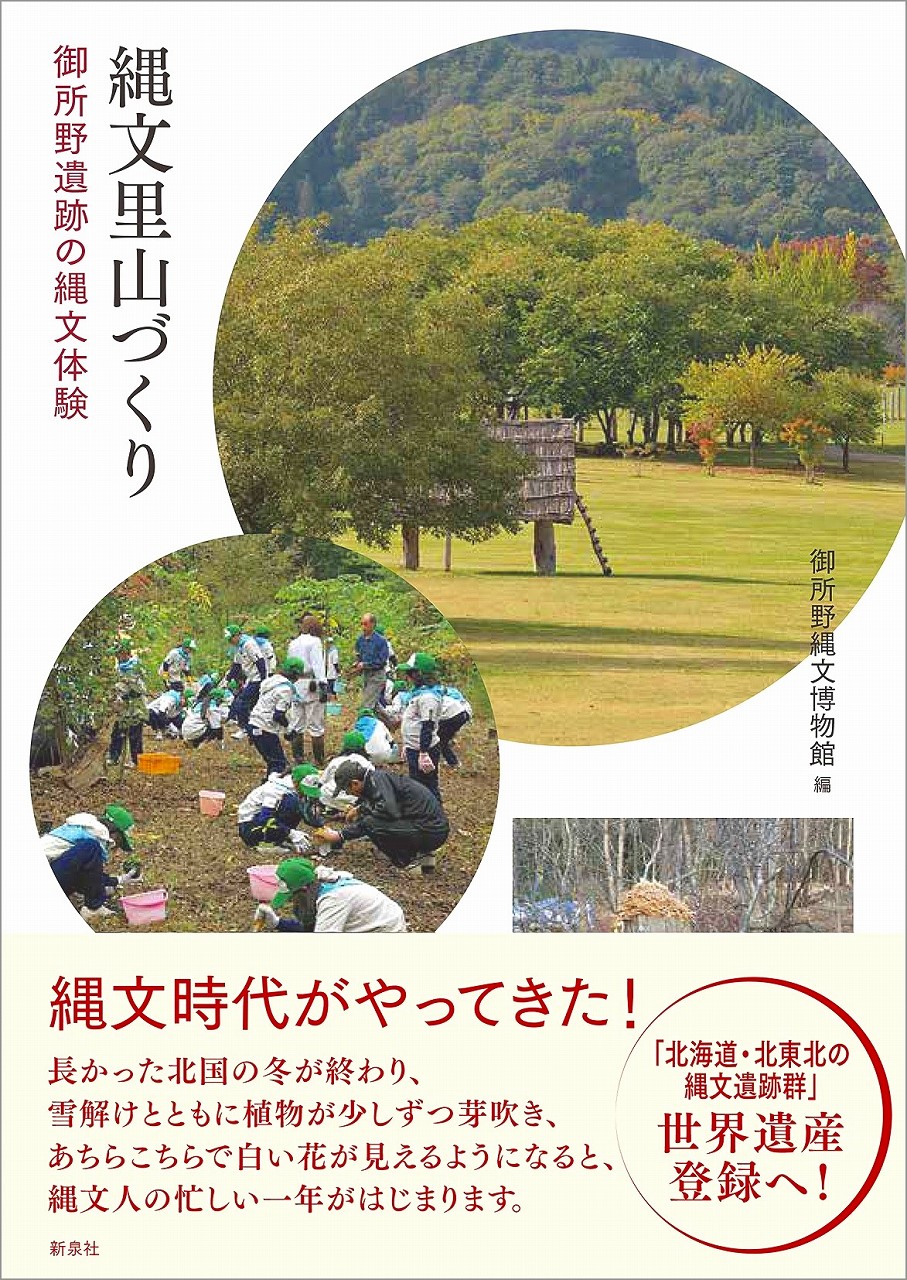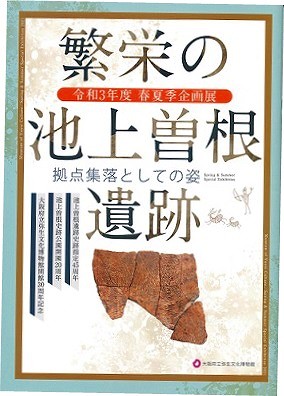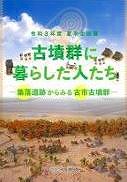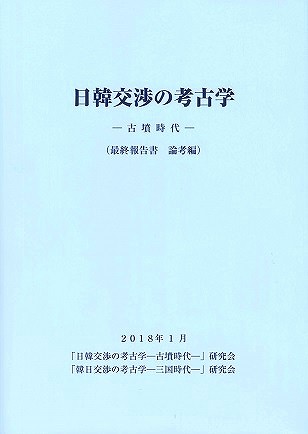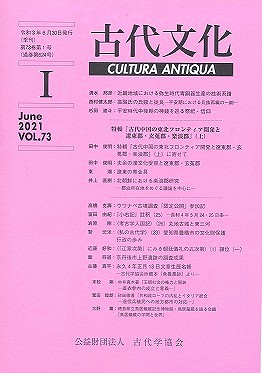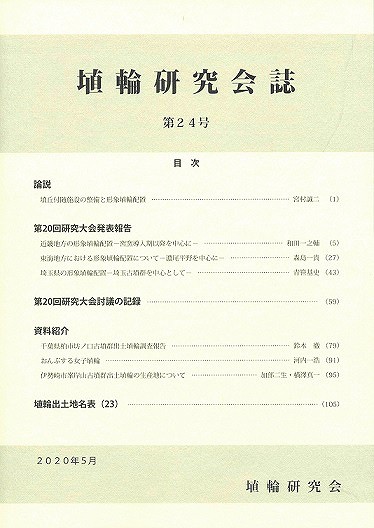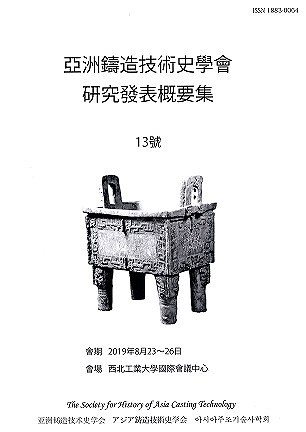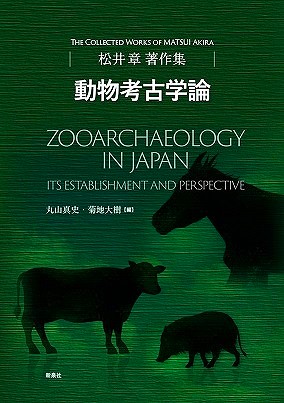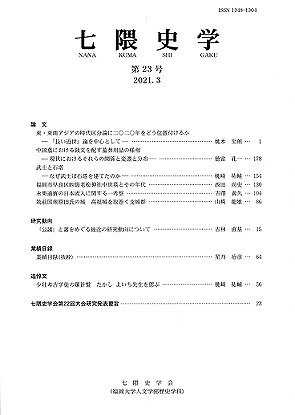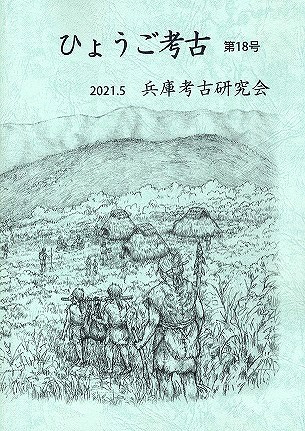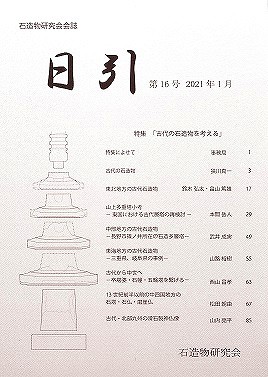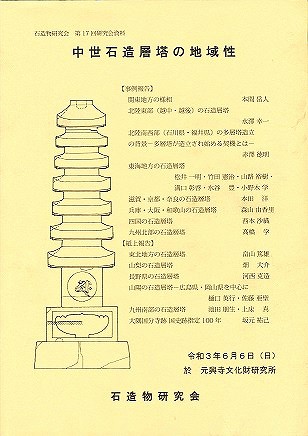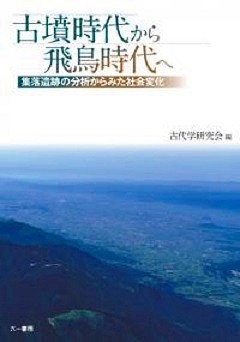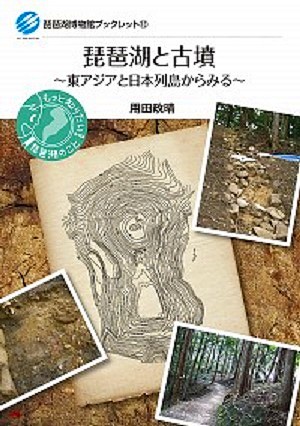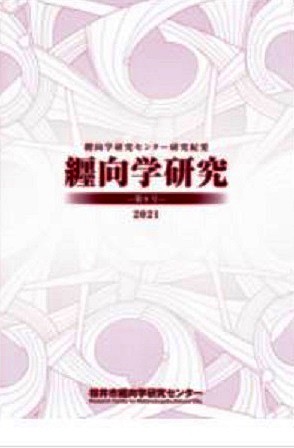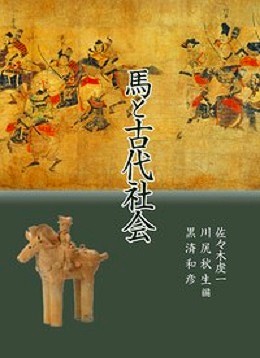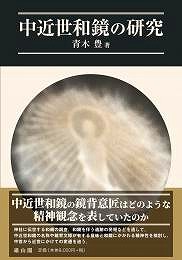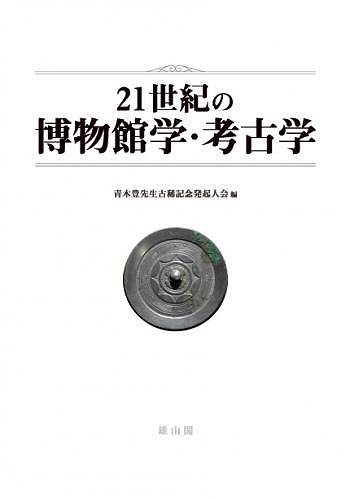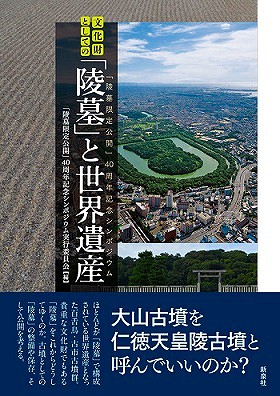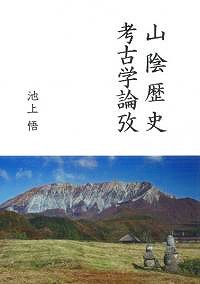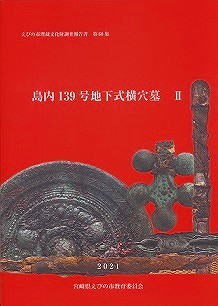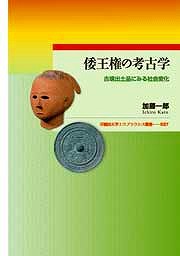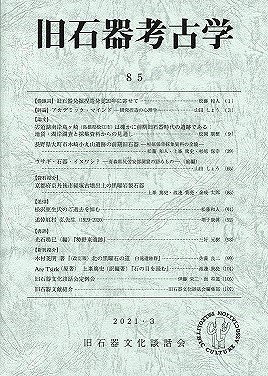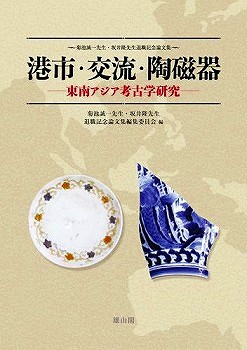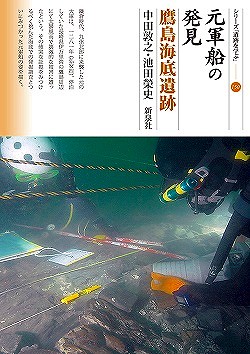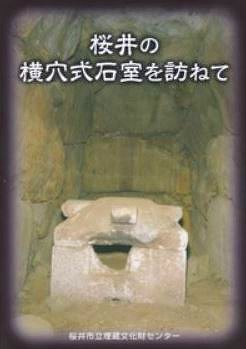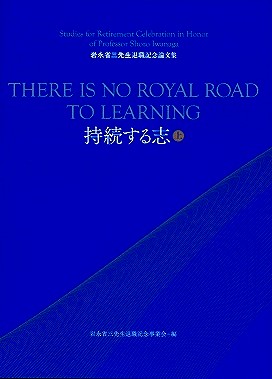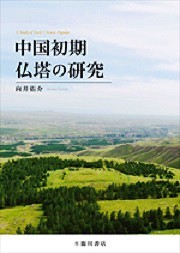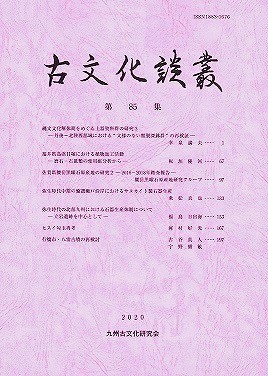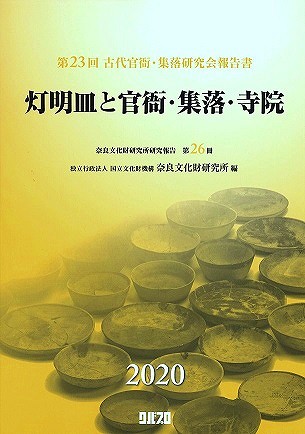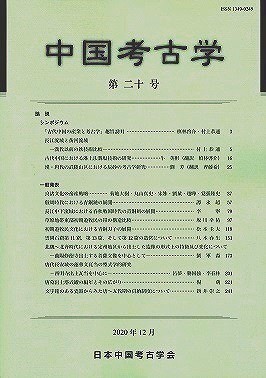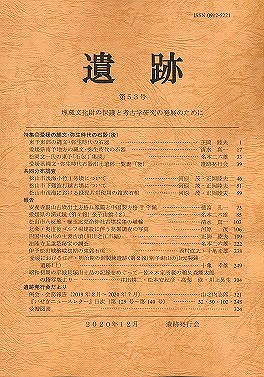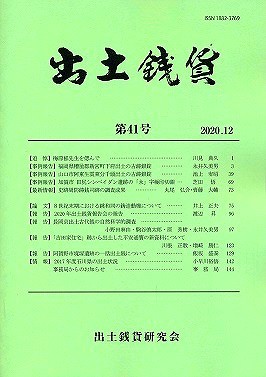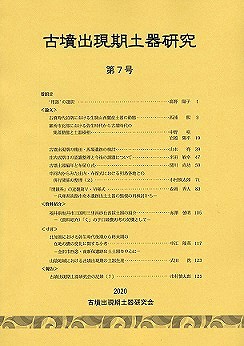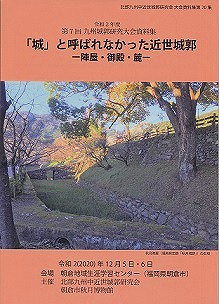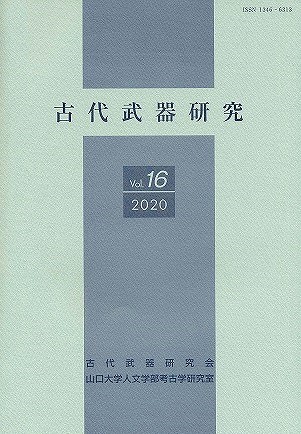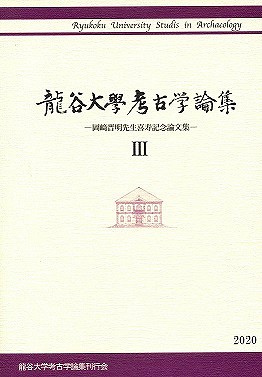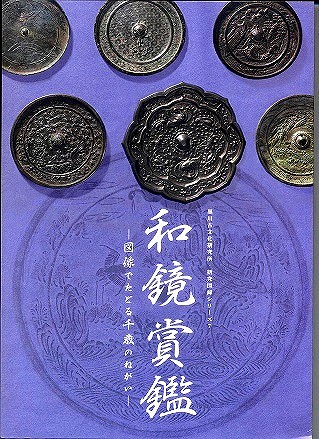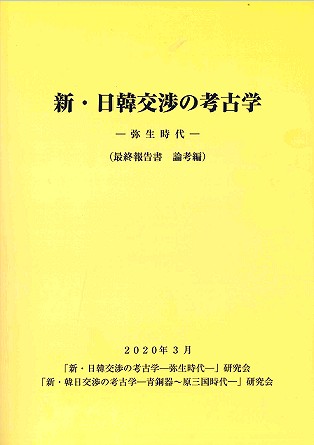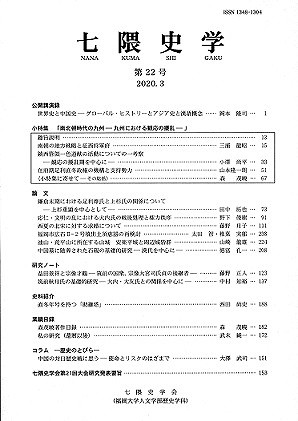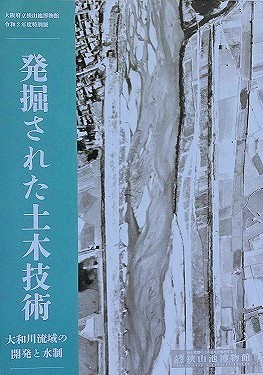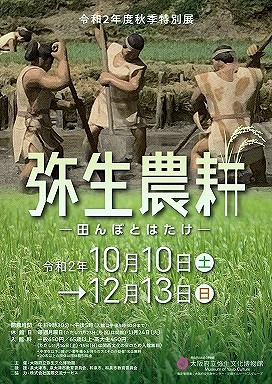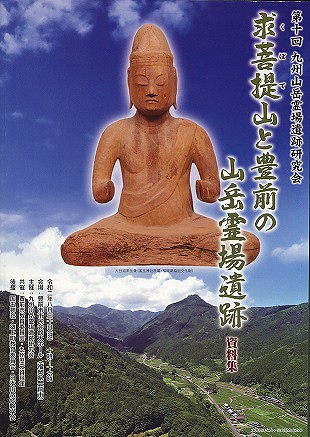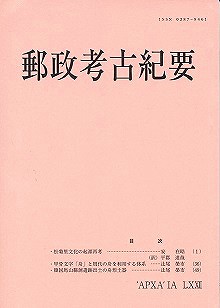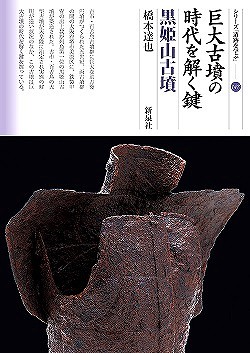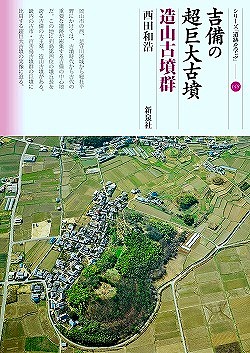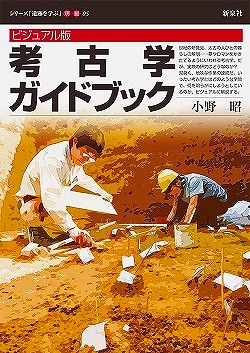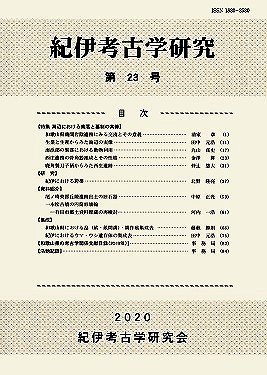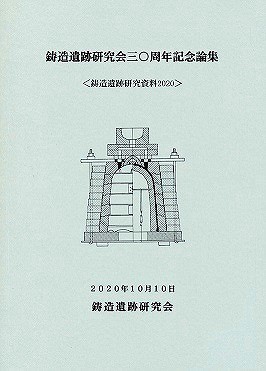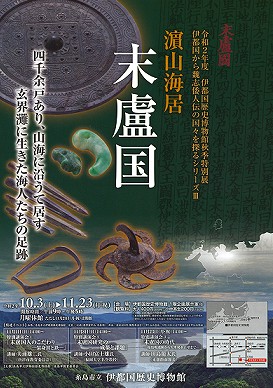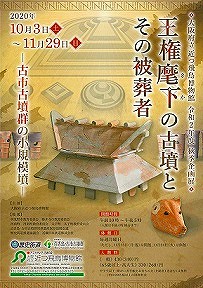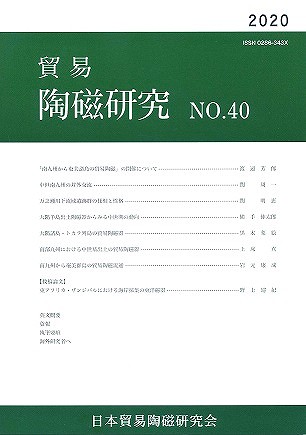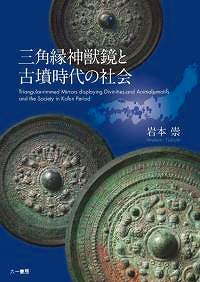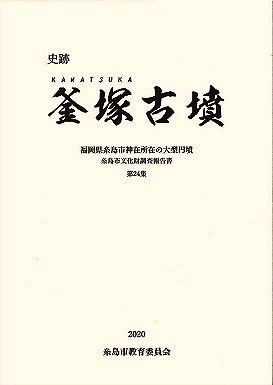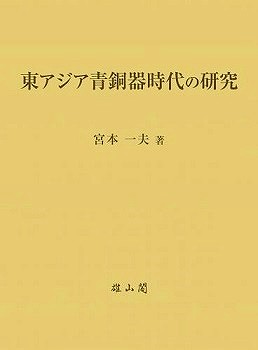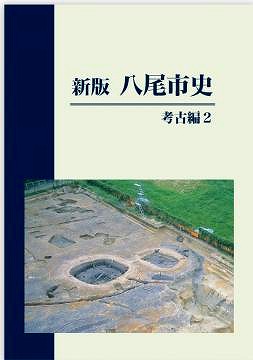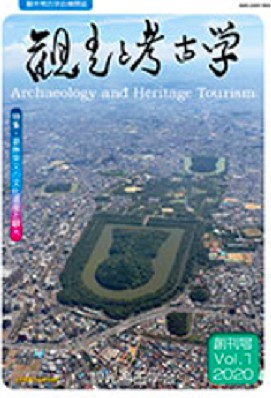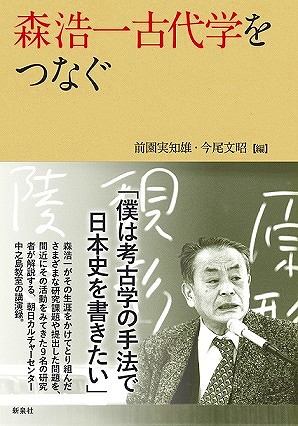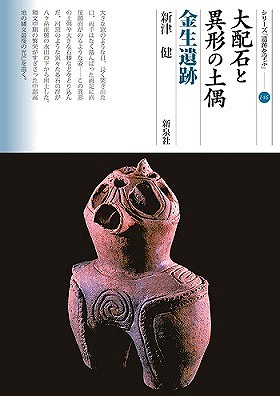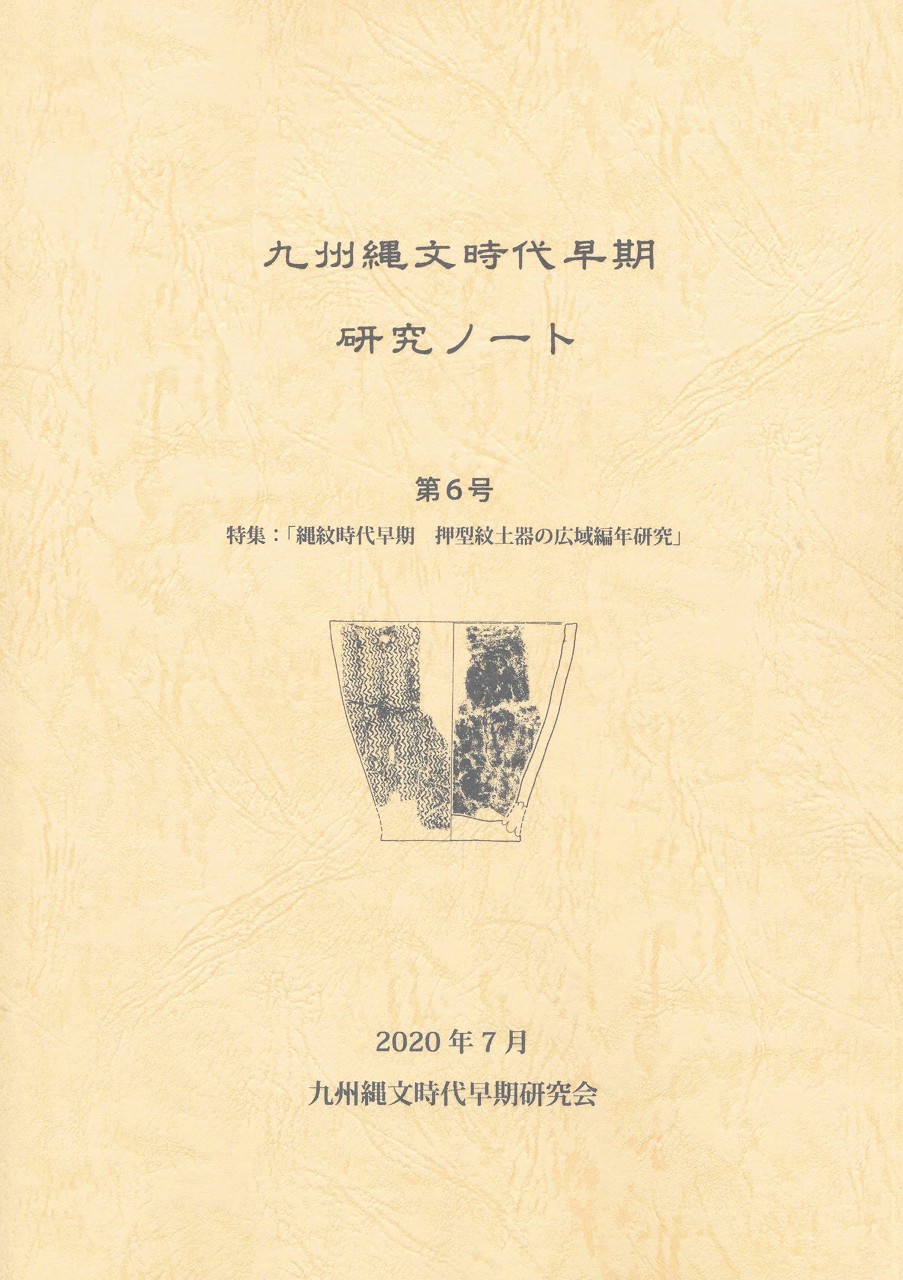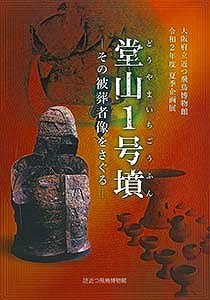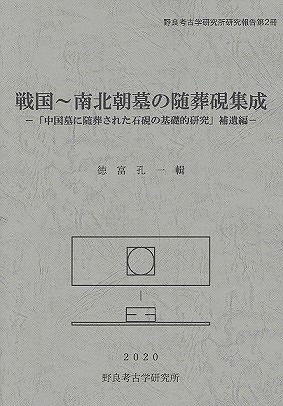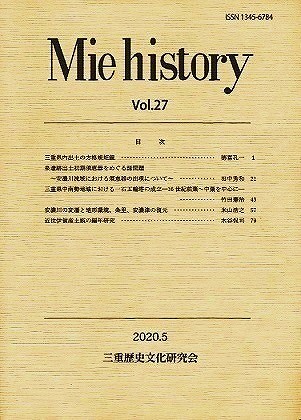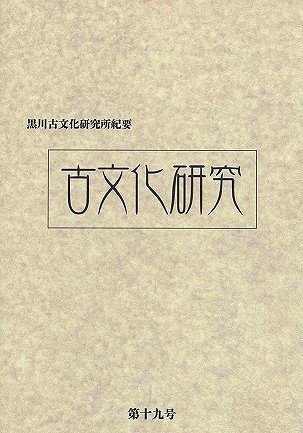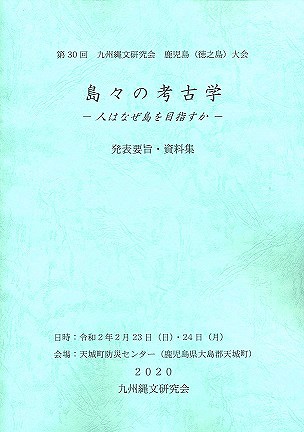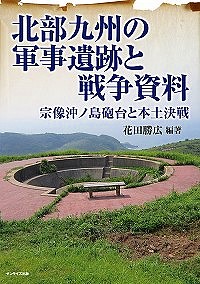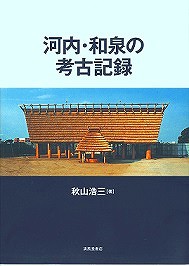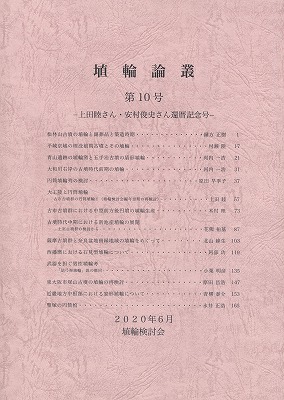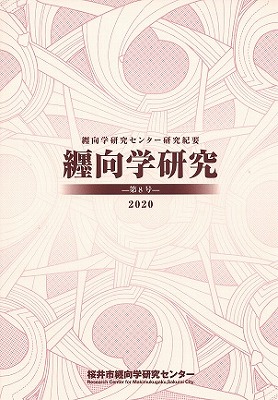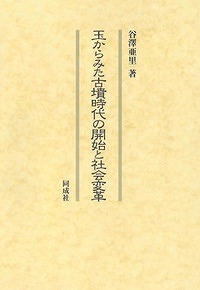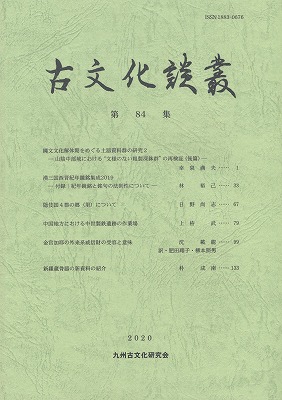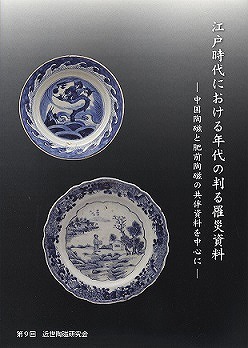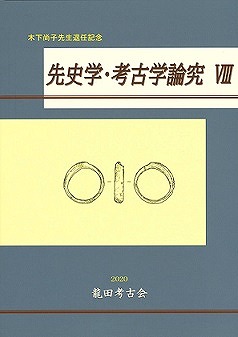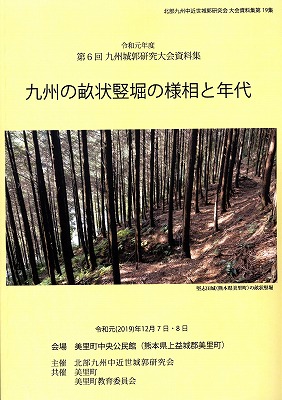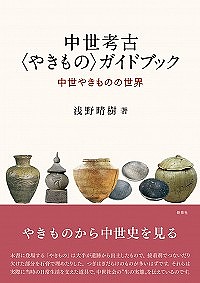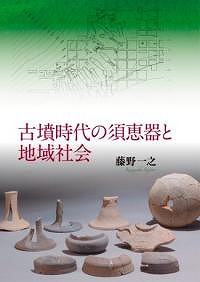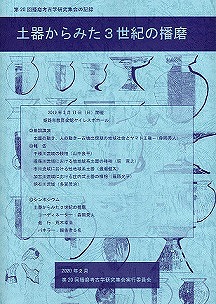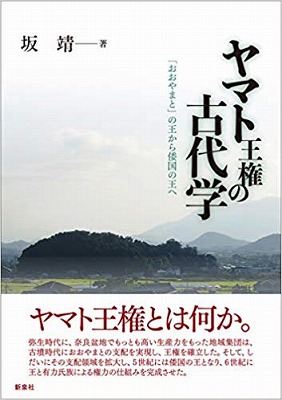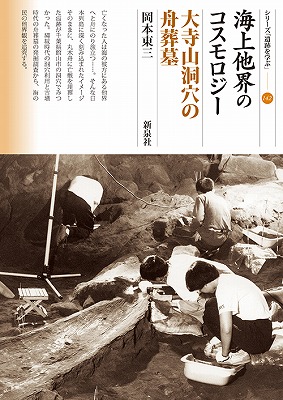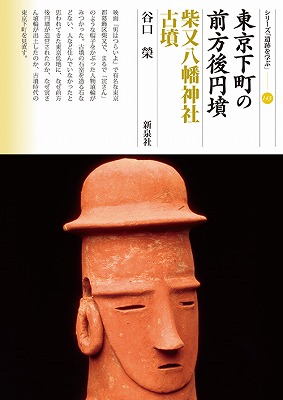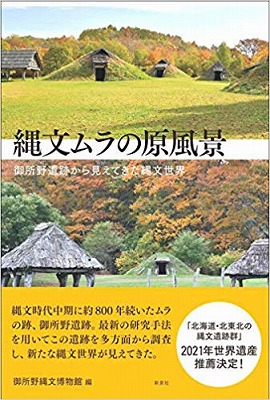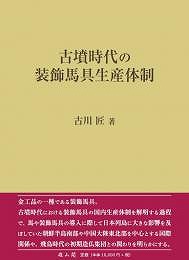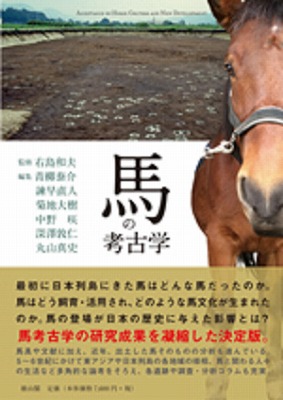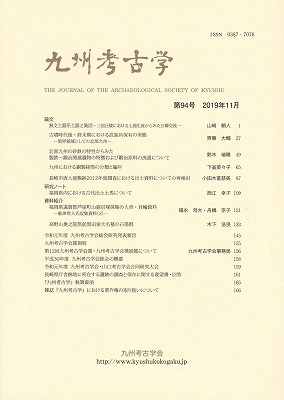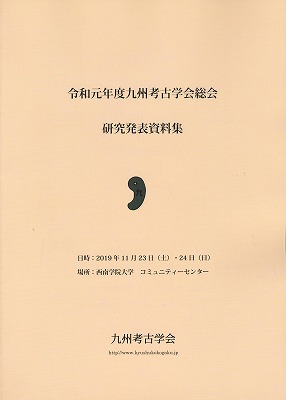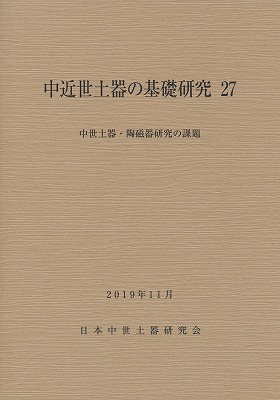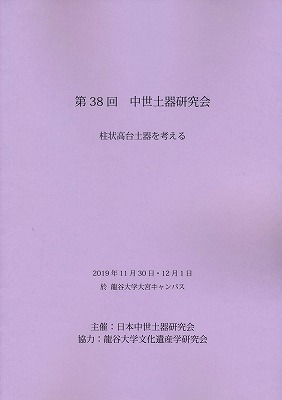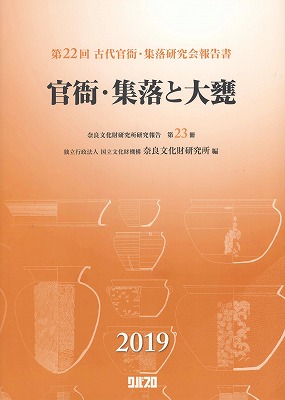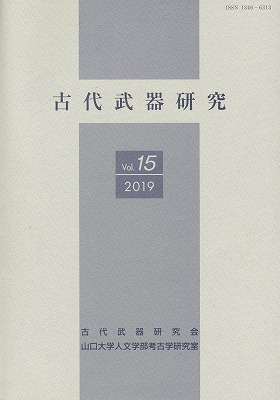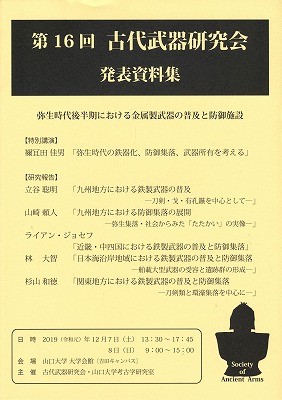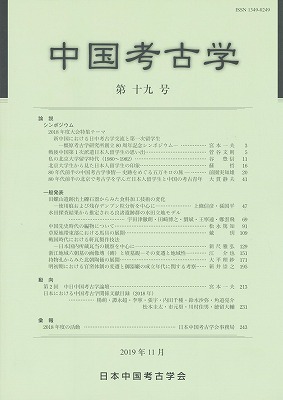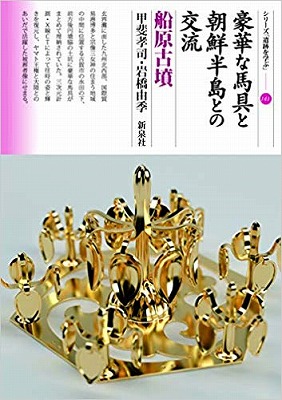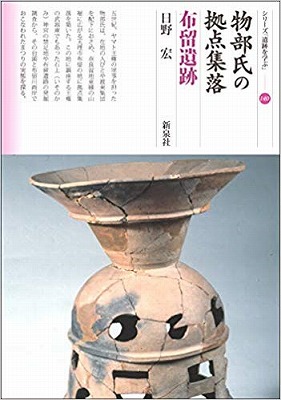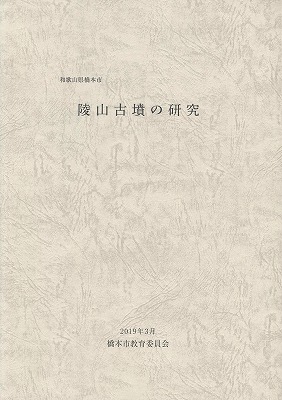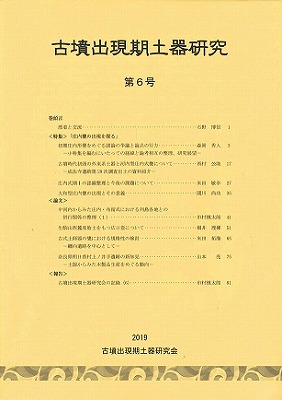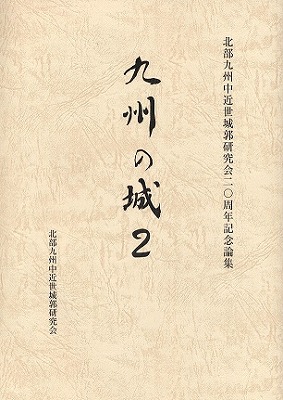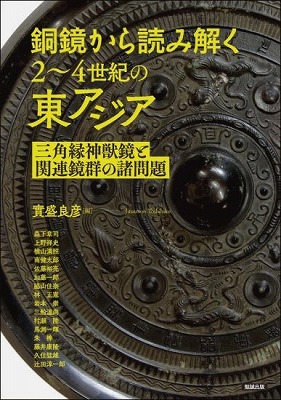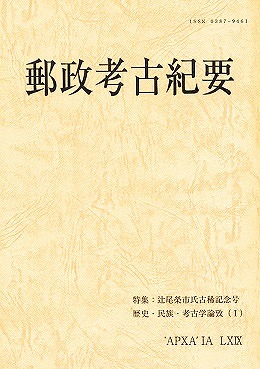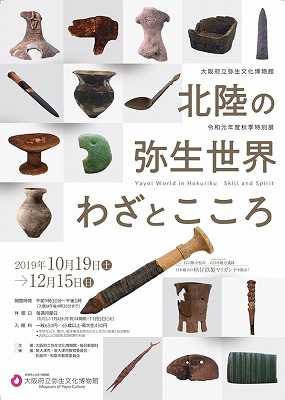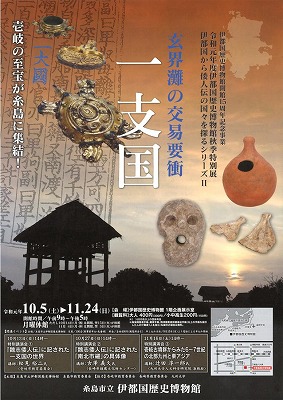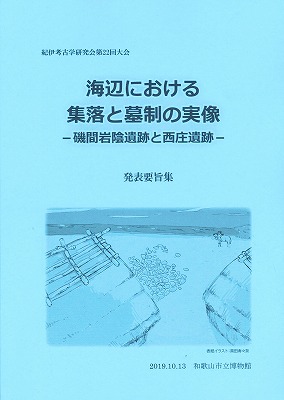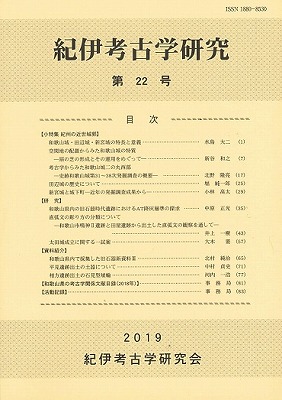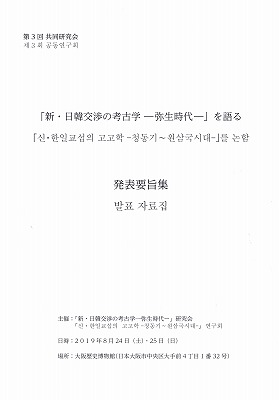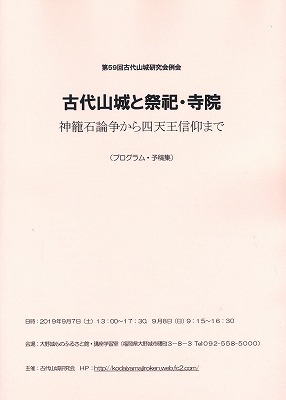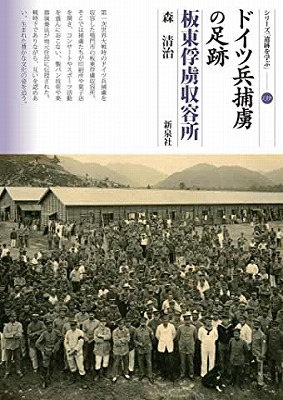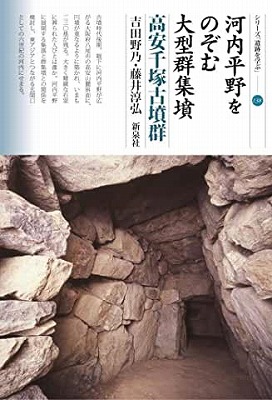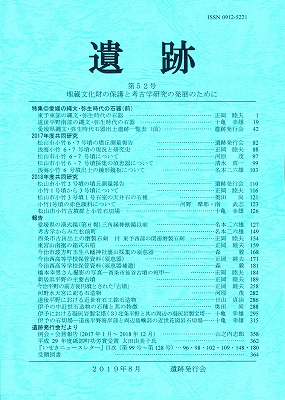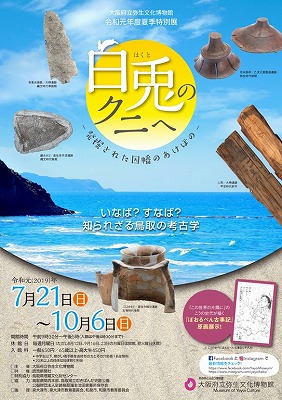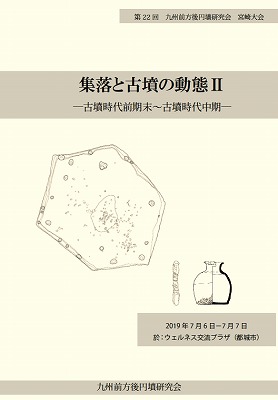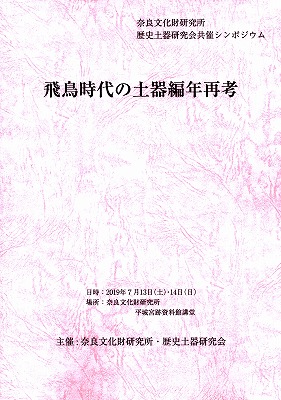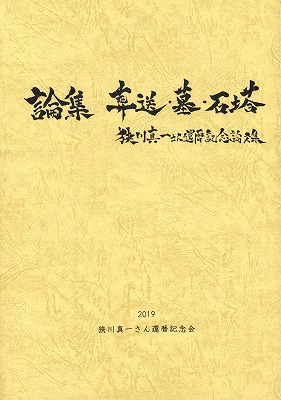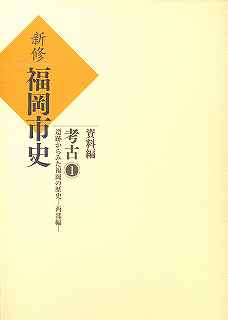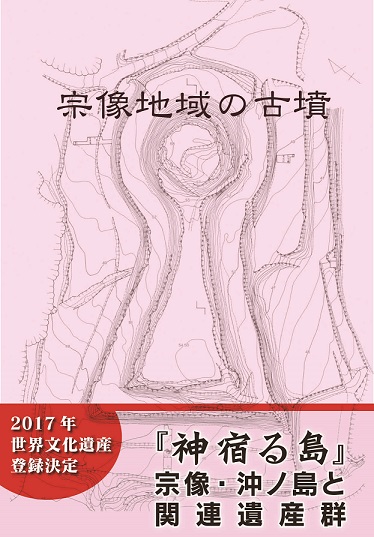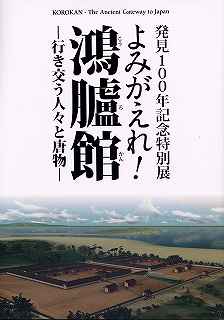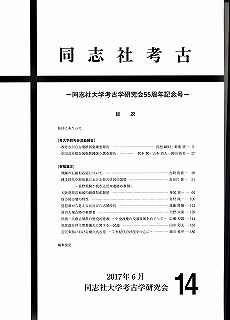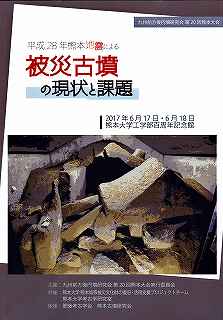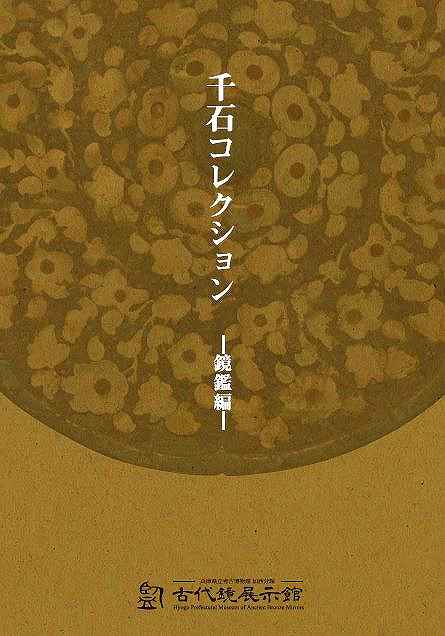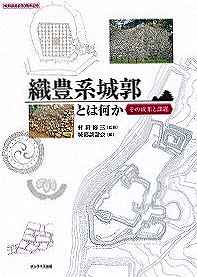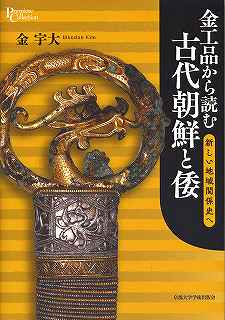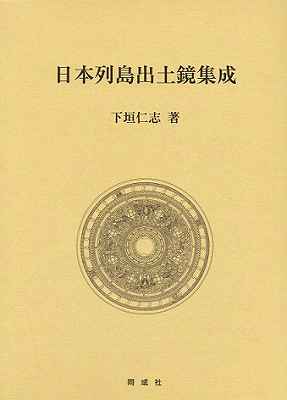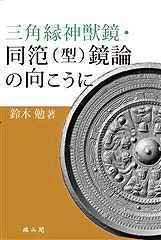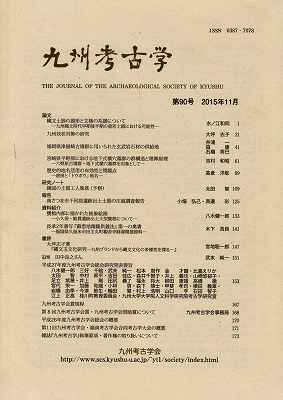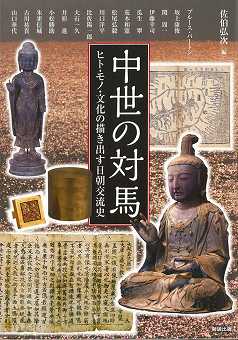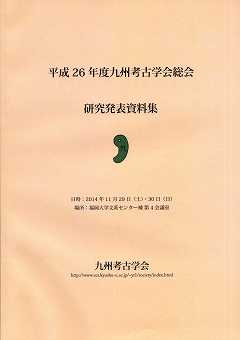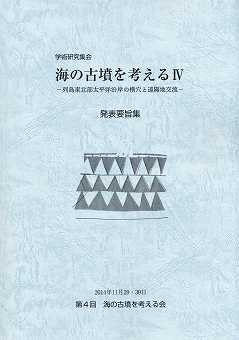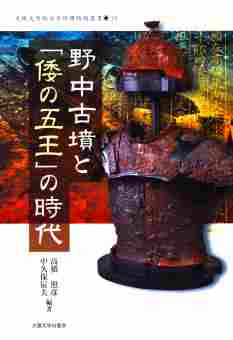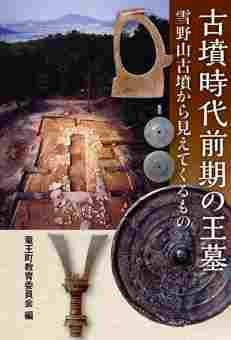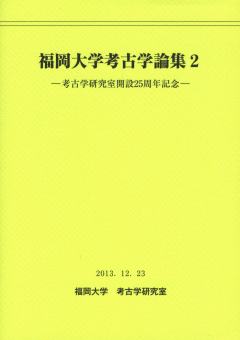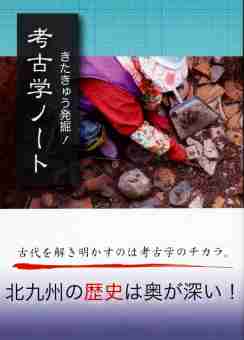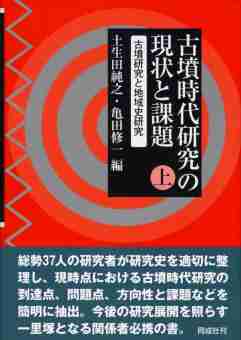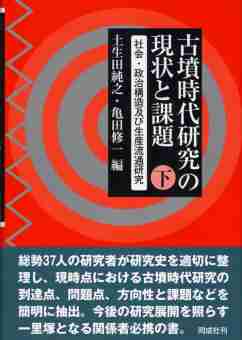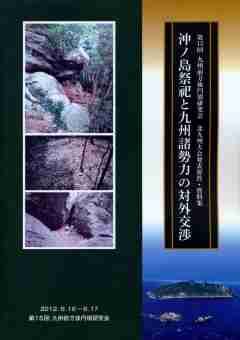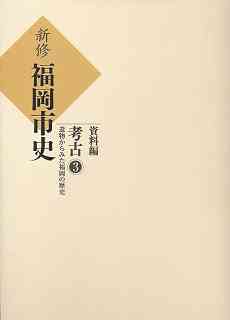| 日 本 考 古 学 図 書 情 報 |
目 次 【内容紹介】
【目次】 【内容紹介】
【目次】 基調講演 岡田憲一
「縄文のおわり、弥生のはじまり」…………… 1 報告2
大本朋弥
「播磨における縄文時代中期末~弥生時代前期 【内容紹介】 【目次】 序 言……………………………………………………………………………
Ⅲ 第Ⅱ部 各地における首長墓系譜の分析 〈報告〉 第Ⅲ部
目
次 [基調講演] 2.九州・沖縄各県の調査・研究動向(2024年10月~2025年9月)… 77 小川原 励「福岡県の動向」 3.九州旧石器文化の研究 髙橋 愼二「日ノ岳遺跡の石器群ーその2ー」…………………
89 【目次】 木簡研究の最前線 木簡調査研究の周辺 地方官衙の木簡 リレー連載・考古学の旬 第32回 リレー連載・私の考古学史 第23回
【目次】 【目次】 【目次】 添付CD-ROM 播磨の家形石棺個別調査票 【紹介文】 【目次】 第1章 貝塚文化のアウトライン 第2章 貝塚文化研究のあゆみと視点 第3章 貝塚文化の成立と展開 第4章 海を越えた交流 第5章 貝塚文化の終焉 エピローグ――島世界の過去・現在・未来 北海道・本州~九州・琉球の時代区分 【内容紹介】 【目次】 第2章 水中考古学と水中遺跡 第3章 肥前陶磁の生産と流通 第4章 肥前陶磁を積み出した港 第5章 海岸に打ち上げられた肥前陶磁 第6章 日本の海から引き揚げられた肥前陶磁 第7章 世界に運ばれた肥前磁器の貿易路 第8章 世界の海から引き揚げられた肥前磁器 終章 水中遺跡が意味するもの 【目次】 【内容紹介】 【紹介文】 弥生時代は道具として多くの石器が用いられた最後の時代。原産地と 【主要目次】 はじめに 序 章 第1章 金山産サヌカイト製石器の生産と流通 第2章 片岩製石庖丁の生産と流通 第3章 片刃石斧と両刃石斧の生産と流通 第4章 石器の生産と流通にかかわる集落 第5章 弥生時代前期から中期前葉における石器の生産と流通 第6章 弥生時代中期中葉から後葉の特質 終 章 参考文献 【
目次】 【内容紹介】 【目 次】 古代集落の構造と変遷 古代集落構成建物の規模に関する分析手法について 豊前・豊後における古代集落の構造と変遷 古代武蔵国多磨郡の集落と武蔵国府 史料からみた村と古代集落遺跡 Ⅱ 討 議 討議① 【内容紹介】 【目次】 前編 後編 あとがき 【目次】 古墳時代刀剣類研究の課題と今後の方向性 出雲市上塩冶築山古墳出土の赤鞘の大刀と錫装刀子 趣旨説明 【目次】 報告 紙上報告
【目次】 〈特集:須恵器生産の中世 変容と展開〉 【目次】 愛媛県の須恵器(1)
一特殊須恵器一 光 江
章………… 1 市場南組窯跡産須恵器編年の再検討(後篇) 三 吉 秀 充…………
25 須恵器の布目痕について 一新しい観察表現への期待ー ………………………………………………………………………………………… 福岡県糟屋郡粕屋町大字内橋カラヤ遺跡 【発表題目】 研究発表2 樋口太地(三重県埋蔵文化財センター) 研究発表3 枡家 豊_(島取県教育文化財団調査室) 研究発表4 菊池 望(東京国立博物館) 研究発表5 魚津知克(福井県教育庁埋蔵文化財調査センター) 研究発表6 繰納民之(京都国立博物館) 研究発表7 土屋隆史(宮内庁書陵部) 研究発表8 金 宇大(滋賀県立大学) 【内容紹介】 瀬戸内の弥生土器・集落を精緻に分析し、さらに船舶復元や海上から 【目次】 本書の主な目次 序(寺沢薫) 第1部 弥生・古墳時代の瀬戸内海と海上交通 付論1 準構造船と描かれた弥生船団 第2部 今後の瀬戸内歴史研究に向けて あとがき(柴田圭子) 【内容紹介】 【目次】 第1章 貯蔵具と食器の変革 第2章 弥生・古墳時代移行期における土器の丸底化 第3章 東アジアにおける窯技術の拡散 第4章 民族誌からみた窯焼きと野焼きの接点 第5章 土器様式の変革と渡来の構造 終章 土器からみた漢周縁地域としての韓半島と倭 参考文献 【内容紹介】 【目次】 第Ⅱ部 遺跡のあゆみ―発掘調査が語るもの― 【内容紹介】 【目次】 第2章 弥生時代後半期の手工業 第3章 弥生時代後期後葉以降の手工業 第4章 墳丘墓の系譜とその発展 第5章 大型化する墳丘墓 第6章
棺槨を石で囲う墳丘墓 第7章 手工業生産の展開と墳丘墓の形成 目 次 《活動報告》 《古代学への提言 96》 【内容紹介】 第1章 甲の型式と変遷 第2章 冑のかぶり方と錣の変遷 第3章 甲冑構成と武装の変遷 第4章 武器・武具の生産・授受・使用 第5章 武器・武具の履歴・扱いと社会的機能 第6章 古代アジアの武装と伝播・受容・変遷 第7章 武装の特質と軍事組織 終 章 古墳時代軍事構造の歴史的意義 【紹介文】 金山として著名な佐渡島。銀も豊富に産出し、経済・貿易に多大な影響力を 【目次】 第2章 西三川砂金山 第3章 鶴子銀山 第4章 相川金銀山 第5章 佐渡奉行所と鉱山都市 第6章 近代佐渡鉱山と終焉 【内容紹介】 序章 倭の五王の時代を考える-----------------------------辻田淳一郎
1 第一章 同型鏡からみた倭の五王の時代--------------------辻田淳一郎
15 コラム 同型鏡群の鈕孔形態と製作技術--------------------辻田淳一郎
48 第二章 倭の五王の南朝遣使とその背景----------------------田中史生
57 第三章 倭の五王と百舌鳥・古市 ---------------------------
一瀬和夫 85 第四章 倭の五王の時代の王宮と社会------------------------古市
晃 119 第五章 倭の五王と東国の古墳時代社会-----------------------若狭 徹
147 【内容紹介】 目 次 第三章 河内湖沿岸出土の舟運関連資料 論 考 【内容紹介】 第Ⅰ部 遺跡の概要―淡路島遺跡群とは― 第Ⅱ部 遺跡のあゆみ―発掘調査が語るもの― 【内容紹介】 はじめに…………………………………………………………………………… 01
【内容紹介・目次】 天体災害痕跡研究 地震・火山災害痕跡研究 気象災害痕跡研究 過去と現代の災害を伝承する 最近の発掘から/紀伊国守護 畠山氏一門の居館 【内容紹介】 目 次 目次 紙上報告
【紹介文】 【目次】 第2章 高座郡衙 第3章 寺院・川津・祭祀場 第4章 郡衙のある風景 第5章 奇跡の遺跡保存 【目 次】 論
文 龍造寺氏の筑後支配と国衆 ……………………………中村
知裕………… 7 新刊紹介 コラム-歴史のとびら- 七隈史学会第26回大会研究発表要旨 …………………………………………
139
目 次 目 次 【研究ノート】 【開催趣旨】 【報告】 【内容紹介】(博物館HPより抽出) ごあいさつ 今里幾次主要著作目録 ………………………………………… 54 【内容紹介】 日本考古学界の第一人者が徹底討論するシリーズ第1弾! 序文 考古学が解明する邪馬台国の時代(辻 秀人) 【内容紹介】 目次 前編 後編 あとがき 【概要文】 以後続巻予定 本書で取り上げる主な遺跡/本書で扱う時代年表 第1章 日本列島にきた家畜文化 第2章 家畜のはじまりと広がり 第3章 家畜の考古学をめぐる新視点 終章 アジアの家畜文化をながめる(菊地大樹) 【内容紹介】 【目次】 第1章 日本とユーラシア先史土器研究を比較する 第2章 縄文・弥生人の生活と土器 第3章 先史土器の境界をさぐる 第4章 先史土器研究の方法論 第5章 考古科学による先史土器の研究 あとがき(小林青樹・高瀬克範・滝沢 誠・福田正宏・山田康弘) 【紹介文】 日本海をのぞむ鳥取市東部・青谷の低地から、大量の人骨や 【目次】 第2章 青谷上寺地遺跡の発掘と集落像 第3章 地下の弥生博物館 第4章 交易拠点としての港湾集落 第5章 青谷上寺地遺跡のこれから < 大目次> 第1章 古代韓半島の精密鋳造技術 第2章 古代韓半島の線彫り技術 第3章 統一新羅の神業「線刻團華雙鳥文金箔・」 第4章 玄界灘を渡った鋳造と毛彫りの技術
第二部 系譜論と製作地論 論考Ⅰ 三角縁神獣鏡・系譜論は製作地辿り着けるか? 論考Ⅱ 甲冑と移動する渡来系工人ネットワーク 【紹介文】 日本海をのぞむ鳥取市東部・青谷の低地から、大量の人骨や 【目次】 第2章 青谷上寺地遺跡の発掘と集落像 第3章 地下の弥生博物館 第4章 交易拠点としての港湾集落 第5章 青谷上寺地遺跡のこれから 【紹介文】
古墳時代最大の内乱「磐井(いわい)の乱」の当事者、筑紫君磐井の 【目次】 第1章 筑紫君磐井の墓 第2章 岩戸山古墳の実像 第3章 石製表飾の語るもの 第4章 敵か味方か? 磐井と継体 第5章 朝鮮半島情勢と「磐井の乱」 第6章 律令国家への道 【紹介文】 【目次】 第2章 外交の最前線・筑紫 第3章 姿をあらわした鴻臚館 第4章 鴻臚館と古代の外交 第5章 アジアの交流拠点・福岡の原点 目次 発表1 京都府「京丹後市松田古墳群B支群(松田墳墓群)の調査 目次 【基調報告】 武蔵型板碑の生産および 【付録】見学会資料………………………………………………(87) 目次 日引20号刊行にあたって
渡辺昇 【論 考】 志々伎山薩摩塔の銘文に関する一考察 大石一久
5 【石造物研究会の軌跡】 会誌『日引』バックナンバー 一覧
300 執筆者 一覧
309 【本資料集推薦コメントのご紹介】 草戸千軒町遺跡の発掘調査とその成果 ……………………………… 2 ────────────────────────────────── ◯
第2章 たべる ◯
第3章 だす ◯
第4章 ささげる
目次 著者一覧 ……………………………………………………………………277 ──目 次──────────────────────── 〈研究展望・動向〉 〈連 載〉
目 次 《研究ノート》 《研究メモ》 《シリーズ遺跡紹介18》 《展 望》 《古代学への提言 95》
【目次】 【論文】 【随想】 目次 【内容簡介】 口絵 【目次紹介】 草戸千軒町遺跡の発掘調査とその成果 ……………………………… 2 第26回九州前方後円墳研究会長崎大会 九州の古墳時代遺跡出土鏡をめぐる諸問題 辻田淳一郎 …… 1 筑前西部~中部地域における弥生時代終末から 【ご案内】 2025年3月15日~6月15日まで国立科学博物館で開催された特別展 …………………………………………………………………………… 日本を代表する青銅器の一つに、弥生時代の祭祀に使用された「銅 第1章 銅鐸鑑賞のてびき ……………………………………………1 第2章 銅鐸600年の変化~兵庫の銅鐸を中心に~ ………………12 出品目録・写真目録・挿図目録 ……………………………………86 【ご案内】 大阪大学考古学研究室が創設されて以来の教員として研究室を 【目次】 序………………………………………………………高橋
照彦 ⅰ 埋蔵文化財の保護と考古学研究の発展のために 【ご案内】 ──────────────────────────────── 例 言(部分) 序 言 ………………………………………………………………… ⅰ 【内容紹介】 本書は、関西大学文学部考古学研究室開設70周年を記念して刊行された。 【目次】 ◇序文(井上主税)
目 次
目 次 【目次】 骨角器研究と骨角製装身具類研究 骨角製装身具類の地域様相 特定素材・器種からみる装身具類 他素材から見る装身具類 他装身具共伴・着装人骨 最近の発掘から リレー連載・考古学の旬 第29回 リレー連載・私の考古学史 第20回 連載・現状レポート これからの博物館と考古学 書評/論文展望/報告書・会誌新刊一覧/考古学界ニュース ──────────────────────────── 目 次 目 次 第2部 天理市域主要古墳のカルテ 1.上殿古墳………………27
37.ヒエ塚古墳………………63 【内容照会】 概要文彩陶・黒陶から三彩・白磁・青磁へと製陶技術を進化させた 【内容紹介】 本書は、関西大学文学部考古学研究室開設70周年を記念して刊行された。 【目次】 ◇序文(井上主税) 【目次】 吉江 崇:外記政の衰退に関する覚書 ───────────────────────── 例 言 はじめに-本研究の目的と経緯
武末 純一 …… 1 ……………………………………………………………………… **************************************************** 第Ⅱ部 遺跡のあゆみ―発掘調査の成果と遺跡の未来― ……………………………………………………………………… 第1章 炉と竈の比較 第2部 原史・古代の住まいと建物 第1章 丘陵上に立地する弥生時代集落の景観 【考古学と文化史 2 刊行にあたって】 【内容】 【目次】 【内容紹介】 【目次】 【目次】 <目次> 第1章 七支刀と古代東アジア 【第33回 九州縄文研究会福岡大会 開催要項】より 趣 旨:第33回福岡大会では、後期の鐘崎式土器および併行期の 【目 次】 【記念講演】 【九州・沖縄各県における当該土器型式期の資料集成】 福岡県における縄文時後期の小池原上層式~鐘崎式及び併行期 【紹介文】 ネアンデルタール人やデニソワ人ら旧人たちが生きていた時代のアジア 【目次】 第1章 考古学と文化人類学の知見が豊かにするパレオアジア新人文化 第1部 考古学的視点 第2章 人類の進化と狩猟技術の発達【佐野勝宏】 第2部 文化人類学的視点 第11章 植物資源の道具利用の多面性 第3部 パレオアジア:新人文化の形成 第19章 アジア旧石器時代の石器技術と新人の拡散【西秋良宏】 ─────────────────────────── 目次 第2章 おらあとうの考古学 第3章 井戸尻文化の中心地 第4章 山岳農耕民のくらし 第5章 縄文図像学の世界 吉岡康暢先生卒寿記念論文集 学究無限 刊行のご案内より 北陸地方の古代史・考古学研究のみならず、古代・中世考古学研究を 執筆者一覧 ─────────────────────────── 【目次】 第2章 原の辻遺跡を掘る 第3章 一支国を構成する弥生集落 第4章 「南北市糴」の交易網 第5章 これからの一支国 【ご案内】 本書は第3回吉野ヶ里学シンポジウム「弥生後期の集落と墓制ー有明 【目次】 基調講演 「縄文のおわり、弥生のはじまり」 目 次 本 文 目 次 【目次】 序 【内容簡介】 第1章 研究の現状と課題 第2章 高麗陶器の分類と編年 第3章 高麗陶器の生産 第4章 高麗陶器大型壺の消費とその用途 第5章 九州・琉球列島における高麗陶器の消費 第6章 生産と消費からみた高麗陶器の特質 終章 中世東北アジア陶磁史からみた高麗陶器 【内容紹介】 九州西方海域を巡る技術・疫病・信仰― 序章 海の十字路 第2章 海を跨がる疫病―疱瘡― 第3章 海を渡った信仰―潜伏キリシタン― 終章 周縁海域の交流―内と外― プロローグ 埴輪の世界 古墳時代の3世紀から6世紀にかけて埴輪はにわが作られました。 第1章 王の登場 埴輪は王(権力者)の墓である古墳に立てられ、古墳からは副葬 第2章 大王の埴輪 ヤマト王権を統治していた大王の墓に立てられた埴輪は、大きさ 第3章 埴輪の造形 埴輪が出土した北限は岩手県、南限は鹿児島県です。日本列島の 第4章 国宝 挂甲の武人とその仲間 埴輪として初めて国宝となった「埴輪 挂甲の武人」には、同じ 第5章 物語をつたえる埴輪 埴輪は複数の人物や動物などを組み合わせて、埴輪劇場とも呼ぶ エピローグ 日本人と埴輪の再会 古墳時代が終わると埴輪は作られなくなりますが、江戸時代に入 近世陶磁研究会 第13 回大会 近世陶磁研究会 会 長 大橋 康二 当研究会の前身九州近世陶磁学会は10 周年記念の2000 年に『九州陶磁 【目次】 口絵写真 ………………………………………………………… P1 東アジアの農耕社会、日本列島の弥生農耕起源の解明につながる 第2章 将軍山積石塚と老鉄山積石塚の石室 …………宮本一夫
13 第3章 将軍山積石塚出土土器 …………………………宮本一夫
41 第4章 将軍山積石塚出土石器 ………………………松尾樹志郎
61 第5章 牧羊城址購入遺物 ………………松本圭太・松尾樹志郎
71 第6章 羊頭窪貝塚出土土器の圧痕調査 第7章 遼東半島の積石塚 ………………………………宮本一夫
115 第8章 将軍山積石塚からみた遼東半島の先史社会 ……宮本一夫 141 図版編 …………………………………………………………………
155 参考文献 203 群集墳とは何か 【目次】 第2章 東国における群集墳造営の画期 第3章 群集墳の形成と構成 第4章 群集墳の被葬者 群集墳論関係論文一覧 (日高 慎) 卷頭言 古典・文学と考古学研究のいま(谷口 榮) 古 代 中 世 近 世 最近の発掘から リレー連載・考古学の旬 第28回 リレー連載・私の考古学史 第19回 書評/論文展望/報告書・会誌新刊一覧/考古学界ニュース 文化財保護法にみる古墳の保存と活用 日本列島における盛土構造物の保護と整備の考え方 盛土構造物のリスクと課題―整備に向けた諸条件― 東アジアにおける王墓の整備事情 最近の発掘から リレー連載・考古学の旬 第27回 リレー連載・私の考古学史 第18回 書評/論文展望/報告書・会誌新刊一覧/考古学界ニュース ─────────────────────────────── 特 集
文化財写真における高感度ノイズ・長時間ノイズの取扱を 世界遺産アンコールワットクメール美術の清華を見る 東南アジアの古代美術の中でも、カンボジアのクメール族は 【目次】 【紹介文】 マチュピチュ遺跡やナスカの地上絵、あるいはシカン文化のきらびや 【目次】 01 アンデス文明とは もっとアンデス文明を知るために読んでほしい本 【ご案内】 古代の王権と和泉の首長による須恵器生産について窯跡、集落、 【目次】 序 〈広瀬和雄〉 序 章 古代和泉の須恵器生産・集落・古墳の考古学研究に 第一章 泉北丘陵窯跡群の須恵器生産 第二章 古代集落と土地開発 第三章 古墳と古代氏族 第四章 須恵器生産と茅渟県 終 章 古代開発のモデル 2023年12月に開催された奈良文化財研究所第27回古代官衙・ Ⅰ
報告 ………………………………………………………… 9 Ⅱ 討議 ………………………………………………………
125 【論文】神功開寳考 一銭径と重量から読み解く貨幣政策― 【目次】 『古代武器研究』 Vol. 19 の刊行にあたって 【論文】 目 次 【紹介文】 埴輪はいつ、どうして生まれ、どんな種類のものがつくられ、なぜ 【目次】 第1章 埴輪に注目した先人たち 第2章 埴輪のはじまり・広がり・おわり 第3章 埴輪の役割 第4章 器財埴輪と動物埴輪 第5章 人物埴輪をめぐって 第6章 埴輪の製作 あとがき 和歌山県立紀伊風土記の丘令和6年度特別展 「数多の古墳を築く 一群集墳 世界各地の旧石器時代女性小像や、線刻画にみる女性象徴を集成し、 【本書の主な目次】 序論 ヴィーナスの始原を求めて 第Ⅰ部 上黒岩の女性象徴 第Ⅱ部 旧石器時代の女性象徴 後論 旧石器時代の女性象徴とは何だったのか 集成 旧石器時代の女性象徴 総論 1 古代 2 中世 3 近世 4 近代 ドローンで洞窟遺跡を撮ってみた! 【目次】 第1章 第2章 第3章 【内容紹介】 考古学・博物館資料のデジタル化は記録、保存、公開共有の新しい 【目次】 2 博物館DX の実践と展開 3 最新のDX技術 【ご案内】 【目次】 ごあいさつ …………………………………………………… 3 発刊の辞 ※2024年11月16日・17日に開催のシンポジウム「東日本における土器 ………………………………………………………………………………… 出土土器からみた古墳の年代(追加分) 2024年11月16日・17日に開催されたシンポジウム「東日本における 目 次 第1分冊 第2分冊 【目録】 論文 翻訳 研究ノート 資料紹介 目次 日程 目 次 活動・出版物の記録 【目次】 ……………………………………………………………………………… 和歌山県立紀伊風土記の丘令和6年度特別展 「数多の古墳を築く 一群集墳 (韓国語題目)が表記できませんので以下のURLから全体目次と 目 次 中近世の城づくり
高田 徹 ………… 1 ………………………………………………………………………………… 『筑前国 怡土城成れり」その実像をめぐって 松尾洋平 ………… 75 ごあいさつ(抜粋) 【ご案内】 【目次】 ご挨拶 【内容簡介】 国防と外交、西海道の統治を司った大宰府。倭王権と古代豪族との関係、 【目次】 第Ⅰ部 九州の古代豪族と倭王権 第Ⅱ部 筑紫における大宰府の成立 終章 大宰府成立史のまとめと今後の課題 【開催趣旨】 【書評】 英文概要 【内容紹介】 【目次】 第二章 生業と社会の様相 第三章 生活と文化・習俗の背景 第四章 祭祀・儀礼の系譜と展開 第五章 宗教と信仰の実相 滋賀県立安土城考古学博物館 大道和人著 【目次】 第1章 日本古代製鉄の研究動向 【ご紹介】 【内 容】[展示会案内より] 伊都国歴史博物館は、今秋開館20周年を迎えます。 【目 次】[章立]〕 第Ⅰ章 集落・墳墓の展開とマツリ 【内 容】 古墳時代を通じた古墳編年と時期区分の再構築を目的として、 〈基調報告〉 第Ⅱ部 土器編年の検討 ──目 次───────────────────────── 〈史料紹介〉 〈研究展望・動向〉 〈連 載〉 〈書 評〉 〈新刊紹介〉 目次
「『続日本紀』記載の古代山城―茨城と常城の輪郭」 目 次 ≪古代学への提言 93≫ 公開講演録 1 目的 古墳時代から飛鳥時代には、様々な器物に関して製作技術の受容・ 土師器・須恵器・埴輪・瓦磚は、これまでの研究・展示では個別独立して
目 次 列島国制史の根本的諸問題(Ⅱ)古代中国帝国主義の列島支配と 弥生時代玄界灘沿岸地域の外来系土器の年代と以東の併行関係 纒向遺跡第195次調査SK38土坑から出土した植物および昆虫類について ミロク谷石棺を対象とした三次元計測 編集後記 【内容紹介】 身近な遺跡データから読み解く縄文社会の資源利用 【目次】 序章
縄文時代における資源利用技術研究の射程 第1章 問題の所在:縄文時代の資源利用と社会 第2章 方法論の検討:縄文時代石器の研究 第3章 九州縄文時代磨製石斧の動態 第4章 九州縄文時代打製石斧の動態 第5章 九州縄文時代縦長剥片石器の動態:博多湾沿岸地域の分析 第6章 九州縄文時代資源利用の石器モデル:分析結果の統合 第7章 遺跡立地変遷と石器モデル:博多湾沿岸地域の分析 第8章 議論:資源利用技術からみた九州縄文時代社会 終章
結論と展望 付表 【紹介文】 埴輪のきほんを網羅した入門書。 「踊る埴輪」は、じつは踊っていない? 東京国立博物館の研究員が、埴輪の種類や役割、歴史、つくり方など、専 【目次】 はじめに――はにわとは? I
はにわの種類 II
はにわの歴史と古墳 III はにわのつくり方 IV
はにわの研究 おわりに――わたしとはにわ 古墳時代とはにわの年表 【紹介文】 日本列島の西端、長崎県佐世保市の山間にある福井洞窟は、旧石器時代 【目次】 第2章 姿をあらわした福井洞窟 第3章 福井洞窟をふたたび掘る 第4章 狩猟採集民と福井洞窟 第5章 保存と活用の展望 【紹介文】 江戸時代の城が蘇ったら素晴らしいかもしれない。しかし、そこには 【目次】 Ⅰ 名古屋城天守木造化のゆくえ プロローグ 近世城郭の到達点、名古屋城 Ⅱ 各地の城郭復元・修復事情 プロローグ 観光立国と文化財保護 あとがき 農耕社会が安定期に入った弥生時代中期、大陸より祭器や副葬品として 【目次】 競合と交易の時代へ―プロローグ 変わりゆく弥生社会 金属器の伝達者 東北アジアの粘土帯土器文化 環黄海交易ネットワークの形成 政体の交代と楽浪郡 東アジア世界への参入 連動し続ける東北アジア社会―エピローグ あとがき 道具を使って文字を書く―。今日では当たり前の行為である筆記の 【目次】 人類と文字 東アジアの文字とその歴史 書くという行為 墨書を彩る道具たち 古代文房具を使用した人々と社会 文字と文房具と古代国家―エピローグ あとがき 【紹介文】 【目 次】 第2章 伊都国形成期の糸島 第3章 三大王墓と伊都国の墓制 第4章 伊都国の国邑 第5章 王都をとりまく拠点集落群 【目 次】 1 内蒙古・長城地帯におけるスキト・シベリア青銅装飾品の 目次/lndex 【目 次】 流雲文縁方格規矩鏡の編年1(下) 一つの木簡史料を加えての備前国東部郡界の再考と 中攻掩体に関する考古学的研究 魏晋南北朝時代の「馬俑」について(下) 大 平 理 沙 …… 117 土生田純之君の急逝を悼む
小 田 富士雄 …… 143 【内容簡介】 2019年7月6日、百舌鳥(もず)・古市(ふるいち)古墳群が世界遺産に 序 年譜 ………………………………………………………………………
7 編集後記 【紹 介】 もくじ 目 次 特輯 古代ギリシア史研究の現在地(3) 王権と帝国
藤井
崇:特輯「古代ギリシア史研究の現在地(3)王権と帝国」 目 次 執筆者一覧 特輯 古代ギリシア史研究の現在地(3) 王権と帝国
藤井
崇:特輯「古代ギリシア史研究の現在地(3)王権と帝国」 目 次 第3章 考古学と民族学・民俗学・地理学・ ・石井龍太 【目次】 光石鳴巳・山本 誠・白石 純・森先一貴 中園
聡・平川ひろみ・太郎良真妃・春成秀爾・中川 渉 神野
恵・河西 学・篠宮 正
目 次 発表1 大阪府「柏原市大県郡条里遺跡の調査 【紹介文】 ─────────────────────────────── 第2章 縄文のタイムカプセル 第3章 縄文編みかごの世界 第4章 東名縄文ムラ 第5章 東名遺跡のこれから 【内容簡介】 【目次】 第1章 交差資料からみる日韓古墳の編年と年代観 第2章 百済漢城期の土器編年再考 第3章 鉄製凹字形刃先考 第4章 筒形銅器考 第5章 金海大成洞古墳群出土の倭系遺物考 第6章 良洞里古墳群出土の倭系遺物考 第7章 海を渡った馬形帯鉤 第8章 韓半島出土の倭系甲冑からみる日韓関係 第9章 高句麗の南進と百済そして倭 第10章 「倭の五王」遣使伴う倭系古墳 第11章 長鼓墳(前方後円形古墳)出現の歴史的背景 終章 古墳時代前半期の日朝関係 【内容簡介】 北米民族誌との比較による縄文社会像復元へのあらたなアプローチ 目 次 武庫川回廊と甲山黒色ガラス質安山岩Aについて 目次
目次 著者一覧 ………………………………………………………………………277 序 京都平野の前期初頭の首長墓としては福岡県苅田町の石塚山古墳が挙げ 令和5(2023)年12月27日 …………………………………………………………………………………… 【本文目次】 第1章 遺跡の位置と環境 〔参考資料〕 第3章 調査の成果 第4章 出土遺物 付章 あとがき …………………………………………………………………
82 【目 次】 筑前における集落と古墳の動態 筑後における集落と古墳の動態 肥前東部 …………………………………………………… 79 長崎県本土部 ……………………………………………
109 豊前地域における集落と古墳の動態―総括― ………… 163 豊前南部・豊後における集落と古墳の動態 …………
201 日向(宮崎県域) ………………………………………… 225 大隅・薩摩地域における弥生時代終末期から飛鳥時代の集落 ……………………………………………………………………… <残部少> ●81149 集落と古墳の動態 Ⅲ 【目次】 開催趣旨・例言・日程 辻田淳一郎 谷澤亜里 西嶋剛広 齋藤大輔 桃﨑祐輔 参考資料 ………………………………………………………………227 【紹介文】 横浜市北部に位置する大塚・歳勝土遺跡は、集落の全体像がわかる プロローグ 大塚・歳勝土遺跡とは 第1章 環濠集落・大塚遺跡 第2章 墓域・歳勝土遺跡 第3章 弥生集落の研究へ 第4章 発掘から保存まで 【内容簡介】 縄文土器・弥生土器・土師器の焼成方法は、古くは全て野焼きである はじめに…………………………………………………………………1 考古学に人生を捧げた泰斗が綴る、日本考古学の原点と発展のあゆみ はしがき Ⅱ 雑誌、辞(事)典、地域史を編む場 (1)編集委員の眼-「雑誌」編集に Ⅲ 動向 追悼 Ⅳ 八十路を辿る V 学史展望 あとがき 【概略】 第Ⅰ章 匈奴の歴史 大阪の名刹として知られている四天王寺は、飛鳥時代の創建以来、現在 【目次】(章立て) プロローグ 四天王寺と古代王権 舘野和己 ………………
10 【概要】 前方後円墳出現の百年も前に築かれた本遺跡は、後の古墳時代到来に 【目次】 第1章 遺跡のある場所 第2部 遺跡の諸相―調査経過と祭祀の品々― 第7章 調査研究の経過 ●82022 三万田東原遺跡 九州縄文人のアクセサリー工房 ●82176 大宰府跡(新日本の遺跡 2) ○82254 旧相模川橋脚
関東大震災によって蘇った中世の橋
【目 次】 道後平野西部出土の銭貨 ………………………
山之内志郎 1 報告 【紹介文】 激動する古代東アジア情勢の中で、国防と対外交渉の拠点となった 第2章 大宰府の発掘 第3章 軍都・大宰府 第4章 政都・大宰府 第5章 大宰府の栄華 第6章 大宰府史跡 広瀬史学の集大成! 第2章 成立・展開・終焉 第4章 異質な文化の接触・共存 広瀬史学の集大成! 第5章 社会構成論 第6章 文化論 第7章 『日本書紀』と考古学 第8章 日本考古学の未来 広瀬和雄先生年譜・研究業績目録 【内容紹介】 【目次】 第2章 甲斐銚子塚古墳出現の背景 第3章 甲斐の方墳とその周辺 第4章 甲斐の横穴式石室 終章
律令社会への展望 【目次】 【論文】 関東大震災による液状化で地表に現れ、史跡と天然記念物の2つの性格 〈
本書の主 な目次 〉 第Ⅰ部 遺跡の概要―旧相模橋脚とは― 第1章 驚きの発見と保存への道 第Ⅱ部 遺跡のあゆみ―発掘調査が語るもの― 第3章 発掘調査の概要 ●82022 三万田東原遺跡 九州縄文人のアクセサリー工房 ●82176 大宰府跡(新日本の遺跡 2) 【論文】 【内容簡介】 日本における醗酵の起源が、弥生時代から古墳時代前半の「巻き包み」 【目次】 第Ⅰ部 技術史的考察 第1章 巻き包みとは何か 第Ⅱ部 文化史的考察 第1章 園芸の巻き包み 【内容簡介】 律令体制以前から地方豪族が構築していた歴史的支配の存在を踏まえ、 序にかえて 第一部 郡司と地域社会 第二部 「郡的世界」の実態を探る 【内容紹介】 古墳に樹立された器材埴輪群はなぜ埋葬施設側を向くものがあるのか? 第1章 問題の所在と本書の構成 【紹介文】 装飾品である貝輪は、そのかたち・色・艶・質感から古来より多くの 【目次】 第Ⅰ章 食用の貝と利器用の貝 第Ⅱ章 東日本における縄文時代の貝輪 第Ⅲ章 東日本における弥生時代の貝輪 第Ⅳ章 東日本におけるオオツタノハ製貝輪 第Ⅴ章 九州地方における縄文時代の貝輪 第Ⅵ章 南西諸島におけるオオツタノハ製貝輪 第Ⅶ章 考古学・生物学的調査が明かすオオツタノハ製貝輪の実態 【紹介文】 海を越えていくつもの文化が交錯し発展を遂げたオホーツク海沿岸の 目次 第1章 北の海に暮らした人びと 第2章 東北アジア世界と北海道 第3章 東北アジア考古学と常呂 第4章 常呂の遺跡とともに むすびにかえて
<目次> 第2章 円弧状なめくりたがねと移動する渡来系工人ネットワーク 第3章 日本書紀の物語-大王・渡来系工人・在来工人のあつれきー 第4章 線刻鉄刀と象嵌技術 第5章 移動する渡来系工人ネットワークのひろがり 付録 金工技術カタログ その1<115~ > 【内容ご紹介】 家形埴輪は、埴輪が古墳上に配置された全期間にわたって存続した 【目次】 古墳時代並行期の日韓の社会と考古資料…………………山本孝文
14 生活と祭祀の基礎資料 日韓の武器・武具・馬具 支配者の象徴的器物と身体装飾 古墳と葬送祭祀 韓半島の中の倭系文物 目 次 栃木県栃木市小野巣根古墳群4号墳出土の埴輪 中国地方の形象埴輪配置 …………… 林 弘幸(16) 第21回研究大会討議の記録 ……………………(60) ………………………………………………………………… 目 次 【研究発表】 玉製作遺跡の発掘調査とその成果-三万田東原遺跡の事例から- … 39 張 睿帆:唐代定窯での細白磁生産について 【内容簡介】 郡衙遺跡を中心に、地方官衙の構造と展開の様相を考古学的に検証。 【目次】 序 章 本書の構成 第1章 国郡制に関する考古学的研究 第2章 地方官衙遺跡に関わる事例検討 第3章 郡衙正倉に関わる諸問題 終 章 郡衙研究の成果と課題 【内容簡介】 序 章 出雲古代史研究と本書の概要 第Ⅱ部 古代出雲国の部民制・氏族と交流 第Ⅲ部 『出雲国風土記』と古代出雲の実態 【内容簡介】 大きく変わりつつある博物館について、その基礎知識を整理し、 【目次】 ◇本書の執筆者(執筆順) 第Ⅰ部 博物館の概念とその基盤 【内容簡介】 人類はミルクをいつからどのように利用してきたのか。考古生化学の進展 【目次】 【目 次】 大和の大型横穴式石室にみられる構築技法の系譜 ≪シリーズ遺跡紹介16≫ 大阪府高槻市上牧遺跡の調査………笹 栗 格 41 ≪古代学への提言 91≫ 考古学は共同主観的創造上の秩序にどこまで迫れるのか?
【内容簡介】 第一章 秦漢封泥とは
谷 豊信 3 第一章 秦の文官のリテラシー 第一章 秦帝国の形成と秦郡の変遷 鶴間和幸 121 目 次 ─────────────────────────────
上巻 目次 序 ………………………………………宮本一夫先生退職記念事業会 下巻 目次 日本における古墳時代天井壁画からの考察………………………福田匡朗 501 編集後記………………………………………宮本一夫先生退職記念事業会
1009 【目 次】 序文 ……………………立正大学特別栄誉教授 坂誥 秀一
i 【内容】(本書より) 【目 次】 目 次 ≪特集 2022年度拡大例会シンポジ ≪古代学への提言 89≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 古代の九州諸国を統括しつつ、平時には外交、戦時には国防の最前線を はじめに―大宰府の先進性と辺境性 第Ⅰ部 遺跡の概要―大宰府跡とは― 第1章 大宰府の環境 第4章 大宰府跡の発掘調査 あとがき 【紹介文】 海を越えていくつもの文化が交錯し発展を遂げたオホーツク海沿岸の 目次 第1章 北の海に暮らした人びと 第2章 東北アジア世界と北海道 第3章 東北アジア考古学と常呂 第4章 常呂の遺跡とともに むすびにかえて 【紹介文】 明治年間、秋田県で農作業中の水田から杉の角材が隙間なく列を 【目次】 第1章 謎の城柵の発見 第2章 払田柵跡を掘る 第3章 出土文字資料は語る 第4章 払田柵跡の正体を探る 【内容】 古墳はまぎれもなく墓であり、そこには被葬者の性格や社会関係だけで 序 章 本書のねらいと立場 【内容】 Ⅰ 論 考 佐藤 宏之 縄文草創期の範囲について 【内容紹介】 著者のライフワークである弥生時代の社会のあり方を展開する最新 第1章 本書のねらいと構成 第2章 弥生時代中期における青銅器生産の定着と展開 第3章 弥生時代後期における青銅器の拡散 第4章 弥生社会における青銅器生産の位置づけ 第5章 青銅器の生産からみる弥生社会 【ご紹介】(HPより抜粋) 伊都国歴史博物館では冬季特別展として、東京国立博物館が所蔵する、日本列島 青銅器部分名称・展示品出土地・主要展示品 目 次 執筆者一覧 この図録は、奈良県立橿原考古学研究所附属博物館において令和5(2023) 目次 目 次 【資料集成】 目 次 目 次 目 次……………………………………………………………………ⅲ 文化遺産と文化財 -文化遺産学概説 備忘- 木許守さん略年譜 ……………………………………………………135 【本書目次】 ■第2章 弥生文化とその周辺 ■第3章 北東アジアの古墳文化 ■第4章 古代統一国家群の諸相 ■第5章 中・近世の東アジア ■第6章 シルクロードの考古学 ■第7章 東アジア考古学の諸問題 ■第8章 北東アジアの世界文化遺産 目 次 <出版社HPより> <出版社HPより> <出版社HPより> 巻頭言 【内容簡介】 ■本図録は黒川古文化研究所における第130回展観「魏晋南北朝の 出土銭貨研究会の会長就任にあたって ……… 松
村 恵 司 1 目 次 報告 紙上報告 目 次 【総合計議】 …………………………………………………………95 目 次 【ポスター発表要旨】 目 次 *********************************************************** 平成25年(2013)、福岡県古賀市の船原古墳に隣接した土坑に ・総 論 船原古墳の調査・研究最前線 【内容簡介】 漢の皇帝に「漢委奴国王」の金印を授けられた王が君臨し、 【目次】 第1章 奴国の王都 第2章 須玖岡本王墓と王族墓 第3章 奴国の王宮にせまる 第4章 弥生時代のテクノポリス 第5章 これからの須玖遺跡群 無刻突帯文系土器群の研究 幸 泉 満 夫 …… 1 論文
墓地からみた北部九州初期弥生社会 翻訳 研究ノート
目 次 南島先史時代の石製玉類出現の背景 ……………………………… 8 今回取り上げる円筒埴輪とその仲間たちは、土管のような筒状で 目 次 1.問題提起 2.研究発表 3.紙上報告 【目 次】 〔追悼文集〕 〔橘昌信先生年譜・業績一覧〕 ……………………………………429 【紹介】 【内容簡介】 なぜ先史時代の人々は海峡を越えてまで交流することを求めたのか。
目 次 第3章 すべては自然環境から始まる ………………………………29 第4章 土器から見える交流の世界 …………………………………39 第5章 土器文化の融合と分離………………………………………103 第6章 石器・骨角器はどのように伝わったか……………………133 第7章 装身具はなぜ広域に伝わるのか……………………………179 第8章 交流と先史社会の構造の変化………………………………211 参考文献 225 【内容簡介】 東部ユーラシアにおける〈交通〉のなかで日本の古代国家はいかに 【目次】 【内容簡介】 律令国家が成立する過程で、古代大和の宮都空間はどのように 【目次】 序 章 飛鳥から藤原京そして平城京へ 【内容簡介】 律令制下、九州諸国の総管・防衛・外交など多機能を有した 【内容簡介】 全国的な統治が進んだ古墳時代、大王家や豪族などの 半世紀にわたる著者の考古学研究から著された、モノに 1
遺物論 【内容簡介】 【内容簡介】 「邪馬台国」はどこにあったのか。江戸時代から続く邪馬台国論争は、 【目次】 はじめに 【内容簡介】 本書は令和五年9月30日から12月3日の間に開催する秋季特別展 ……………………………………………………………………………… 目 次 Ⅰ 律令制下の交通体制 【内容簡介】 本書『琉球諸島の歴史人類学-信仰と習俗の民族誌』は、従来の 【目次】 《文字化けがございますので原文紹介はこちらをクリックしてご覧いただけます(PDF)》 群馬県南西部には、イタリア・ポンペイのように、榛名山噴火の 【目次】 第2章 館の構造を読み解く 第3章 遺物が語るもの 第4章 聖水祭祀 第5章 古墳時代の地域社会 第6章 三ツ寺Ⅰ遺跡の首長像 【紹介文】 7世紀後半から9世紀にかけ、律令国家は蝦夷の激しい抵抗を受けな 目次 第2章 木炭窯を掘る 第3章 製鉄炉を掘る 第4章 製鉄経営の解明 第5章 律令国家の対蝦夷政策 第6章 その後の製鉄遺跡 【内容紹介】 いくつもの論争が弥生文化研究を進化させてきた。 【目次】 1 論争とは何か―論争の機能と構造とは 【投稿論文】 英文概要 【内容簡介】 埴輪生産遺跡はどのような背景のもとにそこで営まれたのか。 …………………………………………………………………………… 第Ⅰ部 拡大例会・シンポジウム記録集 第Ⅱ部 考察 第Ⅲ部 誌上報告 第Ⅳ部 総括 第Ⅴ部 埴輪生産関連遺跡集成 …………………………… 371 後 記 …………………………………………………… 384 縄文時代から古墳時代にかけて、九州地方における考古学研究の主要な …………………………………………………………………………………… 総論 1 縄文時代 2 弥生時代 3 古墳時代 《文字化け箇所があるため原文紹介はこちらをクリックしてご覧ください(PDF)》 紙上報告 ……………………………………………………………………………… 目 次(第1分冊) 【本大会での年代観について】 ★第24回九州前方後円墳研究会大分大会土器検討部会 ★山崎賴人※・杉本岳史※・一木賢人※・作山航平※・三津山靖也: 【★ありは第24回大会発表者、★なしは誌上報告者】 紀元前10世紀頃、無文土器文化との接触により九州北部の 【目 次】 01 弥生文化とは? 弥生時代とは? 訪ねてみたい弥生文化関連遺跡
【2026年2月22日 【入荷】
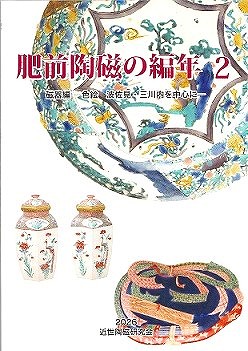
書籍番号
82908
書 名
肥前陶磁の編年 2 磁器編 色絵
-波佐見・三川内を中心にー
シリーズ
(近世陶磁研究会
第14回大会冊子)
データ
A4 379頁
ISBN/ISSN
編著者
出版年
2026年2月
出版者
近世陶磁研究会
価 格
5,500円(税込)
肥前陶磁概論(磁器中心に)[再掲〕
………………………………………… 1
肥前
有田の色絵・色絵素地(碗・皿)
…………………………………… 5
肥前
鉢・猪ロ・蓋付鉢・合子・水指・蓋置・薬壺(色絵以外) ………
57
肥前 香炉・火入・灰落し
………………………………………………… 93
肥前
仏飯器・水滴・人形・灯火具・緒締玉・戸車 …………………… 101
肥前
瓶・花生・仏花器・油壺・水注 …………………………………… 113
肥前
壺・唾壺 ……………………………………………………………… 141
肥前
波佐見 ………………………………………………………………… 157
肥前
平戸・三川内 …………………………………………………………
189
西日本の消費地遺跡の年代が判る資料ー肥前色絵波佐見・三川内を中心に一
……………………………………………………………………………
215
消費地遺跡の年代が判る資料-江戸遺跡を中心に ……………………
281
参考資料 肥前陶磁古窯跡関係報告書等一覧 ……………………………
372
※「肥前陶磁概論(磁器中心に)」は、近世陶磁研会 2025
「肥前陶磁の編年
1
磁器編ー碗・皿を中心に-」に掲載したものを、本書の利便性を勘案
し再掲した。
※資料作成については、執筆担当者が作成し、事務局が編集した。
※資料の中には未発表資料もあり、本資料から論文等に引用される場合は、
必す各資料の執筆者に照会されたい。
【2026年2月12日 【入荷】

書籍番号
82903
書 名
群集墳からみた播磨
シリーズ
(第25回播磨考古学研究集会 資料集)
データ
A4 238頁
ISBN/ISSN
編著者
第25回研究集会実行委員会編集
出版年
A4 238頁
出版者
第25回研究集会実行委員会
価 格
3,000円(税込)
本書は、2026年2月7日開催の第25回播磨考古学研究集会「群集墳
からみた播磨」の当日資料集です。
この資料集は、地域報告および
基調講演資料を各々担当者が作成、加えて群集墳を集成した資料編
の二部構成になっています。
【地域報告資料】
「讃容、赤穂郡域」…………………………………島田 拓… 1
「宍禾・揖保・神前・餝磨郡域の群集墳」………中濱 久喜… 7
「印南・賀古・賀毛・託賀の群集墳」……………山本 原也…20
「明石・美嚢郡域」…………………………………中久保辰夫…30
【基調講演資料】
「群集墳と古墳時代後期の社会」 …………………太田
宏明…42
【群集墳資料集成】
佐用町(讃容郡)
…………………………………………………(資1)
赤穂郡上郡町(「赤穂郡」)
……………………………………(資2)
赤穂市(「赤穂郡」)
……………………………………………(資4)
相生市(「赤穂郡」)
…………………………………………(資19)
たつの市南部(揖保郡)
………………………………………(資20)
揖保郡太子町(揖保郡)
………………………………………(資38)
姫路市西部(揖保郡)
…………………………………………(資44)
たつの市北部(揖保郡)
………………………………………(資61)
宍粟市(宍禾郡)
………………………………………………(資79)
姫路市(飾磨郡)
………………………………………………(資85)
神崎郡神河町(神前郡) ………………………………………(資109)
加古川市(賀古・印南郡) ……………………………………(資110)
高砂市(印南郡) ………………………………………………(資118)
加西市(賀毛郡) ………………………………………………(資119)
小野市(賀毛郡) ………………………………………………(資136)
加東市(賀毛郡) ………………………………………………(資143)
西脇市(託賀郡) ………………………………………………(資151)
多可郡多可町(託賀郡) ………………………………………(資164)
三木市(美嚢郡) ………………………………………………(資169)
神戸市(「明石郡」) …………………………………………(資177)
【2026年2月12日 【入荷】
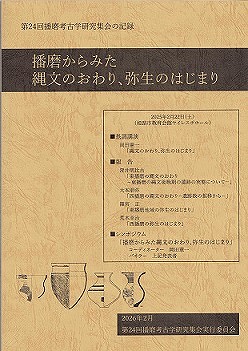
書籍番号
82904
書 名
播磨からみた縄文のおわり、弥生のはじまり
シリーズ
(第24回播磨考古学研究集会の記録)
データ
A4 157頁
ISBN/ISSN
編著者
第24回研究集会実行委員会編集
出版年
2025年8月
出版者
第24回研究集会実行委員会
価 格
2,200円(税込)
本書は2025年2月22日(土)に開催した第24回播磨考古学研究集会「播磨
からみた縄文のおわり、弥生のはじまり」の記録集です。
【講演・報告資料】
報告1
深井明比古「東播磨の縄文のおわり
ー東播磨の縄文後晩期の遺跡の実態についてー ……… 21
までの遺跡動態」…………………… 29
報告3 篠宮 正 「東播磨地域の弥生のはじまり」
……………… 53
報告4
荒木幸治 「西播磨の弥生のはじまり」 ……………………
79
【シンホジウム記録】
「播磨からみた縄文のおわり、弥生のはじまり」 ………………… 115
【資料集成補遺】
………………………………………………………… 145
【2026年2月9日 【入荷】
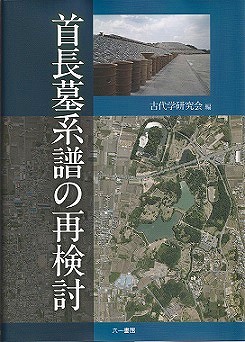
書籍番号
82902
書 名
首長墓系譜の再検討
シリーズ
データ
B5 303頁
ISBN/ISSN
978-486445-191-8
編著者
古代学研究会編著
出版年
2025年8月
出版者
六一書房
価 格
5,500円(税込)
古墳時代では、歴代の首長が一定の範囲に墳墓を営む状況がみられ、これが
首長墓系譜と呼ばれてきた。本書は、各地の首長墓系譜の中で墳丘築造企画、
副葬品組成、埋葬施設構造がどのように継承されていたのか検討を行い、そ
こから古墳時代における首長位の継承の問題に迫ったものである。
古代学研究会2022年度拡大例会シンポジウムをもとにした成果報告書。
第Ⅰ部 拡大例会シンポジウムの記録集
〈趣旨説明〉
開催趣旨
………………………………………………………………太田宏明
3
〈基調講演〉 …………………………………………………………田中晋作
5
古墳時代の政権構造と首長墓系譜
〈報告〉
埋葬施設からみた古墳時代前期・中期の首長墓系譜
……………上田直弥 35
埋葬施設からみた古墳時代後・終末期の首長墓系譜
……………太田宏明 63
副葬品からみた古墳時代前・中期の首長墓系譜 …………………岩本 崇
101
副葬品からみた古墳時代後期の首長墓系譜 ………………………絹畠 歩
121
墳丘築造企画からみた首長墓系譜 …………………………………木許 守
149
岩橋千塚古墳群における首長墓系譜 ……………………………瀬谷今日子
173
日本中世前期の在地領主・在地集団・家 …………………………永野弘明 195
―シンポジウム「首長墓系譜の再検討」に寄せて―
九州地域の首長墓群 …………………………………………………藏冨士寛
215
―埋葬施設からみた九州中・北部地域の首長墓系列―
横穴式木室にみる集団性と首長層の地域交流
…………………田村隆太郎 235
東海地方の横穴墓における首長墓系譜 ……………………………大谷宏治
251
下野地域南部における首長墓系譜の再検討 ………………………荒井啓汰 271
―しもつけ古墳群の横穴式石室を中心に―
総括
……………………………………………………………… 太田宏明 295
【2026年2月5日 【入荷】

書籍番号
82896
書 名
九州旧石器
第29号 黒曜石・安山岩・流紋岩
シリーズ
―石器石材が物語る旧石器時代像―
データ
A4 136頁
ISBN/ISSN
編著者
日高優子(宮崎県旧石器文化談話会)編集
出版年
2025年12月
出版者
九州旧石器文化研究会
価 格
3,000円(税込)
…………………………………………………………………………………
1.黒曜石・安山岩・流紋岩
一石器石材が物語る旧石器時代像ー(第51回
九州旧石器文化研究会
予稿集)
堤 隆「黒曜石が語る旧石器時代人像」……………………
1
隅田 祥光「波長分散型XRFとエネルギー分散型XRFを利用した
黒曜石製石器原産地判別法の体系化」………
9
[基調報告]
辻田 直人「土黒川流域の石器石材と集落遺跡」………………
19
越知 睦和「九州の安山岩製石器からみた行動領域」…………
35
沖野 誠・桑村 壮雄「祖母・傾山系流紋岩からみた行動領域」 47
馬籠 亮道・寒川 朋枝「南九州における石器石材と行動領域」
59
越知 睦和「佐賀県の動向」
高橋 央輝「長崎県の動向」
赤池 麗樹「熊本県の動向」
桑村 壮雄「大分県の動向」
藤木 聡「宮崎県の動向」
馬籠 亮道「鹿児島県の動向」
金城 翼「沖縄県の動向」
藤木 聡「東南九州の旧石器時代から縄文時代における水晶利用
の変遷と特質」 ……………………………………
95
日高 優子「丸州山地南端部における石器石材整理の試み―
―チャート・珪質石材を中心に―」
……………
109
大場 正善「小型ナイフ形石器と小型台形石器の
プランティング」
……………………………… 121
【2026年1月25日 【入荷】
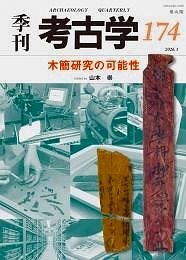
書籍番号
82886
書 名
季刊 考古学 第174号 特集 木簡研究の可能性
シリーズ
データ
B5 124頁
ISBN/ISSN
978-4-639-03102-4
編著者
桑門智亜紀編集
出版年
2026年2月
出版者
(株)雄山閣
価 格
2,640円(税込)
令和の木簡研究…………………………………………………山本 崇
14
古代における記録木簡と帳簿 … …………………………… 武井紀子
19
中世の木簡 … …………………………………………………
佐藤亜聖 23
近世の木簡
…………………………………………………… 岩淵令治 27
平城宮東大溝出土の「考文付札」をめぐって ……………
桑田訓也 31
考古学的視点からみた木簡研究の可能性
……………… 浦 蓉子 35
国語学からみた木簡 …
………………………………………犬飼 隆 39
文学からみた木簡 …………………………………………
井上さやか 41
木簡の保存処理 ………………………………………………
松田和貴 47
木簡と貝類
……………………………………………………… 山崎 健 51
木簡研究における記録写真の歴史 … ………………………
中村一郎 55
木簡研究とIIIF
………………………………………………… 垣中健志 59
三次元計測が照らし出す、木簡研究の可能性……………… 山本祥隆
63
削屑調査の可能性
…………………………………………… 藤間温子 67
【コラム】木簡の樹種同定 …………………………………
藤井裕之 71
多賀城跡木簡
…………………………………………………… 吉野 武 73
古代但馬の出土文字資料 ……………………………………… 山本
崇 77
長登木簡と日本古代の銅生産
……………………………… 黒羽亮太 81
大宰府木簡 ……………………………………………………
酒井芳司 86
最近の発掘から
須玖岡本遺跡岡本地区28次調査の甕棺墓
―福岡県春日市須玖岡本遺跡― ………………………… 井上義也 91
初源、そして連続と断絶―日本列島の旧石器文化観―
… 森先一貴 95
細石刃-希望のかけらを手に …………………………………
堤 隆 101
書評/論文展望/報告書・会誌新刊一覧/考古学界ニュース
【2026年1月25日 【入荷】
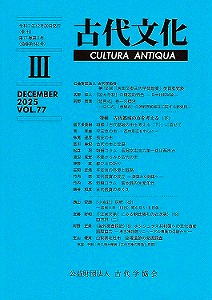
書籍番号
82882
書 名
古代文化 第77巻 第3号(642号)
シリーズ
特輯 古代都城の市を考える(下)
データ
B5 132頁
ISBN/ISSN
0045-9232
編著者
出版年
2025年12月
出版者
古代学協会
価 格
2,970円(税込)
公益財団法人 古代学協会
第12回「角田文衞古代学奨励賞」受賞者発表
髙野
柾人:「国大寺制」の構造的特色―日中比較試論―
前野
智哉:『延喜式」巻ーの標注
―「弘仁式」「貞観式」の神祇祭祀規定に関する新史料―
……………………………………………………………………………
特輯 古代都城の市を考える(下)
國下多美樹:特輯「古代都城の市を考える(下)」に寄せて
南 孝雄:平安京の市―西市周辺を中心に―
妹尾 孝雄:長安の市
宮川 麻紀:古代の市と交易
松井 忍:特輯コラム
長岡京右京六条―坊は西市か
渡辺
晃宏:木簡からみる古代の市
神野
恵:都びとの祈り
古閑 正浩:平安京の外港と陸路
竹内
亮:古代銭貨の成立―銀銭から銅銭ヘ―
竹内 亮:特輯コラム
富本銭の生産年代
嶋谷 和彦:古代銭貨のゆくえ
……………………………………………………………………………
西山
史朗:『小右記』註釈(42)
―長和4年(1015)閏6月5、6日条―
近藤
好和:〈『江家次第』にみる朝廷儀礼の式次第〉(19)
四方拝(ニ)
村野
正景:〈海外調査探訪〉(8)ホンジュラス共和国への文化遺産
国際協力―考古博物館リニューアル事業の活動から―
生山
優実:山梨県北杜市垈場遺跡の発掘調査
水谷
千秋:舟久保大輔著『古代王権の神話と思想』
【2026年1月25日 【入荷】
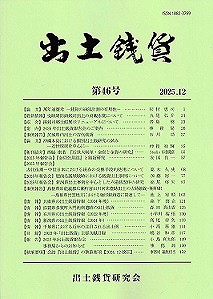
書籍番号
82884
書 名
出土銭貨 第46号
シリーズ
データ
B5 154頁
ISBN/ISSN
1882-3769
編著者
出土銭貨研究会編集
出版年
2025年12月
出版者
出土銭貨研究会
価 格
2,750円(税込)
【論文】萬年通寳考―銭貨の細部計測の有用性 ……… 松村 恵司
1
【最新情報】史跡周防鋳銭司出土の貞観永寳について… 丸尾 弘介
21
【紹 介】鋳銭司郷土館展示リニューアルについて ……青島 啓
23
【案 内】2026年出土銭貨報告会のご案内
………………事 務 局 26
【事例報告】茨城県内出土の古代銭貨 ……………………石川 功
27
【論 文】沖縄本島における個別出土銭研究の試み
―近世琉球を中心に― …………………… 仲程
祐輝 36
【新刊紹介】西脇康著『近世大判座・金座と金貨の研究』……
studi K5書籍部 55
【2025年報告会】『金局公用誌』と銭貨研究 …………
安国 良一 57
【2025年報告会】
古代後期ー中世日本における紙券の交換手段的使用について
高木 久史 68
【2025年報告会】肥前名護屋城跡における銭貨出土事例について
加藤 裕一 77
【2025年報告会】新潟県出土事例を中心とした六道銭習俗の研究
高尾 将矢 87
【事例報告】島根県旧能義郡広瀬町富田川河床遺跡出土の古鋳銀錠・
極印銀 ―島根県出雲地方における極印銀鋳造に関連して―
池上 宥昭 103
【情 報】兵庫県の出土銭貨情報(2024年度)
…………森下 真企 121
【情 報】滋賀県多賀町大門池南遺跡の出土銭貨 ………森田真由香
125
【情 報】石川県の出土銭貨情報(2022年度) …………小早川裕悟
130
【情 報】新潟県の出土銭貨情報(2024年)
…………高尾 将矢 133
【情 報】千葉県における近年の注目される出土例 …小高 春雄 141
【目 録】2023年「出土銭貨」主要文献目録
………嶋谷 和彦 147
【報 告】2025年出土銭貨報告会
……………………小島貢太郎 149
事務局からのお知らせ ……………………………事 務 局 150
【執筆要項】会誌『出土銭貨』の執筆要項【2024.12改正】…
事務局 編集担当 152
【2026年1月25日 【入荷】
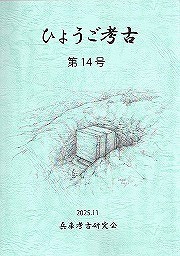
書籍番号
82885
書 名
ひょうご考古 第14号 附CD-ROM
シリーズ
データ
B5 94頁
ISBN/ISSN
編著者
兵庫考古研究会編集
出版年
2025年12月
出版者
兵庫考古研究会
価 格
1,430円(税込)
1はじめに ……………………………………………………………3
2石棺石材の名称 ……………………………………………………4
(1)竜山石
(2)高室石
(3)火山礫凝灰岩
3石材からみた家形石棺の分布
……………………………………5
(1)竜山石製石棺の分布
(2)高室石製石棺の分布
(3)火山礫凝灰岩製石棺の分布
(4)砂岩製石棺・凝灰岩質砂岩製石棺の分布
4家形石棺の型式分類 ……………………………………………10
(1)蓋石
(2)組合式石棺
(3)刳抜式石棺
(4)石櫃
5播磨の家形石棺 …………………………………………………15
(1)型式からみた播磨の家形石棺
(2)家形石棺の製作
(3)家形石棺製作終焉後の製品
6おわりに …………………………………………………………24
お世話になった機関と諸氏
参考文献
付載1石棺仏・非石棺仏 …………………………………………28
付載2中世の紀年銘を有する高室石製石造物 …………………36
編集後記
…………………………………………………………39
表紙解説
…………………………………………………………40
播磨の家形石棺計測一覧表
………………………………………41
播磨の家形石棺略測図
……………………………………………64
【2026年1月21日 【近刊】
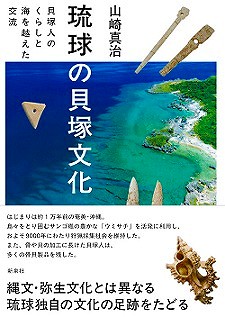
書籍番号
82881
書 名
琉球の貝塚文化 貝塚人のくらしと海を越えた交流
シリーズ
データ
A5 264頁
ISBN/ISSN
978-4-7877-2509-7
編著者
山崎 真治著
出版年
2026年2月
出版者
新泉社
価 格
3,300円(税込)
はじまりは約1万年前の奄美・沖縄。
貝塚人は、島々をとり囲むサンゴ礁の豊かな「ウミサチ」を活発に
利用し、およそ9000年にわたり狩猟採集社会を維持し、多くの骨貝
製品を残した。南海産大型巻貝は弥生文化の貝製腕輪の素材として
好まれ、膨大な数の貝が本土に運ばれた。
「くらし」と「交流」を軸に、縄文・弥生文化とは異なる、もう一つ
の先史文化の足跡をたどる。
プロローグ――貝塚文化とはなにか
1 琉球貝塚文化の視点
2
貝塚文化をとりまく環境
3 サンゴ礁が育んだ貝塚
4「貝塚人」のなりたち
5
貝塚文化のタイムライン
1 貝塚文化研究の嚆矢
2
米軍統治下での学術研究
3
貝塚時代の編年と研究の進展
1 貝塚文化前史――琉球の旧石器文化
2 貝塚時代の幕あけ
3
貝塚文化の隆盛
4 貝塚人のくらし
5 葬墓制と貝塚人のコスモロジー
6 奄美群島・先島諸島の文化的特色
1
琉球のアウトバウンド・コネクション
2
琉球の域内サプライ・チェーン
3 弥生貝交易の時代
4 古代ヤコウガイ交易
1
拡張する中世世界
2 変容する文化、継承される文化
貝塚文化のおもな遺跡
主要参考文献
【2026年1月21日 【近着】

書籍番号
82865
書 名
海に眠る古伊万里―水中考古学からアプローチ―
シリーズ
データ
A5 216頁
ISBN/ISSN
978-4-639-03103-1
編著者
野上 建紀著
出版年
2026年1月
出版者
(株)雄山閣
価 格
3,850円(税込)
四半世紀にわたる水中考古学調査をもとに、国内外の海中・海浜などから
発見された肥前磁器を紹介し、肥前磁器の生産と流通、積み出し港と貿易
路など陶磁器研究における水中考古学の意義と可能性を明らかにする。
第1章 海と陶磁器、考古学
土器の誕生と陶磁器/陶磁器と水中考古学/タイムカプセルとしての沈没
船 ほか
水中遺跡ができるまで/水中考古学のあけぼの/元寇船の発見/中世以前の
遺跡と近世以降の遺跡/海底遺跡の土地は誰のもの?
ほか
肥前陶磁の誕生/大量輸出時代/国内市場の開拓/展海令後の海外の磁器市
場 ほか
伊万里津への道/旅陶器/海外向け製品と積出港
ほか
動き出す陶磁器、漂着のメカニズム/東シナ海―吹上浜/瀬戸内海―陶片狂
コレクション/太平洋―興津海浜遺跡/日本海―珠洲の海と海岸/北海道―
松前町小松前 川河口
ほか
伊万里湾―鷹島海底遺跡/玄界灘―池尻海底遺跡/瀬戸内海―下荷内島沖/
日本海
―タラバ/太平洋―神津島沖海底遺跡/東北―陸奥湾脇野沢沖/北海
道―上ノ国漁港遺跡 ほか
肥前磁器の貿易路/スペイン船/ポルトガル船とインド洋の船
ほか
ヨーロッパ船籍の船/その他のオランダ連合東インド会社の船/スウェー
デン東インド会社の船 ほか
水中公園/海底遺跡の見学方法/海底遺跡ミュージアム構想/水中の戦争遺
跡と墓標 ほか
【2026年1月19日 【入荷】

書籍番号
82880
書 名
古墳出現期土器研究 第12号
シリーズ
データ
A4 86頁
ISBN/ISSN
編著者
古墳出現期土器研究会編集
出版年
2025年12月
出版者
古墳出現期土器研究会
価 格
1,100円(税込)
巻頭言
畿内第六様式の再検討
………………………………………田中 元浩 1
―「庄内式」提唱60年に寄せて―
<論文>
布留式期における山陰系高坏の展開…………………………中野 咲 3
箸墓古墳出土土器と築造時期の関係
………………………杉山 拓己 27
庄内式期Ⅴ=布留式期Ⅰの認識整理と今後の課題…………米田 敏幸 41
―庄内式の終焉と布留式の開始について―
<研究ノート>
新沢一遺跡の特異な台付水差形土器…………………………西浦 煕 57
―附.大和盆地西南部と中河内間における交流関係の動態―
極小型有稜高坏についての若干の検討 ……………………市村慎太郎 63
<コラム>
庄内式以前
……………………………………………………森岡 秀人 73
【2026年1月14日 【入荷】
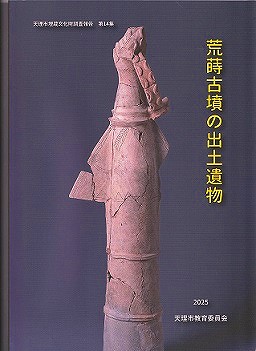
書籍番号
82866
書 名
荒蒔古墳の出土遺物
シリーズ
(天理市埋蔵文化財調査報告 第14集)
データ
A4 83頁
ISBN/ISSN
編著者
天理市教育委員会編集
出版年
2025年11月
出版者
価 格
1,600円(税込)
荒蒔古墳は昭和63~平成元(1988~89)年度に調査を実施し、
大和屈指の後期形象埴 輪群・円筒埴輪群が多量に出土した埋没
古墳です。主要な出土遺物を全点収録し、実測図・3次元計測陰
影図を多数掲載しています。
【目次】
I.はじめに……………………………………………………石田大輔 1
1.調査に至る経緯…………………………………………………… 1
2.調査成果の公開・活用
………………………………………… 1
3.遺物整理報告の公開……………………………………………… 1
Ⅱ.荒蒔古墳の位置………………………………………… 石田大輔 2
Ⅲ.調査の概要 ……………………………………………………… 3
1.調査の経過
…………………………………………… 石田大輔 3
2.第1次調査… ………………………………………………… 泉武 7
3.第2次調査 ………………………………………………
松本洋明 7
Ⅳ.遺物の出土状況…………………………………………
石田大輔 10
1.出土位置の特定…………………………………………………… 10
2.家形埴輪……………………………………………………………
11
3.剣形埴輪・盾形埴輪……………………………………………… 12
4.石見型埴輪・蓋形埴輪……………………………………………
12
5.人物埴輪…………………………………………………………… 12
6.動物埴輪……………………………………………………………
12
7.円筒埴輪…………………………………………………………… 13
8.土
……………………………………………………………… 13
Ⅴ.出土遺物
…………………………………………………石田大輔 14
1.遺物報告の方法 …………………………………………………
14
2.家形埴輪
………………………………………………………… 14
3.剣形埴輪 …………………………………………………………
15
4.双脚輪状文埴輪
………………………………………………… 15
5.盾形埴輪
………………………………………………………… 15
6.石見型埴輪 ………………………………………………………
15
7.蓋形埴輪
………………………………………………………… 15
8.靫形埴輪 …………………………………………………………
16
9.人物埴輪
………………………………………………………… 16
10.馬形埴輪
………………………………………………………… 17
11.犬形埴輪・猪形埴輪
…………………………………………… 18
12.鶏形埴輪
………………………………………………………… 18
13.円筒埴輪・朝顔形埴輪
………………………………………… 19
14.土
器 …………………………………………………………… 19
Ⅵ.まとめn ………………………………………………… 石田大輔 20
1.埴輪の樹立位置 ……………………………………………………
20
2.荒蒔古墳の時期
…………………………………………………… 20
3.荒蒔古墳の特質 ……………………………………………………
21
遺物図面・写真 ………………………………………………………
24
表目次(第1表~第3表)
図目次(第1図~第17図)
写真目次(写真1~写真58)
【2026年1月13日 【入荷】
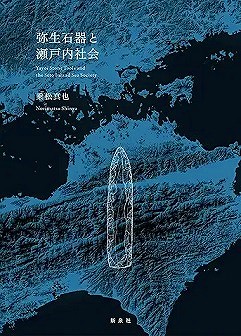
書籍番号
82834
書 名
弥生石器と瀬戸内社会
シリーズ
データ
B5 244頁(上製本)
ISBN/ISSN
978-4787725059
編著者
乗松 真也著
出版年
2026年1月
出版者
新泉社
価 格
8,800円(税込)
消費地の特定が可能な石器の材質的特性により、具体的な交流の単位
や流通経路を明らかにすることができる。それを瀬戸内海特有の地勢
や生業と重ね合わせることで、水稲農耕社会の「交換」のあり方にせ
まる。
第1節 課題と目的
第2節 対象とする範囲と時期
第1節 本章の目的
第2節 金山産サヌカイト製石器の生産
第3節 金山産サヌカイト製石器の流通
―弥生時代中期後葉の四国北西部を対象とした検討―
第1節 本章の目的
第2節 研究の対象
第3節 片岩製石庖丁の製作工程
第4節 各遺跡で生産された石庖丁の特徴
第5節 片岩製石庖丁の生産と流通
第1節 本章の目的
第2節 石斧の分類
第3節 片刃石斧と両刃石斧の製作工程
第4節 片刃石斧と両刃石斧の生産面での特徴
第5節 片刃石斧と両刃石斧の生産地と流通
第1節 本章の目的
第2節 研究方法と対象
第3節 生産地,加工地,流通中継地の設定
第4節 生産地,加工地,流通中継地の集落
第5節 石器の生産と流通にかかわる集落
第1節 本書の目的
第2節 研究の方法と対象
第3節 四国北東部における石庖丁の生産と流通
第4節 各地域における石庖丁の生産と流通
第5節 石庖丁と片刃石斧の生産と流通
第1節 本書の目的
第2節 石材の変化
第3節 石庖丁と片刃石斧の石材ごとの流通範囲
第4節 石器の広域流通を支えた事象
第1節 金山産サヌカイト製打製石剣の盛行
第2節 打製石庖丁の採用
第3節 広域流通石器の二者
第4節 石材資源と瀬戸内海の利用
第5節 中期的生産体制の解体
第6節 結論─瀬戸内地方の特質とその背景─
遺跡文献
図・表出典
おわりに
【2026年1月13日 【在庫切・再入荷未定】
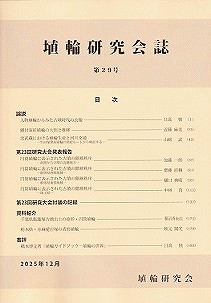
書籍番号
82830
書 名
埴輪研究会誌 第29号
シリーズ
データ
B5 188頁
ISBN/ISSN
1341-318X
編著者
出版年
2025年12月
出版者
埴輪研究会
価 格
論説
人物埴輪からみた古墳時代の衣服…………………日高 慎
(1)
鰭付家形埴輪の大別と推移…………………………近藤
麻美 (25)
北武蔵における埴輸生産と河川交通………………山﨑
武 (43)
一生出塚窯産埴輪の供給ルートから検証する一
第23回研究大会発表報告
円筒埴輪に表示された古墳の階層秩序
…………加藤 一郎 (57)
―前期から中期の近畿地方―
円筒埴輪に表示された古墳の階層秩序 …………齋藤 直樹 (81)
―群馬県西部地域―
円筒埴輪に表示された古墳の階層秩序
…………樋口 典昭 (95)
―群馬県東部地域―
円筒埴輪に表示された古墳の階層秩序
…………中林 菖 (113)
―埼玉県―
第23回研究大会討議の記録
………………………………… (133)
資料紹介
千葉県飯籠塚古墳出上の壺形・円筒埴輪……… 蓼沼香未由
(173)
栃木県・赤麻愛宕塚の盾形埴輪 …………………
秋元 陽光 (179)
書評
橋本博文著「埴輪ガイドブック―-埴輪の世界』
日高 慎 (183)
【2025年12月21日 【入荷】

書籍番号
82858
書 名
古代集落の構造と変遷 5
シリーズ
(第28回 古代官衙・集落研究会報告書)(奈良文化財研究所研究報告第46冊)
データ
A4 216頁
ISBN/ISSN
978-4-87805-179-1
編著者
奈良文化財研究所編
出版年
2025年12月
出版者
株式会社 クバプロ
価 格
4,180円(税込)
2024年12月に開催された奈良文化財研究所第28回古代官衙・集落研究会
の報告書。
Ⅰ 報 告
道上 祥武(奈良文化財研究所)
― 第27回古代官衙・集落研究会の報告を受けて―
大澤 正吾(文化庁)
長 直信(文化庁)
江口 桂(府中市役所)
浅野 啓介(文化庁)
討議②
【2025年12月21日 【入荷】

書籍番号
82857
書 名
第21回 古代武器研究会 発表資料集
シリーズ
(陪冢・大量器物埋納と巨大古墳時代―軍事組織論を再考する―)
データ
A4 94頁
ISBN/ISSN
編著者
古代武器研究会編集
出版年
2025年12月
出版者
古代武器研究会
価 格
1,700円(税込)
今回の武器研では、巨大古墳の時代の基準資料を見直します。古墳時代中期
には巨大古墳の周辺に配置された陪冢を中心として大量の器物埋納の存在が
よく知られています。とくにそれらの出土資料群の中でも武器・武具にもと
づく軍事組織に関する研究は、この時代の社会構造を復元する上で重要な役
割を果たしてきました。しかしながら、これまでの研究はその多くを、古い
調査報告に拠っています。また近年では、武器・武具はもちろん農工具など
の鉄製品や埴輪、土器など各種器物の研究が深化しています。陪冢出土資料
の全体像を踏まえた研究も、あらためて検討の余地があるのではないかと考
えます。そこで、本研究会では、武器・武具による軍事組織論のみならず、
多角的な資料から巨大古墳の時代像を見直す機会にしたいと思います。
序言
関連地図
関連系図
第1章 蘇我氏の墓
第2章 蘇我出自の女性墓
第3章 蘇我氏の終焉墓
第4章 八角形墳と舒明陵
第5章 薄葬令と孝徳陵
第6章 牽牛子塚古墳と斉明天皇
第7章 阿武山鎌足墓
前編まとめ 前方後円墳から八角形墳へ
第8章
天武・持統の合葬と聖なるライン
第9章 悲運、2人の皇子墓
第10章 真弓丘の皇子墓
第11章 壁画古墳の諸問題
第12章 キトラ古墳と吉野盟約の皇子たち
第13章 聖徳太子信仰と古墳の改修
第14章 斉明は父墓を改葬したのか
第15章 天智陵の完成と持統天皇・石上麻呂
第16章 火葬古墳と文武天皇
第17章 飛鳥時代の墓前祭祀
後編まとめ 飛鳥古墳の特異性
付録 飛鳥古墳の皇陵治定略史
【2025年12月21日 【入荷】

書籍番号
82856
書 名
古代武器研究 Vol.20
シリーズ
データ
A4 143頁
ISBN/ISSN
1346-9313
編著者
古代武器研究会
出版年
2025年12月
出版者
古代武器研究会
価 格
2,200円(税込)
『古代武器研究』Vol.20の刊行にあたって
塚本 敏夫 古代武器研究会代表幹事
【論文】
菊地 芳朗 福島大学………………………………………1
鹿角装刀剣の社会的意味
俊輔 千葉大学大学院人文科学研究院 …………………9
蛇行剣再論
北山 峰生 奈良県立橿原考古学研所 …………17
拵えの特徴と副葬古墳からみた象嵌装大刀の特質
大谷 宏治 静岡県文化財課 ……………………33
装飾付大刀の表徴性と地域社会一出雲地域をもとにして一
吉松 優希 島根県古代文化センター …………49
魏晋南北朝の刀剣
藤井 康隆 佐賀大学芸術地域デザイン学部 …61
初期鉄器時代~三国時代における長柄武器の変遷と背景
金 跳咏慶北大学校考古人類学科(金 宇大訳) 115
【事例報告】
坂本 豊治 出雲弥生の森博物館
奥山 誠義・水野 敏典・北井利幸・河﨑衣美
小倉 頌子・中尾真梨子・
平井 洸史 奈良県立橿原考古学研智所………115
中尾遺跡の鉄矛について
片岡 啓介 倉吉市経済観光部文化財課………123
【総合討論】 ………………………………………………………………130
【2025年12月18日 【入荷】
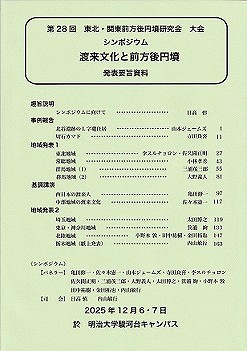
書籍番号
82835
書 名
渡来文化と前方後円墳
シリーズ
(第28回 東北・関東前方後円墳研究会大会 《シンポジウム》発表要旨資料)
データ
A4 182頁0
ISBN/ISSN
編著者
第28回大会実行委員会編集
出版年
2025年12月
出版者
東北・関東前方後円墳研究会
価 格
2,200円(税込)
シンポジウムに向けて ………………
日高 慎
事例報告
北谷遺跡のL字竈住居 ………………山本ジェームズ
1
切石カマド ………………………………
寺田良喜 11
地域発表1
東北地域 ……………… 李スルチョロン・佐久間正明 27
常総地域
……………………………… 小林孝秀 43
群馬地域(1) …………………………… 三浦茂三郎
55
群馬地域(2)
……………………………… 大野義人 81
基調講演
西日本の渡来人 ……………………………
亀田修一 97
中部地域の渡来文化 …………………… 佐々木憲一
117
地域発表2
埼玉地域 …………………………………… 太田博之
119
東京・神奈川地域 ………………………… 箕浦 絢
133
北陸地域 ………… 小野本敦・田中祐樹・金田拓也
147
栃木地域(紙上発表) ……………………… 内山敏行
163
【2025年12月18日 【入荷】

書籍番号
82852
書 名
関西近世考古学研究 31「近世都市の井戸」
シリーズ
データ
A4 256頁
ISBN/ISSN
編著者
関西近世考古学研究会編集
出版年
2025年11月
出版者
関西近世考古学研究会
価 格
3,200円(税込)
講演
近世都市開発と井戸………………………………………………鈴木 正貴
1
近世大坂の井戸 …………………………………市川 創・小田木
富慈美 21
京都の事例ー近世井戸の構造変遷と空間配置について一
……… 中谷 俊哉・鈴木 康高・加藤 雄太
41
有岡城跡・伊丹郷町遺跡の事例 ……………………………… 原田
将典 61
和歌山城跡・和歌山城下町遺跡の事例 …………金澤
舞・福佐 美智子 81
滋賀の事例
……………………………………… 馬場 将史・樫木 規秀 101
江戸、下町の井戸~町人地を中心として~ ……………… 仲光
克顕 121
小田原城と城下町の事例 ……………………………………… 田中 里奈 133
松本城下町の事例 ………………………… 足立 とも与・髙山 いず美
151
奈良町遺跡の井戸
…………………………………………… 中島 和彦 169
名古屋城下町の井戸 ……………………………………………
濵﨑 健 177
堺環濠都市遺跡の近世井戸遺構
………………………………永井 正浩 197
徳島城下町における井戸の様相
………………………………西本 沙織 211
松江城下町遺跡の井戸
……………………………小山 泰生・伊藤 徳広 221
萩城下町の事例
…………………………………………………柏本 秋生 235
長崎の事例
………………………………………………………竹村 南洋 249
【2025年12月18日 【入荷】

書籍番号
82853
書 名
中近世土器の基礎研究 31 特集:須恵器生産の中世
変容と展開
シリーズ
データ
A4 88頁
ISBN/ISSN
編著者
出版年
2024年11月
出版者
日本中世土器研究会
価 格
3,300円(税込)
いままた中世須恵器を考える …………………………………新田 和央
1
北東日本海沿岸地域の中世須恵系陶器―珠洲窯を中心にして一
……………………………………水澤 幸一
5
西播磨における須恵器生産の展開と変容―編年の再検討を中心に―
…………………………………稲本 悠一 15
亀山焼と勝間田焼の基礎的研究 ………………………………柴田 亮 27
十甁山窯跡群における中世窯業の成立過程 …………………谷本 峻也 43
九州における中世須恵器の生産 ………………………………出合 宏光 55
カムイヤキの基礎的研究
―徳之島カムイヤキ陶器窯跡出土資料の再整理品の分析を中心に―
……………………………與嶺友紀也 65
〈投稿論文〉〉
「篠鉢」を焼いた地方窯
ー但馬孫兵ヱ谷窯跡からみた平安時代須恵器生産―
……………………稲本悠ー・仲田周平 75
研究会記録………………………………………………………………………
87
【2025年12月11日 【入荷】
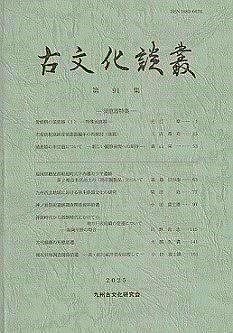
書籍番号
82849
書 名
古文化談叢 第91集ー須恵器特集―
シリーズ
データ
B5 166頁
ISBN/ISSN
1883-0676
編著者
武末 純一編集
出版年
2025年11月
出版者
九州古文化研究会
価 格
2,400円(税込)
ー須恵器特集ー
森 山 榮 一 ……… 53
第2地点B区出土の「筒状銅製品」について
福 島 日出海 ……… 63
九州西北地域における弥生鉄器文化の研究
柴 田 亮 …… 77
沖ノ島祭祀遺跡調査関係資料拾遺
小 田 富士雄 ……… 97
評制時代から郡制時代にかけての
地方行政組織の変遷について
一福岡平野の場合一 日 野 尚 志 ……… 115
古代横櫛の形態変遷
大 熊 久 貴 …… 141
榎坂貝塚調査関係拾遺 ―故・前川威洋君を回想して一
小 田 富士雄
……… 161
【2025年12月11日 【品切】
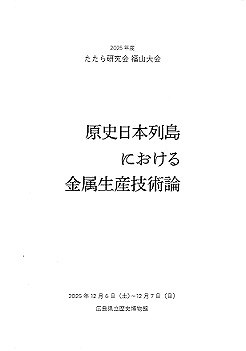
書籍番号
82837
書 名
原史日本列島における金属生産技術論
シリーズ
(たたら研究会 2025年度大会要旨集)
データ
A4 73頁
ISBN/ISSN
編著者
たたら研究会編集
出版年
2025年12月
出版者
たたら研究会
価 格
研究発表1 ライアンジョセフ(岡山大学)
「古墳出現期における刀剣類の生産・流通・保有」
「三重県高茶屋大垣内遺跡からみた鍛冶技術の受容と伝播
―漁撈具との関係に着目して―」
「鳥取県長瀬高浜遺跡出土金属器について」
「弥生・古墳時代の青銅器生産における系譜性の検証
~無茎銅鏃を手がかりに~」
「日本海側からみた渡来系鉄器製作技術論」
「古墳時代における鉄製農工漁具の生産・流通・副葬の構造」
「古墳時代後期における金属製玉の製作と流通」
「出現期蕨手刀の製作主体と生産拡大過程」
【2025年12月3日 【近日入荷】
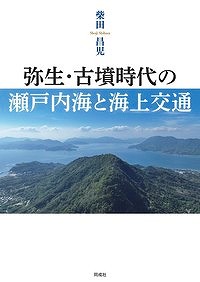
書籍番号
82832
書 名
弥生・古墳時代の瀬戸内海と海上交通
シリーズ
データ
B5 338頁
ISBN/ISSN
978-4868320128
編著者
柴田 昌児著
出版年
2025年12月
出版者
同成社
価 格
11,000円(税込)
の遺跡視認性など多様な実験から、往時の瀬戸内世界の実相に迫る。
第1章 本書の目的と課題
第2章 瀬戸内海における高地性集落の展開
第3章 西部瀬戸内弥生社会の地域的展開
第4章 瀬戸内海における土器製塩と集団関係
第5章 海上活動と地域集団
第6章 海上交通と地域社会―第1部結語にかえて―
付論2 朝鮮半島系準構造船(加耶タイプ)の生産と日韓の造船技術
第7章 海上アクティビティーと高地性集落
―双方向視認検証予備実験を経て―
第8章 「間」からみる瀬戸内―瀬戸内全誌のための素描―
【2025年12月3日 【入荷】
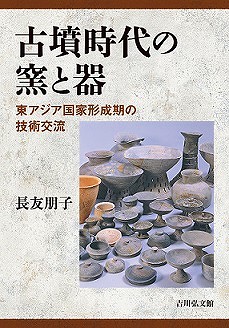
書籍番号
82795
書 名
古墳時代の窯と器 東アジア国家形成期の技術交流
シリーズ
データ
A5 272頁(上製本)
ISBN/ISSN
978-4642093705
編著者
長友 朋子著
出版年
2025年12月
出版者
吉川弘文館
価 格
9,900円(税込)
古墳時代に韓半島から伝来した窯による土器作りは、日本列島における土器
の生産体制に画期的な変化をもたらした。在来の製法より高度な技術である窯
焼成を、なぜスムーズに受容できたのか。窯が導入される以前の製作技術や調
理・食事の変化、民族考古学の成果など、土器をとりまく要素を多角的に考察。
「古墳時代の産業革命」の背景を解明する。
序章 窯焼成と野焼きの接点
1 弥生・古墳時代の社会と土器生産
2 本書の構成
3 本書が対象とする地域と時代、用語の整理
第1節 貯蔵具と食器の研究史
第2節 器の変革と案の導入
第3節 風納土城の土器からみた百済土器組成
第4節 日本列島における器の変革
第5節 日本列島の俎・案の受容と展開
第6節 器の変革と饗宴・交易
第1節 弥生時代終末期の土器丸底化に関する研究
第2節 日本列島における丸底土器の製作技法と使用方法
第3節 弥生時代併行期における韓半島の初現丸底土器
第4節 弥生時代後期・終末期の韓半島の土器
第5節 丸底化と土器にみる日韓交流
第1節 東アジアの古代窯分類
第2節 窯構造と焼成温度からみた窯の系譜
第3節 初期須恵器と軟質土器の製作地
第4節 窯技術をもつ渡来集団と生産体制
第1節 民族誌からみた野焼き
第2節 民族誌からみた窯焼きと野焼きの接点
第1節 韓半島の竈
第2節 韓半島における穀物の受容と地域差
第3節 韓半島の甑の地域色
第4節 日本列島の甑と渡来人の故地
1 窯のはじまりと土器の変革
2 窯導入による文化変容
3 古墳時代の土器生産
あとがき
索引
【2025年12月3日 【入荷】

書籍番号
82804
書 名
湯浅党城館跡
シリーズ
(新日本の遺跡 8)
データ
四六版 170頁
ISBN/ISSN
978-4868320104
編著者
川口 修実著
出版年
2025年11月
出版者
同成社
価 格
1,980円(税込)
百姓たちから前文の片仮名書言上状で訴えられたことで有名な武士団・
湯浅党。中世前半期、紀伊国で権勢を誇った彼らの歴史や時代背景を
追いながら、城館跡や関連遺跡を考古学的に解説する。
第Ⅰ部 遺跡の特性―湯浅党城館跡とは―
第1章 訴えられた地頭
第2章 紀伊半島の特質と湯浅党の本拠
第3章 湯浅氏・湯浅党の歴史
第4章 南北時代の動乱と湯浅党の石造物
第5章 一門の拠点―湯浅城跡の発掘調査
第6章 他門の拠点―藤並館跡の発掘調査
第7章 湯浅党の関連遺跡
第8章 遺跡の現状と今後
【2025年12月3日 【入荷】

書籍番号
82627
書 名
弥生墳丘墓と手工業生産
シリーズ
(考古学選書 6)
データ
A5 266頁(上製本)
ISBN/ISSN
978-4-868320012
編著者
猪熊 兼勝著
出版年
2025年5月
出版者
同成社
価 格
6,600円(税込)
中国地方を中心とした弥生墳丘墓の変遷を、手工業生産や交易活動との相関を
ふまえて概括。弥生墳丘墓造営の根源的な事由を究明する。
第1章 弥生時代前半期の手工業
1.弥生時代の実年代と初期鉄器文化
2.玉類製作の技術とその変容
3.市場の形成と専業的生産遺跡
1.手工業の専業化と水田稲作の拡大
2.鉄器の普及とその保有形態
3.管玉生産の変革とガラスの2次生産
4.手工業生産の集約と複合化
1.水銀朱生産と水晶製玉作り
2.朝貢献上品の集約的生産
1.弥生時代前半期の墳墓
2.弥生墳丘墓の萌芽
3.四隅突出型墳丘墓の成立と佐田谷・佐田峠墳墓群
4.備後北部における墳丘墓の変容
1.丹後地域における墳丘墓の変容
2.山陰・北陸地方の四隅突出型墳丘墓
3.山陽地方吉備地域の墳丘墓
1.石囲い木棺墓・木槨墓の成立と発展
2.石囲い墓の変遷と終焉
1.手工業生産と墳丘墓グループの形成
2.弥生社会の終焉と前方後円墳の成立
【2025年11月17日 【入荷】
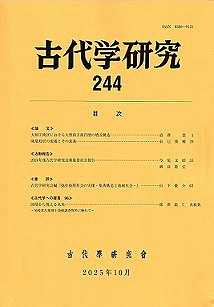
書籍番号
82820
書 名
古代学研究 第244号
シリーズ
データ
B5 70頁
ISBN/ISSN
0386-9121
編著者
古代学研究編集局
出版年
2025年10月
出版者
古代学研究会
価 格
990円(税込)
《論 文》
大和王陵区における大型前方後円墳の墳丘構造
………………沼 澤 豊 1
陵墓島居の変遷とその意義………………辰 巳 俊 輔 29
2024年度古代学研究会陵墓委員会報告…今 尾 文 昭 55
鍋 島 隆 宏
《書 評》
古代学研究会編『弥生後期社会の実像
ー集落構造と地域社会一」 山 下 俊 介 65
回帰から視える未来………………………深 澤 敦 仁 表紙裏
~尾崎喜左雄博士発掘調査資料に触れて~
【2025年11月15日 【入荷】

書籍番号
82802
書 名
古墳時代の甲冑と軍事構造
シリーズ
(考古学選書 8)
データ
A5 258頁
ISBN/ISSN
978-4868320098
編著者
川畑 純著
出版年
2025年10月
出版者
同成社
価 格
7,150円(税込)
古墳時代の甲冑の型式分類と編年、また古代アジア各地の武装
との比較などから軍事構造の実態を追及し、軍事組織の歴史的
意義に迫る。
【目 次】
序 章 古墳時代軍事構造解明の意義
1.軍事構造分析の視点と研究史
2.本書の構成と軍事構造解明の意義
1.編年の意義
2.革綴板甲の研究史と課題
3.革綴板甲の編年
4.革綴板甲と鋲留板甲の関係
5.鋲留板甲の変遷と段階設定
6.頸甲の分類と編年
7.
肩甲の変遷
8. 頸甲・肩甲の変遷の意義
1.冑の被り方と錣の検討の意義
2.冑の被り方
3.冑の型式変化と被り方
4.錣の分類
5.錣の変遷
6.甲冑の使用と改良
1.検討の前提
2.衝角付冑の変遷と組み合わせ
3.眉庇付冑の変遷と組み合わせ
4.頸甲の変遷と組み合わせ
5.甲冑の段階設定とその評価
6.武装の変遷
1.生産と授受に関する課題と検討の意義
2.甲冑の系統の意義
3.甲冑の授受と流通
4.生産体制・授受方式の変遷と社会的機能
5.流通・入手・使用に関する課題と分析の視点
6.武器・武具の生産契機
7.甲冑の保有と使用の実態
8.武器・武具の入手と軍事組織としての編成
1.社会的機能の検討の前提
2.武器・武具の伝世と長期保有
3.武器・武具の履歴と価値づけ
4.武器・武具の社会的機能
1.古代アジアの武装との比較検討の意義
2.中国の武装
3.中国西南部・東北部および周辺地域の武装
4.中央アジア・西アジアの武装
5.古代アジアの武装の変遷と日本列島の武装の成立
6.日本列島の武装の特質
1.武装の特質と軍事組織解明の視点
2.甲冑の形態的特徴と使用法
3.武器・武具の使用法
4.武器・武具出土古墳の社会的位置づけ
5.古墳時代社会における軍事組織の位置づけ
1.本書で明らかにしたこと
2.古墳時代の軍事構造
3.古墳時代軍事構造の歴史的意義
【2025年11月6日 【入荷】

書籍番号
82819
書 名
多彩な鉱山開発の軌跡 佐渡金銀山
シリーズ
(シリーズ「遺跡を学ぶ」 175)
データ
A5 96頁
ISBN/ISSN
978-4-7877-2535-6
編著者
小田由美子・宇佐美亮著
出版年
2025年11月
出版者
新泉社
価 格
1,870円(税込)
もった。古くから砂金を採取した西三川砂金山、戦国時代に本格的な鉱山開
発がはじまった鶴子銀山、徳川幕府の支配下で大鉱山都市が出現した相川金
銀山の発掘調査から、佐渡金銀山の実態を明らかにする。
第1章 佐渡島と金銀
1 金の島、佐渡島
2 なぜ佐渡島で金銀が採れるのか
3 三つの代表的鉱山
1 砂金山開発の歴史
2 絵巻に描かれた砂金採掘技術
3 大流しの遺構
4 砂金鉱山集落
1 銀鉱山の発見と開発
2 鉱石採掘の遺構
3 代官屋敷
4 鉱山集落
5 新穂銀山
1 徳川幕府による開発
2 相川の採掘活動
3 選鉱と石磨の石切場
1 奉行所の変遷
2 奉行所の発掘調査
3 選鉱・精錬遺構の発掘調査
4 臨海鉱山都市の形成
1 近代佐渡鉱山の誕生
2 産業遺産の保存・活用にむけて
【2025年11月3日 【入荷】
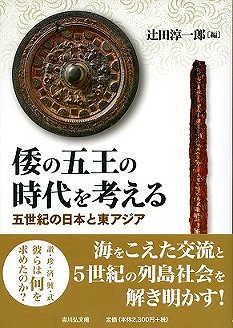
書籍番号
82796
書 名
倭の五王の時代を考える
五世紀の日本と東アジア
シリーズ
データ
A5 224頁
ISBN/ISSN
978-4642084680
編著者
辻田 淳一郎編
出版年
2025年2月
出版者
吉川弘文館
価 格
2,530円(税込)
「倭の五王」讃・珍・済・興・武が、中国南朝と交流を深めた五世紀はどの
ような時代だったのか。銅鏡や古墳の変遷、中国史書や記紀、銘文刀剣など
の出土文字資料により、考古学と文献史学の双方から考察する。さらに執筆
者たちによる、研究の最前線での討論を収録。東アジアの情勢を視野に、豪
族の割拠した列島社会と、南朝遣使の実態を論じる。
はじめに―古墳時代の鏡と日本の古代国家形成― 25
一 同型鏡群の製作地と製作背景をめぐる諸問題
―同型鏡群の「特鋳説」― 19
二 同型鏡群の授受と「人制」―「参向型」一類と二類― 34
おわりに 40
はじめに 57
一 東晋に遣使朝貢した「倭国使」をめぐって 58
二 中国官爵の意味をめぐって 65
三 対中外交の意味とその途絶をめぐって 74
おわりに 80
はじめに 85
一 巨大古墳の築造へ 86
二 最大の墳墓の築造と中国宋への遣使 98
三 倭の五王の遣使本格化と巨大古墳の動き 106
おわりに―倭の五王が百舌鳥・古市で直接関与した時間帯― 116
はじめに 119
一 五世紀の王宮 120
二 王族のあり方 126
三 五世紀の中央支配権力 133
四 雄略天皇の統治とその後の展開 139
おわりに 145
はじめに 147
一 古墳前期後半の東日本の大型古墳 149
二 中期前半の東国 161
三 中期中葉の東国 167
四 中期後半の東国 172
五 中期における畿内政権と地方政権 176
六 前方後円墳秩序と倭の五王の時代 180
おわりに 186
【2025年11月3日 【入荷】
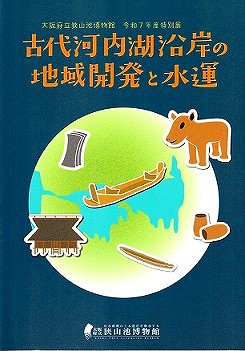
書籍番号
82810
書 名
古代河内湖沿岸の地域開発と水運
シリーズ
(大阪府立狭山池博物館図録44 令和7年度特別展)
データ
A4 95頁
ISBN/ISSN
編著者
大阪府立狭山池博物館編集
出版年
2025年8月
出版者
大阪府立狭山池博物館
価 格
1,100円(税込)
目 的
4・5世紀の倭国では、朝鮮半島の情勢変化の影響を大きくうけて、半島
からの渡来系集団の移住が急増しました。古代河内湖沿岸では、倭王権が渡
来系集団とその先端技術を政策的に受け入れ、地域開発と交易・物流ネット
ワークの整備が加速していきました。
今回の特別展では、王権の港として瀬戸内海と河内湖沿岸を結ぶ水運の結
節点となった難波津、その交易と物流を支えた舟運関連資料を紹介いたしま
す。あわせて河内湖沿岸の地域開発として鉄器生産・馬匹生産・塩生産・玉
類生産の発展について考えます。(HPより)
ごあいさつ………………………………………………………………………… 3
目次・凡例………………………………………………………………………… 4
第一章 王権と港津
河内湖周辺における流通・交易からみた古墳時代……………(飯塚) 8
難波津の成立とその構造………………………………………(小山田)12
第二章 河内湖沿岸の地域開発
河内湖沿岸の地域開発……………………………………………(山田)24
鉄器の生産
…………………………………………………………(〃)26
馬の飼育
……………………………………………………………(〃)31
塩の生産
……………………………………………………………(〃)35
玉類の生産…………………………………………………………(河原)38
河内湖沿岸に集まる全国各地の土器……………………………(飯塚)40
外来系土器が物語る国際交流………………………………………(〃)42
準構造船の船材……………………………………………………(河原)46
船の埴輪と絵画………………………………………………………(〃)51
推進具とアカトリ……………………………………………………(〃)53
〈コラム〉運ばれてきた船形陶質土器…………………………………(〃)54
港・船からみた古代日本と筑紫 大庭 康時………… 56
潟湖の時代
ー山陰における弥生・古墳時代の船と津ー 池淵 俊一………… 66
倭と加耶の船 小山田 宏一………… 78
報告書・参考文献……………………………………………………………… 88
図版目録………………………………………………………………………… 91
出品目録………………………………………………………………………… 93
展示協力者・協力機関………………………………………………………… 95
あとがき………………………………………………………………………… 96
凡例
本書は、大阪府立狭山池博物館令和七年度特別展「古代河内湖沿岸の地域
開発と水運」の展示解説図録です。
図録構成と展示構成は一部異なるところがあります。本書に掲載した写真
は展示品以外の参考資料を含みます。以下省略
【2025年11月3日 【入荷】
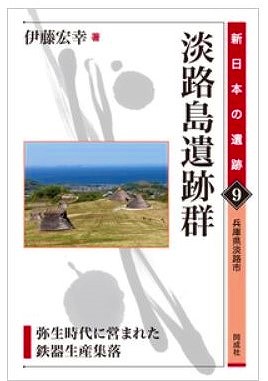
書籍番号
82805
書 名
淡路島遺跡群―弥生時代に営まれた鉄器生産集落
シリーズ
(新日本の遺跡 9)
データ
四六版 138頁
ISBN/ISSN
978-4868320111
編著者
伊藤 宏幸著
出版年
2025年11月
出版者
同成社
価 格
1,980円(税込)
島の山間部に突如現れ、短期間で姿を消した弥生時代後期の「鍛冶屋
のムラ」。以降の鉄器普及にも影響を与えた遺跡群の実像にせまる。
【目次】
第1章 五斗長垣内遺跡と舟木遺跡
第2章
鉄器生産
第3章 五斗長垣内遺跡の発掘調査
第4章
舟木遺跡の発掘調査
第5章 遺跡の現在と未来
【2025年10月23日 【入荷】
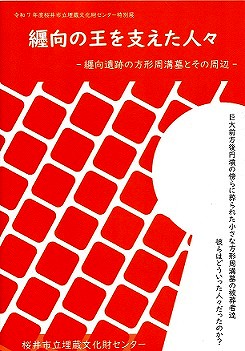
書籍番号
82809
書 名
纒向の王を支えた人々―纒向遺跡の方形周溝墓とその周辺―
シリーズ
(令和7年度特別展 桜井市立埋蔵文化財センター展示図録 第47册)
データ
A4 25頁
ISBN/ISSN
編著者
桜井市教育委員会編集
出版年
2025年10月
出版者
桜井市教育委員会
価 格
1,300円(税込)
桜井市立埋蔵文化財センターでは令和7年10月1日(水曜日)~令和7年11月30日
(日曜日)の期間、令和7年度特別展『纒向の王を支えた人々 ‐纒向遺跡の方形周
溝墓とその周辺‐』を開催いたします。
纒向遺跡には箸墓古墳のような壮大な古墳だけでなく、小規模で地味な墳墓も存
在します。今回取り上げる墳墓はそのひとつ、方形周溝墓です。方形周溝墓は弥
生時代から続く伝統的な墓の形式ですが、前方後円墳が築造される纒向遺跡でも
連綿と築造されるのです。大規模な古墳のかたわらで方形周溝墓を営み、葬られ
た人々はどのような存在だったのでしょうか。展示を通じて考えてみたいと思い
ます。(HPより抽出)
1.弥生時代の方形周溝墓と社会………………………………………………… 03
2.桜井市内の弥生時代方形周溝墓……………………………………………… 04
3.纒向遺跡の前方後円墳の築造時期…………………………………………… 05
4.纒向遺跡における方形周溝墓の出現と展開………………………………… 08
5.纒向遺跡のそのほかの墓……………………………………………………… 09
6.纒向遺跡の方形周溝墓の性格………………………………………………… 10
7.方形周溝墓の被葬者…………………………………………………………… 13
8.方形周溝墓その後……………………………………………………………… 13
9.おわりに………………………………………………………………………… 14
資料集
参考文献
凡例
【2025年10月23日 【入荷】

書籍番号
82808
書 名
季刊 考古学 第173号 特集 災害・防災考古学と現代日本
シリーズ
データ
B5 132頁
ISBN/ISSN
978-4-639-03084-3
編著者
桑門智亜紀編集
出版年
2025年11月
出版者
(株)雄山閣
価 格
2,640円(税込)
災害・防災考古学の提唱と防災への貢献(斎野裕彦)
クロヴィス彗星衝突説とその後の論争(出穂雅実)
遺跡に埋もれた災害伝承と防災行動の復元(斎野裕彦)
太平洋島嶼地域における巨大津波とその伝承
―理学の視点から―(中田光紀・後藤和久)
北海道南西部における津波と伝承(中田裕香)
奈良盆地北部における地震痕跡の分析による歴史地震像の再構築
―平城宮・京跡発掘調査成果を中心とした検討―(村田泰輔)
小田原市根府川沖海底に残されていた関東大震災の痕跡調査と
災害伝承(林原利明)
巨大噴火災害の考古学的アプローチから学ぶこと
―鬼界アカホヤ噴火を例に―(桒畑光博)
古墳時代後期の榛名山噴火の被災・復興と災害伝承(杉山秀宏)
平安期の開聞岳噴火と災害伝承(松﨑大嗣)
平安期の十和田噴火と災害伝承(米代川流域)(村上義直)
平安期の十和田噴火と災害伝承(太平洋側)(丸山浩治)
前近代アイヌ文化期の火山噴火災害と伝承(関根達人)
気象災害痕跡研究の視点と課題(井上智博)
河川活動に伴う地形変化と人間活動のかかわり
―河内平野南部の事例―(大庭重信)
【特別コラム】小学生が考えた防災と考古学
―kid’s
考古学の活動から―(西脇導宣・佐古和枝)
東日本大震災の津波堆積層の剥ぎ取り資料製作と防災への活用
(川又隆央・渡邉正巳)
震災遺構中浜小学校と語り部活動(山田隆博・渡邉修次)
阪神・淡路大震災と東日本大震災の復興調査とこれからの防災
(禰冝田佳男)
―和歌山県金屋土居跡―(川口修実)
リレー連載・考古学の旬 第31回/現在を過去へ投影する
―不問の前提を問う―(小野昭)
リレー連載・私の考古学史 第22回/好きなことを楽しく(千田嘉博)
連載・現状レポート これからの博物館と考古学-博物館法改正を受けて-
第4回/下関市立考古博物館の30年とこれからの考古楽の実践
(濱﨑真二)/「モノ・ヒト・コトのつながるところ」
対馬博物館(尾上博一)
書評/論文展望/報告書・会誌新刊一覧/考古学界ニュース
【2025年10月20日 【入荷】
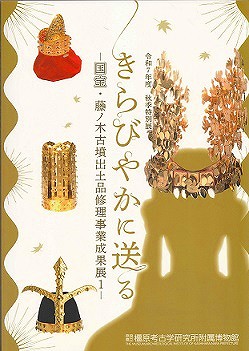
書籍番号
82797
書 名
きらびやかに送る―国宝藤ノ木古墳出土品修理事業成果展1
シリーズ
(奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 特別展図録第98冊)(平成7年度 秋季特別展)
データ
A4 87頁
ISBN/ISSN
編著者
奈良県立橿原考古学研究所附属博物館編集
出版年
2025年10月
出版者
奈良県立橿原考古学研究所附属博物館
価 格
1,800円(税込)
未盗掘の大型古墳として著名な藤ノ木古墳は多量の須恵器、馬具、武器・
武具などが出土し、鞍金具は東アジア屈指の名宝として注目されていま
す。石棺内からも冠、玉類、銅鏡、刀剣、大帯、履などの副葬品が出土
し、被葬者はかなりの権力者であったことが想定されています。今回は、
現在進行中の国宝・藤ノ木古墳出土品修理事業が節目の5年目を迎えた
ことを記念して修理が完了した冠、銅鏡、銀装刀子、履などの被葬者の
周辺に置かれた葬送用大型装身具を中心に、修理の状況および関連出土
品を紹介しながら、従来の切り口とは違う角度から藤ノ木古墳の実態に
迫ってみたいと思います。(博物館チラシより抜粋)
目次、例言
概説 きらびやかに送る ……………………………………………………… 5
展示関連地図 …………………………………………………………………… 6
プロローグ 藤ノ木古墳とは
……………………………………………… 7
第1章
葬送用大型装身具 …………………………………………………15
第2章 冠 ……………………………………………………………………19
第3章 銅鏡
…………………………………………………………………29
第4章
装飾刀子 ……………………………………………………………41
第5章 履 ……………………………………………………………………51
第6章 そのほか
……………………………………………………………61
第7章
保存科学の仕事・役割 ……………………………………………67
エピローグ 藤ノ木古墳のあと ……………………………………………79
参考資料 ………………………………………………………………………82
出品目録…………………………………………………………………………83
参考文献…………………………………………………………………………85
付 国宝奈良県藤ノ木古墳出土品の修理と保存科学 ………………………86
関連行事、協力機関・協力者
………………………………………………87
あとがき、奥付…………………………………………………………………88
……………………………………………………………………………………
<関連書新刊>
82735 藤ノ木古墳金銅製馬具のルーツを辿る-韓日の精密鋳造と毛彫り
の技術ー(「文化財と技術 別冊3)
鈴木 勉著
2025年4月 A5 190頁
工芸文化研究所 ¥1,100(税込)
https://www.chugoku-shoten.com/mokuji/jmokuji/82735/82735.html
【2025年10月20日 【入荷】

書籍番号
82793
書 名
ここまでわかった高安城~高安城・外郭線の検討~
シリーズ
(第69回古代山城研究会例会 プログラム・予稿集)
データ
A4 72頁
ISBN/ISSN
編著者
古代山城研究会
出版年
2025年10月
出版者
古代山城研究会
価 格
1,100円(税込)
「高安城の研究史」
向井一雄(古代山城研究会・代表)…………… 1
「地形可視化技術を用いた古代山城の探求-高安城の城壁線を追う-」
松尾洋平(古代山城研究会)……………………21
「高安城の全体プラン-平群町側の城壁痕跡-」
松波宏隆(京都文教大学非常勤講師)…………41
「瀬戸内の古代山城における城壁構造について」
山元敏裕(高松市埋蔵文化財センター)………47
「大廻小廻山城跡の城壁構造」
乗岡
実(元 岡山市教育委員会) ……………51
「永納山城の城壁」
渡邊芳貴(西条市教育委員会)
………………60
【2025年10月13日 【入荷】
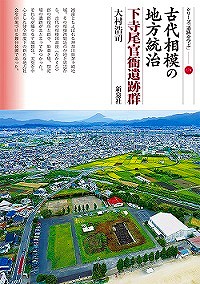
書籍番号
82792
書 名
古代相模の地方統治 下寺尾官衙遺跡群
シリーズ
(シリーズ「遺跡を学ぶ」 174)
データ
A5 96頁
ISBN/ISSN
978-4-7877-2534-9
編著者
大村 浩司著
出版年
2025年10月
出版者
新泉社
価 格
1,870円(税込)
湘南ともよばれる神奈川県茅ヶ崎地域。その相模湾間近の台地と周辺
から、古代の相模国高座(たかくら)郡の郡役所と郡寺、船着き場、
祭祀場の遺跡がまとまってみつかった。それらが織りなす風景は、天
皇を中心とした律令制度下の新たな地方社会を印象づける舞台装置で
あった。
第1章 古代相模国と地方官衙の研究
1 海と低地と台地のまち、茅ヶ崎
2 古代相模国と高座郡
3 郡衙遺跡の研究
1 「遺跡群」としてみる高座郡衙
2 下寺尾西方遺跡の調査
3 高座郡衙の構成と変遷
1 郡衙周辺寺院―七堂伽藍跡
2 郡衙を支えた川津
3 律令的祭祀と仏教的祭祀
4 官衙南部地域の関連遺跡
1 地形と交通を重視した選地
2 高座郡衙の三つの風景
1 校舎建替えか遺跡保存か
2 「重なる史跡」のこれから
【2025年10月1日 【入荷】

書籍番号
82773
書 名
七隈史学 第27・28合併号
シリーズ
データ
B5 314頁
ISBN/ISSN
1348-1304
編著者
桃﨑 祐輔編集
出版年
2025年7月
出版者
七隈史学会
価 格
2,2000円(税込)
シンポジウム参加記「比較史の観点からみる『検証 ナチスは「良いこと」
もしたのか?』」
田野大輔・小野寺拓也・松井康浩・大澤武司・伊藤亜希子
(文筆:藤丸祐大)……………… 1
薩摩藩種子島における西国流人の犯罪と生活
-「種子島家譜」の分析から- …………………山田悠太朗…………
23
『新唐書』党項伝の再検討
-「編纂史料の基礎的分析法」の実践として- …森田
悠斗………… 78
大宰府と7~8世紀の東アジア都市史 ……………妹尾
達彦………… 94
モンゴルと崇恩演福寺
-クビライ政権期における「易禅為教」との関連を中心に-
………………………藤本 幸音………… 97
十八世紀末イギリスの奴隷貿易廃止運動と地方都市
:港湾都市ブリストルを中心に ……………………冨野
悟………… 117
弥生時代の掘立柱建物と祖先祭祀
~原始・古代風葬考~ ……………………………朝岡
俊也………… 314
那津官家研究史 …………………………………………神
啓崇………… 298
金属器模倣土器編年試案
-土師器杯Cと須恵器杯Hの法量分布から- ……弓削 怜子…………
278
特別史跡大宰府跡周辺における近年の発掘調査成果について
-官衙と瓦窯を中心に- ………………髙橋 学・福盛
雅久 ……… 244
古代官衙・城の外郭について
-大宰府を中心に- …………………………………山村
信榮 ……… 228
古代・中世移行期における北部九州の考古資料からみた対外交渉と流通
-警固銘瓦・筑紫牛・出現段階石鍋に注目して- 桃﨑 祐輔…………
206
古松崇志著『ユーラシア東方の多極共存時代-大モンゴル以前』
……………………………………新貝 隼士………… 151
七隈史学会編・山田貴司責任編集『室町九州の紛争・秩序・外交』
……………………………………中村 昂希………… 159
植民地時代を生きた朝鮮知識人と向き合う …………柳
忠煕………… 137
【2025年9月30日 【品切れ】
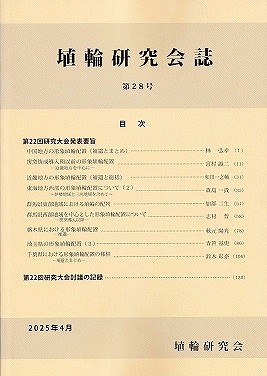
書籍番号
82743
書 名
埴輪研究会誌 第28号
シリーズ
データ
B5 153頁
ISBN/ISSN
1341-318X
編著者
出版年
2025年4月
出版者
埴輪研究会
価 格
第22回研究大会発表要旨
中国地方の形象埴輪配置(補遺とまとめ) ………林 弘幸(1)
窖窯焼成導入期以前の形象埴輪配置 ……………宮村 誠二(11)
ー近畿地方を中心に一
近畿地方の形象埴輪配置(補遺と総括) …………和田一之輔(31)
東海地方西部の形象埴輪配置について(2) ………森島 一貴(35)
~伊勢地域と三河地域を含めて~
群馬県東部地域における埴輪の配列 …………加部 二生(51)
群馬県西部地域を中心とした形象埴輪配置について
-窖窯導入以降-
…………志村 哲(58)
栃木県における形象埴輪配置 ……………………秋元 陽光(78)
-補遺-
埼玉県の形象埴輪配置(3) ………………………青笹 基史(86)
千葉県における形象埴輪配置の様相 ……………鈴木
彩奈(106)
-補遺とまとめ-
第22回研究大会討議の記録
……………………………………(130)
【2025年9月18日 【入荷】【ご注文承り中】
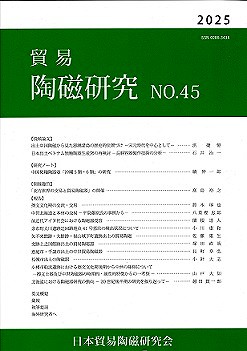
書籍番号
82770
書 名
貿易陶磁研究 第45号
シリーズ
データ
A4 185頁
ISBN/ISSN
0286-343X
編著者
日本貿易陶磁研究会編集
出版年
2025年9月
出版者
日本貿易陶磁研究会
価 格
3,850円(税込)
【投稿論文】
出土中国陶磁から見た澎湖諸島の歴史的位置づけ
-宋元時代を中心として- …………………… 洪 [女睫-目]憶
…… 1
日本出土ベトナム無釉陶器生産窯の再検討
-長胴容器製作技術の分析- …………………… 石 井
治 一 …… 28
中国褐釉陶器壺「沖縄5類・6類」の研究 …… 續 伸 一
郎 …… 53
「北方世界の交易と貿易陶磁器」の開催 ……… 髙 島
裕 之 …… 65
擦文文化期の交流・交易 ………………………… 鈴 木
琢 也 …… 67
中世北海道と本州の交易
-平泉藤原氏の事例から- …………………… 八 重 樫 忠 郎 ……
82
前近代アイヌ社会における陶磁器受容 ………… 関
根 達 人 …… 86
余市町大川遺跡迂回路地点41号墓坑の検出状況
について ………………………………………… 小
川 康 和 …… 97
矢不来館跡・大館跡・福山城下町遺跡出土の
貿易陶磁 ………………………………………… 佐
藤 雄 生 …… 103
史跡上之国館跡出土の貿易陶磁器 ……………… 塚
田 直 哉 …… 116
恵庭市・千歳市出土の中世貿易陶磁器 ……… 長
野 章 弘 …… 138
札幌市出土の陶磁器 …………………………… 小
針 大 志 …… 151
小樽市船浜遺跡における擦文文化期後期から中世の様相について
-擦文土器及び中世陶磁器の時期的・属性的特徴からの一考察-
……………………………… 山 戸 大 知 ……
155
北海道における陶磁器研究の動向
ー20世紀後半期の研究を振り返って一 …… 越
田 賢一郎 …… 165
英文概要
彙報
執筆要項
海外研究者へ
【2025年9月18日 【入荷】【ご注文承り中】
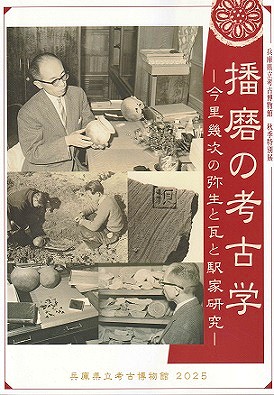
書籍番号
82771
書 名
播磨の考古学―今里幾次の弥生と瓦と駅家研究―
シリーズ
(兵庫県立考古博物館特別展示図録No.36)
データ
A4 60頁
ISBN/ISSN
編著者
兵庫県立考古博物館編集
出版年
2025年8月
出版者
兵庫県立博物館
価 格
1,700円(税込)
今里幾次(1919-2017)は、兵庫県の考古学研究の黎明期を牽引した
考古学者です。特に播磨の弥生土器と古瓦の研究を行い、兵庫県の歴史
研究に大きな足跡を残しました。姫路市に生まれた今里は、17歳で銀行
に勤め始めた頃から考古資料の採集を始めます。21歳で学会誌に論文を
発表して以来、銀行員としての職業をもちながら生涯に渡り考古学の研
究を進めました。
本展では、ご遺族から考古資料を引継いだことを記念し、今里の業績
と資料を披露するとともに、その研究から発展した最新の考古学研究の
成果についても紹介します。
目次
例言・凡例
一 考古学との出会い ………………………………………… 1
二 辻井縄文遺跡の発見 ……………………………………… 7
三 播磨弥生文化の研究 ……………………………………… 13
四 古瓦研究と駅家 …………………………………………… 25
五 その後の播磨の考古学 …………………………………… 33
展覧会関連地図 ………………………………………………… 37
各論 今里幾次の弥生研究に想う… 森岡秀人 ……………… 38
今里幾次と播磨弥生研究…… 篠宮 正 ……………… 42
今里幾次と古代寺院研究…… 菱田哲郎 ……………… 46
魚橋瓦窯跡ー平安後期瓦生産研究の曙光ー
……………………池田征弘……………… 50
引用・参考文献 ………………………………………………… 56
展示目録 ………………………………………………………… 58
謝辞・協力 ……………………………………………………… 60
【2025年9月11日 【入荷】【ご注文承り中】
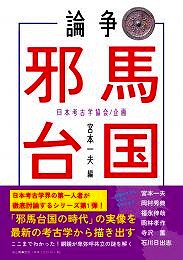
書籍番号
82746
書 名
論争 邪馬台国
シリーズ
データ
A5 184頁
ISBN/ISSN
978-4639030683
編著者
日本考古学協会企画 宮本
一夫編
出版年
2025年8月
出版者
(株)雄山閣
価 格
2,750円(税込)
討論のさきにみえたものとは?「邪馬台国の時代」の実像を最新の考古学から
描き出すここまでわかった!銅鏡が卑弥呼共立の謎を解く
【目次】
歴史考古学からみた倭王権の形成(岡村秀典)
三角縁神獣鏡と親魏倭王(福永伸哉)
「邪馬台国の時代」と古墳(岡林孝作)
纒向王権と邪馬台国論(寺沢 薫)
弥生時代研究からみた邪馬台国の時代(石川日出志)
弥生時代の楽浪交易からみた邪馬台国の時代(宮本一夫)
討論 考古学が解明する邪馬台国の時代
【2025年9月11日 【入荷】【ご注文承り中】
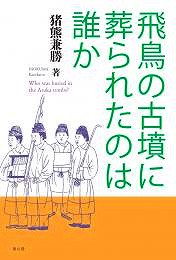
書籍番号
82748
書 名
飛鳥の古墳に葬られたのは誰か
シリーズ
データ
A5 258頁
ISBN/ISSN
978-4639030461
編著者
猪熊 兼勝著
出版年
2025年8月
出版者
(株)雄山閣
価 格
2,970円(税込)
これまでタブー視されてきた飛鳥古墳の被葬者論に挑む!
長年、高松塚古墳・キトラ古墳などの発掘調査に携わった著者が考古学的に
検証する。
序言
関連地図
関連系図
第1章 蘇我氏の墓
第2章 蘇我出自の女性墓
第3章 蘇我氏の終焉墓
第4章 八角形墳と舒明陵
第5章 薄葬令と孝徳陵
第6章 牽牛子塚古墳と斉明天皇
第7章 阿武山鎌足墓
前編まとめ 前方後円墳から八角形墳へ
第8章 天武・持統の合葬と聖なるライン
第9章 悲運、2人の皇子墓
第10章 真弓丘の皇子墓
第11章 壁画古墳の諸問題
第12章 キトラ古墳と吉野盟約の皇子たち
第13章 聖徳太子信仰と古墳の改修
第14章 斉明は父墓を改葬したのか
第15章 天智陵の完成と持統天皇・石上麻呂
第16章 火葬古墳と文武天皇
第17章 飛鳥時代の墓前祭祀
後編まとめ 飛鳥古墳の特異性
付録 飛鳥古墳の皇陵治定略史
【2025年9月11日 【入荷】【ご注文承り中】
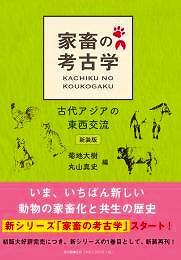
書籍番号
82745
書 名
家畜の考古学 古代アジアの東西交流【新装版】
シリーズ
データ
A5 213頁
ISBN/ISSN
978-4639030485
編著者
丸山真史 菊地大樹編
出版年
2025年5月
出版者
(株)雄山閣
価 格
3,080円(税込)
いま、いちばん新しい動物の家畜化と共生の歴史、新シリーズ「家畜の
考古学」スタート!初版大好評完売につき、新シリーズの1巻目として、
新装再刊!
イノシシ・ブタ編
ウマ編
イヌ・ネコ編
ウシ編
ニワトリ編
海を渡らなかった家畜たち
【目次】
序章 家畜研究と人類史(丸山真史)
日本列島にきた家畜(丸山真史)
動物骨と卜い(宮崎泰史)
埴輪に象られた家畜(日高 慎)
東北アジア先史時代動物形製品からみた動物観(古澤義久)
西アジア・中央アジアにおける牧畜のはじまり(新井才二)
牧畜のきた道(菊地大樹)
草原地帯の牧畜
―キルギス共和国アク・べシム遺跡における動物の利用―(植月 学)
遊牧民の動物文様からなにがわかる?
―スキト・シベリア動物文の歴史的意義―(松本圭太)
黄河の羊、長江の豚(今村佳子)
ニワトリのはじまりと広がり(江田真毅)
環境史のなかの家畜
―古代中国における馬・牛と人の関係史―(村松弘一)
乳の恵(平田昌弘)
家畜はなにを食べるの?(板橋 悠)
古代DNA
からみた家畜の起源と系統(覚張隆史)
【2025年9月11日 【入荷】【ご注文承り中】
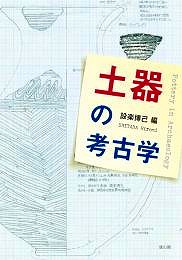
書籍番号
82747
書 名
土器の考古学
シリーズ
データ
A5 266頁
ISBN/ISSN
978-4639030478
編著者
設楽 博己著
出版年
2025年8月
出版者
(株)雄山閣
価 格
2,970円(税込)
考古学の基本はすべて土器にある最新の土器研究と科学分析から、古代の
くらしがみえてきた?
序文(高瀬克範・福田正宏)
日本の先史土器研究(設楽博己)
韓半島の先史土器研究(古澤義久)
シベリア・極東の先史土器研究(福田正宏)
中国の先史土器研究(石川岳彦)
西アジアの先史土器研究(三宅 裕)
縄文土器の始まりと終わり(工藤雄一郎)
弥生土器の始まりと終わり(小林青樹)
葬送儀礼と縄文土器―高砂貝塚の墓域分析を中心に―(山田康弘)
葬送儀礼と弥生土器(小林青樹)
縄文土器の立体画とまつり(中村耕作)
弥生土器の平面画とまつり(小林青樹)
縄文土器と集団の移動(西村広経)
弥生土器からさぐる海人集団の動向(杉山浩平)
Column 縄文時代の土器埋設遺構が示す地域のつながり(太田 圭)
Column 土器製塩研究の到達点(田邊えり)
縄文土器の時間と空間(小林謙一)
Column 土器の編年表(小林青樹・杉山浩平・林 正之)
弥生土器の時間と空間(山下優介)
縄文土器の東西差と社会(千葉 豊)
Column 春日式土器編年逆転の顛末(東 和幸)
Column 西日本の大洞系土器(小久保竜也)
弥生土器の東西差と社会(根岸 洋)
北海道島の先史土器(榊田朋広)
Column オホーツク土器にみられる動物意匠(熊木俊朗)
Column 土器を使わないアイヌ文化(高瀬克範)
琉球列島の先史土器(山崎真治)
型式と様式(高瀬克範)
木器と土器(春成秀爾)
Column
土器とジェンダー(羽生淳子)
Column 土器づくりと文様施文(齋藤瑞穂)
精製土器と粗製土器(千葉 豊)
先史土器と民族考古学(根岸 洋)
土師器研究の特質(滝沢 誠)
須恵器研究の特質(田中 裕)
埴輪研究の特質(日高 慎)
先史土器と陶磁器研究の比較(堀内秀樹)
Column 土器の実測図の歴史(設楽博己・淺間 陽)
Column 土器と学校教育(中島博司)
年代測定と食性分析における土器の役割(國木田 大)
弥生時代に炊飯器はあったのか―残存脂質分析の視点―(庄田慎矢)
Column 先史土器の使用痕研究(久保田慎二)
Column 先史土器の漆と赤色顔料の塗彩からわかること(根岸 洋)
レプリカ法による土器圧痕研究の到達点(太田 圭・守屋 亮)
Column 土器の潜在圧痕とはなにか(國木田 大)
Column 土器の系統と核ゲノム(藤尾慎一郎)
編者言(設楽博己)
【2025年8月25日 【入荷】【ご注文承り中】
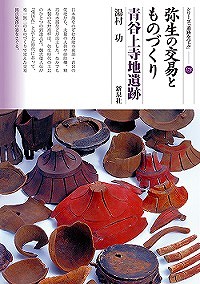
書籍番号
82732
書 名
弥生の交易とものづくり
青谷上寺地遺跡
シリーズ
(シリーズ「遺跡を学ぶ」 173)
データ
A5 96頁
ISBN/ISSN
978-4-7877-2533-2
編著者
湯村 功著
出版年
2025年8月
出版者
新泉社
価 格
1,870円(税込)
砂防柵、精巧な木器などが出土した。なかでも木製の花弁高
杯は、弥生時代の工芸のひとつの到達点だ。魏志倭人伝が「
倭国乱」と記した時代にあって、唯一無二のものづくりで栄
えた交易拠点集落の姿をさぐ
る。
第1章 弥生人骨と脳の発見
1 弥生人の脳が残っていた!
2 散乱して出土した人骨
3 殺傷痕や病変のある人骨
4 埋められた人骨の謎
1 遺跡の立地
2 発掘調査の歴史
3 中心域と遺跡の変遷
1 相次いだ新発見
2 多種多量、保存状態のよい出土遺物
3 集落構造をさぐる
1 もうひとつのキャッチフレーズ
2 どこと交易をしていたのか
3 交易拠点ならではの祭祀
4 集落の終焉と青谷上寺地遺跡の意義
【2025年8月12日 【入荷】【ご注文承り中】
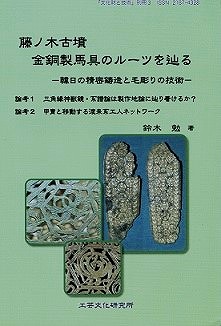
書籍番号
82735
書 名
藤ノ木古墳金銅製馬具のルーツを辿る-韓日の精密鋳造と毛彫りの技術ー
シリーズ
(「文化財と技術 別冊3)
データ
A5 190頁
ISBN/ISSN
2187-4328
編著者
鈴木 勉著
出版年
2025年4月
出版者
工芸文化研究所
価 格
1,100円(税込)
第一部 藤ノ木古墳金銅製馬具のルーツを辿る
-韓日の精密鋳造と毛彫りの技術ー
1.飾履塚古墳の名前の由来となった飾履
2.金銅製獅噛文帯金具の精密鋳造「埋け込み法」
3.高敞郡鳳徳里古墳出土金銅製飾履の精密鋳造技術
4.陜川玉田M3号墳出土環頭大刀4振りの鋳造技術
5.公州水村里遺跡Ⅱ-1号墳出土銀象嵌環頭大刀の鋳造技術
6.4,5世紀代の環頭大刀の鋳造技術
(象嵌大刀などを事例として)
7.6世紀百済の鋳造技術
1.線彫り技術は最先端技術
2.漢城期百済 -3系統の線彫り技術-
3.熊津期百済の線彫り技術
4.泗?期百済の線彫り-中国北朝から百済・倭への技術移転-
5.新羅の線彫り技術
1.線刻團華雙鳥文金箔の発見
2.線彫りの表現技法
3.線彫りの細かさ(基準精度)
4.使用工具と技術
5.金工の祖・中国をしのぐ精緻な線彫り
1.日本列島の毛彫り技術史の例外2例
2.日本列島の鋳造技術(二層式鋳型)
3.北朝から百済、日本列島へ移動する(渡来系)工人、
そして定住への道
4.造像銘・墓誌の毛彫り技術 -藤ノ木馬具以降-
1.ヒトの系譜と生誕地
2.製作地に辿り着けない三角縁神獣鏡系譜論
3.三角縁神獣鏡製作地論
4.型式学の運用方法に対する疑問
1.同一規格(?)の大量生産品は畿内で製作されたことに
なるか?
2.「大和王権下か地方政権下か」二者択一の製作地論
3.工人(古代人)の拠り所
【2025年7月29日 【ご注文承り中】
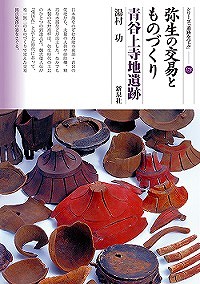
書籍番号
82732
書 名
弥生の交易とものづくり
青谷上寺地遺跡
シリーズ
(シリーズ「遺跡を学ぶ」 173)
データ
A5 96頁
ISBN/ISSN
978-4-7877-2533-2
編著者
湯村 功著
出版年
2025年8月
出版者
新泉社
価 格
1,870円(税込)
砂防柵、精巧な木器などが出土した。なかでも木製の花弁高
杯は、弥生時代の工芸のひとつの到達点だ。魏志倭人伝が「
倭国乱」と記した時代にあって、唯一無二のものづくりで栄
えた交易拠点集落の姿をさぐ
る。
第1章 弥生人骨と脳の発見
1 弥生人の脳が残っていた!
2 散乱して出土した人骨
3 殺傷痕や病変のある人骨
4 埋められた人骨の謎
1 遺跡の立地
2 発掘調査の歴史
3 中心域と遺跡の変遷
1 相次いだ新発見
2 多種多量、保存状態のよい出土遺物
3 集落構造をさぐる
1 もうひとつのキャッチフレーズ
2 どこと交易をしていたのか
3 交易拠点ならではの祭祀
4 集落の終焉と青谷上寺地遺跡の意義
【2025年7月29日 【ご注文承り中】

書籍番号
82733
書 名
筑紫君磐井と「磐井の乱」 岩戸山古墳〔改訂版〕
シリーズ
(シリーズ「遺跡を学ぶ」094)
データ
A5 96頁
ISBN/ISSN
978-4-7877-2542-4
編著者
柳澤 一男著
出版年
2025年6月
出版者
新泉社
価 格
1,870円(税込)
墓である岩戸山古墳は、武人・力士・馬などをかたどった多くの石製
品で飾られていることでも有名だ。北部九州から朝鮮半島の古墳も視
野に入れ、継体王権と磐井の関係、磐井の乱の実像にせまる。改訂版
では、近年調査が進んでいる朝鮮半島の古墳の情報を修正した。
1 奈良時代の史書に記録された古墳
2 磐井墓探しの歴史
1 南筑後の古墳と岩戸山古墳
2 八女の首長墓系列
3 北部九州最大の岩戸山古墳
1 石製表飾と石人石馬
2 甲冑形石製品の盛行
3 多様な石製品の登場
4 岩戸山古墳の石製表飾
5 岩戸山古墳以後の石製表飾
1 文献にみる「磐井の乱」
2 有明首長連合の形成と衰退
3 九州勢力の再結集─継体王権との連携
1 朝鮮半島の倭系古墳
2 「磐井の乱」の要因
1 九州諸勢力の動向
2 ミヤケの設置
【2025年7月29日 【入荷】【ご注文承り中】
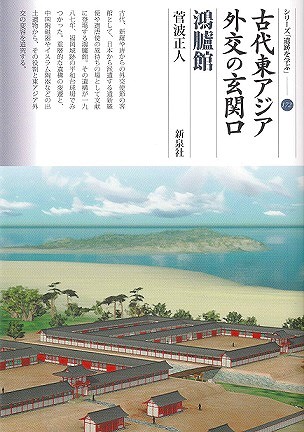
書籍番号
82731
書 名
古代東アジア外交の玄関口 鴻臚館
シリーズ
(シリーズ「遺跡を学ぶ」 172)
データ
A5 96頁
ISBN/ISSN
978-4-7877-2532-5
編著者
菅波 正人著
出版年
2025年8月
出版者
新泉社
価 格
1,870円(税込)
古代、新羅や唐からの外交使節の客館として、日本から派遣する
遣新羅使や遣唐使の風待ちの場として文献に登場する鴻臚館。
その遺構が一九八七年、福岡城跡の平和台球場でみつかった。
重層的な遺構の変遷と、中国陶磁器やイスラム陶器などの出土遺
物から、その役割と東アジア外交の変容を追究する。
第1章 「幻の鴻臚館」発見
1 幻の鴻臚館
2 鴻臚館の発見
1 筑紫大郡の登場
2 筑紫館の登場
1 鴻臚館の時期区分
2 筑紫館の成立:第Ⅰ期(7世紀後半~8世紀前半)
3 筑紫館の整備:第Ⅱ期(8世紀前半~末)
4 鴻臚館の登場:第Ⅲ期(9世紀初頭~後半)
5 唐物交易の場:第Ⅳ期(9世紀後半~10世紀前半)
6 鴻臚館の廃絶:第Ⅴ期(10世紀後半~11世紀前半)
7 鴻臚館の食料供給
1 筑紫館の新羅外交
2 唐物交易の時代
3 鴻臚館から博多へ
【2025年7月18日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82727
書 名
近畿弥生の会研究資料集 近畿弥生の会夏場所第28回集会(京都場所)発表要旨・論考集
シリーズ
データ
A4 114頁
ISBN/ISSN
編著者
近畿弥生の会編集
出版年
2025年7月
出版者
近畿弥生の会
価 格
1,100円(税込)
―複数埋葬から単数埋葬へ―」
……………… 1
菅 博絵(公益財団法人京都府埋蔵文化財調査研究センター)
発表2 滋賀県「滋賀県栗東市中沢遺跡(2024ー01)の調査
―大型掘立柱建物を伴う弥生時代の集落―】」 … 11
近藤 広(公益財団法人栗東市スポーツ協会)
発表3 奈良県「橿原市土橋遺跡(第20次)の調査
―弥生時代中期後葉の方形周溝墓群―」 …………
23
蓮井寛子(奈良県立橿原考古学研究所)
発表4 和歌山県「新宮市八反田遺跡の調査
―紀伊半島南東岸の集落―」
……………… 31
小林高太(新宮市教育委員会)
発表5 兵庫県「姫路市和久遺跡の調査―播磨における弥生時代から
古墳時代初頭にかけての集落遺跡の一例―」 ……
41
福井 優(姫路市教育委員会)
発表6 大阪府「茨木市郡遺跡・倍賀遺跡の調査
―居住域の広がりと新たな墓域の発見―」 …………
70
鹿野 塁(公益財団法人大阪府文化財センター)
―論考篇―
【論文】
琵琶湖沿岸地域における弥生中期土器編年および地域性の形成について
佐々木仁志
……… 86
【研究ノート】
近畿地域とその周辺地域における鉄器鍛冶炉を持つ竪穴建物の諸特徴に
ついて
上田裕人 …………… 104
【2025年7月18日 【入荷】【ご注文承り中】
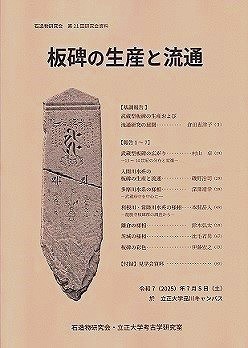
書籍番号
82725
書 名
板碑の生産と流通
シリーズ
(石造物研究会 第21回研究会資料)
データ
A4 95頁
ISBN/ISSN
編著者
石造物研究会関東大会事務局
出版年
2025年7月
出版者
石造物研究会・立正大学考古学研究室
価 格
2,200円(税込)
流通研究の展開………………………………………倉田恵津子 (3)
【報告1~7】
武蔵型板碑の広がり
…………………………………村山 卓(19)
―13~14世紀の分布と変遷―
入間川水系の
板碑の生産と流通
……………………………………磯野治司(29)
多摩川水系の様相…
…………………………………深澤靖幸(39)
―武蔵府中を中心に―
利根川・常陸川水系の様相 …………………………本間岳人(49)
―龍腹寺板碑群の調査から―
鎌倉の様相………………………………………………鈴木弘太(59)
茨城の様相………………………………………………比毛君男(67)
板碑の彩色………………………………………………伊藤宏之(77)
【2025年7月18日 【入荷】【ご注文承り中】
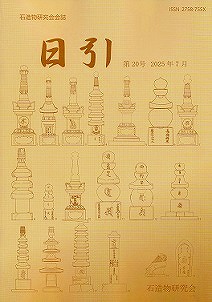
書籍番号
82726
書 名
日引 第20号
シリーズ
(石造物研究会会誌)
データ
B5 310頁
ISBN/ISSN
2758-755X
編著者
石造物研究会編集
出版年
2025年7月
出版者
石造物研究会
価 格
4,400円(税込)
古墳の石材を転用した石造物
中岡敬善 17
-古代~近代における石棺・石室材の転用例について-
大和円福寺の宝篋印塔
本間岳人 29
-3D計測の成果と新出銘文-
高野山西南院所在の石塔 西山祐司
41
鎌倉時代の高野山町石の生産と建立
奥田 尚 47
和歌山城跡出土の凝灰岩製笠塔婆
北野隆亮 59
-讃岐から紀伊に搬人された中世石塔-
近畿地域に搬人された中世讃岐産石造物について
松田朝由 71
一乗谷朝倉氏遺跡における石造物研究の現状と課題
藤井佐由里 83
美作国誕生寺宝篋印塔の基礎的分析
柴田 亮 95
防長地域における防長型無縫塔の展開
内田大輔 107
肥後相良氏の造塔行為と菊鹿型宝篋印塔の誕生
高 橋 学 119
川内川流域における鎌倉・南北朝期板碑の一事例
税田脩介 131
-えびの市彦山寺跡板碑の計測-
総見院織田家一族墓所の石塔実測記
狭川真一 141
白井愛梨
緑色片岩製石造物の分布圏における石材・塔種の様相
木谷智史 151
-和歌山県橋本市地蔵寺の調査事例より-
分割された家形石棺
矢野定治郎 165
-綾塚古墳にみられる矢穴技法の検討-
蘇洞門石材小考
太田まり子 177
村山 卓
山陰地域の一石彫成五輪塔と一石五輪塔について
八峠 興 189
滑石製の狛犬
渡辺 昇 201
勿谷石製狛犬の変容
山下 立 215
ー永正期から天文期へー
石造若木神坐像
畠山篤雄 227
熊谷美知子
愛媛県高鴨神社サムハラ塔
十亀幸雄 239
-習俗化した法華信仰-
三田市藍本日出坂墓地の調査
江﨑周二郎 249
ー江戸~明治時代の背光五輪塔・墓標
和泉国日根郡における六地蔵、六観音の様相
三好義三 261
琉球亀甲墓閑話
松原典明 273
考古学における近・現代戦争関連碑研究序論
大下 明 285
ニュースレター『ひびき』バックナンバー 一覧
306
編集後記
【2025年7月18日 【再掲】【ご注文承り中】
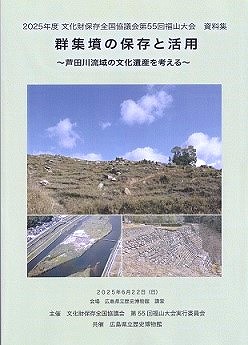
書籍番号
82711
書 名
群集墳の保存と活用~芦田川流域の文化遺産を考える~
シリーズ
(2025年度 文化財保存全国協議会第55回福山大会 資料集)
データ
A4 62頁
ISBN/ISSN
編著
文全協第55回福山大会実行委員会編集
出版年
2025年6月
出版者
文全協第55回福山大会実行委員会
価 格
1,400円(税込)
「本書、森岡秀人の「古墳時代群集墳の調査・研究の過去・現在と展望」
12Pの報告は、これまでの50年近くの考古学研究史を概観するだけでなく、
文献史学の郷戸などの小家族への研究史、評価を含め現在の群集墳研究の
問題点を網羅し、到達点を示す必読書で、これから群集墳を研究しようと
する考古学徒必携の論文と言える。」
前行橋市歴史資料館館長 宇野愼敏
───────────────────────────────
【目次紹介】
鈴木康之氏(県立広島大学名誉教授)
福山地域における砂留群の構築と保存活動 …………………………10
向井厚志氏(福山市立大学教授)
───────────────────────────────
古墳時代群集墳の調査・研究の過去・現在と展望 …………………14
森岡秀人氏(奈良県立橿原考古学研究所共同研究員)
1.古墳時代群集墳とは一体何か
2.群集墳析出の時間軸上の問題点
3.空間分析における群集墳析出と構造比較上の議論
4.群集墳の群構造と支群・小支群・個別墳、その先にある個人埋葬
の把握はいかに
5.群集墳被葬者層と古墳時代の集落研究
6.群集墳の消滅の諸問題―令制社会の前夜、7世紀史における
高制度化―
7.地域の群集墳の保存と活用に向けて
8.基調報告を終えるにあたって
───────────────────────────────
御領古墳群と御領の古代ロマンを蘇らせる会の活動 ………………25
端本てる子氏(御領の古代ロマンを蘇らせる会代表)
津山市日上畝山古墳群の保存と活用(県指定遺跡)…………………32
小郷利幸氏(津山弥生の里文化財センター主任)
特別史跡岩橋千塚古墳群と地域・学校・博物館 ……………………39
萩野谷正宏氏(和歌山県立紀伊風土記の丘学芸課長)
赤色立体地図及びQGIS等高線図から古墳を探る …………………47
曳野律夫氏(本庄考古学研究所代表)
見学会資料6月21日(土)
堂々川砂留 御領古墳群 江草古墳 吉備津神社
寄稿「備後一宮・吉備津神社の備前焼狛犬」 ………………………61
鈴木重治氏(東洋陶磁学会・名誉会員)
【2025年7月15日 【再入荷】【ご注文承り中】
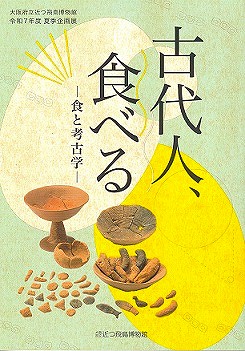
書籍番号
82699
書 名
古代人、食べる―食と考古学―
シリーズ
(大阪府立近つ飛鳥博物館図録93)(大阪府立近つ飛鳥博物館 令和7年度夏季企画展)
データ
A4 71頁
ISBN/ISSN
編著
大阪府立近つ飛鳥博物館編集
出版年
2025年6月
出版者
大阪府立近つ飛鳥博物館
価 格
1,600円(税込)
【開催趣旨】
──────────────────────────────────
“食べる”という行為は、私たちが生きてゆくうえで欠かせません。もちろん、
古代に生きた人々も同様でした。しかし、古代の人びとがどのようなものを、
いかにして食べていたかということについては、まだまだ明らかになってい
ません。それは、日本の風土の特性上、食材となるような有機物は早い段階
で腐るなどして朽ちてしまうためで、そのために遺跡などから食物が出土す
ることは、きわめてまれです。
今回の展示では、そのように遺跡からあまり出土することのない植物や動物
・魚の骨など、食物にかかわる直接的な痕跡のほか、石器や土器、木製品な
どの道具のうち、食にかかわるものを紹介し、おもに弥生時代から奈良時代
にかけての古代人の“食”に迫りたいと思います。“食”にかかわる行為として、
“とる・たべる・だす・ささげる”という4つのテーマを取り上げ、それらを
物語る資料を展示し、それらの変化やその背景について考えます。
私たちが祖先から連綿と受け継いできた“食べる”という行為は、あまりにも
身近で普段は気にかけることが少ないかも知れません。だからこそ、この展
示をきっかけとして、古代人そして現代の私たちの“食べる”という行為にあ
らためて注目し、想いを巡らせてもらえればと思います。
──────────────────────────────────
【展示構成とおもな展示品】
──────────────────────────────────
◯ 第1章 とる
・動物遺存体(シカ・イノシシ・ノウサギ・タヌキ)/田原本町教育委員会
・魚介類遺存体(フグ・タイ・ウニ・ハマグリ)/大阪府教育委員会・大阪
府立弥生文化博物館
・植物遺存体(炭化米・モモ核・アズキ・ウリ・ノブドウ)/田原本町教育
委員会・石鏃/田原本町教育委員会
・手網枠/大阪市教育委員会
・石包丁/大阪府教育委員会・大阪府立弥生文化博物館
・弥生土器(甕・壺・鉢・高坏・把手付鉢)/大阪府教育委員会・大阪府立
弥生文化 博物館
・土師器(甕・壺・鉢)/大阪市教育委員会
・須恵器(壺・高坏・器台・瓶)/大阪市教育委員会
・韓式系土器(甑・鍋・鉢)/大阪市教育委員会
・木簡(進物○/加須津毛瓜/醤津毛瓜/醤津名我∥○/加須津韓奈須比∥
○右種四物○九月十九日)/奈良文化財研究所
・ちゅう木/奈良市教育委員会
・寄生虫卵・花粉パネル/画像提供 奈良市教育委員会
・行者塚古墳出土
食物形土製品・土師器・笊形土器/加古川市教育委員会
・ナガレ山古墳出土
食物形土製品・土師器/河合町教育委員会
・一須賀古墳群出土
子持器台/大阪府教育委員会・大阪府立近つ飛鳥博物館
【2025年7月15日 【再入荷・残部少】【ご注文承り中】
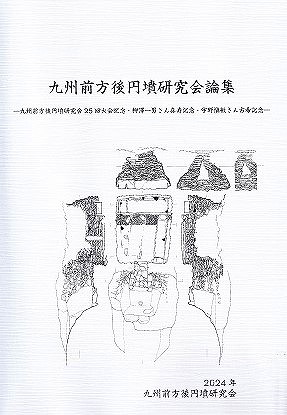
書籍番号
82307
書 名
九州前方後円墳研究会論集
シリーズ
―九州前方後円墳研究会第25回大会記念・柳澤一男さん喜寿記念・宇野愼敏さん古稀記念―
データ
A4 277頁
ISBN/ISSN
編著者
九州前方後円墳研究会編集
出版年
2024年6月
出版者
九州前方後円墳研究会
価 格
3,960円(税込)
柳澤一男さん近影
字野愼敏さん近影
論集刊行にあたって思いつくままに 田中 裕介
論集刊行にあたって 杉井 健
宗像地域における古墳時代首長墓の動向
………………池ノ上 宏 01
成川式土器の甅形小型壺
…………………………………大西 智和 11
延岡平野部の古墳時代墓制について
……………………甲斐 康大 21
筑紫君磐井の乱勃発の真因について
……………………蒲原 宏行 29
墳丘の内に石を見出すこと
………………………………小嶋 篤 39
佐賀県東部地域における古墳時代終末期の大型石室
…小松 譲 47
竹並横穴墓群の刀剣秩序と京都平野の軍事的特質
……齊藤 大輔 57
阿蘇谷における古墳築造系譜試論
………………………杉井 健 67
有明海・八代海沿岸地域の家形石棺
……………………高木 恭二 77
福岡県福津市久末出土の装飾付須恵器とその周辺
……田上 浩司 87
九州島東海岸における古墳時代小型丸底製塩土器
……田中 裕介 95
墳端外側テラスについての一考察 ………………………玉川 剛司
105
遠賀川流域における前期の小型古墳と集団墓
…………田村 悟 115
有明海沿岸地域の古墳時代前期墳墓の築造
……………檀 佳克 125
―石人山古墳以前の八女古墳群の理解に向けて―
豊前地域における拠点集落の一様相
……………………長 直信 131
―黒田畑堀遺跡2区における厩舎遺構の発見とその意義―
北部九州における装飾古墳の築造とその背景 ………辻田 淳一郎 141
宮崎県都城市菓子野2007-1号地下式横穴墓出土のイモガイ製釧
………………中村 友昭
151
下那珂馬場古墳の検討―採集資料の紹介を通して― …西嶋 剛広
161
島内114号地下式横穴墓出土の龍文銀象嵌大刀
………橋本 達也 169
新聞から読む大分の考古学―消滅した南大分の古墳群―
………………服部 真和 179
前方後円墳と豪族居館の方位と天文景観―赤塚古墳と小部遺跡の検討―
……………弘中 正芳 189
佐賀県下における外来系瑪瑙製玉類の出土傾向 ……渕ノ上 隆介 199
九州・近畿地方における古墳時代集落の立地とその変動
………………古川 匠
205
筑紫平野北部の三国丘陵上の古墳と集落と馬飼い(予察)
………………宮田 浩之 215
北九州における海岸部古墳について
…………………宮元 香織 223
南九州西沿岸部における板石積石棺墓の変遷 ………三好 栄太郎 233
御塔山古墳と周辺集落との関係
………………………吉田 和彦 243
山崎砂丘遺跡出土の特殊扁壷について
………………和田 理啓 253
……………………………………………………………………………………
柳澤一男さん 字野愼敏さん 略年譜・著作目録・記念写真 ………259
柳澤一男さん 略年譜 …………………………………………………261
柳澤一男さん 著作目録 ………………………………………………262
字野愼敏さん 略年譜 …………………………………………………267
宇野愼敏さん 著作目録 ………………………………………………268
九州前方後円墳研究会。柳澤一男さん・宇野愼敏さん 写真 ………273
【2025年7月10日 【入荷】【ご注文承り中】
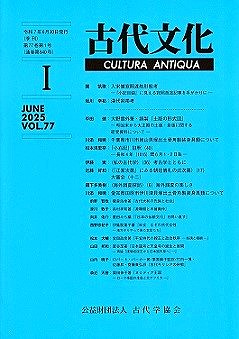
書籍番号
82723
書 名
古代文化 第77巻 第1号(640号)
シリーズ
データ
B5 125頁
ISBN/ISSN
0045-9232
編著
出版年
2025年6月
出版者
(公財)古代学協会
価 格
2,970円(税込)
〈論 攷>
[龍/共]
凱歌:入宋僧寂照渡航形態考
ー「小記目録』に見える寂照首途記事を手がかりに
………… 1
坂川 幸祐:漢代剣帯考 ………………………………………………… 21
〈研究ノート〉
平田 健:大野雲外筆・調製『土版の形式図』』
ー明治末から大正期の土版・岩版に関する研究資料について
… 40
川添 和暁:千葉県市川市姥山貝塚出土骨角製装身具類について …
51
〈主 釈〉
松本満里奈:「小右記』註釈(40)-長和4年(1015)閏6月1・2日条-
…………… 59
伊藤 実:〈私の古代学〉(36)考古学とともに ……………………
67
近藤 好和:〈『江家次第』にみる朝廷儀礼の式次第〉(17)大嘗会(十ニ)
…… 78
國下多美樹:〈海外調査探訪〉(6)海外調査の楽しさ
………………… 85
〈図版解説〉
川添 和暁:愛知県田原市伊川津貝塚出土骨角製装身具類について … 90
〈書 評〉
前野 智哉:鷺森浩幸著『古代大和の氏族と社会』 …………………… 92
滑川 敦子:長村祥知著『源頼朝と木曾義仲』 ………………………… 95
向井 佑介:重田みち編『「日本の伝統文化」を問い直す』 ………… 98
西野悠紀子:伊集院葉子著『采女 なぞの古代女性一地方からやって来た
女官たち』 ……………………………………………………101
松本 大輔:安田政彦著『平安時代の親王と政治秩序ー処遇と婚姻-』
………104
山田 邦和:冨谷至著『日本国号と天皇号の誕生と展開
ー再論「漢倭奴国王から日本国天皇へ」 …………………107
〈新刊紹介〉
山内 暁子:ロバート・パーカー著/栗原麻子監訳/竹内一博・佐藤昇・齋藤
貴弘訳 『古代ギリシアの宗教』 ……………………………111
森近 天音:栗田伸子著『ヌミディア王国一口一マ帝国の生成と北アフリ
カー』 …………………………………………………………112
【2025年7月8日 【入荷】【ご注文承り中】
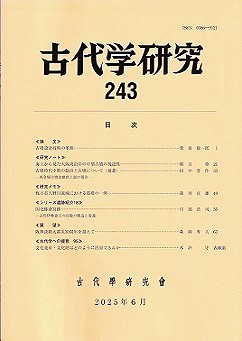
書籍番号
82716
書 名
古代学研究 第243号
シリーズ
データ
0386-9121
ISBN/ISSN
0386-9121
編著
古代学研究編集局
出版年
2020年3月
出版者
価 格
990円(税込)
《論 文》
古墳設計技術の革新…………………………………柴 原 聡一郎
1
海上から見た大阪湾沿岸の中型古墳の視認性……朝 日 格 21
古墳時代中期の鎹出上古墳について(補遺)………田 中 晋 作 33
-珠金塚古墳北槨出上鎹の報告-
枚方市天野川流域における霞堤の一例……………森 井 貞 雄 49
国史跡斎宮跡…………………………………………川 部 浩 司 55
-古代伊勢斎王の宮殿の構造と変遷-
阪神淡路大震災30周年を迎えて……………………森 岡 秀 人 61
文化遺産・文化財はどのように活用できるか……木 許 守 表紙裏
【2025年7月4日 【入荷】【ご注文承り中】
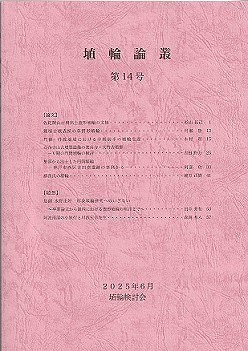
書籍番号
82714
書 名
埴輪論叢 第14号
シリーズ
データ
A4 65頁
ISBN/ISSN
編著
埴輪検討会事務局編集
出版年
2025年6月
出版者
埴輪検討会
価 格
2,090円(税込)
佐紀陵山古墳出上蓋形埴輪の文様………………………………杉山 拓己 1
鶯塚古墳表採の草摺形埴輪………………………………………村瀨 陸
13
丹後・丹波地域における中期前半の埴輪生産…………………木村
理 15
心合寺山古墳築造後の楽音寺・大竹古墳群
ーV期の円筒埴輪の検討ー …………………………………吉田
野乃 25
集落から出上した円筒埴輪
ー神戸市西区吉田南遺跡の事例からー
……………………阿部 功 33
蘇我氏の埴輪
……………………………………………………鐘方 正樹 41
恩師 水野正好 形象埴輪研究へのいざない
~卒業論文から畿内における蓋形埴輪の検討まで~ ……田中
秀和 53
阿波南部の小旅行と川西宏幸先生 ……………………………森岡 秀人
57
【2025年7月1日 【品切】
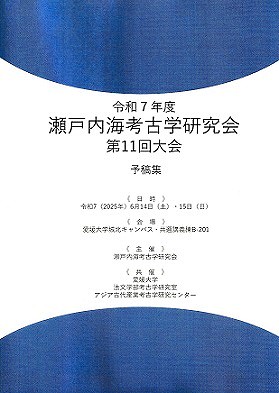
書籍番号
82708
書 名
令和7年度 瀬戸内海考古学研究会第11回大会予稿集
シリーズ
データ
A4 64頁
ISBN/ISSN
編著
愛媛大学東アジア古代産業考古学研究センター編集
出版年
2025年6 月
出版者
瀬戸内海考古学研究会
価 格
(税込)
頁
陸と海から古瀬戸内旧石器時代を見直す ……………森先一貴
1
縄文時代草創期/早期移行期の芸予諸島
ー上島町宮ノ浦遺跡の調査成果より一 ……………村上恭通
5
弥生時代・瀬戸内の南北交流一芸予を例に一 ………伊藤 実
15
西部瀬戸内系器台の西への広がりについて ………松村さを里 21
朝鮮半島系土器からみた古墳時代日韓交流における西部瀬戸内
…………………松永悦枝 29
中四国地方の古代製塩土器
ー西部瀬戸内地域と山陰地域を中心として一 ……福本佳織 37
西部瀬戸内地域における朝鮮王朝陶磁器 ……………益田千遥 47
西部瀬戸内を越えて一中世後期貿易陶磁器の流通ー
…………………………………柴田圭子 57
【2025年6月27日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82707
書 名
佐紀古墳群 航空レーザ測量調査報告書
シリーズ
データ
A4 巻頭カラー10 頁本文178頁
ISBN/ISSN
978-4864451888
編著
村瀨 陸 柴原 聡一郎著
出版年
2025年7月
出版者
株式会社 六一書房
価 格
3,850円(税込)
本書は、2023年に実施した佐紀古墳群の航空レーザ測量の調査報告書
である。佐紀古墳群は、奈良市北縁部に位置し、大型前方後円墳をは
じめとする約70基が確認されている。しかし、多くが陵墓地であるこ
とから、これまで精緻な測量図が整備されていなかった。そこで筆者は、
クラウドファンディングを活用した調査を計画して実施することができ
た。調査により、大型前方後円墳の詳細な墳丘構造が明らかになっただ
けでなく、周辺地形も合わせて測量できたことで、なぜそこに古墳が造
られたのかなども可視化できた。
本書では、測量調査報告だけでなく、佐紀古墳群に関する既往の研究
史をまとめたものや、調査成果をもとにした論考6編を収録した。今後の
佐紀古墳群を研究する上で重要な一冊となるように努めた。
【目次】
1 航空レーザ測量実施風景(佐紀古墳群東群)
2 佐紀古墳群空中写真1
3 佐紀古墳群空中写真2
4 段彩傾斜量図(佐紀古墳群全景)
5 段彩傾斜量図(佐紀古墳群西群)
6 段彩傾斜量図(佐紀古墳群南群)
7 段彩傾斜量図(佐紀古墳群東群)
8 段彩傾斜量図(鳥瞰図)1
9 段彩傾斜量図(鳥瞰図)2
10 佐紀池ノ尻古墳段彩傾斜量図
第1章 調査の概要
第1節 調査の目的
第2節 クラウドファンディングの経過
第3節 調査の経過
第4節 実施の意義
第2章 地理・歴史的環境と既往の調査
第1節 地理・歴史的環境
第2節 佐紀古墳群調査一覧
第3章 佐紀古墳群における調査・研究のあゆみ
第1節 埴輪の調査研究
第2節 副葬品の調査研究
第3節 墳丘の調査研究
第4節 大型古墳群論における佐紀古墳群
第4章 航空レーザ測量調査
第1節 航空レーザ測量の範囲と方法
第2節 佐紀古墳群
第3節 その他の古墳
第4節 その他の遺跡
第5節 新発見の古墳
第6節 大型前方後円墳の復元
第5章 大型前方後円墳の設計
第1節 分析の前提
第2節 設計の復元
第6章 佐紀古墳群の研究
第1節 前方部後部埋納施設の諸問題
第2節 墳丘付加施設としての基壇
第3節 佐紀池ノ尻古墳の研究
第4節 佐紀古墳群における古墳設計技術の展開
第5節 佐紀陵山古墳とその類型墳
第6節 佐紀古墳群の発展過程とその意義
【2025年6月27日 【入荷】【ご注文承り中】
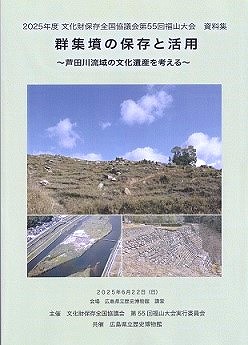
書籍番号
82711
書 名
群集墳の保存と活用~芦田川流域の文化遺産を考える~
シリーズ
(2025年度 文化財保存全国協議会第55回福山大会 資料集)
データ
A4 62頁
ISBN/ISSN
編著
文全協第55回福山大会実行委員会編集
出版年
2025年6月
出版者
文全協第55回福山大会実行委員会
価 格
1,400円(税込)
鈴木康之氏(県立広島大学名誉教授)
福山地域における砂留群の構築と保存活動 …………………………10
向井厚志氏(福山市立大学教授)
───────────────────────────────
古墳時代群集墳の調査・研究の過去・現在と展望 …………………14
森岡秀人氏(奈良県立橿原考古学研究所共同研究員)
1.古墳時代群集墳とは一体何か
2.群集墳析出の時間軸上の問題点
3.空間分析における群集墳析出と構造比較上の議論
4.群集墳の群構造と支群・小支群・個別墳、その先にある個人埋葬
の把握はいかに
5.群集墳被葬者層と古墳時代の集落研究
6.群集墳の消滅の諸問題―令制社会の前夜、7世紀史における
高制度化―
7.地域の群集墳の保存と活用に向けて
8.基調報告を終えるにあたって
───────────────────────────────
御領古墳群と御領の古代ロマンを蘇らせる会の活動 ………………25
端本てる子氏(御領の古代ロマンを蘇らせる会代表)
津山市日上畝山古墳群の保存と活用(県指定遺跡)…………………32
小郷利幸氏(津山弥生の里文化財センター主任)
特別史跡岩橋千塚古墳群と地域・学校・博物館 ……………………39
萩野谷正宏氏(和歌山県立紀伊風土記の丘学芸課長)
赤色立体地図及びQGIS等高線図から古墳を探る …………………47
曳野律夫氏(本庄考古学研究所代表)
見学会資料6月21日(土)
堂々川砂留 御領古墳群 江草古墳 吉備津神社
寄稿「備後一宮・吉備津神社の備前焼狛犬」 ………………………61
鈴木重治氏(東洋陶磁学会・名誉会員)
【2025年6月12日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82688
書 名
九州島の古墳時代における銅鏡の様相
シリーズ
(第26回九州前方後円墳研究会 長崎大会発表資料集)
データ
A4 218頁
ISBN/ISSN
編著者
九州前方後円墳研究会長崎大会実行委員会編集
出版年
2025年6月
出版者
九州前方後円墳研究会長崎大会実行委員会
価 格
3,700円(税込)
九州島の古墳時代における銅鏡の様相
開催趣旨
古墳時代において倭(畿内)王権が一元的に流通を管理し、その流通が
地域と倭(畿内)とのネットワークを反映した威信財と言われる銅鏡を
取り上げます。
本大会では古墳や祭祀遺跡から出土した銅鏡が、どのようにして九州
へ流入したのかを議論します。地域(律令制の旧国単位等)ごとに一覧表
と分布図を作成し、「九州島における銅鏡の様相」と「銅鏡が流入する
経緯」を明らかにします。対象とする時代は、その前代を含む弥生時代
終末期から古墳時代終末期までとします。
銅鏡が出土した古墳等はその時期にどのような場所にあったのか、前回
まで行ってきた「集落と古墳の動態」等の成果を参考にして分析します。
古墳や集落の集中するところか、それとも遺跡が希薄なところに突如と
して鏡を副葬した墳墓が出現するのか
を分析し、その後も同じ地域に古墳が継続するのか否かなどを整理し、
地域の中で墳墓を選定していただき、時期ごとに「地域へ銅鏡が流入す
る経緯」を提示していただきます。また、「日本列島内における九州地
域の銅鏡の様相」についても議論したい。
第26回九川前方後円墳研究会長奇大会実行委員会
……………………………………………………………………………………
目 次
基調発表
沖ノ島遺跡出土鏡一覧表
辻田淳一郎 …… 12
地域発表
古墳時代の銅鏡の流人・伝世・副葬・廃棄 久住猛雄 ……
15
遠賀川流域における弥生・古墳時代の銅鏡 安部和城・松浦宇哲
……… 33
二日市地峡から筑後地域における銅鏡の流入 秦 憲二 …… 57
筑前北東部における出土鏡について
宮元香織 …… 71
豊前地域における銅鏡の流入について
安藤壮平・安部和城・古谷真人・83
豊後における古墳時代銅鏡の分布とその意義 西 貴史・諸岡初音
……… 103
日向(宮崎県域)
朝川千聖・清水航平
……… 123
鹿児島県域(大隅・薩摩地域)の古墳時代鏡 橋本達也 …… 141
肥後地域における銅鏡の様相
原口雅隆 …… 151
肥前東部(佐賀県)における銅鏡の様相 徳富孔一 ……
171
肥前西部
古門雅高 …… 195
壱岐島出土古墳時代銅鏡について
田中聡一 …… 213
【2025年6月10日 【ご注文いただいてからの入手となります】【ご注文承り中】
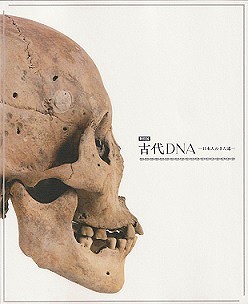
書籍番号
82691
書 名
特別展「古代DNA―日本人のきた道―」
シリーズ
データ
B5変型 152頁
ISBN/ISSN
編著者
出版年
2025年3月
出版者
東京新聞
価 格
3,700円(税込)
「古代DNA―日本人のきた道―」の図録です。
2025年7月19日~9月23日まで、名古屋市科学館で開催予定です。
(ご注文いただいてからの入手になります)
【目次】
[座談会]いま、どうして「古代DNA」展なのか
―最新の研究成果と本展の見どころ
展覧会関連年表
展覧会関連遺跡地図
プロローグ
~21世紀の日本人起源論~
[解説]古代ゲノム研究の成果を読み解くために
第1章──────────────────────────
最初の日本人―ゲノムから見た旧石器時代の人々
【インタビュー】 スバンテ・ペーポ博士
[コラム]白保竿根田原洞穴遺跡について
[コラム]白保人骨が語ること
―形質から見た白保の人々
第2章──────────────────────────
日本の基層集団―縄文時代の人と社会
【頭骨の一人語り】 縄文人の一人語り
セクション1 縄文人とは誰なのか
―DNAから見た縄文人の実像
[コラム]古代ゲノムを読み解く主成分分析とは
土クション2 縄文時代の環境と定住生活の確立
セクション3 多様な縄文人
セクション4 科学分析からわかること
セクション5 縄文人の精神文化
セクション6 日本における穀物の出現と農耕の始まり
【トピック1】 イヌのきた道
第3章──────────────────────────
日本人の源流さまざまな弥生人とその社会
【頭骨の一人語り】 弥生人の一人語り
セクション1 DNAが語る多様な弥生人
セクション2 弥生時代早期の人々とくらし
セクション3 弥生時代前期の人々のくらし
セクション4 伊勢湾沿岸地域の水田稲作民と狩猟採集民
セクション5 多様なDNAをもつ渡来系弥生人の
むらの人々と生活道具
[コラム]家族関係が希薄な人々
―青谷上寺地遺跡の人骨の調査から
セクション6 弥生人の食性分析
第4章──────────────────────────
国家形成期の日本―古墳時代を生きた人々
【頭骨の一人語り】 古墳時代人の一人語り
セクション1 DNAから見た古墳時代の人と社会
セクション2 古墳時代の始まり
セクション3 渡来人が伝えた新技術
セクション4 多様な文化と古墳時代人
セクション5 DNA分析で判明した血縁関係
【トピック2】 イエネコの歴史
[コラム]弥生時代の年代観の変化で何が変わったか
第5章──────────────────────────
南の島の人々―琉球列島集団の形成史
【頭骨の一人語り】 南島の古代人の一人語り
セクション1 ゲノムから見た琉球列島集団の形成
セクション2 縄文人の南北移動
セクション3 弥生貝交易の始まり
セクション4 貝交易の展開―弥生中期の海上遠距離交易
セクション5 古墳時代の貝交易とその後
第6章──────────────────────────
北の大地の人々―縄文人がアイヌになるまで
セクション1 ゲノムが語るアイヌへの道すじ
セクション2 北海道の先史古代文化
セクション3 オホーツク文化の流入
セクション4 先住民・アイヌの文化
エビローグ
~そして日本人が生まれた~
[コラム]人骨をデジタイズする―教育や研究に貢献する最新技術
超高精細の8KCG映像―
[コラム]ヒトの年代を測る―炭素14年代法
図版出典・参考文献
【2025年5月31日 ★【品切】
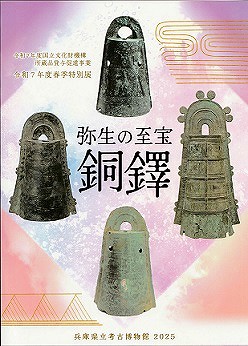
書籍番号
82684
書 名
弥生の至宝
銅鐸
シリーズ
(令和7年度春季特別展)(兵庫県立博物館展示図録No.35)
データ
A4 91頁
ISBN/ISSN
編著者
兵庫県立博物館編集
出版年
2025年4月
出版者
兵庫県立博物館
価 格
鐸」があります。近畿地方を中心に広がりを見せる銅鐸は、兵庫県
内から67点が出土しており、日本一の出土量を誇ります。いにしえ
の美と技術の結晶である銅鐸を大阪・関西万博の開催にあわせて展
示するとともに、国立文化財機構所蔵品貸与促進事業の補助を受け
東京国立博物館に所蔵されている銅鐸の「里帰り」もおこないます。
また、銅鐸を作る際に使用された鋳型や道具、後世の人々によって
描かれた絵図なども展示し、神秘のベールにつつまれた銅鐸につい
て、様々な面から考えます。
──────────────────────────────
目次
ごあいさつ
例言・凡例
トピック 銅鐸の響き~舌による音の聞きくらべ~ …………15
間 章 記録に残された銅鐸
………………………………………26
トピック 淡路の地誌に記された銅鐸絵図
……………………29
第3章 銅鐸をつくる…………………………………………………39
トピック 高坏形土製品と真土 …………………………………43
連 携 望塚銅鐸復元プロジェクトふりかえりインタビュー
…………………44
実 験 青銅の熔解・土製鋳型への鋳造・鋳掛の実験………57
第4章 銅鐸のさいご
………………………………………………68
トピック 復元銅鐸破砕実験の詳細と検討
……………………72
主要参考文献……………………………………………………………90
謝辞………………………………………………………………………91
【2025年5月31日 【品切】

書籍番号
82685
書 名
待兼山考古学論集
Ⅳ―福永伸哉先生退任記念―
シリーズ
データ
B5 788頁
ISBN/ISSN
編著者
大阪大学考古学研究室編集
出版年
2025年3月
出版者
大阪大学考古学研究室
価 格
【並 製】品切(税込)
【上製本】品切(税込)
牽引されてこられた、福永伸哉先生の定年退任を記念して刊行さ
れた。阪大では『待兼山考古学論集』として、これまで都出比呂
志先生の退任記念号と大阪大学考古学研究室開設の周年記念号の
計3巻を刊行してきたが、2冊目の退任記念号となる。
本論集は、福永先生と長く親交を深められてきた方々から、学
生時代より厳しい指導を受けてきた卒業・修了生等に至るまで、
阪大考古学研究室の関係者、総勢67名から寄稿されたものである。
──────────────────────────────
インターネットのクチコミ評価を用いた
史跡に対する利用者の受け止め方把握方法
……………………伊藤 文彦 1
欧州の開発主導考古学
………………………………岡村 勝行 13
東胡の後裔… …………………………………………中村 大介
23
4~6世紀シルクロードの文明交流と東アジア ……朴 天
秀 33
台湾出土の越窯系青磁
………………………………盧 柔 君 49
北アメリカ先史時代ミシシッピ文化における防御
施設の地域性
…………………………………佐々木憲一 59
瀬戸内旧石器時代の人類活動に関する小考 ………森先 一貴
77
出土石器全点を対象とした素材選択性についての分析方法の検討
―翠鳥園遺跡出土節気を対象に― ………三好
元樹 85
土木・施設材の樹種からみた木材利用の変遷
……中原 計 95
弥生~古墳時代における掘立柱建物と
「特定区画/居館」の性格の変遷
……………三好 玄 105
弥生墓制からみた和泉地域の特質 …………………蓮井 寛子 115
弥生時代後期における地域間交流網の動態
―北摂地域出土生駒山西麓産土器の数量的分析をもとに―
………………………………………………西浦 熙 129
弥生時代~古墳時代における竪穴住居建築材の変遷
―鳥取県域の調査例を中心に―
…………髙田 健一 141
東日本における布掘り柱掘形をもつ掘立柱建物 …髙橋 浩二 151
古墳出現前夜の饗宴と土製支脚 ……………………中久保辰夫 161
丹生水銀鉱床群における弥生・古墳時代の辰砂採掘動向
―周辺地域の水銀朱関連遺物出土状況を手掛かりとして―
…………………………………………………石井 智大 171
関部双孔鉄剣の日韓比較研究 ……………ライアン・ジョセフ 185
大廓エクスパンション再論 …………………………北條 芳隆 195
弥生墓及び前方後円墳における棺外副葬 …………禰冝田佳男 205
近江の雪野山古墳・安土瓢箪山古墳の被葬者とその性格
―四道将軍の派遣を補佐した有力氏族の首長墳
……………………………………………………笠原好彦 215
SfM-MVSを用いた倭鏡の研究
―御旅山古墳出土内行花文倭鏡について …林
正憲 241
古墳時代前半期における副葬品配置の対称性 ……三浦
俊明 251
古墳時代前期における円筒埴輪と円筒形器台の展開
………………………………………………… 金澤 雄太 261
讃岐地域産刳抜式石棺の再検討 ……………………高上
拓 275
滑石製石釧が提起する諸問題について ……………上田
直弥 286
「笊形土器」の検討
…………………………………金澤 舞 295
百舌鳥古墳群出土の家形埴輪について
……………橘 泉 309
紀伊地域における初期須恵器生産および
土師器生産にみえる影響関係 …………………仲辻 慧大 319
甑からみた韓半島の地域差と日本列島の甑の系譜
……………………………………………………
長友 朋子 329
阿蘇市長目塚古墳出土行方不明土器の発見とその意義
―朝鮮半島系土器の存在 …………………………杉井
健 339
大仙陵古墳の甲冑とその年代 ………………………橋本
達也 357
近畿地方における埴輪工人の移動とその背景
……木村 理 367
古墳時代後半期における長頸鏃の規範の在り方 …三好裕太郎 379
河内地域における釘付式木棺の導入―百済系文物導入の一様相―
……………………………………………………平井 洸史 389
古墳時代中期における製塩技術の移動 ……………岩﨑 郁実 399
5~6世紀の倭国と百済の戦略的な接近とその背景
……………………………………………………禹 在 柄 411
東北地方における形象埴輪の組成と配置 …………東影
悠 431
首長系譜にみる埴輪製作者の動態
…………………和田一之輔 441
古墳時代後期の乙訓地域における埴輪生産の一様相
……………………………………………………
山口 等悟 451
高坏形器台にみる日韓土器型式変化の連動性
……我妻 佑哉 461
杯身・杯蓋からみた須恵器製作技術の伝播にかんする試論
―特異な製作痕跡に着目して― …………飯塚 信幸 471
轡と雲珠・辻金具の対応からみる古墳時代後期初頭の馬具製作
…………………………………………………肥田 翔子 483
二上山白色凝灰岩製組合式家形石棺の製作体制 …上村
緑 495
岩橋型横穴式石室の石材獲得
―点紋片岩の分布と石材採取地点の検討から―
…………………………………………………瀬谷今日子 605
関東地方における横穴式石室の先進と未熟 ………寺前 直人 517
横穴式石室出土土器の器種構成の変遷とその背景 野島 悠之 531
近畿地方における須恵器台付子持壺の位置づけ
―古墳出土資料を中心に― ………………前田 俊雄 541
須恵器子持器台に関する小考
―ミニチュア炊飯具副葬古墳との関係を中心に―
………………………………………………… 岩越 陽平 553
6世紀の妃墓と大王墓
………………………………清家 章 565
欽明陵・敏達陵の比定をめぐる追考
―東漢坂上氏の議論を含めて― …………高橋 照彦 577
一墳丘に複数の埋葬施設をもつ後期古墳について
………………………………………………… 黒石 哲夫 587
備中南部における横穴式石室の展開
─三須丘陵の古墳群を中心に― …………金田 善敬 601
中津市定留鬼塚遺跡の皮袋形提瓶からみた
須恵器の生産と流通 ……………………………越智 淳平 611
竪穴建物出土の耳環について ………………………横田 真吾 623
古墳時代鍍金の色調計測の可能性 …………………田中 由理 633
圭頭大刀の生産と流通(補遺) ……………………豊島 直博 643
古墳文化と北方文化の相互関係―東北北部を中心に―
………………………………………………… 菊地 芳朗 653
蘇斯岐屯倉と丹波の杣 ………………………………桐井 理揮 669
古墳時代から古代における須恵器甕生産 …………木村 理恵 679
三河・遠江地方出土製塩土器の分布・用途に関する考察
………………………………………………… 大林 元 685
山林寺院の立地について
―飛鳥・奈良時代における大和国およびその周辺の事例研究―
…………………………………………………奥村 茂輝 701
建物の[土専]敷舗装―四半敷の検討― …………中川 二美
717
讃岐地域における東播系須恵器鉢の流通 …………谷本 峻也
727
中世における埋葬姿勢―西日本の事例を中心に―
…………………………………………………西本 沙織 737
中・四国地方における中世城郭に構築された畝状空堀群
…………………………………………………岡寺 良 751
発掘調査成果からみる太田城と太田城水攻めの実態
………………………………………………… 大木 要 763
考古学と椀貸伝説―郷土史という視点からの伝承とモノ―
…………………………………………………
角南聡一郎 775
考古学研究室の歴史(2018年4月~)
………………………… 785
編集後記
執筆者一覧
【2025年5月27日 【入荷】【ご注文承り中】
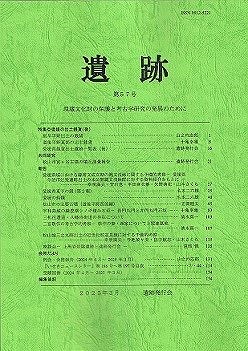
書籍番号
82675
書 名
遺跡 第57号 特集◎愛媛の出土銭貨(後)
シリーズ
データ
A5 460頁 (上製本)
ISBN/ISSN
0912-5221
編著者
十亀幸雄編集
出版年
2025年3月
出版者
遺跡発行会
価 格
1,980円(税込)
───────────────────────────────
特集◎愛媛の出土銭貨(後)
風早平野出土の銭貨 …………………………
山之内志郎 1
道後平野東部の出土銭貨 …………………………… 十亀幸雄 8
愛媛県銭貨出土遺跡一覧表(後) ……………
遺跡発行会 16
共同研究
松山市宮ヶ谷古墳の墳丘測量報告 ………………
遺跡発行会 21
報告
愛媛県域における縁帯文成立期の縄文浅鉢に関する予備的考察
-
愛媛県今治市辻堂遺跡出土の未公開縄文浅鉢群に対する資料
紹介をもとに- ………………幸泉満夫・菅百恵・平田麻衣葉・
矢野萌花・山本さくら 27
愛媛県東予の鏡(第2報) …………………………… 名本二六雄
35
愛媛の鈴鏡 …………………………………
名本二六雄 40
松山市の主要古墳(道後平野西部編)
…………………正岡睦夫 45
宇和島城の織豊期シノギ積み石垣-
長門丸門と井門丸門石垣-
………………… 十亀幸雄 83
三机往還道・八幡浜街道の存在について ……………
清水真一 103
二宮敬作の考古学的考察-
敬作の妻・西家についてと関連墓地-
……………
清水真一 107
松山城三之丸跡出土の近世化粧道具類に対する予備的考察
…………幸泉満夫・寺地菜々美・畠中航志・山本さくら 115
座談会-
上黒岩岩陰遺跡と遺跡発行会- …………… 遠部 慎 125
会所だより
例会・会務報告(2024 年4月~
2025 年3月) … 山之内志郎 131
『いせきニュースレター』第186 号~第197 号目次 ………7・44・114
受贈図書(2024年4月~2025年3月) ………………………………
134
編集後記 ……………………………………………………
134
【2025年5月27日 【入荷】【ご注文承り中】
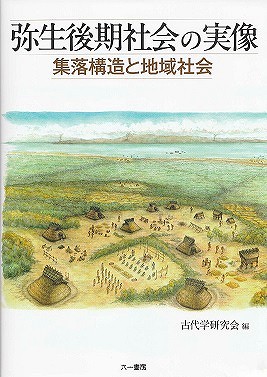
書籍番号
82681
書 名
弥生後期社会の実像 集落構造と地域社会
シリーズ
データ
B5 437頁
ISBN/ISSN
978-4-86445-184-0
編著者
古代学研究会編
出版年
2025年5月
出版者
六一書房
価 格
6,600円(税込)
本書は、令和4年(2022)3月5日に行われた2021年度古代学研究会拡大例会
シンポジウム「弥生後期社会の実像―集落構造と地域社会一』の記録と
令和5年(2023)5月20日に行われた古代学研究会2023年度5月例会ミニシン
ポジウム「近畿弥生後期社会の体系的把握に向けて』の成果をもとにその
後の知見を新たに加えた論文集である
────────────────────────────────
【目 次】
────────────────────────────────
序 ………………………………………………………………森岡秀人 i
例 言 …………………………………………………………………
V
本書の目的と分析方法……………………………三好 玄・田中元浩 ⅶ
第Ⅰ部 弥生後期の集落構造と地域社会
(事例報告)
河内地域における弥生後期の集落構造と集団関係 ……三好 玄 3
和泉地域における弥生後期の集落構造と地域社会>
……三好 玄 21
大和地域における集落構造と社会の変化…………………山本 亮 37
紀伊地域における集落構造の変化…………………………田中元浩
55
近江地域の建物構成と集落構造……………………………中居和志 75
讃岐地域における弥生時代後期の集落構造………………渡邊
誠 91
播磨地域における中後期の集落構造分析…………………荒木幸治 109
山城における弥生後期の集落動向…………………………桐井理揮 129
東摂津地域における弥生時代後期の集落構造……………清水邦彦 149
西摂津地域における建物構成と集落構造…………………園原悠斗 165
吉備南部における弥生時代後期から古墳時代前期の集落構造
ー備前・旭川下流域東岸の分析を中心としてー ……河合 忍 183
筑前地域(西部)の弥生時代後期集落………………………森本幹彦
203
出雲地域における弥生後半期の集落遣……………………坂本豊治
233
<シンポジウムの記録〉
拡大例会シンポジウム討論の記録…………… 作成:塚本紘太郎 251
5月例会ミニシンポジウム討論の記録
……… 作成:塚本紘太郎 267
第Ⅱ部 遺物からみた弥生後期社会
石器からみた弥生時代後期…………………………… 瀬谷今日子 287
弥生時代後期における銅鐸の生産と流通……………… 戸塚洋輔 299
青銅器生産からみた弥生時代後期……………………… 清水邦彦 321
第Ⅲ部 総括と今後の展望
〈総括〉
弥生後期社会の実像とその評価……………
田中元浩・三好 玄 335
〈今後の展望〉
弥生時代「後期」をどのように評価するのか………… 伊藤淳史 374
ー近畿地方を中心とする研究史からー
弥生時代後期~古墳時代変化のモデル化をめぐる断想
………
若林邦彦 379
近畿弥生後期社会の諸問題…………………………… 禰冝田佳男 387
ー20世紀の研究視点から考えるー
弥生時代後期の近畿の南部と北部……………………… 森岡秀人 395
一時空間をめぐる確執の淵源一
集団組織原理にかんする理論的検討…………………… 三好 玄 416
ー「出自集団論」批判ー
後
記
編者・執筆者一覧
【2025年5月27日 【入荷】【ご注文承り中】
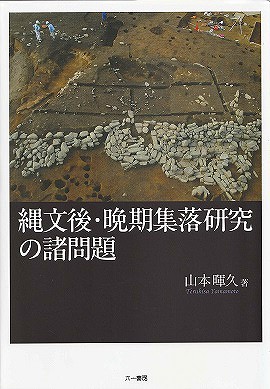
書籍番号
82682
書 名
縄文後・晩期集落研究の諸問題
シリーズ
データ
B5 574頁 (上製本)
ISBN/ISSN
978-4-86445-186-4
編著者
山本輝久著
出版年
2025年5月
出版者
六一書房
価 格
16,500円(税込)
本書は.関東・中部域を中心とした地域における縄文時代後・晩期
集落研究にかかわる諸問題について論じたものである。
本書では.関東・中部域を主たる検討対象地域としているが.それと
対照する意味で.東北地方北半部~北海道域の盛土遺構.環状列石.
周堤墓についても論じている本書は筆者のこれまでの研究成果に基
礎をおいているが.すべて書き下ろし原稿からなる。
………………………………………………………………………………
【目 次】
例 言 ………………………………………………………………… ⅱ
第1章 間題の所在 ………………………………………………… 1
第2章 後・晩期集落研究の諸問題―関東・中部域を中心として
― …………… 7
第1節 環状盛土集落・中央窪地集落……………………………
9
第2節 大形住居・多重複住居 ………………………………… 129
第3節 住居型式と出入凵施設の発達 ………………………… 163
第4節 円筒形深掘土坑 ………………………………………… 201
第5節 土坑墓と配石墓 ………………………………………… 243
第6節 住居の廃絶と火入れ行為 ……………………………… 347
第7節 焼獣骨片撒布の意味 …………………………………… 373
第3章 東北北部・北海道域における盛土遺構,環状列石,周堤墓
…………… 395
第1節 東北北部・北海道の盛土遺構研究の現状と課題 ……
399
第2節 環状列石(環状石籬・ストーンサークル)
…………… 411
第3節 周堤墓(環状上籬)
……………………………………… 449
第4章 結語
……………………………………………………… 483
おわりに
…………………………………………………………… 489
挿図出典文献
……………………………………………………… 493
引用・参考文献
…………………………………………………… 497
【2025年5月22日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82631
書 名
考古学論叢
Ⅳ
シリーズ
データ
B5 808頁
ISBN/ISSN
編著者
関西大学文学部考古学研究室編集
出版年
2024年12月
出版者
関西大学文学部考古学研究室
価 格
11,000円(税込)
卒業生・関係者による、51篇の論考を掲載。各論考では、旧石器・縄文時
代から近世・近代までの幅広い時代を対象に、地域も日本列島や朝鮮半島、
中国、南アジアなどにわたり、考古資料等の詳細な検討にもとづいた多様
なテーマを取り扱っている。
旧石器時代遺跡石器分布の潜在構造(山口卓也)
南九州における押型文土器の地域性(山下大輔)
鳥取市桂見遺跡出土の縄文時代編組製品(濵田竜彦)
極東地域における卜骨(入江文敏)
周防灘沿岸の古墳にみる4・5世紀の変化と画期とその背景(宇野愼敏)
磐田原台地の古墳(土生田純之)
古墳時代前期の石棺需給システム(北山峰生)
固定されたダイドコロ(合田茂伸・合田幸美)
古墳時代前期の王宮について(米川仁一)
「儀杖の系譜」再論(樋上昇)
盤龍鏡の副葬が意味するもの(上林史郎)
浜松市美術館所蔵「伝大和国」出土三角縁神獣鏡の再発見とその意義
(徳田誠志)
蓋形埴輪立飾りの変容(鐘方正樹)
中河内における古墳時代前期の製塩土器(山田隆一)
中期畿内政権の九州地方管理・経営戦略(藤田和尊)
古墳時代中期における畿内政権の構造変化(田中晋作)
北陸における初期群集墳の一検討(伊藤雅文)
大仙陵古墳・上石津ミサンザイ古墳の墳丘(十河良和)
古墳の築造から見た古道の歴史(泉森皎)
倭国における打延式頬当の消長(藤井陽輔)
断夫山古墳築造の背景(深谷淳)
近畿地方における後期大型円墳の再検討(西森忠幸)
6世紀中頃の岩橋千塚古墳群(丹野拓)
西日本における横穴式石室構築技術の地域性について(太田宏明)
巨石巨室横穴式石室の成立から見た畿内と東国(右島和夫)
播磨における古墳時代後期の階層性(尼子奈美枝)
小型矩形立聞環状鏡板付轡について(大谷宏治)
飛鳥の帰化人の遺跡と古墳(河上邦彦)
終末期古墳にあらわれた佛教的様相(石野博信)
律令国家の陵(辰巳俊輔)
古墳時代終末期の「岩屋山式」横穴式石室の規格構造について(西光慎治)
古代日本銅鋺分類の課題(小栗明彦)
大和の行基建立寺院の考古学的検討(近藤康司)
高坏(猪熊兼勝)
空海請来白螺具雑考(菅谷文則)
日宋貿易期の中国製黄緑釉褐彩花文陶器盤の一例とその周辺(森岡秀人)
山陰地方における古代末~中世前期の墓(中森祥)
石工念心と芸予地域の中世石造物(海邉博史)
堺環濠都市遺跡における16世紀前半の一括資料(永井正浩)
近代宮崎県における古墳保存と祖先崇拝(尾谷雅比古)
兵庫県芦屋市呉川遺跡出土のプラスチック製品(竹村忠洋)
保存処理前遺物の保管管理とその取扱い(伊藤健司)
移築民家の展示(井藤徹)
文化財保護啓発に関わる一つの試み(西本安秀)
倭系遺物からみた新羅の中央と地方(井上主税)
大韓民国全羅南道長興郡韓国重要無形文化財(製瓦匠)韓亨俊瓦窯の調査
とその評価(藤原学・中野咲・青木美香)
中国の一輪車(佐々木堯)
『作庭記』にみられる中国古代造園の技法(汪勃)
中国隋唐時代における石葬具に関する諸問題(周吟)
南アジア二つの文明社会(上杉彰紀)
考古学的遺跡のマネージメントにみるユネスコ世界遺産の動向による影響
(中西裕見子)
関西大学文学部考古学研究室小史(続)
【2025年5月15日 【入荷】【ご注文承り中】
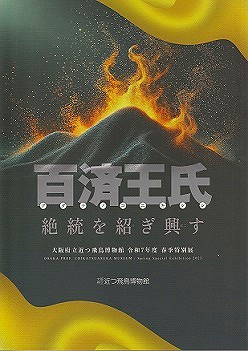
書籍番号
82674
書 名
百済王氏-絶統を紹ぎ興す-
シリーズ
(大阪府立近つ飛鳥博物館図録92)(大阪府立近つ飛鳥博物館
令和7年度 春季特別展)
データ
A4 150頁
ISBN/ISSN
編著者
大阪府立近つ飛鳥博物館編集
出版年
2025年4月
出版者
大阪府立近つ飛鳥博物館
価 格
2,200円(税込)
ごあいさつ……………………………………………………………………
3
目次・凡例…………………………………………………………………… 4
巻頭論考
百済王氏考
舘野和己…………………… 8
プロローグ ………………………………………………………………… 15
多賀城碑【拓本】/金象嵌七支刀/古代官人像
第1章 百済と倭の交流 …………………………………………………
17
高井田山古墳/蔀屋北遺跡/伊加賀遺跡/小倉東遺跡E1号墳/
四天王寺/上町谷窯/難波京朱雀大路跡/
陶邑窯跡群(TK三二一号窯)
もっと知りたい 煙突形土製品について 矢田幸大……… 40
第2章 百済の滅亡と倭への来住 ………………………………………
42
第1節 難波の百済王氏
細工谷遺跡/堂ケ芝廃寺/難波宮跡/難波京/勝山南遺跡/
生野東遺跡/桑津遺跡/伶人町遺跡/平城京
もっと知りたい 古代における鉛ガラスの生産 久永雅宏… 64
第2節
河内の百済王氏 ……………………………………………… 66
百済寺跡/百済寺遺跡/禁野本町遺跡
もっと知りたい 花粉分析からみる土地利用と百済王氏
東藤隆浩…… 82
第3章 多賀城赴任と黄金の発見 ……………………………………… 84
多賀城跡・多賀城廃寺跡/山王遺跡/市川橋遺跡/平安宮豊
楽殿跡/平安京跡
もっと知りたい 多賀城様式軒瓦の成立と東国経営
谷﨑仁美 …105
エピローグ …………………………………………………………………107
付 論 ………………………………………………………………………109
・「多賀城跡の調査成果」古田和誠(宮城県多賀城跡調査研究所)
・「百済寺跡出土の[土專]仏について」北川咲子(大阪府教育庁文化財
保護課)
分析報告 ……………………………………………………………………117
・「勝山南遺跡出土の鋳造関係資料に関する蛍光X線分析」降幡順子・
市川 創
展示品目録……………………………………………………………………138
図版一覧………………………………………………………………………141
引用・参考文献一覧…………………………………………………………145
展示協力機関・協力者………………………………………………………149
【2025年5月13日 【入荷】【ご注文承り中】
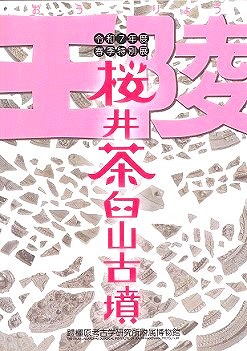
書籍番号
82670
書 名
王陵 桜井茶臼山古墳
シリーズ
(奈良県立橿原考古学研究所附属博物館 特別展図録第97冊)(令和7年度春季特別展)
データ
A4 88頁
ISBN/ISSN
編著者
奈良県立橿原考古学研究所編集
出版年
2025年4月
出版者
奈良県立橿原考古学研究所
価 格
1,700円(税込)
例言
展示関連地図等
概説 王陵 桜井茶臼山古墳……………………………………… 5
序章
ヤマト王権と王陵の発生…………………………………… 7
第1章 王陵を築く…………………………………………………… 11
第2章 王陵を支えた人々…………………………………………… 21
第3章 明らかとなった王陵の副葬品……………………………… 33
コラム 桜井茶臼山古墳の玉杖から八ツ手葉形銅製品へ……… 37
コラム 桜井茶臼山古墳の腕輪形石製品………………………… 39
第4章 王陵の隔絶性………………………………………………… 49
終章 継承される王の権力ーメスリ山古墳ー ………………… 77
コラム 鉄器と埴輪にみるメスリ山古墳の画期性……………… 82
出品目録………………………………………………………………… 86
主な参考文献…………………………………………………………… 87
展覧会中の行事
協力機関・協力者
【2025年4月25日 【入荷】【ご注文承り中】
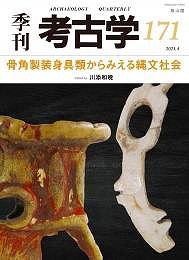
書籍番号
82638
書 名
季刊 考古学 第171号
シリーズ
特集 骨格製装身具類から見える縄文社会
データ
B5 134頁
ISBN/ISSN
978-4-639-03037-8
編著者
桑門智亜紀編集
出版年
2025年5月
出版者
雄山閣出版
価 格
2,640円(税込)
―社会集団様相へのアプローチ―(川添和暁)
北海道島(縄文・続縄文期)(青野友哉)
東北地域(骨角牙製品)(川添和暁)
東北地域(貝輪)(山田凛太郎)
西関東・長野(吉永亜紀子)
新潟・北陸・関西地域(川添和暁)
東海地域―渥美半島の着装資料を中心に―(増山禎之)
中国・四国地域(田嶋正憲)
九州島(中尾篤志)
鹿角製装身具類からみえる地域間関係(川添和暁)
関東地方におけるベンケイガイ製貝輪の生産と流通(阿部芳郎)
サメ製装身具―サメ椎骨製耳飾を中心に―(中沢道彦)
骨角器に利用された動物質素材の使われ方(樋泉岳二)
緑色系石材の位相(栗島義明)
貝輪(連着)形土製品(高橋満)
土製垂飾
―関東地方の縄文時代中期の土製大珠を中心として―(宮内慶介)
土製耳飾り(吉岡卓真)
装身具着装人骨の埋葬属性(山田康弘)
装身具着装人骨の食生活からみた縄文社会の階層性
(米田穣・水嶋宗一郎・佐宗亜衣子)
骨角製装身具類における痕跡学的研究(鹿又喜隆)
横穴式石室の2人の被葬者―島根県出雲市上塩冶築山古墳―
(坂本豊治・奥山誠義・北井利幸・河﨑衣美・中尾真梨子・小倉頌子)
若宮大路周辺遺跡群出土の木造人物像
―神奈川県鎌倉市若宮大路周辺遺跡群―(小野田宏)
石人石馬はなぜ壊されたのか
―群像を樹立する葬送儀礼の背景―(河野一隆)
ただひたすらモノを見る(石川日出志)
-博物館法改正を受けて-
第2回遺跡と博物館とまちづくり(宮坂清)
兵庫県立考古博物館―ふれる・体感する考古学のワンダーランド―
(岡本一秀・山本誠)
【2025年4月24日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82636
書 名
辰馬考古資料館 考古学研究紀要 7
シリーズ
データ
A4 107頁(図版13頁)
ISBN/ISSN
編著者
辰馬考古資料館編集
出版年
2024年12月
出版者
公益財団法人
辰馬考古資料館
価 格
3,300円(税込)
【目 次】
────────────────────────────
辰馬考古資料館所蔵の土偶・土製品・石製品……………………
矢野健一・林 亮太・迫田 圭一郎・菅井 佳穂・
小久保 茉優・岡 昭伸 1
伝持田古墳群出上鏡三次元計測について…………岡本 篤志 61
伝持田占墳群出上連作鏡と中期後半の倭製鏡……森下 章司 71
伝宮崎県持田古墳群出土銅鏡の化学分析…………難波 洋三 83
伝宮崎県持田古墳群出土連作鏡の接置関係推定…青木 政幸 91
【2025年4月20日 【入荷】【ご注文承り中】
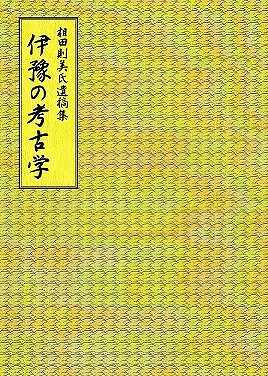
書籍番号
82635
書 名
相田則美氏遺稿 伊豫の考古学究
シリーズ
データ
B5 61頁
ISBN/ISSN
編著者
相田則美氏遺稿集刊行会
出版年
2024年12月
出版者
価 格
1,400円(税込)
序
例 言
第一編 玄界灘を渡った伊予海人たちー緑色片岩製箱式石棺の研究(一)ー
第一章 はじめに ………………………………………………………… 1
第二章 松山平野の地質と石棺材 ……………………………………… 2
第三章 石棺製作とエ人集団 …………………………………………… 3
第一節 石棺製作の技術 ……………………………………………… 3
第二節 砥部石工集団の形成 …………………………………………10
第四章 石棺の移動と展開 ………………………………………………11
第一節 砥部地域 ………………………………………………………11
(一) 釈迦面山一号墳の編年的位置 ………………………………11
(二) 粘土被覆と下部構造 …………………………………………12
(三) 石棺製作開始とその推移 ……………………………………14
(四) 釈迦面山古墳群の構造 ………………………………………17
第二節 伊予地域 ………………………………………………………20
第三節 三津浜沿岸地域 ………………………………………………20
第四節 北条浅海原地域 ………………………………………………20
(一) 浅海原の緑色片岩製箱式石棺 ………………………………20
(二) 風早の石棺群と石棺材 ………………………………………22
第五章 被葬者の階層と出身集団 ………………………………………24
第六章 首長と海人・海古たち …………………………………………24
第七章 結 語 ……………………………………………………………24
挿 図
図1 松山平野の箱式石棺とその移動 ……………………… 2
図2 猪の窪古墳・釈迦面山1号墳位置図 …………………… 4
図3 猪の窪古墳墳丘実測図 ………………………………… 4
図4 猪の窪古墳埋葬施設・人骨検出状況実測図 ………… 5
図5 猪の窪古墳出土鉄製品実測図 ………………………… 6
図6 釈迦面山1号墳墳丘実測図 ……………………………… 8
図7 釈迦面山1号墳1号石棺実測図 ………………………… 9
図8 釈迦面山1号墳2号石棺実測図 ………………………… 9
図9 土壇原遺跡群各遺跡位置図 ……………………………14
図10 大分県海部地域の主要古墳 ……………………………16
図11 釈迦面山南遺跡遺構配置図 ……………………………18
図12 北条浅海地域の古墳分布図 ……………………………21
表
表1 愛媛県の箱式石棺(地区別石棺一覧表) ………………11
表2 松山市北条地区の箱式石棺の石材 ……………………21
表3 北条地区の箱式石棺材とその比率 ……………………23
第二編 道後・北条平野における首長墓の埋葬施設
第一章 はじめに ………………………………………………………29
第二章 古墳時代中期の埋葬施設 ……………………………………29
第一節 素鵞神社古墳の石棺と副葬品 ……………………………29
第二節 蓮華寺の舟形石棺 …………………………………………37
第三節 丸山古墳の組合式石棺 ……………………………………38
挿 図
図1 素鵞神社古墳周辺地形と古墳分布図 …………………29
図2 素鵞神社古墳墳丘測量図 ………………………………33
図3 素鵞神社古墳出土遺物実測図 …………………………33
図4 蓮華寺石棺周辺地形図 …………………………………38
図5 蓮華寺石棺実測図 ………………………………………38
図6 丸山古墳墳丘測量図・石棺実測図 ……………………39
図7 上小田古墳石棺実測図・墳丘測量図 …………………40
第三編 松山市出土の青磁四耳小壺について(草稿)
挿 図
図1 青磁四耳小壺
……………………………………………45
図2 青磁四耳小壺出土地周辺の古墳
………………………46
図3 青磁鉄斑文盤ロ瓶
………………………………………47
図4 越窯青磁天鶏壺
…………………………………………47
図5 越窯青磁盤ロ壺
…………………………………………47
図6 青磁鶏頸壺
………………………………………………47
図7 参考資料:青磁有蓋四耳壺
……………………………49
表
表1 松山市古三津出土の青磁四耳小壷 ……………………51
付 編 相田則美氏の足跡
【2025年4月16日 【入荷】【ご注文承り中】
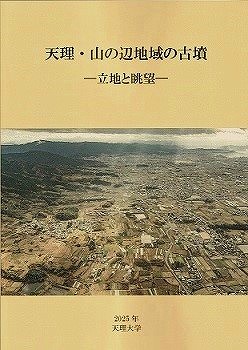
書籍番号
82634
書 名
天理・山の辺地域の古墳―立地と眺望―
シリーズ
データ
A4 98頁
ISBN/ISSN
編著者
桑原久雄(研究代表)編集
出版年
2025年3月
出版者
天理大学
価 格
2,200円(税込)
第1部 天理・山の辺地域の古墳ー動向・立地・眺望ー
1. 天理市域における古墳の動向…………………
石田大輔 1
2.
天理市域における古墳の立地………………… 池田保信 7
3. 天理・山の辺地域における古墳の立地・地形・眺望
………… 桑原久男 13
4.
奈良盆地東南部における古墳の眺望分析…… 宇佐美智之 23
2.野田古墳………………28 38.マバカ古墳………………64
3.寺山30号墳……………29 39.馬ロ山古墳………………65
4.櫟本墓山古墳…………30 40.波多子塚古墳……………66
5.和爾下神社古墳………31 41.二ノ瀬池古墳……………67
6.東大寺山古墳…………32 42.西山塚古墳………………68
7.赤土山古墳……………33 43.フサギ塚古墳……………69
8.東大寺山25号墳………34 44.矢ハギ塚古墳……………70
9.東大寺山26号墳………35 45.弁天塚古墳………………71
10.東大寺山1号墳
………36 46.栗塚古墳…………………72
11.岩屋大塚古墳…………37 47.下池山古墳………………73
12.ハミ塚古墳……………38 48.東殿塚古墳………………74
13.塚平古墳………………39 49.西殿塚古墳………………75
14.石上大塚古墳…………40 50.火矢塚古墳………………76
15.ウワナリ塚古墳………41 51.燈籠山古墳………………77
16.石上・豊田226号墳
…42 52.中山大塚古墳……………78
17.狐ヶ尾8号墳
…………43 53.小岳寺塚古墳……………79
18.豊田トンド山古墳……44 54.黒塚古墳…………………80
19.豊田狐塚古墳…………45 55.アンド山古墳……………81
20.別所大塚古墳…………46 56.南アンド山古墳…………82
21、別所鑵子塚古墳
……47 57.天神山古墳………………83
22.塚山古墳………………48 58.行燈山古墳………………84
23.袋塚古墳………………49 59.櫛山古墳…………………85
24.小半坊塚古墳…………50 60.ヲカタ塚古墳……………86
25.塚穴山古墳……………51 61.ノベラ古墳………………87
26.西山古墳………………52 62.石名塚古墳………………88
27.北池1号墳
……………53 63.柳本大塚古墳……………89
28.峯塚古墳………………54 64.上の山古墳………………90
29.西天井山古墳…………55 65.渋谷向山古墳……………91
30.東天井山古墳…………56 66.シウロウ塚古墳…………92
31.須川1号墳
……………57 67.龍王山48号墳……………93
32.笠神山古墳……………58 68.御墓山古墳………………94
33.小墓古墳………………59 69.星塚1号墳
………………95
34.西乗鞍古墳……………60 70.星塚2号墳
………………96
35.東乗鞍古墳……………61 71.荒蒔古墳…………………97
36.ノムギ古墳……………62 72.岩室池古墳………………98
【2025年4月16日 【近日入荷】【ご注文承り中】
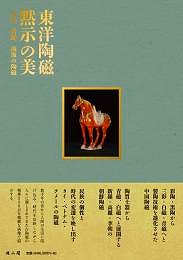
書籍番号
82626
書 名
東洋陶磁 黙示の美―中国、朝鮮、南海の陶磁―
シリーズ
データ
A4 208頁
ISBN/ISSN
978-4-639-03042-3
編著者
彩廣軒主人編著
出版年
2025年4月
出版者
雄山閣出版
価 格
7,150円(税込)
中国陶磁
陶質土器から青磁、白磁へと展開する新羅・高麗・李朝の朝鮮陶磁
民族の個性と時代の変遷を映し出すタイ・ベトナム・クメールの陶磁
数千年の昔から人間の生活に溶け込み、時代を反映しながら人々に親
しまれてきた古陶磁の清華208点を精細な画像で紹介する。
【2025年4月14日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82631
書 名
考古学論叢
Ⅳ
シリーズ
データ
B5 808頁
ISBN/ISSN
編著者
関西大学文学部考古学研究室編集
出版年
2024年12月
出版者
関西大学文学部考古学研究室
価 格
11,000円(税込)
卒業生・関係者による、51篇の論考を掲載。各論考では、旧石器・縄文時
代から近世・近代までの幅広い時代を対象に、地域も日本列島や朝鮮半島、
中国、南アジアなどにわたり、考古資料等の詳細な検討にもとづいた多様
なテーマを取り扱っている。
旧石器時代遺跡石器分布の潜在構造(山口卓也)
南九州における押型文土器の地域性(山下大輔)
鳥取市桂見遺跡出土の縄文時代編組製品(濵田竜彦)
極東地域における卜骨(入江文敏)
周防灘沿岸の古墳にみる4・5世紀の変化と画期とその背景(宇野愼敏)
磐田原台地の古墳(土生田純之)
古墳時代前期の石棺需給システム(北山峰生)
固定されたダイドコロ(合田茂伸・合田幸美)
古墳時代前期の王宮について(米川仁一)
「儀杖の系譜」再論(樋上昇)
盤龍鏡の副葬が意味するもの(上林史郎)
浜松市美術館所蔵「伝大和国」出土三角縁神獣鏡の再発見とその意義
(徳田誠志)
蓋形埴輪立飾りの変容(鐘方正樹)
中河内における古墳時代前期の製塩土器(山田隆一)
中期畿内政権の九州地方管理・経営戦略(藤田和尊)
古墳時代中期における畿内政権の構造変化(田中晋作)
北陸における初期群集墳の一検討(伊藤雅文)
大仙陵古墳・上石津ミサンザイ古墳の墳丘(十河良和)
古墳の築造から見た古道の歴史(泉森皎)
倭国における打延式頬当の消長(藤井陽輔)
断夫山古墳築造の背景(深谷淳)
近畿地方における後期大型円墳の再検討(西森忠幸)
6世紀中頃の岩橋千塚古墳群(丹野拓)
西日本における横穴式石室構築技術の地域性について(太田宏明)
巨石巨室横穴式石室の成立から見た畿内と東国(右島和夫)
播磨における古墳時代後期の階層性(尼子奈美枝)
小型矩形立聞環状鏡板付轡について(大谷宏治)
飛鳥の帰化人の遺跡と古墳(河上邦彦)
終末期古墳にあらわれた佛教的様相(石野博信)
律令国家の陵(辰巳俊輔)
古墳時代終末期の「岩屋山式」横穴式石室の規格構造について(西光慎治)
古代日本銅鋺分類の課題(小栗明彦)
大和の行基建立寺院の考古学的検討(近藤康司)
高坏(猪熊兼勝)
空海請来白螺具雑考(菅谷文則)
日宋貿易期の中国製黄緑釉褐彩花文陶器盤の一例とその周辺(森岡秀人)
山陰地方における古代末~中世前期の墓(中森祥)
石工念心と芸予地域の中世石造物(海邉博史)
堺環濠都市遺跡における16世紀前半の一括資料(永井正浩)
近代宮崎県における古墳保存と祖先崇拝(尾谷雅比古)
兵庫県芦屋市呉川遺跡出土のプラスチック製品(竹村忠洋)
保存処理前遺物の保管管理とその取扱い(伊藤健司)
移築民家の展示(井藤徹)
文化財保護啓発に関わる一つの試み(西本安秀)
倭系遺物からみた新羅の中央と地方(井上主税)
大韓民国全羅南道長興郡韓国重要無形文化財(製瓦匠)韓亨俊瓦窯の調査
とその評価(藤原学・中野咲・青木美香)
中国の一輪車(佐々木堯)
『作庭記』にみられる中国古代造園の技法(汪勃)
中国隋唐時代における石葬具に関する諸問題(周吟)
南アジア二つの文明社会(上杉彰紀)
考古学的遺跡のマネージメントにみるユネスコ世界遺産の動向による影響
(中西裕見子)
関西大学文学部考古学研究室小史(続)
【2025年4月14日 【入荷】【ご注文承り中】
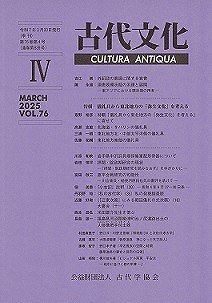
書籍番号
82623
書 名
古代文化 第76巻 第4号(639号)
シリーズ
データ
B5 146頁
ISBN/ISSN
0045-9232
編著者
出版年
2025年3月
出版者
古代学協会
価 格
2,970円(税込)
陳 永強:須恵器環状瓶の系講と展開
ー東アジアにおける環状瓶の再考ー
………………………………………………………………
特輯 儀礼具から東北地方の「弥生文化」を考える
斎野 裕彦:特輯「儀礼具から東北地方の「弥生文化」を考える」
に寄せて
高瀬 克範:北海道・サハリンの儀礼具
三浦 一樹:東北地方北・中部太平洋側の儀礼具
佐藤 祐輔:東北地方南部の儀礼具
………………………………………………………………
川添 和暁:岩手県中沢浜貝塚採集軍配形骨器について
岩田 慎平:摂関:院政期研究の現状
ー「摂関・院政期研究を読みなおす」を手がかりに一
宮田 敬三:源平合戦研究の可能性
ー川合康氏・勅使河原拓也氏の書評を承けて一
佃 美香:『小右記』注釈(39)ー長和4年6月27~30日条ー
丹羽野 裕:〈私の古代学〉(35)私の発掘調査歴
近藤 好和:〈『江家次第』にみる朝廷儀礼の式次第)(16)
大嘗会(十一)
西本 昌弘:米田雄介先生を偲ぶ
長島 雄一:福島県河沼郡柳津町池ノ尻遺跡出土の
人体像把手付土器
村田麻里子:野口淳・村野正景編『博物館DXと次世代考古学』
古藤 真平:大隅清陽著『菅原道真 神になった天才詩人』
家塚 智子:野口孝子著『平安貴族の空間と時間
藤原道長の妻女と邸宅の伝領』
山田 邦和:梶川敏夫著『ビジュアル再現 平安京
ー地中に息づく都の栄華ー』
【2025年4月2日 【入荷ご注文後のお取り寄せになります。】【ご注文承り中】
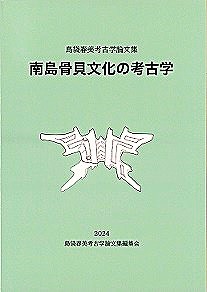
書籍番号
82615
書 名
南島骨貝文化の考古学
シリーズ
(島袋春美考古学論文集)
データ
B5 341頁
口絵16頁カラー
ISBN/ISSN
978-490241239
編著者
島袋春美考古学論文集編集会編
出版年
2025年3月
出版者
(有)沖縄文化社
価 格
6,500円(税込)
【ご案内】
─────────────────────────
50年以上にわたる沖縄先史時代の骨貝製品研究の集大成
蝶形骨製品に関する一連の研究は特筆
─────────────────────────
【目次】
─────────────────────────
第Ⅰ部 サンゴ礁の貝類利用(第1章~第9章)
第Ⅱ部 奄美・沖縄の貝製品利用(第1章~第10章)
第Ⅲ部 蝶形骨製品と獣形貝製品(第1章~第8章)
第Ⅳ部 漁網錘の民俗誌考古学(第1章~第5章)
【2025年3月31日 【入荷】【ご注文承り中】
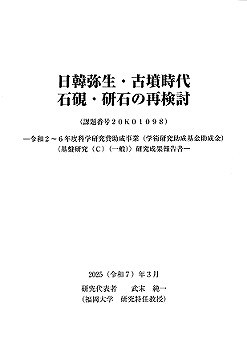
書籍番号
82613
書 名
日韓弥生・古墳時代石硯・研石の再検討
シリーズ
データ
A4 130頁 カラー図版16頁
ISBN/ISSN
編著者
研究代表者 武末 純一編集・発行
出版年
2025年3月
出版者
価 格
1,600円(税込)
1.本書は令和2~6(2020~2024)年度科学研究費助成事業(学術研究助成基金
助成金)く基盤研究(C)(一般)〉「日韓弥生・古墳時代石硯・研石の再
検討」(課題番号 20K01098、研究代表者:武末純一)の研究成果報告書
である。
2.本研究の研究代表者・分担者と役割および研究協力者は下記の通りで
ある。
武末 純一(研究代表者) 福岡大学研究特任教授 総括および楽浪土器、
天秤権・棹秤権の研究
足立 達朗(研究分担者) 九州大学比較社会文化研究院助教
石材同定
・研究
村田 裕一(研究分担者)
山口大学人文学部准教授 砥石と石硯・研石
の同定・研究
古澤 義久(研究分担者)
福岡大学人文学部准教授 中国銭貨と中国東
北地域の石硯・研石の研究
岡見 知紀(研究協力者)
奈良県立橿原考古学研究所主任研究員
李
健茂(研究協力者) 元文化財庁長官
金
武重(研究協力者) 元中原文化財研究院院長
李 暎澈(研究協力者) 大韓文化財研究院院長
李 東冠(研究協力者)
国立中央博物館学芸研究士
趙
晟元(研究協力者) 国立慶州文化遺産研究所特別研究員
鄭 仁盛(研究協力者) 嶺南大学校教授
朴 章鎬(研究協力者) 嶺南大学校講師
3.本書には上記研究代表者・研究分担者の論考のほかに、研究協力者で
ある岡見知紀の論考と福岡大学大学院生の永山亮による集成も収録し
た。
4.本書の刊行費用は、科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)く
基盤研究(C)(一般))「日韓弥生・古墳時代石硯・研石の再検討」(課
題番号20K01098)による。
5.本書は武末純一が編集した。
6.本書をなすにあたっては以下の方々のご教示・ご協力を得た。記して
謝意を表する(順不同、敬称略)。
崔鍾圭、蘇培慶、申敬澈、金斗喆、李昌熙、安星姫、朴昌烈、高旻廷、
オジェジン、林智娜、安京淑、任慧斌、河野一隆、山本亮、松本玲子、
秦憲二、坂元雄紀、小川泰樹、吉田東明、柳田康雄、榎本義嗣、久住猛
雄、松﨑友理、重藤輝行、吉原大輔、樋口芙弥、井上義也、山崎悠郁子、
山崎頼人、常松幹雄、岡部裕俊、角浩行、平尾和久、甲斐孝司、宇野愼
敏、中村利至久、山口裕子、山内亮平、小松譲、渡部芳久、寺田正剛、
片多雅樹、白石渓冴、田中聡一、松見裕二、[艸/蜑]父雅史、 石松直、
宮崎歩、尾崎光伸、山川聡大、深田浩、是田敦、真木大空、坂本豊治、
勝部智明、前田詞子、山根拓朗、石原渉、瀬川敬也、古橋慶三、寺前公
基、佐伯英樹、伴野幸一、川畑和弘、藤田三郎、池田保信、久田正弘、
中屋克彦、林大智、福海貴子、室正一、湯尾和宏、羽深忠司、笹澤正史、
設楽博己、石川岳彦、佐藤宏之、福田正宏、根岸洋、金崎由布子、新井
才二、桃﨑祐輔、前崎智行、森山龍輝、藤原孝大
────────────────────────────────
目 次
弥生・古墳時代硯研究史
古澤 義久 …… 3
日本における板石硯・研石と認定された石製品の集成
永山 亮 …… 25
日本列島出土の板状石硯における器種認定基準設定に向けての基礎的整理
村田 裕一 …… 41
漢代遼東の硯について
古澤 義久 …… 59
石硯およひ候補品の岩石学的調査
足立 達朗 …… 77
薬師ノ上遺跡出上石製品に付着した黒色物質の分析
岡見 知紀 …… 83
再論布留遺跡出土“板石硯・研石"
No7・No8 古澤 義久 …… 89
弥生時代の日韓の権(補説)
武末 純一 …… 95
石硯と砥石などの区別-総括に代えてー
武末 純一 …… 106
【2025年3月26日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82609
書 名
条里制・古代都市研究 第40号
シリーズ
(条里制・古代都市研究会 2024)
データ
B5 100頁
ISBN/ISSN
2187-1026
編著者
条里制・古代都市研究会編集
出版年
2025年2月
出版者
条里制・古代都市研究会
価 格
4,400円(税込)
CONTENTS
特集:地方官衙と地域社会
………………………………………………………………………
鐘 江 宏
之:8・9世紀の国雑任と地域社会
1
門 井 直
哉:国府の成立とその影響について
21
江 浦
洋:平城京北辺坊における条坊遺構の調査 33
田 中 龍 一:西大寺弥勒金堂の調査成果と金堂院の復元 45
田 部 剛
士:伊勢国府における方格街区の検討
57
丸 山 利 枝:長者屋敷官衙遺跡(中津市)周辺の確認調査 67
:第27回現地研究会
75
:事務局だより
77
:会員一覧
80
:条里制・古代都市関係文献目録
86
【2025年3月25日 【入荷】【ご注文承り中】
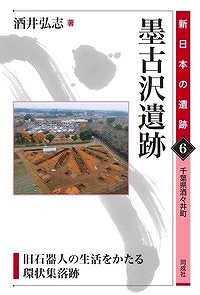
書籍番号
82607
書 名
墨古沢遺跡 旧石器人の生活をかたる環状集落跡
シリーズ
(新日本の遺跡 6)
データ
四六版 170頁
ISBN/ISSN
978-4886219992
編著者
酒井 弘志著
出版年
2025年3月
出版者
同成社
価 格
1,980円(税込)
★「新日本の遺跡」★(監修:水ノ江和同・近江俊秀)
****************************************************
このたび「日本の遺跡」シリーズを継承しつつ、大幅に
リニューアルした「新日本の遺跡」シリーズを開始いたし
ます。日本列島の遺跡を再評価し、地域から日本の歴史を
照射する新シリーズ
………………………………………………………………………
【内容紹介】
………………………………………………………………………
三万四千年前、人々は狩猟具となる石器をつくるために千葉
に集まった? 日本最大級の環状ブロック群から旧石器人の
生活が見えてくる。
………………………………………………………………………
【目次】
………………………………………………………………………
第Ⅰ部 遺跡の概要―墨古沢遺跡とは―
第1章 国史跡への挑戦
第2章 環状ブロック群とは
第3章 墨古沢遺跡の環状ブロック群の発見
第4章 範囲確認調査と自然科学分析の成果
第5章 なぜ環状ブロック群はつくられたか
第6章 整備・活用に向けた挑戦
<既刊>
82022 三万田東原遺跡 九州縄文人のアクセサリー工房
(新日本の遺跡 1)大坪 志子著 ¥1,980(税込)
https://www.chugoku-shoten.com/mokuji/jmokuji/82022/82022.html
82176 大宰府跡
(新日本の遺跡 2) 赤司善彦著 ¥1,980(税込)
https://www.chugoku-shoten.com/mokuji/jmokuji/82176/82176.html
82254
旧相模川橋脚 関東大震災によって蘇った中世の橋
(新日本の遺跡 3)大村浩司著
¥1,980(税込)
https://www.chugoku-shoten.com/mokuji/jmokuji/82254/82254.html
82270
楯築遺跡 吉備に築かれた弥生時代最大の墳丘墓
(新日本の遺跡 4)宇垣匡雅著
¥1,980(税込)
https://www.chugoku-shoten.com/mokuji/jmokuji/82270/82270.html
82445 亀ヶ岡石器時代遺跡
縄文社会の共同墓地とまつりの
場(新日本の遺跡 5)羽石智治著¥1,980(税込)
https://www.chugoku-shoten.com/mokuji/jmokuji/82445/82445.html
【2025年3月25日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82608
書 名
竈と住まいの考古学
シリーズ
データ
B5 408頁(上製本)
ISBN/ISSN
978-4886219985
編著者
合田 茂伸 合田 幸美著
出版年
2025年3月
出版者
同成社
価 格
15,400円(税込)
【内容紹介】
………………………………………………………………………
古代を中心に弥生から近世まで、竈や炉の検出遺構を詳細に
分析・検証。日本の住まいの変革期を、煮炊きの場所から新
たに捉えなおす。
………………………………………………………………………
【目次】
………………………………………………………………………
第1部 原史・古代の竈
第2章 日本列島における出現期の竈
第3章 古墳時代中期の竈
第4章 古墳時代の竈の出土状態
第5章 西日本の竈の構造と炊爨具の構成
第6章 竈・温突(オンドル)
第7章 中世の竈
第8章 近世の竈
第9章 中世・近世の竈の絵画資料
第10章 朝鮮半島の竈
第11章 中国の壁竃
第12章 竈形土器
第13章 竈形土器は韓式系土器であろうか
第14章 「小型炊飯具」の分布と消長
第15章 U字形土製品からみた竈遺構の復元
第2章 斜面の建築
第3章 原史・古代の建物と景観
第4章 古墳出現期の竪穴建物
第5章 古墳時代の炉と竈
第6章 竈の出現と住まいの変革
【2025年3月24日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82595
書 名
考古学と文化史 2
シリーズ
(同志社大学考古学シリーズ 14)
データ
A5 680頁
ISBN/ISSN
編著者
同志社大学考古学研究室編集
出版年
2025年4月
出版者
同志社大学考古学研究室
価 格
4,400円(税込)
────────────────────────────────
二〇二三(令和五)年は、考古学研究室の初代教員である酒詰仲男先生が
同志社大学にご着任されて七〇年、二代教員である森浩一先生がご逝去
されて一〇年の節目であった。そこで、考古学研究室の関係者にお声が
けして、前者については六月二八日に記念祝賀会を、後者については一
〇月七日に偲ぶ会を開催した。いずれも多くの関係者にお集まりいただ
き、それぞれの節目について感厩を共有することができた。
また、森先生がご着任された一九六六年に始まった木曜定例研究会、通
称「定例研」も昨年(二〇二四)一〇月に一、二〇〇回目を迎え、辰巳和
弘氏(一九六五年度生)に定例研が始まった頃の考古学研究室についてお
話いただいた。ここ数年の考古学研究室での出来事を振り返ると、日本
の考古学界に数々の業績と人材を輩出してきた同志社大学考古学研究室
の歴史と伝統の深さと大きさを、改めて痛感する次第である。これもひ
とえに、卒業生を中心とした考古学研究室関係者のご理解とご協力の賜
物である。記して心から感謝申し上げたい。
ところで、今回からしばらくの間、この同志社大学考古学シリーズは二
年間隔での刊行を目指すこととした。それは、三年間隔だと大学院へ進
学した学生や、学部で卒業して就職する学生が、まとめた卒業論文を活
字にする機会を逸することが多いためである。もちろん、従来どおりに
多くの関係者には自己研鑽の場として、今まで以上の論文投稿を期待す
るものである。
さて、今回のテーマは「考古学と文化史2」とした。その設定理由は、
ここ数年の考古学研究室関連の行事の原点を考える時、前シリーズ同様
に、考古学研究室開設当時の本学文化学科文化史学専攻(現文化史学科)
の在り方や、一九八二年に本シリーズが創刊された当時の趣旨を忘れな
いようにするためである。今回も五八名による多くの論文が集まった。
各執筆者もご多忙のなか、同じ想いでご執筆いただいたと確信する。
心から感謝を表したい。
本書の編集にあたり、山田邦和・鋤柄俊夫・若林邦彦・浜中邦弘氏に
は編集委員として、実際の編集や査読にご尽力いただいた。また、考古
学研究室事務員である松藤薫子・廣田幸氏には各種事務についてお手伝
いいただいた。末尾ではあるが、記してお礼を申し上げるものである。
二〇二五年四月一日
同志社大学文学部教授 水ノ江 和 同
────────────────────────────────
【目 次】
────────────────────────────────
『考古学と文化史2」目次
刊行にあたって ………………………………………… 水ノ江 和 同
古植生からみたAT下位石器群の特徴に関する一試論 …
面 将 道
北陸地方における刃部磨製斧形石器の石材について
ー透閃石岩(ネフライト)はどこで採取したかー ……麻
柄 一 志
京都盆地の旧石器時代遺跡
ーいわゆる地山の性格についてー ……………………手 島
美 香
ある石器製作者による瀬戸内技法の模倣
………………長 屋 幸 二
五色台から金山へ
ー石材利用の変化とその背景ー ………………………朝 井
琢 也
遺跡の引き算の概念と実例
………………………………廣 重 知 樹
縄文時代中期末葉"北白川C式土器”の研究
ー文様帯構成の分析による編年の再検討ー …………松
原 諒 汰
石製装身具の再加工と再利用
………………………… 水ノ江 和 同
準構造船の出現期について
ーアイヌ民族例も援用してー …………………………鈴 木 信
西播磨地域における凸帯文土器の特質 …………………春 名 英 行
清水風遺跡出土の「盾と戈をもつ人物」画から見る弥生祭場の風景
…………………藤 田 三 郎
弥生時代定義にみる文化/社会区分の相克と困難な選択肢
…………………若 林 邦 彦
鉛同位体比からみた外縁付鈕2式の銅鐸群 ………………清 水
邦 彦
有鉤銅釧の製作時期・鋳型素材に関する一考察
………叶 井 陽
弥生時代の石製鍛冶具に関する考察
ー淡路市所在五斗長垣内遺跡・舟木遺跡出土資料の検討からー
…………………菅 榮太郎
卓状墓の広がり(二) ………………………………………福 島
孝 行
種子島における弥生時代から古墳時代並行期の石器について
…………………石 堂 和 博
鍵手文と縦横帯交差文 ……………………………………杉 山
拓 己
神宮創祀に至る在地構造の変革
ー多気郡域の帆立貝式古墳の再評価ー
……………穂 積 裕 昌
安芸・備後地域におけるヒスイ製勾玉副葬をめぐる一様相
…………………岸 本 晴 菜
石棺の埋納
ー古墳時代前期ー中期前半の刳抜式石棺についてー
…………………真 鍋 昌 宏
韓半島における大型送風管の製作技法について
ー「輪台技法」としての認識と技法の復元・意図をめぐってー
…………………辻 川 哲 朗
下げ美豆良と上げ美豆良 …………………………………日
高 慎
古墳時代鉄器副葬の地域性に関する検討
ー滋賀県安養寺古墳群と妙見山古墳群の渡来系鉄器の導入をめぐって
…………………槇 和 泉
古墳時代の「水屋」
ー囲形埴輪の評価をめぐってー …………………松
田 度
埴輪に描かれた馬
ー飯田古墳群における馬匹文化の一例ー
…………春 日 字 光
太鼓形埴輪の型式学的検討 ………………………………柴 田
将 幹
古墳時代ガラス玉の製作技法
……………………………福 島 雅 儀
北へ向かう毛野の古墳文化 ………………………………深 澤
敦 仁
火雨塚古墳の基礎的検討
…………………………………佐 藤 純 一
倭鍛冶・韓鍛冶の文化史学的研究
ー生駒山地西麓における古墳時代後期の鍛冶揉業ー
…………………真 鍋 成 史
葡萄唐草文軒平瓦の再検討 ………………………………服 部
伊久男
恭仁宮大極殿院平面プランの復元とその評価 …………古
川 匠
古墳その後
ー素描ー
………………………………………………浜 中 邦 弘
播磨北西部における古代鉄生産
ー技術系譜と背景ー
…………………………………大 道 和 人
延暦年間の信濃国高句麗人賜姓記事の考古学的研究 …川
崎 保
古代の手洗と洗盤 …………………………………………森
川 実
中世都市見付のもう一つの姿を考える
ー予察ー
………………………………………………鋤 柄 俊 夫
博多遺跡群周辺における古代から中世のガラス資料について
…………………比 佐 陽一郎
宝篋印塔と納経 ……………………………………………原 田
昭 一
和鏡のもつ意味
ー出土遺構の違いから考えるー
……………………濵 喜和子
水中遺跡の「一括性」
ー陸上遺跡基準資料との比較検討ー
………………石 田 蓮
中世霊場「天橋立」の再編
ー十四世紀前半を中心にー
…………………………河 森 一 浩
信長死後の安土城造瓦集団についての一考察 …………山 口
誠 司
戦国期の平泉寺と朝倉氏との関係
………………………宝 珍 伸一郎
地形環境からみた摂津国中島の中世城館
ー野田・福島合戦における利用に着目してー
……岡 本 健
中世後期~近世の瓦灯(燈)について
……………………堀 寛 之
豊後府内に搬入された手づくね成形土師器皿について
…………………山 本 尚 人
二尊院所蔵の位牌についての一考察 ……………………井 上
智 代
二条家邸跡出土の江戸の土人形について
………………加 藤 雄 太
出土京焼研究の方法(一)平碗の属性
ー文様を中心としてー
………………………………角 谷 江津子
魏志倭人伝における哭泣の意味 …………………………門 田
誠 一
熨人略考
ー火熨斗の挿柄台と漢~西晋期における服装史・布帛史の一側面ー
…………………江 介 也
ソンマ・ヴェスヴィアーナ在
ローマ時代遺跡出土石臼の設置場所 ……………………反 田
実 樹
人文知と考古学・考古学者
ー森浩一の著作と一九七〇年代ー
…………………今 尾 文 昭
天皇陵古墳の名称問題 ……………………………………山 田
邦 和
考古学史に見る遺跡保存の取り組みと課題
ー少子高齢化・人口減の時代に改めて考えるー
…鈴 木 重 治
地域史を実感するためのスローサイクリング …………藤 川
智 之
【2025年3月23日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82600
書 名
唐代都城中枢部の考古学的研究
シリーズ
データ
A4 513頁 (上製本)
ISBN/ISSN
978-4864451857
編著者
城倉 正祥著
出版年
20254年3月
出版者
六一書房
価 格
9,900円(税込)
本書では、唐王朝(618-907)が造営した都城を「唐代都城」と
定義し、その歴史的意義を考古学的に追及することを目的とした。
唐王朝が造営した長安城(京師)・洛陽城(陪京)は、同時代の東ア
ジア諸国に大きな影響を与えたが、その歴史性を考究するには、
広い視野で唐代都城を相対化する作業が不可欠である。そのため、
唐長安城・洛陽城を中国都城の通時的発展史の中に位置付ける(第
1章)とともに、同時代の地方都市との比較(第2章)、東アジア周辺
国の都城との比較(第3・4章)を試みた。その成果は、以下の通り
である。
第1章では、秦~清までの都城の変遷・発展の中で、唐長安城・
洛陽城を位置付けた。唐王朝の造営した都城は、7世紀中葉~ 8世
紀中葉にかけて国際的に高い影響力を保持していたが、国内にお
いて後世の都城に強い影響を与えたのは、北宋東京開封城で成立し
た新しい様式だった。
第2章では、唐の安西四鎮の1つである砕葉城を分析対象とし、
西域シルクロード都市の特徴を明らかにした。唐の国内においては、
皇帝権力の中枢である京師・陪京を頂点とし、東では揚州城などの
海港型、西では砕葉城など内陸型の交易商業都市が、それぞれ異な
る機能と構造を持って展開した点を論じた。
第3章では正門、第4章では正殿の遺構に注目し、唐王朝が造営し
た都城と渤海・日本などの周辺国が造営した都城との国際的な比較
を行った。分析によって、唐王朝の国家的儀礼の舞台であった宮城
正門、正殿の構造が周辺国に強い影響を与えた点が明らかになった。
これは、唐皇帝の主催する国家的儀礼に各国使節が参加することで
得た情報に基づき、その舞台空間が模倣対象となった点を示唆して
いる。特に、唐帝国の国内支配や国際秩序が1年に1度更新される儀
礼、すなわち「元会」の舞台が主要な模倣対象となり、各国の支配
体制に合致する形でその空間が二次的に再現された点が重要である。
本書では、この現象を「儀礼(空間)の連鎖」と呼称した。外交使節
を通じて取得した情報に基づく各国独自の選択的な模倣こそが、東
アジアにおける都城の伝播の実態だと考える。
以上の分析を通じて、唐代都城の歴史性を考究した。発掘された
遺構の考古学的な分析に基づく東アジア都城の研究は、文献史学・
建築史学などの隣接分野とは異なる角度から、都城の歴史性を浮かび
上がらせる作業に他ならない。
序章 研究の課題と目的
第1
章 中原都城から草原・明清都城へ 都城通史からみた唐代都城
の位置
第1 節 中国都城の通時的研究と今後の課題
1. 中国都城研究における通史的視点
2. 都城研究の考古学的展望 外郭城研究の重要性と将来性
3. 分析対象、分析方法、概念定義
第2
節 中原都城(秦漢・魏晋南北朝・隋唐・宋)の平面配置
1. 秦漢の都城
2. 魏晋南北朝の都城
3.
隋唐・宋の都城
第3 節 草原都城(遼・金・元)と明清都城の平面配置
1. 遼の都城
2. 金の都城
3. 元の都城
4. 明清の都城
第4 節 中原都城から草原・明清都城へ
1. 中原都城の構造的特色と周辺国への影響
2. 中原都城から草原都城への変化とその意義
3. 都城の完成形 明清都城の構造的特色
4. 唐代都城の歴史的位置
第2
章 唐砕葉城の歴史的位置 都城の空間構造と瓦の製作技法に注目
して
はじめに
第1
節 唐砕葉城の調査研究史と課題
1.アク・ベシム遺跡の位置・歴史と平面配置
2.文献に記載される唐砕葉城
3.アク・ベシム遺跡に関する調査研究略史
4.アク・ベシム遺跡の発掘された主要遺構
5.論点と課題
第2
節 唐砕葉城の空間構造とその特色 西域都市・中原都城との
比較から
1.衛星画像の分析に基づく唐砕葉城の平面配置
2.唐代西域都市の空間構造と砕葉城
3.北庭故城と砕葉城の設計原理
4.唐代都城の階層性とその展開
第3
節 唐砕葉城出土瓦の製作技法とその系譜
1.対象資料と用語の整理
2.砕葉城出土板瓦の製作技法
3.砕葉城出土瓦当の年代と系譜
4.西域都市の瓦生産とその系譜
第4
節 唐砕葉城の歴史的位置
第3 章 東アジア古代都城門の構造・機能とその展開
第1 節 東アジア古代都城門の研究史と課題
1.思想空間としての唐代都城と「門遺構」研究の意義
2.中国古代都城門の研究史
3.日本古代都城門の研究史
4.本章の比較視座と研究課題
第2
節 東アジア古代都城門の分析視角
1.分析対象と分析方法
2.中国都城門の種類と構造
3.日本都城門の種類と構造
第3
節 中原都城(漢・唐・宋)と草原都城(遼・金・元)の門遺構
1.漢の都城門
2.魏晋南北朝の都城門
3.唐~宋の都城門
4.遼・金・元の都城門
第4
節 高句麗・渤海都城の門遺構
1.高句麗の都城門
2.渤海の都城門
第5
節 日本都城の門遺構
1.7 世紀の都城門
2.8 世紀の都城門
第6
節 東アジア古代都城門の構造・機能とその展開
1.連体式双闕門の発展と唐代都城門の諸類型
2.唐代都城の構造と門の階層性 含元殿の成立
3.唐代都城の解体と再編成 北宋以降の正門の変遷
4.唐代都城門の東アジアへの展開
おわりに
第4
章 太極殿・含元殿・明堂と大極殿 唐代都城中枢部の展開とその
意義
はじめに
第1
節 東アジア古代都城中枢部の変遷に関する研究史
1.日本都城における中枢部の研究
2.日中古代都城の比較研究
3.中国都城における中枢部の研究
4.論点と課題
第2
節 東アジア古代都城の遺構比較に関する方法論
1.比較視座と方法論
2.分析対象遺構
第3
節 東アジア古代都城の正殿遺構
1.中原都城(秦・前漢・後漢・魏晋南北朝・隋唐・北宋)の正殿遺構
2.草原都城(遼・金・元)の正殿遺構
3.明清都城の正殿
4.高句麗・渤海都城の正殿遺構
5.日本都城の正殿遺構
第4
節 中原都城における正殿の発展と唐代における東アジアへの
展開
1.中原都城における正殿の発展と草原・明清都城への継承
2.高句麗・渤海都城における正殿の構造とその特色
3.日本都城における正殿の構造とその特色
4.唐代東アジア都城の正殿遺構 規模と構造の比較
5.儀礼・饗宴空間としての都城中枢部と東アジアへの展開
終章 唐代都城中枢部の構造とその展開
要旨(日本語)
要旨(中国語)
索引(事項・遺物・遺構・歴史的人名)
【2025年3月21日 【入荷】【ご注文承り中】
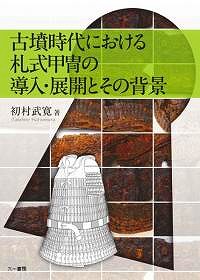
書籍番号
82601
書 名
古墳時代における札式甲冑の導入・展開とその背景
シリーズ
データ
B5 371頁
ISBN/ISSN
978-4864451703
編著者
初村 武寛著
出版年
2025年3月
出版者
六一書房
価 格
5,500円(税込)
古墳時代中期に日本列島にもたらされた札式甲冑は、構造の革新を
行いながら次第に数を増し、古墳時代後期には倭の甲冑の中核を担う
ようになる。札式甲冑は先行研究においても扱われてきた遺物ではあ
ったが、その構造や用途については不明な点が多かった。本書では特
に古墳時代中期の資料を中心として、札式甲冑の構造復元と用途の検
討に踏み込み、札式甲冑の導入から展開における過程を検討する。
また、本書では著者が近年取り組んでいる3Dデータからの資料比較
として、札式甲冑の導入・展開期に存在する同型鏡群・鈴付銅器を取
り上げ、再考を試みる。
序章 札式甲冑研究史と本書の目指すところ
第1部 古墳時代中期における札式甲冑の導入と展開
第1章 古墳時代中期における札甲の変遷
第2章 日本列島における導入期札甲の構造と副葬の背景
第3章 古墳時代中期における札式付属具の基礎的検討
第4章 倭への重装騎兵装備の導入―和歌山県大谷古墳の事例から
第5章 古墳時代中期における渡来系遺物の受容とその画期
第2部 古墳時代後期における甲冑の製作用途とその性格
第6章 裲襠式札甲を含む武装の解明とその意義 愛知県大須二子山
古墳出土甲冑セットと副葬状況に着目して
第7章 衝角付冑と札式付属具の連結過程
第8章 日本列島における朝鮮半島系札甲副葬古墳とその周辺
第9章 革札を用いた札甲の構造とその意義
第10章 古墳時代以後―飛鳥寺東大寺例にみる札甲の構造
第3部 札式甲冑の導入展開期における副葬品群の様相
第11章 同型鏡群の比較検討からみた副葬品の製作入手伝世
第12章 鈴付銅器の変遷と用途
終 章 日本列島における渡来系技術の受容とその背景
引用文献
挿図表写真出典
初出一覧
【2025年3月21日 【入荷】【ご注文承り中】
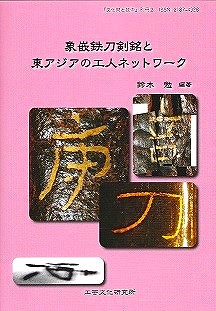
書籍番号
82599
書 名
象嵌鉄刀剣銘と東アジアの工人ネットワーク
シリーズ
(「文化財と技術 別冊2)
データ
A5 236頁
ISBN/ISSN
2187-4328
編著者
鈴木 勉編著
出版年
2024年12月
出版者
工芸文化研究所
価 格
1,100円(税込)
1. 七支刀って何?
2.七支刀復元研究に辿りつくまで
3.七支刀復元研究から見えた古代東アジア
4.七支刀を復元して
(付説1)古代のマザーメタル「はがね」>
(付説2)九州の有樋鉄戈と中国の文化と技術
第2章 後漢鉄刀剣の「「さんずいシ柬」と中平銘鉄刀の
「いとへん練」
1.中平銘鉄刀製作地論
2.中平銘鉄刀の文字の特徴
3.中平銘鉄刀はいつどこで作られたか
4.中平銘鉄刀と霊帝信仰
5.古代中国の「さんずいシ柬」と極東アジアの「いとへん練」
6.中平銘鉄刀が日本列島製なら東アジア古代史はどう変わるか
第3章 市原市稲荷台1号墳出土王賜銘鉄剣
1.象嵌技術と線彫り
2.王賜銘鉄剣の蹴り彫り象嵌
3.「王賜」の背景
第4章 さきたま稲荷山古墳出土金象嵌辛亥銘鉄剣
1.象嵌研究のはじまり
2.線彫り技術と象嵌
3.稲荷山金象嵌辛亥銘鉄剣を復元する
4.顕彰刀の発注者と移動する渡来系工人ネットワーク
第5章 韓半島出土金象嵌銘文
1.昌寧校洞11号墳有銘円頭大刀金象嵌銘
2.東博蔵有銘環頭大刀金象嵌銘
3.移動する渡来系工人ネットワークで見える象嵌技術のひろがり
第6章 福岡市元岡G6号墳出土庚寅銘大刀 ―謎の一文字「れん」
と製作年―
1.庚寅銘の検討
2.謎の一文字「れん」をめぐって
3.発掘担当者大塚紀宜氏の見解から製作年を絞る
4.文字の技術史からみた製作年
5.庚寅銘大刀の釈文・訓読・解釈
第7章 古代韓半島における象嵌技術と工人ネットワーク(金跳咏)
1.はじめに
2.研究史と問題の所在
3.三国時代における象嵌技術と展開
4.古墳時代における象嵌技術の受容
5.象嵌技術からみた日韓交渉
第8章 倭装系製品の象嵌技術
1.連弧輪状文と旧来の渡来系工人集団
2.円文象嵌の技術移転
3.福島県弘法山5号横穴墓(6世紀後半)のなめくり象嵌
4.百済の毛彫り技術から毛彫り象嵌へ
5.展望
………………………………………………………………………………
<既刊>
82244 移動する渡来系工人ネットワーク
(「文化財と技術 別冊1)
鈴木 勉著/2024年4月 A5 222頁
工芸文化研究所 ¥1,100(税込)
(目次等は以下のURLよりご覧いただけます)
https://www.chugoku-shoten.com/mokuji/jmokuji/82244/82244.html
【2025年3月6日 【入荷】【ご注文承り中】
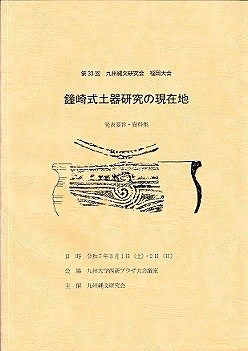
書籍番号
82591
書 名
鐘崎式土器研究の現在地
シリーズ
(第33回 九州縄文研究会福岡大会 発表要旨・資料集)
データ
A4 308頁
ISBN/ISSN
編著者
九州縄文研究会福岡大会事務局編集
出版年
2025年3月
出版者
九州縄文研究会
価 格
4,000円(税込)
土器群を取り上げる。鐘崎式土器は、福岡県宗像市上八こうじょ
う(鐘崎)貝塚出土資料を標識とする土器型式で、九州を代表す
る磨消縄文土器として古くから注目されてきた。当該期をめぐっ
ては、集落の大規模化が始まるとともに、竪穴建物の構造や石器
組成など、中・四国地方以東からの影響が見られる段階にあたり、
九州縄文社会の変動期であることが知られている。
縄文社会の復元を進めるうえで、土器研究の深化は必須であり、
編年研究の精度を高めるだけではなく、地域性の抽出、併行関係
・系譜関係の整理など、取り組むべき課題は多い。こうした状況
を踏まえて、今回は当該期の一括性の高い資料をできる限り集成
し、鐘崎式併行期の地域性や地域間の関係、型式変化の方向性や
後続型式との繋がり、市来式に代表される在地土器型式との関連
性などを整理することで、鐘崎式土器研究の現在地を確認し、今
後の研究の方向性を探る契機としたい。
縄文晩期農耕と縄文文化の終焉
宮本 一夫(九州大学名誉教授) …………… 1
【研究発表】
鐘崎式の構造と編年
小南 裕一(北九州市役所)……………………17
鹿児島県薩摩半島出土の市来式土器について
鮫島
えりな(鹿児島県教育庁文化財課)
前迫 亮一((公財)鹿児島県文化振興財団
上野原縄文の森) ……35
中国地方における小池原上層式・鐘崎式系土器の波及と地域間
交流 幡中
光輔(出雲市市民文化部)………………41
鐘崎式土器期の石器と遺構-薩摩半島地域を事例として-
板倉 有大(福岡市埋蔵文化財課)……………61
【紙上発表】
鐘崎式土器研究のこれまでと現在地
林 潤也(大野城市心のふるさと館)…………77
南四国の平城Ⅰ式/古池原上層式から鐘崎式にかけての様相
松本 安紀彦(高知県史編さん室)
……………87
【ポスター発表】
岡垣町榎坂貝塚出土の縄文後期中葉土器
永山 亮・井内 達也・古澤 義久・
小田 富士雄(福岡大学)…………………………99
黒橋貝塚の調査盛夏について
金田 一精(熊本市文化財課)
…………………102
大王遺跡発掘調査について
山中 俊樹(都城市文化財課)
…………………103
の土器群の様相
福永 将大(九州大学総合研究博物館) …………105
佐賀県における鐘崎式土器及び併行期土器群の様相
堤 英明(佐賀県文化課文化財保護・活用室)
…135
長崎県の様相
中尾 篤志(長崎県教育委員会) …………………141
大分県における鐘崎式土器出土遺跡の概要
横澤 慈(大分県立埋蔵文化財センター)…………155
熊本県における縄文時代後期の小池原上層式
~鐘崎式及び並行期の土器群(市来式)の様相
藤森 あきの(熊本県教育庁文化課)
……………193
宮崎県の動向
金丸 武司(宮崎市文化財課)………………………234
鹿児島県の動向 鮫島 えりな(鹿児島県教育庁文化財課)
前迫 亮一((公財)鹿児島県文化振興財団
上野原縄文の森)…………251
沖縄県における小池原上層式~鐘崎式及びその並行期の土器群
亀島 慎吾・奥平 大貴(沖繼県教育庁文化財課)、
金城 翼・大堀 皓平
(沖縄県立埋蔵文化財センター)……278
【2024年の動向】
各県の調査事例と報告書 ………………………………………292
【研究会の記録】
第32回九州縄文研究会大分大会の記録
九州縄文研究会大分大会事務局……298
【2025年3月6日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82590
書 名
パレオアジア
新人文化の形成
シリーズ
―考古学・文化人類学からのアプローチ―
データ
A5 512頁 (上製本)
ISBN/ISSN
978-4-7877-2416-8
編著者
西秋良宏・野林厚志編著
出版年
2025年3月
出版者
新泉社
価 格
7,150円(税込)
で、新人たちは、いかに適応し、旧人集団と交替したのか。太古の交替
劇を過去と現在の文化の証拠をもとに考察する。
の理解【野林厚志・西秋良宏】
第3章 タケ仮説と人類史【山岡拓也】
第4章 島への移住と水産資源の開発
―ウォーレシアにおける現生人類の漁労技術と海洋適応
【小野林太郎】
第5章 考古学にみる集団と社会
―西アジア・ネアンデルタール研究からの視点【西秋良宏】
第6章 集団接触による物質文化形成
―東アジア旧石器文化の例【加藤真二】
第7章 新人のアジア拡散における装身具の出現パターンと役割
【門脇誠二】
第8章 狩猟採集民の学習行動と文化伝達
―旧石器時代の考古資料からの理解【髙倉純】
第9章 洞窟壁画にみる狩猟民の世界観【竹花和晴】
第10章 狩猟採集民から農耕牧畜民の世界観へ【前田修】
―インドネシア、西ティモールの事例から
【中谷文美・上羽陽子・金谷美和】
第12章 技術の継承経路と社会
――ウズベキスタンの陶業を事例に【菊田悠】
第13章 狩猟行動に関する通文化比較
――熱帯湿潤地域を事例に【彭宇潔】
第14章 人類の移動拡散ベクトルについての批判的省察
――南方経路上の考古遺物への民族移動誌の投影より【高木仁】
第15章 異集団接触にともなうニッチ喪失
――和人社会によるアイヌ民族支配を事例として【大西秀之】
第16章 新人文化におけるビーズ装飾と社会
――狩猟採集民のビーズ利用から考える【池谷和信】
第17章 境界オブジェクトとしての獣人表象【山中由里子】
第18章 墓制からみる集団と社会
――中央アジア草原地帯の事例を中心として【藤本透子】
第20章 民族誌データの定量分析と考古学への援用
――帰納的解釈と生業類型のプロジェクション【野林厚志】
【2025年3月4日 【入荷】【ご注文承り中】
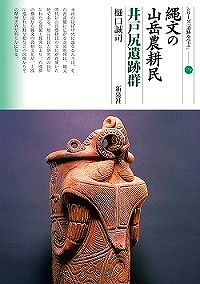
書籍番号
82589
書 名
縄文の山岳農耕民 井戸尻遺跡群
シリーズ
(シリーズ「遺跡を学ぶ」 170)
データ
A5 96頁
ISBN/ISSN
978-4-7877-2340-6
編著者
樋口 誠司著
出版年
2025年3月
出版者
新泉社
価 格
1,870円(税込)
(シリーズ「遺跡を学ぶ」)は下記のURLより出版社サイトで
ご覧いた だけます。
https://www.shinsensha.com/iseki/
───────────────────────────
【紹介文】
本州のほぼ中央に連なる八ヶ岳。その西南麓に広がる高原地帯は、
縄文時代に山岳農耕民の文化が花開いた地である。地元住民と研
究者の長年にわたる発掘・探究により、石器群の構成から縄文の
農耕文化が、土器に描かれた蛙や蛇などの図像からその精神世界
が明らかになる。
第1章 八ヶ岳山麓の縄文遺跡
1 おらあとうの村の遺跡発掘
2 おらあとうの村の井戸尻編年
1 八ヶ岳南麓の井戸尻文化
2 井戸尻文化とは何か
1 藤森栄一の縄文農耕論
2 遠山郷で学んだこと
3 縄文農耕を支えた石器群
4 列島につらなる新石器製作技術
5 パン状炭化物の発見
1 縄文土器の図像学
2 縄文の神話と富士眉月弧
3 高原の縄文王国収穫祭
【2025年3月3日 【品切】【ご提供不可】
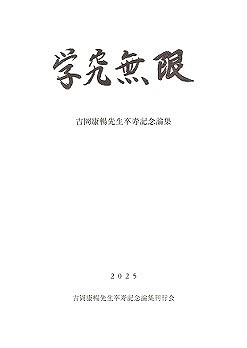
書籍番号
82587
書 名
学究無限 吉岡康暢先生卒寿記念論集
シリーズ
データ
A4 466頁
ISBN/ISSN
編著者
吉岡康暢先生卒寿記念論集刊行会編集
出版年
2025年3月
出版者
吉岡康暢先生卒寿記念論集刊行会
価 格
品 切
牽引し、珠洲焼の学問的位置づけを確立された吉岡康暢先生が令和7
年4月に卒寿の慶賀をお迎えになられます。先生に学恩のある石川考
古学研究会と北陸古代土器研究会の会員が中心となった41編の論文を
はじめとして、先生が積年の地域研究を大成されたご高論を加えた論
文集を作成いたしました。
目 次
刊行の辞 発起人代表 小嶋芳孝
吉岡康暢先生略歴・著作目録……………………………………………1
吉岡 康暢 わたしのナツメロ帖………………………………………8
吉岡 康暢 加賀立国と国府・国分寺再考 …………………………19
足立 拓朗 北陸地方における縄文時代の陥し穴 …………………63
松永 篤知 石川県域における「編む」から「織る」への編織技術
革新
………………………………………………………71
戸根比呂子 石材採取から見る南加賀の玉生産 ……………………81
中江 隆英 北陸南西部の結合器台に関する再考 …………………91
前田 清彦 方形墳墓の墳頂部面積と葬送祭祀……………………101
田嶋 明人 土器推移に見る「社会史」との関連…………………111
河村 好光 能美市秋常山1号墳の墳丘調査………………………115
新美祥人夢 福井県若狭町脇袋丸山塚古墳出土の形象埴輪………125
池野 正男 越中・能登の5~7世紀の手工業生産遺跡と置き竈
………………135
入江 文敏 若狭・越における渡来系遺物・遺構の変遷
-渡来系鉄器・古墳主体部の観点から- 147
松葉 竜司 福井県美浜町興道寺採集の須恵器と興道寺窯跡に関する
再評価……………………………………………………157
内山 敏行 古墳時代後期の有蓋食器-使い方と性格を考える-
……………163
望月 精司 須恵器甕の丸底と平底-作り方と使い方を考える-
……………173
桃﨑 祐輔 金属器模倣土器の出現と隋使来航……………………183
村上 昂之 南加賀・越前における切石積横穴式石室の構築技法
-積方技法と石材縦横比を中心に-
…………195
伊藤 雅文 横穴墓造営の背景についての一考察…………………205
畑中 英二 鏡山古窯址群と西河原遺跡群-須恵器生産と地方官衙-
………215
田中 広明 仏鉢の生産と使用をめぐる人々………………………225
出越 茂和 加賀地方の古代土器編年と年代………………………235
川畑 誠 再考・能登における須恵器生産の終焉………………245
堀内 和宏 9・10世紀の津軽地方の地域社会と交流-土師器甕に注
目して- ………………………………………………255
井上 尚明 古代港湾遺跡の再検討…………………………………265
安中 哲徳 道との遭遇-能登・加賀の古代道路遺構と大領遺跡-
…………275
金田 章裕 古代の荘所・溝所・川所再考…………………………285
福田 健司 「牧」を管理・運営した遺跡-状況証拠と物的証拠-
…………295
森田喜久男 加賀立国と能美郡………………………………………307
横幕 真 古代・中世における祠の形態-祠状木製品を中心に-
…………317
兼康 保明 柱穴埋納土器考…………………………………………327
野村 将之 石川県立歴史博物館所蔵「刷毛目大壺」の検討
-加賀地方で出土する「ハケ調整陶器」との比較を
通して- ………………………………………………335
藤田富士夫 富山県における経塚のランドスケープから
-山岳崇拝型経塚の提唱- ……………………345
向井 裕知 中世横江荘のかわらけ…………………………………353
韓 盛旭 沖縄出土高麗靑瓷と‘癸酉年高麗瓦匠造’銘瓦の検討
……………363
小林 正史 『長楽寺永禄日記』(1565年)における食器の使い分け
…………375
岡 佳子 17世紀の京焼……………………………………………387
木立 雅朗 「赤い土」を白く焼く-土器焼成技術の基礎研究ノート
- ………………………………………………………399
山川 均 赤膚焼の成立-赤膚山元窯関連史料を中心に- …409
北野 博司 筑前黒田家が参加した公儀石垣普請…………………417
鹿島昌也・泉田侑希 北陸における近代煉瓦研究事始……………427
高橋 照彦 唐三彩陶枕の基礎的検討-初期唐三彩をめぐる試論-
…………437
辻尾 榮市 遭難する渤海船、沈没する日本船……………………447
小嶋 芳孝 渤海滅亡後のクラスキノ城跡と墳墓群-刀伊の本拠地を
考える-…………………………………………………457
【2025年3月1日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82586
書 名
魏志倭人伝の海上王都 原の辻遺跡
シリーズ
データ
A5 96頁
ISBN/ISSN
978-4-7877-2531-8
編著者
松見 裕二著
出版年
2025年3月
出版者
新泉社
価 格
1,870円(税込)
(シリーズ「遺跡を学ぶ」)は下記のURLより出版社サイトで
ご覧いた だけます。
https://www.shinsensha.com/iseki/
───────────────────────────
【紹介文】
玄界灘に浮かぶ壱岐島には、邪馬台国の時代に渡来人と倭人が
往来する海上の王国「一支国」があった。
その中心となる原の辻遺跡で発見された巨大な環濠集落や国内
最古の船着き場、さらには島内の拠点集落遺跡の発掘成果から
見えてくる、交易大国の姿とは。
第1章 「魏志」倭人伝の島
1 海上の王都、原の辻
2 壱岐島の環境
3 「魏志」倭人伝に記された壱岐島
4 壱岐島のあけぼの
1 原の辻遺跡の発見と調査の歴史
2 発掘でみえてきた遺跡の様相
3 「南北市糴」を物語る交易品
4 集落の時期的変遷
1 車出遺跡群――独自の文化を築く集団
2 カラカミ遺跡――もう一つの交易拠点
1 東アジア情勢で変化した交易網
2 一支国をめぐる各国の交易戦略
3 楽浪交易の終焉と一支国
1 一支国研究の今後
2 さいごに
【2025年2月27日 【品切】
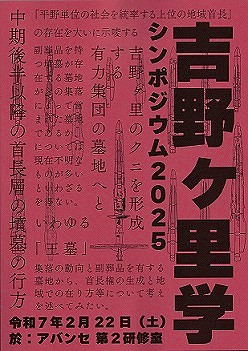
書籍番号
82584
書 名
吉野ヶ里学シンポジウム
2025
シリーズ
(弥生後期の集落と墓制-有明海沿岸を中心に-)
データ
A4 98頁
ISBN/ISSN
編著者
吉野ヶ里学研究会編集
出版年
2025年2月
出版者
価 格
★【品切】(税込)
海沿岸を中心に発表資料集。
目 次
論旨説明:拠点集落の首長とその墳墓
ー弥生時代中期から後期の地域集落群の動向の一例ー ………… 1
七田 忠昭(佐賀県立佐賀城本丸歴史館)
長崎県島原半島周辺における弥生後期の集落と墓制 …………… 17
寺田
正剛(長崎県埋蔵文化財センター)
佐賀平野における弥生後期の集落と墓制
………………………… 29
渡部
芳久(佐賀県立博物館・美術館)
筑後地域における弥生後期の集落と墓制
………………………… 43
山崎
頼人(京都文化博物館)
大庭
孝夫(福岡県教育庁文化財保護課)
熊本県域における弥生時代後期の集落と墓制
…………………… 59
福田
匡朗(熊本県教育庁文化課)
薩摩・大隅の集落と墓制ー弥生後期を中心にー
………………… 73
石田
智子(鹿児島大学法文学部)
【2025年2月25日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82580
書 名
播磨からみた縄文のおわり、弥生のはじまり
シリーズ
(第24回播磨考古学研究集会 資料集)
データ
A4 661頁
ISBN/ISSN
編著者
第24回播磨考古学研究集会実行委員会編集
出版年
2025年2月
出版者
価 格
3,500円(税込)
岡田憲一(奈良県立橿原考古学研究所)
報告1 深井明比古「東播磨の縄文のおわり
-東播磨の縄文後晩期の遺跡の実態について-」……7
報告2 大本朋弥「西播磨の縄文のおわり-遺跡数の推移から-」 ……15
報告3 篠宮 正「東播磨地域の弥生のはじまり」
………………………35
報告4 荒木幸治「西播磨の弥生のはじまり」 ……………………………55
【資料集成】
「播磨の縄文後期~弥生中期前葉遺跡集成」
……………………………79
【2025年2月25日 【入荷】【ご注文承り中】
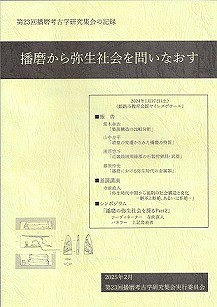
書籍番号
82581
書 名
播磨から弥生社会を問いなおす
シリーズ
(第23回播磨考古学研究集会にの記録)
データ
A4 133頁
ISBN/ISSN
編著者
第23回播磨考古学研究集会実行委員会編集
出版年
2025年2月
出版者
第23回播磨考古学研究集会実行委員会
価 格
1,500円(税込)
【講演・報告資料】
趣旨説明 荒木幸治「播磨から弥生時代を間い直す」………
1
報告1
荒木幸治「集落構造の比較分析」………………… 3
報告2 山中良平「墳墓の変遷からみた播磨の特質」…… 37
報告3
園原悠斗「近畿地域周縁部の石製狩猟具・武器」 53
報告4 藤原怜史「播磨における弥生時代の金属器」…… 77
基調講演
寺前直人「弥生時代中期から後期の社会構造と変化
ー継承と断絶、あるいは拒絶-」89
【シンポジウム記録】
「播磨の弥生社会を探るPart2」
…………………………… 107
【2025年2月25日 【品切】【ご提供不可】

書籍番号
82583
書 名
徳島市美馬市 国指定史跡「段の塚穴」
―出土遺物の調査―
シリーズ
データ
A4 97頁
ISBN/ISSN
編著者
『段の塚穴』刊行会
出版年
2024年12月
出版者
価 格
品切
例言・凡例 …………………………………………………………ⅰ
目次 …………………………………………………………………ⅱ
第1章 刊行にいたる経緯 …………………………………… 1
1.調査対象遺物とその来歴 ………………………………… 1
2.出土遺物調査の経過 ……………………………………… 1
第2章 「段の塚穴」を取り巻く環境 ………………………… 3
1.地理的歴史的環境 ………………………………………… 3
2.「段の塚穴」の概要 ……………………………………… 7
3.「段の塚穴」をめぐる考古学史 ………………………… 11
第3章 出土遺物の観察 ……………………………………… 23
1.出土遺物の概要 …………………………………………… 23
2.出土遺物の所見 …………………………………………… 23
第4章 総括 …………………………………………………… 46
1.出土遺物の検討 …………………………………………… 46
2.出土遺物の位置づけ ……………………………………… 49
附編1 願勝寺1号墳出土遺物 ………………………………… 51
1.願勝寺1号墳の概要 ……………………………………… 51
2.出土遺物の概要 …………………………………………… 51
3.小結 ………………………………………………………… 54
附編2 (伝)七人塚古墳出土遺物ほか ……………………… 58
1.七人塚古墳の概要 ………………………………………… 58
2.出土遺物の概要 …………………………………………… 58
3.小結 ………………………………………………………… 60
【2025年2月25日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82579
書 名
纒向学研究 第13号 2024
シリーズ
(纏向学研究センター研究紀要)
データ
A4 106頁
ISBN/ISSN
編著者
出版年
2024年12月
出版者
桜井市纏向学研究センター
価 格
1,700円(税込)
倭国破砕鏡儀礼と二、三の問題
……………小山田 宏一 ……… 1
弥生国家論への二、三の補足
-水林彪氏の論評への答論として- ………… 寺沢 薫 ……… 27
吉備池廃寺と百済大寺
-比定説の新たな検証- ……………………渡里 恒信 ……… 61
植生・環境の変遷からみた纒向遺跡の遷移と画期
…………………… 金原 正明・金原 正子・西村 奏 ……… 71
山田寺跡出土礎石の三次元計測調査報告
-各所に運ばれた礎石-
……………
大脇 潔・廣瀬 覚・丹羽 惠次・藤村 裕美 … 89
【2025年2月17日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82564
書 名
高麗陶器の考古学
シリーズ
データ
A5 250頁 (上製本)
ISBN/ISSN
978-4886219978
編著者
主税 英德著
出版年
2025年2月
出版者
同成社
価 格
6,600円(税込)
高麗陶器はどのように生産、使用されたのか。器種分類、窯構造、
用途など多様な視点から考古学的に分析し、高麗陶器の全体像に
迫る。
【目次】
第1節 韓国における高麗陶器研究の現状と課題
第2節 日本における高麗陶器研究の現状と課題
第3節 問題の所在と本書の目的
第4節 資料・方法・用語の整理
第1節 本章の課題
第2節 器種分類
第3節 大型壺の分類と編年
第4節 盤口形口縁をもつ器種と編年
第5節 器種構成の変遷
第6節 小結
第1節 本章の課題
第2節 楊広道地域における窯構造の変遷
第3節 慶尚道・全羅道地域における窯構造
第4節 特定器種の生産に特化した窯の出現
第5節 小結
第1節 本章の課題
第2節 大型壺の消費に関する検討
第3節 大型壺の消費様相
第4節 時期別の分布からみる大型壺の消費様相と窯跡との関係
第5節 小結
第1節 課題、資料と方法
第2節 九州・琉球列島出土の高麗陶器
第3節 九州・琉球列島への流入背景
第4節 小結
第1節 生産の時間的変遷
第2節 消費の時間的変遷
第3節 生産と消費からみた画期とその背景
【2025年2月17日 【入荷】【ご注文承り中】
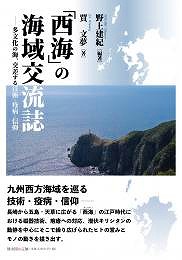
書籍番号
82574
書 名
「西海」の海域交流誌-多文化の海、交差する技術・疾病・信仰-
シリーズ
データ
A5 270頁(精装)
ISBN/ISSN
978-4-639-02025-6
編著者
野上 建紀 賈 文夢編著
出版年
2025年2月
出版者
文物出版社
価 格
4,180円(税込)
長崎から五島・天草に広がる「西海」の江戸時代における磁器技術、
疱瘡への対応、潜伏キリシタンの動静を中心にそこで繰り広げられ
たヒトの営みとモノの動きを描き出す。
【目次】
第1章 海を越えた技術―磁器の技―
第1節 大陸から伝わる磁器生産技術
第2節 窯場の整理統合と陶工追放
第3節 原料産地の殖産興業
第4節 海を渡る陶石
第5節 島と島の交流―五島焼―
第1節 天然痘と「無痘地」
第2節 疱瘡死者が眠る墓
第3節 疱瘡患者と死者のための器
第4節 「無痘地」における疱瘡禍
第5節 隔離と差別
第1節 海を渡る人々
第2節 五島はやさしや土地までも
第3節 再移住する人々
第4節 キリシタン弾圧と人の移動
第5節 墓からみたキリシタンの移住
第6節 移住の変化
第1節 外界からの技術
第2節 水際としての防疫
第3節 周縁に潜む信仰
第4節 技術、疫病、信仰をめぐる人々
【2025年2月13日 【入荷】【ご注文承り中】
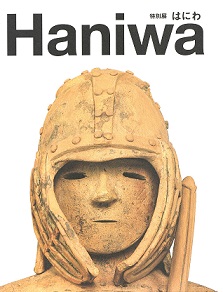
書籍番号
82572
書 名
特別展 はにわ
シリーズ
(挂甲の武人 国宝指定50周年記念 九州国立博物館開館20周年記念)
データ
A4変型 295頁
ISBN/ISSN
編著者
九州国立博物館等編集
出版年
2024年10月
出版者
NHK
価 格
4,400円(税込)
日本列島で独自に出現、発達した埴輪は、服や顔、しぐさなどを
簡略化し、丸みをもつといった特徴があり、世界的にも珍しい
造形として知られています。ここでは東京国立博物館の代表的な
所蔵品のひとつである「埴輪 踊る人々」を紹介します。
この埴輪は、東京国立博物館が創立150周年を機に、文化財活用
センターとクラウドファンディングなどで寄附をつのり、2022年
10月から解体修理を行いました。2024年3月末に修理が完了し、
本展が修理後初のお披露目となります。
<出品目録は以下のYRLよりご覧いただけます>
https://www.chugoku-shoten.com/mokuji/jmokuji/8257201/8257201.pdf
品が出土します。副葬品は、王の役割の変化と連動するように、
移り変わります。古墳時代前期(3~4世紀)の王は司祭者的な役
割であったので、宝器を所有し、中期(5世紀)の王は武人的な役
割のため、武器・武具を所有しました。後期(6世紀)は官僚的な
役割を持つ王に、金色に輝く馬具や装飾付大刀が大王から配布さ
れました。このほか各時期において、中国大陸や朝鮮半島と関係
を示す国際色豊かな副葬品も出土します。ここでは国宝のみで古
墳時代を概説し、埴輪が作られた時代と背景を振り返ります。
や量、技術で他を圧倒しています。天皇の系譜に連なる大王の古
墳は、時期によって築造場所が変わります。古墳時代前期は奈良
盆地に築造され、中期に入ると大阪平野で作られるようになりま
す。倭の五王の陵みささぎとしても名高い、大阪府の百舌鳥もず
・古市ふるいち古墳群は世界文化遺産に登録されています。
そして後期には、継体けいたい大王の陵とされる今城塚いましろ
づか古墳が淀川流域に築造されます。本章では、古墳時代のトッ
プ水準でつくられた埴輪を、その出現から消滅にかけて時期別に
見ることで、埴輪の変遷をたどります。
幅広い地域で、埴輪は作られました。それらの埴輪は、当時の地
域ごとの習俗の差、技術者の習熟度、また大王との関係性の強弱
によって、表現方法に違いが生まれています。その結果、各地域
には大王墓の埴輪と遜色ない精巧な埴輪が作られる一方で、地域
色あふれる個性的な埴輪も作られました。ここでは各地域の高い
水準で作られた埴輪や、独特な造形の埴輪を紹介します。
工房で作成された可能性も指摘されるほど、兄弟のようによく似
た埴輪が4体あります。そのうちの1体は、現在アメリカのシアト
ル美術館が所蔵しており、日本で見られる機会は限られています。
今回、5体の挂甲の武人を史上初めて一堂に集め、展示します。
なお、国宝「埴輪 挂甲の武人」は近年修理と調査研究を行い、
『修理調査報告 国宝 埴輪 挂甲の武人』(2024年、東京国立博
物館発行)として報告書を刊行しました。ここではその最
新の研究成果も紹介します。
べき何かしらの物語を表現します。ここではその埴輪群像を場面
ごとに紹介します。例えば、古墳のガードマンである盾持人たて
もちびと、古墳から邪気を払う相撲の力士など、多様な人物の役
割分担を示します。また、魂のよりどころとなる神聖な家形埴輪
は、古墳の中心施設に置かれ、複数組み合わせることで王の居館
を再現したのではないかと考えられます。このほか動物埴輪も、
種類ごとに役割が異なります。この章の動物埴輪は、従来にない
ダイナミックな見せ方で展示します
ると考古遺物への関心が高まり、埴輪がふたたび注目を浴びるよ
うになります。著名人が愛蔵した埴輪、著名な版画家の斎藤清が
描いた埴輪、埴輪の総選挙(群馬HANI-1グランプリ)でNo.1に
なった埴輪など、芸術家や一般市民など幅広い層で埴輪が愛され
ています。ここでは近世以降、現代にいたるまで埴輪がどのよう
に捉えられてきたかについて紹介し
ます。
【2025年2月13日 【品切】
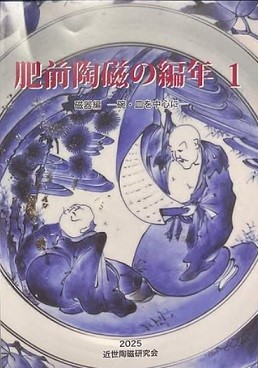
書籍番号
82573
書 名
肥前陶磁の編年 1 磁器編-碗・皿を中心に-
シリーズ
(第13回近世陶磁研究会 資料集)
データ
A4 頁
ISBN/ISSN
編著者
近世陶磁研究会
出版年
2025年2月
出版者
近世陶磁研究会
価 格
(税込)
の編年』をまとめ刊行しました。九州の陶磁器窯跡資料を中心に、編年
作業を行ったものでした。以来、20年以上経過し、新たにそのような窯
跡の編年成果を求められ、現在、できうる窯跡の成果をまとめることと
しました。今回は、九州陶磁の核となる肥前陶磁のうち、磁器の碗皿に
絞って、編年作業を行ないました。そして、前回は編年ができていなか
った鍋島を新たに加えることとしました。また、これらに関わる消費
地遺跡の年代が判る出土例も提示します。大会では、併せて、肥前陶磁
の良好な出土例として、秋田県久保田城跡についてと、肥前陶磁にも関
わるマジョリカ陶器について学ぶ場とします。(大会案内より)
肥前陶磁概論(陶器中心に)…………………………………大橋 康二
1
肥前 碗(色絵以外)…………… 野上 建紀・伊達 惇一朗・賈
文夢 5
肥前・有 皿(色絵以外)
…………………………………村上 伸之 35
鍋島 ………………………………
鮎川 和樹・長沼 茜里・船井 向洋 115
消費地遺跡の年代が判る資料-関西の被災資料を中心に-
………………… 赤松 和佳・小山 泰生・山本 文子・加藤 雄太 155
消費地遺跡の年代が判る資料-江戸の武家地を中心に-
………………………………………………………………髙島 裕之 199
【2025年2月5日 【入荷】【ご注文承り中】
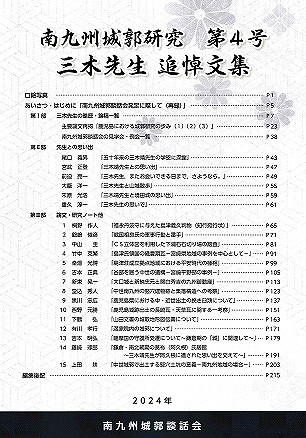
書籍番号
82569
書 名
南九州城郭研究 第4号 三木先生追悼文集
シリーズ
データ
A4 215頁
ISBN/ISSN
編著者
南九州城郭研究編集
出版年
2024年12月
出版者
南九州城郭研究
価 格
2,500円(税込)
あいさつ・はじめに 「南九州城郭談話会発足に際して (再録)」
…………………… P5
第I部 三木先生の略歴・論稿一覧 ……………………… P7
主要論文再掲
「鹿児島における城郭研究の歩み (1)
(2)
(3)」 …………………………………………… P23
南九州城郭談話会の見学会・例会一覧 ……………… P38
第Ⅱ部 先生との思い出
尾口 義男
「五十年来の三木靖先生の学恩に深謝」
………………………… P43
宮武 正登
「三木靖先生との思い出」 ……………… P47
前迫 亮一
「三木先生, またお会いできる日まで, さよう
なら。」
…………………………………………… P49
大籠 洋一
「三木先生と山城散歩」 ………………… P55
末原 光浩
「三木靖先生と境田城の思い出」 ……… P59
重久 淳一
「三木先生の思いで」 …………………… P61
第Ⅲ部 論文・研究ノート他
1 桐野 作人
「福永丹波守に与えた島津義久判物 (知行宛
行状)」
………………………………… P65
2 鶴嶋 俊彦
「戦国相良氏の軍事行動と番手」……… P71
3 中山
圭 「CS立体図を利用した下浦石石切り場の踏査」
…………………
P81
4 竹中 克繁
「島津氏領国の織豊期瓦
-宮崎県地域の事例を中心として-」…P91
5 菜畑 光博
「島津荘成立拠点地域における平安時代の
様相」
………………………………… P99
6 吉本 正典
「谷部を囲う中世の遺構
-宮崎平野部の事例-」 ………
P105
7 新東 晃一
「大口城と新納忠元と関白秀吉の九州御動座」
…………………… P113
8 堂込 秀人
「中世南九州の竪穴建物跡と集落構造への
考察」
……………………………… P123
9 黑川 忠広
「鹿児島県における中近世出土の挽き臼類に
ついて」
…………………………… P137
10
西野 元勝 「鹿児島城跡出土の長崎瓦天草瓦に関する
一考察」 …………………………… P151
11 下鶴 弘
「山田文書の城取地形図伝書について」
………………… P163
12 有川
孝行 「満家院内の城郭について」………… P171
13 吉本 明弘
「薩摩国の守護所変遷について
~鎌倉期の「城」に関連して~」… P179
14 藤崎 琢郎 「鎌倉 南北朝期の莫祢
(阿久根) 氏居館
~三木靖先生が阿久根に遺された思い出
を交えて~」 ……………… P191
15 上田 耕
「中世城郭で出土する竪穴土坑の意義
-南九州地域の場合-」 ………… P203
編集後記 …………………………………………………
P215
【2025年1月30日 【入荷】【ご注文承り中】
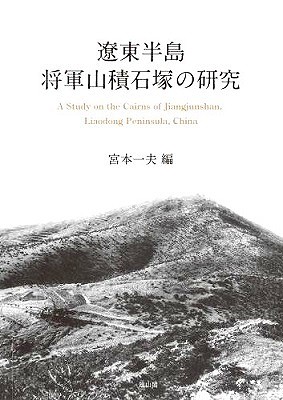
書籍番号
82548
書 名
遼東半島将軍山積石塚の研究
シリーズ
データ
B5 232頁(上製本)
ISBN/ISSN
978-4-639-03028-7
編著者
宮本 一夫編
出版年
2025年1月
出版者
雄山閣出版
価 格
13,200円(税込)
遼東半島の先史社会を明らかにする。
京都帝国大学考古学研究室が戦前に行った遼東半島先史遺跡の発掘
についての研究報告書『文家屯』、『遼東半島四平山積石塚の研究』
、『遼東半島上馬石貝塚の研究』につづく最終巻。
目次
序 ……………………………………………………………吉井秀夫 ⅰ
第1章 調査の経過と周辺の遺跡 ………………………宮本一夫
1
1.発掘調査の経過 1
2.将軍山積石塚調査日誌 5
3.整理調査の経過 9
4.遼東半島先史時代の遺跡 11
1.将軍山積石塚と老鉄山積石塚の位置 13
2.将軍山積石塚の配置 16
3.将軍山積石塚の石室 17
4.老鉄山積石塚 38
5.将軍山山頂部 39
1.土器の名称 41
2.将軍山積石塚出土土器黒陶 42
3.将軍山積石塚出土褐陶 44
4.将軍山山頂出土土器 53
1.はじめに 61
2.将軍山Ⅳ・Ⅴ号積石塚出土石器 61
3.将軍山山頂窯址出土石器 64
4.将軍山山頂出土石器 65
5.将軍山遺跡出土石器の時期的位置づけ 66
1.はじめに 71
2.青銅鏃 74
3.貨 幣 75
4.石 器 76
5.小 結 76
…………………………小畑弘己・村上由美子・永益英敏 77
1.調査概要 77
2.調査の手順 77
3.調査結果 84
4.考 察 85
5.まとめ 87
1.はじめに 115
2.四平山積石塚・将軍山積石塚の編年的な位置づけ 117
3.遼東半島の積石塚の変遷 131
4.おわりに 139
1.遼東半島の先史土器編年 143
2.遼東半島先史土器編年上の将軍山積石塚調査の意義 148
3.遼東半島先史遺跡調査からみた遼東半島先史社会 149
おわりに 209
要 旨 211
中文抄訳 214
英文抄訳 216
【2025年1月30日 【入荷】【ご注文承り中】
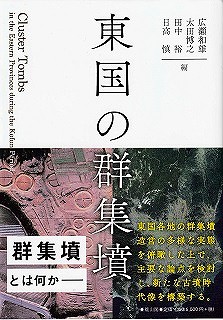
書籍番号
82549
書 名
東国の群集墳
シリーズ
データ
A5 236頁(上製本)
ISBN/ISSN
978-4-639-03022-5
編著者
広瀬和雄・太田博之・田中 裕・日高
慎編
出版年
2025年1月
出版者
雄山閣出版
価 格
6,600円(税込)
東国各地の群集墳造営の多様な実態を俯瞰した上で、主要な論点を
検討し、新たな古墳時代像を構築する。
第1章 群集墳研究の現在と課題
群集墳の形成と展開
―古墳時代における中間層の政治的創出―(広瀬和雄)
群集墳論研究史(日高 慎)
「多数高密度型」群集墳の成立とその意義(田中 裕)
茨城(田中 裕)
栃木(賀来孝代・足立佳代)
群馬(加部二生)
埼玉(太田博之)
千葉(小沢 洋)
東京(紺野英二)
神奈川(柏木善治)
東国における群集墳造営の諸画期(太田博之)
東国の群集墳・横穴墓群分布図
初期群集墳の形成過程と群構成(小森哲也)
群集墳の群構成(池上 悟)
飯塚・藤井古墳群にみる首長墓と群集墳(秋元陽光)
群馬県における首長墓と群集墳(加部二生)
群集墳の被葬者層―東京・神奈川―(柏木善治)
群集墳の変質と被葬者像
―南武蔵を中心として―(松崎元樹)
関東西部地域における中期群集墳の被葬者(太田博之)
【2025年1月30日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82566
書 名
古墳出現期土器研究 第11号
シリーズ
データ
A4 93頁
ISBN/ISSN
編著者
古墳出現期土器研究会編集
出版年
2024年12月
出版者
古墳出現期土器研究会
価 格
1,100円(税込)
庄内式と布留式の境目のこと………………………米田 敏幸 1
<論文>
畿内地域における布留形甕の出現…………………田中 元浩 3
甕形土器の構成と遺跡間変異………………………杉山 拓己 35
一布留形甕成立期の奈良盆地東南部を中心として一
庄内式期IVの認識整理と今後の課題(後編)………米田 敏幸 39
<資料紹介>
平尾城山古墳出土土器についての整理……………式田 洸 51
<コラム>
土器と銅鏡……………………………………………森岡 秀人 55
一縺れ合い、
鬩ぎ合いのお話一
<例会報告>
古墳出現期土器研究会の記録
(9)…………………市村慎太郎 75
【2025年1月30日 【入荷】【ご注文承り中】
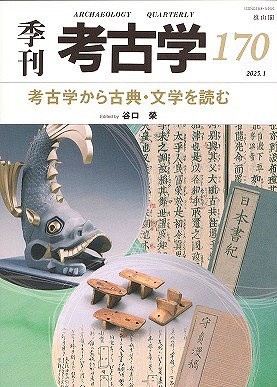
書籍番号
82565
書 名
季刊 考古学 第170号 特集 考古学から古典・文学を読む
シリーズ
データ
B5 130頁
ISBN/ISSN
978-4-639-02841-3
編著者
桑門智亜紀編集
出版年
2025年1月
出版者
雄山閣出版
価 格
2,640円(税込)
インタビュー:古典・文学考古学事始め
―坂詰秀一先生と古典考古学―(坂詰秀一 聞き手:谷口 榮)
記・紀と考古学―崇神天皇の将軍派遣伝承を中心として―(森田喜久男)
大宰府と古代松浦郡―考古学から『万葉集』を読み解く―(菅波正人)
『日本霊異記』の三谷寺と寺町廃寺(松下正司)
『出雲国風土記』の前原坡と水鳥
―前原埼の歴史風景を探る―(谷口 榮)
『吾妻鏡』の記事と遺跡からの「事実」
―古典と考古学が示す二つの「真実」―(馬淵和雄)
『庭訓往来』と中世社会(伊藤宏之)
『信長公記』と安土城天主の唐様(谷口 榮)
琉球王朝とグスク
―考古学的視点から『おもろさうし』を読む―(宮城弘樹)
江戸の暮らしと食―考古学と文献から―(古泉 弘)
近世文芸と考古学(古泉 弘)
『新編武蔵風土記稿』にみる中世の城跡と屋敷跡(深澤靖幸)
古典を考古学する(『別冊季刊考古学』4,1993より再録)(坂詰秀一)
縄文時代中期の表裏型顔面把手の発見
―神奈川県座間市蟹ケ澤遺跡―(佐柄雄斗)
縄文時代後期後葉~晩期中葉にかけての拠点集落跡
―福島県南相馬市天神谷地遺跡―(神林幸太朗)
世界遺産初登録から30年,国際条約と国内の文化財保護制度の邂逅は
何をもたらしたか(中村俊介)
発掘調査と考古学の国際化(宮本一夫)
連載・現状レポート
これからの博物館と考古学-博物館法改正を受けて- 第1回
巻頭言(水ノ江和同)/八戸市博物館と考古学(市川健夫)/綿貫観
音山古墳と共に歩みつづける群馬県立歴史博物館(深澤敦仁)
【2025年1月30日 【入荷】【ご注文承り中】
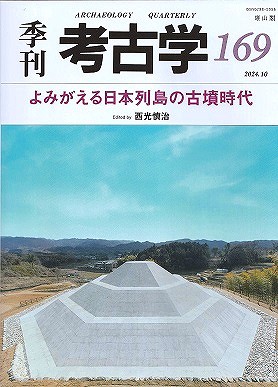
書籍番号
82567
書 名
季刊 考古学 第169号 特集 よみがえる日本列島の古墳時代
シリーズ
データ
B5 133頁
ISBN/ISSN
978-4-639-02999-1
編著者
中国航誨博物館編著
出版年
2024年11月
出版者
雄山閣出版
価 格
2,640円(税込)
―整備の方向性―(小野友記子)
「整備遺産」としての保存と活用(西光慎治)
妙見山 1 号墳(小野隼弥)
森将軍塚古墳(小野紀男)
雨の宮古墳群(福永 徹)
柳井茶臼山古墳(大岡弘明)
大安場古墳群(荒木麻衣)
五色塚古墳・小壺古墳(橋詰清孝)
昼飯大塚古墳(中井正幸)
心合寺山古墳(藤井淳弘)
宝塚 1
号墳(村田 匡)
兜山古墳(深川義之)
千足古墳(西田和浩)
私市円山古墳(廣富亮太)
保渡田古墳群(関屋夕紀子)
ガランドヤ古墳(渡邉隆行)
賤機山古墳(毛利舞香)
二子塚古墳(内田 実)
武蔵府中熊野神社古墳(廣瀬真理子)
牽牛子塚古墳(西光慎治)
【コラム】来訪者視点からの古墳整備(辰巳俊輔)
地盤工学からみた古墳の構造特性とリスク(三村 衛)
土の力学的視点を取り入れた遺構の維持管理(澤田茉伊)
古代の技術者も地質リスクを考慮したか?(北田奈緒子・井上直人)
遺跡整備にみる水・塩対策(脇谷草一郎)
中国大陸における盛土構造物の整備
―魏晋南北朝時代の中国陵墓の調査と公開―(村元健一)
朝鮮半島における盛土構造物の整備(井上主税)
縄文時代中期の石棒祭祀跡と弥生時代前期集落
―愛知県設楽町根道外遺跡―(川添和暁)
学術的泥炭層調査の先駆け
―埼玉県さいたま市真福寺貝塚―(吉岡卓真)
瀬田遺跡SZ4500と奈良盆地の社会(山本 亮)
歩み,来た道(難波洋三)
【2025年1月14日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82550
書 名
文化財写真研究 VOL.14
シリーズ
データ
A4 126頁
ISBN/ISSN
編著者
文化財写真技術研究会編集
出版年
2024年9月
出版者
文化財写真技術研究会
価 格
4,900円(税込)
CONTENTS
───────────────────────────
Foreword
雑誌カメラマンの眼をちょっと文化財撮影に 小川忠博 02
───────────────────────────
記念講演
考古学・人類学研究における絵葉書の活用
一多様なメディアとしての考古学絵葉書ー 平田 健 06
───────────────────────────
デジタルシフトの光と陰~ソフト側から~
デジタルシフトの光と陰 (趣旨説明) 栗山雅夫 18
褪色カラー写真のデジタイズ復元
奥山敏康 20
ブック印刷の要素技術開発について
めぐって
川口武彦 32
一ソフトウェアを用いたノイズ低減処理を中心に一
文化財建造物のデジタル撮影
大澤 正 48
ひかり拓本による碑文の可視化
上椙英之 54
合成写真による課題解決
戸部秀樹 58
一焦点合成と無反射撮影による3D写真計測一
───────────────────────────
光 (テカ)
り物の撮影
中村一郎 62
───────────────────────────
基礎講座
───────────────────────────
遺跡の撮影 その6
一瓦窯 (の発掘調査) を撮る一 栗山雅夫・道上祥武 82
───────────────────────────
Photo 会長の眼
Essay
レンズの歪みとデジタル修正
井上直夫 74
───────────────────────────
能登半島地震における富山県高岡市の
史跡の被害状況について
田上和彦 78
LETTER
───────────────────────────
BOX
第13回文化財写真技術研究会参加記
庄子善昭 80
───────────────────────────
文化財写真技術ミニ講習会inあきた
加藤 竜120
───────────────────────────
SUPER
SHOT
石棒クラブ活動と文化財写真 三好清超・田邊朋宏100
───────────────────────────
シリーズ
発掘調査報告書 私の工夫
New 行政文書として適切であること、
Horizon 学術的な記録として的確であること、
理解しやすいこと
中山愉希江106
───────────────────────────
Gallery
FOOTWORK
112
───────────────────────────
【2024年12月28日 【入荷】【ご注文承り中】
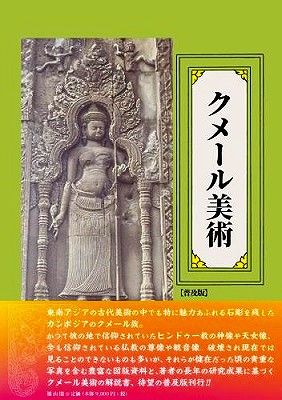
書籍番号
82535
書 名
クメール美術【普及版】
シリーズ
データ
B5 225頁 (上製本)
ISBN/ISSN
978-4-639-03015-7
編著者
伊東照司著
出版年
2024年12月
出版者
雄山閣出版
価 格
9,900円(税込)
特に魅力あふれる石彫を残した。アンコールワットに代表さ
れる寺院建築に残されたヒンドゥー教の神像や天女像、仏教
の尊像や観音像。カンボジア内戦によって失われた文化財を
含む、貴重な図版資料も多数集録。
序…………………………………………………… 1
総論………………………………………………… 5
第一章 女神像崇拝の美術
……………………………… 9
第二章 アンコールの踊り子たち ………………………
21
第三章 プノンペン博物館の名品
……………………… 63
第四章 仰望 プレア・ヴィヘア ……………………… 117
第五章 バイヨンの尊顔 ………………………………… 163
第六章 七世大王の観音 ………………………………… 189
第七章 クメール美術の衰退 …………………………… 209
結 論 …………………………………………… 215
参考文献…………………………………………… 219
尊王系譜…………………………………………… 220
跋…………………………………………………… 223
【2024年12月28日 【入荷】【ご注文承り中】
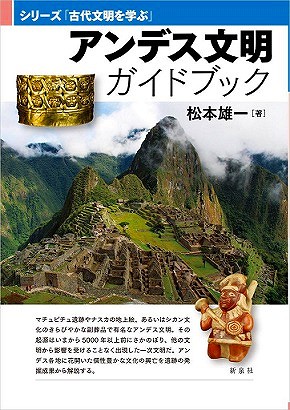
書籍番号
82520
書 名
アンデス文明ガイドブック
シリーズ
(シリーズ「古代文明を学ぶ」)
データ
A5 96頁
ISBN/ISSN
978-4-7877-2411-3
編著者
松本 雄一著
出版年
2025年1月
出版者
新泉社
価 格
1,980円(税込)
かな副葬品で有名なアンデス文明。その起源はいまから5000年以上前
にさかのぼり、他の文明から影響を受けることなく出現した一次文明
だ。アンデス各地に花開いた個性豊かな文化の興亡を遺跡の発掘成果
から解説する。
02 アンデスという環境
03 アンデス文明の展開と時代区分
04 先土器時代の神殿
05 神殿を造りつづけた人々
06 チャビン・デ・ワンタル遺跡
07 北高地の巨大神殿、クントゥル・ワシとパコパンパ
08 神殿を造ることで社会が変わる
09 モチェ:アンデス最初の国家
10 ナスカ:地上絵を造った人々
11 ワリ:インカに先立つ帝国
12 宗教都市ティワナク
13 シカン:北海岸の黄金文化
14 チムー王国の首都チャン・チャン
15 インカ帝国の実態1:文書資料と考古学
16 インカ帝国の実態2:政治経済システム
17 インカ帝国の実態3:地方支配と帝国の終焉
18 マチュピチュはどのような遺跡なのか
19 文字なき社会の情報メディア
20 日本のアンデス研究1:その歴史と現状
21 日本のアンデス研究2:考古学者と現地社会
アンデス文明を知るためのペルーの博物館
【2024年12月26日 【入荷】【ご注文承り中】
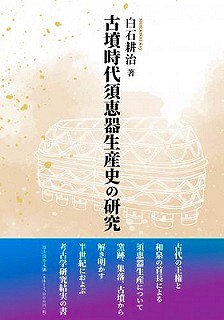
書籍番号
82534
書 名
古墳時代須恵器生産史の研究
シリーズ
データ
A5 460頁 (上製本)
ISBN/ISSN
978-639-03024-9
編著者
白石耕治著
出版年
2024年12月
出版者
雄山閣出版
価 格
13,200円(税込)
古墳から解き明かす半世紀におよぶ考古学研究結実の一書、
ついに刊行。
あたって
第一節 須恵器窯構造の地域性
第二節 須恵器生産の変革期
特論一 須恵器蓋坏の製作技法の着眼点
第三節 須恵器編年の試行
第四節 須恵器編年 ―六、七世紀の谷山池地区を例として―
第五節 斑鳩藤ノ木古墳の須恵器
第一節 首長居館―府中・豊中遺跡群―
特論二 府中・豊中遺跡群の「御船代」
第二節 地域開発の拠点集落―大園遺跡―
第三節 泉北丘陵の集落遺跡
第四節 槇尾川流域の首長居宅―万町北遺跡―
第一節 和泉北部の前・中期古墳の展開
第二節 群集墳とその被葬者
第三節 土師質陶棺と被葬者の系譜
特論三 蔵骨器様の有蓋鉢の系譜について
第一節 泉北丘陵窯跡群の地域論
第二節 中・後期の首長系譜の整理
第三節 地域開発と古代氏族
【2024年12月25日 【28日入荷予定】【ご注文承り中】

書籍番号
82539
書 名
古代集落の構造と変遷 4
シリーズ
(第27回 古代官衙・集落研究会報告書)(奈良文化財
研究所研究報告第43冊)
データ
A4 146頁
ISBN/ISSN
978-4-87805-176-0
編著者
中国航誨博物館編著
出版年
2024年12月
出版者
株式会社 クバプロ
価 格
3,630円(税込)
集落研究会の報告書。
目 次
序 ………………………………………………………………… 3
目次 ……………………………………………………………… 5
例言 ……………………………………………………………… 6
開催趣旨 ………………………………………………………… 7
プログラム ……………………………………………………… 8
古代集落における「建物群」の把握に関する試算
…………………
清野 陽一・道上 祥武 11
奈良・平安時代の竪穴建物の使用人数
ー志波城周辺集落をモデルケースにしてー 松島 隆介 25
柳瀬川流域における集落の構造と変遷
ー柳瀬川中流域の古代遺跡を中心としてー 中野 光将 39
美濃国加茂・武儀郡における古代集落の構造と変遷
……………… 島田 崇正 85
【2024年12月24日 【入荷】【ご注文承り中】
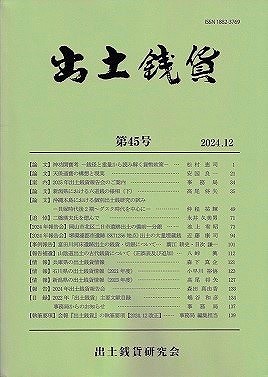
書籍番号
82536
書 名
出土銭貨 第45号
シリーズ
データ
B5 140頁
ISBN/ISSN
1882-3769
編著者
出土銭貨研究会編集
出版年
2024年12月
出版者
出土銭貨研究会
価 格
2,750円(税込)
………………… 松村
恵司 1
【論文】天保通寳の構想と現実 ……… 安国
良一 21
【案内】2025年出土銭貨報告会のご案内
………………………… 事 務 局 34
【論文】新潟県における六道銭の様相 (下)
……………………… 高尾 将矢 35
【論文】沖縄本島における個別出土銭研究の試み
一貝塚時代後2期~グスク時代を中心に一
…………… 仲程 祐輝 49
【追悼】二橋瑛夫氏を偲んで …………
永井久美男 71
【2024年報告会】岡山市北区二日市遺跡出土の備前一分銀
…………………… 池上 宥昭 73
【2024年報告会】堺環濠都市遺跡
(SKT1256 地点) 出土の
大量埋蔵銭
近藤 康司 94
【事例報告】富田川河床遺跡出土の銭貨・切銀について
…………………廣江 耕史・目次 謙一 101
【報告補遺】山陰道出土の古代銭貨について
(正誤表及び追加) …… 八峠 興 112
【情報】兵庫県の出土銭貨情報 ……… 森下
真企 121
【情報】石川県の出土銭貨情報 (2021年度)
……………………… 小早川裕悟 123
【情報】新潟県の出土銭貨情報 (2023年度)
……………………… 高尾 将矢 127
【報告】2024年出土銭貨報告会 …………森田真由香 133
【目録】2022年「出土銭貨」 主要文献目録
……………………… 嶋谷 和彦 134
事務局からのお知らせ …… 事 務 局 137
【執筆要項】会報『出土銭貨』の執筆要項【2024.12改正】
事務局 編集担当 139
【2024年12月23日 【入荷】【ご注文承り中】
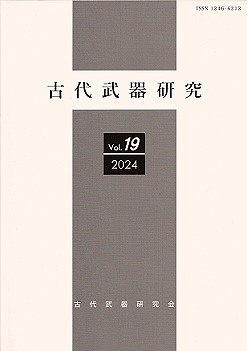
書籍番号
82537
書 名
古代武器研究 Vol.19
シリーズ
データ
A4 114頁
ISBN/ISSN
1346-6313
編著者
出版年
2024年12月
出版者
古代武器研究会
価 格
2,200円(税込)
塚本
敏夫 古代武器研究会代表幹事 …… 2
戦国・漢代併行期の北・東アジアにおける鉄器生産システ
ムの枠組み 村上 恭通 愛媛大学
…………………… 5
出土品に遺る有機質痕跡を追う
奥山 誠義 奈良県立橿原考古学研究所 … 11
古墳時代の武器・武具類を対象とした近年の保存科学的調
査成果についてー北部九州の事例を中心として一
比佐陽一郎 奈良大学 …………………… 15
武器・武具・馬具の復元模造品製作の実践とその意義
塚本 敏夫 元興寺文化財研究所 ………… 27
弥生時代後半期に生じる武器の材質転換と系譜関係
園原 悠斗 兵庫県教育委員会 …………… 43
武器形青銅器造形における鋳造と研磨
吉田 広 愛媛大学ミュージアム ………… 59
【事例報告】
二つの広形銅戈鋳型ー福岡市高畑遺跡23次調査出土資料ー
吉武 学・常松幹雄 福岡市文化財活用部
……………… 75
富雄丸山古墳出土蛇行剣および[單/黽-十]龍文盾形銅鏡
村瀬 陸 奈良市教育委員会文化財課埋蔵文化
財調査センター
…………………………… 83
特別史跡熊本城跡千葉城地区出土の紀年銘象嵌鉄刀
三好栄太郎・林田和人
熊本市熊本城調査研究
センター/熊本市文化財課
……………… 91
【総合討議】…………………………………………………… 99
コーディネーター 塚本敏夫、 寺前直人
発言者 常松幹雄、比佐陽一郎、吉田
広、奥山誠義、
村上恭通、橋本達也、徳富孔一、三好栄太郎、
豊島直博、水野敏典、園原悠斗、ライアン・
ジョセフ、鈴木崇司、田中晋作
【2024年12月23日 【入荷】【ご注文承り中】
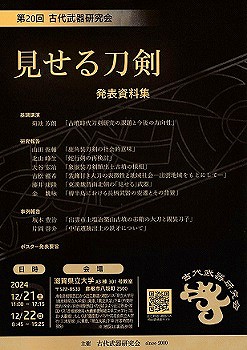
書籍番号
82538
書 名
第20回 古代武器研究会 発表資料集
シリーズ
(見せる刀剣)
データ
A4 82頁
ISBN/ISSN
編著者
古代武器研究会編集
出版年
2024年12月
出版者
古代武器研究会
価 格
1,700円(税込)
第20回「古代武器研究会」 開催にあたって………………ⅰ
日程 ……………………………………………………………ⅱ
【基調講演】
菊池 芳朗(福島大学行政政策学類)
「古墳時代刀剣研究の課題と今後の方向性」……1
【研究報告】
山田 俊輔 (千葉大学大学院人文科学研究院)
「鹿角装刀剣の社会的意義」………………………5
北山 峰生(奈良県立橿原考古学研究所)
「蛇行剣の再検討」
…………………………………11
大谷
宏治(静岡県スポーツ・文化観光部文化局文化財課)
「象嵌装刀剣類出土古墳の様相」
…………………17
吉松 優希
(島根県古代文化センター)
「装飾付大刀の表徴性と地域社会一出雲地域をもとに
して一」
……………………………………………33
藤井
康隆(佐賀大学芸術地域デザイン学部)
「東漢魏晋南北朝の「見せる」武器」 ……………41
金 跳咏 (慶北大学校考古人類学科)
「韓半島における長柄武器の変遷とその背景」 …43
【事例報告 】
坂本 豊治(出雲弥生の森博物館)
「出雲市上塩冶築山古墳の赤鞘の大刀と錫装刀子」
…………………………67
片岡 啓介
(倉吉市)
「中尾遺跡出土の鉄矛について」…………………73
【ポスター発表要旨】
春日 勇人 (考古学研究会会員)
「武器形青銅器の伝来と弥生時代前半期の人口動態
の関係性」…………………………………………79
橋本 達也(鹿児島大学総合研究博物館)
「木甲の製作技術一弥生時代後期前半・糸島市深江
石町遺跡出土例―」………………………………80
岡安 光彦
「倭兵は
「戦争の犬」 だったのか? 一軍事史学お
よびディアスポラ社会学からの考察」…………81
小嶋 篤(九州歴史資料館)
「戦場の歴史学一天慶四年、大宰府陥落―」……82
【2024年12月18日 【入荷】【ご注文承り中】
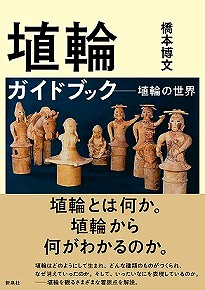
書籍番号
82518
書 名
埴輪ガイドブック 埴輪の世界
シリーズ
データ
A5 160頁
ISBN/ISSN
978-4-7877-2414-4
編著者
橋本 博文著
出版年
2025年1月
出版者
新泉社
価 格
2,750円(税込)
消えていったのか。そして、いったいなにを表現しているのか。
──埴輪を観るさまざまな着眼点を解説。
はじめに
埴輪の起源説話
埴輪の種類
水戸黄門さんと埴輪
家老が記録した埴輪
外国人の埴輪研究
埴輪群への注目
埴輪はどこで生まれたか
卑弥呼の墓?の埴輪
東国最古の埴輪を求めて
埴輪の編年
埴輪の地域性
最果ての埴輪
埴輪の終焉
朝鮮半島の埴輪
塚廻り古墳群で考えたこと
本物の大王墓の埴輪群
大きな古墳に大きな埴輪、小さな古墳に小さな埴輪
小さな古墳から大量の埴輪
埴輪のある古墳とない古墳
埴輪祭祀の復活?
楕円円筒埴輪と鰭付き円筒埴輪
底抜け壺の語ること
家形埴輪と豪族居館
堅魚木をあげた家形埴輪
犬と猪と狩人
埴輪の馬はなにを物語る
鶏形埴輪の性格
魚形埴輪の魚はなに?
全身像と半身像
ひざまずく埴輪はどういう人?
饗応する女性埴輪
装身具からみた男女差・職掌差
「黥面文身」とイレズミ
おしゃれだった古墳時代の男性
農夫も耳飾り
上げ美豆良と下げ美豆良
女性埴輪のヘアスタイル
女性埴輪の衣装
巫女埴輪の認定
大刀・弓を持つ女性埴輪
人物埴輪のかぶり物
五体の武人埴輪
武人埴輪は首長か
武人埴輪と靫負
盾持ち人埴輪の異形
鵜匠・鷹匠・猪飼い・馬飼い
渡来人をかたどった埴輪
埴輪窯のカミマツリ
同じ古墳に上手な埴輪と下手な埴輪
埴輪を科学する
中二子古墳の埴輪はどこから来たか
埴輪に残った製作者の指紋
ケンブリッジの女性埴輪
分離造形した埴輪
「木の埴輪」と「石の埴輪」
円筒棺と埴輪棺
渡来人がつくった埴輪
朝鮮半島の埴輪は誰がつくったのか
保存・整備・活用への提言
参考文献
【2024年12月11日 【再入荷】【ご注文承り中】
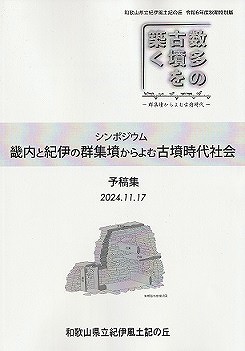
書籍番号
82487
書 名
シンポジウム「畿内と紀伊の群集墳からよむ古墳時代社会」(予稿集)
シリーズ
(数多の古墳を築く―群集墳からよむ古墳時代―(特別展)
データ
A4 52頁
ISBN/ISSN
編著者
和歌山県立紀伊風土記の丘編集
出版年
2024年11月
出版者
和歌山県立紀伊風土記の丘
価 格
600円(税込)
からよむ古墳時代―」シンポジウム「畿内と紀伊の群集墳からよむ古墳時代
社会」
予稿集
目次
群集墳と古墳時代社会
太田宏明……… 1
副葬品からみた群集墳の被葬者像一畿内地域を中心にー
絹畠 歩……… 17
群集墳と土器使用儀礼
仲辻慧大……… 30
紀伊地域における6・7世紀の群集墳の展開
萩野谷正宏……… 42
4
【2024年12月11日 【入荷待】【ご注文承り中】

書籍番号
82517
書 名
始原のヴィーナスー旧石器時代の女性象徴―
シリーズ
データ
B5 426頁
ISBN/ISSN
978-4886219893
編著者
春成 秀爾著
出版年
2024年11月
出版者
株式会社 同成社
価 格
16,500円(税込)
古代人の世界観に迫る。著者積年の研究テーマを集大成した渾身の
大著。
1章 上黒岩岩陰遺跡
2章 石偶と線刻棒
3章 タカラガイと三角形垂飾り
4章 上黒岩の女性象徴の意義
1章
女性象徴の研究課題
2章 後期旧石器時代前半の女性小像
3章 後期旧石器時代末の女性小像
4章 後期旧石器時代前半~中頃の女性絵画
5章 後期旧石器時代末の女性絵画
6章 後期旧石器時代の女性器象徴
7章 後期旧石器時代の男性象徴
8章 後期旧石器時代の線刻棒
集成 旧石器時代の動物象徴ほか
【2024年12月10日 【入荷】【ご注文承り中】
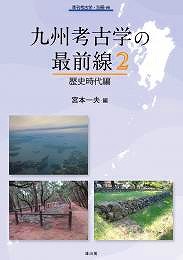
書籍番号
82500
書 名
季刊考古学・別冊46 九州考古学の最前線 2 歴史時代編
シリーズ
データ
B5 152頁
ISBN/ISSN
978-4639030034
編著者
宮本 一夫編
出版年
2024年11月
出版者
雄山閣出版
価 格
2,860円(税込)
九州考古学の現在2 ― 歴史時代―(宮本 一夫)
大宰府政庁と政庁周辺官衙(杉原 俊敏)
鴻臚館(菅波 正人)
阿恵官衙遺跡周辺の官衙関連遺跡について(西垣 彰博)
太宰府条坊(井上 信正)
対馬金田城(森
悠統)
大野城(宮地 聡一郎)
基肄城(中島 恒次郎)
大宰府外郭線(吉田
東明)
元岡・桑原遺跡群の製錬炉(長家 伸)
喜界島城久遺跡の調査成果と課題(島袋 未樹)
8~9世紀の水害遺跡(坂上 康俊)
島津荘成立拠点地域における平安時代の考古学的調査研究の現状
(桒畑 光博)
発掘調査からみた中世博多の変遷(田上勇一郎)
博多遺跡群出土の中世初頭港湾遺構(大庭 康時)
箱崎遺跡(中尾 祐太)
元寇防塁跡(福永
将大)
鷹島海底遺跡(池田 榮史)
竹松遺跡(川畑 敏則)
九州・南島出土の高麗陶器(主税 英徳)
九州の板碑(原田 昭一)
北部九州の山城(岡寺
良)
九州南部三国の中世城館跡(吉本 正典)
芦屋釜―中世の鋳造技術復元の取り組み―(新郷 英弘)
大友館(五十川 雄也)
九州のキリシタン墓(田中 裕介)
小倉城(佐藤
浩司)
中津城(浦井 直幸)
豊後府内城(木村 幾多郎)
杵築城跡(国史跡)(吉田 和彦)
近世柳川城下町遺跡の調査と課題(堤 伴治)
古高取内ヶ磯窯跡(岸本 圭)
近世城下町における鉄器生産
―久留米城下町遺跡第30次調査を中心に―(長谷川 桃子)
三重津海軍所跡(中野 充)
金山水車(轟精練所)跡(前迫 亮一)
三池炭鉱と関連施設(森井 啓次)
九州大学食器(谷 直子・田尻 義了)
海軍築城航空基地と稲童掩体(山口 裕)
【2024年12月10日 【入荷】【ご注文承り中】
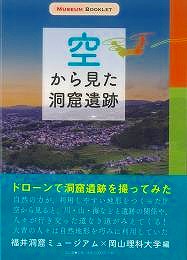
書籍番号
82499
書 名
空から見た洞窟遺跡
シリーズ
データ
A5 112頁
ISBN/ISSN
978-4639030096
編著者
福井洞窟ミュージアム×岡山理科大学編
出版年
2024年10月
出版者
雄山閣出版
価 格
2,200円(税込)
自然の力が、利用しやすい地形を作った?
空から見ると、川・山・海などと地形の関係や、人々が行き交った道
なき道がみえてくる!
大昔の人々は自然地形を巧みに利用していた。
空からみた西海の海と山(栁田裕三)
【Column】西海国立公園「九十九島」(蓮田 尚)
北部九州の洞窟遺跡(高橋央輝・栁田裕三)
【河川争奪と洞窟遺跡】福井洞窟(栁田裕三・伴 祐子)
【Column】「特別史跡」福井洞窟(栁田裕三)
【古写真が語る岩陰地形】直谷岩陰(栁田裕三・伴 祐子)
【Column】写真記録の考古学(石田成年)
【縄文人が行き交った洞窟遺跡】橋川内洞窟 (栁田裕三)
【洞窟祭祀のはじまり】岩谷口第1・第2岩陰(栁田裕三)
【川のほとりのキャンプサイト】石屋洞穴(松元一浩)
【埋葬と洞窟】岩下洞穴(栁田裕三)
【相浦川流域最上流の岩陰遺跡】大古川岩陰(中原彰久)
【Column】中四国の洞窟遺跡(伴 祐子)
【立地と環境から見える岩陰の暮らし】白蛇山岩陰遺跡(野田千輝)
【国境の峠に位置する洞窟遺跡】盗人岩陰(伊達惇一朗)
【棚田に囲まれた風光明媚な岩陰遺跡】百田岩陰遺跡(鮎川和樹)
【Column】対馬の遺跡立地と博物館(尾上博一)
【縄文時代の多様な埋葬方法】枌洞穴(衞藤美紀・丸山利枝)
【石灰岩層に形成された地形と遺跡】小半鍾乳洞と前高洞穴(福田 聡)
【Column】砂岩洞窟のなりたち(西山賢一)
空から見た奇岩地形(松尾秀昭)
【国指定名勝・平戸領地方八竒勝 奇跡のアーチ橋】眼鏡石と石橋
(中原彰久)
【国指定名勝・平戸領地方八竒勝 洞窟に残る信仰の世界】
巌屋宮と福石山 (鐘ケ江 樹)
【Column】水流と地形が織り成す景色(溝上隼弘)
【国指定名勝・耶馬渓〈競秀峰の景〉】青の洞門 (衞藤美紀)
第4章
空から見た洞窟遺跡(柳田裕三・德澤啓一)
【Column】2024年度企画展『空から見た洞窟遺跡』プレイベント
「洞窟遺跡の保存と活用を考える大学生モニターツアー」レポート
(德澤啓一)
【2024年12月10日 【入荷】【ご注文承り中】
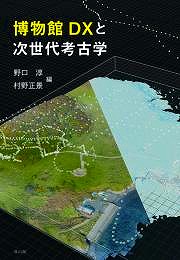
書籍番号
82501
書 名
博物館DXと次世代考古学
シリーズ
データ
A5 200頁
ISBN/ISSN
978-4639030003
編著者
野口 淳 村野 正景
出版年
2024年9月
出版者
雄山閣出版
価 格
2,640円(税込)
あり方や利用者の特別な体験をもたらす。
博物館DXの背景や考え方、世界的な動向や日本での取り組みの現状
がわかる初めての書! 多くの企業により新たな技術やサービスも
紹介!
1 博物館DX の理論と制度
まえがき 本書の趣旨(村野正景)
次世代考古学とは何か―小松大学次世代考古学研究センターとホン
ジュラスの博物館への協力(中村誠一)
博物館DXの課題と展望(中尾智行)
文化政策の転換と博物館の役割(朝倉由希)
次世代技術が変える未来の考古学・博物館(野口 淳)
ミュージアムDXと社会的課題―京都府京都文化博物館の実践と展望
(村野正景)
収蔵資料のデジタル化と仲間づくり―石棒クラブと飛騨みやがわ考
古民俗館の取組み(三好清超)
自然史系資料のデジタル公開と課題(佐久間大輔)
文化資源のデジタル化・公開手法の開発―立命館アート・リサーチ
センターの運用と展開(矢野桂司・赤間 亮)
博物館デジタルアーカイブとジャパンサーチでつくるエコシステム
(阿児雄之)
デジタルアーカイブで広がる寺社史料の可能性―菅公御神忌1125年半
萬燈祭に際する『北野文叢』のデータベース公開(西山 剛)
DX時代の資料・情報管理専門職とはどのような存在なのか(岡崎 敦)
Volumetric
Video―無形文化財のアーカイブとその活用(中川源洋)
赤外線カメラ【IRシステム】
―8,000万画素の高精細な赤外線画像(宮田正人)
点群データ活用ソフトInfiPoints―3D立体視ディスプレイがもたらす
新たな展示体験(中川大輔)
3DスキャンアプリScaniverse―AR体験へつながる3Dモデルの可能性
(白石淳二)
ニコンZ8・Z6Ⅲ・ZfによるピクセルシフトとHDR撮影―高解像度一辺倒
から+高演色・高質感描写への展開(片山 響・堀内保彦)
広域・景観フォトグラメトリ― ランドスケープの再現(嘉本 聡)
デジタルアーカイブシステムADEAC―デジタルアーカイブの構築のこれ
から(田山健二)
I.B.MUSEUM
SaaS
―博物館デジタルアーカイブのプラットフォーム(内田剛史)
ARタイムマシーン―博物館で体験する時空の旅(町田香織)
文化財建築3Dアーカイブ―フォトグラメトリとレーザースキャナの場合
(平山智
予・長坂匡幸)
みんキャプ―市民参加型の3Dデジタルアーカイブ活動(久田智之)
文化財BIMとXRプラットフォームSTYLY― 建築デジタルアーカイブのXR
活用(桑山優樹)
4 ディスカッション 博物館DXのいまとこれから
モデレーター 関 雄二/パネラー 中村誠一・中尾智行・朝倉由希・村野
正景・野口
【2024年12月6日 【品切】【ご注文承り中】
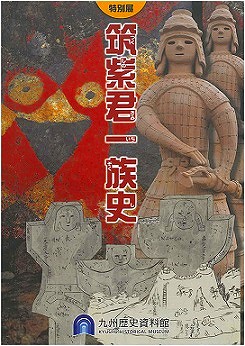
書籍番号
82503
書 名
特別展 筑紫君一族史
シリーズ
データ
A4 168頁
ISBN/ISSN
編著者
九州歴史資料館編集
出版年
2024年10月
出版者
九州歴史資料館
価 格
筑紫君磐井,その一族が刻んだ足跡をたどる。
ヤマト王権と矛を交えた筑紫君磐井,糟屋屯倉を献上した
筑紫君葛子,百済救援に向かい唐軍と戦った筑紫君薩野馬,
そして筑紫神を祀った甕依姫。彼らの歴史は,倭国が日本国
へと転換する「日本創成の風景」とともにありました。
ヤマト王権が記した虚実ある『日本書紀』等の文字史料と,
筑紫君自らが築いた古墳や集落等の考古資料の双方を眺める
ことで,「筑紫君一族史」の実像にせまります。
日本初の発見となった「馬甲着装馬形埴輪」をはじめとした
新資料と,最新研究の成果を多数収録しています。
第一部 筑紫君一族史
総 論 筑紫君一族史
…………………………………… 8
第一章
甕依姫の時代 …………………………………… 23
一 ツクシの二柱
……………………………………… 24
二
祝と豪族 …………………………………………… 28
三 筑紫神坐す地
……………………………………… 32
四
八女津媛坐す地 …………………………………… 36
第二章 有明首長連合の時代 …………………………… 39
一 有明海とヤマト王権
……………………………… 40
二
八女古墳群の勃興 ………………………………… 46
三 筑紫と火の交わり
………………………………… 55
第三章 筑紫君磐井の時代 ……………………………… 61
一 「筑紫君磐井の墓」探索史
……………………… 62
二
岩戸山古墳の実像 ………………………………… 70
三 今城塚古墳の威容
………………………………… 82
四
筑紫君の対外交流 ………………………………… 90
五 筑紫君磐井の乱
…………………………………… 98
第四章 筑紫国造の時代 …………………………………101
一 乱後のツクシ
………………………………………102
二
筑紫国造の奮戦 ……………………………………110
三 筑紫・火を貫く南北路
……………………………115
四
ミヤケが果たした役割 ……………………………126
第五章 筑紫君薩野馬の時代 ……………………………129
一 百済救援と筑紫君
…………………………………130
二
筑紫大宰の備え ……………………………………133
三 大宰府と律令国家
…………………………………138
四
筑紫国造磐井墓の北二里 上妻郡衙 ………………141
終 章 最果ての豪族 筑紫君 ……………………………142
第二部 筑紫海の日々
………………………………………143
総 論
筑紫海の日々 ……………………………………144
第一章
筑紫海の赤と黒 …………………………………148
第二章
山辺の村 …………………………………………150
第三章
海辺の村 …………………………………………152
出品目録
………………………………………………………156
参考文献
………………………………………………………166
【2024年12月5日 【入荷】【ご注文承り中】
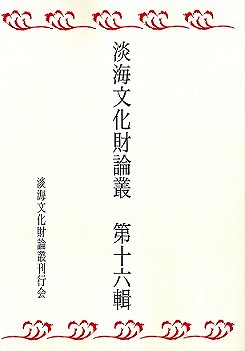
書籍番号
82514
書 名
淡海文化財論叢 第16輯
シリーズ
―伊藤潔さん・大崎哲人さん・川畑和弘さん・田井中洋介さん・細川眞理子さん・松下 浩さん・丸山雄二さん還暦記念―
データ
A4 201頁
ISBN/ISSN
編著者
淡海文化財論叢刊行会編集
出版年
2024年10月
出版者
淡海文化財論叢刊行会
価 格
6,000円(税込)
目 次
* * *
田井中 洋介 東近江市蒲生地区の近世石造物に関する覚書
―石工銘資料を中心に― …………………………… 3
杉山
紗南 考古資料と3Dモデル
細川
眞理子
妹尾 裕介
―博物館資料としての活用と課題― ……………… 9
* * *
西山 集
福満遺跡一次・二次調査出土凸帯文土器の再検討 … 15
春名 英行
細川 修平 大岩山銅鐸群の課題整理のために
…………………… 22
用田 政晴
畿内外縁部の古墳時代首長
―播磨と近江の結界と渡津・船津一 ……………… 28
西中
久典 大津市錦織検出の埋没古墳について ………………… 35
辻川
哲朗 高島市・音羽西遺跡T4出土埴輪の再検討 ………… 41
山本 一博 依知秦氏研究ノート②
―淵川の流路― ……………………………………… 47
宮崎 幹也 竪穴建物の構造と調査方法
…………………………… 52
田中 勝弘 古代集落と地域開発(一七)
―大津市真野廃寺・衣川廃寺建立の背景 ………… 58
小谷
徳彦 宮町遺跡NR13258に関する覚書 …………………… 64
大橋 信弥 国家プロジェクトとしての近江の鉄(下)
―列島における鉄生産の開始をめぐって― ……… 70
佐伯
英樹 蜂屋廃寺の礎石 ………………………………………… 78
髙梨 純次 甲賀市甲南町・矢川神社の神像群について
………… 82
上垣 幸徳
近江における南北朝期以降の宝篋印塔I類 ………… 88
明日
一史 百済寺遺跡坊跡分布域の再検討
―赤色立体地図の活用― …………………………… 92
宮崎
雅充 名勝旧秀隣寺庭園の下層遺構について ……………… 98
本田 洋 多賀新左衛門尉の系譜
(三)
―多賀貞能の場合(補遺)― …………………………104
畑中
英二 遺跡化の検討
―滋賀県長浜市小谷城跡を事例に (中)― …………110
山口
誠司 安土城所用軒平瓦の再考(四) …………………………116
木戸 雅寿 大津城復元推定考
………………………………………120
小林
隆 江戸時代の大名や旗本は封建領主だったのか ………128
寺前 公基 烏丸宣定の画業について
………………………………134
杉江
進 天明六年近江国八幡町騒動の記録と薬屋五兵衛
―関連史料の紹介から― ……………………………139
林 昭男
彦根城馬屋に関する考古学的検討 ……………………147
古川 与志継
近江天保一揆の関係史料について(14)
―天保八年の土地調査を中心に― …………………153
高橋
大樹 ある村堂の由来と霊宝伝来
―知内観音堂の歴史的変遷― ………………………159
水谷
光希 近代における滋賀県での製茶業と甲賀郡 ……………165
井上 優
森大造「井上敬之助像」の制作史料について ………171
佐野
正晴 長浜市余呉町文室の綾の神
―ある民間信仰の神の性格の検討― ………………177
渡邊
浩貴 近江国柏木御厨故地現地調査報告I
土山
祐之
―甲賀市水口町植地区における聞き書き集― ……183
高橋
順之 コロナ禍と民俗芸能
―伊吹山奉納太鼓踊の中止と復活― ………………189
岡 智康 矢穴技法による破壊現象
………………………………196
* * *
執筆者一覧
編集後記
【2024年11月28日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82497
書 名
東日本における土器からみた古墳社会の成立
シリーズ
データ
A4 425頁
ISBN/ISSN
編著者
東日本古墳確立期土器検討会編集
出版年
2024年11月
出版者
東日本古墳確立期土器検討会
価 格
4,500円(税込)
からみた古墳社会の確立」(石川県金沢市で開催)の発表要旨+資料集
補遺の冊子です。
発表要旨 開催趣旨 (西川修一)……………………………………………1
土器推移にみる 「社会史」 との関連 (田嶋明人) ……………………5
定型化した古墳の成立一東日本からみえる課題を添えてー (田中 裕)
…………………11
墳墓出土土器と墳墓の年代
-葬送祭祀儀礼研究を媒介として-
(古屋紀之) ………………23
近畿の様相
(市村慎太郎)…………………………………………………41
東海の様相
(早野浩二)……………………………………………………53
北陸南西部の様相
(安中哲徳・中江隆英)………………………………63
北陸北東部の様相
(滝沢規朗)……………………………………………81
関東南部の様相
(小橋健司) ……………………………………………99
関東北部の様相
(深澤敦仁) ……………………………………………117
関東東部の様相 (稲田健一)
……………………………………………137
東北南部の様相 (青山博樹)
……………………………………………151
土器編年と前方後円墳集成2~4期 (山本
亮)…………………………165
関東北部
群馬県
………………………………………………………………189
北陸南西部
北加賀
(追加分)……………………………………………………249
福井県
………………………………………………………………307
中部
長野県
………………………………………………………………336
甲斐(追加分)
………………………………………………………366
東海東部
静岡県(伊豆・駿河・遠江)
………………………………………398
【2024年11月28日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82498
書 名
出土土器からみた古墳の年代(全2冊)
シリーズ
データ
A4 1054頁
ISBN/ISSN
編著者
東日本古墳確立期土器検討会編集
出版年
2024年8月
出版者
日本古墳確立期土器検討会
価 格
8,600円(税込)
土器からみた古墳社会の確立」(石川県金沢市)の資料集です。
東北~近畿の古墳出土土器の集成。 地域ごとに、概要、一覧表、時
期消長表、文献資料、図版を掲載。
東北南部(山形県・宮城県・福島県)…………………………………1
関東東部
常陸………………………………………………………………… 99
下野…………………………………………………………………137
関東南部
千葉県(安房・上総・下総)………………………………………159
南武蔵………………………………………………………………289
相模…………………………………………………………………339
北陸
北陸北東部(越後・越中・能登)…………………………………397
北陸南西部(加賀)…………………………………………………453
中部
甲斐…………………………………………………………………499
東海西部
岐阜県(美濃・飛騨) ……………………………………………521
愛知県・三重県……………………………………………………603
近畿北部
近江…………………………………………………………………677
丹後・丹波…………………………………………………………736
摂津・山城…………………………………………………………805
近畿中部
河内・和泉…………………………………………………………875
大和北部等…………………………………………………………956
大和南部 …………………………………………………………1013
【2024年11月25日 【入荷】【ご注文承り中】
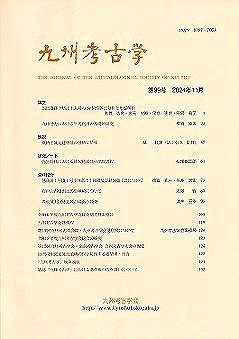
書籍番号
82494
書 名
九州考古学 第99号
シリーズ
データ
A4 323頁(精装)
ISBN/ISSN
0387-7078
編著者
九州考古学編集幹事
出版年
2024年11月
出版者
九州考古学会
価 格
2,700円(税込)
広田遺跡下層出土人骨のSr同位体比分析と形態解析
椋
浩史・米元 史織・足立 達朗・田尻 義了 1
九州地方における牛馬利用の基礎的研究
櫻庭 陸央 23
風納土城瓦建物址の性格と位相 蘇 栽潤(訳:小池
史哲) 47
弥生時代における鉄製穂摘具の出現過程
松尾樹志郎 61
菖蒲浦1号墳1号主体部出土銅鏡及び鉄製農工具について
徳富孔一・平井 洸史 73
岩戸山古墳出土馬形埴輪について
渡邉 響 83
豊前竜王城跡北麓の縄張り調査
浦井 直幸 95
令和6年度九州考古学会総会研究発表要旨
103
九州考古学会賞規程
119
第17回九州考古学会賞・九州考古学会奨励賞について
九州考古学会事務局 120
令和5年度九州考古学会総会の概要
123
第15回九州考古学会・嶺南考古学会 合同考古学大会の概要
124
旧門司駅関連施設遺構の保存に関する要望書・回答
127
『九州考古学』
執筆要項
131
雑誌『九州考古学』における著作権の取り扱いについて
132
【2024年11月25日 【入荷】【ご注文承り中】
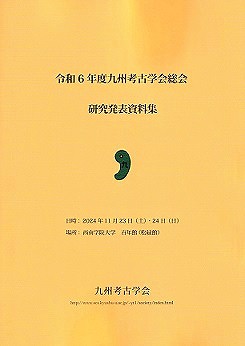
書籍番号
82493
書 名
令和6年度九州考古学会総会研究発表資料集
シリーズ
データ
A4 149頁
ISBN/ISSN
編著者
九州考古学会編集
出版年
2024年11月
出版者
九州考古学会
価 格
2,200円(税込)
土器から考える九州地方における弥生~古墳時代の米調理
──────────────────────────────
先史時代における様々な米調理一中国長江下流域を例として一
……………………1
久保田 慎二
使用痕分析からみた弥生土器の利用と集団関係
…………………11
石田 智子
菊池川流域における古墳時代初頭の長胴丸底甕の使用方法に関する
研究 ………………………………………………………………………20
向井 悠里子
九州南部の米調理法の変遷 ……………………………………………29
松島 隆介
残存脂質分析からみた成川式土器の調理対象
……………………39
宮田 佳樹・大西 智和・鐘ヶ江 賢二・中村 直子・
久保田 慎二
韓半島原三國~三國時代の土器調理 …………………………………49
呉 昇桓
(翻訳:永山亮・大山清加・井内達也・嶋田真子・玉山愛梨・
上田麻央 渋谷美咲 島田聖 森江天信・ 古澤義久)
研究発表
──────────────────────────────
黒橋貝塚の調査成果について ………………………………………69
金田一精
韓国・青銅器時代における集落動態と中心集落
-慶尚南道地域を対象として一 ………………………………76
端野 晋平・裵 徳煥
弥生時代除草具の基礎的検討一大形石庖丁と鉄鎌を対象として一
………………86
松尾 樹志郎
豊後高田市所在の大原古墳の調査 ……………………………………96
玉川 剛司・大田 悠人
鹿児島城跡の考古学~近年の調査成果を中心に~
………………106
西野 元勝
洋式船修繕施設の稼働実態解明を目的とした廃棄土坑出土遺物の定量
的調査 …………………………………………………………………116
中野 充
「西南戦争の弾痕」調査成果報告
…………………………………126
美濃口 雅朗
北九州市門司港地区で検出した明治期鉄道遺構の学術的価値と懸念
される諸問題……………………………………………………………134
佐藤 浩司
ポスター発表
──────────────────────────────
深江石町遺跡出土木甲について………………………………………144
江崎 靖隆
観音山古墳群平石群の古代墳墓について-いわゆる「末期古墳」の
可能性……………………………………………………………………146
上田 龍児・澤田 康夫
九州大学箱崎キャンパス跡地内遺跡における中世の火葬場跡……148
福永 将大・谷 直子・宮本一夫
【2024年11月25日 【入荷】【ご注文承り中】
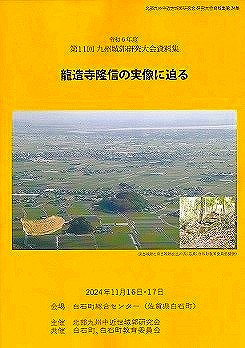
書籍番号
82490
書 名
龍造寺隆信の実像に迫る
シリーズ
(北部九州中近世城郭研究会論文集)
データ
A4 224頁
ISBN/ISSN
編著者
北部九州中近世城郭研究会編集
出版年
2024年11月
出版者
北部九州中近世城郭研究会
価 格
2,200円(税込)
ご挨拶
目次
1. 基調講演
宮武正登(佐賀大学教授) 城郭から見た龍造寺氏の実像
一龍造寺氏系城郭の基礎的理解一 ………………1
宮島敦子
(佐賀大学名誉教授) 龍造寺隆信の龍造寺氏家督継承に
ついて ……………………………………………………9
2.
研究発表
宮崎博司(佐賀県立名護屋城博物館学芸課長)
瓦から見た北部九州の城一須古城跡を中心に一
………………27
鶴嶋俊彦(肥後考古学会副会長)
龍造寺氏の筑後 肥後侵攻と城郭
……………41
山崎龍雄(北部九州中近世城郭研究会)
龍造寺氏の筑前国侵攻
…………………61
3. 紙上報告
宮崎俊輔
(天草市観光文化部文化課) 史跡棚底城跡の整備とまち
づくり ……………………………………………………79
江頭直希
(白石町教育委員会生涯学習課 )
令和5年度における須古城跡の発掘調査概要について 89
4.
九州各県報告~城館整備の状況を中心に~
〔福岡県〕 岡寺
良・若杉善満 福岡県の城郭整備の状況について
……………99
〔佐賀県〕 市川浩文
佐賀県における史跡城館の整備状況 …105
[長崎県] 大野安生 長崎県の城郭整備の状況について ……115
〔熊本県〕 米村 大・中山 圭
熊本県の城郭整備事例 ……121
〔大分県〕
小柳和宏 大分県における史跡城館の整備状況 …131
〔宮崎県〕 白岩 修 宮崎県の城郭整備の状況について ……139
〔鹿児島県〕上田 耕 鹿児島県内の城郭調査研究の動向
……147
5. 2023年度研究大会パネルディスカッションの記録
城館・考古・文献から大友氏の勢力圏を俯瞰する ……………159
北部九州中近世城郭研究会発行書籍の販売案内
…………………174
【2024年11月25日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82491
書 名
九州の城 3
シリーズ
(北部九州中近世城郭研究会論文集)
データ
A4 224頁
ISBN/ISSN
編著者
北部九州中近世城郭研究会編集
出版年
2024年11月
出版者
北部九州中近世城郭研究会
価 格
3,800円(税込)
序
「怡土城」と「肥前国庁」
について
瓜生秀文 1
国指定史跡女山神籠石発掘調査簡易報告
瓜生 建 19
竪堀登城路をもつ肥前の城郭
鶴嶋俊彦 31
北九州地方の大規模城郭の背景-国人衆と城督について-
中村修身 45
毛利鎮真と城-永禄~天正期大友氏の豊筑支配の一事例-
藤野正人・若杦善満・岡寺 良
59
御飯ノ山城跡再考
山崎龍雄 83
合志福原の城郭について
米村 大 109
長崎県波佐見町の新発見5城郭
大野安生 115
長崎県佐世保市鳶の巣城の<再>発見
大野安生 121
城郭石垣に残された矢穴-大分県の事例を中心に-
浦井直幸 125
CS立体図を活用した山城調査について~熊本県内の山城跡を事例に~
中山 圭 137
黒田氏の城郭石垣と採石 植田紘正
157
中津城と中津城下町の形成~細川忠興の土木事業~ 小柳和宏
169
名護屋城天守移築に関する一考察
~名護屋城天守瓦から探る廃城後天守の行方~
坂井清春 189
大分縣佐伯城跡の近代~廃城から公園化までの道のり~ 福永素久
199
1.
研究大会
211
2.
北部九州中近世城郭情報紙
218
3.
研究会論文集
223
編集後記
執筆者一覧
【2024年11月22日 【入荷】【ご注文承り中】
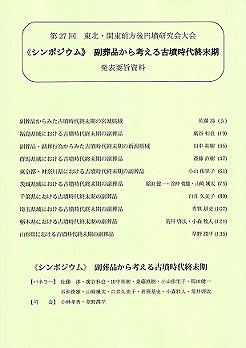
書籍番号
82489
書 名
副葬品から考える古墳時代終末期
シリーズ
(第27回東北・関東前方後円墳研究会 《シンポジウム》発表要旨資料)
データ
A4 142頁
ISBN/ISSN
編著者
第27回大会実行委員会編集
出版年
2024年1月
出版者
東北・関東前方後円墳研究会
価 格
1,600円(税込)
副葬品からみた古墳時代終末期の宮城県城
佐藤 渉 (5)
福島県域における古墳時代終末期の副葬品
廣谷 和也 (19)
副葬品・副葬行為からみた古墳時代終末期の新潟県域
田中 祐樹 (35)
群馬県域における古墳時代終末期の副葬品
斎藤 直樹 (47)
東京都・神奈川県における古墳時代終末期の副葬品
小山 侑里子 (61)
茨城県域における古墳時代終末期の副葬品
稲田 健一・谷仲 俊雄・山崎颯太 (75)
千葉県における古墳時代終末期の副葬品
白井 久美子 (89)
埼玉県域における古墳時代終末期の副葬品
青笹 基史(107)
栃木県における古墳時代終末期の副葬品
荒井 啓汰・小森 牧人(121)
山形県における古墳時代終末期の副葬品
草野 潤平(135)
<バックナンバー在庫>
81894 東北・関東における方墳の展開
(第26回東北・関東前方後円墳研究会 《シンポジウム》発表要旨資料)
2023年7月 A4 146頁 ¥2,200(税込)
https://www.chugoku-shoten.com/mokuji/jmokuji/81894/81894.html
81893
後期の中の変革―536年イベントにみる気候変動との関わり
(第25回東北・関東前方後円墳研究会 大会シンポジウム 発表要旨資料)
2020年2月 A4 124頁
¥2,200(税込)
https://www.chugoku-shoten.com/mokuji/jmokuji/81893/81893.html
【2024年11月21日 【入荷】【ご注文承り中】
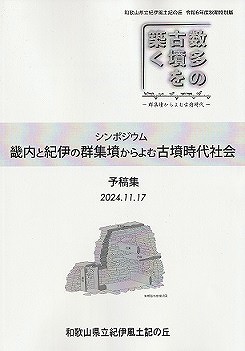
書籍番号
82487
書 名
シンポジウム「畿内と紀伊の群集墳からよむ古墳時代社会」(予稿集)
シリーズ
(数多の古墳を築く―群集墳からよむ古墳時代―(特別展)
データ
A4 52頁
ISBN/ISSN
編著者
和歌山県立紀伊風土記の丘編集
出版年
2024年11月
出版者
和歌山県立紀伊風土記の丘
価 格
600円(税込)
からよむ古墳時代―」シンポジウム「畿内と紀伊の群集墳からよむ古墳時代
社会」
予稿集
目次
群集墳と古墳時代社会
太田宏明……… 1
副葬品からみた群集墳の被葬者像一畿内地域を中心にー
絹畠 歩……… 17
群集墳と土器使用儀礼
仲辻慧大……… 30
紀伊地域における6・7世紀の群集墳の展開
萩野谷正宏……… 42
4
【2024年11月20日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82486
書 名
九州旧石器 第28号 第50回記念大会特集号
シリーズ
(九州旧石器文化研究の展望―九州・沖縄と東アジア―)
データ
A4 222頁
ISBN/ISSN
編著者
松本 茂編集
出版年
2024年11月
出版者
九州旧石器文化研究会
価 格
4,500円(税込)
合わせてご覧いただけます)
https://www.chugoku-shoten.com/mokuji/jmokuji/82486/82486.pdf
───────────────────────────────
目 次
木﨑 康弘 はじめに
1.
九州旧石器文化研究の展望-九州・沖縄と東アジア-
九州旧石器文化研究会 第50
回記念大会 予稿集
[趣旨説明要旨]
木﨑 康弘 九州「旧石器」文化研究の可能性……………… 1
[記念講演要旨]
李起吉(翻訳:田中 聡一)
韓国における発達した石刃技法の出現と内在的発展の技術
伝統………………………………………………………… 7
(韓国語題目) …………………………………………… 19
李作[女亭](翻訳:大堀 皓平・後藤 雅彦)
台湾旧石器文化の起源を探る-長濱文化の石器技術
と古人類資料に関する考察- …………………
25
探尋臺灣舊石器文化來源-長濱文化石器技術與古人
類資料的討論- ………………………………… 40
[解説要旨]
岩谷 史記 九州旧石器文化研究会の活動 ………………… 52
九州旧石器文化研究会のあゆみ(1979年~2024年)
……… 60
[研究報告要旨]
1 大堀 皓平 琉球列島の人類文化
-物質文化を主として- …………… 63
2 沖野 誠 九州旧石器文化の年代と環境
………………… 79
3 杉原 敏之 九州における石刃技術の展開 …………………
87
4 鎌田 洋昭 南九州・南西諸島における台形様石器群と礫塊
石器 ……………………………………………… 97
5 芝 康次郎 細石刃石器群の出現をめぐる諸課題
-「モザイク展開仮説」をめぐって-
………111
6 栁田 裕三・高橋 史輝 西北九州における旧石器時代の遺跡
群形成と洞窟遺跡 ………………121
7 加藤 真二 中国旧石器文化からみた九州旧石器文化 ……137
2.九州・沖縄各県の調査・研究動向 …………………………………147
小川原 励 福岡県の動向
越知 睦和 佐賀県の動向
辻田 直人・高橋 史輝・栁田裕三 長崎県の動向
岸田 裕一 熊本県の動向
桑村 壮雄 大分県の動向
藤木 聡 宮崎県の動向
寒川 朋枝 鹿児島県の動向
大堀 皓平 沖縄県の動向
3.九州旧石器文化の研究
山田 しょう 石製狩猟具の世界的研究動向(補遺2) ………155
寒川 朋枝・岩永 雅彦 動物利用に関する実験使用痕分析
-西北九州産石材を素材として- 173
保坂 康夫・庄田 慎矢・村上 夏希・金井 拓人・馬籠 亮道・
倉本 るみ子 鹿児島県出土の礫群の残存脂質分析と焼石使用履歴
分析の成果 ………………………………………181
早田 勉・山崎 真治
奄美・沖縄諸島における広域指標テフラに関する新たな
知見…………………………………………………………189
浅海 竜司 最終氷期の沖縄はどのくらい寒かったか?
-石筍と遺跡貝化石による地質考古学的手法からの
復元- ………………………………………………201
髙橋 愼二 日ノ岳遺跡-その1 ………………210
桑村 壮雄 大分県由布市に所在する山下池遺跡の採集資料に
ついて ………………………………………………214
【2024年11月13日 【入荷】【ご注文承り中】
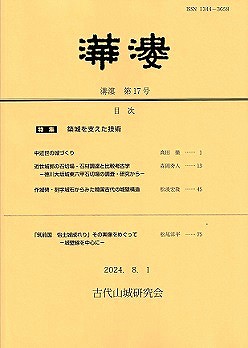
書籍番号
82485
書 名
溝[シ婁] 第17号 特集 築城を支えた技術
シリーズ
データ
A4 84頁
ISBN/ISSN
1344-3658
編著者
古代山城研究会編集
出版年
2024年8月
出版者
古代山城研究会
価 格
1,650円(税込)
特 集 築城を支えた技術
近世城郭の石切場・石材調達と比較考古学 森岡秀人 ………… 13
ー徳川大坂城東六甲石切場の調査・研究からー
作城碑・刻字城石からみた韓国古代の城壁構造 松波宏隆 …………
45
ー城壁線を中心にー
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
<お知らせ>
下記の予稿集はすでに品切れとなっておりますが、研究会より
PDFデータご覧いただけるようにお手配いただきました。
URLよりご覧いただけます。
古代山城と祭祀・寺院~神籠石論争から四天王信仰まで~
(第59回古代山城研究会例会)(プログラム・予稿集)
2019年9月
https://www.chugoku-shoten.com/mokuji/jmokuji/82485d/82485d.pdf
【2024年11月9日 【入荷】【ご注文承り中】
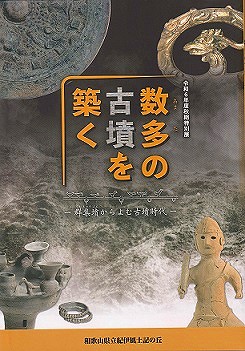
書籍番号
82481
書 名
数多の古墳を築く―群集墳からよむ古墳時代―
シリーズ
(令和6年度秋季特別展)
データ
A4 93頁
ISBN/ISSN
編著者
和歌山県立紀伊風土記の丘
出版年
2024年10月
出版者
和歌山県立紀伊風土記
価 格
1,700円(税込)
本展示では、岩橋千塚古墳群をはじめ、奈良県・大阪府など近畿地方
の大規模群集墳と、和歌山県域の群集墳を紹介します。そして、古墳
時代後半期に群集墳が出現した歴史的背景と和歌山県域の特色を考古
資料から探りたいと思います
…………………………………………………………………………………
目 次
序 章 群集墳とはなにか……………………………………………… 1
第一章 数多の古墳を築く……………………………………………… 4
第一節 大和における群集墳の展開………………………………… 4
第二節 河内における群集墳の展開………………………………… 19
第三節 近畿地方の群集墳概観……………………………………… 29
第二章 岩橋千塚と紀伊の群集墳……………………………………… 31
第一節 岩橋千塚古墳群……………………………………………… 31
第二節 紀伊の群集墳………………………………………………… 49
第三章 群集墳の時代の終焉…………………………………………… 71
第一節 大和・河内における群集墳の終焉………………………… 71
第二節 紀伊の群集墳の終焉………………………………………… 75
付論 橫穴式石室導入期における紀伊の群集墳 萩野谷 正宏 … 83
図版目録…………………………………………………………………… 85
展示品目録………………………………………………………………… 89
参考文献一覧……………………………………………………………… 92
【2024年10月31日 【入荷】【ご注文承り中】
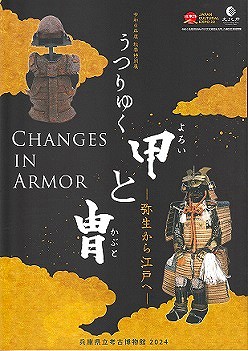
書籍番号
82471
書 名
うつりゆく甲と冑-弥生から江戸へ-
シリーズ
(令和6年度 秋季特別展)(兵庫県立考古博物館特別展示図録 34)
データ
A4 75頁
ISBN/ISSN
編著者
兵庫県立考古博物館編集
出版年
2024年9月
出版者
兵庫県立考古博物館
価 格
1,700円(税込)
弥生時代以降に激化した集団間の争いは、敵を攻めるための武器だけで
なく自身の身を守るための甲冑(かっちゅう/よろいかぶと)を生み出
しました。
これらの甲冑は社会情勢や戦い方の変化に対応し、防御性や機動性とい
った機能を向上させ発展していきます。その一方で、いつの時代も甲冑
には機能的に不要とも思える装飾が施されました。
本展覧会では、弥生時代から近世までの、兵庫県内外で出土・伝世し
た代表的な甲冑を一堂に紹介し、その変遷をたどるとともに、戦いに臨
んだ武人たちの甲冑に込められた思いを探ります。
目次・例言・凡例
第一章 甲冑の出現
……………………………………………………… 1
第二章 鉄製甲冑の成立と進化 ………………………………………… 7
古墳づくりと軍事行動 ………………………………………… 24
第三章 武士の時代へ …………………………………………………… 26
トヒック 描かれた武人たちの姿 ………………………………………… 48
展示解説 甲冑の変遷をたどる …………………………………………… 58
資料解説 ……………………………………………………………………… 62
出土遺跡の位置 ……………………………………………………………… 69
出品目録 ……………………………………………………………………… 70
図版目録 ……………………………………………………………………… 72
主要参考文献 ………………………………………………………………… 72
謝辞・関連行事・奥付
【2024年10月31日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82431
書 名
大宰府の成立と古代豪族
シリーズ
(古代史選書 49)
データ
A5 356頁 (上製本)
ISBN/ISSN
978-4-88621-991-6
編著者
中国航誨博物館編著
出版年
2024年10月
出版者
同成社
価 格
9,350円(税込)
筑紫大宰・総領の関係等を掘り下げ、その成立過程を解明する.
序章 大宰府成立史への本書の視点
第一章 古墳群からみた九州の古代豪族と倭王権
第二章 那津官家修造記事の再検討
第三章 筑紫国造の地域支配
―筑紫君と胸肩君、水沼君の動向を中心に―
第四章 倭王権の九州支配と筑紫大宰の派遣
第五章 筑紫における総領について
第六章 筑紫大宰と筑紫総領―職掌と冠位の再検討―
第七章 朝倉橘広庭宮名号考
第八章 文献史料からみた古代の水城
第九章 大宰府と大野城
第十章 大野城跡出土柱根刻書再考
第十一章 筑紫における評の成立
第十二章 大宰府成立期の木簡―七世紀木簡を中心に―
【2024年10月18日 【入荷】【ご注文承り中】
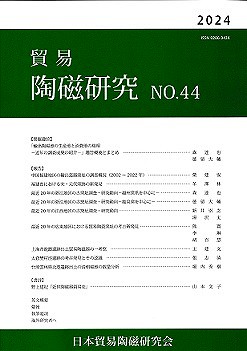
書籍番号
82454
書 名
貿易陶磁研究 第44号
シリーズ
データ
A4 158頁
ISBN/ISSN
0286-343X
編著者
日本貿易陶磁研究会編集
出版年
2024年10月
出版者
日本貿易陶磁研究会
価 格
3,850円(税込)
「輸出陶磁器の生産地と消費地の様相
-近年の調査成果の紹介-」趣旨概要とまとめ …………森 達 也
徳 富 大 輔
【報告】
中国福建地区の輸出瓷器窯址の調査概況(2002~2022年)…栗
建 安
福建省における宋・元代窯跡の新発見………………………羊 澤
林
最近20年の浙江地区の古窯址調査・研究動向-越州窯系を中心に-
………森 達 也
最近20年の浙江地区の古窯址調査・研究動向ー龍泉窯を中心に-
………徳 富 大 輔
最近20年の江西地区の古窯址調査・研究動向………………新 井 崇
之
湯 沢 丈
最近20年の広東地区における貿易陶瓷窯址の考古新発見…熊 寰
李
琳
胡
百 慧
上海青龍鎮遺跡出土貿易陶磁器の一考察……………………王 建
文
太倉樊村涇遺跡の考古発見とその認識………………………張
志 清
台湾雲林県北港遺跡出土の清朝磁器の数量分析……………堀 内 秀 樹
野上建紀『近世陶磁器貿易史』………………………………山 本 文 子
彙報
執筆要項
海外研究者へ
【2024年10月18日 【入荷】【ご注文承り中】
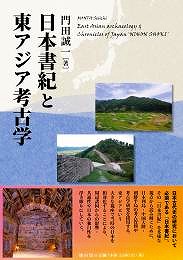
書籍番号
82446
書 名
日本書紀と東アジア考古学
シリーズ
データ
A5 240頁
ISBN/ISSN
978-4639030102
編著者
門田 誠一著
出版年
2024年10月
出版者
雄山閣出版
価 格
3,960円(税込)
日本古代史の研究において必須である『日本書紀』。その『日本書紀』
を多様な視点から読み解くために、日本列島・中国大陸・朝鮮半島の
考古資料や考古学研究を援用する。東アジアという大きな視座で当時の
日本を相対化することにより、周辺諸国からの影響・共通性や日本の
独自性を浮き彫りにしていく。
第一章 物質と人の交流と交渉
第一節 文物交流とその背景
第二節 移入された物と地域像
第三節 武具・武器と装飾品にみる交流
第四節 軍事施設を示す語句と実態
第五節 人と物の関係と地域相
第一節 住居の文化とその広がり
第二節 新羅の匠と新羅斧
第三節 刀剣と古墳時代の社会
第四節 東アジアにおける倭の製塩
第五節 銭貨と交換財の文化
第一節 角抵と力士の文化的様相
第二節 香文化の東伝
第三節 文字文化と出土文字資料
第四節 身体変工の思想と背景
第五節 礼俗の姿態と考古資料
第一節 桃の儀礼と祭祀
第二節 竈祭祀の系譜
第三節 殺牛の儀礼・祭祀
第四節 殉死と従死
第五節 倭の殯と東アジアの考古資料
第一節 神仙思想・初期道教と雲母
第二節 日本古代仏教の淵源
第三節 仏教遺物と地域交渉
第四節 葬送と荘厳にみる仏教信仰
第五節 仏教・儒教と孝の展開
【2024年10月18日 【入荷】【ご注文承り中】
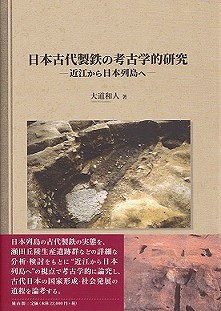
書籍番号
82447
書 名
日本古代製鉄の考古学的研究―近江から日本列島へ―
シリーズ
データ
B5 464頁(精装)
ISBN/ISSN
978-4639030072
編著者
大道 和人著
出版年
2024年10月
出版者
雄山閣出版
価 格
24,200円(税込)
近江から日本列島へ―古代製鉄の実態解明に挑む。
古代、鉄や鉄器をどれはど生産し保有てきるかが日本列島内での
国家形成と、各地域の発展に大きな役割を果たしていた。古代日
本での製鉄は、いつ、どこて、誰によって始められたのか?
古代国家の形成と社会発展を「鉄」の動きから探る、著者入魂の
大著、ついに刊行。
第2章 日本古代製鉄の開始について
第3章 日列列島各地の製鉄開始期の様相
第4第 古代製鉄展開期の様相
第5章 日本古代製鉄の開始と展開
第6阜 結語
【2024年10月17日 【入荷】【ご注文承り中】
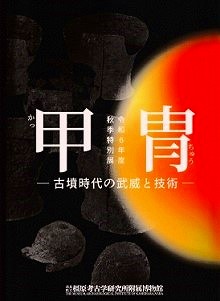
書籍番号
82456
書 名
甲冑―古墳時代の武威と技術―
シリーズ
(令和6年度 秋季特別展 特別展図録第96冊)
データ
A4
ISBN/ISSN
978-4910272313
編著者
奈良県立橿原考古学研究所編集
出版年
2024年10月
出版者
奈良県立橿原考古学研究所
価 格
1,700円(税込)
国家形成期にあたる古墳時代には、ヤマト王権により列島各地の
政治的な統合が進められます。『宋書』倭国伝に記された倭王武
の上表文は、統合に軍事が重要な役割を果たしたことを示します。
こうしたなか、鉄製の武器・武具は飛躍的な発展を遂げていきま
す。特に、複雑な立体構造をもつ甲冑の製作には高度な技術と大
量の素材が必要なため、ヤマト王権の下、一元的に生産されたと
考えられてきました。同時に、甲冑は威信財的な側面をも有して
います。本展覧会では、古墳時代の甲冑について、大和の出土品
と各地の良好な出土例を多数展示し、その変遷を通観するととも
にこれを巡る様々な問題に迫ります。(研究所HPより)
……………………………………………………………………………
ごあいさつ
目次、例言
展示関連地図
……………………………………………………… 5
プロローグ
ここに始まる-円照寺墓山1号墳出上甲青- …… 7
第Ⅰ章 木製の甲 ………………………………………………… 11
第Ⅱ章 鉄製甲冑の出現ー前期の甲冑ー ……………………… 15
第Ⅲ章 中期型甲胃の成立と展開 ……………………………… 23
第Ⅳ章 武器の変革ー挂甲の出現- …………………………… 45
第Ⅴ章 藤ノ木古墳の時代の甲冑 ……………………………… 55
第Ⅵ章 大和出土の甲冑 ………………………………………… 63
第Ⅶ章 末永雅雄の甲冑研究 …………………………………… 73
エピローグ ………………………………………………………… 79
出品目録 …………………………………………………………… 81
写真提供・撮影 …………………………………………………… 83
おもな参考文献 …………………………………………………… 84
展覧会中の行事
協力機関・協力者
【2024年10月17日 【入荷】【ご注文承り中】
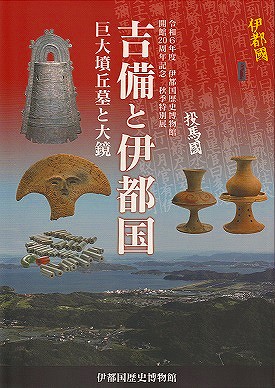
書籍番号
82455
書 名
吉備と伊都国 巨大墳丘墓と大鏡
シリーズ
(令和6年度伊都国歴史博物館 開館20周年記念 秋季特別展)
データ
A4 72頁
ISBN/ISSN
編著者
糸島市立伊都国歴史博物館
出版年
2024年10月
出版者
伊都国歴史博物館
価 格
1,100円(税込)
これを記念し、特別展「吉備と伊都国」を開催します。
吉備は、現在の岡山県と広島県の東部を指す地域です。温暖で、天気
の良い日が多いことから、「晴れの国」とも称されています。
気候が安定し、肥沃な土地が広がっていたことから、弥生時代には稲
作が盛んになり、多くの人々が暮らしていたようです。
また、吉備は瀬戸内海のほぼ中央部に位置していることから、海上交
通の要衝として発展し、弥生時代の終わりごろになると富を蓄え、権
力を掌握した王が誕生します。
王は巨大な墓に葬られ、そこで生まれた風習や文化は、後のヤマト王
権の成立に深く関わったと考えられます。特別展では吉備の王墓「楯
築墳丘墓」出土品をはじめ、重要文化財を含む貴重な資料を借りて展
示します。吉備の繁栄ぶりや伊都国とのあゆみ方の違いなどもぜひ、
ご覧ください。
第Ⅱ章 東西交流から見た吉備と伊都の弥生社会
第Ⅲ章 吉備王墓と伊都国の王墓~楯築墳丘墓と伊都国三王墓
第Ⅳ章 墳丘墓から古墳へ
【2024年10月11日 【入荷】【ご注文承り中】
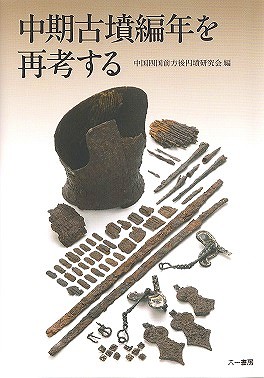
書籍番号
82453
書 名
中期古墳編年を再考する
シリーズ
データ
B5 432頁
ISBN/ISSN
978-4864451833
編著者
中国四国前方後円墳研究会編
出版年
2024年10月
出版者
六一書房
価 格
5,500円(税込)
前書『前期古墳編年を再考する』(2018年刊)をうけて、中期古
墳編年の再検討をおこなう。そして、中期古墳に副葬される各
種副葬品の編年研究の到達点を確認するとともに、埴輪編年や
土器(土師器・須恵器)編年との対応関係にも配慮することによ
り、副葬品を指標とした中期古墳広域編年を新たに提示する。
さらに、暦年代、王権構造、東アジア国際交流など古墳時代
中期社会の実相に迫るうえで不可欠な論点を取り込みつつ、新
たな中期古墳編年に即して中国四国諸地域の動向を浮き彫りに
する。
【目 次】
序……………………………………………………古瀬 清秀
1
例 言
目 次
趣旨説明
中期古墳編年を再考する…………………岩本 崇
1
第Ⅰ部 広域編年の検討
古墳時代中期編年の研究史と課題
………和田 晴吾 1
〈研究報告〉
銅 鏡
………………………………………岩本 崇 21
玉 類
………………………………………米田 克彦 33
石製模造品
…………………………………北山 峰生 45
帯金式甲冑 …………………………………川畑
純 57
札式甲冑
……………………………………初村 武寛 69
鉄 鏃
……………………………………尾上 元規 81
刀剣ヤリ鉾
…………………………………齊藤 大輔 93
馬 具 ……………………………………片山健太郎
105
金工品
………………………………………土屋 隆史 117
農工漁具 ……………………………………魚津 知克 129
埴 輪 ……………………………………野﨑 貴博
141
〈基調報告〉
西日本地域の古墳時代中期の土器研究と暦年代
………………田中 清美 155
〈研究報告〉
畿内地域の中期土師器編年と外来系土器
………………………中野 咲 169
〈地域報告〉
九州北部
……………………………………重藤 輝行 181
山陰東部
……………………………………君嶋 俊行 193
山陰中西部
…………………………………松山 智弘 205
山陽東部
……………………………………河合 忍 217
山陽中部
……………………………………村田 晋 229
山陽西部
……………………………………小林 善也 239
四国南東部
…………………………………田川 憲 251
四国北東部
…………………………………蔵本 晋司 263
四国北西部
…………………………………三吉 秀充 271
四国南東部
…………………………………宮里 修 283
第Ⅲ部 古墳時代中期の社会と中国四国
〈研究報告〉
中期古墳の相対編年と暦年代
……………岩本 崇 296
古墳時代中期における馬具の暦年代
……諫早 直人 309
河内政権と中四国
…………………………岸本 直文 323
文献からみた古墳時代中期と東アジア
…田中 史生 335
〈地域報告〉
山陰東部
……………………………………森藤 徳子 347
山陰中西部
…………………………………吉松 優希 357
山陽東部
……………………………………寒川 史也 367
山陽中部
……………………………………村田 晋 377
山陽西部
……………………………………岡田 裕之 387
四国南東部
…………………………………栗林 誠治 397
四国北東部
…………………………………真鍋 貴匡 405
四国北西部
…………………………………冨田 尚夫 413
四国南東部
…………………………………宮里 修 421
総
括
中期古墳編年の到達点と課題・展望
……岩本 崇 433
後 記
…………………………………………岩本 崇 438
執筆者一覧
【2024年10月7日 【入荷】【ご注文承り中】
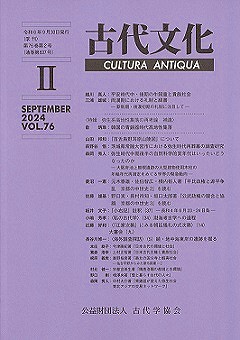
書籍番号
82443
書 名
古代文化 第76巻 第2号(637号)
シリーズ
データ
B5 146頁
ISBN/ISSN
0045-9232
編著者
出版年
2024年9月
出版者
古代学協会
価 格
2,970円(税込)
〈論 攷〉
越川 真人:平安時代中・後期の牛飼童と貴族社会
三浦 雄城:両漢期における礼制と緯書
ー莽新期・後漢初期の礼制に注目してー
…………………………………………………………………
〈特輯 弥生系高地性集落の再考論 補遺〉
兪 炳[王録-金]:韓国の青銅器時代高地性集落
山田 邦和:「百舌鳥野耳原山陵図」について
萩野谷 悟:茨城県常陸大宮市における弥生時代再葬墓の調査研究
森岡 秀人:弥生時代中期後半の自然科学的実年代はいったいどう
なったのか
ー大阪府池上曽根遺跡の大型建物使用木柱の
年輪年代再測定をめぐる学界の緊急動向ー
菱沼 ー憲:元木泰雄・佐伯智広・横内裕人著「平氏政権と源平争
乱京都の中世史2」を読む
佐藤 雄基:野口実・長村祥知・坂口太郎著「公武政権の競合と協
調京都の中世史3」を読む
〈注 釈〉
板井 文子:「小右記」註釈(37)ー長和4年6月23・24日条ー
小嶋 芳孝:く私の古代学〉(34)渤海考古学への道程
近藤 好和:く『江家次第』にみる朝廷儀礼の式次第〉
(14) 大嘗会(九)
長谷川修一:く海外調査探訪〉(5)続・地中海東岸の遺跡を掘る
本庄 総子:今津務紀著「日本古代の環境と社会」
鷺森 浩幸:上村正裕著「日本古代王権と貴族社会」
梶原 義実:斎野裕彦著「最北の国分寺と蝦夷社会
ー仙台平野からみた律令国家ー」
村元 健一:宇都宮美生著「隋唐洛陽の都城と水環境」
野口 剛:相澤央著「雪と暮らす古代の人々」
森岡 秀人:中村大介著「青鋼器が変えた弥生社会
東北アジアの交易ネットワーク」
【2024年10月5日 【入荷】【ご注文承り中】
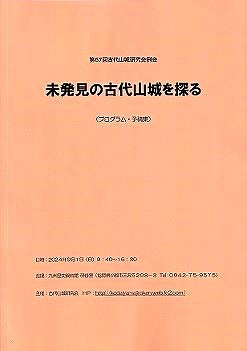
書籍番号
82437
書 名
未発見の古代山城を探る
シリーズ
(第67回古代山城研究会例会)(プログラム・予稿集)
データ
A4 64頁
ISBN/ISSN
編著者
古代山城研究会
出版年
2024年9月
出版者
価 格
1,100円(税込)
松尾洋平(古代山城研究会)……………… 1
「史書非記載山城―長者山城の概要」
向井一雄(古代山城研究会・代表)……… 19
「未発見の古代山城の探索―長門城・三野城・稲積城 他」
向井一雄
…………………………………… 24
「石垣高尾遺跡の調査」 丸林禎彦(久留米市教育委員会)… 48
「古代山城及び関連遺跡の評価について」
赤司善彦(大野城心のふるさと館・館長) 54
<関連書在庫>
82130 長者山城跡 新発見の安芸の古代山城
調査報告書
(古代山城研究会 研究報告書)(付図一枚)
2024年1月
価 格 1,100円(税込)
【2024年10月1日 【入荷】【ご注文承り中】
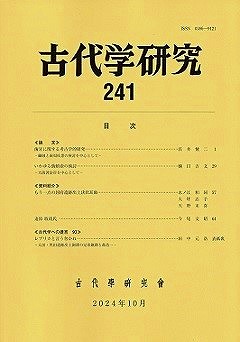
書籍番号
82430
書 名
古代学研究 第241号
シリーズ
データ
B5 64頁)
ISBN/ISSN
0386-9121
編著者
古代学研究編集局
出版年
2024年10月
出版者
価 格
990円(税込)
≪論 文≫
歯牙に関する考古学的研究………………………長 井 健 二 1
―齲蝕と歯周疾患の検計を中心として―
いわゆる飯蛸壺の検討……………………………樋 口 吉 文 29
―大阪湾沿岸を中心として―
≪資料紹介≫
もう一点の国府遺跡出土塊状耳飾………………水ノ江 和 同 57
大 坪 志 子
天 野 末 喜
追悼 坂靖氏
………………………………………今 尾 文 昭 64
レプリカと言う勿かれ……………………………田 中 元 浩 表紙裏
―太田・黒田遺跡出土鋼鐸の兄弟銅鐸と森浩一 ―
【2024年9月30日 【入荷】【ご注文承り中】
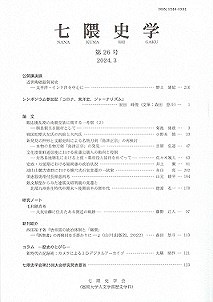
書籍番号
82428
書 名
七隈史学 第26号
シリーズ
データ
B5 216頁
ISBN/ISSN
1348-1304
編著者
桃﨑 祐輔編集
出版年
2024年3月
出版者
七隈史学会
価 格
2,200円(税込)
近世陶磁器貿易史
-太平洋・インド洋を中心に-
………………………… 野上 建紀 …
216
シンポジウム参加記「コロナ、東洋史、ジャーナリズム」
……………………安田 峰俊(文筆:森田 悠斗)… 1
論 文
観応擾乱期の南朝皇族に関する一考察(2)
―興良親王を題材として―
…………………………………菊池 康貴 … 3
戦国初期大友氏の内紛と大内氏 ……………小野本 慎 … 23
新発見の押形と文献史料による名物刀剣「島津正宗」の再検討
―本物の名物刀剣「島津正宗」の発見―
…………………吉原 弘道 … 47
文化度朝鮮通信使における萩藩公儀人の動向と役割
―対馬易地聘礼における上使・幕府役人接待をめぐって―
…………………………佐々木颯人 … 63
安政・万延期における福岡藩の政治状況
……………………井上 翼 … 81
油山山麓古墳群における横穴式石室変遷の一試案
…………永山 亮 … 202
須恵器突帯付長頸壺再考 ……………………山元 瞭平 …
184
銘文類型からみた連弧文昭明鏡の変遷と
北部九州弥生時代中期末~後期前半の暦年代
……………徳富 孔一 … 170
研究ノート
毛利鎮真考
―大友宗麟に仕えたある側近の軌跡― …藤野 正人 … 97
新刊紹介
西田祐子著『唐帝国の統治体制と「羈縻」
―『新唐書』の再検討を手掛かりに―』(山川出版社、2022)
……………森田 悠斗 … 113
コラム-歴史のとびら-
新時代の記録術:カメラによる3Dデジタルアーカイブ
…………………大隣 昭作 … 121
七隈史学会第25回大会研究発表要旨
………………………… 123
【2024年9月27日 【入荷】【ご注文承り中】
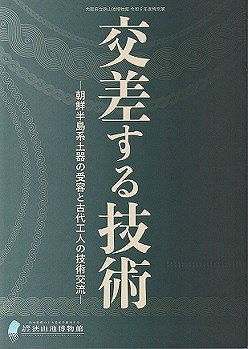
書籍番号
82426
書 名
交差する技術―朝鮮半島系土器の受容と古代工人の技術交流―
シリーズ
(大阪府立狭山池博物館 図録 42)
データ
A4 75頁
ISBN/ISSN
編著者
大阪府立狭山池博物館編集
出版年
2024年9月
出版者
大阪府立狭山池博物館
価 格
1,700円(税込)
変容・交流が活発になり始める。新しい技術はどこからやってきて、
どのように
伝わるのか。そしてそれは考古資料からどのようにうかがえるのか。
扱われてきたが、今回の展示ではそれらの間にみられる技術の交流にも目を
向ける。
●目次(凡例や参考文献等を除く)
・第1章 古墳時代の土器-土師器と須恵器-
・第2章 海を渡った土器製作技術-朝鮮半島系土器技術の受容-
・第3章 交じり合う土器製作技術-土師器と須恵器の折衷-
・第4章 器物をこえた製作技術の交流
・特別論考
飯塚信幸(当館学芸員)「須恵器からみた古墳時代後期における加耶
・新羅とのつながりー陶邑窯跡群およびその周辺を対象にー」
(博物館HPより抽出)
【2024年9月27日 【入荷】【ご注文承り中】
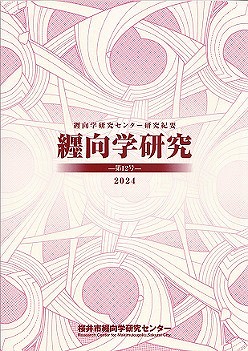
書籍番号
82427
書 名
纒向学研究 第12号 2024
シリーズ
(纏向学研究センター研究紀要)
データ
A4 120頁
ISBN/ISSN
編著者
出版年
2024年3月
出版者
井市纏向学研究センター
価 格
1,700円(税込)
序
二次的国家形成
―寺沢薫氏の弥生・古墳時代政治史論に寄せて―
…水林 彪…… 1
…柳田 康雄…… 33
辟邪と呪縛
―古墳被葬者≒死者像の2面性に関する手稿― ………豊岡 卓之……
67
……………… 松田 和花・佐々木 香奈・梅原 若羽・宮路 淳子・
初宿 成彦… 91
………村上 朋・青木 智史・金原 正明…… 111
【2024年9月24日 【10月25日刊行予定・未入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82422
書 名
九州縄文時代における資源利用技術の研究
シリーズ
データ
B5 376頁 (上製本)
ISBN/ISSN
978-4639030058
編著者
板倉 有大著
出版年
2024年9月
出版者
雄山閣出版
価 格
18,700円(税込)
地域で蓄積が進む行政発掘資料の分析と関連研究成果の援用から、
「沖積低地利用」という観点に着目し、縄文時代の植物利用、居
住様式、人口、社会複雑化などのテーマに切り込む。
遺跡発掘の現場から積み上げられた包括的な考古学研究の成果。
植物利用論/居住様式論/本書における問題の所在
縄文時代石器研究方法論の現在/本書における石器研究法
九州縄文時代の磨製石斧/分析の方法:磨製石斧の性能分析/九州縄文
時代の土器編年:本書における時間軸の概要/各事例の分析/九州縄文
時代磨製石斧の動態
九州縄文時代の打製石斧/分析の方法:打製石斧の性能分析/各事例の
分析/九州縄文時代打製石斧の動態
九州縄文時代の縦長剥片石器/分析の方法:縦長剥片石器の性能分析/
各事例の分析/博多湾沿岸地域における縄文時代縦長剥片石器の動態
磨製石斧モデルの整合性/打製石斧モデルの整合性/縦長剥片石器モデ
ルの整合性
縄文時代前期以降の遺跡立地/分析の方法:遺跡立地変遷の把握/博多
湾沿岸地域の遺跡立地変遷/九州縄文時代資源利用モデル
植物利用/居住様式/縄文時代経済・社会のシステムモデル
付表1 磨製石斧データ/付表2 打製石斧データ/
付表3 遺跡立地データ
【2024年9月18日 【入荷】【ご注文承り中】
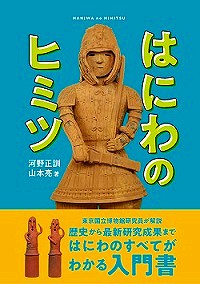
書籍番号
82418
書 名
はにわのヒミツ
シリーズ
データ
A5 128頁
ISBN/ISSN
978-4-7877-2415-1
編著者
河野 正訓 山本 亮 著
出版年
2024年10月
出版者
新泉社
価 格
2,200円(税込)
どんな動物が埴輪になった?
“最初の埴輪”はどんなもの?
埴輪づくりはむずかしい?
門的かつわかりやすく解説する。
また、同館の埴輪コレクションを代表する国宝「挂甲(けいこう)の武人」
の最新研究成果も紹介。
この国宝「挂甲の武人」や「踊る埴輪」などの超有名埴輪のほか、東北・
宮城県から九州・宮崎県まで広い地域のさまざまな埴輪が登場する。
知るともっと埴輪が好きになるヒミツが満載の1冊。
ヒミツ1 はにわといえば円筒埴輪
ヒミツ2 死者の魂が宿る――家形埴輪
ヒミツ3 魔をよけ、権威を示す――器財埴輪
ヒミツ4 はにわになった人たち――人物埴輪
ヒミツ5 踊る埴輪┌|∵|┘のすべて
ヒミツ6 王の物語を伝える動物――動物埴輪
ヒミツ7 とくべつなトリ
ちょっとしたヒミツ8 |コラム| 木のはにわと石のはにわ
ヒミツ9 はにわは古墳があってこそ!
ヒミツ10 はにわのドラマチック物語
ちょっとしたヒミツ11 |コラム| はにわ? 土偶?
ヒミツ12 最初のはにわ?
ヒミツ13 円筒埴輪の誕生――3世紀
ヒミツ14 家とニワトリの創出――4世紀
ヒミツ15 はにわ界の革命――5世紀
ヒミツ16 東日本のはにわブーム――6世紀
ちょっとしたヒミツ17 |コラム| 殉葬と相撲とはにわ
ヒミツ18 はにわ職人と工房
ヒミツ19 はにわ職人の腕前
ヒミツ20 ねずみ色のはにわ――東海・北陸地方
ヒミツ21 ご当地はにわ――関東地方
ちょっとしたヒミツ22 |コラム| はにわづくりは難しい
ヒミツ23 壮大なる、はにわ3Dパズル
ヒミツ24 はにわ史にのこる奇跡の再会
ヒミツ25 国宝のはにわ、最新調査成果
はにわをもっと知るためのおすすめの本
【2024年9月18日 【入荷】【ご注文承り中】
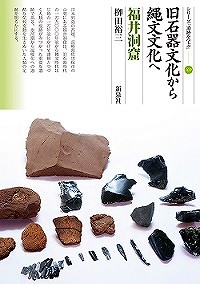
書籍番号
82419
書 名
旧石器文化から縄文文化へ 福井洞窟
シリーズ
(シリーズ「遺跡を学ぶ」169)
データ
A5 96頁
ISBN/ISSN
978-4-7877-2339-0
編著者
栁田 裕三著
出版年
2024年10月
出版者
新泉社
価 格
1,870円(税込)
の1万9000年前から縄文時代はじめの1万前にかけての人類の痕跡が連綿
とみつかった重要な遺跡である。氷河期から温暖化への過酷な気候変動
を生きぬいた人類の足跡を明らかにする。
───────────────────────────────
(シリーズ「遺跡を学ぶ」)は下記のURLより出版社サイトでご覧いた
だけます。
https://www.shinsensha.com/iseki/
───────────────────────────────
第1章 福井洞窟に魅せられて
1 狩猟採集民がみた洞窟
2 福井洞窟の発見
1 地下六メートルまで
2 学史に残る層位的編年研究
1 地下鉄工事みたいな発掘現場
2 地層を明らかにする
3 あらたな発見
4 明らかになった人間活動の変遷
1 激変する環境と福井洞窟
2 福井洞窟の形成と利用
3 旧石器文化から縄文文化へ
4 洞窟での暮らしを解き明かす
【2024年9月18日 【近着】【ご注文承り中】
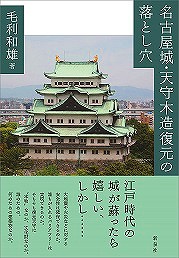
書籍番号
82366
書 名
名古屋城・天守木造復元の落とし穴
シリーズ
データ
A5 344頁
ISBN/ISSN
978-4-7877-2306-2
編著者
毛利 和雄著
出版年
2024年7月
出版者
新泉社
価 格
2,750円(税込)
さまざまな難問が。大地震や火災などに対する安全性は確保できるの
か。誰もが入れるバリアフリーは実現できるのか。そもそも復元天守
は〝本物〟なのか、文化財なのか。誰のための、何のための建築物な
のか。
はじめに
1 天守木造化計画はこうして始まった
2 名古屋城跡の本質的価値はどこにある?
3 木造天守の建築は許可されるのか?
4 奇襲作戦、現・天守を先行解体せよ?
5 石垣補修と基礎構造の見直し
6 誰のための天守木造化か
エピローグ 天守木造化かコンクリート天守の存続か
1 熊本城──熊本震災からの復興の象徴
2 首里城──沖縄県民のアイデンティティの象徴
3 姫路城──日本の世界遺産第一号
4 江戸城──江戸城天守は東京のランドマークか?
5 大阪城──耐震補強・長寿命化し登録文化財
6 安土城──「幻の安土城」復元プロジェクト
7 小田原城──木造化も視野に耐震補強
8 岡山城──観光振興と歴史展示の両立
9 福山城──お城をJR駅前の顔に
10 尾道城──景観形成で城郭風建築物を除却
11 広島城──国際平和文化都市の天守復興
12 大洲城──城泊の試み
13 高松城──悲願の木造天守の復元
14 丸亀城──「石垣の名城」で大規模崩落
15 仙台城──守るべきは石垣、櫓復元を断念
16 松江城──国宝天守の耐震補強
17 肥前名護屋城──崩れた石垣が語る歴史
エピローグ 歴史的建造物の復元とは
【2024年9月11日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82354
書 名
青銅器が変えた弥生社会 東北アジアの交易ネットワーク
シリーズ
(歴史文化ライブラリー602)
データ
四六版 272頁
ISBN/ISSN
978-4642306027
編著者
中村 大介著
出版年
2024年71月
出版者
吉川弘文館
価 格
1,980円(税込)
【内容簡介】
導入された銅剣・銅矛・銅鐸などの青銅器は、列島社会をどのように変
えたのか。青銅器をめぐる交易網の形成と、それにアプローチする弥生
人の行動を考古学の視点から追究。東北アジア社会の変動の中に弥生文
化を位置づけ、階層化社会から国家形成へとつながる
変革を読み解く。
首長墓の出現
粘土帯土器をもつ移住者と青銅器生産
王墓形成までの争乱
中国東北地方の動乱と粘土帯土器文化
朝鮮半島の粘土帯土器文化
鉄器の導入と燕国
燕・秦・漢の経済活動
鉛同位体比分析からみた青銅原料流通
西日本の交易ネットワーク
漢の拡大と東アジアの変動
衛氏朝鮮の盛行と楽浪郡設置
繁栄する楽浪・韓・倭
朝鮮半島南部の原三国時代と首長墓
北部九州における王墓の時代
東アジア社会変質の立役者
交易のかたち
引用・参考文献
【2024年9月11日 【入荷】【ご注文承り中】
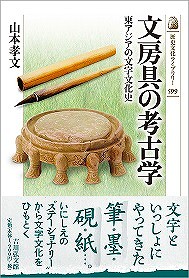
書籍番号
82407
書 名
文房具の考古学
シリーズ
(歴史文化ライブラリー599)
データ
四六版 280頁
ISBN/ISSN
978-4642059992
編著者
山本 孝文著
出版年
2024年6月
出版者
吉川弘文館
価 格
2,090円(税込)
【内容簡介】
文化は、いかに生まれ発展してきたのか。文字が持つ権威・宗教性
・芸術性などの側面に触れつつ、文字の種類や記録法などの歴史を
紹介。文字と同時に変化し日本へ伝播した筆・墨・硯・紙など、
筆記具の造形や装飾に着目し、著者独自の実験も交えて描き出す、
古代東アジアの文化史。
移りゆく文字と文房具―プロローグ
人類による文字の営み
文字前史―文字と記号
人間は文字で何をしてきたか
漢字の誕生と広がり
韓半島の初期文字使用
日本の初期文字使用
筆記行為のあれこれ
文房具―もう一つの文字文化
研究素材としての文房具
筆 文字を生み出すアジアのペン
墨 記録を伝える悠久のインク
硯 現代に残る筆記の記憶
書写材料 文字を体現するメディア
書写の実験考古学
文房具を使った人とその場所
文房具が使われた社会
参考文献
【2024年9月6日 【入荷】【ご注文承り中】
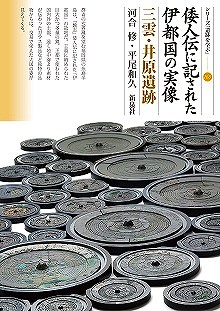
書籍番号
82406
書 名
倭人伝に記された伊都国の実像 三雲・井原遺跡
シリーズ
(シリーズ「遺跡を学ぶ」168)
データ
A5 96頁
ISBN/ISSN
978-4-7877-2338-3
編著者
河合 修・平尾和久著
出版年
2024年9月
出版者
新泉社
価 格
1,870円(税込)
群青の玄界灘を望む福岡県の糸島半島は、「魏志」倭人伝に記された
「伊都国」の故地だ。王墓に納められた巨大かつ多量の鏡、王都で使
われた国内外の土器、遠く地中海より素材が伝わったガラス製品など
独特の品物からは、交易で栄えた大国の姿が見えてくる。
───────────────────────────────
(シリーズ「遺跡を学ぶ」)は下記のURLより出版社サイトでご覧いた
だけます。
https://www.shinsensha.com/iseki/
───────────────────────────────
第1章 鏡の王国と「魏志」倭人伝
1 鏡の王国
2「倭人伝」に記された伊都国の姿
1 稲作開始のころ
2 王権誕生への胎動
1 三雲南小路王墓の発掘
2 三雲南小路王墓の出土品
3 被葬者像を探る
4 幻の王墓・井原鑓溝遺跡
5 伊都国域の墓制
6 最後の伊都国王墓・平原王墓
7 平原王墓の出土品
8 平原王墓の時代
1 三雲・井原遺跡の規模と変遷
2 三雲・井原遺跡を特徴づける出土品
1 海と陸のネットワークを探る
2 拠点的な弥生集落
3 これからの三雲・井原遺跡
【2024年8月30日 【入荷】【ご注文承り中】
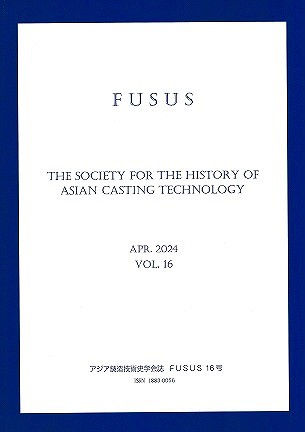
書籍番号
82374
書 名
アジア鋳造技術史学会誌 FUSUS 16号
シリーズ
データ
A4 103頁
ISBN/ISSN
1883-0056
編著者
FUSUS編集委員会
出版年
2024年4月
出版者
文物出版社
価 格
2,200円(税込)
二系統 :松本圭太
15 東京国立博物館所蔵の中国北方(商代)の鐸・円筒金具のポ
リゴンデータ解析による技法研究 :高濱 秀、三船
温尚
29
二里頭期・二里岡期爵の鋳型構造と製作技法
:内田 純子、樋口
陽介、廣川 守、山本 堯、新郷 英弘
43 古代侯馬陶范与現代石膏模具技法的対比分析
:万 俐、田 建花、戈 暢
47 ポリゴンデータのフィッティング球解析による泉屋博古館
所蔵青銅鏡の面反りと製作技術の検討 :廣川
守、三船温尚
61
三角縁神獣鏡製作の実態把握と工人および工人集団の同異
:清水 康二、清水 克朗、字野 隆志
71 出光美術館所蔵金鋼如来五尊像の3Dポリゴンデータ分析に
よる形状の特色と鋳造技法
:三宮千佳、三船温尚
85
享保7年は(1722)銘の長野市善光寺の鋳銅地蔵菩薩坐像とそ
の原型の享保8年(1723)銘の横浜市光明寺木造地蔵菩薩坐像
のポリゴンデータ比較による鋳造技術と生産体制の検討
:三船
温尚、杉本 和江、村田 愛加、三宮 千佳
101 アジア鋳造技術史学会 第12・13回表彰審査結果(中国支部)
:劉 煜、陳 建立、廉 海萍
103 アジア鋳造技術史学会 第13回表彰審査結果(日本支部)
:黒澤 浩、児島 大輔、比佐 陽一郎、釆睾 真澄
【2024年8月30日 【入荷】【ご注文承り中】
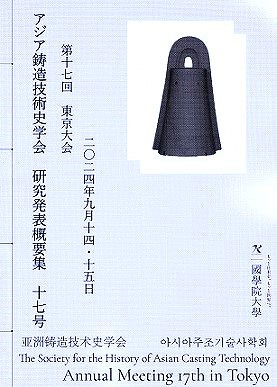
書籍番号
82381
書 名
アジア鋳造技術史学会研究発表概要集 第17号 2023 東京大会
シリーズ
データ
A4 68頁
ISBN/ISSN
編著者
出版年
2024年8月
出版者
アジア鋳造技術史学会
価 格
1,100円(税込)
高濱秀/三船温尚
中国北方系錂のポリゴンデータ解析
Mai SUZUKI/Yoshiyuki IIZUKA
Metalwork Techniques on
Forged Horse Ornaments from Khitan:
Focus on the Collection
Stored in the Equine Museum of Japan
李情情/万俐/軒超
江南宋元出土青銅器祷造工芸的探討
王漢卿
“蘇州片”刻版術的復原研究(上)
内田純子/廣川守/三船温尚/樋口陽介/新郷英弘/山本堯
二里岡~殷墟一期爵の母模技術
鈴木舞/三船温尚
殷周青銅器の設計規格についての一試論
―黒川古文化研究所蔵小克鼎からの検討―
常逸航/楊歓/杜静楠/楊軍昌
基于定量計算的中国古代陶范中草木灰的鋳造功能研究
楊歓/房明慧/何毓霊/楊軍昌
基于考古学観察與凝固模擬的亜長牛尊造工芸研究
楠惠美子/渡邊緩子/隅英彦/平尾良光/深澤太郎
國學院大學所蔵伝滋賀県大岩山出土銅鐸の鉛同位体比分析
―突線鈕式銅鐸からみた弥生時代中期末から後期における青銅器の
製作と埋納―
鄧穎[女睫-目]/楊歓/房明慧/杜静楠/楊軍昌
中原地区夏商青銅容器鉛含量変遷研究
張穎/劉煜/羅二虎
風箱背漢墓出土銅器的成分、工芸与砿料来源
川村佳男
青銅製浄瓶の形態と製作技法の遷移に関する初歩的研究
―内視鏡カメラによる内面の観察を踏まえて―
川辺敬子/オレガリオ・マルティン・サンチェス
西南イベリア半島タルテッソス時代の梨形水瓶蝋型分鋳技法について
の研究
鈴木瑞穂/井上義也/山崎悠郁子/武末純一
須玖遺跡群における鋳造鉄器および鋳造系の鉄素材の利用について
張周瑜/陳建立/張鳳
[シ繩-糸]池窖蔵鉄[金華]冠与鉄板的工芸特点研究
周霊美
濟州島供養工芸の文化史的意義
松本隆
善明寺鉄造阿弥陀如来坐像の鋳造技法の想定
宮崎甲
鋳造仏における分割木造原型の内抜き法―関鋳物師遺物仏像木型―
長柄毅一/三船温尚/杉本和江
江戸大仏鋳造過程における湯流れ、凝固過程の検証
【2024年8月23日 【入荷】【ご注文承り中】
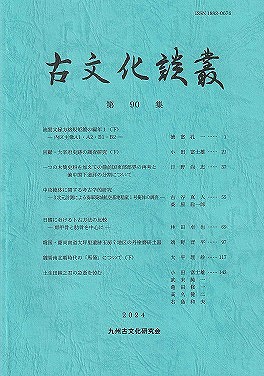
書籍番号
82378
書 名
古文化談叢 第90集
シリーズ
データ
B5 160頁
ISBN/ISSN
1883-0676
編著者
武末純一編集
出版年
2024年8月
出版者
九州古文化研究会
価 格
2,200円(税込)
―内区主像A1・A2・B1・B2― 徳 富 孔 一
…… 1
回顧・大宰府史跡の調査研究(下) 小 田 富士雄 ……
21
備中国下道評の分割について 日 野 尚 志 ……
37
―3次元計測による海軍築城航空基地稲童1号掩体の調査―
古 谷 真 人 …… 55
柴 原 聡一郎
日韓におけるト占方法の比較
―肩甲骨と肋骨を中心に― 林 田 卓 也
…… 69
韓国・慶尚南道大坪里遺跡玉房7地区の丹塗磨研土器
端 野 晋 平 …… 97
武 末 純 一
亀 田 修 一
高 久 健 二
右 島 和 夫
【2024年8月8日 【入荷】【ご注文承り中】
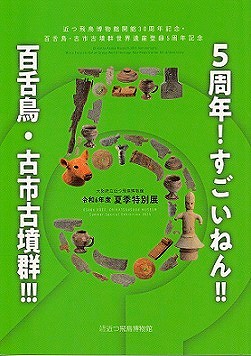
書籍番号
82367
書 名
5周年! すごいねん!!
百舌鳥・古市古墳群!!!
シリーズ
(令和6年度夏季特別展 近つ飛鳥博物館開館30周年記念 百舌鳥・古市古墳群世界遺産登録5周年記念)
データ
A4 110頁
ISBN/ISSN
編著者
大阪府立近つ飛鳥博物館編集
出版年
2024年7月
出版者
大阪府立近つ飛鳥博物館
価 格
1,700円(税込)
登録されました。古墳群が世界遺産登録から5周年を迎えることを記念
して、今夏、古墳群についてより多くの方に知っていただくため、特別
展を開催します。
特別展では、登録後を中心とする近年の発掘調査成果を中心に展示す
ることで、古墳群の価値と魅力、そして調査・研究の最前線をお伝えし
ます。(博物館HPより抜粋)
【2024年7月24日 【入荷】【ご注文承り中】
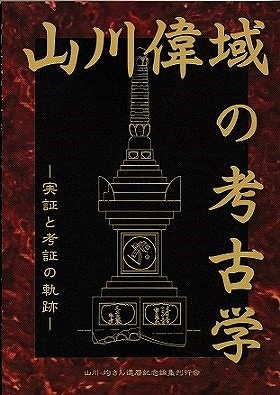
書籍番号
82357
書 名
山川偉域の考古学―実証と考証の軌跡―
シリーズ
データ
A4 113頁
ISBN/ISSN
編著者
山川均さん還暦記念論集刊行会
出版年
2024年5月
出版者
価 格
3,300円(税込)
目次
著作目録 …………………………………………………………………
9
【献呈論文】
山陰地域における弥生時代前期の環濠遺跡について
……………… 三宅 和子 15
陸地となった玉名牟田旧地形復元の試み―古代以前の玉名牟田―
………………
宇田 員将 23
因能馬場と賀野構跡 ………………………………………… 南 憲和
31
大和上庄南城の縄張構造に関する一考察 ………………… 金松
誠 35
城壁に見る張り出し施設の機能とその伝播についての基礎的考察
―福建省に所在する城郭遺跡を中心に― ………… 山本 正昭
41
尾呂志地区の城館跡 ……………………………………… 鐸木
厚太 49
平安京内における物流拠点
―平安京左京九条三坊九町の発掘調査を通して― … 佐藤
亜聖 57
いわゆる「板金剛」について―基礎的様相の検討とその存在意義―
……………… 本村 充保
65
益田市周辺における中世後期の石塔の様相―宝篋印塔を中心に―
……………… 佐伯 昌俊 73
軒丸瓦にみる笵型形状と身体動作に関する試論
―置塩城跡出土軒丸瓦の検討から― ……………… 山下 大輝
81
松浦武四郎の礎
―「一畳敷」九十一廃大安寺五重塔上壇(東口沓脱石)について―
…………… 伊藤 敬太郎 87
河内長野市における日本遺産の活用について ………… 山川 綾子
95
山川塾のススメ …………………………………………… 関広
尚世 99
【コラム】
内山瓦窯跡 ……………………… 本村 充保(写真提供:武田 浩子) 105
原田遺跡
………………………………………………… 荒木 浩司 106
筒井城 ………………………………………………… 下大迫 幹洋
107
中国石造物調査 …………………………………………… 佐藤 亜聖
108
平城京十条関連遺跡(平城京南方遺跡) ………………… 佐藤 亜聖
109
『日本石造物辞典』と山川さん ………………………… 佐藤 亜聖
111
【2024年7月23日 【品切】
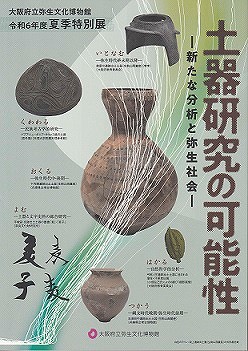
書籍番号
82360
書 名
土器研究の可能性-新たな分析と弥生社会-
シリーズ
(令和6年度夏季特別展 大阪府立弥生文化博物館図録77)
データ
A4 116頁
ISBN/ISSN
編著者
大阪府立弥生文化博物館編集
出版年
2024年7月
出版者
大阪府立弥生文化博物館
価 格
広く世界各地で出土し、時代や地域によってさまざまな特徴をもつ
土器は、年代をはかる「ものさし」あるいは地域と地域のつながり
を示す指標として重視され、考古学のもっとも基本的な分析対象の
一つとされています。
その研究の歴史は古く、膨大な成果が積み重ねられてきましたが、
近年、自然科学、民族考古学、文字史料との総合研究など、新たな
視点に基づく多様なアプローチが試みられています。
本展では、このような土器研究の新たな展開を紹介したうえで、個
性的な粘土と高度な技術を用いて生産され、弥生時代像の解明にお
いて重要な位置を占めてきた、生駒山西麓産(いこまやませいろく
さん)土器について検討を行います。この土器群の生産・流通を新
たな視点から捉えなおし、その背景にある弥生社会の特質に迫ります。
2 もくじ・凡例
3 ごあいさつ
4 プロローグ
8 第Ⅰ部 土器研究の新展開
9 第1章 はかる―自然科学的分析―
16 第2章 くわわる―民族考古学的研究―
(コラム)土器が回る?
人が回る?
24 第3章 よむ―土器と文字史料の総合研究―
(コラム)弥生時代絵画の解釈
28 第Ⅱ部 生駒山西麓産土器の展開
29 第4章 つかう―縄文時代晩期・弥生時代前期―
36 第5章 おくる―弥生時代中・後期―
(コラム)弥生博所蔵・船橋遺跡出土土器の性格
(コラム)模倣された生駒山西麓産の壺
50 第6章 いとなむ―弥生時代終末期以降―
(コラム)生駒山西麓産土器にかんする研究の歴史
60 エピローグ
63 特別論考・論考
64 籾圧痕の背後に見えるもの
―土器に隠された穀物の探求とその意義―
熊本大学大学院教授 小畑弘己
74 土器の民族考古学的研究の可能性
早稲田大学文学部准教授 中門亮太
84 器名考証研究から生活用具論へ
―土器を語るための二つのコトバ―
奈良文化財研究所 室長 森川 実
98 生駒山西麓産土器と二上山産サヌカイト
大阪府立弥生文化博物館 館長 禰冝田佳男
108 図版目録
109 出品目録
111 主な参考文献
115 展示にかかわる遺跡地図
116 お世話になった関係者・機関
【2024年7月22日 【入荷】【ご注文承り中】
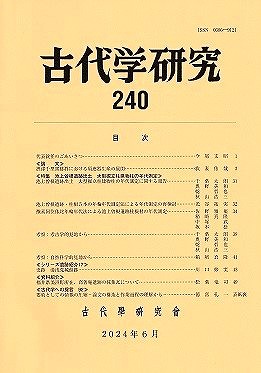
書籍番号
82356
書 名
古代学研究 第240号
シリーズ
データ
B5 60頁
ISBN/ISSN
0386-9121
編著者
古代学研究編集局
出版年
2024年6月
出版者
価 格
990円(税込)
代表就任のごあいさつ……………………………今 尾 文
昭 1
≪論 文≫
摂津千里窯跡群における須恵器生産の展開
…我 妻 佑 哉 3
≪特集 池上曽根遺跡出土 大型掘立柱建物柱の年代測定≫
池上曽根遺跡出土 大型掘立柱建物柱の年代測定に関する報告
…千 葉 太 朗
31
奥 野 美 和
乾 哲 也
秋 山 浩 三
池上曽根遺跡・柱根5本の年輪年代測定法による年代測定の再検討
…光 谷 拓 実
32
酸素同位体比年輪年代法による池上曽根遺跡柱根材の年代測定
…佐 野 雅 規
34
箱 﨑 真 隆
中 塚 武
坂 本 稔
考察:考古学的見地から ……………………… 千 葉 太 朗
39
奥 野 美 和
乾 哲 也
秋 山 浩 三
考察:自然科学的見地から……………………… 箱 﨑 真 隆 41
≪シリーズ遺跡紹介17≫
史跡 湯浅党城館跡
…………………………… 川 口 修 実 43
≪資料紹介≫
福井県美浜町所在、高善庵遺跡の採集瓦について
……… 松 葉 竜 司 49
≪古代学への提言 92≫
要約としての情報の圧縮-論文の構造と作業過程の理解から-
………………徳富孔一 表紙裏
【2024年7月22日 【入荷】【ご注文承り中】
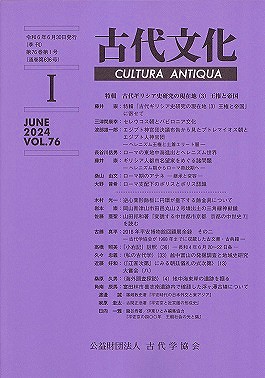
巻頭カラー図版
岡山県津山市田邑丸山2号墳出土の三角縁神獣鏡(1)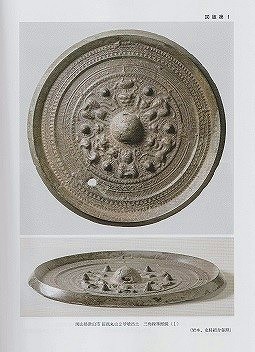
書籍番号
82352
書 名
古代文化 第76巻 第1号(636号)
シリーズ
データ
B5 146頁
ISBN/ISSN
0045-9232
編著者
出版年
2024年6月
出版者
古代学協会
価 格
2,970円(税込)
に寄せて
三津間康幸;セレウコス朝とバビロニア文化
波部雄一郎:エジプト神官団決議布告から見たプトレマイオス朝と
エジプト人神官団
-ヘレニズム王権と土着工リート層-
長谷川岳男:ローマの東地中海進出とヘレニズム世界
藤井 崇:ギリシア人都市名望家をめぐる諸問題
―ヘレニズム期から口一マ帝政期へ-
桑山 由文:口一マ期のアテネ-継承と変容-
大野 普希:ローマ支配下のポリスとポリス認識
…………………………………………………………………
木村 光一:逆心葉形飾板に円環が垂下する飾金具について
岩本 崇:岡山県津山市田邑丸山2号墳出土の三角縁神獣鏡
佐藤 亜聖:山田邦和著「変貌する中世都市京都 京都の中世史7」
を読む
古藤 真平:2018年平安博物館回顧展余録 その二
-古代学協会が1968年までに収蔵した古文書・古典籍-
高橋 照美:『小右記』註釈(36)-長和4年6月20~22日条-
久々 忠義:〈私の古代学〉(33) 越中富山の発掘調査と地域史研究
近藤 好和:〈『江家次第』にみる朝廷儀礼の式次第〉(13)
大嘗会(八)
桑原 久男:〈海外調査探訪〉(4)地中海東岸の遺跡を掘る
角南 辰馬:富田林市喜志南遺跡内で確認した浮ヶ澤古墳について
渡邊 誠:篠崎敦史著『平安時代の日本外交と東アジア』
家原 圭太:古閑正浩著『平安京と近京圏の形成史』
日向 ー雅:朧谷寿著/伊東ひとみ編集協力
『平安京の四〇〇年 王朝社会の光と陰』
【2024年7月22日 【重版・再入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82355
書 名
古代学と遺跡学―坂靖さん追悼論文集―
シリーズ
(重版)
データ
A4 537頁 巻頭カラー図版
ISBN/ISSN
978-4-600-01393-6
編著者
坂靖さん追悼論文集刊行会
出版年
2024年2月
出版者
坂靖さん追悼論文集刊行会
価 格
5,800円(税込)
巻頭図版
目次
<特別収録>
寺口千塚古墳群(平石谷川地区)第1次調査とその問題点
―とくに多葬の問題について― 坂 靖
1
葛城川扇状地における縄文時代中・後期の遺跡動態 小泉翔太
9
西北九州の朝鮮半島系筒形容器に関する覚書 岡部裕俊
21
長崎県原の辻遺跡にみる大型砥石の二相 水野敏典
29
扇状地・低中位段丘における古墳時代集住遺跡群形成の過程
―「坂モデル」についての覚書―
若林邦彦 37
近江湖南地域における古墳時代前期の鍛冶
大道和人 45
弥生墳丘墓と前期古墳の性格の相違
―上器配置と玉類副葬の様相から―
三好 玄 53
副葬品配置から見た玉の副葬―玉副葬の変化を考える―
廣瀬時習 61
定型化以前の直弧文
杉山拓己 69
古墳時代前期における円筒埴輪の型式変化
―いわゆる「極狭口縁」を中心に―
宇野隆志 77
五色塚古墳出上埴輪の割付技法
村瀬 陸 85
佐紀古墳集団と南山城
古川 匠 93
葛城王朝と欠史八代―初期ヤマト政権の動向をめぐって―
米川仁一 101
空中写真を利用した墳形の再検討
―大和高田市所在茶臼山古墳を例として―
北中恭裕 111
葛城山麓の古墳を考える―首長墓の選地から―
千賀 久 115
物部氏の首長層居宅
小栗明彦 121
南郷遺跡群の論点―坂靖説の検討―
青柳泰介 129
ヤマト王権の鉄器生産論と南郷遺跡群
村上恭通 139
南郷角田遺跡出上の小鉄片再考
―遺跡出土の鍛造剥片・金属片との比較から―
真鍋成史 143
南郷角田遺跡出土の小札状鉄製品 吉村和昭
151
南郷遺跡群の銅製品について 平井洸史 155
南郷遺跡群における古墳時代中期の山陰東部系土器 中野 咲 163
大県・大県南遺跡の古墳時代中期の鍛冶工房の再検討 田中清美 171
古墳時代の金工品に共有される文様
―日韓の心葉形唐草文を素材に― 山本孝文 181
渡来系鉄製農具刃先の「定着」と「非定着」
―又鍬先・又鋤先、サルポ形刃先、タビ形刃先― 魚津知克 189
紀伊における両頭金具の受容と展開―弓矢儀礼創出素描― 佐藤純一 197
紀伊の製塩土器 田中元浩 207
初期群集墳序説―兵庫県播磨地域の様相から― 阿部 功 215
鳥取県米子市宗像1号墳・5号墳のトレース図 森下浩行 223
備前邑久地域の首長墳とその経済的基盤 亀田修一 233
黒井峯遺跡におけるムラの姿と馬の相関
―黒井峯遺跡Ⅱ・Ⅲ群の再検討を通して― 深澤敦仁 243
上野一之宮・貫前神社周辺の古墳時代後期遺跡 右島和夫 251
群像のなかの太鼓形埴輪
―和歌山市・井辺八幡山古墳の事例を中心に― 松田 度 259
岩橋千塚のヒレ付き円筒台―跪坐人物埴輪の一例として― 丹野 拓 267
九州地方の盾持ち人埴輪の実態 岡﨑晋明 275
『東京人類学会雑誌』掲載の人物埴輪 日高 慎 283
ネリー・ナウマンの「人物埴輪論」を読む 川崎 保 291
古墳時代の動物毛利用の実態を知るための基礎的研究
―奈良県内古墳出土品を例として― 奥山誠義 239
香久山と畝傍山
―原材料としての鉄バクテリア塊の史的意義― 髙橋幸治 307
高取町内検出の大型大壁建物 木場幸弘 315
出土状況からみた三重県北野遣跡出土の有孔広口筒形土器 川崎志乃 319
陶棺のサイズに関する一試考
―近畿地域と告備地域の比較を中心に― 絹畠 歩 325
小山田古墳と舒明天皇陵 清水康二 333
「宜用小石」の石槨について―大化薄葬令と高安山1号墳― 米田敏幸 341
阪神地方枢要部の「権力核」的地域形成過程をめぐる一考察
―古墳時代首長系譜の様相から古代前半期の官衙領域確立に向けて―
森岡秀人 349
南郷遺跡群周辺の古代 大西貴夫 361
畝傍山麓の古代寺院―大窪寺と山本寺の建立背景― 清水昭博 369
南河内の土師器椀生産―宮都への供給という観点から― 木村理恵 377
飛鳥京跡苑池にみる二つの流水施設 東影 悠 385
藤原宮の幢幡図像について 塚田良道 393
宮殿構造からみた伊勢神宮・斎宮の成立
―前期難波宮と皇大神宮・斎王宮殿域の連関― 川部浩司 401
古代志摩国の原像―海産物生産の一断面― 穂積裕昌 411
益田池の復元 北山峰生 419
日本における鬼門の導入と展開 岡見知紀 427
図像からみた古代絵馬の特質―出土絵馬を中心に― 前田俊雄 433
大和国西京瓦屋についての一考察―尻江田瓦屋を中心に― 岡田雅彦 441
春秋戦国時代長平之戦いの兵士埋葬坑について 神谷正弘 449
朝鮮半島青銅器文化と社会 宮里 修 455
韓国ソウル夢村土城を理解するための新資料 權五榮(李東奎訳) 463
百済漢城期における諸墓制の木棺復元 金武重(平郡達哉訳) 469
百済食器にみる飲食文化 韓志仙(中野咲訳) 477
韓半島海洋祭祀遺跡調査研究の動向 平郡達哉 485
百済大通寺の創建瓦―公州班竹洞出土瓦を中心に― 李炳鎬(井上直樹訳) 493
朝鮮時代における鍛冶工房跡の分布と官営製鉄の特徴
―高興・鉢浦萬戸城の製鉄工房跡を中心に― 金 想 民 505
プレ・アンコール期の土器編年構築に向けた予察
―サンボー・プレイ・クック遺跡出土資料を中心として― 本村充保 513
メラネシアにおける巨石遺跡の消長と社会変化
―ソロモン諸島ロヴィアナ地域を事例として― 長岡拓也 519
ユニバーサル・ミュージアムの取り組みについて
―橿原考古学研究所附属博物館の事例― 北井利幸 527
あとがき
【2024年7月18日 【入荷】【ご注文承り中】
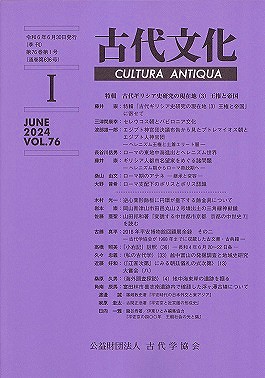
巻頭カラー図版
岡山県津山市田邑丸山2号墳出土の三角縁神獣鏡(1)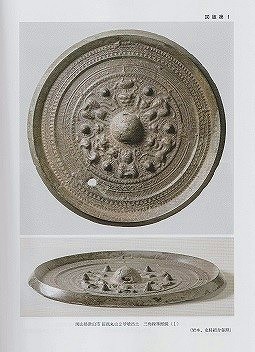
書籍番号
82352
書 名
古代文化 第76巻 第1号(636号)
シリーズ
データ
B5 146頁
ISBN/ISSN
0045-9232
編著者
出版年
2024年6月
出版者
古代学協会
価 格
2,970円(税込)
に寄せて
三津間康幸;セレウコス朝とバビロニア文化
波部雄一郎:エジプト神官団決議布告から見たプトレマイオス朝と
エジプト人神官団
-ヘレニズム王権と土着工リート層-
長谷川岳男:ローマの東地中海進出とヘレニズム世界
藤井 崇:ギリシア人都市名望家をめぐる諸問題
―ヘレニズム期から口一マ帝政期へ-
桑山 由文:口一マ期のアテネ-継承と変容-
大野 普希:ローマ支配下のポリスとポリス認識
…………………………………………………………………
木村 光一:逆心葉形飾板に円環が垂下する飾金具について
岩本 崇:岡山県津山市田邑丸山2号墳出土の三角縁神獣鏡
佐藤 亜聖:山田邦和著「変貌する中世都市京都 京都の中世史7」
を読む
古藤 真平:2018年平安博物館回顧展余録 その二
-古代学協会が1968年までに収蔵した古文書・古典籍-
高橋 照美:『小右記』註釈(36)-長和4年6月20~22日条-
久々 忠義:〈私の古代学〉(33) 越中富山の発掘調査と地域史研究
近藤 好和:〈『江家次第』にみる朝廷儀礼の式次第〉(13)
大嘗会(八)
桑原 久男:〈海外調査探訪〉(4)地中海東岸の遺跡を掘る
角南 辰馬:富田林市喜志南遺跡内で確認した浮ヶ澤古墳について
渡邊 誠:篠崎敦史著『平安時代の日本外交と東アジア』
家原 圭太:古閑正浩著『平安京と近京圏の形成史』
日向 ー雅:朧谷寿著/伊東ひとみ編集協力
『平安京の四〇〇年 王朝社会の光と陰』
【2024年7月16日 【入荷】【ご注文承り中】
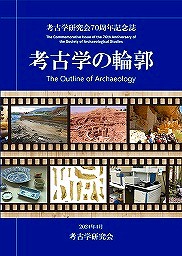
書籍番号
82351
書 名
考古学の輪郭
シリーズ
(考古学研究会70周年記念誌)
データ
B5 255頁
ISBN/ISSN
編著者
考古学研究会編集
出版年
2024年4月
出版者
考古学研究会
価 格
2,000円(税込)
─────────────────────────────────
第1章 考古学と現代社会 ・関森想
1「日本」考古学の特質
10 考古学と刊行物・広報・データ
・岡村勝行 ベース・高田祐一
・溝ロ孝司 ・芝康次郎
・平川ひろみ
2 埋蔵文化財行政と考古学
第2章 日本と世界の考古学
・肥後弘幸 11 東アジア世界からの視点
・南 健太郎
・山本孝文
3 考古学と博物館
・向井佑介
・吉田 広 12
東南アジア考古学からの視点
・瀬谷今日子
・丸井雅子
・魚津知克
・小野林太郎
4 考古学と学校教育 13
南アジア考古学からの視点
・八田友和
・上杉彰紀
・村野正景
14 中央アジア考古学からの視点
・佐古和枝
・久米正吾
5 考古学と地域コミュニティ
・山内和也
・松田 陽 15
太平洋諸島からの視点
・坂本和也
・石村智
・柏原正民
・島﨑達也
6 考古学とマスメディア
・山野ケン陽次郎
・中村俊介 16
極北・東北アジア世界からの視点
・今井邦彦
・高瀬克範
7 陵墓の保全と学際研究
・高倉 純
・福尾正彦 17
西アジア考古学からの視点
・中久保辰夫
・三宅 裕
8 世界遺産と考古学
・有松 唯
・中澤寛将 18
北米大陸の考古学からの視点
・飯塚信幸
・羽生淳子
9 考古学と遺跡保存
・佐々木憲一
・鈴木重治 19
中南米大陸の考古学からの視点
・禰冝田佳男
・青山和夫
・渥美賢吾
・渡部森哉
・三好裕太郎
………………………………………………………………………………………
20
欧州考古学からの視点
・仁木 宏
・ロラン・ネスプルス 32
近世における考古学と文献史
・堀内秀樹
神話学 33
近現代における考古学と保存問題
21
旧石器時代・縄文時代と民族学
・野﨑貴博
・三好元樹
・出原恵三
・吉田泰幸
・若槻真治
22 縄文時代研究と狩猟採集民の民族誌 34
考古学と美術史学
・根岸
洋
・畑中英二
23
考古学と民俗学
・藤原貞朗
・角南聡一郎
24
考古学と地理学・景観学 第5章 考古学と理学・分析科学
・山口雄治 35
放射性炭素年代測定
・寺村裕史
・小林謙一
25
考古学と神話学 36
分析科学(金属 青銅器)
・後藤
明
・戸塚洋輔
・齋藤 努
第4章 考古学と歴史学・美術史学 37
分析科学(金属 鉄器)
26
弥生時代における考古学と文献史 ・塚本敏夫
・森岡秀人
・鈴木瑞穂
・寺前直人 38
分析科学(胎土)
・渡邉義浩
・中園 聡
27
古墳時代における考古学と文献史 ・白石
純
・小森哲也 39
分析科学(玉類)
・古市 晃
・大坪志子
28
飛鳥時代における考古学と文献史 ・田村朋美
・松本建速 40
自然科学的分析科学(石材)
・向井一雄
・森 貴教
・大熊久貴 41
分析科学(顔料)
29 奈良・平安時代における考古学と文献史
・西本和哉
・高橋照彦 42
分析科学(アスファルト)
・馬場
基
・上條信彦
30
中世における考古学と文献史 43 三次元計測
・佐藤亜聖
・青木 弘
・中井淳史
・桜井英治
31 戦国織豊期城郭・都市研究における考古学と
文献史学
・岡寺 良
………………………………………………………………………………………
第6章 考古学と環境学・地球科学 52 DNA分析からみた考古学
44
考古学と古気候変動
・神澤秀明
・小野
昭
・安達 登
・井上智博 53
考古学からみたDNA分析
・中塚
武
・谷口康浩
45
考古学と感染症学
・清家 章
・瀧川
渉 54
考古学と植物学1:植物遺存体から
・長岡朋人 みた生活環境
46
考古学と地質学
・佐々木由香
・別所秀高
・那須浩郎
・趙
哲済
55 考古学と植物学2:植物圧痕から
47
考古学と災害 みた生活環境
・相原淳一
・小畑弘己
・斎野裕彦
・山下優介
48
考古学と森林科学
56 考古学と動物学1:動物遺存体から
・中原
計 みた海産資源利用
・樋上
昇
・丸山真史
49
考古学と海洋学
・黒住耐二
・佐々木蘭貞
57 考古学と動物学2:動物遺存体から
みた陸産資源利用
第7章 考古学と自然人類学
・山崎 健
50
形質人類学的研究1
・江田真毅
・端野晋平 58
動物の考古生化学からみた食環境
・奈良貴史
・渋谷綾子
・波田野悠夏
・庄田慎矢
51
形質人類学的研究2
59 植物の考古生化学からみた生活史
・中川朋美
・日下宗一郎
・萩原康雄
・板橋 悠
【2024年7月16日 【入荷】【ご注文承り中】
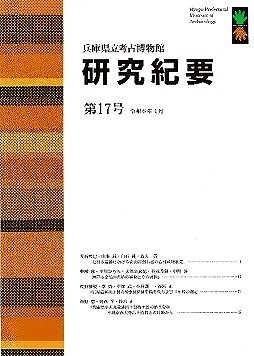
書籍番号
82346
書 名
兵庫県立考古博物館研究紀要 第17号
シリーズ
データ
A4 323頁(精装)
ISBN/ISSN
編著者
兵庫県立考古博物館編集
出版年
2024年3月
出版者
兵庫県立考古博物館
価 格
1,650円(税込)
序 菱田哲郎
「七日市遺跡における安山岩製石器の石材産地推定」…………
1
「神戸市念仏山古墳の埴輪とその評価」 ……………………… 13
佐野雅規・李 貞・中塚 武・小林謙一・篠宮 正
「岩屋遺跡出土材の酸素同位体年輪年代および14C年代の測定」
………………………37
「兵庫県小犬丸遺跡出土製塩土器の胎土分析
―平城京西大寺出土資料との比較から」…………………55
【2024年7月16日 【入荷】【ご注文承り中】
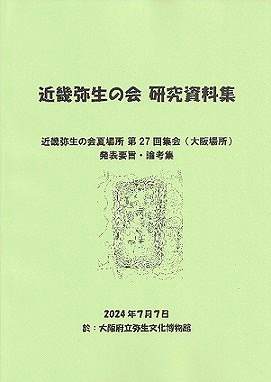
書籍番号
82350
書 名
近畿弥生の会夏場所
第27回集会(大阪場所)発表要旨・
論考集
シリーズ
(近畿弥生の会研究資料集)
データ
A4 164頁
ISBN/ISSN
編著者
近畿弥生の会編集
出版年
2024年7月
出版者
近畿弥生の会
価 格
1,100円(税込)
-弥生時代中期後葉から後期の方形周溝墓-」
……………… 5
後川 恵太郎(公益財団法人大阪府文化財センタ-)
発表2 京都府「京都市中久世遺跡の調査
-中・後期の居住域-」 ………… 17
渡邊 都季哉(公益財団法人京都市埋蔵文化財研究所)
発表3 滋賀県「栗東市霊仙寺・北中小路遺跡の調査
-弥生時代末から古墳時代初頭の周溝付建物・棟持柱付建物を
複数検出-」
……… 29
佐伯英樹(公益財団法人栗東市スポーツ協会)
発表4 奈良県「田原本町阪手東遺跡の調査
-弥生時代中期の方形周溝墓群-」 ………… 43
清水琢哉(田原本町教育委員会)
発表5 和歌山県「和歌山平野の弥生時代水田2例
-友田町遺跡と井辺遺跡-」 …………
67
菊井佳弥(奈良市教育委員会)
発表6 兵庫県「川西市加茂遺跡の調査
-弥生時代中期の台地上の集落-」 ………… 83
朝井琢也(川西市)
-論考集-
【論文】
「奈良県内における周溝墓葬制の基礎的検討
-弥生中期を対象として-」 蓮井 寛子 ………
91
「弥生時代後半期における暴力の痕跡」 荒田
敬介 ………117
【研究ノート】
「有鉤銅釧の製作時期に関する予察」
叶井 陽 ………133
「大阪湾岸域における凸帯文土器から遠賀川式土器への移行過程」
春名 英行 ………145
「打製尖頭器の機能分化と分類」
園原 悠斗 ………155
【2024年7月16日 【入荷】【ご注文承り中】
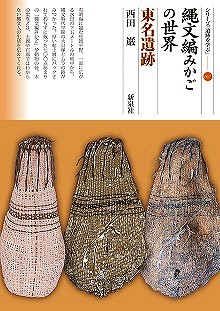
書籍番号
82345
書 名
縄文編みかごの世界 東名遺跡
シリーズ
(シリーズ「遺跡を学ぶ」167)
データ
A5 96頁
ISBN/ISSN
978-5010-7767-0
編著者
西田 巌著
出版年
2024年8月
出版者
新泉社
価 格
1,870円(税込)
有明海に臨む佐賀平野、一面に広がる水田の下五メートルの地中から、
縄文時代早期の大貝塚とムラの跡がみつかった。厚い粘土層にパック
されて朽ちずに残った七〇〇点あまりの「縄文編みかご」や動物の骨、
木の実などは、土器や石器ではわからない縄文人の生活を伝えてくれ
る。
(シリーズ「遺跡を学ぶ」)は下記のURLより出版社サイトでご覧いた
だけます。
https://www.shinsensha.com/iseki/
───────────────────────────────
【目次】
第1章 地中深くに貝塚が
1 奇跡の発見
2 居住域の調査(一次調査)
3 湿地性貝塚の調査(二次調査)
1 奇跡的にそろった三つの環境
2 居住域の遺構
3 貝層を調べる
4 貝塚に残されたもの
5 湿地に残されたもの
1 列島最古・最多
2 徹底的に調べる
3 編みかごの復元
4 復元からみえてきたこと
1 東名縄文人
2 生業の移り変わり
3 ものづくりの広域交流
4 変動する環境を生きぬく
5 東名縄文人たちはどこへ
1 東名遺跡の保存
2 東名遺跡のこれから
【2024年7月16日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82344
書 名
日韓古墳時代研究
シリーズ
(元韓国東洋大学校文化財発掘保存学科教授)
データ
B5 218頁
ISBN/ISSN
978-4886219879
編著者
柳本 照男著
出版年
2024年7月
出版者
同成社
価 格
9,350円(税込)
日韓の関連出土資料を分析し、相対的年代観と古墳編年を再検証。
さらに特徴的な遺物に考察を加え、3~5世紀の日朝関係を追究する。
序章 本書の構成と時代・時期区分
【2024年6月14日 【入荷】【ご注文承り中】
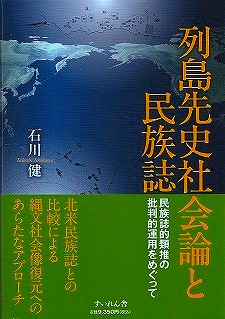
書籍番号
82236
書 名
列島先史社会論と民族誌
シリーズ
データ
A5 392頁 (上製本)
ISBN/ISSN
978-4-86369-731-7
編著者
石川 健著
出版年
2024年5月
出版者
株式会社 すいれん舎
価 格
9,350円(税込)
第Ⅰ章 民族誌的アナロジーをめぐる問題と本書における方法および
対象
第Ⅱ章 カナダ北西海外狩猟採集民の民族誌・エスノヒストリーの
検討
第Ⅲ章 列島縄文時代の社会
―九州を中心とした後期後葉から晩期の社会―
第Ⅳ章 列島縄文時代の社会
―房総半島における中期から後期中葉の社会―
第Ⅴ章 列島先史社会とカナダ北西海岸にみる諸社会の相対化
終章 結論―相対化と民族誌の運用について―
【2024年6月13日 【入荷】【ご注文承り中】
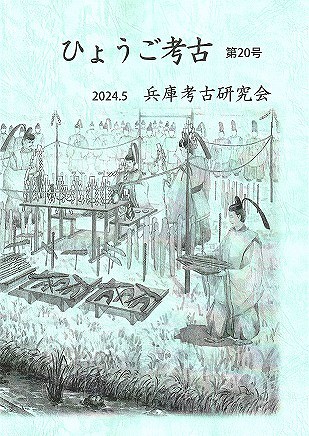
書籍番号
82314
書 名
ひょうご考古 第20号
シリーズ
データ
A4 101頁
ISBN/ISSN
編著者
兵庫考古研究会編集
出版年
2024年5月
出版者
兵庫考古研究会
価 格
1,430円(税込)
………………山口 卓也……… 1
神鍋遺跡の石錘について …………和田 長治……… 15
兵庫県・淡路国南部中の御堂銅鐸及び銅舌の徹底再観察と
展望の二、三 ………………森岡 秀人……… 21
柱状体部を持つ弥生器台―「東備西播系器台」の設定―
………山中 良平……… 45
宍粟市山崎町宇原の「大型器台」
………………………白谷朋世・萬代和明……… 62
宍粟市山崎町宇原採集の石包丁
………友久 伸子……… 73
小野市王塚古墳出土の未報告資料の紹介
…………山本原也・横山杏里紗……… 75
小野市岩倉2号墳の三次元計測 ………山本 原也……… 83
但馬出土遺物実測記―和田長治氏採集資料など―
…………………渡辺 昇……… 93
【2024年6月12日 【品切】
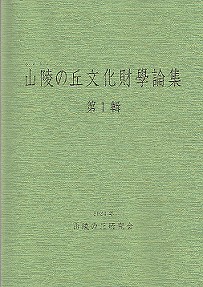
書籍番号
82309
書 名
山陵の丘文化財學論集 第1輯
シリーズ
データ
A4 228頁
ISBN/ISSN
編著者
出版年
2024年4月
出版者
山陵の丘研究会
価 格
3税込)
粟原寺・石位寺と額田王 東野 治之………
1
橿原土偶と馬場川土偶
-近畿地方における縄文晩期土偶の編年と系統- 岡田 憲一……… 6
大分県出土の縄文時代石錘 横澤
慈……… 17
船岡遺跡の再検討-遺跡の再評価と土器製塩における
遺跡内分業の観点から- 松葉 竜司………
27
斎宮の造営過程における古墳の削平 小原 雄也………
38
横穴式石室の壁体構築技術に関する試行的検討
-奈良県 三ツ塚12号墳の事例-
髙野 学……… 45
六角(菱形)[土専]仏考-旧壱志郡天花寺廃寺出土資料から-
和氣 清章……… 59
都城形土師器と布留式甕の関係性に対する予察
三好美穂・小森俊寛……… 67
平城京の重圏・重郭文軒瓦をめぐって
原田憲二郎……… 84
王宮中枢正殿群の系譜-藤原宮大極殿後殿に関連して-
相原 嘉之……… 95
奈良市北室町出土の土師器台付皿とその出土地に関する考察
-奈良春日社祭儀土器の研究(2)- 池田
裕英……… 107
古代山城の築城技術に関する一様相
-北部九州の神籠石系山城を中心に- 大庭 孝夫……… 119
飛騨における中世土師器皿の分類と変遷 三好 清超………
128
若狭における[土専]列建物について 西島 伸彦………
140
キリスト教信仰普及と中世地域社会の一断面
-中世石塔からみた野津院の動向- 神田 高士……… 145
奈良県香芝市所在屯鶴峯日本軍地下壕について
-地表面調査を中心に- 伊藤
厚史……… 158
新潟県笛吹田遺跡出土の琴柱形石製品 山岸 洋一………
169
筑紫・宮地嶽古墳の被葬者
花田 勝広……… 172
大分県内における近世城下町総構えの構造に関する覚書
吉田 和彦……… 182
対 談
「水野正好
古墳を語る」 水野正好先生と語り合う会……… 193
【2024年6月10日 【入荷】【ご注文承り中】
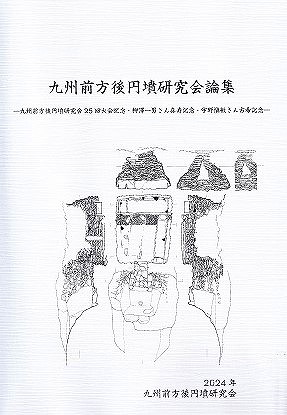
書籍番号
82307
書 名
九州前方後円墳研究会論集
シリーズ
―九州前方後円墳研究会第25回大会記念・柳澤一男さん喜寿記念・宇野愼敏さん古稀記念―
データ
A4 277頁
ISBN/ISSN
編著者
九州前方後円墳研究会編集
出版年
2024年6月
出版者
九州前方後円墳研究会
価 格
3,960円(税込)
柳澤一男さん近影
字野愼敏さん近影
論集刊行にあたって思いつくままに 田中 裕介
論集刊行にあたって 杉井 健
宗像地域における古墳時代首長墓の動向 ………………池ノ上 宏
01
成川式土器の甅形小型壺 …………………………………大西 智和
11
延岡平野部の古墳時代墓制について ……………………甲斐 康大
21
筑紫君磐井の乱勃発の真因について ……………………蒲原 宏行
29
墳丘の内に石を見出すこと ………………………………小嶋 篤
39
佐賀県東部地域における古墳時代終末期の大型石室 …小松 譲
47
竹並横穴墓群の刀剣秩序と京都平野の軍事的特質 ……齊藤 大輔
57
阿蘇谷における古墳築造系譜試論 ………………………杉井 健
67
有明海・八代海沿岸地域の家形石棺 ……………………高木 恭二
77
福岡県福津市久末出土の装飾付須恵器とその周辺 ……田上 浩司
87
九州島東海岸における古墳時代小型丸底製塩土器 ……田中 裕介
95
墳端外側テラスについての一考察 ………………………玉川 剛司
105
遠賀川流域における前期の小型古墳と集団墓 …………田村 悟
115
有明海沿岸地域の古墳時代前期墳墓の築造 ……………檀 佳克
125
―石人山古墳以前の八女古墳群の理解に向けて―
豊前地域における拠点集落の一様相 ……………………長 直信
131
―黒田畑堀遺跡2区における厩舎遺構の発見とその意義―
北部九州における装飾古墳の築造とその背景 …………辻田 淳一郎 141
宮崎県都城市菓子野2007-1号地下式横穴墓出土のイモガイ製釧
………………中村 友昭
151
下那珂馬場古墳の検討―採集資料の紹介を通して― …西嶋 剛広
161
島内114号地下式横穴墓出土の龍文銀象嵌大刀
………橋本 達也 169
新聞から読む大分の考古学―消滅した南大分の古墳群―
………………服部 真和 179
前方後円墳と豪族居館の方位と天文景観―赤塚古墳と小部遺跡の検討―
………………弘中 正芳
189
佐賀県下における外来系瑪瑙製玉類の出土傾向 ………渕ノ上 隆介
199
九州・近畿地方における古墳時代集落の立地とその変動
………………古川 匠
205
筑紫平野北部の三国丘陵上の古墳と集落と馬飼い(予察)
………………宮田 浩之
215
北九州における海岸部古墳について ……………………宮元 香織
223
南九州西沿岸部における板石積石棺墓の変遷 …………三好 栄太郎
233
御塔山古墳と周辺集落との関係 …………………………吉田 和彦
243
山崎砂丘遺跡出土の特殊扁壷について …………………和田 理啓
253
………………………………………………………………………………………
柳澤一男さん 字野愼敏さん 略年譜・著作目録・記念写真 …………259
柳澤一男さん 略年譜 ……………………………………………………261
柳澤一男さん 著作目録 …………………………………………………262
字野愼敏さん 略年譜 ……………………………………………………267
宇野愼敏さん 著作目録 …………………………………………………268
九州前方後円墳研究会。柳澤一男さん・宇野愼敏さん 写真 …………273
【2024年6月10日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82308
書 名
ビワノクマ古墳 2
シリーズ
―昭和30年(1955)の緊急発掘調査及び墳丘確認調査の報告―
データ
A4本文83頁
カラー・モノクロ図版24頁
ISBN/ISSN
編著者
出版年
2024年3月
出版者
行橋市教育委員会
価 格
3,190円(税込)
ビワノクマ古墳は、昭和30(1955)年5月に、福岡県行橋市延永区の
戦没者墓地造成中に発見され、当時の九州大学文学部国史学教室の鏡
山猛先生が中心となり発掘された。発掘には、九州大学文学部考古学
研究室第1代助手の渡邉正氣先生、第2代助手の小田富士雄先生も参加
されている。昭和33(1958)年6月に九州大学文学部考古学研究室が設立
されるに至り、それらの資料が国史学研究室から考古学研究室に移管
・収蔵され、今日に至っている。
昭和30(1955)年の第1次調査後、平成21(2009)年の行橋市教育委員会に
よる墳丘測量調査の第2次調査以来、平成23(2011)年の第5次調査に至
る墳丘の発掘調査により、ビワノクマ古墳は古墳時代前期の墳長約50m
の前方後円墳であることが明らかとなった。この度、行橋市教育委員会
では、ビワノクマ古墳の第1次調査の発掘報告書を刊行することとし、
令和3(2021)年度から令和5(2023)年度の報告書刊行事業を実施している。
九州大学考古学研究室では、これまで平成元(1989)年に福岡市老司古墳、
平成5(1993)年に福岡県京都郡苅田町番塚古墳、平成27(2015)年に福岡
県飯塚市山の神古墳の発掘報告書を刊行してきた。この度、ビワノクマ
古墳の発掘報告書を刊行できることを誠にうれしく思う次第である。整
理調査に当たっては、発掘調査に当たられた小田富士雄先生を中心に、
辻田淳一郎准教授をはじめとした九州大学考古学研究室の室員が協力す
る形で、進めることができた。
られるが、それに次ぐ古墳時代前期の首長墓としてビワノクマ古墳を見
なすことができる。本古墳は竪穴式石槨であり、副葬品として鏡、刀剣、
鉄鏃、靫、甲冑小札などが存在する。本報告書ては、現在の古墳時代研
究の水準に照らして、それぞれの遺物の学術的価値を最大限に位置づけ
ることを試み、ビワノクマ古墳の遺跡としての評価、ならびに歴史的な
位置づけを行っている。この試みを以て、永く発掘報告書を公開してこ
なかった責めを塞ぎたい。そして、ビワノクマ古墳が行橋市民の歴史的
な遺産として今後も永く顕彰されることを願っている。最後に、甲冑小
札の整理を担当していただいた福岡市埋蔵文化財センターの松﨑友理さ
んに感謝したい。
九州大学大学院人文科学研究院考古学研究室 宮本一夫
(本書「序」より転載)
第1節 地理的環境 ……………………………………………………
1
第2節 歴史的環境 ……………………………………………………
3
第2章 調査の経過と経緯
第1節 発掘
………………………………………………………… 7
第2節 第1次調査 ……………………………………………………
7
第3節 県史跡への指定 ………………………………………………
7
第4節 行橋市教育委員会による墳丘確認調査 ……………………
9
第5節 第1次調査の報告書刊行へ
………………………………… 10
1.
延永ビワノクマ古墳調査について(行橋市) ………………… 12
2.
埋蔵文化財発掘調査届出書(行橋市) ………………………… 13
3.
福岡県文化財指定申請書(福岡県) …………………………… 15
4.
福岡県行橋市琵琶隈古墳(日本考古学年報) ………………… 16
第1節 墳丘の調査と復元
(1)第2~5次調査の概要 …………………………………………… 17
(2)後円部墳丘の追加調査(第7次調査)の成果 …………………
20
第2節 内部主体(埋葬施設)
(1)石室上面の状況 …………………………………………………
24
(2)石室内部の構成と石積>
……………………………………… 24
(3)石組からみた石室形成過程 …………………………………… 28
第3節 遺物出土状況 …………………………………………………
24
第1節 鏡 ………………………………………………………………… 31
第2節 装身具 …………………………………………………………
33
第3節 武器
(1)素環頭大刀 ………………………………………………………
34
(2)鉄剣 ……………………………………………………………… 35
(3)鉄鏃 ………………………………………………………………
36
第4節 武具
(1)靫 …………………………………………………………………
37
(2)小札式甲冑 ……………………………………………………… 40
第5節 封土より出土した遺物
(1)鏡 …………………………………………………………………
53
(2)鉄斧 ……………………………………………………………… 53
(3)土器 ………………………………………………………………
54
第5章 総括
第1節 墳丘と内部主体 ………………………………………………
57
第2節 遺物>
………………………………………………………… 58
1.土壙墓の調査―豊前京都郡発見の木蓋土壙と無蓋土壙― …… 60
2.ビワノクマ古墳墳丘下出土の箱式石棺 …………………………
65
3.ビワノクマ遺跡出土人骨の形質的特徴
………………………… 67
【2024年6月10日 【入荷】【ご注文承り中】
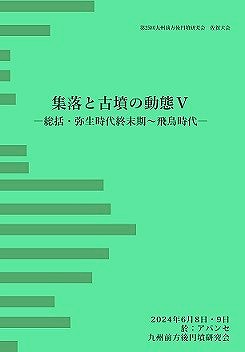
書籍番号
82273
書 名
集落と古墳の動態 Ⅴ―総括・弥生時代終末期~飛鳥時代―
シリーズ
(第25回九州前方後円墳研究会 佐賀大会発表資料集)
データ
ISBN/ISSN
編著者
第25回九州前方後円墳研究佐賀大会実行委員会
出版年
2024年6月
出版者
第25回九州前方後円墳研究佐賀大会実行委員会
価 格
3,300円(税込)
―弥生時代終末期~飛鳥時代― ………………………
1
平尾和久・上田龍児・小嶋篤
―弥生時代終末期~飛鳥時代― ……………………… 41
小嶋篤・中島圭・山崎賴人
徳富孔一・塩見恭平・土井翔平
野澤哲朗
肥後における集落と古墳の動態、総括
―弥生時代後期後半~飛鳥時代― …………………… 129
林田和人
長直信・安部和城
弘中正芳
今塩屋毅行
と古墳 …………………………………………………………259
松﨑大嗣
―古墳時代中期末~古墳時代後期―
(第23回九州前方後円墳研究会 福岡大会発表資料集)
2022年9月 A4 467頁/
九州前方後円墳研究会福岡大会実行委員会 ¥4,400(税込)
https://www.chugoku-shoten.com/mokuji/jmokuji/81149/81149.html
●72328 古墳時代の地域間交流 2
(第17回九州前方後円墳研究会 大分大会)
2014年6月 A4 241頁/大分大会¥3,300(税込)
https://www.chugoku-shoten.com/mokuji/jmokuji/72328/72328.html
【2024年6月10日 【在庫少】【ご注文承り中】

書籍番号
72328
書 名
古墳時代の地域間交流 2
シリーズ
(第17回 九州前方後円墳研究会 大分大会)
データ
A4 241頁
ISBN/ISSN
編著者
第17回九州前方後円墳研究会大分大会実行委員会
出版年
2014年6月
出版者
価 格
3,300円(税込)
「鏡からみた古墳時代の地域間関係とその変遷
―九州出上資料を中心として」…………………………1
渕ノ上隆介
「腕輪形石製品」
……………………………………………………27
「玉類からみた古墳時代の地或間関係
―前期の北部九州地域を中心に―」 …………………49
松浦宇哲
「古墳出上農工具からみた北部九州の地域性
―福岡県内出土事例を中心に―」 ……………………69
中村友昭
「琉球列島産貝製品からみた地或間交流」
………………………91
「甲冑から見た九州と倭王権との地域間交流」…………………115
「北部九州における装飾武器の特質とその背景」………………141
三好栄太郎
「鉄鏃からみた地或間交流」………………………………………159
「馬具からみた九州の地或間交流
―舶載馬具と国産規格品馬具に着目して―」…………188
【2024年6月5日 【入荷】【ご注文承り中】
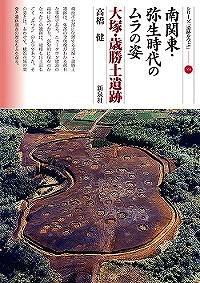
書籍番号
82306
書 名
南関東・弥生時代のムラの姿 大塚・歳勝土遺跡
シリーズ
(シリーズ「遺跡を学ぶ」 166)
データ
A5 96頁
ISBN/ISSN
978-4-7877-2336-9
編著者
高橋 健著
出版年
2024年7月
出版者
同成社
価 格
1,870円(税込)
稀有な事例である。ニュータウン建設の最中にみつかり、部分的に
保存のかなったこの遺跡は、規模も出土品もごく〝ふつう〟のムラ
であった。その姿とは。あわせて、横浜市域の開発と遺跡調査の歴
史もふり返る。
──────────────────────────────
(シリーズ「遺跡を学ぶ」)は下記のURLより出版社サイトでご覧い
ただけます。
https://www.shinsensha.com/iseki/
──────────────────────────────
【目次】
1 ムラの立地と大きさ
2 ムラがあった時代
3 ムラのかたち
4 ムラに住んだ人びと
1 方形周溝墓とはなにか
2 歳勝土遺跡の方形周溝墓
3 歳勝土遺跡と大塚遺跡
1 鶴見川・早渕川流域の弥生時代遺跡
2 集落をめぐる議論
3 稲作をめぐる問題
1 戦後横浜の考古学
2 港北ニュータウン遺跡群の調査
3 大塚・歳勝土遺跡を残す
【2024年5月27日 【入荷】【ご注文承り中】
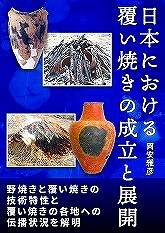
書籍番号
82289
書 名
日本における覆い焼きの成立と展開
シリーズ
データ
A4 382頁
ISBN/ISSN
979-8884912366
編著者
岡安 雅彦著
出版年
2024年3月
出版者
Independently
published
価 格
5,500円(税込)
と考えられてきた。しかし、近年では弥生土器は覆い焼きで焼成され
ていることが明らかとなってきた。
本書は野焼きと覆い焼きの技術的な特性について説明するとともに、
日本において、覆い焼きが北部九州に伝わった後、各地にいつ伝播し
ていったのかを、各県40点、合計1,936点の弥生土器・土師器のカラ
ー写真を使って紹介した。その他補足写真・図版も含めて使用した
点数は合計2,262点に上る。土器焼成技術と覆い焼きの伝播に関する
概要を1冊で理解できるものとなっている。
【目次】
第1章 野焼きから覆い焼へ 製作技術と焼成技術………………3
(1)野焼き型黒斑と覆い型黒斑……………………………………4
(2)黒斑の形成過程
(3)土器の製作工程…………………………………………………6
① 粘土採取………………………………………………………7
② 成形……………………………………………………………8
③ 施文・調整 …………………………………………………10
(4)土器の焼成
① 覆い型黒斑の特徴
…………………………………………12
② 土器の焼成遺構
……………………………………………14
③ 焼成粘土塊
…………………………………………………15
④ 破裂痕
………………………………………………………17
⑤ 火襷
…………………………………………………………18
⑥ 内面黒斑
……………………………………………………19
⑦ 民族事例に見る覆い焼き-タイ-
………………………20
⑧ 民族事例に見る覆い焼き-中国-
………………………21
⑨ 野焼きの焼成方法
…………………………………………22
⑩ 焼成実験による異斑の残存状況(野焼き)
………………28
⑪ 覆い焼きの焼成方法 ………………………………………26
⑫ 焼成実験による黒斑の残存状況(灰覆い焼き) …………28
(5)覆い焼きの成立と各地への波及 …………………………30
第2章 各地の様相
…………………………………………………37
福岡県・・39 佐賀県・・・49
長崎県・・59 熊本県・・65
大分県・・71
宮崎県・・77 鹿児島県・・83 愛媛県・・89
高知県・・95 香川県・ 101
徳島県・ 107 山口県・・ 113
島根県・ 119 鳥取県・
125 広島県・ 131 岡山県・ 137
兵庫県・・ 143 大阪府・
149 奈良県・ 157 和歌山県 163
京都府・ 169 滋賀県・・ 175
福井県・ 181 石川県・ 187
三重県・ 193 岐阜県・
199 愛知県・・ 205 静岡県・ 213
富山県・ 219 新潟県・
225 長野県・ 231 山梨県・・ 237
神奈川県 241 東京都・
249 埼玉県・ 255 千葉県・ 261
群馬県・・ 267 栃木県・
273 茨城県・ 279 福島県・ 285
宮城県・ 291 山形県・・ 297
岩手県・ 303 秋田県・ 309
青森県・ 315 北海道・
321
第3章 野焼きから覆い焼きへ その技術と伝播…………………327
掲載資料所蔵先・出典一覧……………………………………371
あとがき…………………………………………………………377
【2024年5月25日 【近刊】【ご注文承り中】
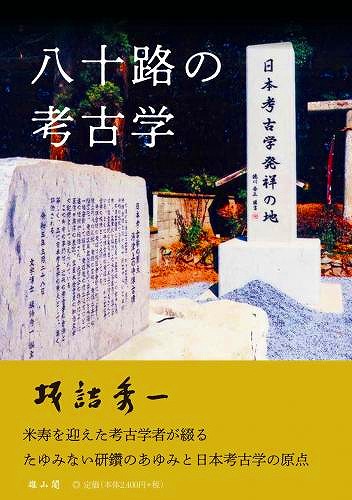
書籍番号
82255
書 名
八十路の考古学
シリーズ
データ
A5 226頁
ISBN/ISSN
978-4886219466
編著者
坂詰秀一著
出版年
2024年5月
出版者
(株)雄山閣
価 格
2,640円(税込)
◎戦後の日本考古学を牽引してきた第一人者坂詰秀一が、日本考古学
の歩みを振り返
る!
◎学界の要職を歴任、「考古学ジャーナル」や「季刊考古学」など数々
の専門誌の創
刊に関わり、誰よりも学史に精通する長老格。“学界の生き字引”に
よる貴重な回顧録は研究者なら必読!
◎米寿を迎えてなお、研鑽を続ける研究姿勢―考古学を志す若い読者に
こそ触れてほしい「坂詰考古学」の精華!
【目次】
Ⅰ 考古学史を考える
(1)日本考古学の原点
(2)「日本考古学発祥の地」副碑の撰文
(3)戦後60年、考古学研究の歩み(年表)
(4)戦後の考古学研究の歩みと歴史学
(5)斎藤 忠と日本考古学史
(6)閑却の「日本考古学史」のこと
(7)明治時代の考古学を思う
(8)『國史大辭典』(初版)と考古学
(9)忘却の或る考古学研究者
(10)「関東学生考古学会」のこと
(11)日本考古学における学際研究の回顧
思う-
(2)月刊『考古学ジャーナル』創刊50周年の回想
(3)『季刊考古学』創刊時の指向
(4)『仏教考古学事典』新装版(坂詰秀一編)編者言
(5)『新日本考古学辞典』(江坂輝弥・芹沢長介・坂詰秀一編)刊行に際
して
(6)『武蔵野事典』(武蔵野文化協会編)刊行の辞
(7)『品川区史 2014』刊行にあたって
(8)『伊東市史』の編さんに思う
(9)『伊東市史』史料編の完結
(10)新しい(府中)市史を編さんにあたって
(11)『府中市史を考える』(第1号)巻頭言
(1)日本考古学界の動向(2018~2022)・総論
(2)日本考古学と用語
(3)所謂「64体制」の以前と以後
(4)考古学研究と著作権問題
(5)コロナ禍と考古学
(6)埋蔵文化財と「観光考古学」
(7)近現代を考古学する
(8)「考古企業」への期待
(9)追悼
1 追悼 竹内 誠先生
2 大塚初重先生 追悼の辞
3 追悼 戸田哲也氏
4 関 好延さんを偲んで
(1)私の立正考古学人生
(2)カピラ城跡を探る-ティラウラコット発掘余話-
(3)来し方 八十路の考古回想
(4)私の高校考古
(5)「考古ボーイ」の頃
(6)職業としての考古学
(7)「宗教考古学」彷徨録
(8)頽齢渇望録
(9)節節の感慨
1 ポスト定年の日日
2 ポスト定年の考古学
3 「喜寿」を迎えて
4 八十路の考古学
5 「傘寿」を迎える
6 立正大学特別栄誉教授の感懐
7 考古学史の重要性
(10)「傘寿」を過ぎし日々-過日録抄-
1 平成乙未(平成27.2015)
2 平成丙申(平成28.2016)
3 平成丁酉(平成29.2017)
4 平成戊戌(平成30.2018)
5 平成己寅(平成31-令和元・2019)
6 令和庚子(令和2.2020)
7 令和辛丑(令和3.2021)
8 令和壬寅(令和4.2022)
1 The Greater East Asia Co-Prosperity Sphere
and Archaeology in
Japan
2 Excavation at Lumbini in
Nepal
【2024年5月25日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82272
書 名
遊牧国家 匈奴の歴史と文化遺産
シリーズ
データ
B5 300頁
ISBN/ISSN
978-4639029854
編著者
ゲレグドルジ エレグゼン/梁時恩著
大谷育恵訳
出版年
2024年5月
出版者
(株)雄山閣
価 格
9,900円(税込)
紀元前3世紀以降、蛮族として中国史書に登場し、中国王朝との
対立抗争と和睦を繰り返してきた騎馬遊牧民匈奴の知られざる
実像を、近年の進展著しい発掘調査の成果と400点を超える文化
遺産のカラー写真を通して明らかにする。
【目次】
1. 匈奴の歴史的背景
2.
匈奴の政治制度
3. 匈奴の領域と外交
4. 匈奴人
第Ⅱ章 匈奴の文化遺産
1. 匈奴の墓地遺跡
2.
匈奴の生活を伝える遺産
3. 匈奴時代の岩画
第Ⅲ章 匈奴の物質文化
1. 衣服と装身具
2. 土器と容器
3.
馬具と馬車
4. 武器
5.
織物
6. 遊具、楽器、線刻画
【2024年5月23日 【入荷】【ご注文承り中】
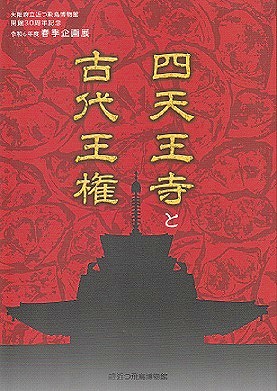
書籍番号
82280
書 名
四天王寺と古代王権
シリーズ
(近つ飛鳥博物館開館30周年記念 令和6年度春季企画展・図録89)
データ
A4 79頁
ISBN/ISSN
編著者
大阪府立近つ飛鳥博物館編集
出版年
2024年4月
出版者
大阪府立近つ飛鳥博物館
価 格
1,210円(税込)
にいたるまで法灯が守り伝えられているわが国でも貴重な歴史遺産の一
つです。四天王寺は、中央集権国家の基礎が築かれ、大陸からの先進文
化の受け入れが盛んだった飛鳥時代の初めに創建されました。北には外
交の玄関口にあたる難波津を擁し、洗練された仏教文化を対外的に示す
役目を果たしていました。聖徳太子が建立したとして有名ですが、創建
以来、その時々の政治体制の変化に応じて伽藍の整備・改修が繰り返さ
れたことはあまり知られていません。四天王寺の伽藍造営の歴史は、わ
が国の政治体制の変遷を物語ってくれるのです。
今回の展示では、出土瓦の最新研究からわかってきた飛鳥時代から平安
時代初めの四天王寺の歴史をご紹介します。小さな瓦の破片が紡ぐ壮大
なストーリーをご覧ください。(本展示会案内より抜粋)
第一章 四天王寺と上宮王家
……………………………………… 14
第二章 四天王寺と難波政権 ………………………………………
28
第三章 四天王寺と律令国家形成鞏の政権
……………………… 36
第四章 四天王寺と聖武天皇
……………………………………… 43
第五章 四天王寺と称徳・道鏡政権 ………………………………
53
第六章 四天王寺と平安の新都造営
……………………………… 61
第七章 四天王寺と橘氏 ……………………………………………
66
エピローグ
【2024年5月21日 【入荷】【ご注文承り中】
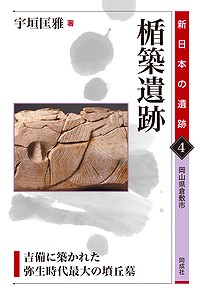
書籍番号
82270
書 名
楯築遺跡 吉備に築かれた弥生時代最大の墳丘墓
シリーズ
(新日本の遺跡 4)
データ
四六版 142頁
ISBN/ISSN
978-4886219862
編著者
宇垣 匡雅著
出版年
2024年6月
出版者
同成社
価 格
1,980円(税込)
いかなる役割を果たしたのか。発掘成果から時代の節目を読み解く。
第1部 遺跡の概要―楯築墳丘墓とは―
第2章 墳丘と構造物
第3章 円礫堆
第4章 中心埋葬
第5章 大量の土器
第6章 遺跡の特性
第8章 出土遺物
第9章 弧帯文石
第10章 出土遺物と墳丘の築造
第11章 遺跡のその後と整備・周辺案内
…………………………………………………………………………………
(新日本の遺跡シリーズ●既刊・〇近刊)
(新日本の遺跡 1)
大坪 志子著/2023年11月 四六版 146頁 ¥1,980(税込)
https://www.chugoku-shoten.com/mokuji/jmokuji/82022/82022.html
2024年3月 四六版 154頁 ¥1,980(税込)
https://www.chugoku-shoten.com/mokuji/jmokuji/82176/82176.html
(新日本の遺跡 3)
大村 浩司著 2024年5月 四六版 136頁 ¥1,980(税込)
https://www.chugoku-shoten.com/mokuji/jmokuji/82254/82254.html
【2024年5月17日 【入荷】【ご注文承り中】
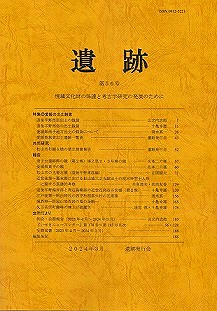
書籍番号
82258
書 名
遺跡 第56号 特集◎愛媛の出土銭貨
シリーズ
データ
A4 188頁
ISBN/ISSN
0912-5221
編著者
十亀幸雄編集
出版年
2024年3月
出版者
遺跡発行会
価 格
2,200円(税込)
特集◎愛媛の出土銭貨
道後平野南部の出土銭貨
………………………… 十亀幸雄 11
愛媛県南予地方出土の銭貨について …………… 清水真一
26
愛媛県銭貨出土遺跡一覧表 ……………………
遺跡発行会 43
共同研究
松山市打越古墳の墳丘測量報告 ……………… 遺跡発行会 52
唐子台遺跡群の鏡(第2報)雉之尾2・3号墳の鏡
……………… 名本二六雄 57
愛媛県東予の鏡 …………………………… 名本二六雄 60
松山市の主要古墳(道後平野東部編) ……………
正岡睦夫 71
近世後期~幕末期における松山城三之丸跡出土の座天神型士人形
に関する基礎的考察 ……………… 幸泉満夫・前田友香 129
道後平野海岸部と周辺島嶼部の近世花崗岩石切場(第2報)
…… 十亀幸雄 139
江戸後期~明治時代の西宇和郡真穴村の瓦産業…
清水真一 156
境界神―四国山地西部の鬼の金剛― ……………
十亀幸雄 165
久万高原町霧峰の棟上げ破魔矢
…… 遠部 慎・十亀幸雄 178
会所だより
例会・会務報告(2023年4月~2024年3月) …… 山之内志郎 185
『いせきニュースレター』第174号~第185号目次 …… 56・128
受贈図書(2023年4月~2024年3月) ………………………… 188
編集後記 ……………………………………………………… 188
【2024年5月17日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82274
書 名
遠の朝廷 大宰府〔改訂版〕
シリーズ
(シリーズ「遺跡を学ぶ」第4期 076)
データ
A5 96頁
ISBN/ISSN
978-4-7877-2246-1
編著者
杉原 敏之著
出版年
2024年6月
出版者
新泉社
価 格
1,870円(税込)
筑紫の地に、律令国家の巨大な官衙、大宰府が成立する。大陸を望
む西の要衝で外交や軍事を担い、西海道諸国島を統治した、政庁を
中枢とする遠の朝廷(とおのみかど)大宰府の実像を明らかにする。
近年の発掘調査の成果をふまえ確かな歴史像を描く、<改訂版>
………………………………………………………………………………
(シリーズ「遺跡を学ぶ」)は下記のURLより出版社サイトでご覧
いただけます
https://www.shinsensha.com/iseki/
………………………………………………………………………………
【目 次】
第1章 古都・大宰府
1 古都大宰府の風景
2 風景の源
1 大宰府政庁の発掘
2 甦る大宰府政庁
3 大宰府の成立はいつか
1 国防の最前線・筑紫
2 平野を遮断する水城
3 巨大な朝鮮式山城・大野城
1 大宰府の官衙・大宰府庁域
2 大宰府条坊の復元
3 古代都市・大宰府
1 府の大寺・観世音寺
2 大陸と西海の文化
3 古代大宰府の終焉
1 先学者たち
2 大宰府史跡の歩み
【2024年5月16日 【品切】
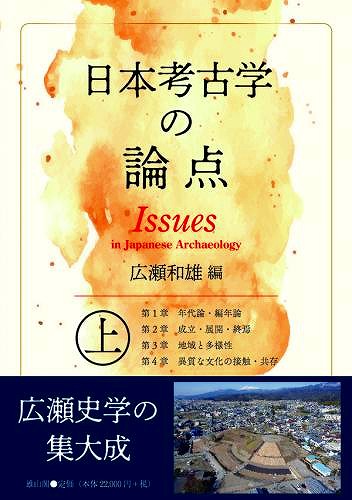
書籍番号
82252
書 名
日本考古学の論点(上)
シリーズ
データ
B5 506頁 (上製本)
ISBN/ISSN
978-4639029830
編著者
広瀬和雄編
出版年
2024年5月
出版者
(株)雄山閣
価 格
執筆者120名超の大論集、ついに刊行 最新の研究成果を通覧、
日本考古学の現在地をみる。
上巻(目次)
日本考古学の論点㊤
はじめに~広瀬史学を未来へ~ 山中 章
序 章
古墳時代研究の論点
―新しい古墳時代像と前方後円墳国家― 広瀬和雄
第1章 年代論・編年論
縄紋時代の年代
―縄紋土器型式編年の実年代化における論点―
小林謙一
弥生時代の暦年代―弥生早・前期を中心に― 藤尾慎一郎
古墳出土土器と古式土師器の編年研究 山本 亮
古墳時代の時期区分と埴輪編年 廣瀬 覚
円筒埴輪編年研究の現状と課題 辻川哲朗
円筒形埴輪の消滅 河内一浩
須恵器編年について
白石耕治
埼玉古墳群と出土須恵器 酒井清治
青銅鏡からみた古墳時代編年 林 正憲
古墳時代甲冑の形式・編年・年代論提要 橋本達也
考古年代測定における自然科学的研究法の活用 今村峯雄
21世紀の炭素14年代法 坂本 稔
濃尾平野における弥生墳丘墓の多様性 島田崇正
前方後円墳出現と畿内弥生社会 禰冝田佳男
箸墓古墳の段築構造と墳形規格 梅本康広
桜井茶臼山古墳の銅鏡群と倭王の性格 福永伸哉
前方後方墳の墳丘形態・形状について
―近畿地域の基礎分析― 熊井亮介
倭王権の播丹戦略―大型前方後円墳をどうみるか―
岸本道昭
古墳時代社会複雑化の地域的差異 佐々木憲一
奈良盆地の首長墳における畿内型石室変遷の仕組みとその背景
………………太田宏明
横穴式石室の展開に関する一考察
―畿内と濃尾地方の事例から― 鈴 千夏
群集墳論の探究 中井正幸
後期群集墳における集団形成 細川修平
葛城地域の群集墳にみる土器配置の多様性 東影 悠
新沢千塚古墳群と石光山古墳群の検討
―ヤマト王権とのかかわりについて― 深谷 淳
群集墳の形成と展開―摂津三島の群集墳から―
内田真雄
茨城県那珂市白河内古墳群1号墳と虎塚古墳の関連性について
………………生田目和利
東国横穴墓群形成に関する一試考(1) 松崎元樹
横穴と末期古墳―古墳時代の終末にかんする試論― 菊地芳朗
前方後円墳から方墳へ
―大王墳の墳形変化をめぐる論点の整理― 高橋照彦
第3章 地域と多様性
畿内大弥生・古墳社会の空間構造 一瀬和夫
畿内における前方後円墳造り出しの地域性 髙木清生
東日本の大型化する壺形埴輪
―磯浜古墳群出土埴輪の理解に向けて― 蓼沼香未由
下毛野摩利支天塚古墳の築造位置
秋元陽光
古墳時代の東と西 右島和夫
古代国家形成期における在地勢力の競合
―那須国造碑の建立と後期古墳から― 眞保昌弘
墳丘規模・数からみた関東地方後・終末期首長墓 小森哲也
総社古墳群と山王廃寺 前原 豊
古代伊勢・国境の地理学―辿りついたら多度― 竹内英昭
美濃地域の後期古墳の地域性
―石材の使用方法から地域を考える― 森島一貴
集落遺跡が示す首長墓の出現過程
―キビ地域をケーススタディとして― 草原孝典
前方後円墳の分布からみた倭政権と吉備
平井典子
交流する山陰 変化する弥生墓制 肥後弘幸
北陸における布掘り柱掘形をもつ掘立柱建物の性格について
―石川県上荒屋遺跡の検討を中心にして― 髙橋浩二
ヒスイ玉生産からみた吹上遺跡の成立
湯尾和広
九州における古墳文化の受容と横穴系埋葬施設の創出
―研究史を中心に― 蒲原宏行
皆と私の縄文文化研究の半世紀
―埋蔵文化財行政と縄文研究の歴史― 岡村道雄
海と山から見た弥生時代の四国
柴田昌児
中国鏡と列島先史社会の評価 上野祥史
白山信仰と記紀神話 小路田泰直
壊された古墳、遺された古墳―平城京を例として― 土居規美
古墳文化と貝塚時代後期文化
―大隅諸島における様相― 石堂和博
古墳文化と続縄文文化・貝塚文化
―境界から見る文化と人間集団― 藤沢 敦
魏晋南北朝考古からみる日本古墳文化
藤井康隆
東アジア都市史と日本の古墳文化 妹尾達彦
建築史と考古学 玉井哲雄
考古学と民俗学―柳田国男の塚・古墳論を中心に― 市川秀之
考古学と歴史学と民俗学の学際協業の有効性について
―律令的神祇祭祀の萌芽― 新谷尚紀
【2024年5月16日 【入荷】【ご注文承り中】
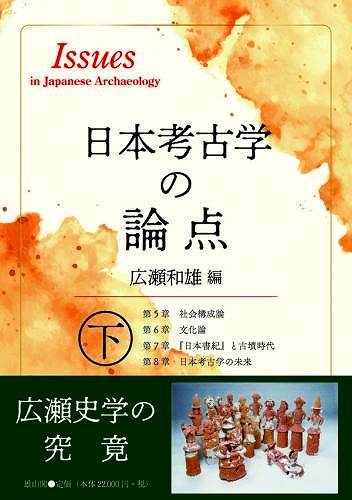
書籍番号
82253
書 名
日本考古学の論点(下)
シリーズ
データ
B5 534頁 (上製本)
ISBN/ISSN
978-4639029847
編著者
広瀬和雄編
出版年
2024年5月
出版者
(株)雄山閣
価 格
24,200円(税込)
執筆者120名超の大論集、ついに刊行 最新の研究成果を通覧、
日本考古学の現在地をみる。
下巻
日本考古学の論点㊦
はじめに~広瀬和雄博士の喜寿を壽ぐ~ 池上 悟
弥生時代大規模遺跡形成と首長的なもの
―『万物の黎明』に刺激されて― 若林 邦彦
楯築円丘墓祭祀論―前方後円墳祭祀論のための序説― 水林 彪
死の神聖王権論 河野 一隆
古墳時代首長墓の基準について 日高 慎
天皇陵における〝夫婦同葬〟をめぐって 義江 明子
古墳時代前期の列島東部と「豪族居館」
―交換のための実利を伴う儀礼・祭祀という観点から― 田中 裕
ヒメヒコ制・二重王権制と考古学 清家 章
古代日本の紛争と戦争―部族ゾーン理論の視点から― 藤原 哲
弥生・古墳時代の木器生産
―製作技術・流通・分業の視点から― 樋上 昇
地方窯業生産の研究―備前邑久窯跡群を中心に― 亀田 修一
朱の産地推定への期待―朱の硫黄同位体分析の成果と課題―
本田 光子
集落研究と土器研究 笹栗 拓
条里遺構と条里プランの研究 金田 章裕
海洋民論 西川 修一
島嶼部の古墳からみた「海民」について 宮元 香織
海を臨む石棺墓
―茨城県ひたちなか海浜古墳群の一例― 稲田 健一
再論 環頭大刀の文献的考察 清水
みき
ヤスを模した垂飾
―大阪府国府遺跡出土首飾りのモデル― 設楽 博己
絵画土器における二者―見せる・見る絵画土器の創出と祭場 ―
藤田 三郎
古墳のコスモロジー 北條 芳隆
形象埴輪論 高橋 克壽
黒白の水鳥埴輪 賀来 孝代
棺の使用方法と他界観 柏木 善治
古代女性の結髪具について 井上 尚明
池庭造営の系譜と伝播
―平泉、鎌倉から水無瀬、再び鎌倉へ― 前川 佳代
平泉と中世都市 吉田 歓
箱根山宝篋印塔銘文の再検討 本間 岳人
東都の墳丘墓 池上 悟
古墳被葬者論―「祖」の伝承・成立と古墳― 今尾 文昭
倭の五王と百舌鳥・古市古墳群
―讚・珍・濟・興・武の墳墓を考える― 天野 末喜
聖徳太子墓を考える 安村 俊史
ヤマトタケルの出自 古市 晃
7世紀王宮構造の転換点―難波長柄豊碕宮と前後の王宮― 山中 章
日本古代王宮の源流を探る 積山 洋
都城・宮室の成立 山元 章代
7世紀の木簡・金石文と文字 高島 英之
大化前代地域支配に関する諸制度と古墳 高松 雅文
国・県・ミヤケ 舘野 和己
相模国における内陸二評の成立 田尾 誠敏
『日本書紀』による「任那」領域考 仁藤 敦史
デジタル3D計測と中世石造物研究の将来
―大和盆地周辺の厚肉彫り石仏を一例に―
山川 均
近世墓標研究にかかる協業のすすめ 三好 義三
織豊系城郭研究と考古学
―小牧山城の発掘調査成果と評価― 小野 友記子
近世瓦研究の可能性 乗岡 実
考古学研究と史跡の保存・活用
―積石塚古墳の構造研究と史跡石清尾山古墳群の保存活用計画を題
材に― 高上 拓
史跡蛭子山古墳・作山古墳「与謝野町立古墳公園」といふ歴史料理
店の経営に物思ふ 加藤 晴彦
庭園遺跡の保存と活用―樺崎寺跡浄土庭園を事例として― 足立 佳代
これからの埋蔵文化財保護行政―小考― 藤井 幸司
世界遺産 百舌鳥・古市古墳群をめぐる課題
―百舌鳥古墳群を中心に― 白神 典之
「百舌鳥・古市古墳群」世界遺産をめざして 山田
幸弘
世界遺産「百舌鳥・古市古墳群」の保存、活用、そして継承していく
意義 伊藤 聖浩
響き合う埋蔵文化財と世界遺産、そして考古学 中村 俊介
陵墓研究の現状と未来 山田 邦和
陵墓の保存と公開 久世 仁士
印西の旧石器時代―市民の遺跡探訪― 池田 耕平
古墳を歩きながら考えたこと 草野 厚
文化財と市民―地方から― 寺﨑 直利
中学校教育と考古学―学校と地域、資料館― 中濱 久喜
学校教育と考古学―高等学校における実践例を中心に― 吉村 健
高等学校歴史担当教員の「考古学リテラシー」について 石井 研吉
新聞と考古学 今井 邦彦
墳墓の探査 金田
明大
保存科学の過去・現在、そしてこれから 西山 要一
あとがき
広瀬和雄
【2024年5月16日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82271
書 名
甲斐における古墳時代地域社会の研究
シリーズ
データ
B5 272頁 (上製本)
ISBN/ISSN
978-4639029786
編著者
小林健二著
出版年
2024年5月
出版者
(株)雄山閣
価 格
15,400円(税込)
20世紀後半から現在にかけて、山梨県では古墳時代に関する多く
の研究・発掘が蓄積されてきた。
それらの成果を踏まえ、山梨県内の最新の土器編年を提示すると
ともに、年代に沿って古墳や出土遺物の変遷を追うことで、甲斐
の地域社会のあり方、他地方との関わりについても考究を進める。
序章 甲斐の地理的環境と古墳時代
第1節
甲斐の地理的環境と古墳時代/第2節 本書の目的
第1章 甲斐における古墳時代の土器様相
第1節 S字甕の定着
第2節
東海系土器の波及と定着
第3節 古式土師器の成立
第4節 北陸系土器の様相
第5節
畿内系叩き甕の様相
第6節 中期・後期・終末期の土器編年
第7節 土器編年と墳墓の変遷
第1節
甲斐天神山古墳の位置付け
第2節 大丸山古墳の埋葬施設
第3節 甲斐銚子塚古墳出土の腕輪形石製品
第4節 甲斐銚子塚古墳出土の壺形埴輪
第5節 甲斐銚子塚古墳出土の円筒埴輪
第6節 甲斐銚子塚古墳出土の木製品
第7節
中道古墳群の歴史的意義
第1節
古墳時代の周溝墓
第2節 竜塚古墳出現の背景
第1節
無袖石室の様相
第2節 甲斐の積石塚と渡来人
第1節 終末期古墳の変遷
第2節 甲斐における古墳の終焉
【2024年5月15日 【入荷】【ご注文承り中】
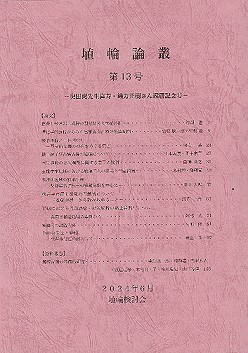
書籍番号
82256
書 名
埴輪論叢 第13号 ―奥田尚先生喜寿・鐘方正樹さん還暦記念号
シリーズ
データ
A4 135頁
ISBN/ISSN
編著者
埴輪検討会事務局編集
出版年
2024年6月
出版者
埴輪検討会
価 格
2,640円(税込)
萱振1号墳出上埴輪の割付技法と生産体制
……………………村瀨 陸 1
理化学的分析からみた富雄丸山古墳の築造期間
………柴原 聡一郎・村瀨 陸
9
猪形埴輪ノート 2024
―写実的な脚の存在をめぐる覚書― ………………………河内
一浩 23
掖上鑵子塚古墳表採の埴輪について
………………山本実慶・田中朱音 27
円筒埴輪の2次調整に関する若干の検討 ………………………白神 典之
31
王権中枢地域における埴輪工人の移動と生産組織
……木村理・廣瀬覚 44
木津川流域の埴輪生産
―薬師堂古墳出土の埴輪分析を中心に― …………………北山
大熙 57
藤井寺市澤田発見の円筒棺について
―「埋蔵物録』から読み取れること― ……………………河内
一浩 67
Ⅴ期における円筒埴輪・形象埴輪の粘上帯貼付に
―兵庫県播磨地域の事例から―
………………………………阿部 功 71
埴輪列の調査方法
…………………………………………………村瀨 陸 81
香山の嶺上と埴輪
―桜井市付近の例として―
……………………………………奥田 尚 97
【資料報告】
鶯塚古墳の基礎的研究 ……………………柴原聡一郎・村瀨陸・古谷真人
・渡辺夏海・木村日向子・水川慶紀・山口等悟 105
【2024年5月15日 【入荷】【ご注文承り中】
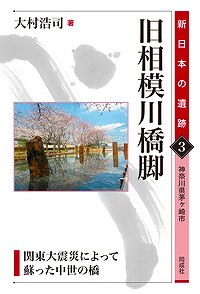
書籍番号
82254
書 名
旧相模川橋脚 関東大震災によって蘇った中世の橋
シリーズ
(新日本の遺跡 3)
データ
四六版 136頁
ISBN/ISSN
978-4886219855
編著者
大村 浩司著
出版年
2024年5月
出版者
同成社
価 格
1,980円(税込)
をもつ稀有な存在である本遺跡の特性を考古学的に解説する。
第2章 旧相模川橋脚の特徴
第4章 中世橋遺構―調査成果①
第5章 近現代遺構―調査成果②
第6章 明らかになった複合遺跡―調査成果③
第7章 地震痕跡の確認―調査成果④
第8章 遺跡の整備・活用と未来への継承
……………………………………………………………………………………
(新日本の遺跡シリーズ既刊)
(新日本の遺跡 1)
大坪 志子著/2023年11月 四六版 146頁 ¥1,980(税込)
https://www.chugoku-shoten.com/mokuji/jmokuji/82022/82022.html
2024年3月 四六版 154頁 ¥1,980(税込)
https://www.chugoku-shoten.com/mokuji/jmokuji/82176/82176.html
【2024年5月15日 【入荷】【ご注文承り中】
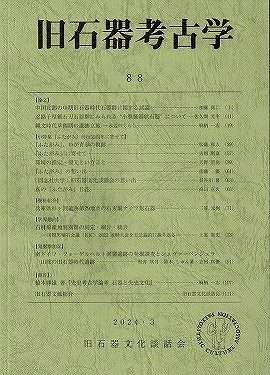
書籍番号
82257
書 名
旧石器考古学 88
シリーズ
データ
B5 114頁
ISBN/ISSN
編著者
旧石器文化談話会編集
出版年
2024年3月
出版者
旧石器文化談話会
価 格
3,850円(税込)
中国北部の中期旧石器時代石器群に関する試論 ……加藤 真二 (1)
忍路子型細石刃石器群にみられる"小型掻器状石器"について
………………佐久間 光平 (11)
縄文時代草創期の遺跡立地―水辺のくらし― ………麻柄 一志 (19)
【小特集『ふたがみ』刊行50周年に寄せて】
『ふたがみ』、わが青春の軌跡…………………………松藤 和人 (39)
『ふたがみ』に寄せて……………………………………吉朝 則富 (57)
環境の推定・復元ということ …………………………天野 哲也 (59)
『ふたがみ」の想い出 ……………………………………後藤 優 (61)
「同志社大学」旧石器文化談話会の思い出……………長谷川 豊 (63)
私の『ふたがみ』日誌 …………………………………高山 正久 (65)
【資料紹介】
兵庫県杉ヶ沢遺跡第29地点の石刃製ナイフ形石器 …三好 元樹 (71)
【学界動向】
石材原産地判別群の同定・細分・統合
―国際黒曜石会議(IOC)2023遠軽大会を方法論的に振り返る―
…………………上峯 篤史
(73)
【発掘参加記】
南ドイツ・フォーゲルヘルト洞窟遺跡の発掘調査とシュヴァーベン
ジュラ山脈の旧石器時代遺跡
……………村井 咲月・鈴本 しゅん菜・吉田 真優 (91)
【書評】
橋本勝雄著『先史考古学論考石器と先史文化』 ……麻柄 一志(107)
旧石器文献紹介…………………………………旧石器文化談話会(111)
【2024年5月11日 【入荷】【ご注文承り中】
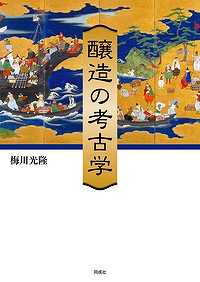
書籍番号
82248
書 名
醸造の考古学
シリーズ
データ
B5 372頁 (上製本)
ISBN/ISSN
978-4886219466
編著者
梅川 光隆著
出版年
2024年5月
出版者
同成社
価 格
13,200円(税込)
の壺にあると提起。考古学を基軸に膨大な資史料を渉猟し、技術史と
文化史の両面から日本の醸造史を論じる。
第2章 巻き包みの土器
第3章 生鮮保存の知恵
第4章 醗酵の経験から技術へ
第5章 酒造の遺構・遺物
総 括 醸造の技術史的考察
第2章 酒樽の縄巻き
第3章 名酒柳の編柳
第4章 中国東海地域の編衣
総 括 醸造の文化史的考察
【2024年5月11日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82206
書 名
古代郡司と郡的世界の実像
シリーズ
(古代史選書48)
データ
A5 360頁 (上製本)
ISBN/ISSN
978-4886219817
編著者
森 公章著
出版年
2024年4月
出版者
同成社
価 格
9,350円(税込)
8~9世紀の国郡支配の実相を出土文字資料も駆使し探究する。
第一章 畿内郡司氏族とその特質
第二章 文献史料から見た古代宗像氏の交流
第三章 出雲地域と倭王権
第四章 渡来系氏族と地域社会
第五章 木簡から見た郡家出先機関と地方支配の様相
第六章 出雲地域と「郡的世界」の実像
第七章 木簡から見た郡司・郡家の行方
【2024年5月3日 【入荷】【ご注文承り中】
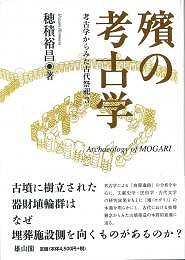
書籍番号
82246
書 名
殯の考古学
シリーズ
(考古学からみた古代祭祀
3)
データ
A5 324頁
ISBN/ISSN
978-4639029762
編著者
穂積裕昌著
出版年
2024年4月
出版者
(株)雄山閣
価 格
4,950円(税込)
考古学による「喪葬遺跡」の分析を中心に、文献史学・民俗学・古代
文学の研究成果をもとに「殯(モガリ)」の本義を明らかにし、古代に
おける喪葬観念からみた古墳築造の本質的意義に迫る。
第2章 殯をめぐる研究史―文献・民俗・考古・古代文学―
第3章 弥生後期から古墳初頭の祭祀と喪葬―大陸との比較から―
第4章 葬所としての古墳―河内黒姫山古墳にみる被葬者封じ込めの発動―
第5章 比自支和気・遊部伝承から読み解く古代の喪葬
第6章 形象埴輪の機能
第7章 古墳時代の殯所構造に関する基礎的確認
第8章 導水施設の本義
第9章 殯宮・殯所・喪屋の重層構造
第10章
飛鳥時代の殯宮―今後の飛鳥時代殯宮を考えるための整理―
終章 喪葬観念の形成と古墳時代の本質―死との関係性の再構築―
【2024年5月1日 【入荷】【ご注文承り中】
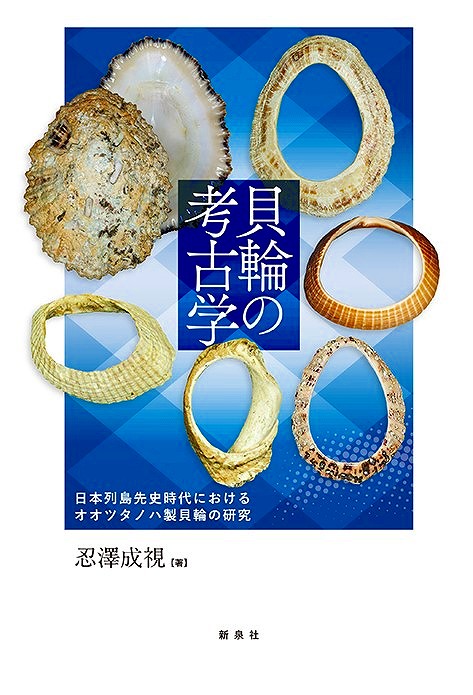
書籍番号
82198
書 名
貝輪の考古学
シリーズ
日本列島先史時代におけるオオツタノハ製貝輪の研究
データ
B5 384頁 (上製本)
ISBN/ISSN
978-4-7877-2305-5
編著者
忍澤 成視著
出版年
2024年3月
出版者
新泉社
価 格
13,200円(税込)
人々を魅了してきた。本書は、とくにオオツタノハ製貝輪に着目し、
縄文時代から弥生・古墳時代にかけての人々と貝との関わりについて、
貝塚や墓などから出土した遺物と現在の生息状況の調査結果から論じ
る。装飾品に使われた貝を調べることで、当時の習俗・交易
ルート・社会形態などさまざまな事柄がみえてくる。
1 食糧としての貝:貝塚にみる食用貝
2 道具の材料になった貝:「搬入貝」の識別
3 貝製装身具:出現の古さと広範な分布の意味
1 縄文時代の「貝輪」の特徴
2 ベンケイガイ製の貝輪
3 貝輪素材変遷の理由
4 貝輪装着にかかわる習俗
5 各集落内で行われた「貝輪製作」
附節 特異なベンケイガイ打ち上げ地:千葉県鴨川市における追跡
調査の記録
1 出土遺跡と貝輪の様相
2 弥生時代に使用された貝輪素材の特徴
3 現生貝調査成果からみた東日本弥生時代の貝輪の様相と展開
1 「西の貝の道」と「東の貝の道」
2 伊豆諸島を起点としたオオツタノハ製貝輪生産
3 南海産の「貝材」の流通と房総半島集落の役割
4 オオツタノハとともに伊豆諸島から運ばれた貝
5 南海産の貝製品を模造した土製品
6 タカラガイ・イモガイ製品にみる社会的役割
1 九州地方出土貝輪の様相
2 東名遺跡出土の縄文時代早期における貝製装身具
3 飛??貝塚出土の縄文時代後期における貝製装身具
4 山鹿貝塚出土の縄文時代後期における貝製装身具
5 佐賀貝塚出土の縄文時代後期における貝製装身具
6 黒橋貝塚出土の縄文時代後期における貝製装身具
7 麦之浦貝塚出土の縄文時代後期における貝製装身具
8 柊原貝塚出土の縄文時代後期における貝製装身具
9 川上(市来)貝塚出土の縄文時代後期における貝製装身具
1 広田遺跡と「西の貝文化」
2 種子島における縄文,弥生・古墳時代のオオツタノハ製貝輪
3 大隅諸島における現生オオツタノハの調査
4 トカラ列島および奄美諸島におけるオオツタノハ製貝輪と現生
貝調査
5 沖縄諸島におけるオオツタノハ製貝輪と現生貝調査
1 オオツタノハ採取と貝輪加工
2 現生貝調査からみた広田遺跡の貝輪の解釈
3 現生貝調査からみたカサガイ系貝輪の評価
4 西日本におけるオオツタノハ製貝輪の流通
5 最高峰の威信財としてのオオツタノハ製貝輪
結びにかえて:残された研究課題と展望
【2024年5月1日 【入荷】【ご注文承り中】
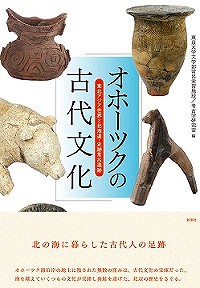
書籍番号
82168
書 名
オホーツクの古代文化 東北アジア世界と北海道・史跡常呂遺跡
シリーズ
データ
A5 216頁
ISBN/ISSN
978-4-7877-2401-4
編著者
東京大学文学部常呂実習施設/考古学研究室
出版年
2024年3月
出版者
新泉社
価 格
2,530円(税込)
地は、北海道の歴史を考える上で欠かすことができない。史跡常呂遺
跡を中心に、オホーツクの古代文化を追究した東京大学常呂実習施設
50年の歩みとともに、住居跡、狩猟・漁労具、人骨、土器のおこげな
ど、様々な資料を駆使した最新の研究成果を紹介する。
はじめに
刊行によせて
本書のねらい
北海道における考古学的文化の変遷
北海道の気候と地域区分
オホーツクの古代遺跡
史跡常呂遺跡関連図
旧石器文化(山田哲)
コラム 常呂川流域の旧石器時代研究(中村雄紀)
コラム 旧石器/縄文時代移行期のミッシングリンクを探る(夏木大吾)
コラム 黒曜石製石器(山田哲)
縄文・続縄文文化(熊木俊朗・福田正宏)
コラム 擦切石斧(夏木大吾)
コラム 幣舞式土器とシマフクロウ(福田正宏)
コラム 縄文時代の漆製品からみた常呂川河口遺跡の漆塗櫛(太田圭)
コラム 弥生化と続縄文(根岸洋)
コラム 常呂川河口遺跡墓坑出土品(中村雄紀)
道東部のオホーツク文化(熊木俊朗)
コラム 銛頭(設楽博己)
コラム 動物意匠遺物(高橋健)
コラム 骨製クマ像(熊木俊朗)
コラム 日本列島の古代船からみたオホーツク文化の船(塚本浩司)
擦文文化からアイヌ文化へ(熊木俊朗)
コラム 常呂川下流域の擦文集落(榊田朋広)
コラム 北日本におけるレプリカ法による土器圧痕調査(太田圭)
コラム 擦文文化のフォーク状木製品(大澤正吾)
コラム 紡錘車と擦文文化(市川岳朗)
東北アジアからみたオホーツクの古代文化(福田正宏・佐藤宏之)
常呂川下流域の古環境(一木絵理)
形質人類学からみた北海道の先史(近藤修)
動物遺体からわかる生業や環境(新美倫子)
常呂の遺跡と食生態分析(國木田大)
北方漁労民の技術(高橋健)
アイヌ文化のクマ儀礼の起源をめぐって(佐藤宏之)
コラム ロシア極東の遺跡を掘る(森先一貴)
東京大学と東北アジア考古学(福田正宏)
コラム 駒井和愛と渤海国の考古学研究(中村亜希子)
東京大学と常呂の出会いとあゆみ(熊木俊朗)
常呂実習施設の発掘調査の歴史と研究成果(熊木俊朗)
コラム 常呂研究室草創のころ(菊池徹夫)
コラム 常呂実習施設初期の発掘実習と職員宿舎(飯島武次)
コラム 常呂実習施設とともに(宇田川洋)
コラム 黒曜石を使う(大貫静夫)
コラム 二〇〇〇年代以降の新たな取り組み(佐藤宏之)
コラム 常呂実習で学んだこと(榊田朋広)
コラム モヨロ貝塚調査と東京大学(米村衛)
大学と地域連携 東大文学部と常呂実習施設の取り組み(熊木俊朗)
文化財の保存活用と地域連携(森先一貴)
世界遺産と地域連携(根岸洋)
史跡常呂遺跡の整備(山田哲・中村雄紀)
ところ遺跡の森案内(中村雄紀)
コラム 東大とのおつきあい(新谷有規)
もっと詳しく学びたい人へ
参考文献
【2024年4月27日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82244
書 名
移動する渡来系工人ネットワーク
シリーズ
(「文化財と技術 別冊1)
データ
A5 222頁
ISBN/ISSN
2187-4328
編著者
鈴木 勉著
出版年
2024年4月
出版者
工芸文化研究所
価 格
1,100円(税込)
-古代の人々の暮らしぶりを!-
第1章 江田船山古墳の銀象嵌鉄刀銘を読む
1.象嵌銘の金石学
2.刀剣と「切れ味」
3.江田船山銀象嵌鉄刀銘が説く「よい材料、よい鍛錬、よい焼き入れ」
4.5世紀のはがね論
コラム1-1 <「切れ味」の歴史的意義と神話を崩した事例>
コラム1-2 <床屋さんのうぶ毛用と剛毛用のかみそり>
コラム1-3 <ずく・はがね・なまがねと鋼>
コラム1-4 <宮地嶽古墳出土刀の復元>
コラム1-5 <釈文と釈読>
1.移動する渡来系工人ネットワーク論はこうして展開された
2.曲線・円文を彫るわざ
3.5世紀末葉までの九州地方の円弧状なめくりたがね
4.九州を移動する渡来系工人ネットワーク
5.トピックス<宮崎県えびの市島内地下式横穴139号墓出土象嵌鍛冶具
が出土>
コラム2-1 <技法と技術>
コラム2-2 <鉄にたがねを打ち込む>
1.雄略紀十三年九月の記事
2.為政者・渡来工人・在来工人の軋轢
3.あやしい死刑宣告
4.書紀編者の執筆意図を探る
-移動する渡来系工人ネットワークの存在を確信する-
1.滝瀨芳之氏が教えてくれた円文線刻鉄刀
2.円文線刻鉄刀について
3.「円文鉄製品」への「円弧状なめくりたがね」の使用について
4.円文鉄製品の分布と移動する渡来系工人ネットワーク
5.象嵌鉄刀・線刻鉄鏃・線刻鉄刀の製作者ならびに製作地
6.トピックス <江田船山古墳から円文線刻鉄刀と?元孔鉄刀が発見さ
れた>
コラム4-1 <加工硬化と作業の力>
コラム4-2 <基準精度>
コラム4-3 <規格品>
コラム4-4 <豊島直博氏の大和王権下賜説>
1.移動する渡来系工人ネットワークを着想したころ
2.古代から現代の移動する工人の事例
(1)
工人の食い扶持と仕事量
(2) 鋳掛け屋さん
(3) 挽物師
(4)
洋服のオーダーメイド
(5) 日本の野鍛冶・韓国の野鍛冶
(6) 近現代の旋盤師
(7) 板前
(8) 梵鐘・大釜など鋳物
(9)
野中古墳三尾鉄の蹴り彫り工人
(10) 中国四川省の僻地では婚姻の準備として
3.東アジアを移動する工人ネットワーク
4.古代の境界について
コラム5-1 <木彫金張り技法>
コラム5-2 <加工の痕跡と技術を隠す技術>
コラム5-3 <蹴り彫りたがねとなめくりたがね>
コラム5-4 <蹴り彫り技術の技術水準>
1.線彫り七種
(1)点打ち
(2)蹴り彫り
(3)打ち込み
(4)なめくり打ち
(5)なめくり挽き
(6)毛彫り
(7)連点打ち
2.立体表現の技術 その種類と見分け方
(1)平面から立体へ
(2)打ち出し、打ち凹ます
(3)彫りくずし
(4)鋳造と彫金
(5)複合技術
3.円文を作る
4.はりがねを作る
5.きさげとせん
6.金属の接合
(1)固相拡散接合
(2)中国と韓半島の細粒細工
(3)日本列島に伝わった細粒細工と堤状連珠文
コラム付-1 金宇大さんの潔さ
【2024年4月26日 【品切】
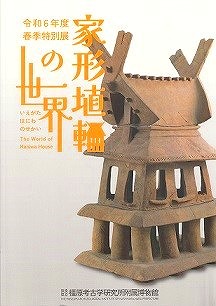
書籍番号
82234
書 名
家形埴輪の世界
シリーズ
(令和6年度 春季特別展 特別展図録第95冊))
データ
A4 88頁
ISBN/ISSN
978-4910272-29-0
編著者
奈良県立橿原考古学研究所編集
出版年
2024年4月
出版者
奈良県立橿原考古学研究所
価 格
と考えられる数少ない種類の一つです。ただし、構造が複雑で大型
品も多いため、その実態がよく分からず、展示で取り上げられる機
会が少ない埴輪でもあります。このたびの展覧会では古墳時代の政
治的な中枢が存在した奈良県内の資料を中心に、東日本と西日本で
最大の製品も展示して、謎の多い家形埴輪の実態に迫ってみたいと
思います。
開催にあたって
目次、例言
概説 家形埴輪の世界………………………………………………… 5
展示関連地図…………………………………………………………… 8
プロローグ 家形埴輪の研究史……………………………………… 9
第1部 宮山古墳の家形埴輪…………………………………………15
第2部 家形埴輪の展開………………………………………………27
エピローグ 家形埴輪の特質…………………………………………77
参考資料…………………………………………………………………79
出品目録…………………………………………………………………83
参考文献…………………………………………………………………85
関連行事、協力機関・協力者…………………………………………87
あとがき、奥付…………………………………………………………88
【2024年4月24日 【入荷】【ご注文承り中】
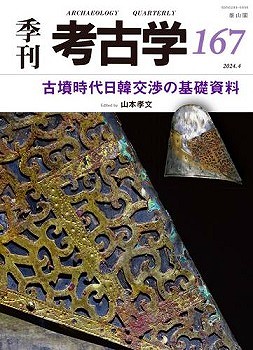
書籍番号
82243
書 名
季刊 考古学
第167号 特集 古墳時代日韓交渉の基礎資料
シリーズ
データ
B5 122頁
ISBN/ISSN
978-4639029793
編著者
桑門智亜紀編集
出版年
2024年5月
出版者
雄山閣出版
価 格
2,640円(税込)
住居・建物とその施設………………………………………重藤輝行 17
陶質土器と須恵器…………………………………………中久保辰夫 21
軟質土器から土師器へ………………………………………寺井 誠 25
窯と土器生産…………………………………………………長友朋子
29
東アジア古代国家の武器体系
―燕(前燕)・高句麗・百済・新羅・加耶・倭の武器体系―
………禹 炳 喆
33
装飾付環頭大刀………………………………………………金 宇
大 38
甲
冑…………………………………………………………橋本達也 42
馬具と馬………………………………………………………諫早直人
46
鏡……………………………………………………………辻田淳一郎 50
玉 類……………井上主税 54
冠と飾履―咸平禮德里新德1号墳出土例の検討を中心に―
……………土屋隆史 58
帯金具…………………………………………………………山本孝文
62
古墳の墳丘形状と構築技術…………………………………青木 敬 66
横穴式石室の導入……………………………………………山本孝文 70
葬送儀礼―飲食物供献儀礼を中心に― …………………松永悦枝
74
倭系古墳………………………………………………………高田貫太 78
円筒埴輪と形象埴輪…………………………………………廣瀬 覚 82
韓半島南部の土師器系土器…………………………………趙 晟 元
86
────────────────────────────────
最近の発掘から
縄文時代後期の四角く並べられた焼人骨
―新潟県阿賀野市土橋遺跡―
………………古澤妥史・村上章久・奈良貴史 91
────────────────────────────────
リレー連載・考古学の旬 第25回
常陸古墳文化研究の最前線………………………………佐々木憲一 95
リレー連載・私の考古学史 第16回
遺跡を介して人と交流した60年…………………………小笠原好彦 102
────────────────────────────────
書評 108/論文展望
112/報告書・会誌新刊一覧 114/
考古学界ニュース
119
────────────────────────────────
【2024年4月15日 【入荷】【ご注文承り中】
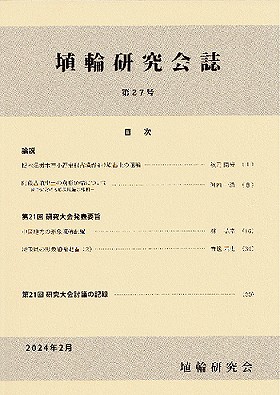
書籍番号
82231
書 名
埴輪研究会誌 第27号
シリーズ
データ
B5 82頁
ISBN/ISSN
1341-318X
編著者
出版年
2024年2月
出版者
埴輪研究会
価 格
1,650円(税込)
論説
………………… 秋元 陽光(1)
阿蔵古墳出土の鶏形埴輪について…… 河内 一浩(8)
―南予における形象埴輪の様相―
第21回研究大会発表要旨
埼玉県の形象埴輪配置(2) ………… 青笹 基史(36)
<↓↓残部少↓↓>(目次は下記URLからご覧ください)
●78746 埴輪研究会誌 第23号
2019年5月 B5 112頁/埴輪研究会 ¥1,650(税込)
https://www.chugoku-shoten.com/mokuji/jmokuji/78746/78746.html
●80387 埴輪研究会誌 第24号
2020年5月 B5 110頁/埴輪研究会 ¥1,650(税込)
https://www.chugoku-shoten.com/mokuji/jmokuji/80387/80387.html
●80756 埴輪研究会誌 第25号
2021年8月 B5 123頁/埴輪研究会 ¥1,650(税込)
https://www.chugoku-shoten.com/mokuji/jmokuji/80756/80756.html
●81466 埴輪研究会誌 第26号
2022年8月 B5 110頁/古代学協会 ¥2,200(税込)
https://www.chugoku-shoten.com/mokuji/jmokuji/81466/81466.html
【2024年4月8日 【入荷】【ご注文承り中】
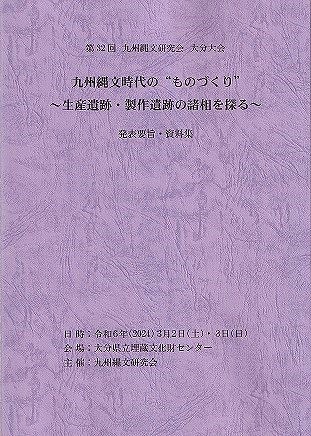
書籍番号
82207
書 名
九州縄文時代の“ものづくり”~生産遺跡・製作遺跡の諸相を探る~
シリーズ
データ
A4 372頁
ISBN/ISSN
編著者
九州縄文研究会大分大会事務局編集
出版年
2024年3月
出版者
価 格
5,720円(税込)
【記念講演】
《回顧》大分県の縄文時代研究 ………………………………………… 1
坂本嘉弘(別府大学非常勤講師、元大分県教育委員会)
姫島産出の石器石材
……………………………………………………… 13
綿貫俊一(大分県立埋蔵文化財センター)
大坪志子(熊本大学埋蔵文化財調査センター)
東名遺跡におけるものづくり-有機質遺物を中心に- ……………… 49
西田 巌(佐賀市教育委員会)
【各県の集成概要報告】
福岡県における縄文時代のものづくり関連遺跡の概要 ……………… 71
梶佐古幸謙(福岡県教育委員会)
佐賀県の生産遺跡・製作遺跡
…………………………………………… 87
堤 英明(佐賀県文化課文化財保護・活用室)
長崎県の生産遺跡・製作遺跡の様相
……………………………………115
中尾篤志(長崎県教育委員会)
熊本県における縄文時代の生産遺跡・製作遺跡の様相
………………135
豊永結花里(熊本県教育委員会)
大分県における縄文時代生産遺跡・製作遺跡の概要
…………………147
横澤 慈(大分県立埋蔵文化財センター)
宮崎県の生産・製作遺跡
…………………………………………………167
金丸武司(宮崎市教育委員会)
鹿児島県における縄文時代生産遺跡・製作遺跡について
……………183
湯場﨑辰巳((公財)上野原縄文の森)
沖縄県における道具の生産・製作の特色
………………………………325
大堀皓平(沖縄県立埋蔵文化財センター)
2023年の動向-各県の調査と報告書-
…………………………………345
第31回沖縄大会討論の記録
………………………………………………351
第14回日韓新石器時代研究会の記録
……………………………………370
【2024年4月8日 【入荷】【ご注文承り中】
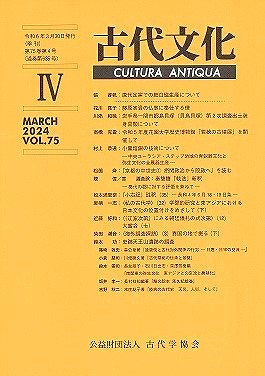
書籍番号
82221
書 名
古代文化 第75巻 第4号(635号)
シリーズ
データ
B5 127頁
ISBN/ISSN
0045-9232
編著者
出版年
2024年3月
出版者
古代学協会
価 格
2,970円(税込)
………………………………………………………………
花川 真子:藤原実資の仏事に奉仕する僧
川添 和暁:岩手県一関市蝦島貝塚(貝鳥貝塚)第2次調査出土装
身具類について
高橋 克壽:令和5年度花園大学歴史博物館「若狭の古墳展」を開
催して
村上 恭通:小量熔銅の技術について
-中央ユーラシア・ステップ地域の青銅器文化と
弥生文化の金属器生産-
松薗 斉:『京都の中世史①摂関政治から院政へ』を読む
陳 偉:章 瀟逸訳:秦簡牘「執法」新釈
-秦代の郡に対する評価を兼ねて-
松本満里奈:『小右記』註釈(35)―長和4年6月18・19日条―
麻柄 一志:〈私の古代学〉(32)学際的研究と東アジアにおける
日本文化の位置付けをめざして(下)
近藤 好和:〈『江家次第』にみる朝廷儀礼の式次第〉(12)
大嘗会(七)
柴田 潮音:〈海外調査探訪〉(3)異国の地で掘る(下)
鈴木 功:史跡天王山遺跡の調査
篠崎 敦史:森公章著『遣唐使と古代対外関係の行方
―日唐・日宋の交流―』
小倉 慈司:川畑勝久著『古代祭祀の伝承と基盤』
鈴木 崇司:長友朋子・石川日出志・深澤芳樹編
『南関東の弥生文化 東アジアとの交流と農耕化』
坂井 孝一:長村祥知編著『龍光院本 承久記絵巻』
吉野 秋二:本庄総子著『疫病の古代史 天災、人災、そして』
【2024年4月6日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82199
書 名
郡衙遺跡からみた地方支配
シリーズ
(考古学選書 5)
データ
A5 274頁(上製本)
ISBN/ISSN
978-4886219305
編著者
大橋 泰夫著
出版年
2024年2月
出版者
同成社
価 格
6,600円(税込)
特に交通や仏教・祭祀との深い関わり、正倉の実態について重点的
に論究し、律令国家の地方支配の実相に迫る。
第1節 郡衙の研究
第2節 官衙と道路・条里
第1節 東国の地域支配と郡衙
第2節 那須官衙遺跡の検討
第3節 郡垣遺跡と郡衙移転
第4節 橘樹官衙遺跡群の検討
第5節 鳥取県石脇第3遺跡と笏賀駅
第6節 横江荘遺跡の検討
第1節 法倉の研究
第2節 坂東における倉の特質
第3節 考古学からみた義倉の一考察
【2024年4月6日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82202
書 名
古代出雲の氏族と社会
シリーズ
(古代史選書47)
データ
A5 306頁(上製本)
ISBN/ISSN
978-4-88621-945-9
編著者
武廣 亮平著
出版年
2024年3月
出版者
同成社
価 格
8,250円(税込)
東西出雲論や出雲国造など古代出雲国の主要なテーマについて
考古学的な研究成果も踏まえ多角的に論究。
また出雲国の部民制や氏族、『出雲国風土記』にみる神社や里
程記事などの考察を通して、出雲古代史研究に新たな議論を提示
する。
【目次】
第Ⅰ部 出雲国造をめぐる諸問題
第一章 東西出雲論と出雲国造の成立―論点の整理と展望―
第二章 出雲国造神賀詞と出雲国造
第三章 額田部臣と出雲の部民制
第四章 日置氏と六世紀の出雲
第五章 勝部氏の性格と出雲の勝部氏
第六章 畿内における出雲氏とその性格
第七章 出雲国の移配エミシとその反乱
第八章 出雲国における官社の成立とその変遷
第九章 『出雲国風土記』の在地史料
【2024年4月6日 【入荷】【ご注文承り中】
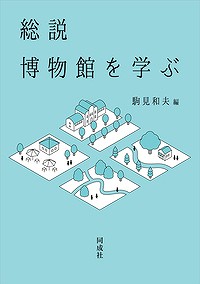
書籍番号
82205
書 名
総説
博物館を学ぶ
シリーズ
データ
A5 194頁
ISBN/ISSN
978-4886219329
編著者
駒見 和夫編
出版年
2024年3月
出版者
同成社
価 格
2,420円(税込)
マネジメントや社会連携の実情をわかりやすく解説する。
学芸員志望者、博物館をもっと知りたい人に最
適の一書。
駒見和夫、滝口正哉、伊豆原月絵、江水是仁、田中裕二、
神庭信幸、森田喜久男、井上由佳、菅井薫、高柳直弥
第1章 博物館・博物館学とは
第2章 博物館の成り立ちと展開
第3章 博物館の法規と倫理
第4章 博物館の分類と活動を担うスタッフ
第Ⅱ部 博物館における資料の形成と活用
第5章 博物館資料とその収集
第6章 文化財の保存管理と博物館
第7章 博物館の調査研究と展示活動
第8章 博物館の学習支援と情報メディア活動
第Ⅲ部 博物館と社会との協働・連携
第9章 社会教育に基づく博物館
第10章 文化観光と文化資源に基づく博物館
第11章 博物館と地域デザイン
【2024年4月6日 【入荷】【ご注文承り中】
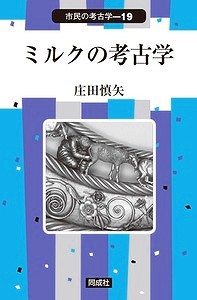
書籍番号
82200
書 名
ミルクの考古学
シリーズ
(市民の考古学 19)
データ
四六版 152頁
ISBN/ISSN
978-4886219497
編著者
庄田 慎矢著
出版年
2024年4月
出版者
同成社
価 格
1,760円(税込)
により「目に見えない」痕跡から解き明かされた新発見が続出!
第1章 わたしたちとミルク
第2章 遺物研究が明らかにしたミルク利用の歴史
第3章 考古生化学が明らかにしたミルク利用の歴史
第4章 土器に残されたミルクの痕跡を求めて
第5章 ミルク考古学のこれから
【2024年4月4日 【入荷】【ご注文承り中】
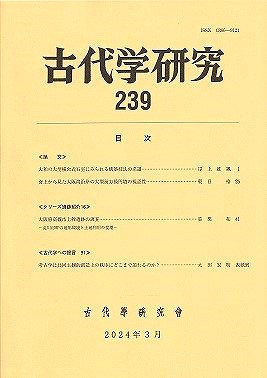
書籍番号
82219
書 名
古代学研究 第239号
シリーズ
データ
B5 50頁
ISBN/ISSN
0386-9121
編著者
古代学研究編集局
出版年
2024年3月
出版者
価 格
990円(税込)
≪論 文≫
……………岸 上 維 颯 1
海上から見た大阪湾沿岸の大型前方後円墳の視認性
…………朝 日 格 25
-淀川河畔の地形環境と土地利用の変遷-
…………………太 田 宏 明 表紙裏
【2024年4月4日 【入荷】【ご注文承り中】
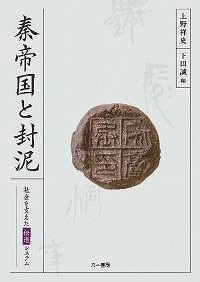
書籍番号
82216
書 名
秦帝国と封泥 社会を支えた伝送システム
シリーズ
データ
B5 185頁
ISBN/ISSN
978-4864451802
編著者
上野祥史 下田 誠編
出版年
2024年3月
出版者
六一書房
価 格
6,600円(税込)
本書は戦国時代後半から、統一秦、楚漢戦争を経て前漢初期に
いたる時期を対象としている(中略)
この時期は、文字や制度が社会を管理する中国歴史時代の幕開けでも
ある。その後は、科挙が象徴するように、ゆたかな識字層に支えられて、
中華帝国は二〇〇〇年の歴史を歩むことになる。(中略)
この秦という社会を支えたシステムを、本書では「捺印」にクローズ
アップしてとらえた。社会を支えたシステムとは、端的にいえば、文字
を利用して制度を運用することであり、それを「捺印」にかかわる三つ
の視座でとらえてきた。一つは、「捺印」の所作や行為を復元すること
であり、一つは「捺印」が組み込まれた一連の行動様式を評価すること
であり、一つは捺した印章の文字を評価することである。
それぞれ、「第一部 封泥の実態」、「第二部 文字を書き印を捺す」、
「第三部 秦封泥の文字と秦の社会」が該当している。(中略)
方法論や関心の異なる研究者が集い、情報や物資の伝達を検討するこ
とは容易ではない。しかし、封泥を共通の資料として、各自が新たな着
眼点を見出し、それを共有することで、少しずつ研究は進展した。こと
に、理化学分析との協業は大きな役割を担った。X線CTスキャン装置を
利用した分析の推進は、各研究者には大きな刺激を与えた。(中略)
新たな研究は、新出資料のみが切り拓くものではない。既存資料の再
評価や分野を横断した検討にもその可能性は潜在している。本書で示し
た、封泥の形態情報の検討、封泥と簡牘資料を対照した検討、あるいは
封泥や印章の文字の検討などは、それぞれの分野に新たな影響を与える
ものと見受ける。秦封泥研究や戦国秦漢時代の研究、文書行政の日中比
較研究等への貢献も望まれる。
本書は、より多くの方の手に届くよう、できるだけ平易な形で示すこ
とを心がけた。内容によっては、専門性が高いもの、あるいは独創性が
強いものも含まれている。そこは、秦漢時代の研究の緻密さゆえと、お
許しを願いたい。(本書“後記”より抜粋)
【目 次】
第一部 封泥の実態
第二章 観峰館所蔵封泥が提起する秦封泥の検討視点
野祥史・瀬川敬也 17
第三章 封泥から復元する「捺印」の所作
―外面形態情報と内部透過情報― 上野祥史 39
第二部 文字を書き印を捺す
―封緘という所作をめぐって― 籾山 明 57
第二章 秦漢時代の小官印とその使用
青木俊介 73
第三章 皇帝の〝手足の指の先〟―秦帝国中央集権の現場―
髙村武幸 95
第四章 官印は誰が捺したのか―実用と象徴の間― 髙村武幸
109
第三部 秦封泥の文字と秦の社会
第二章 秦の郡県と秦封泥―丞印からみた郡と県― 下田 誠
147
第三章 漢字書体ヒエラルキアと秦帝国―書体・書風変遷攷―
松村一徳 159
【2024年3月25日 【入荷】【ご注文承り中】
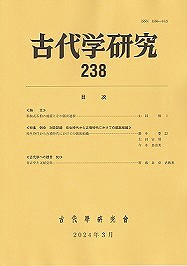
書籍番号
82212
書 名
古代学研究 第238号
シリーズ
データ
B5 54頁
ISBN/ISSN
0386-9121
編著者
古代学研究編集局
出版年
2024年3月
出版者
古代学研究会
価 格
990円(税込)
≪論 文≫
刳抜式石棺の規範とその創出過程…………………山 田 暁
1
≪特集 例会 対談記録 弥生時代から古墳時代にかけての親族組織≫
弥生時代から古墳時代にかけての親族組織………藤 井 整 23
太 田 宏 明
今 井 真由美
≪古代学への提言 90≫》
考古学と文献史料…………………………………實 盛 良 彦 表紙裏
【2024年3月13日 【入荷】【ご注文承り中】
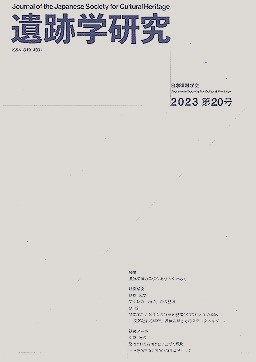
書籍番号
82195
書 名
遺跡学研究 第20号 2023
シリーズ
データ
A4 101頁
ISBN/ISSN
1349-4031
編著者
日本遺跡学会
出版年
2023年12月
出版者
日本遺跡学会
価 格
2,750円(税込)
目次
─────────────────────────────
特集 遺跡保護の多様なあり方を求めて
─────────────────────────────
特集趣旨 恵谷浩子
1
─────────────────────────────
事例報告
─────────────────────────────
多賀城跡の保護の経緯と展望 白崎
恵介
3
─────────────────────────────
福岡県内の遺跡における在り方の事例 入佐 友一郎 13
─────────────────────────────
明日香村における遺跡の保存・管理と活用 相原 嘉之 19
─────────────────────────────
遺跡のあり方と伝える手立て―京都府宇治市の事例―
杉本
宏 25
─────────────────────────────
座談会
─────────────────────────────
遺跡保護の多様なあり方を求めて
─────────────────────────────
パネリスト:白崎 恵介・入佐 友一郎・相原 嘉之・杉本 宏
コメンテーター:増渕 徹・城戸 康利
コーディネーター:坂井 秀弥
─────────────────────────────
研究論文
─────────────────────────────
文化財の「価値」の再整理
伊藤
文彦 45
─────────────────────────────
関東地方における貝塚史跡整備の同質化とその原因
57
─────────────────────────────
―史跡価値の解釈、遺構表現とそのステークホルダー ―
劉 [王路]
─────────────────────────────
研究ノート
─────────────────────────────
整備された古墳が創り上げた風景
―五色塚古墳と宝塚古墳を事例として― 小野 健吉 73
─────────────────────────────
選跡学フォーラム
─────────────────────────────
SITE
05 松山城跡
秋山
邦雄
81
─────────────────────────────
東日本大震災被災地の史跡「浦尻貝塚」の整備 川田
強 83
─────────────────────────────
岐阜県古代・中世寺院跡総合調査について 日置
真穂 89
─────────────────────────────
大阪市における近年、そしてこれからの史跡の活用と整備
95
―大坂城跡と難波宮跡― 佐藤 隆
─────────────────────────────
令和4年度の史跡等の整備について
中井 將胤・小野 友記子・岩井 浩介・玉川 元気 101
─────────────────────────────
遺跡雑感 04 史跡古津八幡山遺跡―隔絶された歴史空間―
林 正憲
32
─────────────────────────────
【2024年3月12日 【入荷】【ご注文承り中】

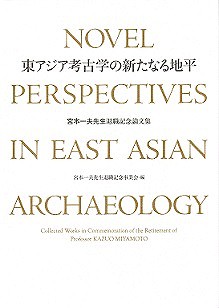
書籍番号
82187
書 名
東アジア考古学の新たなる地平
―宮本一夫先生退職記念論文集(全2冊)
シリーズ
データ
B5 1020頁
ISBN/ISSN
978-4-903316-77-2
編著者
宮本一夫先生退職記念事業会編集
出版年
2024年3月
出版者
有限会社 中国書店
価 格
17,600円(税込)
南部九州における縄文時代草創期土器編年と
イベント・気候変動に関する覚書 ……………………………桒畑光博
3
九州における羽島下層Ⅱ・Ⅲ式土器の様相 ……………………倉元慎平
17
長崎県壱岐市中尾遺跡出土石器群の分析 ………………………自石渓冴
37
西平式土器の成立と展開 …………………………………………福永将大
39
縄文農耕論の可能性 ………………………………………………板倉有大
79
新町遺跡出土人骨に見られる葬送行為の再検討 ………………舟橋京子
99
GISを用いた造墓環境の検討 ……………………………………端野晋平
117
―九州北部弥生時代開始前夜の募地を対象として―
十郎川技法からみた弥生時代初頭期 …………………………梶佐古幸謙 141
―十郎川遺跡出土資料を対象に―
太形蛤刃石斧の出現とその意義 …………………………………森 貴教 155
―弥生時代開始期における両刃石斧の再検討―
器種組成と製作技術からみた板付Ⅰ式土器の成立とその特徴
…………………………………三阪一徳 175
韓半島と北部九州からみる、細形銅戈の変遷と用途について
…………………………………藤元正太 193
大隅半島における弥生時代の横口式土壙墓の系譜 ……………石田智子 209
西北九州における弥生時代後期の石庖丁製作 …………………渡部芳久 229
初期小形[イ方]製鏡の意義 ………………………………………田尻義了 243
北部九州弥生Ⅳ~Ⅴ期の二つの墓地にみる
上位層の析出過程と「対抗/抵抗」 ……………………………溝口孝司 259
―寺田池北遺跡と弥永原遺跡6次調査地点を事例として―
東日本における弥生布生産の間始 ………………………………小林青樹 285
北部九州弥生土器の火山ガラスの評価 ………………………鐘ヶ江賢二 305
―壱岐・原の辻遺跡出土土器を中心に―
土井ヶ浜道跡1112号墓における集骨葬に関する人類学的研究
…………………………………高椋浩史 319
弥生~古墳時代中・四国地方出土イネの粒形質変異 …………上條信彦 335
古墳時代開始過程の北部九州における布留系甕の
地域性に関する一考察 ………………………………………中野真澄 357
玉類からみた吉武遺跡群渡地区木棺墓の位置づけ ……………谷澤亜里 375
古墳時代前期の積石塚古墳における墳丘石材採取の具体的様相Ⅱ
……………………………………梶原慎司 395
須恵器出現期における土器の使用形態 …………………………岡田裕之 407
―山陰・山陽地域を中心に―
居屋敷窯跡産須恵器の研究 ………………………………………三吉秀充 427
鹿児島県の埋葬遺跡から出土する須恵器とその性格 …………大西智和 447
古墳時代後期における横穴式石室の
基準尺度に関する予備的検討 ………………………………辻田淳一郎 465
―博多湾沿岸地域を対象として―
嘉穂盆地と田川盆地の埴輪生産 …………………………………三浦 萌
481
福島県いわき市後田1号墳出土陶棺の系譜とその意義…………絹畠 歩 517
―「日本列島最北の陶棺」をめぐって―
静岡県西部における横穴墓の展開およびその形態の採用過程と集団関係
………………岩橋由季 531
古墳時代の渡来人集団の特性と動態………………………………重藤輝行 551
「算木状木製品」小考………………………………………………小田裕樹 571
古代山口の銭貨生産…………………………………………………丸尾弘介 583
九州大学箱崎キャンパス出土の戦時関連遺物……………………谷 直子 551
新岩里遺蹟の性格……………………………………………………崔 鐘赫 613
―早期を中心に―
栄山江流域における鉄器生産・流通構造の変化とその背景……金 想民 635
―三時代を中心に―
高麗陶器大型壺の消費に関する一様相……………………………主税英徳 653
―完形資料を中心に―
朝鮮時代地方民の特徴と葬送文化…………………………………李ハヤン 673
―金海仙池里遺蹟事例を中心に―
龍山文化期から商文化期にかけての
調理具のサイズバリエーションの地域差………………………齊藤 希 685
―中国北方地域の資料を中心として―
紀元前二千年紀の陶鬲製法について………………………………富 宝財 699
商代における地方型青銅器文化の東西差…………………………譚 永超 723
―江淮地域青銅器と城洋青銅器群を例として―
草原地帯東部の鶴嘴形斧の変遷に関する諸問題…………………戴 [王月] 741
春秋戦国時代山西中南部地域における青鋼器生産体制復元のための基礎的検討
……………………丹羽崇史 759
吉林省通化市万発撥子出土銅釧からみた地域間交流……………古澤義久 777
宋代陶磁の評価と官窯の系諸に関する一考察……………………徳留大輔 793
白沙屯遺跡における植物珪酸体の分析 ………………………李作[女亭] 793
台湾原住民の集団形成史に関する考古学的研究…………………陳 有貝 829
―宜蘭県淇武蘭遺跡の発掘調査から―
境界考古学の空間と移動……………………………………………俵 寛司 845
―対馬と台湾の事例から―
台湾・日本統治時代における耐火煉瓦の動向……………………福本 寛 867
アルタイ山脈東麓における青銅器文化
…………松本圭太・Amgalantugs Tsend・Ishtseren Lochin 883
ストロンチウム同位体比分析に基づくモンゴル高原青銅器時代の人の移動
……………………………………………米元史識・足立達明
905
青銅器時代北モンゴリアにおける鹿石ヘレクスール文化担い手の人物像:
ゴビ・アルタイ県ヒャル・ハラーチ遺跡1号および20号出土人骨を対象と
して …………………………………岡崎健治・米元史織・川久保善智
925
ルチェイキⅡ群土器と紀元前2千年紀の極東東部
……………福田正宏 943
ナミビア農牧社会における食事セットの分類:クラスター分析と二元指標種
分析の比較
……………………………………………………藤岡悠一郎 963
文化遺産教育の現状と課題 ……………………………………主税和買子
979
―ベトナム・ホイアン市を事例に―
学校ボランティア主体の学校博物館づくり………………………村野正景 993
―京都市立翔鸞小学校の事例研究―
【2024年3月11日 【入荷】【ご注文承り中】
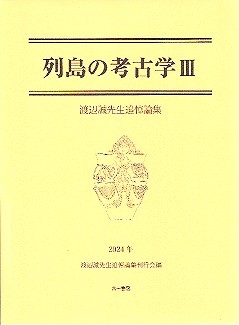
書籍番号
82193
書 名
列島の考古学 Ⅲ 渡辺誠先生追悼論集
シリーズ
データ
B5 680頁 (上製本)
ISBN/ISSN
978-4-86445-171-0
編著者
渡辺誠先生追悼論集刊行会編
出版年
2024年2月
出版者
六一書房
価 格
16,500円(税込)
―思い出を籠めて―
第Ⅰ部 追悼論文
剥片尖頭器の起源について……………………………清水 宗昭
3
榎林式設定までの背景 ………………………………上條 信彦
13
―角田文衛からみた昭和8・13 年二ツ森貝塚調査―
隠された刻印……………………………………………成田 滋彦 25
根挟み考 ………………………………………………長谷川 豊 33
―宮城県田柄貝塚における事例―
大洞貝塚をめぐる学史的背景について………………小林 圭一 43
薄磯貝塚における縄文・弥生時代の閉窩式回転離頭銛考
―特に「薄磯Ⅰ型」「薄磯Ⅱ型」離頭銛の提唱を中心に―
…………大竹 憲治 55
先史文化からの学びと縄文……………………………吉田 泰幸 63
南山大学人類学博物館所蔵姥山貝塚出土中期縄文土器
………………青木 義脩 73
川尻中村遺跡出土の人面把手…………………………安孫子昭二 83
縄文時代における生業形態の変化について…………岩淵 一夫 93
―堅果類から考える複式炉と水場遺構―
縄文時代における甕被葬研究をめぐって……………山本 暉久 105
「大畑系列」土製耳飾について(再考)………………上野 修一 117
―弧線文を中心に―
縄文時代後期前半の小型石棒…………………………長田 友也 125
―垣内型石棒の提唱―
白川型石斧(独鈷石・独鈷状石器)の諸問題…………岡本 孝之 135
秋田県大畑台遺跡の北陸系遺物………………………寺﨑 裕助 147
―縄文時代日本海交流の一端―
“渡辺考古学”ひとつの源流…………………………佐藤 雅一 157
立野式から細久保式へ ………………………………川崎 保 167
―中央高地の押型文土器の変遷に関する研究課題と予察―
縄文時代中期末葉はどのように語られてきたか? …佐 野 隆 177
岐阜県堂之上遺跡の縄文集落と記念物………………藤田富士夫 189
縄文時代における社会変化とその要因………………山本 直人 197
縄文時代の台付土器について…………………………高橋健太郎 205
―東海地方西部・中期後半を対象として―
東海地域における縄文時代の擦切磨製石斧について
…………………長田 紋子 215
北部九州縄文後期住居跡再論…………………………小池 史哲 225
―上唐原型・山崎7 号型住居跡を中心に―
熊本県天草市・沖ノ原遺跡の釣針……………………山﨑 純男 237
鹿児島県大隅半島北部において縄紋時代早期に鬼界カルデラの超巨大
爆発の影響を受けなかった地域の生活環境について
………………清水 周作 249
奄美・沖縄諸島出土のイルカ類について……………盛本 勲 261
万木沢B 遺跡出土の黥面土器…………………………谷藤 保彦 271
台付甕の蓋………………………………………………森 泰通 279
弥生時代のサメ歯鏃……………………………………川添 和暁 291
―長崎県五島市白浜貝塚出土資料について―
多賀城城下の製塩土器…………………………………千葉 孝弥 303
陰陽五行説の理論と図化─秋田城跡出土資料の検討
…………………利 部 修 313
カスミ地名の歴史的背景雑感…………………………内 野 正 325
―東京都多摩市「霞の関」検討から―
七堂伽藍、前から見るか?横から見るか?(1) ………梶原 義実 337
―景観的見地からみた国分寺における伽藍配置の選択 東国編―
木製塔婆考 宮城県仙台市洞ノ口遺跡出土品を手がかりに
…………時 枝 務 347
山梨県の中世石仏 地蔵菩薩立像(2)……………… 坂本 美夫 357
「と云ふ」を調べる……………………………………蔵本 俊明 365
―静岡県菊川市堤城跡を中心に―
宇治産茶臼の形態の変遷について……………………桐山 秀穂 375
旧讃岐国における戦国大名生駒親正の築城思想……西岡 達哉 385
筑前・麻生永犬丸城跡の再照明………………………中山 清隆 397
―失われた城郭と中世永犬丸の景観―
奥州保岩城管内平城主安藤家関連の墓石……………池 上 悟 419
登り石垣の発生と展開…………………………………中 井 均 429
姫路城桜門の新築竣工…………………………………秋 枝 芳 441
昭和の玩具考古学 高知市の玩具店倉庫跡を掘る
……………………岡本 桂典 453
福建省泉州后渚港海洋船にみる宋元時代の海上交通
…………………辻尾 榮市 461
明代華南三彩陶の研究14. 琴高仙人の乗る魚………木村幾多郎 471
チャルチュアパ遺跡のフラスコ状ピット出土種子に関する考察
……………………伊藤 伸幸 485
記録と整理の技術………………………………………宮崎 敬士 497
山陰沿岸のサメ延縄漁…………………………………内田 律雄 505
ミャンマー連邦共和国の発酵ずし・ンガチン………日比野光敏 515
―シャン州北部と東部の場合―
第Ⅱ部 思い出記 ※25名による執筆 約100頁
跋 文
渡辺誠先生 年譜
渡辺誠先生 著作目録
【2024年3月11日 【入荷】【ご注文承り中】
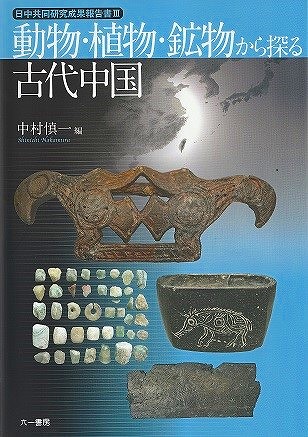
書籍番号
82192
書 名
動物・植物・鉱物から探る古代中国
シリーズ
(日中共同研究成果報告集Ⅲ)
データ
A4 266頁
ISBN/ISSN
978-4-86445-177-2
編著者
中村慎一編
出版年
2024年2月
出版者
六一書房
価 格
4,950円(税込)
われわれ現代人の日々の生活において、動物・植物・鉱物と
いったいわゆる自然物との関係はきわめて希薄になっている。
しかし、新石器時代の中国においては、食料として、道具の材
料として、あるいは建材として、自然物は日常に存在していた。
生活文化の大部分を自然物が占めていたと言い換えてもよい。
考古学的遺跡から出土する遺物のうち、何らかの形で人の手
が加わったものを人工遺物、加わっていないものを自然遺物と
考古学者は呼びならわしている。しかし、その区別は便宜的な
ものにしかすぎない。人工遺物であっても、その素材は粘土
(土器)、石塊(石器)、樹木(木器)、動物骨(骨器)といった自然
物であることに変わりはない。
そこに、狭義の考古学者だけではなく、人類学、動・植物学、
遺伝学、分析化学、地球化学などの専門家が研究に参画する必
然性が生まれる。
本書は、そうした研究者グループにより進められている日中
共同研究プロジェクトの研究成果の一部を収めたものである。
「Ⅰ遺物の考古学的研究」「Ⅱ 動植物遺体と動植物利用に関
する研究」「Ⅲ 出土遺物の考古科学的研究」の3部構成とした
が、この区分もまた便宜的なものである。いわゆる文系の学問
と考えられている考古学であるが、実は自然科学者との協働な
くしてはもはや成り立たなくなっている。逆に言えば、自然科
学との学際的連携によって考古学は新たな飛躍のチャンスを手
に入れた。伝統的な学問としての「中国学」の世界に新風を吹
き込もうとする研究者たちの奮闘する姿がここにある。
巻頭言
中村慎一 ⅰ
例 言
ⅱ
Ⅰ 遺物の考古学的研究
1.田螺山遺跡出土石器とその使用痕分析
上條信彦・原田幹・孫国平 1
2.跨湖橋遺跡出土木器
村上由美子・齋藤哲・中村慎一・蒋楽平 21
3.田螺山出土木器(2) 浦蓉子・川崎雄一郎・鶴来航介・
西原和代・村上由美子・桃井宏和・
山下優介・王永磊・孫国平 41
4.江家山遺跡出土木器
村上由美子・桃井宏和・中村慎一・楼航
79
Ⅱ 動・植物遺体と利用に関する研究
1.現代カザフスタンにおけるキビとアワ
竹井恵美子 93
2.銭塘江流域新石器時代前半の環境と生業の実態
金原正明・金原正子・113
杉山真二・金原美奈子・劉斌・孫国平・蒋楽平・
趙曄・王寧遠・閻凱凱・王永磊・陳明輝
3.良渚古城遺跡群・鍾家港南段地点および卞家山地点出土の鳥類
遺体
199
江田真毅・宋妹・菊地大樹・劉斌
4.中国の新石器時代の遺跡から出土するカメ類の遺骸
平山廉・孫国平・王永磊 205
5.中国浙江省の考古遺跡から出土したサルの化石
―東アジアにおけるマカクザルの分布域の変化に関する考察―
浅見真生・伊藤毅・高井正成・孫国平・王永磊 215
Ⅲ 遺物の考古科学的研究
1.中国産水銀朱を用いた古代日本の遺跡の時代変遷と地域性 235
神谷嘉美・高橋和也・南武志
2.田螺山遺跡出土のチャノキとみられる遺物のDNA分析にむけて
熊谷真彦・水野文月・王瀝 251
【2024年3月4日 【入荷】【ご注文承り中】
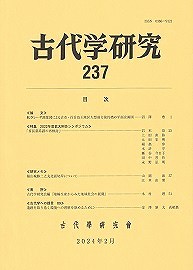
書籍番号
82177
書 名
古代学研究 第237号
シリーズ
データ
B5 58頁
ISBN/ISSN
0386-9121
編著者
古代学研究編集局
出版年
2024年2月
出版者
価 格
990円(税込)
≪論 文≫
航空レーザ測量図による古市・百舌鳥王陵区大型前方後円墳の平面
企画図 ………………沼 澤 豊 1
「首長墓系譜の再検討」…………………………岩 本 崇 25
上 田 直 哉
太 田 宏 明
絹 畠 歩
木 許 守
瀬 谷 今日子
田 中 晋 作
永 野 弘 明
≪研究メモ≫
福山城跡二之丸北面切岸について………………山 岡 渉 37
江 草 由 梨
≪書評≫
古代学研究会編『埴輪生産からみた地域社会の展開』
…………木 村 理
51
遺跡を取り巻く環境への理解を深めるために
……………金 澤 雄 太 表紙裏
【2024年2月29日 【入荷】【ご注文承り中】
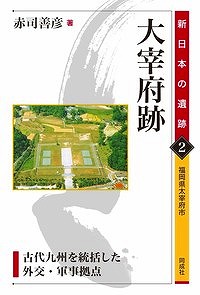
書籍番号
82176
書 名
大宰府跡
シリーズ
(新日本の遺跡 2)
データ
四六版 154頁
ISBN/ISSN
978-4886219336
編著者
赤司善彦著
出版年
2024年3月
出版者
同成社
価 格
1,980円(税込)
***********************************************************
★「新日本の遺跡」刊行開始!★(監修:水ノ江和同・近江俊秀)
***********************************************************
このたび「日本の遺跡」シリーズを継承しつつ、大幅にリニューアル
した「新日本の遺跡」シリーズを開始いたします。日本列島の遺跡を再
評価し、地域から日本の歴史を照射する新シリーズ!(同成社刊行)
────────────────────────────────
【内容紹介】
担った大宰府。考古学的な視点から、その全貌を平易に解説する。
……………………………………………………………………………………
【目次】
第2章 大宰府跡の研究史と保護の歴史
第3章 大宰府の前史と機能
第Ⅱ部 遺跡のあゆみ―発掘調査が語るもの―
第5章 発掘調査成果からみる大宰府の3つの機能
第6章 大宰府跡の保存と活用
────────────────────────────────
<既 刊>
●82022 三万田東原遺跡 九州縄文人のアクセサリー工房
(新日本の遺跡 1)
大坪 志子著/2023年11月 四六版 146頁 ¥1,980(税込)
https://www.chugoku-shoten.com/mokuji/jmokuji/82022/82022.html
【2024年2月28日 【近日入荷】【ご注文承り中】
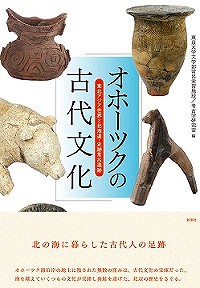
書籍番号
82168
書 名
オホーツクの古代文化 東北アジア世界と北海道・史跡常呂遺跡
シリーズ
データ
A5 216頁
ISBN/ISSN
978-4-7877-2401-4
編著者
東京大学文学部常呂実習施設/考古学研究室
出版年
2024年3月
出版者
新泉社
価 格
2,530円(税込)
地は、北海道の歴史を考える上で欠かすことができない。史跡常呂遺
跡を中心に、オホーツクの古代文化を追究した東京大学常呂実習施設
50年の歩みとともに、住居跡、狩猟・漁労具、人骨、土器のおこげな
ど、様々な資料を駆使した最新の研究成果を紹介する。
はじめに
刊行によせて
本書のねらい
北海道における考古学的文化の変遷
北海道の気候と地域区分
オホーツクの古代遺跡
史跡常呂遺跡関連図
旧石器文化(山田哲)
コラム 常呂川流域の旧石器時代研究(中村雄紀)
コラム 旧石器/縄文時代移行期のミッシングリンクを探る(夏木大吾)
コラム 黒曜石製石器(山田哲)
縄文・続縄文文化(熊木俊朗・福田正宏)
コラム 擦切石斧(夏木大吾)
コラム 幣舞式土器とシマフクロウ(福田正宏)
コラム 縄文時代の漆製品からみた常呂川河口遺跡の漆塗櫛(太田圭)
コラム 弥生化と続縄文(根岸洋)
コラム 常呂川河口遺跡墓坑出土品(中村雄紀)
道東部のオホーツク文化(熊木俊朗)
コラム 銛頭(設楽博己)
コラム 動物意匠遺物(高橋健)
コラム 骨製クマ像(熊木俊朗)
コラム 日本列島の古代船からみたオホーツク文化の船(塚本浩司)
擦文文化からアイヌ文化へ(熊木俊朗)
コラム 常呂川下流域の擦文集落(榊田朋広)
コラム 北日本におけるレプリカ法による土器圧痕調査(太田圭)
コラム 擦文文化のフォーク状木製品(大澤正吾)
コラム 紡錘車と擦文文化(市川岳朗)
東北アジアからみたオホーツクの古代文化(福田正宏・佐藤宏之)
常呂川下流域の古環境(一木絵理)
形質人類学からみた北海道の先史(近藤修)
動物遺体からわかる生業や環境(新美倫子)
常呂の遺跡と食生態分析(國木田大)
北方漁労民の技術(高橋健)
アイヌ文化のクマ儀礼の起源をめぐって(佐藤宏之)
コラム ロシア極東の遺跡を掘る(森先一貴)
東京大学と東北アジア考古学(福田正宏)
コラム 駒井和愛と渤海国の考古学研究(中村亜希子)
東京大学と常呂の出会いとあゆみ(熊木俊朗)
常呂実習施設の発掘調査の歴史と研究成果(熊木俊朗)
コラム 常呂研究室草創のころ(菊池徹夫)
コラム 常呂実習施設初期の発掘実習と職員宿舎(飯島武次)
コラム 常呂実習施設とともに(宇田川洋)
コラム 黒曜石を使う(大貫静夫)
コラム 二〇〇〇年代以降の新たな取り組み(佐藤宏之)
コラム 常呂実習で学んだこと(榊田朋広)
コラム モヨロ貝塚調査と東京大学(米村衛)
大学と地域連携 東大文学部と常呂実習施設の取り組み(熊木俊朗)
文化財の保存活用と地域連携(森先一貴)
世界遺産と地域連携(根岸洋)
史跡常呂遺跡の整備(山田哲・中村雄紀)
ところ遺跡の森案内(中村雄紀)
コラム 東大とのおつきあい(新谷有規)
もっと詳しく学びたい人へ
参考文献
【2024年2月28日 【入荷】【ご注文承り中】
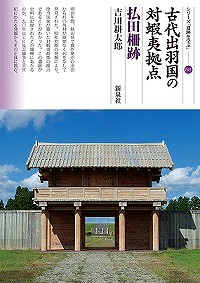
書籍番号
82167
書 名
古代出羽国の対蝦夷拠点 払田柵跡
シリーズ
(シリーズ「遺跡を学ぶ」 165)
データ
A5 96頁
ISBN/ISSN
978-4-7877-2285-2
編著者
吉川耕太郎著
出版年
2024年3月
出版者
新泉社
価 格
1,870円(税込)
なして発見された。昭和初期の発掘により、律令国家が築いた対
蝦夷政策の拠点であることがわかった。この遺跡が史料に記録さ
れたどの城柵にあたるのか、90年以上に及ぶ論争と半世紀にわた
る発掘からその正体に挑む。
1 姿をあらわした城柵
2 律令国家の東北経営と城柵
1 水田に浮かぶ島
2 払田柵跡の構造
3 三重構造の城柵
4 政庁とその変遷
5 工房域と曹司域
6 柵内のその他の調査
7 払田柵創建後の周辺環境
〈コラム〉遺跡にみる自然災害
1 墨書土器・刻書土器
2 木簡
3 漆紙文書
1 払田柵跡の変遷
2 払田柵跡をめぐる諸説
3 払田柵とは何か
4 これからの払田柵跡
【2024年2月21日 【入荷】【ご注文承り中】
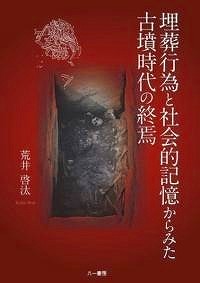
書籍番号
82147
書 名
埋葬行為と社会的記憶からみた古墳時代の終焉
シリーズ
データ
B5 289頁
ISBN/ISSN
978-4864451789
編著者
荒井 啓汰著
出版年
2024年2月
出版者
六一書房
価 格
4,950円(税込)
なく、生きている側の意図や主体性が介在する。本書は、実際に埋葬を
おこなう生者の側に焦点を当て、「埋葬行為」と「社会的記憶」の2つの
概念から古墳時代後・終末期の埋葬施設を検討することで、古墳時代の
終焉とその社会変化に接近するものである。常総地域における箱式石棺
の埋葬行為や、東日本における横穴式石室の利用期間や人骨出土状況の
検討を中心に、6・7世紀における「祖先」や過去の死者への多様な行動
の実態を明らかにする。
【目次】
第1節 本書の目的と立場
第2節 本書の構成
第3節 用語と概念規定
第Ⅰ部 埋葬行為の理論的枠組み
第1章 古墳時代後・終末期の埋葬をめぐる現状
第1節 古墳時代後・終末期における埋葬とその儀礼
第2節 古墳時代後・終末期の社会的状況
第3節 古墳時代後・終末期の埋葬研究の現状
第2章 2つの理論的枠組み 埋葬行為と社会的記憶
第1節 古墳時代後・終末期の埋葬をめぐる2つの問題点
第2節 埋葬行為の理論的枠組み
第3節 社会的記憶の理論的枠組み
第4節 埋葬行為と社会的記憶
第Ⅱ部 古墳時代後・終末期の埋葬行為とその変化
ケーススタディとしての常総地域
第3章 常総地域の地域性と一石棺内複数埋葬の展開
第1節 常総地域の地域的特性と埋葬施設
第2節 常総地域における地域区分と時期区分
第3節 一石棺内複数埋葬の導入と展開
第4節 一石棺内複数埋葬の背景
第4章 箱式石棺の埋葬方法とそのプロセス
第1節 埋葬方法に関する問題と視点
第2節 箱式石棺における埋葬の分類と検討
第3節 埋葬プロセスとその評価
第4節 二次葬的状況をめぐる評価
第5章 箱式石棺における埋葬行為とその変化
第1節 視座と方法
第2節 埋葬行為に関する分類と概念
第3節 各要素の傾向と変遷
第4節 箱式石棺の埋葬行為とその変化
第5節 常総地域における埋葬行為の変容 石棺と石室
第6章 埋葬施設の破壊と再構築 常総地域を中心に
第1節 埋葬施設の破壊と再構築をめぐる論点の整理
第2節 埋葬施設の破壊と再構築の事例
第3節 埋葬施設の破壊と再構築をめぐる社会的状況
第4節 日本列島における古墳の破壊と再利用
第Ⅲ部 横穴式石室における埋葬行為と社会変化
第7章 東日本における横穴式石室の埋葬方法
第1節 横穴式石室の埋葬方法をめぐる視点
第2節 各地域における人骨出土石室の検討
第3節 人骨出土状況からみた埋葬方法の分析
第4節 先葬者に対する儀礼的行為
第5節 東日本の横穴系埋葬施設と埋葬方法
第8章 関東地方における横穴式石室の埋葬行為
第1節 埋葬行為とその視点
第2節 各要素の分布と傾向
第3節 各地域における階層的傾向
第4節 関東地方における埋葬行為の特質
第9章 横穴式石室の利用期間と追葬行為
第1節 横穴式石室における追葬をめぐる議論
第2節 東海地方東部における横穴式石室の利用期間
第3節 横穴式石室の長期利用とその背景
第4節 追葬行為者からみた横穴式石室の利用
第10 章 埋葬行為からみた薄葬化の一側面
第1節 終末期群集墳における薄葬化をめぐる課題
第2節 埋葬施設の小型化と埋葬行為
第3節 群集墳における追葬と再利用の実態
第4節 終末期群集墳における薄葬化と追葬・再利用の関係
第11 章 古墳時代後・終末期における「祖先」の社会的役割
第1節 「祖先」の概念とその意義
第2節 古墳時代研究における「祖先」
第3節 文献史学からみた「祖先」
第4節 古墳時代後・終末期における「祖先」のあり方
終 章 埋葬行為と社会的記憶からみた7世紀の社会変化
第1節 古墳時代後・終末期における「過去の死者」の位置付け
第2節 先葬者への行為と7世紀の社会変化
第3節 結論と課題
参考文献一覧
掲載古墳一覧
図版出典
あとがき
【2024年2月21日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82148
書 名
縄文社会の探究―高橋龍三郎先生古稀記念論集―
シリーズ
データ
B5 541頁(上製本)
ISBN/ISSN
978-4864451765
編著者
高橋龍三郎先生古稀記念論集刊行会編
出版年
2024年1月
出版者
六一書房
価 格
14,300円(税込)
早稲田大学文学学術院教授・高橋龍三郎先生の古稀を記念して刊行。
第一線で活躍する研究者による縄文時代に関する論考(約470ページ)
のほか、調査研究や教育普及活動にまつわる思い出(約50ページ)、
年譜(約20ページ)の三部構成。64 名の研究者による執筆。
…………………………………………………………………………………
【目次】
福田 正宏 北海道先史と宗谷海峡以北―考古学研究の現状と展望―
飯塚 真人 蓮華弧線文土器の提唱
―縄文時代中期前葉の中部高地における一地方類型の検討
岩井 聖吾 武蔵野台地における縄文時代晩期後葉遺跡と浮線文土器群
大網 信良 土器容量からみた縄文土器の型式間関係―関東地方南西部
の中期後葉土器群を対象に
岡本 樹 千葉県における土器製塩―北下遺跡と道免き谷津遺跡出土
製塩土器の比較検討
金子 直行 縄文時代後期の有脚容器考
―動物意匠から獣脚の成立についての予察
川部 栞里 茅山下層式土器の古段階について
小林 圭一 縄文時代晩期香炉形土器の型式変化
佐藤 亮太 西尾市清水遺跡出土土器の再検討
菅谷 通保 縄紋晩期前半編年の見直しと細密沈線文土器
富永 勝也 縄文早期北海道南部の大集落中野A・B 遺跡の土器変遷
中沢 道彦 阿弥陀堂式土器の再検討
長山 明弘 加曽利E(新)式における土器系列の研究(2)
―「円形区劃文土器」の分化とその由来
蜂屋 孝之 異形台付土器出現の契機
細田 勝 大久保山遺跡出土土器の再検討―関東北部中期中葉土器群の
様相
山﨑 太郎 関東における縄文時代後期前半の土器様相について
―朝顔形深鉢土器の広がりの検討
山本 孝司 多摩ニュータウンNo. 72 遺跡61 号住居跡出土土器に関する
一考察
櫛原 功一 柱穴配置による集落分析の有効性
―多摩ニュータウンNo. 446 遺跡の再検討
小島 秀彰 福井県若狭地方における縄文時代後晩期の動き
―生業と社会への視点から
小林 克 東日本縄文中期の家族論序説―民俗と考古の関りから
坂口 隆 北海道美々4 遺跡BS3 周堤墓の基礎的研究
坪田 弘子 縄文時代中期後葉における屋外土器埋設遺構の一様相
―神奈川県三田林根遺跡例を中心に
寺内 隆夫 縄紋時代中期中葉における竪穴建物跡の利用について
―長野県沢尻東原遺跡竪穴建物跡SB13 の土器出土状況より
冨樫 那美 秋田県横手市域における縄文時代の墓制
中門 亮太 青森県における縄文時代後期後葉から晩期の「捨場」
西村 広経 東京湾東岸における縄文時代後・晩期大型竪穴住居跡の再検討
山内 将輝 形成過程から見た縄文時代後期東京湾東岸における貝塚の機能
についての試論
井出 浩正 埋甕炉で共伴する異系統土器―縄文時代中期の社会交流
岩永 祐貴 埋甕における土器の選択
大野 薫 最古の分銅形土偶
忍澤 成視 縄文時代後期における房総半島産貝材の流通と社会形態―千葉
県市原市西広貝塚及び我孫子市下ヶ戸貝塚検出資料からの検討
金子 昭彦 縄文土偶の造形焦点系統論
小林 謙一 南西関東縄紋中期集落における住居跡地への土器廃棄量の検討
佐賀 桃子 水煙把手土器の出土状況について
設楽 博己 通過儀礼の造形―イレズミと抜歯表現のある土偶・土面その他
谷口 康浩 勝坂と阿玉台―土偶表象に表れた文化生態的差異
中村 良幸 縄文中期における土偶過渡期の2 形態
―岩手県内の中期土偶を中心として
根岸 洋 文様にみる象徴性と祖霊観念
渡辺 千尋 縄文時代中期の土器製作に関わる遺物とその特徴
―神奈川県内の出土品を対象に
樋泉 岳二 千葉県我孫子市下ヶ戸貝塚の哺乳類遺体にみられる特殊な状況
について
服部 智至 縄文時代のマダイ利用に関する基礎的研究
―東京湾東岸の貝塚産マダイの分布と組成
佐々木由香 縄文時代の鱗茎利用に関する民俗植物考古学的研究
山本 華 縄文時代と弥生時代のシソ属果実について
―多量圧痕と多数出土事例から
太田 博樹 ゲノム情報から遺跡出土人骨の親族構造を読み解く術
藤田 尚 縄文時代の古病理学
松田光太郎 熊本県における砂の岩石学的特徴と滑石混入土器の製作地推定
―曽畑式土器を例にして
山田 康弘 日本におけるbioarchaeology の方法論と実践例
―考古学的仮説と年代測定・同位体分析・DNA 分析による検証
Ⅱ 思い出
Ⅲ 年 譜
【2024年2月21日 【入荷】【ご注文承り中】
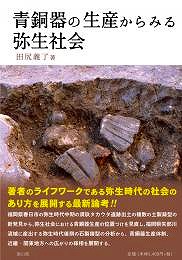
書籍番号
82132
書 名
青銅器の生産からみる弥生時代
シリーズ
データ
A5 184頁 (上製本)
ISBN/ISSN
978-4639029632
編著者
田尻義了著
出版年
2024年2月
出版者
雄山閣出版
価 格
5,940円(税込)
論考!
福岡県春日市の弥生時代中期の須玖タカウタ遺跡出土の複数の土器
鋳型の新発見から、弥生社会における青銅器生産の位置づけを見直
し、福岡県矢部川流域に産出する弥生時代後期の石製鋳型の分析か
ら、青銅器生産体制、近畿・関東地方への広がりの様相を展開する。
【目次】
須玖タカウタ遺跡出土鋳型の衝撃/定着しなかった青銅器製
作技術/変容した青銅器製作技術 円環型銅釧の展開/弥生時
代中期における青銅器製作技術の定着と展開について
青銅器製作技術の広域拡散の様相/拡散した青銅器生産 関東
地方における青銅器生産/青銅器製作技術の地域内拡散 藤木
遺跡出土鋳型の検討/弥生時代後期における青銅器生産の展開
について
鋳型素材の加工と流通について/青銅器の鋳型と鋳型状製品に
ついて/青銅器生産と流通から捉える権力 相互予期と規制/
青銅器祭生産の変化とマツリの変化
これまでの本書のまとめ/鋳型素材流通からみた弥生社会/
おわりに
【2024年2月14日 【入荷】【ご注文承り中】
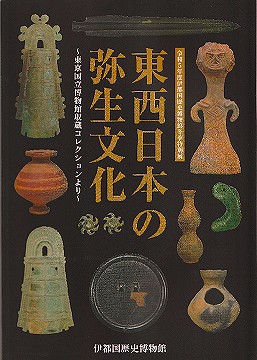
書籍番号
82142
書 名
東西日本の弥生文化~東京国立博物館収蔵コレクションより~
シリーズ
(令和5年度伊都国歴史博物館冬季特別展)
データ
A4 48頁
ISBN/ISSN
編著者
伊都国歴史博物館編集
出版年
2024年1月
出版者
糸島市立伊都国歴史博物館
価 格
770円(税込)
各地から出土した弥生時代の特徴的な資料を展示します。
北は北海道から南は九州まで、日本各地各地で展開した、個性豊かな弥生時代像
を描き出し、当時の糸島(伊都国)の特徴を見出します。
本展では、北海道から九州まで、列島各地から出土した弥生時代(北海道のみ併
行期の続縄文時代)の土器を紹介します。
糸島から出土し、現在、東京国立博物館に収蔵されている資料があります。
今回は、その中から井原で出土した細形銅剣(ほそがたどうけん)と、勾玉・管
玉が里帰りします。
………………………………………………………………………………………………
目 次
第Ⅰ章 稲作文化の到来と土器様式の変化 …………………………………… 3
第Ⅱ章 東西日本列島の土器西日本 …………………………………………… 10
第Ⅲ章 東西日本列島の土器東日本 …………………………………………… 17
第Ⅳ章 列島の多様な青銅器文化 ………………………………………………
24
図版目録・主要参考文献・協力者一覧 …………………………………………
44
【2024年2月14日 【品切】

書籍番号
82138
書 名
古代学と遺跡学―坂靖さん追悼論文集―
シリーズ
データ
A4 537頁 巻頭カラー図版
ISBN/ISSN
978-4-600-01393-6
編著者
坂靖さん追悼論文集刊行会
出版年
2024年2月
出版者
坂靖さん追悼論文集刊行会
価 格
品切れ
巻頭図版
目次
<特別収録>
寺口千塚古墳群(平石谷川地区)第1次調査とその問題点
―とくに多葬の問題について― 坂 靖
1
葛城川扇状地における縄文時代中・後期の遺跡動態 小泉翔太
9
西北九州の朝鮮半島系筒形容器に関する覚書 岡部裕俊
21
長崎県原の辻遺跡にみる大型砥石の二相 水野敏典
29
扇状地・低中位段丘における古墳時代集住遺跡群形成の過程
―「坂モデル」についての覚書―
若林邦彦 37
近江湖南地域における古墳時代前期の鍛冶
大道和人 45
弥生墳丘墓と前期古墳の性格の相違
―上器配置と玉類副葬の様相から―
三好 玄 53
副葬品配置から見た玉の副葬―玉副葬の変化を考える―
廣瀬時習 61
定型化以前の直弧文
杉山拓己 69
古墳時代前期における円筒埴輪の型式変化
―いわゆる「極狭口縁」を中心に―
宇野隆志 77
五色塚古墳出上埴輪の割付技法
村瀬 陸 85
佐紀古墳集団と南山城
古川 匠 93
葛城王朝と欠史八代―初期ヤマト政権の動向をめぐって―
米川仁一 101
空中写真を利用した墳形の再検討
―大和高田市所在茶臼山古墳を例として―
北中恭裕 111
葛城山麓の古墳を考える―首長墓の選地から―
千賀 久 115
物部氏の首長層居宅
小栗明彦 121
南郷遺跡群の論点―坂靖説の検討―
青柳泰介 129
ヤマト王権の鉄器生産論と南郷遺跡群
村上恭通 139
南郷角田遺跡出上の小鉄片再考
―遺跡出土の鍛造剥片・金属片との比較から―
真鍋成史 143
南郷角田遺跡出土の小札状鉄製品 吉村和昭
151
南郷遺跡群の銅製品について 平井洸史 155
南郷遺跡群における古墳時代中期の山陰東部系土器 中野 咲 163
大県・大県南遺跡の古墳時代中期の鍛冶工房の再検討 田中清美 171
古墳時代の金工品に共有される文様
―日韓の心葉形唐草文を素材に― 山本孝文 181
渡来系鉄製農具刃先の「定着」と「非定着」
―又鍬先・又鋤先、サルポ形刃先、タビ形刃先― 魚津知克 189
紀伊における両頭金具の受容と展開―弓矢儀礼創出素描― 佐藤純一 197
紀伊の製塩土器 田中元浩 207
初期群集墳序説―兵庫県播磨地域の様相から― 阿部 功 215
鳥取県米子市宗像1号墳・5号墳のトレース図 森下浩行 223
備前邑久地域の首長墳とその経済的基盤 亀田修一 233
黒井峯遺跡におけるムラの姿と馬の相関
―黒井峯遺跡Ⅱ・Ⅲ群の再検討を通して― 深澤敦仁 243
上野一之宮・貫前神社周辺の古墳時代後期遺跡 右島和夫 251
群像のなかの太鼓形埴輪
―和歌山市・井辺八幡山古墳の事例を中心に― 松田 度 259
岩橋千塚のヒレ付き円筒台―跪坐人物埴輪の一例として― 丹野 拓 267
九州地方の盾持ち人埴輪の実態 岡﨑晋明 275
『東京人類学会雑誌』掲載の人物埴輪 日高 慎 283
ネリー・ナウマンの「人物埴輪論」を読む 川崎 保 291
古墳時代の動物毛利用の実態を知るための基礎的研究
―奈良県内古墳出土品を例として― 奥山誠義 239
香久山と畝傍山
―原材料としての鉄バクテリア塊の史的意義― 髙橋幸治 307
高取町内検出の大型大壁建物 木場幸弘 315
出土状況からみた三重県北野遣跡出土の有孔広口筒形土器 川崎志乃 319
陶棺のサイズに関する一試考
―近畿地域と告備地域の比較を中心に― 絹畠 歩 325
小山田古墳と舒明天皇陵 清水康二 333
「宜用小石」の石槨について―大化薄葬令と高安山1号墳― 米田敏幸 341
阪神地方枢要部の「権力核」的地域形成過程をめぐる一考察
―古墳時代首長系譜の様相から古代前半期の官衙領域確立に向けて―
森岡秀人 349
南郷遺跡群周辺の古代 大西貴夫 361
畝傍山麓の古代寺院―大窪寺と山本寺の建立背景― 清水昭博 369
南河内の土師器椀生産―宮都への供給という観点から― 木村理恵 377
飛鳥京跡苑池にみる二つの流水施設 東影 悠 385
藤原宮の幢幡図像について 塚田良道 393
宮殿構造からみた伊勢神宮・斎宮の成立
―前期難波宮と皇大神宮・斎王宮殿域の連関― 川部浩司 401
古代志摩国の原像―海産物生産の一断面― 穂積裕昌 411
益田池の復元 北山峰生 419
日本における鬼門の導入と展開 岡見知紀 427
図像からみた古代絵馬の特質―出土絵馬を中心に― 前田俊雄 433
大和国西京瓦屋についての一考察―尻江田瓦屋を中心に― 岡田雅彦 441
春秋戦国時代長平之戦いの兵士埋葬坑について 神谷正弘 449
朝鮮半島青銅器文化と社会 宮里 修 455
韓国ソウル夢村土城を理解するための新資料 權五榮(李東奎訳) 463
百済漢城期における諸墓制の木棺復元 金武重(平郡達哉訳) 469
百済食器にみる飲食文化 韓志仙(中野咲訳) 477
韓半島海洋祭祀遺跡調査研究の動向 平郡達哉 485
百済大通寺の創建瓦―公州班竹洞出土瓦を中心に― 李炳鎬(井上直樹訳) 493
朝鮮時代における鍛冶工房跡の分布と官営製鉄の特徴
―高興・鉢浦萬戸城の製鉄工房跡を中心に― 金 想 民 505
プレ・アンコール期の土器編年構築に向けた予察
―サンボー・プレイ・クック遺跡出土資料を中心として― 本村充保 513
メラネシアにおける巨石遺跡の消長と社会変化
―ソロモン諸島ロヴィアナ地域を事例として― 長岡拓也 519
ユニバーサル・ミュージアムの取り組みについて
―橿原考古学研究所附属博物館の事例― 北井利幸 527
あとがき
【2024年2月5日 【入荷】【ご注文承り中】
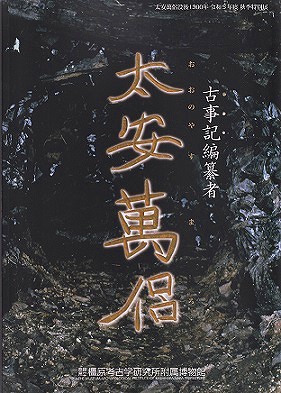
書籍番号
82045
書 名
古事記編纂者 太安萬侶
シリーズ
(太安萬侶没後1300年 令和五年度 秋季特別展 特別展図録第94冊)
データ
A4 87頁
ISBN/ISSN
編著者
奈良県立橿原考古学研究所附属博物館編集
出版年
2023年10月
出版者
奈良県立橿原考古学研究所附属博物館
価 格
1,210円(税込)
年10月7日から11月26日に開催された太安萬侶没後1300年 令和5年度 秋季
特別展『占事記編纂者太安萬侶』の展示解説書である。
目 次
例言
占事記編纂者 太安萬呂
………………………………………………… 5
本展覧会関連地図
………………………………………………………… 7
本展覧会関連年表 …………………………………………………………
8
序章 太安萬侶と古事記
………………………………………………… 9
第一章 太安萬侶が生きた平城京 ……………………………………… 15
第二章 火葬墓―同時代を生きた官人と僧の墓― …………………… 33
コラム 道昭以前の火葬と渡来系氏族 …………………………… 35
第二章 墓誌―名を遺す人々― ………………………………………… 51
コラム 太安萬侶墓の構造と課題 ………………………………… 62
コラム 太安萬侶慕に見え隠れする古代豪族ワニ氏の残影 …… 68
終章 太安高侶墓研究の最前線 ………………………………………… 77
コラム 太安萬侶墓から出土した炭化材の再検討 ……………… 80
資料 ………………………………………………………………………… 82
出品日録 …………………………………………………………………… 84
主な参考文献 ……………………………………………………………… 86
展覧会中の行事 …………………………………………………………… 87
協力機関・協力者・スタッフ …………………………………………… 87
【2024年2月3日 【入荷】【ご注文承り中】
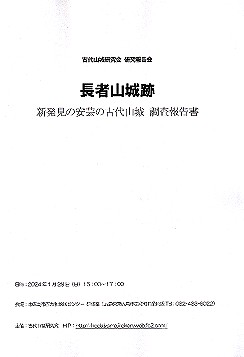
書籍番号
82130
書 名
長者山城跡 新発見の安芸の古代山城
調査報告書
シリーズ
(古代山城研究会 研究報告書)(付図一枚)
データ
A4 24頁
ISBN/ISSN
編著者
古代山城研究会
出版年
2024年1月
出版者
価 格
1,100円(税込) <参考記事>
NHK広島: “かつての安芸国に城が” 広島に新たな古代山城を発見
https://www3.nhk.or.jp/lnews/hiroshima/20240202/4000024935.html
向井一雄(古代山城研究会・代表)「新発見の長者山城跡について」
図版
参考資料
………………………………………………………………………………
★再入荷★
81955 謎の山城・茨城を探る
~古代山城・茨城と芋原の大すき跡~
(第65回古代山城研究会例会)(プログラム・予稿集)
2023年9月 A4 50頁 ¥1,100(税込)
https://www.chugoku-shoten.com/mokuji/jmokuji/81955/81955.html
【2024年1月31日 【入荷】【ご注文承り中】
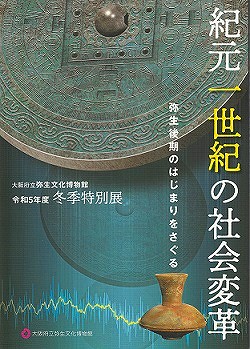
書籍番号
82122
書 名
紀元一世紀の社会変革―弥生後期のはじまりをさぐる―
シリーズ
(令和5年度冬季特別展 大阪府立弥生文化博物館図録76)
データ
A4 112頁
ISBN/ISSN
編著者
大阪府立弥生文化博物館編集
出版年
2024年1月
出版者
大阪府立弥生文化博物館
価 格
1,650円(税込)
【紹介】
紀元一世紀の日本列島では、弥生時代中期から後期への移行にともない、
各地で集落の断絶や土器様式の大きな変化が生じたことが知られていま
す。本展では、近畿地方及び日本海や瀬戸内海沿岸地域の資料を取り上
げ、近年進展めざましい酸素同位体比年輪年代法の研究成果などをまじ
えつつ、集落動態、土器様式、地域間交流などの多角的な視点から、弥
生時代最大の画期とも目されるこの変化が生じた背景にせまります。
もくじ
2 もくじ・凡例
3 ごあいさつ
4 プロローグ
15 第Ⅰ章 繁 栄―弥生時代中期後葉の近畿地方―
27 第Ⅱ章 断 絶―弥生時代後期の始まり―
41 第Ⅲ章 交 流―東アジア情勢の変動―
55 第Ⅳ章 新秩序―祭祀圏の並立―
73 エピローグ
■特別論考
76 鉄製刀剣類からみた弥生時代後期の西日本
岡山大学文明動態学研究所 特任准教授 ライアン・ジョゼフ
■論 考
86 独立棟特柱建物と近畿弥生社会
大阪府立弥生文化博物館 館長 禰冝田佳男
【2024年1月31日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82124
書 名
播磨から弥生社会を問いなおす
シリーズ
(第23回播磨考古学研究集会 資料集)
データ
A4 260頁
ISBN/ISSN
編著者
第23回播磨考古学研究集会実行委員会編集
出版年
2024年1月
出版者
価 格
2,200円(税込)
【講演・報告資料】
報告1 荒木幸治「集落構造の比較分析」……………… 1
播磨の墓調査事例集成……………… (33)
報告2 山中良平「墳墓の変遷からみた播磨の特質」… 89
播磨の集落調査事例集成 ………… (111)
報告3 園原悠斗「播磨における弥生時代石器の特質」
……………… 125
報告4 藤原怜史「播磨における金属器の広がりとその生産」
…………… 133
基調講演 寺前直人「弥生時代中期から後期の社会構造と変化」
…………… 139
「播磨の弥生時代金属器関係資料集成」……………………… 153
「播磨の石器資料集成補遺」…………………………………… 247
【2024年1月31日 【品切】
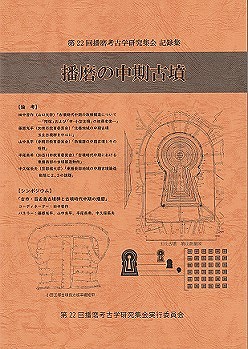
書籍番号
82125
書 名
播磨の中期古墳
シリーズ
(第22回播磨考古学研究集会 記録集)
データ
A4 111頁
ISBN/ISSN
編著者
第22回播磨考古学研究集会実行委員会編集
出版年
2024年1月
出版者
第22回播磨考古学研究集会実行委員会
価 格
【品切】
【論考】
「古墳時代中期の政権構造について―「陪塚」および「中・小型
主墳」の被葬者像―」
田中晋作(山口大学)…………………………… 1
「北播地域の中期古墳 玉丘古墳群を中心に」
藤原光平(加東市教育委員会)………………… 39
「西播磨の中期古墳とその特徴」
山中良平(赤穂市教育委員会)………………… 59
「古墳時代中期における東播西部の古墳築造動向」
平尾英希(加古川市教育委員会)………………
71
「東播東部地域の中期古墳築造動態と2、3の課題」
中久保辰夫(京都橘大学)……………………… 78
【シンポジウム】
「古市・百舌鳥古墳群と古墳時代中期の播磨」 ………………… 93
【2024年1月31日 【2/4 入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82128
書 名
邂逅の考古学-木許守さん還暦記念論文集-
シリーズ
(ナベの会考古学論集 第3集)
データ
B5 135頁
ISBN/ISSN
編著者
出版年
2023年12月
出版者
ナベの会
価 格
2,200円(税込)
序 -日本一の愛妻家考古学者を祝す―……森岡 秀人………ⅰ
…………………木許 守…………1
巨勢山古墳群における木棺直葬墓の副葬品配置について
……尼子 奈美枝……15
石棺型式の共有からみた有明海沿岸地域の首長墓
~北肥後型舟形石棺と横口式家形石棺を採用する古墳を資料として
…………………………太田 宏明………27
ヨーロッパの巨石建造物研究の視点の変化
-ブリテン島の事例を中心に-…………………奥田 智子………41
岩橋千塚古墳群における竪穴式石室について…金澤 舞…………49
写真計測を用いた横穴式石室の記録作成(2)
-奈良県御所市孫九郎山古墳・国見神社参道古墳・條庚申塚古墳-
…………………………金澤 雄太………61
絵葉書セットから推定する古墳の絵葉書の年代
-芦屋神社境内古墳と城山古墳群の絵葉書の撮影年代・発行年代・
使用年代- …………………………竹村 忠洋………69
近世の茶碗焼造に用いた窯道具と釜山窯との比較検討について
…………………………永井 正浩………81
埴輪生産の波及とその変遷………………………花熊 祐基………95
「慶野組銅鐸」の特殊性に関する細部観察からの究め
………森岡 秀人 ……105
墓制からみた中世のはじまり …………………渡邊 邦雄
……123
【2024年1月23日 【入荷】【ご注文承り中】
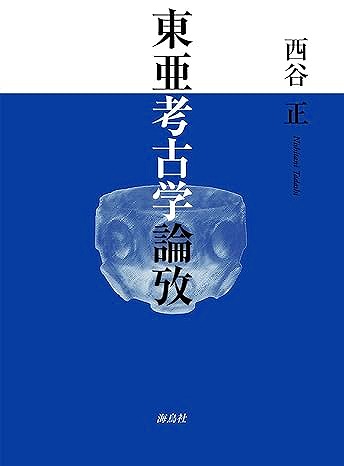
書籍番号
82118
書 名
東亜考古学論攷
シリーズ
データ
A5 650頁(上製本)
ISBN/ISSN
978-4866561561
編 著 者
西谷 正著
出 版 年
2024年1月
出 版 者
海鳥社
価 格
13,200円(税込)
【内容簡介】
鞍形磨臼や支石墓に見る原始の北東アジア関係、陶質土器や鉄、
象嵌など種々の技術革新が物語る南北世界の形成、海底遺跡か
ら明らかになる東シナ海交易の実態、さらにシルクロードを介
した遙か西域との文化交流まで──時空を越えて広がり続ける
探究心の軌跡。
■第1章 [総説]東アジアにおける対外交流の諸段階
第1節 北東アジアの鞍形磨臼
第2節 紀元前後の東アジア
第3節 美松里型土器とその文化について
──中国・東北考古学に触れて
第4節 北東アジアの中の新町支石墓群
第5節 日朝原始墳墓の諸問題
第6節 漢帝国と東アジア世界
第7節 東アジアの中の楽浪郡
第8節 烏丸鮮卑東夷伝の考古学
第9節 倭の国邑と倭国の乱
第10節 中国・東北地方における初期鉄器資料
第11節 済州島と弥生文化
第1節 東アジアの中の武寧王陵
第2節 加耶から見た古代の近畿
第3節 渡来人の虚像と実像
──加賀の渡来文化に関連して
第4節 象嵌技術の系譜
第5節 朝鮮・三国時代の土器の文字
第6節 日本古代の土器に刻まれた初期の文字
第7節 日本出土の朝鮮系土器
第1節 唐・章懐太子李賢墓の礼賓図をめぐって
第2節 泰山における封禅と渡来唐人・破斯人
第3節 拍板について
第4節 朝鮮古代の連珠文
第5節 正倉院の中の新羅文物
第6節 渤海・塔基墓の背景
第1節 1982年度新安海底発見の木簡について
第2節 1983年度新安海底発見の木簡について
第3節 朝鮮陶磁と日本の交流諸問題
第4節 高麗の双鳳文柄鏡について
第5節 石戦について
第6節 高麗・朝鮮両王朝と琉球の交流
第7節 キリシタン考古学の成果
第1節 シルクロードの文化遺産
第2節 新疆から朝鮮・日本まで
第3節 朝鮮古代文化の源流をシルクロードに求めて
第4節 古代の九州・日本にとってのシルクロード
第5節 新疆ウイグル自治区における農業
──その過去と現在
第6節 新疆雑感
第7節 西域から日本まで
第1節 東アジアの「越・韓・琉」──物質文化
第2節 日本と東アジアの水中考古学
第3節 朝鮮半島西南部の水中遺跡
第1節 国境をまたいで登録された高句麗遺跡群
第2節 世界文化遺産に登録された高句麗の遺跡
第3節 公州・扶余地区の世界文化遺産登録戦略
【2024年1月21日 【入荷】【ご注文承り中】
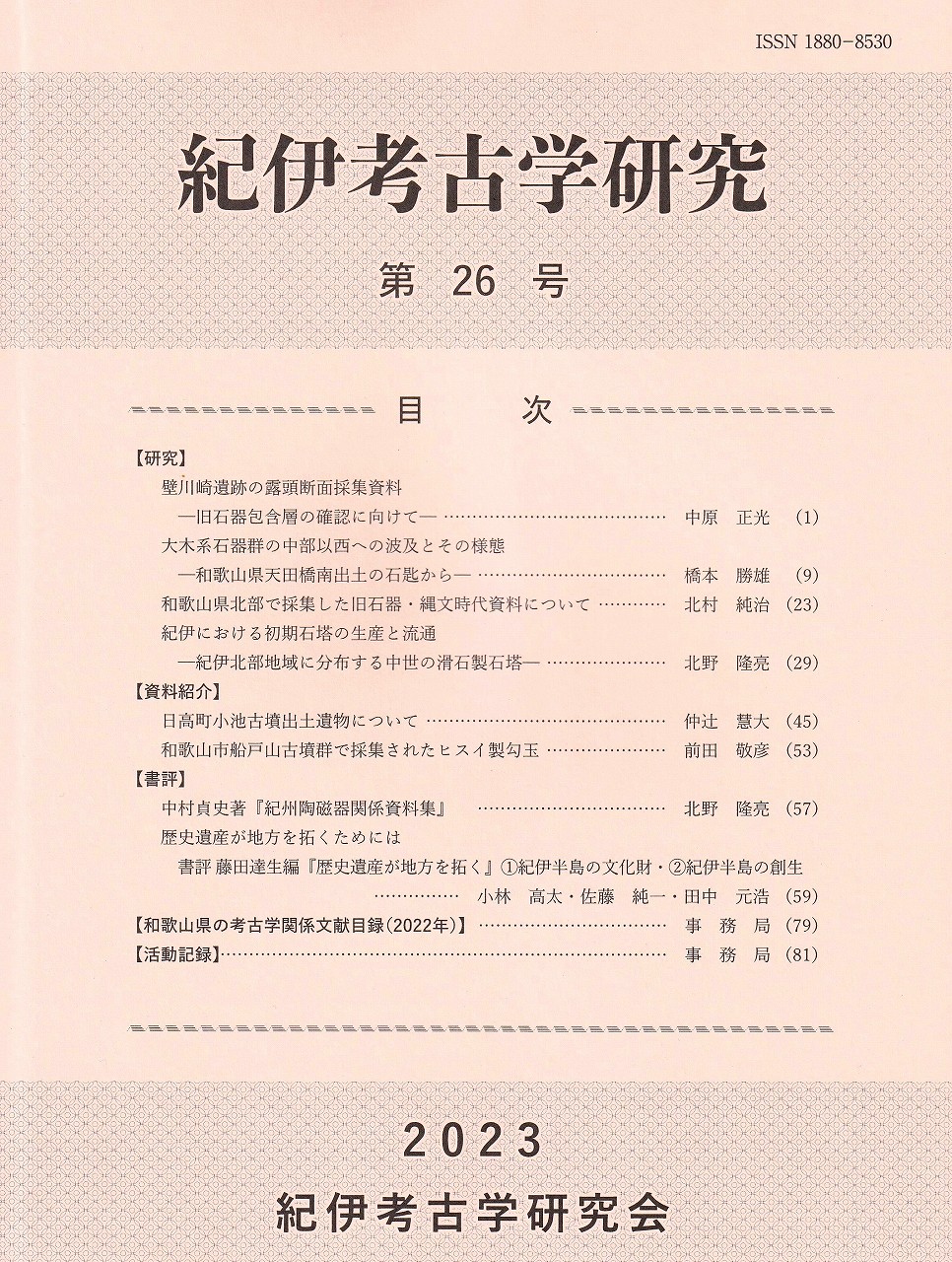
書籍番号
82117
書 名
紀伊考古学研究 第26号
シリーズ
データ
B5 81頁
ISBN/ISSN
1880-8530
編 著 者
紀伊考古学研究会編集
出 版 年
2023年8月
出 版 者
紀伊考古学研究会
価 格
2,200円(税込)
【研究】
壁川崎遺跡の露頭断面採集資料
―旧石器包含層の確認に向けて― ……………中原 正光 (1)
大木系石器群の中部以西への波及とその様態
―和歌山県天田橋南出土の石匙から― ………橋本 勝雄 (9)
和歌山県北部で採集した旧石器・縄文時代資料について
………北村 純治 (23)
紀伊における初期石塔の生産と流通
―紀伊北部地域に分布する中世の滑石製石塔―
………………北野 隆亮 (29)
【資料紹介】
日高町小池古墳出土遺物について ………………仲辻 慧大 (45)
和歌山市船戸山古墳群で採集されたヒスイ製勾玉
………………前田 敬彦 (53)
【書評】
中村貞史著「紀州陶磁器関係資料集』 …………北野 隆亮 (57)
歴史遺産が地方を拓くためには
書評
藤田達生編「歴史遺産が地方を拓く』①紀伊半島の文化財
・②紀伊半島の創生
………………小林 高太・佐藤 純一・田中 元浩 (59)
【和歌山県の考古学関係文献目録(2022年)】 ……事 務 局 (79)
【活動記録】 …………………………………………事 務 局 (81)
【2024年1月21日 【近日入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82108
書 名
古代人の食事と健康
シリーズ
(ものが語る歴史 42)
データ
A5 218頁(上製本)
ISBN/ISSN
978-4-886219299
編 著 者
三舟隆之著
出 版 年
2024年1月
出 版 者
同成社
価 格
4,180円(税込)
【内容簡介】
古代の日本人は何をどのように食べていたのか。食材の解明に
とどまらず、その調理法や保存方法、さらに栄養状態と病気と
の関係までも視野に入れ、学際的な研究成果から古代の食を総
括する。
……………………………………………………………………………
第1章 日本人は何を食べてきたか
1.古代食研究の方法と問題点
2.古代の食を再現する難しさ
3.理化学的アプローチの可能性
第2章 土器と古代食
1.土器から探る古代食研究の可能性
2.土器の名称とその用途
3.土器で米を炊く
4.土器で塩をつくる
5.古代食の再現と土器研究の課題
第3章 文献史料から古代の食を再現する
1.古代の食材とその加工・保存法
2.古代の発酵食品と調味料
3.文献史料にみえる調理法
第4章 古代食再現への試み
1.現代の食品との比較
2.写経所の給食を再現する
第5章 古代人の食と病
1.写経生の食事と病気
2.山上憶良の病気
3.藤原道長と糖尿病
4.天平7・9年の疫病大流行と食事療法
5.『病草紙』にみえる食と病
終 章 古代食研究から何を読み解くか
【2024年1月21日 【入荷】【ご注文承り中】
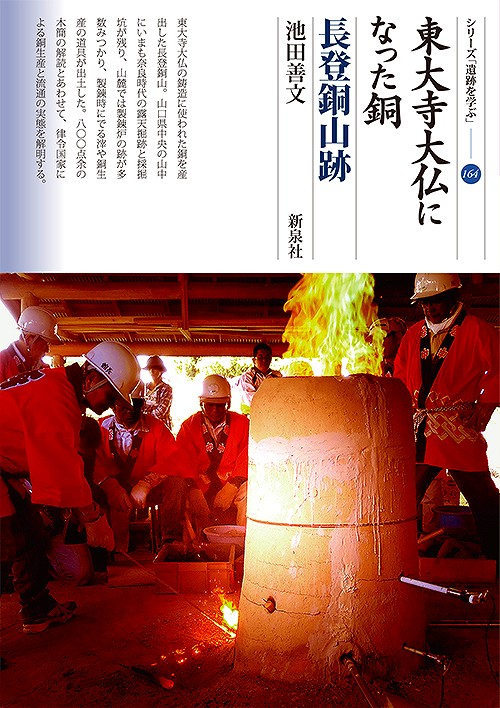
書籍番号
82109
書 名
東大寺大仏になった銅 長登銅山跡
シリーズ
(シリーズ「遺跡を学ぶ」 164)
データ
A5 219頁
ISBN/ISSN
978-4-7877-2334-5
編 著 者
池田善文著
出 版 年
2024年2月
出 版 者
新泉社
価 格
1,870円(税込)
【紹介文】
東大寺大仏の鋳造に産出した銅が使われた長登銅山。山口県
中央の山中にいまも奈良時代の露天掘跡と採掘坑が残り、山
麓では製錬炉の跡が多数みつかり、製錬時にでる滓や銅生産
の道具が出土した。800点余の木簡の解読とあわせて、律令
国家による銅生産と流通の実態を解明する。
【目次】
第1章 大仏鋳造に使われた銅
1 大仏創建時の銅はどこから
2 「奈良登」の伝説とかすかな証拠
第2章 どのように採鉱したのか
1 銅鉱床の生成
2 露天掘跡
3 採掘坑群
4 古代の採鉱技術
第3章 どのように製錬したのか
1 選鉱とその道具
2 製錬作業場
3 古代の炉
4 粘土と木炭
5 大溝と排水溝
第4章 木簡からみた生産の実状
1 長登銅山の役所は
2 採掘の実状
3 製錬の実
4 流通・運搬の実状
第5章 その後の長登銅山
1 その後の長登銅山
2 長登銅山の保存と活
【2024年1月21日 【入荷】【ご注文承り中】
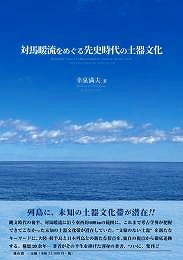
書籍番号
82107
書 名
対馬暖流をめぐる先史時代の土器文化
シリーズ
データ
B5 576頁(上製本)
ISBN/ISSN
978-7-4-63902954-0
編 著 者
幸泉満夫著
出 版 年
2024年1月
出 版 者
雄山閣出版
価 格
24,200円(税込)
【内容紹介】
列島に、未知の土器文化帯が潜在!!
縄文時代の後半、対馬暖流に沿う東西約600㎞の範囲に、これまで
考古学界が把握できてこなかった未知の土器文化帯が潜在していた。
“文様のない土器”を新たなキーワードに、大陸・韓半島と日本列
島との新たな接点を、独自の視点から徹底追跡する。
構想20余年… 著者がその半生を捧げた渾身の著書、ついに、発刊!!
…………………………………………………………………………………
【目次】
第Ⅰ部 対馬暖流ベルト地帯と新たな課題の設定
第1章 対馬暖流ベルト地帯
第2章 西日本の無文系土器をめぐる課題と関連学史
第3章 西日本内部の小地域区分と各基準の設定
第Ⅱ部 対馬暖流ベルト地帯内部における各地の様相
第1章 韓半島東南部域
第2章
北部九州沿岸域
第3章 山陰中部域
第4章 北陸西部域
第Ⅲ部 対馬暖流ベルト地帯周縁の様相
第1章 東西瀬戸内域
第2章
東南四国域
第3章 南四国域
第Ⅳ部 文様のない縄文土器と対馬暖流ベルト地帯
第1章 総括―新たに導かれた17のフェイズと大画期―
第2章 課題と展望
コラム①下関市神田遺跡と対馬暖流ベルト地帯
コラム②隠岐諸島と対馬暖流ベルト地帯
コラム③北陸系土器と中期以前の対馬暖流ベルト地帯
【2023年12月21日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82076
書 名
古墳出現期土器研究 第10号
シリーズ
データ
A4 157頁
ISBN/ISSN
編 著 者
古墳出現期土器研究会編集
出 版 年
2023年12月
出 版 者
古墳出現期土器研究会
価 格
1,320円(税込)
会誌第10号発刊の慶事に寄せて………………森岡 秀人 1
―庄内遺跡の発見からもうすぐ90年、庄内式土器の提唱から
近々60年―
<論文>
庄内形甕の出現とその意義 …………………田中 元浩
3
型式学と分類学・その4 ……………………加納 俊介
23
―型式・形式(器種)・様式―
中河内地域における弥生時代後期の他地域系土器について
………………西浦 熙 41
纒向遺跡各区域の外来系土器出土比率について
………… 市村慎太郎 55
北部九州と山陰の交流 ………………………中川 寧 71
―土器と漆塗り木製品―
庄内式期Ⅳの認識整理と今後の課題(前編)
……………… 米田 敏幸 91
古墳時代中期の北近畿地域における布留系土器の展開と地域色
の発現
―刺突痕跡を持つ高坏を中心として― …中野 咲 103
<コラム>
土器の出入りや影響と人の移動問題をめぐる歩き野帳雑考
………………森岡 秀人 127
<例会報告>
古墳出現期土器研究会の記録(8) ………市村慎太郎人 149
【2023年12月21日 【品切れ】
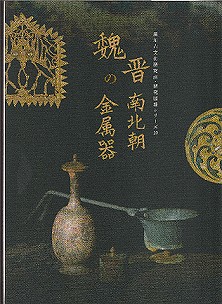
書籍番号
82077
書 名
魏晋南北朝の金属器
シリーズ
(黒川古文化研究所・研究図録シリーズ10)
データ
A4 130頁
ISBN/ISSN
編 著 者
馬渕一輝編
出 版 年
2023年10月
出 版 者
黒川古文化研究所
価 格
品切れ
金属器」(2023年10月14日~11月26日)の開催に伴い編集・発行した。
ただし、展覧会の総目録としてではなく、より研究性の高い図録を
目指して掲載作品を絞った。また、作品ごとに類例や関連論文を掲
載し、魏晋南北朝の器物研究の手引書となるよう配慮した。
(図録より抽出)
───────────────────────────────
目 次
I.
総説 金属器からみた魏晋南北朝の歴史と文化 馬渕一輝 3
Ⅱ. 器物図版
15
1.
後漢・三国時代の青銅器生産 16
2.
両晋十六国時代の胡漢と金製品 32
3. 南北朝時代の革新と響銅
56
4.
魏晋南北朝時代の貨幣 88
Ⅲ.中国地図(三国~南北朝時代)
100
IV.
蛍光Ⅹ線分析による響銅を中心とした金属組成調査 川見典久 102
Ⅴ. 魏晋南北朝時代の五鉢銭
馬渕一輝
108
VI.
仏教文化の東伝と中国青銅器の変容
岡村秀典
114
VⅡ.掲載作品リスト
128
【2023年12月21日 【入荷】【ご注文承り中】
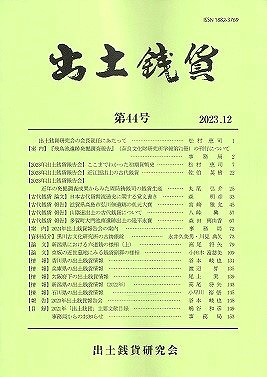
書籍番号
82078
書 名
出土銭貨 第44号
シリーズ
データ
B5 154頁
ISBN/ISSN
1882-3769
編 著 者
出土銭貨研究会編集
出 版 年
2023年12月
出 版 者
出土銭貨研究会
価 格
2,750円(税込)
【案内】『飛鳥池遺跡発掘調査報告』
(奈良文化財研究所学報第71冊)の刊行について
…… 事 務
局 2
【2023年出土銭貨報告会】ここまでわかった初期貨幣史
…… 松 村 恵
司 7
【2023年出土銭貨報告会】近江国出土の古代銭貨
…………… 佐 伯 英
樹 22
【2023年出土銭貨報告会】
近年の発掘調査成果からみた周防鋳銭司の銭貨生産
………………… 丸 尾 弘
介 25
【古代銭貨 論文】日本古代貨幣流通史に関する覚え書き
………………… 森
明彦 33
【古代銭貨 報告】滋賀県高島市弘川佃遺跡の軋元大寳
……… 宮 﨑 雅 允 45
【古代銭貨 報告】山陰道出土の古代銭貨について
…………… 八 峠
興 57
【古代銭貨 報告】多賀町大門池南遺跡出土の隆平永寳
……… 森 田 真由香
67
【案 内】2024年出土銭貨報告会の案内 …………
事 務 局 72
【資料紹介】黒川古文化研究所の古鋳銀錠
………… 永井久美男・川見 典久 73
【論 文】新潟県における六道銭の様相(上) …… 高 尾 将 矢
79
【論 文】京坂の近世墓地にみる銭貨副葬の様相 小田木 富慈美 109
【情 報】香川県の出土銭貨情報 ………………… 谷 本 峻 也
131
【情 報】兵庫県の出土銭貨情報 ………………… 渡
辺 昇 135
【情 報】大阪府下の出土銭貨情報 ……………… 尾
上 実 139
【情 報】新潟県の出土銭貨情報(2022年) ……… 高 尾 将 矢 141
【情 報】石川県の出土銭貨情報 ………………… 小早川 裕 悟 145
【報 告】2023年出土銭貨報告会 ………………… 谷 本 峻 也
148
【目 録】2021年「出土銭貨」主要文献目録 …… 嶋 谷 和 彦
149
事務局からのお知らせ …………………
事 務 局 153
【2023年12月21日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82075
書 名
関西近世考古学研究 29 近世墓地からわかること
シリーズ
データ
A4 222頁
ISBN/ISSN
編 著 者
関西近世考古学研究会編集
出 版 年
2023年12月
出 版 者
関西近世考古学研究会
価 格
3,190円(税込)
講演
「生の近世日本史」から「死の近世日本史」を考える
…………木下 光生 1
江戸時代人骨のライフヒストリーの復元―生物考古学創生―
……長岡 朋人 3
梅田墓(大深町遺跡
0C19―1次)の発掘調査成果 ………大庭 重信 11
寺町旧域の近世墓地 ………………………………………引原 茂治 27
近世・堺の寺墓と三昧場 …………………………………嶋谷 和彦 37
葬制からみた小倉城下町の近世墓地 ……………………佐藤 浩司
55
江戸の近世墓地………………………………………………梅村 忠志 75
加賀藩主前田家墓所とその家臣団の近世墓地……………庄田 知充 91
愛知県内の近世墓地の発掘調査例 ………………………佐藤 公保 107
東海市・長光寺遺跡における近世墓地(子墓)の様相……宮澤 浩司 127
桑名城下町の近世墓地―法盛寺の調査事例を中心として―
………須藤 梢 137
千提寺西遺跡他における近世墓地について―潜伏キリシタンと仏教徒の
墓 ………………合田 幸美 153
明石市の近世墓地―雲晴寺跡、源太塚の調査から― …稲原 昭嘉 167
山陰における近世墓地の考古学的検討 …………………中森 祥 175
大分県下における近世墓地発掘調査の成果について
~女狐近世墓地・中尾近世墓地の発掘調査を中心として~
…………吉田 寛 191
熊本市智照院細川家墓所―熊本藩上級武士一族墓の調査―
………美濃口 雅朗 207
【2023年12月19日 【入荷】【ご注文承り中】
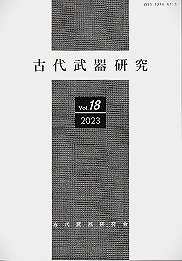
書籍番号
82064
書 名
古代武器研究 Vol.18
シリーズ
データ
A4 115頁
ISBN/ISSN
1346-6313
編 著 者
出 版 年
2022年9月
出 版 者
古代武器研究会
価 格
2,200円(税込)
『古代武器研究」VoI.18の刊行にあたって
塚本敏夫 古代武器研究会代表幹事 ……………………… 2
【論文】
弥生時代の武器の源流:草原地帯から日本列島へ
中村 大介 埼玉大学人文社会科学研究科 ……………… 5
弥生時代併行期における鉄剣をめぐる交流
―朝鮮半島東南部と日本列島を対象として―
鈴木 崇司 駒澤大学大学院・日本学術振興会特別研究員DC2
……………21
古墳時代の外来系武具と倭系武具
内山 敏行 公益財団法人とちぎ未来づくり財団蔵文化財
センター
………37
単龍・単鳳環頭大刀生産の拡大と外来技術工人
金 字大 滋賀県立大学人間文化学部 ………………………51
日本古代の外来系武器類の性能と威儀機能
津野 仁 元 公益財団法人とちぎ未来づくり財団蔵文化財
センター
……………………67
古代の武器・武具生産組織と渡来系技術・文化―雑戸籍を手が
かりに―
田中 史生 早稲田大学文学学術院 …………………………83
コーディネーター 初村武寛、ライアン・ジョセフ
発言者 中村大介・鈴木崇司・内山敏行・金 宇大・津野 仁
・土屋隆史・齊藤大輔・田中史生・橋本達也・森岡秀人
・田中晋作
【2023年12月19日 【入荷】【ご注文承り中】
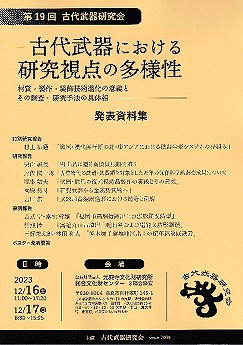
書籍番号
82065
書 名
第19回 古代武器研究会 発表資料集
シリーズ
(古代武器における研究視点の多様性)
データ
A4 84頁
ISBN/ISSN
編 著 者
古代武器研究会編集
出 版 年
2023年12月
出 版 者
古代武器研究会
価 格
1,650円(税込)
──────────────────────────
第19回「古代武器研究会」開催にあたって ……………… ⅰ
日程 …………………………………………………………… ⅱ
【特別研究報告】
村上恭通(愛媛大学)
「戦国・漢代併行期の北・東アジアにおける鉄器生産
システムの枠組み」 ………………………………… 1
【研究報告】
奥山 誠義(奈良県立橿原考古学研究所)
「出土品に遺る有機質痕跡を追う」 …………………9
比佐 陽一郎(奈良大学)
「古墳時代の武器・武具類を対象とした近年の保存科
学的調査成果について」 ………………11
塚本 敏夫(公益財団法人元興寺文化財研究所)
「武器・武具の復元模造品製作の実践とその意義」
…………………………23
園原悠斗(兵庫県教育委員会)
「石製武器から金属製武器へ」………………………39
吉田 広(愛媛大学ミュージアム)
「武器形青銅器造形における鋳造と研磨」…………49
【事例報告】
吉武 学・常松 幹雄(福岡市文化財活用部)
「福岡市高畑遺跡出土の広形銅戈鋳型」……………61
村瀨 陸(奈良市教育委員会坪蔵文化財調査センター)
「富雄丸山古墳出土蛇行剣および龍文盾形銅鏡」…67
三好 栄太郎(熊本市熊本城調査研究七ンター)・
林田 和人(熊本市文化財課)
「熊本城千葉城地区出土の紀年銘象嵌鉄刀」………71
小嶋 篤(九州歴史資料館)
「熊本県菊池市・菊之池A遺跡出土棒状鉄製品の観察」
……………………79
繰納 民之(京都大学大学院)
「古墳時代前・中期の鉄鉾の系列とその意義」……80
高尾 将也(株式会社ノガミ)
「河内駒ヶ谷金剛輪寺旧蔵馬具の出土地」…………81
田中 祐樹(文化庁)・高木公輔(魚沼市教育委員会)
「古林古墳群出上品の復元」…………………………82
徳富 孔一(野良考古学研究所)
「漢代及其前後的墓葬出土の鉄環首刀」……………83
橋本 達也(鹿児島大学総合研究博物館)
「「盾形銅鏡」の系譜」………………………………84
【2023年12月19日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82061
書 名
古代集落の構造と変遷 3
シリーズ
(第26回 古代官衙・集落研究会報告書)(奈良文化財研究所研究報告第39冊)
データ
A4 244頁
ISBN/ISSN
978-4-87805-172-2
編 著 者
中国航誨博物館編著
出 版 年
2023年12月
出 版 者
株式会社 クバプロ
価 格
4,400円(税込)
序 ……………………………………………………………… 3
目次 …………………………………………………………… 5
例言 …………………………………………………………… 6
開催趣旨 ………………………………………………………
7
プログラム ……………………………………………………
8
Ⅰ 報 告 ……………………………………………………
9
古代集落の構造把握にむけた中間まとめ ……道上 祥武 11
出雲国における集落構造と変遷―意宇郡・神門郡を中心に―
……林 健亮 25
伊勢国朝明郡の古代集落の構造と変遷
………川部 浩司 49
律令国家周縁域における集落の構造と変遷―斯波郡北部の集落―
………………西澤 正晴 83
律令国家周縁域における集落構造と変遷
―宮城県における「移民(棚戸)集落」について―
…………………安達 訓仁・佐藤 敏幸 131
千葉県酒々井町飯積原山遺跡の集落構造と性格
……………………木原 高弘 193
文献史料から考える古代集落
…………………磐下 徹 211
Ⅱ 討 論
…………………………………………………… 225
【2023年12月8日 【入荷】【ご注文承り中】
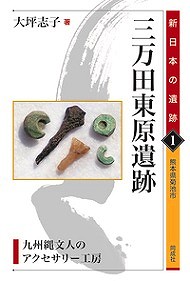
書籍番号
82022
書 名
三万田東原遺跡 九州縄文人のアクセサリー工房
シリーズ
(新日本の遺跡 1)
データ
四六版 146頁
ISBN/ISSN
978-4886219268
編 著 者
大坪 志子著
出 版 年
2023年11月
出 版 者
同成社
価 格
1,980円(税込)
★「新日本の遺跡」刊行開始!★(監修:水ノ江和同・近江俊秀)
***********************************************************
このたび「日本の遺跡」シリーズを継承しつつ、大幅にリニュー
アルした「新日本の遺跡」シリーズを開始いたします。日本列島の
遺跡を再評価し、地域から日本の歴史を照射する新シリーズ!
【内容簡介】
大量の縄文土器が出土し百年以上の研究史をもつ三万田東原遺跡。
近年の調査で判明
した玉製作の実態など、遺跡の魅力を平易に語る。
【目次】
第Ⅰ部 遺跡の特性―三万田東原遺跡とは―
第1章 三万田東原遺跡が注目されてきた訳
第2章 三万田東原遺跡の環境
第Ⅱ部 遺跡のあゆみ―発掘調査が語るもの―
第3章 遺跡発見と郷土の人々
第4章 縄文土器「三万田式」の設定
第5章 1969年の発掘調査
第6章 三万田東原遺跡とクロム白雲母
第7章 三万田東原遺跡の再調査―玉製作の実態解明―
第8章 本遺跡の玉製作からみた日本列島の縄文文化
【2023年12月3日 【入荷】【ご注文承り中】
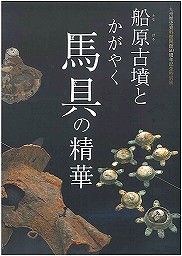
書籍番号
82041
書 名
船原古墳とかがやく馬具の精華
シリーズ
(九州歴史資料館開館50周年記念特別展)
データ
A4 180頁
ISBN/ISSN
編 著 者
九州歴史資料館
出 版 年
2023年10月
出 版 者
九州歴史資料館
価 格
2,200円(税込)
大量の豪華な馬具が埋納されていることがわかりました。これら
の朝鮮半島の影響を受けた馬具たちは当時の国際交流を物語るう
えでも、重要な知見を与えてくれます。今回の展覧会では、船原
古墳と近い時期の国宝の藤ノ木古墳や綿貫観音山古墳、沖ノ島祭
祀遺跡などから出土した高度な金属工芸技術が施された馬具を展
示しております。特に馬冑は日本では3例しか出土しておらず、
今回はそのすべてが一堂に介しております。
金色にかがやき、精緻な文様を生み出す高度な金属工芸技術が
施されたそれらは、まさに古墳副葬品の精華と言えるでしょう。
奈良県藤ノ木古墳や群馬県綿貫観音山古墳から出土した国宝の
馬具をはじめ、列島規模で馬具をご紹介。
【目次】
・序 章 三国丘陵から船原古墳への道
・第一章 船原古墳の世界
・第二章 装飾された馬具の至宝
・第三章 渡来と在来の展開
・第四章 古墳に馬を描く文化
・終 章 古墳を探る科学
特論・資料
【2023年12月1日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82042
書 名
奴国の王都 須玖遺跡群
シリーズ
(シリーズ「遺跡を学ぶ」 163)
データ
A5 96頁
ISBN/ISSN
978-4787723338
編 著 者
井上 義也著
出 版 年
2023年12月
出 版 者
新泉社
価 格
1,870円(税込)
邪馬台国とともに『魏志』倭人伝に大国として記された奴国。
多くの国が乱立するなか、かの地の人びとはなぜ大国を築け
たのか。福岡平野を望む丘陵上に残された王都・須玖遺跡群
から、その繁栄の実態と理由をさぐる。
1 奴国と須玖遺跡群
2 王都・須玖遺跡群
1 王墓の発見
2 王族墓を掘る
3 後期の王墓は存在するか
1 王宮はどこに
2 最有力候補の遺跡
1 圧倒的規模の青銅器生産
2 最古級の青銅器生産遺跡
3 奴国の官営工房
4 青銅器生産の復元と謎
5 ガラス玉の生産
6 鉄器の生産
【2023年11月26日 【入荷】【ご注文承り中】
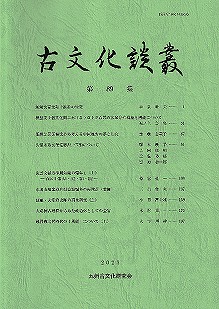
書籍番号
82032
書 名
古文化談叢 第89集
シリーズ
データ
B5 243頁
ISBN/ISSN
1883-0676
編 著 者
武末純一編集
出 版 年
2023年10月
出 版 者
九州古文化研究会
価 格
2,860円(税込)
【目次】
押型文土器文化期におけるトロトロ石器の広域分布現象と機能に
ついて
坂ノ上 奈 央 …… 31
規模と長短軸比から考える中国地方の落とし穴
齋 藤 由美子 …… 67
久留米市良積遺跡出土玉類について 塚 本 映 子 …… 91
吉 田 東 明
比 佐 陽一郎
宮 地 聡一郎
流雲文縁方格規矩鏡の編年 1(上)
―内区主像AI・A2・BI・B2― 徳 富 孔 一 …… 109
市場南組窯跡産須恵器編年の再検討(前篇)
三 吉 秀 充 …… 137
回顧・大宰府史跡の調査研究(上) 小 田 富士雄 …… 159
大成洞古墳群からみた政治体としての金官
木 村 光 一 …… 175
魏晋南北朝時代の「馬俑」について(上)大 平 理 沙 …… 197
【2023年11月26日 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82037
書 名
九州考古学 第98号
シリーズ
データ
B5 172頁
ISBN/ISSN
0387-7078
編 著 者
九州考古学編集幹事
出 版 年
2023年11月
出 版 者
九州考古学会
価 格
2,750円(税込)
―埋葬属性間の相関分析と空間分析を中心として―
端野 晋平
1
吉野ケ里遺跡出土層灰岩製石器の石材原産地推定と考古
学的意義 森 貴教・柚原 雅樹・渡部 芳久
梅﨑惠司・川野 良信 23
古墳時代後・終末期における鐔付大刀の副葬とその性格
―北部九州を対象に― 出見 優人 41
野多目地域の開発史 朝岡 俊也
63
栄山江流域三国時代上器生産体系の展開様相と地域性
李 志映(訳:小池 史哲)
87
西北九州の大珠
―長崎県・大野台支石墓群と狸山支石墓群の大珠再検討―
水ノ江和同・大坪 志子
中尾 篤志・栁田 裕三 111
資料紹介
福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁池等の旧石器関連資料について
―中原志外顕寄贈資料を中心として― 福島日出海 123
関行丸古墳第3屍床出上の方格T字鏡 徳富 孔ー 135
高野山奥之院発見の門司城主長岡勘解由造立の五輪塔
木下 浩良 143
令和5年度九州考古学会総会研究発表要旨 147
九州考古学会賞規程 161
第16回九州考古学会賞・九州考古学会奨励賞について
九州考古学会事務局 162
令和4年度九州考古学会総会の概要 164
令和5年度九州考古学会夏季大会 宮崎大会の概要 165
沖縄県名護市嘉陽上グスクの保存と活用についての要望書
・回答 167
「九州考古学』執筆要項 171
雑誌『九州考古学』における著作権の取り扱いについて 172
【2023年11月26日】【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82036
書 名
令和5年度九州考古学会総会研究発表資料集
シリーズ
データ
九州考古学会編集
ISBN/ISSN
編 著 者
A4 163頁
出 版 年
2023年11月
出 版 者
九州考古学会
価 格
2,200円(税込)
九州考古学の展望―コロナ禍を経て―
──────────────────────────────
令和の九州旧石器研究動向―西北九州を中心として― ………… 1
栁田裕三
新里貴之
一支国を構成する弥生集落の現状と課題
―近々の調査成果を踏まえて― …………………………… 18
松見裕一
熊本市出土「甲子年」銘文鉄刀について ………………………… 28
林田和人・三好栄太郎
阿恵官衙遺跡周辺の官衙関連遺跡について ………………………
34
西垣彰博
韓半島南部地域出土土師器系土器からみた韓日交流 …………… 44
趙晟元
研究発表
──────────────────────────────
福岡県糸島市上鑵子遺跡出土弥生土器毛筆彩色絵画発見 ……… 73
柳田康雄
佐賀市七ケ瀬遺跡の発掘調査について一2,3区の概要報告 …… 83
馬場晶平
宇佐市小部遺跡における古墳時代前期豪族居館の大型建物と周辺景
観の復元 ………… 89
弘中正芳
九州の横穴式石室墳 ………………………………………………… 99
小嶋 篤
史跡長者屋敷官衙遺跡周辺確認調査について ……………………109
丸山利枝
国指定史跡ホゲット石鍋製作遺跡の再評価 ………………………118
東 貴之
湖州鏡の分布と流通 …………………………………………………128
高尾将矢
大村・五島・天草地方の「疱瘡墓」について ……………………138
賈 文夢・野上建紀
幕末期における蒸気船燃料の条件
―発掘調査で出土した石炭の実態調査中間報告― ……148
中野 充
ポスター発表
──────────────────────────────
大万寺裏遺跡群の発掘調査成果 ……………………………………158
藤川貴久
近世五島焼の窯跡と製品について―近年の発掘調査から― ……160
野上建紀・賈 文夢・椎葉 萌
蓋井島における戦争遺跡の3D調査について ………………………162
田尻義了・中原周ー・藤原彰久・池田拓・中山元智・高橋寛宇
【2023年11月26日】 【入荷】【ご注文承り中】
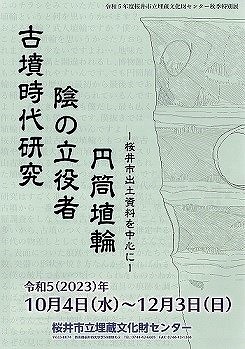
書籍番号
82034
書 名
古墳時代研究陰の立役者 円筒埴輪-桜井市出土資料を中心に―
シリーズ
(桜井市埋蔵文化財センター展示図録 第46冊)
データ
A4 12頁
ISBN/ISSN
編 著 者
桜井市教育委員会編集
出 版 年
2022年9月
出 版 者
桜井市教育委員会
価 格
660円(税込)
地味な印象を受けるかもしれません。けれども古墳時代研究に
おいてとても大きな役割を果たしてきました。
桜井市は最古級の円筒埴輪が出土する箸墓古墳以来、長きにわた
って円筒埴輪が樹立され続けた地域です。本企画展では、桜井市
域出土の円筒埴輪を通して、「地味」な円筒埴輪が古墳時代研究に
果たす役割を知っていただければと思います。
(桜井市埋蔵文化財センターHPより)
【2023年11月26日】 【入荷】【ご注文承り中】
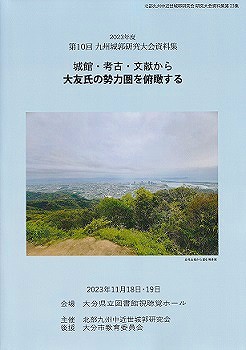
書籍番号
82035
書 名
城館・考古・文献から大友氏の勢力圏を俯瞰する
シリーズ
(2023年度 第10回 九州城郭研究大会資料集)
データ
A4 168頁
ISBN/ISSN
編 著 者
北部九州中近世城郭研究会編集
出 版 年
2023年11月
出 版 者
北部九州中近世城郭研究会
価 格
2,200円(税込)
日程
ご挨拶
目次
中西義昌
縄張り研究から大友氏の勢力圏を俯瞰する ………1
五十川雄也 豊後府内と大友氏遺跡 …………………………………17
浦井直幸 高崎城と加判衆の城郭~豊後・豊前南部を中心に~ …27
山崎龍雄 大友氏の領国支配―筑前国博多の状況― ………………37
山田貴司 筑後における大友氏分国支配の展開過程
―菊池氏との関係を中心に― …………………………59
松尾大輝 文献史料から見た大友氏の筑前国志摩・香椎支配 ……69
若杦善満 豊前北部地域の大友氏支配に関わる中世城館・遺物 75
鶴嶋俊彦 大友氏の肥後支配と城郭 ………………………………85
藤野正人 永禄末筑前争乱- ………………………………………97
小澤太郎 高良山とその周辺における大友氏関連の城館 ……117
4.資料
大友氏の城郭リスト(暫定版) ………………………………………129
大友氏に関係する主要城郭縄張り図 ………………………………140
5.2022年度研究大会シンホジウムの記録
侵攻と抵抗―城郭に見る「天下統一」の様相― …………………151
【2023年11月26日】 【品切】

書籍番号
82033
書 名
九州旧石器 第27号 橘昌信先生追悼論文集
シリーズ
データ
A4 440頁
ISBN/ISSN
編 著 者
越知睦和(佐賀県旧石器文化談話会)編集
出 版 年
2023年11月
出 版 者
九州旧石器文化研究会
価 格
〔献呈論文〕
旧石器時代の構造変動………………………安 斎 正 人……… 1
海を渡った旧石器人―回顧と展望― ……松 藤 和 人……… 11
石の本遺跡群8区石器群の年代・技術・行動
……森 先 一 貴……… 23
宮崎平野の礫塊石器と定着的行動戦略……阿 部 敬……… 33
西多羅ヶ迫遺跡からみる後期旧石器時代初頭の台形様石器の製作技術
について 鎌 田 洋 昭……… 45
人吉市石清水遺跡における剥片尖頭器石器群と剥片剥離技術
村﨑孝宏・岸田裕一… 55
九州における石刃技術の系譜………………杉 原 敏 之……… 65
AT降灰期石器群における石器石材獲得戦略~根引池石器群・栗山
石器群の比較 川道 寛・辻田直人… 75
松山平野における旧石器文化の様相―AT降灰前後を中心に―
………鵜 久 森 彬……… 87
愛媛県における先史石製民具の研究-旧石器時代・年代観-
………沖 野 実……… 95
琉球列島の剥片石器石材産地とその利用について
………山 崎 真 治………109
ナイフ形石器文化終末期の九州地方南部の様相
……荻 幸 二………121
相模野第Ⅳ期に起こった石器群の変化とその背景
………絹 川 一 徳………131
二道梁-林富事件について…………………加 藤 真 二………143
日本列島と朝鮮半島の湧別系細石器………大谷 薫・安蒜政雄…153
古本州島における細石刃石器群の出現と展開-古本州島と周辺地域
での年代的整理を中心に- 芝 康 次 郎………165
西南日本における船野期細石器群の展開…白 石 浩 之………179
九州細石刃文化の始源と展開について……清 水 宗 昭………189
西北九州における船野型と福井型-北方系細石器文化の影響を探る
萩原博文・栁田裕三…199
清武川中・下流域における細石刃石器群…秋 成 雅 博………211
佐世保市福石観音境内岩陰採集の細石刃核について
……川 内 野 篤………221
後阿蘇狩人記―南小国町市原小学校郷上資料室資料の紹介―
………池 田 朋 生………227
鹿児島の石器石材をさがしもとめて-地下資源鉱床付近の探索と石材
の確認- 宮 田 栄 二………235
熊本県菊池市における旧石器時代の様相について
……阿 南 亨…………245
旧石器時代集落における活動内容の一考察-西ガガラ遺跡第1地点の
分析を通じて 藤 野 次 史………251
「石飛遺跡」発見記-水俣の人、斎藤俊三の遺跡発見のこと-
……大 﨑 康 弘………261
島原市の礫石原遺跡について………………山 下 祐 雨………271
うきは市新川遺跡群の石器群………………江島伸彦・小川原励…281
岩戸遺跡で表採した石器……………………髙 橋 愼 二………289
(資料紹介)田野盆地出上の「槍先形尖頭器」について
………金 丸 武 司………293
(資料紹介)多久採集の「槍先形尖頭器」について~別府大学付属博
物館所蔵資料より~ 越 知 睦 和………297
福井洞窟の縄文時代初頭の年代……………三 好 元 樹………305
人吉盆地における縄文時代精神文化―トロトロ石器と岩偶―
………日 髙 優 子………315
柏原式上器小考………………………………林 潤 也………325
九州南東部地域における縄文土器編年研究の現状
………吉 本 正 典………339
南九州貝殻文系上器と押型文上器との接点~春日堀遺跡出上資料の
紹介~ 黒 川 忠 広………351
稲荷山式土器の年代…………………………遠 部 慎………355
大型石包丁に装着具はあるのか?…………日 髙 広 人………367
長崎出島和蘭商館跡・岩原目付屋敷跡出上のガン・フリントとその
背景 藤 木 聡………377
新出の「對馬國住吉社 神寶」図について
………志 賀 智 史………387
橘先生との共同研究の思い出………………佐 藤 宏 之………395
困ったときには橘先生………………………堂 込 秀 人………398
旧石器と縄文―橘先生、江本さん、古森さんとの思い出―
………池 田 朋 生………400
橘先生、長い間ありがとうございました…永 友 良 典………401
橘 昌信先生の想い出………………………安 楽 勉………402
橘先生との出会い……………………………髙 橋 愼 二………404
橘昌信先生との思いで………………………山 田 洋 一 郎………405
橘昌信先生との思い出………………………川 内 野 篤………406
橘 昌信先生ありがとうございました……鎌 田 洋 昭………408
私の考古学事始―橘昌信先生との思い出を中心に―
………遠 部 慎………410
〔九州・沖縄各県の調査・研究動向〕 ………………………415~426
小川原励「福岡県の動向」桑村壮雄「大分県の動向」越知睦和「佐賀
県の動向」
岩谷史記「熊本県の動向」髙橋央輝「長崎県の動向」藤木聡「宮崎県
の動向」
中原一成「鹿児島県の動向」大堀皓平「沖縄県の動向」
【2023年11月26日】 【近日入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82021
書 名
対馬海峡をめぐる先史考古学
シリーズ
データ
A5 280頁 (上製本)
ISBN/ISSN
978-4886219206
編 著 者
廣瀬 雄一著
出 版 年
2023年11月
出 版 者
同成社
価 格
7,150円(税込)
本書は2022年8月に、大韓民国、国立釜山大学校に提出した文学博士
請求論文、原題「大韓海峡をめぐる新石器時代の交流研究(ハング
ル)」の日本語訳を加筆修正したものである。(本書、あとがきより
抜粋)
土器を中心とした第1ネットワーク、石器や骨角器中心の第2ネット
ワーク、装身具中心の第3ネットワークを設定し、その交流の様相を
構造的に解明する。
序章 本書の課題と展望…………………………………………………1
第1節 本書の視点 1
第2節 交流の考古学の現状と課題 2
第1章 本書の構想と構成………………………………………………5
第1節 本書の基本構想 5
第2節 ネットワークの設定にあたって 6
第3節 本書の構成 8
第2章 韓日新石器時代交流史とその研究動向 ……………………11
第1節 土器系統論の展開 11
第2節 石器研究史の検討 13
第3節 土器編年研究と絶対年代の間題点 15
第4節 交流関係土器の確認と間題点 17
第5節 土器交差年代確立とその限界 20
第6節 交流背景の研究―組織的漁撈民交流論の限界― 22
第7節 生業と交流構造変化の研究 24
第8節 既存研究の間題点と本書の視点 25
第1節 領域の地理的環境による設定 29
第2節 海の環境の重要性(対馬暖流の意味) 34
第3節 気候変動が変化の始まり 37
第1節 土器交流が語るもの 39
第2節 土器交流の時代 51
第3節 西唐津式土器成立に対する朝鮮半島系土器の影響 90
第1節 曽畑式上器の幾何学的文様の系統 103
第2節 土器底部からわかること 115
第3節 土器の胎土は語る 122
第4節 縄文中期・後期前半―境界の縄文上器― 126
第5節 縄文後期後半以降の交流―隔離の構造― 130
第1節 第2ネットワークとは何か 133
第2節 新石器時代漁撈用石器―石銛の系譜― 134
第3節 鯨取り―先史捕鯨の復元― 141
第4節 結合式釣針と外洋性漁撈活動 148
第5節 狩猟と漁撈 153
第6節 工具と素材の流通 167
第1節 第3ネットワークの特色 179
第2節 儀礼具から見た第3ネットワーク 200
第3節 第3ネットワークの意味 207
第1節 土器から見た社会の変化 211
第2節 石器の類似性の意味 214
第3節 装身具流通の本質 217
第4節 選択的交流と排他性の社会の変動 218
第5節 交流史研究の目指す方向 222
あとがき 265
【2023年11月1日】 【近刊】【ご注文承り中】
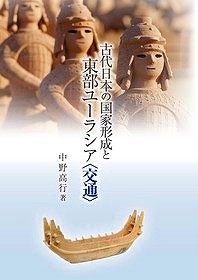
書籍番号
81994
書 名
古代日本の国家形成と東部ユーラシア〈交通〉
シリーズ
データ
A5 368頁 (上製本)
ISBN/ISSN
978-4-8406-2269-1
編 著 者
中野高行著
出 版 年
2023年12月
出 版 者
株式会社 八木書店
価 格
9,900円(税込)
形成されたのか継体天皇の即位、白村江の戦い、高麗郡建郡、遣唐
使の派遣、渤海との外交など重要な事例を〈交通〉の視点から再検
証し、日本古代国家の形成史を描く諸国とのネットワーク形成と国
家成立の関係を解明!
序 章 問題の所在
一
古代国家形成と〈交通〉/二 石母田正の「交通」/
三
妹尾達彦氏のグローバル・ヒストリー/四 ブローデル/
五 本書の構成
第一章 五・六世紀の国際関係像
一
分析の対象・内容と視点/二 五世紀に相当する『日本書紀』
の外交記事①-朝鮮側の史料との比較-/三 五世紀に相当する
『日本書紀』の外交記事② -『百済記』について-/四 六世紀
に相当する『日本書紀』の外交記事-「任那日本府」を中心に-
/五『古事記』の外交記事/六 結 語
付論1 渡来系移住民-普遍的価値・技術を担った人々-
一 帰化人と渡来人/二 五世紀の渡来系移住民/三 六世紀の渡来
系移住民/四 七世紀の渡来系移住民/五 八・九世紀の渡来系移
住民
第二章 継体天皇と琵琶湖-淀川水系
問題の所在/一 継体天皇関連遺跡/二 継体天皇の血縁関係-
近江息長氏を中心に-/三 継体天皇の三宮と淀川水系の港津/
四 琵琶湖-淀川水系流域の諸氏族/結 語
第三章 日本海沿岸諸地域と新羅・加耶
問題の所在/一 古代日朝をめぐる伝説/二 古代日本海域の交易
の実相/結 語-ヤマト王権との関係-
第四章 天智朝創建寺院と正史
問題の所在/一
朱鳥元年の「五寺」と大宝年間「四大寺」の創建
記事/二 天智朝の寺院建設記事の特徴/三
法隆寺西院伽藍の創建
と上宮王家所有の名代/四
舒明-天智系寺院の伽藍配置/結 語
第五章 唐・新羅戦争前後の新羅と倭国
問題の所在/一「白村江の戦い」前後の倭国/二 百済滅亡後の新
羅/三「唐・新
羅戦争」後の新羅/四「白村江の戦い」後の倭国/結 語
第六章 高麗郡建郡の背景
問題の所在/一
高麗郡関係史料と高麗王若光/二 建郡前後の高麗
郡-考古学的視点から-/三
高麗郡建郡と新羅郡建郡/四 高麗郡・
新羅郡の建郡と武蔵守・入間郡領/五
朝鮮系三郡と仏教/結 語-
高麗郡建郡の史的意義-
付論2 『令集解』の注釈書
一
問題の所在/二『古記』について/三『令釈』について/四『跡
記』について/五『穴記』について/六『讃記』について/七『朱
記』について/八『令集解』注釈書をめぐる論争の特徴と今後の課題
第七章 承和度遣唐使発遣と遣新羅使紀三津
問題の所在/一 承和度の遣唐使出国までの経緯-小野篁と紀三津を
中心に-/二 遣新羅使紀三津の帰朝記事/三 執事省牒の諸問題/
四 小野篁と『続後紀』編者の春澄善縄の関係/結 語
第八章 渤海国王宛慰労詔書の〈斗牛〉
問題の所在/一〈斗牛〉についての辞典類の説明/二「北斗七星」
「牽牛星」「斗宿」「牛宿」/三「禰軍墓誌」の「牛斗」の検討/
四 蘇軾「前赤壁賦」に対する解釈/結 語
付論3 高校における朝鮮史教育の展望-前近代を中心に-
一 問題の所在/二 新学習指導要領における歴史系科目/三 朝鮮史
教育の可能性/四 朝鮮史研究と朝鮮史教育/五 教育現場のトレンド
/六 総括と若干の補足終 章 総 括
一
問題の所在/二 各章の結論と課題/三 日本古代の都城と王都
(ミヤコ)
あとがき
索 引
【2023年11月1日】 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82016
書 名
古代大和の王宮と都城
シリーズ
(古代史選書 46)
データ
A5 314頁
ISBN/ISSN
978-5010-7767-0
編 著 者
小澤 毅著
出 版 年
2023年11月
出 版 者
同成社
価 格
7,700円(税込)
変化したのか。王宮と都城のほか、寺院や古墳、条里について、
考古学・文献史学・歴史地理学の成果から多角的に検証。
当時の測量技術にも言及し、宮都空間の包括的な解明をめざす。
第一章 飛鳥の都と古墳の終末
第二章 小山田古墳の被葬者をめぐって
第三章 高市大寺の所在地
第四章
「狂心渠」の経路と高市大寺・香具山宮
第五章 藤原宮の構造と特質
第六章 日本古代の測量技術をめぐって
第七章 平城京と条里の関係
第八章 平城宮中央区大極殿の南面階段
第九章 平城宮中央区大極殿後殿の規模
【2023年11月1日】 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
81996
書 名
古代大宰府の政治と軍事
シリーズ
(古代史選書 45)
データ
A5 338頁
ISBN/ISSN
978-4886219244
編 著 者
松川 博一著
出 版 年
2022年9月
出 版 者
同成社
価 格
8,800円(税込)
大宰府の特質を政治。
軍事の両面から論究。古代都市・大宰府の実像に迫る。
【目次】
序章 大宰府研究の軌跡
第I部
大宰府の政治と官人一大宰府のまつりごと―
第一章 大宰府の官司
第二章
大宰府の官衛と木簡
第二章 木簡からみた筑紫館の役割
第四章 大宰府と官道の整備
第五章
大宰府官人の餞宴と駅家
第六章 菅原道真と大宰府
第Ⅱ部 大宰府の軍事と宗教一大宰府のまもりー
第七章 大宰府軍制の特質と展開
第八章 律令制下の大宰府と古代山城
第九章 大宰府と寺社
終章
大宰府研究の課題
【2023年11月1日】 【入荷】【ご注文承り中】
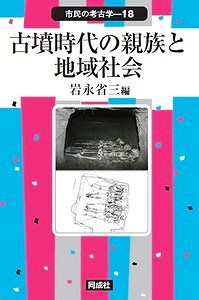
書籍番号
81995
書 名
古墳時代の親族と地域社会
シリーズ
(市民の考古学
18)
データ
A5 186頁
ISBN/ISSN
978-4886219251
編 著 者
岩永 省三編
出 版 年
2023年10月
出 版 者
同成社
価 格
1,990円(税込)
親族組織はその過程でいかに変容したのか。
学際的な分析も踏まえその実相に迫る。
【目次】
第1章 威信財と親族関係 ……………………辻田淳一郎
第2章 儀礼と親族関係 …………………………舟橋京子
第3章 なぜ人骨の形態に地域差が生じたのか
…………………高椋浩史、米元史織
第4章 地下式横穴墓から地域社会を考える
…………………………………吉村和昭
第5章 須恵器生産と氏族認識……………………菱田哲郎
第6章 親族関係からみる国家形成………………岩永省三
【2023年10月26日】 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
82006
書 名
日本先史考古学の諸問題
シリーズ
データ
B5 498頁(上製本)
ISBN/ISSN
978-4-86445-175-8
編 著 者
田中 英司著
出 版 年
2023年11月
出 版 者
六一書房(発売)
価 格
8,800円(税込)
【内容簡介】
則した考古学本来の手法による30余編の論考を選んで収録。
Ⅰ遺物論には縄文時代の石鏃製作やナイフ形石器の型式設定、
縄文前期の抉入尖頭器の認識とその意義から、石器文様論の
確立に至る新たな石器研究を提起した。また博物館収蔵の国
外資料についての分析と考察も行った。
Ⅱ遺跡・遺構論では発掘時の詳細な原位置観察に基づいた、
神子柴遺跡をはじめとするデポについての一連の論考、墓や
居住、石器製作の実態解明を具体的に提示した。
Ⅲ研究史では現代にいたる石器実測図の変遷を江戸期の石器
図にまで遡って、その意義と今後の方向性を定めた。また大
森貝墟碑建設に関する新たな発見史料を紹介するとともに、
モースの大森貝塚の位置に関して再考した。丹念な資料探査
で100年ぶりに見つかった鳴鹿山鹿の石器についても考察した。
Ⅳ時代論には日本先史時代への自己の年代観を表明するとと
もに、関連科学主導へと変質する考古学の現状に警鐘を鳴ら
した。最後に著者が属した発掘者談話会での日常的な随感も
収録した。いずれも著者独自の視点から生み出された「モノ
を究めたい」という多彩な論考の数々を網羅し、考古学本来
の分析の醍醐味や意義をあらためて喚起した。
………………………………………………………………………
【目次】
岡本東三 田中英司さんのこと 山溜穿石
縄文時代における剥片石器の製作について
武蔵野台地Ⅱb期前半の石器群と砂川期の設定について
折断と縄文時代の剥片石器製作
砂川型式期石器群の研究
埼玉の石器と北海道の石器
小岩井渡場遺跡出土の抉入尖頭器
オーストラリア・アボリジニのガラス製槍先
抉入意匠の石器文化
土器のような石器
アドミラルティ諸島のスーベニア
抉入尖頭器の構成要素
石器文様論
2 遺跡・遺構論
石斧の出土状態と着柄
神子柴遺跡におけるデポの認識
住居・墓・アトリエ・デポ 土肥 孝氏の指摘に対して
木葉形尖頭器のデポ 富士見市羽沢遺跡
収蔵・複合デポ 神子柴遺跡
縄文草創期の墓 器物の配置と撒布
もうひとつの製作工程 泉福寺洞穴の細石器
日本先史時代のデポ
状態の原位置論
斧のある場所
デポの視点
デポと交易
縄文時代における黒曜石のデポ
デポをめぐる問題
摩滅痕をもつ尖頭器のデポ 西大宮バイパスNo.4遺跡の石器群
3 研究史
観察と記録 石器実測図の生成
大森貝墟碑の建設 佐々木忠次郎から稲村坦元宛て書簡より
新たに発見された鳴鹿山鹿の「献納石鏃」
4
時代論
先土器時代研究の動向
岩宿の先土器・無土器・旧石器
分かりやすさの代償
斧の意義
日本旧石器時代の実態 -旧石器時代を考える-
『発掘者』の綴りより
原点にもどれるのか?/石器の一期一会/「原位置」をみつめて
/不要不急
略歴・職歴・研究年譜
描き手と書き手
あとがきに代えて
【2023年10月25日】 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
81992
書 名
四面の鏡―海を越えつながる王―
シリーズ
(開館25周年記念企画展)
データ
A4 48頁
ISBN/ISSN
編 著 者
野洲市歴史民俗博物館編集
出 版 年
2023年10月
出 版 者
銅鐸博物館
価 格
1,760円(税込)
野洲市三上山下古墳から出土した2面の獣帯鏡は、群馬県
高崎市綿貫観音山古墳と韓国公州市武寧王陵から出土した
鏡と同型鏡であると知られています。
これら4面の同型鏡は、当時の鏡を媒体とした王権のネッ
トワークが、製作地である中国と朝鮮半島、倭国の近江・
東国を結ぶ東アジア規模で展開していたことを示す資料と
して注目されます。また、これらの同型鏡が副葬されてい
た古墳の被葬者は、継体大王と関連の深い人物であったと
考えられます。
今回の展示では、この4面の同型鏡や様々な資料から、継体
大王が活躍した6世紀前半の国内情勢について考えます。
【目次】
ごあいさつ
目次・凡例
序章 謎の大王、継体
今城塚古墳
第一章 野洲と継体大王
林ノ腰古墳
円山古墳
甲山古墳
第二章 四面の鏡
三上山下古墳出土獣帯鏡
武寧王陵出土獣帯鏡
武寧王陵
綿貫観音山古墳出土獣帯鏡
綿貫観音山古墳
第三章 継体大王を支えた王たち
淀川流域
物集女車塚古墳
青松塚古墳
近 江
鴨稲荷山古墳
山津照神社古墳
尾 張
断夫山古墳
味美二子山古墳
下原古窯跡群
コラム 年代のものさし
コラム 三上山下古墳出土獣帯鏡
コラム 継体大王と桜井谷窯跡群
展示資料解説
展示資料目録
図版目録・写真
参考・引用文献
展示協力機関・協力者
【2023年10月20日】 【入荷】【ご注文承り中】
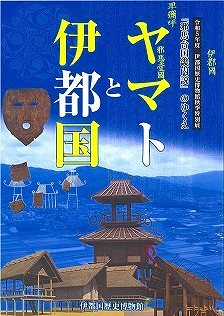
書籍番号
81993
書 名
ヤマトと伊都国 「邪馬台国畿内説」のゆくえ
シリーズ
(令和5年度 伊都国歴史博物館秋季特別展)
データ
A4 72頁
ISBN/ISSN
編 著 者
糸島市立伊都国歴史博物館編集
出 版 年
2022年9月
出 版 者
糸島市立伊都国歴史博物館
価 格
1,100円(税込)
いまだ決着していません。
その候補地は日本列島各地に散在し、有力なものとしては畿内説と九
州説が挙げられます。
伊都国歴史博物館では秋季特別展として、奈良盆地の拠点集落であ
る田原本町の唐古・鍵遺跡と、畿内における「邪馬台国」の有力候補
地とされる桜井市の纒向遺跡で出土した重要文化財を含む貴重な品々
を展示します。
あわせて、伊都国の遺跡や出土品とも比較し、当時の近畿と北部九州
の状況も解説します。
概要:奈良県の唐古・鍵遺跡、纒向遺跡と伊都国関連の遺跡について
比較・紹介。
第Ⅰ章 弥生時代のヤマトと伊都国~唐古・鍵遺跡と三雲・井原遺跡~
第Ⅱ章 王権誕生 ~纒向遺跡~
第Ⅲ章 行き交う人々 ~ヤマトと北部九州~
第Ⅳ章 ヤマトのまつり・伊都国のまつり ~鬼道を事とし、
能く衆を惑わす~
第Ⅴ章 ヤマトの鏡・伊都国の鏡 ~銅鏡百枚の実像~
おわりに
主要展示品目録・図版目録・主要参考文献・協力者一覧
【2023年10月11日】 【品切】
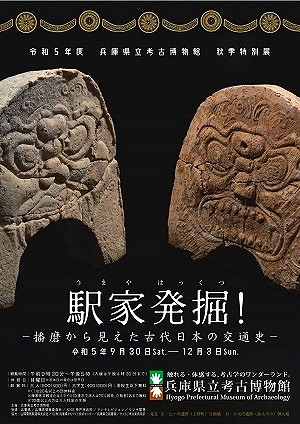
書籍番号
81988
書 名
駅家発掘!―播磨から見えた古代日本の交通史
シリーズ
(兵庫県立考古博物館特別展図録N0.32)
データ
A4 78頁
ISBN/ISSN
(令和五年度 秋季特別展)
編 著 者
兵庫県立考古博物館編集
出 版 年
2023年9月
出 版 者
兵庫県立考古博物館
価 格
1,650円(税込)
「駅家発掘!―播磨から見えた古代日本の交通史―」の展示図録
です。日本が本格的な国家建設に取りかかった1,300年前、奈良の
都と九州の大宰府を結ぶ山陽道沿いには、行き交う使者が馬を乗り
継ぐ「駅家」という施設が建設されました。播磨の駅家は遺跡から
所在を推定できるものが多く、当館では開館以来継続的に発掘調査
を実施しています。
この全国最先端の調査研究により、文献に記された駅家の遺構が
現地で次々と見つかるなど新たな発見がありました。
本展では、県内および山陽道各地の調査事例をもとに、古代の交通
インフラの実態を紹介します。
ごあいさつ
律令国家と中央集権体制
平城京特別史跡平城宮跡
播磨国調邸平城京左京五条四坊八坪、九坪
播磨国府本町遺跡
葦屋駅家深江北町遺跡
古代山陽道福里地点
印鐸神社
特別史跡大宰府政庁跡
国指定史跡鴻臚館跡
Ⅱ 唯一の大路「山陽道」
布勢駅家小大丸遺跡
岸本道昭(たつの市立埋蔵文化財センター)
野磨駅家国指定史跡落地遺跡
島田 拓(上郡町郷土資料館)
Ⅲ 山陽道の駅家を掘る
賀古駅家 古大内遺跡
坂元遺跡
邑美駅家 長坂寺遺跡
大市駅家 向山遺跡
高田駅家 辻ケ内遺跡
池田征弘((公財)兵庫県まちづくり技術センター)
Ⅳ 山陽道往還
明石駅家 大蔵中町遺跡
夷守駅家 内橋坪見遺跡
西垣彰博(粕屋町教育委員会)
小田駅家 毎戸遺跡
西野望(矢掛町教育委員会)
下道圀勝圀依母夫人骨蔵器
下道氏墓域出土骨蔵器
Ⅴ 考察編
一 播磨国駅家の調査研究最前線
―播磨国駅家の「定様」―
二 土器から見た播磨の駅家
三 駅家と播磨国府系瓦
池田征弘((公財)兵庫県まちづくり技術センター)
四 播磨から見えた古代日本の交通史
参考文献
出品目録
謝辞・協力
【2023年10月9日】 【入荷】【ご注文承り中】
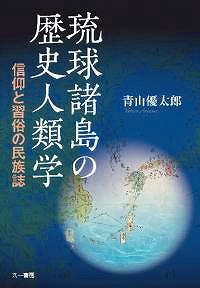
書籍番号
81987
書 名
琉球諸島の歴史人類学 信仰と習俗の民族誌
シリーズ
データ
A5 253頁 (上製本)
ISBN/ISSN
978-4864451741
編 著 者
青山優太郎著
出 版 年
2023年9月
出 版 者
六一書房
価 格
3,850円(税込)
琉球沖縄研究史に一石を投じるものである。
従来の琉球沖縄研究では、特定の地域における特定の風習や文化
の研究が、単発的に行われるきらいがあった。また、琉球諸島全域
の視点より考察を試みた研究においても、地域差に言及するのみで、
その歴史的経緯、社会的背景に言及したものは多いとは言えない。
これは、歴史学や民俗学といった各学問領域が、各々の視点、関心
でのみ研究を行い、学際的な研究が積極的に行われてこなかったこ
との帰結である。しかし、例えばイレズミ習俗である針突などは、
元々、現存する習俗を扱う民俗学の研究対象であったが、現在は消
失しており、よって、同学問領域のみでの研究は難しく、複合的な
研究方法が求められる。ここから、本書では、琉球における土着と
外来の信仰、習俗を歴史人類学的見地より捉え、考究している。
具体的には、琉球沖縄社会に根づいており、かつ女性信仰と男系相
続、祖先祭祀といった観念がより顕著であるオナリ神信仰、御嶽、
門中制度、清明祭、媽祖信仰、針突の6種の起源や性質、機能、伝播、
変遷を考察する。これにより、各々が複雑に絡み合う琉球社会を巨
視的かつ重層的に把握でき、より実態に迫ることができる。
現在、琉球諸島では固有の言語や風習、文化の復興を目指す、ア
イデンティティ再興の動きが見られる。ここから、本書において琉
球の信仰や風習を考察することは、独自の風習、文化を見直す潮流
と軌を一にし、また何らかの視点や視座を提供すると考えられる。
発刊にあたって
序 章
一 琉球諸島概観
二 先行研究
三 本書の課題と構成
四 研究方法
第一章 琉球文化圏におけるオナリ神信仰の研究―その実態および
実例
はじめに
一 古謡におけるオナリ神
二 オナリ神信仰と女性神役
おわりに
第二章 琉球諸島における御嶽の研究 その機能と動態
はじめに
一 古文献における「御嶽」
二 御嶽を構成する諸要素 環境・祭祀者・性質
三 御嶽の変容 近現代期における御嶽
おわりに
第三章 琉球文化圏における門中制度の基礎的研究
はじめに
一 門中制度の研究史
二 門中制度の歴史
三 門中制度とは何か 門中の基礎的概念およびその実態
四 門中制度における禁忌行為や観念
おわりに
第四章 琉球諸島における清明祭および中国・清明節の比較研究
―清明期祖先祭祀の予備的考察
はじめに
一 中国・清明節の概観
二 古文献・史料に見る琉球の清明(祭)
三 琉球の清明祭
第五章 近現代琉球諸島における媽祖信仰の変容に関する一考察
はじめに
一 媽祖信仰の由来およびその輪郭 132
二 琉球の媽祖信仰受容と浸透
三 現代沖縄における対媽祖意識
四 近代社格制度と媽祖信仰
五 欧米新宗教の伝来と媽祖信仰
おわりに
第六章 琉球諸島におけるイレズミ習俗・針突の研究
はじめに
一 針突の歴史と研究史
二 近代以前の針突―文献史(資)料から―
三 近代における針突研究史
―「琉球処分」から第二次世界大戦まで―
四 近代における針突研究史―第二次世界大戦後から現代まで―
五 針突をめぐる社会的背景―イレズミ禁止令と教育政策―
おわりに
[コラム] 針突の起源を考える
―アジアにおける文化伝播の視点から―
主要参考文献
初出一覧
あとがき
【2023年9月25日】 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
81895
書 名
菟原 Ⅲ―森岡秀人さん古稀記念論集―
シリーズ
データ
B5 360頁
口絵カラー1頁
ISBN/ISSN
編 著 者
森岡秀人さん古稀記念会編集
出 版 年
2023年9月
出 版 者
森岡秀人さん古稀記念会
価 格
3,300円(税込)
目 次
巻頭写真
菟原Ⅲ 発刊にあたって
巻頭コラム
古稀までの考古学、古稀からの考古学
1
―インタビューから垣間みる森岡秀人さんの最近の日常―
献呈論文
古墳時代中期の馬具保有古墳についての一考察
尼子奈美枝 11
弥生時代の播磨における居住形態
荒木 幸治 19
-竪穴建物変遷の小地域分析-
近江の石造宝篋印塔の変遷における鏡神社塔の位置について
上垣 幸徳 39
近畿地方における小形[イ方]製鏡の系譜に関する一考察
-和泉市惣ヶ池遺跡鏡を中心に-
上田 裕人 49
三雲城の滋賀県史跡指定の経過について 氏丸 隆弘 63
古墳時代の家族形態と親族構造について 太田 宏明 67
-集落遺跡・群集墳・首長墓系譜の分析から-
一石五輪塔の製作技法~徳島市丈六寺所在未製品を巡って~
海邉 博史 75
掖上鑵子塚古墳の墳丘
木許 守 83
ウィリアム・ゴーランドの滋賀県来訪記録に関する覚書
-近江の考古学黎明期異聞-
田井中洋介 93
『伊勢物語』と芦屋市の「みやび」 竹村 忠洋 105
-古代の摂津国菟原郡芦屋郷からつながる「芦屋」のイメージ-
瀬戸内島嶼部の砂質海岸で検出された中世の埋没塩田面の
遺跡形成過程-愛媛県弓削島の高浜八幡神社境内発掘地での
地形学・土壌微細形態学による検討から-
辻 康男 123
芦屋市金津山古墳の墳丘盛土
土井 和幸 141
堺出土の官窯系朝鮮白磁 永井 正浩
155
滋賀県における凸帯文土器の炭素14年代について
中村 健二 165
湖北の説話を考える③
西原 雄大 171
展望 山陰弥生墓研究上の課題
西村 葵 189
泉佐野における南北朝時代の城郭-樫井城と土丸・雨山城-
西村 歩
201
兵庫県東南部における弥生時代中期サヌカイトの供給状況
禰冝田佳男 221
八十塚古墳群岩ヶ平支群出土の武器と馬具
-八十塚古墳群は、武器・武具の少ない古墳群といえるのか-
白谷 朋世・西岡 崇代 231
摂津市光蓮寺所蔵の弥生時代前期の広口壺について
濱野 俊一 251
弥生時代木棺の小口板の木取りについて
福永 伸哉 263
-神戸市北青木遺跡の事例を起点にして-
[土専]列建物研究 藤本 史子 275
画文帯神獣鏡2例について 村川 義典
295
出土遺物から見た城館遺構論
山上 雅弘 301
火葬の導入をめぐる憶測-2つの書評に答えて- 渡邊 邦雄
319
滑石製模造品祭祀の初源
渡辺 昇 333
執筆者紹介 340
森岡秀人さん略年譜 341
森岡秀人さん主要著作目録(還暦以降) 345
【2023年9月21日】 【入荷】【ご注文承り中】
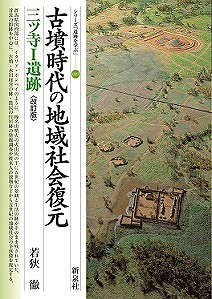
書籍番号
81965
書 名
古墳時代の地域社会復元 三ツ寺Ⅰ遺跡〔改訂版〕
シリーズ
(シリーズ「遺跡を学ぶ」第1期 003)
データ
A5 96頁
ISBN/ISSN
978-4-7877-0433-8
編 著 者
若狭 徹著
出 版 年
2023年9月
出 版 者
新泉社
価 格
1,870円(税込)
【紹介文】
火山灰の下に5世紀の景観と生活の跡がそのまま残されていた。
首長の館跡を中心に、古墳・水田経営の跡・農民の住居跡の発掘
調査や渡来人の遺物などから5世紀の地域社会の全体像を復元する。
第1章 首長居館の発見
1 居館発見以前
2 姿をあらわした巨大施設
1 三ツ寺Ⅰ遺跡の位置と全体像
2 濠を掘り、川を堰き止め、石を積む
3 館内部には何があったか
4 見えないものを想定する
5 築造・改築・廃棄のプロセス
1 遺物の出土状態
2 首長が独占した先進技術─冶金遺物
3 祭儀のための道具たち
4 土器たちの語るもの
1 三ツ寺Ⅰ遺跡の特性
2 水の祭儀を司る首長
1 首長による政治・経済活動
2 古墳から見る首長の政治領域と儀礼
3 人びとの暮らしと神マツリ
【2023年9月21日】 【入荷】【ご注文承り中】
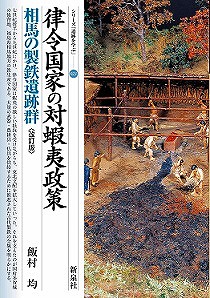
書籍番号
81966
書 名
律令国家の対蝦夷政策 相馬の製鉄遺跡群〔改訂版〕
シリーズ
(シリーズ「遺跡を学ぶ」第1期 021)
データ
A5 96頁
ISBN/ISSN
978-4-7877-0631-4
編 著 者
飯村 均著
出 版 年
2023年9月
出 版 者
新泉社
価 格
1,870円(税込)
がらも、東北支配を拡大していった。それを支えたのが国府多賀城
の後背地、福島県相馬地方の鉄生産である。大量の武器・農耕具・
仏具を供給するために推進された古代製鉄の全貌を明らかにする。
第1章 真金吹く郷
1 古代の鉄づくり
2 姿をあらわした製鉄遺跡群
3 律令国家と製鉄遺跡群第2章 木炭窯を掘る
1 木炭窯の種類
2 木炭窯の展開
1 箱形炉
2 竪形炉
3 「踏みふいご」付設の箱形炉
4 製鉄炉の展開
1 製鉄技術はどこからきたのか
2 何がつくられたのか
3 指導者の墓と管理施設
4 国府多賀城とのかかわり
1 蝦夷の反乱と行方軍団
2 郡司層による生産体制の整備
3 鉄生産の広がりと環境破壊
【2023年9月21日】 【近着】【ご注文承り中】
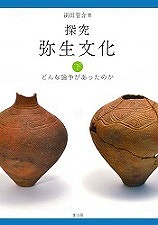
書籍番号
81967
書 名
探究 弥生文化(下)―学説はどう変わってきたか―
シリーズ
データ
A5 168頁
ISBN/ISSN
978-4639029212
編 著 者
浜田晋介著
出 版 年
2023年8月
出 版 者
(株)雄山閣
価 格
2,640円(税込)
現在も大きな影響を与え続けている探究論争の内容をわかりやすく
解説。
2 弥生土器規定論争―弥生土器は古墳から出土するのか
3 弥生竪穴論争―弥生の竪穴は住居か
4 ミネルヴァ論争―縄文と弥生の関係とは
5 文化伝播・変容論争―弥生文化を作ったのは誰だ
6 弥生戦争論争―戦争の証拠は何か
【2023年9月19日】 【入荷】【ご注文承り中】

書籍番号
81964
書 名
貿易陶磁研究 第43号
シリーズ
データ
A4 199頁
ISBN/ISSN
0286-343X
編 著 者
日本貿易陶磁研究会編集
出 版 年
2023年9月
出 版 者
日本貿易陶磁研究会
価 格
3,850円(税込)
【目次】
高麗陶器器種構成の変遷-窯跡出土資料を中心に-
………………主 税 英 德
【開催趣旨】
あの遺跡、再びの共有と展開 …………………小 野 正 敏
【報告・コメント】
平泉遺跡群出土の貿易陶磁器研究の2000年以降の新研究と
新発見について ………………八重樫 忠 郎
「平泉遺跡群出土の貿易陶磁研究について」(八重樫忠郎氏)に
よせて ………………水 口 由紀子
鴻臚館・博多-古代・中世の国際貿易拠点-
………………………田 上 勇一郎
古代・中世日本における貿易の拠点と制度
…………………………荒 木 和 憲
鎌倉市今小路西遺跡(御成小学校内)-発掘調査から32年の現在-
………………松 吉 里永子
文献史料にみえる「鎌倉中」御家人の鎌倉屋敷
-松吉里永子報告に寄せて- ………………田 中 大 喜
今帰仁グスクにおける貿易陶磁研究-年代観と出土量を中心に-
………………瀬 戸 哲 也
瀬戸哲也氏「今帰仁グスクからみた琉球列島の出土貿易陶磁研究」
に寄せて ………………池 谷 初 恵
北の世界の貿易陶磁器-南部氏関連城館を中心に-
………………布 施 和 洋
北日本における陶磁器研究からみえる中世社会
-「布施和洋」報告へのコメント- ……工 藤 清 泰
一乗谷、城下町の陶磁器消費への視点 ………小 野 正 敏
小野正敏「一乗谷、城下町の陶磁器消費への視点」に対する
コメント-中世消費遺跡研究の潮流- ……鈴 木 康 之
堺環濠都市遺跡から出土した貿易陶磁器
-「琉球貿易」、「南蛮貿易」を中心として-
………………續 伸一郎
中世後期の堺と対外貿易 ………………………岡 本 真
近世都市江戸出土の貿易陶磁器研究 …………堀 内 秀 樹
【資料紹介】
首里城二階殿地区から出土したチャンパ黒釉四耳壺
續 伸一郎
彙報
執筆要項
海外研究者へ
【2023年9月14日】 【入荷】【ご注文承り中】
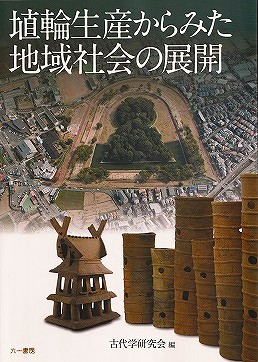
書籍番号
81958
書 名
埴輪生産から見た地域社会の展開
シリーズ
データ
B5 385頁
ISBN/ISSN
978-4-86445-173-4
編 著 者
古代学研究会編
出 版 年
2023年9月
出 版 者
六一書房
価 格
5,500円(税込)
古墳築造の一環として埴輪生産が行われたとき、それを支えた
地域基盤はどのようなものであったのか。
古墳築造と埴輪生産によって、各地域にはどのような変化が表
れたのか。
本書では、埴輪生産遺跡をキーワードに、古墳時代の地域社
会の在り方、さらには地域と王権との関係を考古学的分析により
明らかにすることを目的とする。畿内の埴輪生産のみならず須
恵器生産、須恵器と埴輪が同時生産された尾張との比較を通じ、
それぞれの特徴を描き出す。文献史学にみえる「土師氏」は埴輪
生産とどのような関係にあり、埴輪生産から「部民制」や「上番」
はどう読み解けるのか、その具体像に迫る。各地の埴輪生産遺跡
を検討の中心に据え、古墳への供給関係、周辺集落との関係、埴
輪生産から読み解く古墳時代の権力構造など、多角的な分析をも
とに埴輪生産の歴史的背景を解明する。巻末には、全国の埴輪生
産遺跡集成を収録。
古代学研究会2019年度拡大例会・シンポジウムをもとにした成
果報告書。
目 次
序 ………………………………………………………森岡秀人 ⅰ
例 言 ……………………………………………………………
V
〈趣旨説明〉
地域社会の展開と手工業生産 …………………東影 悠 3
―埴輪生産遺跡と集落・古墳の対比から―
〈報告〉
古墳時代前期の埴輪生産関連遺跡と集落・古墳
………………金澤雄太 11
埴輪生産遺跡と集落からみる中期埴輪生産の実相
………原田昌浩
35
生産遺跡からみた後期の埴輪生産の実態 ……花熊祐基 57
―古墳・集落との比較を通じて―
須恵器生産と地域社会の展開 ………………中久保辰夫 77
埴輪生産遺跡、集落と地域社会 ………………早野浩二 97
―尾張とその周辺地域―
文字資料からみた埴輪生産・造墓の労働力と土師氏
……溝口優樹 117
〈シンポジウムの記録〉
シンポジウム討論 ………………………作成:東影 悠 143
〈ミニシンポジウムの記録〉
ミニシンポジウム討論
…………………作成:山口等悟 161
古墳時代前期の埴輪生産関連遺跡と集落・古墳(追補)
…………………金澤雄太 191
埴輪生産遺跡と集落からみる中期埴輪生産の実相(補遺)
…………………原田昌浩 201
後期埴輪生産と地域社会 ………………………花熊祐基 209
古墳時代須恵器生産に関する研究の現状と課題
…………………中久保辰夫 219
尾張とその周辺地域における埴輪生産と地域社会(補論)
…………………早野浩二 229
文字資料からみた埴輪生産・造墓をめぐる諸問題
………溝口優樹 237
集落研究と古墳研究 ……………………………森岡秀人 249
ヤマト王権と埴輪生産 ……………………………坂 靖 263
埴輪の生産体制論 ………………………………高橋克壽 273
埴輪生産の進展と王権 …………………………廣瀬 覚 289
埴輪生産と地域社会の動向 …………………和田一之輔 299
九州北部の古墳と集落 …………………………小嶋 篤 311
―八女古墳群の造営と「筑紫縦貫道」―
関東・東北の埴輪生産遺跡と供給圏 …………東影 悠 321
土師器生産と埴輪生産 …………………………三好 玄 329
-前期後葉の画期の評価―
埴輪生産からみた地域社会と王権
……………東影 悠・三好 玄 341
執筆者一覧
【2023年9月14日】 【近刊】【ご注文承り中】
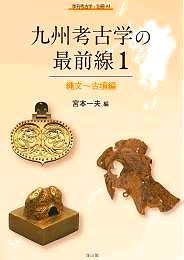
書籍番号
81963
書 名
季刊考古学・別冊43 九州考古学の最前線 1 縄文~古墳編
シリーズ
データ
B5 152頁
ISBN/ISSN
978-4639029427
編著者
宮本 一夫編
出版年
2023年9月
出版者
(株)雄山閣
価 格
2,860円(税込)
【内容紹介】
テーマについて、現状と課題、最新の研究動向をまとめる。
【目次】
九州考古学の現在1―先史時代―
(宮本 一夫)
九州縄文文化の始まり―福井洞窟― (栁田裕三)
南部九州における縄文時代草創期土器編年とイベント・気候変動に関する
研究展望 (桒畑
光博)
九州縄文時代における大規模集落遺跡の出現
―アミダ遺跡における生業戦略― (福永
将大)
クロム白雲母製玉類の製作
―熊本県菊池市・三万田東原遺跡の発掘調査から― (大坪
志子)
植物圧痕からみた九州の縄文農耕と栽培植物 (小畑弘己)
九州の無刻目突帯文土器の様相と刻目突帯文土器の出現
(宮地聡一郎)
耳栓からみた縄文時代日韓交流 (古澤
義久)
弥生時代の始まりと支石墓・磨製石剣 (平郡 達哉)
板付式土器の成立 (三阪 一徳)
弥生時代北部九州の米 (上條 信彦)
渡来的弥生時代人
(米元 史織)
石斧生産と弥生社会 (森 貴教)
「漢委奴国王」金印
(大塚 紀宜)
弥生時代の墓制
(溝口 孝司)
弥生時代の小形?製鏡 (田尻 義了)
弥生時代のガラス製玉類 (谷澤 亜里)
弥生時代の鉄製武器―刀剣研究を中心とした課題と展望― (立谷 聡明)
楽浪系・三韓系土器からみた弥生時代の北部九州(森本幹彦) 弥生時代の
板石硯 (久住 猛雄)
古墳時代の鏡
(辻田淳一郎)
沖ノ島研究―世界遺産登録後の歩み―
(福嶋真貴子)
九州における古墳時代人骨 (高椋 浩史)
古墳時代の親族関係と儀礼 (舟橋 京子)
九州の初期須恵器
(三吉 秀充)
渡来系集落 (重藤 輝行)
玄界灘沿岸における6・7世紀の武器と武装 (齊藤 大輔)
九州における古墳時代の胴丸式小札甲
(松﨑 友理)
古墳時代の馬具 (西
幸子)
島内地下式横穴墓群 (橋本
達也)
南九州の地下式横穴墓
(吉村 和昭)
九州の装飾古墳
(藏冨士 寛)
屯倉の成立
(菅波 正人)
庚寅銘大刀と鋳銅鈴からみた元岡G6号墳の時代背景と東アジア
(桃﨑 祐輔)
船原古墳
(甲斐 孝司)
壱岐島の古墳と副葬品
(田中 聡一)
【2023年9月13日】 【入荷】【ご注文承り中】
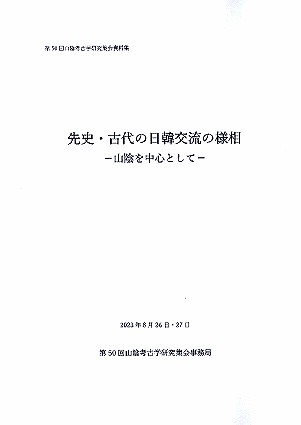
書籍番号
81956
書 名
先史・古代の日韓交流の様相―山陰を中心として―
シリーズ
(第50回 山陰考古学研究集会資料集)
データ
A4 約170頁
ISBN/ISSN
編 著 者
出 版 年
2023年8月
出 版 者
第50回山陰考古学研究会事務局
価 格
2,750円(税込)
目 次
寄稿文① 渡辺貞幸「研究運動としての山陰考古学研究集会-第50回
研究集会に寄せて-」………………………… 1
寄稿文② 中原斉「研究集会が果たしてきたこと、目指すべきもの
-第50回山陰考古学研究集会を迎えて-」 …… 2
基調報告① 趙晟元(前 釜慶大学校博物館)
「韓半島南部地域出土土師器(系)土器からみた
日韓交渉」 …………………………………… 3
基調報告② 亀田修一(岡山理科大学)
「古墳時代の山陰と朝鮮半島」 ……………… 22
地域報告① 山崎頼人(小郡市教育委員会)
「山陰における無文土器からみた日韓交渉」 70
地域報告② 高尾浩司(鳥取県地域づくり推進部文化財局文化財課)
「鉄器からみた弥生時代の交流」 …………… 96
地域報告③ 松尾充晶(島根県立古代出雲歴史博物館)
「山陰西部における古墳時代の渡来系遺物」…122
地域報告④ 君嶋俊行(鳥取県教育文化財団)
「山陰東部における古墳時代の渡来系遺物」…140
誌上発表 土屋隆史(宮内庁書陵部)
「獅?文帯金具の文様系列と製作技術-鳥取県高山
古墳出土獅?文帯金具の検討を中心に」 ……162
【2023年9月9日】 【品切】
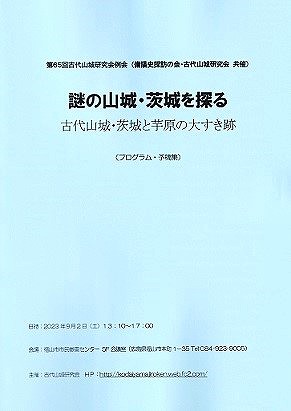
書籍番号
81955
書 名
謎の山城・茨城を探る~古代山城・茨城と芋原の大すき跡~
シリーズ
(第65回古代山城研究会例会)(プログラム・予稿集)
データ
A4 50頁
ISBN/ISSN
編著者
古代山城研究会
出版年
2023年9月
出版者
古代山城研究会
価 格
目 次
田口義之(備陽史探訪の会・会長)「備陽史探訪の会と古代山城の探索」
松尾洋平(古代山城研究会)「古代山城「茨城」の実像を探る
―含同踏査の成果から―」
向丼一雄(古代山城研究会・代表)「茨城と抜原郷」
村田 晋(広島県教育事業団)「備後茨城周辺の終末期古墳について」
山岡 渉(広島市文化振興課)「蔵王山・亀ヶ岳の鉄塔改築に伴う試掘・
確認調査から」
【2023年9月4日】 【品切】【ご注文承り中】
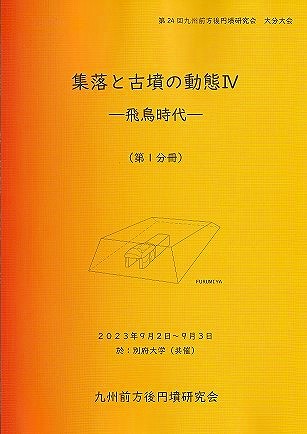
書籍番号
81896
書 名
集落と古墳の動態 Ⅳ―飛鳥時代―(全2冊)
シリーズ
(第24回 九州前方後円墳研究会大分大会 発表資料集)
データ
A4 832頁
ISBN/ISSN
編著者
第24回九州前方後円墳研究会大分大会実行委員会編集
出版年
2023年8月
出版者
第24回九州前方後円墳研究会大分大会実行委員会
価 格
※資料集の正誤表がございます。以下のURLよりご覧いただき
印刷して資料集に挟んでいただければ幸いです。
https://www.chugoku-shoten.com/mokuji/jmokuji/20230902/20230902.pdf
………………………………………………………………………………
<九州前方後円墳研究会>HPより
主 旨:九州前方後円墳研究会では、第21回大会から新たなテーマと
して、集落を軸に古墳との関係を数回に分けて検討していくことに
なりました。 前回まで前期、中期、後期を検討してまいりましたが、
今回の研究会も引き続き、
集落を軸にして古墳・古墳群との関係を検討します。今回検討の対象
とする時期は7世紀(飛鳥時代)です。後期段階で爆発的に増加した
古墳は、当該時期で減少します。
そのことと集落も対応して減少するのか?しないのか?。古墳の減少
とも連動するかのようにも見える7世紀後半から出現する官衙関連施設
とどう関連するのか? 古墳と集落、そしてその延長線上、あるいは
対立軸でもある首長(豪族)居館・寺院・官衙関連施設(牧・ミヤケ・
評・郡家といった機関)・古代山城・祭祀遺跡等も検討対象とし、
当該期の様相にせまっていけたらと思います。
開催趣旨・例言 ……………………………………………………… ⅰ
大会日程 ……………………………………………………………… ⅱ
第1分冊目次 ………………………………………………………… ⅲ
第2分冊目次 ………………………………………………………… ⅳ
資料作成にあたっての留意点 ………………………………………
ⅵ
(代表執筆:久住猛雄・長直信)
「九州島における飛鳥時代の土器
-土器検討部会のまとめと遺跡動態分析にあたっての留意点-」 1
【地域の発表、および誌上報告】
【福岡県(その1)】
久住猛雄(福岡市埋蔵文化財センター)
「6世紀中頃~7世紀代の比恵・那珂遺跡群
―「那津官家」・「筑紫大宰」・「長津宮(磐瀬行宮)」関連遺跡に
ついて―」
………………………………………………………… 27
★長直信(文化庁)
「豊前中部地域における墳墓と集落動態の基礎的研究
―飛鳥時代を中心に―」
………………………………………… 67
目 次(第Ⅱ分冊)
【福岡県(その2)】
★上田龍児・山元瞭平(大野城心のふるさと館)
「7世紀の博多湾沿岸地域」 ………………………………………
1
★下原幸裕(福岡県教育庁)
「太宰府周辺における7世紀の集落について」 …………………
67
・高橋渉※(※小郡市教育委員会 ※※大刀洗町教育委員会)
「御原郡周辺における7世紀代の集落と墳墓の動態」 ………… 93
★太田智(宗像市)
「宗像周辺の7世紀代の動態―古墳・須恵器生産を中心に―」 141
小嶋篤(九州歴史資料館)
「遠賀川流域と飛鳥時代」 ……………………………………… 161
西垣彰博(粕屋町教育委員会)
「糟屋地域における7世紀の集落と古墳の動態について」 …… 215
中島圭(朝倉市教育委員会)
「7世紀における朝倉~浮羽地域の集落と古墳の動態」 ……… 255
小川原励(久留米市市民文化部文化財保護課)
「古墳時代終末期の集落と古墳の動態―久留米市域―」 …… 269
檀佳克(八女市教育委員会)
「福岡県南部―南筑後地域(集落と古墳の動態―古墳時代終末期)」
…………………… 287
安部和城((公財)北九州市芸術文化振興財団埋蔵文化財調査室)
「豊前国企救郡・筑前国遠賀郡東部(北九州市域)における集落と
古墳の動態―6世紀後半から8世紀―」………………………… 295
【佐賀県】
★塩見恭平(佐賀県文化課文化財保護・活用室)
「佐賀平野(嘉瀬川以東)の集落と古墳について
―6世紀末~8世紀初頭―」
…………………………………… 365
徳富孔一(野良考古学研究所)
「嘉瀬川以西地域における集落と古墳の動態―飛鳥時代―」… 385
【長崎県】
野澤哲朗(諫早市)
「肥前西部における7世紀代の集落と墳墓の動向」 ……………… 423
田中聡一(壱岐市教育委員会)
「壱岐島における7世紀代の集落と古墳の動態」 ………………… 447
尾上博一(対馬博物館)
「対馬における7世紀代の集落と墳墓の様相」 …………………… 459
【熊本県】
★林田和人(熊本市文化市民局)
「熊本県地域における飛鳥時代の集落概観」 …………………… 463
【大分県】
丸山利枝(中津市歴史博物館)
「豊前南部(下毛郡)における集落と墳墓の動態」 ……………… 519
弘中正芳(宇佐市教育委員会)
「7世紀の宇佐郡・国碕郡における集落と古墳の動態」 ………… 535
玉川剛司(別府大学)
「豊後国速見郡(大分県別府市・日出町・杵築市)の集落と古墳の動態」
…… 547
★越智淳平(大分県教育庁)
「豊後地域における飛鳥時代(古墳時代終末期)の古墳と集落の動態」
………567
工藤心平(竹田市教育委員会)
「竹田市(竹田・直入地域)の7世紀代の集落と古墳の様相」 …… 625
若杉竜太(日田市教育庁)
「筑後川上流域~日田・玖珠地方~における集落と古墳-7世紀代を
中心として-」
…………………………………………………… 633
【宮崎県】
★今塩屋毅行(宮崎県立西都原考古博物館)
「日向における古墳時代終末期の集落と古墳」 ………………… 647
【鹿児島県】
松﨑大嗣(指宿市教育委員会)
「大隅・薩摩地域における飛鳥時代の集落と古墳」 ……………
695
【2023年8月27日】 【入荷】【ご注文承り中】
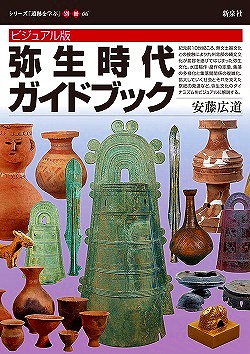
【紹介文】
書籍番号
81942
書 名
ビジュアル版 弥生時代ガイドブック
シリーズ
(シリーズ「遺跡を学ぶ」別冊06)
データ
A5 96頁
ISBN/ISSN
978-4-7877-2330-7
編 著 者
安藤 広道著
出 版 年
2023年9月
出 版 者
新泉社
価 格
1,870円(税込)
縄文文化が変容を遂げてはじまった弥生文化。水田稲作・畠
作の定着、集落の多様化と集落間関係の複雑化、拡大してい
く社会とそれを支えた祭祀の発達など、弥生文化のダイナミ
ズムをビジュアルに解説する。
02 弥生文化をどのようにとらえるのか
03 縄文文化から弥生文化への変容
04 弥生文化・弥生時代の枠組み
05 弥生文化の農耕技術
06 弥生文化の食糧事情
07 日常生活の道具
08 弥生文化の集落
09 人びとのすがたと人口
10 集落間、地域間の関係の進展
11 祭祀・儀礼の発達
12 集団間の争い
13 墓からわかること
14 弥生文化の世界観を探る
15 弥生文化をとりまく世界
16 石製利器から鉄製利器へ
17 祭祀の変質
18 墳丘墓の展開
19 記録された弥生文化
20 前方後円墳の成立
21 超大型集落の終焉と弥生社会の特質
本書で紹介した遺跡
【2023年8月3日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
趣旨説明 |
【2023年8月3日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
講 演 シンポジウム 後期の中の変革―536年イベントにみる気候変動との |
【2023年8月3日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 はじめに………………………………………………………………1 |
【2023年7月21日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【目次】 Foreword |
【2023年7月21日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
郵政考古学会では、大阪府茨木市に所在する東奈良遺跡の発掘調査に ・真に依って生きた!か?なぁ… 藤澤 典彦 (1) |
【2023年7月19日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
《原文紹介はこちらをクリックしてご覧いただけます(PDF)》 目次 |
【2023年7月19日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
《原文紹介はこちらをクリックしてご覧いただけます(PDF)》 口頭発表 鈴木舞/三船温尚 川辺敬子/オレガリレオ・マルティン・サンチェス 南健太郎 吉田広 清水克朗/清水康二/宇野隆志 鈴木舞/飯塚義之 北風嵐/小松隆= 邵艶兵/楊軍昌/譚[目分][目分]/蒋鳳瑞/史永 王漢卿 松本隆/宮崎甲/三枝一将 [Web発表] 万俐/馬新民/鄭東平 李倩倩/韓超/万俐 |
【2023年7月3日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 発表1 兵庫県「新温泉町初瀬谷・柏谷古墳群の調査」 ……………
3 |
【2023年7月1日】 【品切】
|
|
目 次 |
【2023年6月30日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【目次】 森川 実:東大寺写経所の瓮・堝と春の茹菜 |
【2023年6月27日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容紹介】 隋煬帝が建設した洛陽城は何故宋代まで長期間の使用に耐えうる 【目次】 序章 隋唐洛陽城の都城史研究の動向と諸問題 ◎
第1部 隋唐洛陽城をとりまく水環境◎ |
【2023年6月20日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【目次】 【論文】 平尾稲荷山古墳出土埴輪と(伝)平尾稲荷山古墳出上三角縁神獣鏡 【埴輪検討会シンポジウム2022「埴輸の分類と編年」概要と講評】 |
【2023年6月19日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 〔論文〕 加熱処理を伴う石器製作とその前後の進行過程 |
【2023年6月13日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 西宮市甲山の黒色ガラス質安山岩と甲山山頂遺跡の |
【2023年6月13日】【再入荷】【ご注文承り中】
|
|
─────────────────────────── |
【2023年6月6日】 【ご注文承り中】
|
|
【内容紹介】 「魏志」倭人伝や「後漢書」東夷伝は、倭をどのようにみていたのか。 【目次】 第1章 本居宣長と偽僭説 |
【2023年6月6日】 【ご注文承り中】
|
|
【内容紹介】 『魏志』倭人伝が描いた社会は、 【目次】 第一章 卑弥呼の性格 |
【2023年6月6日】 【ご注文承り中】
|
|
【内容紹介】 『魏志』倭人伝の方位と距離の記述は誤りではなかった! 第一章 考古学からみた邪馬台国研究の歴史 |
【2023年6月3日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【目次】 シンポジウム特集「新しい歴史教育と地域」 |
【2023年6月3日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 |
【2023年6月3日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 |
【2023年5月25日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容紹介】 陶磁器考古学の泰斗・大橋康二先生の喜寿を記念して、先生 ◎目 次◎ 実事求是―大橋先生の研究― ………………金沢 陽……… ⅰ 第Ⅲ章 日本陶磁 Ⅲ-1 西播磨の陶磁器窯の技術について……赤松和佳…… 171 Ⅳ-1 江戸遺跡出土広東碗の編年と消費動向 第Ⅴ章 陶磁貿易 Ⅴ-1 ウィーン・ロースドルフ城所蔵の陶磁器 第Ⅵ章 海外陶磁 Ⅵ-1 ドイモイ政策後のベトナム陶磁研究の進展 執筆者紹介 ……………………………………………………… 441 |
【2023年5月25日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【目次】 Ⅱ 縄文/弥生時代 Ⅲ 弥生時代 Ⅳ 古墳時代 Ⅴ 古代 |
【2023年5月25日】 【近日入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容紹介】 考古学研究は資料を見ること[認知]、資料についての情報を 【目次】 はじめに 第1章 考古学の基礎的作業 第2章 自然科学について 第3章 何をよりどころに論じてきたのか 第4章 意味論へ 第5章 幻の力 第6章 歴史の復元 おわりに/後記 |
【2023年5月24日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【目次】 【論文】 平尾稲荷山古墳出土埴輪と(伝)平尾稲荷山古墳出上三角縁神獣鏡 【埴輪検討会シンポジウム2022「埴輸の分類と編年」概要と講評】 |
【2023年5月19日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【目次】 |
【2023年5月19日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 古墳時代的須恵器文様の終焉 ………………………………………………………………………… |
【2023年5月11日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
国宝銅鐸出土の加茂岩倉遺跡や、山陰地方独特の弥生墳丘墓として 〔目次〕 第2章 古代出雲に向き合う 第3章 開眼する古代出雲 第4章 石見の遺跡と地域史探訪 第5章 地域の明日を見つめる |
【2023年5月11日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
──────────────────────────────── かつて日本列島の王都であり仏教信仰の中心地でもあった「飛鳥」地方 第1部 飛鳥中心の寺々 |
【2023年5月11日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
|
【2023年4月27日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介文】(HPより) |
【2023年4月18日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容簡介】 古代国家形成期に水陸の複合的交通網が構築される様相を 【目次】 第Ⅰ部 国家形成期研究への考古学的視角 第Ⅱ部 地域社会の構造 第Ⅲ部 水上交通志向の社会における首長権―弥生時代末 第Ⅳ部 列島規模に及ぶ交通システム成立と組織化の過程 終章 本書のまとめと展望 |
【2023年4月7日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介文】 大阪南部、和泉地域に営まれた弥生の巨大環濠集落・池上曽根 【目次】 第1章 弥生文化の発信地 第2章 開発と保存のせめぎ合い 第3章 目ざめた巨大環濠集落 第4章 弥生実年代のゆくえ 第5章 弥生都市論のゆくえ |
【2023年4月7日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介文】 古墳時代から平安時代にかけて、大阪南部に営まれた列島 【目次】 第1章 古墳研究の現場にて 第2章 陶邑遺跡群の発掘 第3章 陶邑遺跡群の構成 第4章 文献史料にみる陶邑 第5章 型式編年の手法と陶邑編年 |
【2023年4月7日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介文】 土器を赤く塗り、棺に朱を敷きつめ、魏志倭人伝に「朱丹を以て 【目次】 第1章 弥生人が求めた朱 第2章 辰砂採掘遺跡の探究 第3章 採掘の実態解明へ 第4章 朱の生産にせまる 第5章 若杉山辰砂採掘遺跡のこれから 参考文献 |
【2023年3月23日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容簡介】 序 章 古墳時代における馬具の受容と展開の解明をめざして 第Ⅰ章 馬具研究の現状と課題 第Ⅱ章 日本列島における馬具と騎馬文化の受容 第Ⅲ章 金銅装馬具の国産過程とその歴史的背景 第1節 筑紫の君の誕生と磐井の上番 第Ⅳ章 日本列島騎馬文化受容と馬具国産化の歴史的意義 |
【2023年3月23日】 【近日入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容簡介】 後期旧石器時代の北関東における狩猟採集民の動態を、石器 【目次】 第2章 分析方法 第3章 関東平野北西部の地理的環境について 第4章 関東平野北西部の地形発達史と古環境変遷 第5章 石器群の編年観 第6章 関東平野北西部における後期旧石器集団の居住形態の 第7章 旧石器時代の環境適応史の復原に向けて 資料編 関東平野北西部の石器群 |
【2023年3月22日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 ≪研究メモ≫ ≪書 評≫ ≪シリーズ遺跡紹介15≫ ≪古代学への提言 88≫ |
【2023年3月22日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 《研究ノート》 ≪シリーズ遺跡紹介14≫ ≪活動報告≫ ≪古代学への提言 87≫ |
【2023年3月16日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
◆ご案内◆ |
【2023年3月13日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 巻頭言 中村慎一 ⅰ |
【2023年3月13日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 第Ⅱ部 古墳壁画や戸籍・考古資料等から描く古代 多摩丘陵産のプランド・黒川炭を焼く 第Ⅳ部 託すょ夢―神奈川県考古学会と発掘調査
|
【2023年3月13日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 はじめに ………………………………………… ⅰ 第1章 発掘された日本の近現代生活 |
【2023年3月12日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
◆概 要◆ 【特集論文】 築城期における仙台城跡の様相 【報告】 織豊期城郭研究会 2019年度彦根研究集会の報告(木村 聡) 【特別論文】 【研究ノート】 【資料紹介】 【発掘情報】 【情報】 |
【2023年3月9日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容簡介】 『福岡大学考古学論集3』―邦訳編―は、2020年3月に 細形銅剣の機能と使用方法 趙 鎮先 2 |
【2023年3月9日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
◆概 要◆
【目 次】 まえがき ……………………………………………………… ⅰ |
【2023年3月9日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介文より】 第2章 中国大陸における初期鉄器文化 …………… 27 第4章 東周代燕国の東方進出 ……………………… 53 第5章 伝小郡出土東周式銅戈からみた東北アジアの 第6章 中国東北・朝鮮半島の甕棺墓 ……………… 91 第7章 彩画鏡の変遷 ……………………………… 107 第8章 夫余と沃沮の初期鉄器文化 ……………… 129 第9章 楽浪系土器の変遷 ………………………… 155 第10章 遼東・山東系土器と楽浪系土器と北部九州 第11章 ベトナム漢墓からみた士燮政権 ………… 203 第12章 朝鮮半島における初期鉄器時代の始まりと展開 第13章 北部九州の弥生時代の鍛冶遺構 ………… 251 第14章 弥生時代の鍛冶と交易 …………………… 273 終章 東アジアの初期鉄器時代の始原と展開 …… 295 参考文献 …………………………………………………315 |
【2023年2月22日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
製鉄遺跡の発掘調査成果を元に、箱形炉と竪形炉の 【目次】 第1章 鉄の基本事項 第2章 東北地方南部の古代製鉄炉とその特徴 第3章 古代製鉄炉の生成鉄と復元操業 第4章 復元した箱形炉と竪形炉の実験 第5章 実験操業から見える古代製鉄技術 巻末表 実験にかかわる操業メモ・一覧および木炭・ |
【2023年2月22日】 【【品切】
|
|
◆目 次◆ |
【2023年2月22日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【展覧会紹介文より抜粋】 もくじ Ⅲ 島原・天草一揆 受難へ 論 考 |
【2023年2月9日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容簡介】 |
【2023年2月6日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容紹介】 いま、いちばん新しい動物の家畜化と共生の歴史 【目次】 本書で取り上げる主な遺跡 ⅳ 序章 家畜研究と人類史……………………………丸山真史 1 |
【2023年2月6日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容簡介】 【目次】 第Ⅰ編 灰塚山古墳発掘調査報告……………………… 1 第Ⅱ編 灰塚山古墳論考編……………………………… 109 第Ⅲ編 第2主体部出土人骨…………………………… 197 |
【2023年2月6日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容簡介】 【目次】 序 第Ⅱ部 渤海使船の来航 第Ⅲ部 古代能登と境界世界 |
【2023年2月3日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
◆概 要◆ ★【目次】★ 第1章 朝鮮考古学史 |
【2023年2月2日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介文】 全国で約600基発見されている装飾古墳のなかで、図文の複雑 【目次】 第2章 王塚古墳の構造 第3章 装飾古墳の世界 第4章 王塚の壁画を読む 第5章 王塚の壁画を生み出したもの 第6章 壁画保存への苦難の歩み |
【2023年2月2日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介文】 【目次】 第2章 中世の町を掘る 第3章 人びとの暮らし 第4章 内陸と瀬戸内をつなぐ町 第5章 よみがえる「草戸千軒」 |
【2023年2月2日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 |
【2023年2月2日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
第二部 渡来人 |
【2023年2月2日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 |
【2023年2月2日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 |
【2023年2月2日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 |
【2023年2月2日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介文】 福島県郡山盆地の南端、阿武隈川東岸の丘陵に築造された 【目次】 第1章 真っ赤に塗られた石棺 第2章 多彩な正直古墳群 第3章 正直古墳群と同時代の遺跡 第4章 大安場一号墳と建鉾山祭祀遺跡 第5章 正直古墳群の意義 |
【2023年2月2日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容紹介】 |
【2023年2月2日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
『郵政考古紀要第 77 号 ―山本忠尚先生追悼論攷―』 |
【2023年1月18日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
◆目 次◆ |
【2023年1月18日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
………………目 次………………………… 【特集 紀伊の戦前・戦後の考古学】 |
【2023年1月18日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 誌上報告 |
【2023年1月18日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
はじめに ………………………………………………………… 1 1 大和郡山城天守台付近の石材 …………………………… 2 |
【2023年1月13日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目次 |
【2023年1月13日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【目次】 |
【2023年1月5日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容説明】 弥生時代中期の南関東地方に、中里遺跡をはじめとする 【目 次】(章立) 序論 関東地方の水稲農耕と交易……………………… 1 |
【2023年1月5日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 特集 復元という遺産 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |
【2022年12月22日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介文】 東北新幹線や宇都宮・高崎線など北へむかう線路が集中 【目次】 第1章 姿をあらわした巨大貝塚 第2章 かきがらやまの記憶 第3章 縄文時代の東京低地 第4章 巨大貝塚を解明する 第5章 縄文時代の水産加工場 第6章 内陸に運ばれた干し貝 |
【2022年12月22日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 Ⅰ 報告 …………………………………………………
9 |
【2022年12月19日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【目 次】 巻頭言 |
【2022年12月19日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【ご紹介】 |
【2022年12月19日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【例言・凡例(抜粋)】 一 本書は令和四年十月一日(土)から十一月二十七日(日) 目 次 |
【2022年12月19日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
◆目 次◆ 田中史生 「文献からみた武器・武具生産組織と渡来系 中村大介 「青銅短剣を持つ人々 鈴木崇司 「外来系武器から見る弥生社会の様相」 内山敏行 「古墳時代の外来系武具と倭系武具」 金 宇大 「装飾付大刀生産の拡大と外来技術工人」 津野 仁 「日本古代の武器比較試行」 |
【2022年12月19日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 『古代武器研究』V01.17の刊行にあたって 古墳時代の軍事と外交 |
【2022年12月19日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
◆概 要◆ ●目次(凡例や参考文献等を除く) |
【2022年12月19日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 |
【2022年12月5日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
◆目 次◆ |
【2022年11月30日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介】 中華帝国の中核都市と周縁都市双方の実態を最新の考古学 【目次】 第一部 中核都市の空間構造 |
【2022年11月30日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介文】 序 章 本書の目的と内容 |
【2022年11月29日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
◆【紹介文】◆ 【目次】 序 章 モンゴル考古学へのいざない 第1章 人類拡散の回廊 第2章 牧畜と騎乗のはじまり 第3章 最初の統一王朝 第4章 トルコ系民族の興亡 第5章 モンゴル民族の勃興 終 章 モンゴル考古学のあゆみ |
【2022年11月28日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
◆目次◆ 九州考古学会創立90周年記念事業の記録 |
【2022年11月18日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【目次】 コロナ禍における考古学教育と博物館 |
【2022年11月28日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 図版1~9 基調講演 地域別報告 紙上報告 |
【2022年11月11日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介文】 北海道南西部、アイヌ語で「美しい」の意味をあらわす 【目次】 第1章 「ピリカ」のドラマ |
【2022年11月7日】 【品切】【ご注文承り中】
|
|
<基調講演> |
…………………………………………………………………………………………………………
【2022年11月7日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 古墳出現期の伊勢湾西岸地域における鍛冶技術の変遷と |
…………………………………………………………………………………………………………
【2022年11月4日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介】 考古学者が実証的、理論的に解き明かす日本における階級社 【目 次】 第1部 国家形成の理論的検討 第2部 弥生時代社会の位置 第3部 古墳時代から古代へ 第4部 東アジアにおける国家形成の比較研究 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2022年10月25日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
例 言 ……………………………………………………………… |
…………………………………………………………………………………………………………
【2022年10月25日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
≪開催趣旨≫ この大和川が、大阪平野に流れ始める石川との合流地点 今回の展示では、船橋・国府遺跡を中心に、これまでの |
【2022年10月19日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介文】 【目次】 |
【2022年10月19日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介】 埋葬施設と儀礼の分析から複眼的な古墳時代像を復元 序章 本書の目的と課題 第1章 古墳時代竪穴系埋葬施設研究の現状 第2章 立面形態から見た畿内竪穴式石室の地域性 第3章 前期首長墓の系列展開と埋葬施設構造の変遷 第4章 摂津前期古墳の葺石と内部構造 第5章 竪穴式石室の広域普及と地域性 第6章 畿内における粘土槨の展開過程とその画期 第7章 粘土槨の広域展開とその背景 第8章 竪穴系埋葬施設から見たヤマト政権の対地域 第9章 「棺制」の変遷と葬制の変革 第10章 古墳時代の葬制秩序と政治権力 終章 総括と展望 おわりに/引用・参考文献/棺槨論争主要関係論文一覧 |
【2022年10月6日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容簡介】 |
【2022年10月6日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容簡介】 |
【2022年10月6日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介】 |
【2022年10月6日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【目次】 |
【2022年10月6日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
◆概 要◆
第1章 古墳を飾る 第2章 戦う、装う 第3章 祈りと供宴 |
【2022年10月6日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【目次】 ・巻頭言 |
【2022年9月22日】 【品切れ】
|
|
【趣 旨】 【報 告】 |
【2022年9月22日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介文】 当館には国内では希少な中国玉器コレクションが所蔵され |
【2022年9月22日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介文】 緒 言 第1部 地域論 |
【2022年9月22日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介文】 【目次】 第1章 総国から上総国へ 第2章 天平の国家構想 国分寺建立 第3章 上総国分僧寺の造営 第4章 上総国分尼寺の全貌 第5章 国分寺研究の最前線 |
【2022年9月20日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【報告】 博多遺跡群第221次調査出土の貿易陶磁器について 【翻訳】 新安沈船引揚げ陶磁器に見る元朝と鎌倉時代の喫茶文化の |
【2022年9月20日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目次 ◇特集「美と祈りの誕生 古代日本と東アジアの玉」 |
【2022年9月2日】 【品切】
|
|
【内容簡介】 |
【2022年8月22日】 【品切】
|
|
目 次 |
【2022年8月18日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【目 次】 |
【2022年8月12日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介文】 日本の鉄は、明治時代初期まで九割以上が中国地方で生産
第1章 金属学者たたらを歩く 第2章 砂鉄の採取──砥波上鉄穴 第3章 中国山地のたたら──都合山鈩・砥波鈩 第4章 山陰沿岸部のたたら──価谷鈩 第5章 たたらの実像 第6章 たたらを活かした地域づくり |
【2022年8月10日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
『古代九州と東アジア・拾遺篇』 |
【2022年8月10日】 【残部少】【ご注文承り中】
|
|
目 次 |
【2022年8月4日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容簡介】 第1章 古代官道の路線復元の視点と方法 |
【2022年8月3日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容紹介】 |
【2022年8月3日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容紹介】 |
【2022年8月3日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容簡介】 …………………………………………………………………………… |
【2022年8月3日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 |
【2022年8月2日】 【再入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介】 序章 本書の目的と研究方法/倭人の習俗・社会に対する同時代 |
【2022年7月28日】 【品切れ】
|
|
例 言(抜粋) |
【2022年7月28日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 |
【2022年7月28日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 |
【2022年7月28日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容簡介】 〈目次〉 序 章 藤原京研究の概要と研究目的 第2章 藤原京成立前史 第3章 藤原京の京域 第4章 藤原京の造営に要した造成土量 第5章 藤原京の建物建築に要した土木量 第6章 藤原京における宅地班給とその実態 第7章 藤原京の景観―出土遺構を中心に― 第8章 藤原京の宅地建物遺構 第9章 藤原京の役所 終 章 藤原京の成立にみる歴史的意義 |
【2022年7月9日】 【品切れ】
|
|
目 次 |
【2022年7月5日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 |
【2022年7月5日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【目次】 中川 渉 永惠裕和 森永速男・山本 誠 |
【2022年7月1日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
《文字化けのため原文目次は以下のURLからご覧ください(PDF)》 目 次 山口県美祢市秋吉台周辺の古代銅製錬跡出土の 復元鋳造した三角縁神獣鏡の成分解析 1 千年紀の長城地帯における青銅装飾品の製作技法
|
【2022年7月1日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【目次】 |
【2022年7月1日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
はじめに ──────────────────── ⅰ |
【2022年6月24日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容簡介】 序 章 日中都城の比較にあたって 第一章 中国都城の変遷 第二章 中国都城と儒教 第三章 前期難波宮と中国宮城 第四章 難波宮と朱雀大路 第五章 藤原京と中国都城 補 論 新羅慶州との比較 第六章 奈良時代の都城と中国都城 第七章 複都制と中国都城 終 章 古代都城の行方 |
【2022年6月21日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介文】 【目次】 新しい信仰 飛鳥の寺院 王たちの奥津城 斑鳩 上宮王家の奥津城 大王家の系譜 |
【2022年6月21日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容紹介】 |
【2022年6月17日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【目次】 |
【2022年6月8日】 【近日入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介文】 【目次】 第2章 北陸の方形の系譜 第3章 倭王権との結びつき 第4章 築造のピークと終焉 第5章 能美古墳群の造営集団 第6章 現代に生きる能美古墳群 |
【2022年6月8日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容】 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2022年6月8日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容簡介】 序 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2022年6月8日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容簡介】 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2022年5月27日】 【品切れ】
|
|
本書は、堺市博物館の特別展「海を越えたつながりー倭の五王と |
…………………………………………………………………………………………………………
【2022年5月21日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容簡介】 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2022年5月15日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容簡介】 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2022年4月15日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
参加開始 ≪紙上発表≫ 新潟県新発田城跡から出土した鍋島焼 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2022年4月11日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2022年4月11日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 第2章 調査の経緯と経過 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2022年4月11日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2022年4月4日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
《文字化けのため原文目次は以下のURLからご覧ください(PDF)》 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2022年4月4日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
鈴木 崇司:鉄剣生産からみる東日本弥生社会 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2022年3月31日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【論 文】 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2022年3月30日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
埋蔵文化財の保護と考古学研究の発展のために |
…………………………………………………………………………………………………………
【2022年3月19日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介文】 【目次】 第2章 壁画発見の余波 第3章 壁画の保存をめぐって 第4章 近年の調査成果が語る新事実 第5章 未来に伝える 参考文献 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2022年3月18日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2022年3月18日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2022年3月17日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
ごあいさつ(抜粋) 【目次】 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2022年3月17日】 【20220324入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容紹介] アジアで求められる博物館の専門人材とは? 【目次】 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2022年3月17日】 【20220324入荷】【ご注文承り中】
|
|
【目次】 第Ⅱ部 関連科学と考古学 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2022年3月6日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目次 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2022年3月6日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介文】 発見時の鮮やかだった高松塚壁画群が、国宝となり文化庁が 【目次】 プロローグ 消える白虎 ――隠された事実 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2022年3月6日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介文】 縄文集落の本当の姿は? 北に八ヶ岳、南に富士山、西に 【目次】 第1章 縄文集落がみつかった |
…………………………………………………………………………………………………………
【2022年3月3日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 高霊三国時代の土器窯について-松林里遺跡を中心に- |
…………………………………………………………………………………………………………
【2022年2月17日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
巻頭言 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2022年2月16日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介文】 ●先1期の装飾古墳 ●第1期の装飾古墳 ●第2期の装飾古墳 ●第3期の装飾古墳 まとめに代えて |
…………………………………………………………………………………………………………
【2022年2月15日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
特集 遺跡のなかの民俗学 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2022年2月11日】 【品切】【ご注文承り中】
|
|
<刊行会では販売してますのでご注文は下記のアドレスへ |
…………………………………………………………………………………………………………
【2022年1月23日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容紹介】 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2022年1月20日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【目次】 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2022年1月20日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
2021年 関西近世考古学研究会 第31回大会 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2022年1月17日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
論文
|
…………………………………………………………………………………………………………
【2022年1月17日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
本巻は、福岡市東部地域(中央区・博多区・東区・南区)に 第Ⅳ部 主要遺跡解説 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年12月28日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年12月24日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
長年にわたって文化庁で国の文化行政を担い、都道府県・ 【目次】 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年12月21日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
本書は、2018年12月15日に大阪市立自然史博物館において開催さ
目 次 第I部 拡大例会シンポジウム記録集 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年12月21日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年12月21日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【事例報告】京都市御土居跡出土の慶長丁銀極印鑽 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年12月21日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年12月15日】 【近日入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介文】 世界各地に存在する王墓と装飾墓を俯瞰的に比較し、 【目次】 第Ⅰ部 世界篇 第Ⅱ部 日本篇 第Ⅲ部 装飾墓篇 装飾古墳正射投影画像 装飾古墳データベース |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年12月15日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
今回は「古代集落を考える」と題するシリーズを立ち上げ、 【目次】 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年12月15日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
本文目次 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年12月15日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年12月10日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介文] 【目次] 第2章 最大の激戦地、田原坂 第3章 田原坂を掘る 第4章 地形で勝ち、地形に負ける 第5章 そして、音は消えた |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年12月10日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年12月8日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【目 次】 第一部 美術と技術の歴史 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年12月7日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
──────────────────────────── |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年12月7日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
押型文土器のいわゆる枝回転文について |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年12月3日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年11月13日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹 介】 【主な掲載資料】 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年11月13日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
掲げつづける文化の灯火/福岡県知事 服部 誠太郎 【特集】港市二〇〇〇年 博多・福岡 ○博多湾を守る自然のゆりかご~地勢の恵み~/磯 望 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年11月13日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介文】 【目次】 はじめに 第1章 縄文時代研究事始め 第1問 縄文時代研究はいつ始まったか 第2章 縄文時代の研究と論争をみる 第5問 貝塚の巨人伝説とは何か 第3章 縄文時代の関連学問をみる 第26問 民族考古学とは何か 第4章 縄文人の道具をのぞく 第38問 縄文土器は何に使われたか 第5章 縄文人の生業と技術を探る 第63問 縄文人の主食は何か 第6章 縄文人の生活と社会を考える 第87問 縄文人はどのような住居に住んでいたのか 第7章 縄文時代の争点を考える 第98問 縄文時代はいつから始まるか おわりに |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年11月13日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介文】 【目次】 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年11月13日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
令和三年度の伊都国歴史博物館秋季特別展は、伊都国から倭人伝 主な展示品 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年11月13日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容簡介】 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年11月13日】 【在庫切】【ご注文承り中】
|
|
特集1:「島津家墓所について」 特集2:「鹿児島県考古学会70年の歩み」 論文・研究ノート 書評 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年11月13日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
例 言 本資料は、鋳造遺跡研究会の2021年10月17日に開催された |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年11月13日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年11月13日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
**************目 次******************** 【特集 躍動する熊野の武士団―その本拠と特質を探る―】 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年10月5日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【投稿論文】 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年10月5日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
≪開催趣旨≫ |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年10月5日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
トンネルの歴史や掘削の方法、本展で取り上げたトンネルの 【目次】
|
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年10月1日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【目次】 〈特輯 常陸の古墳文化 補遺〉 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年9月29日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【刊行元内容簡介】 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年9月8日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
<残部僅少> <目次> 第Ⅰ章 調査の経過 …………(泉森) |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年8月23日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【目次】 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年8月10日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
《原文目次は以下のURLからご覧いただけます(PDF)》 製作技術 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年8月10日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
《原文目次は以下のURLからご覧いただけます(PDF)》 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年8月7日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目次・内容 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年8月2日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
目次 1 江戸時代後期に鋳造された青銅貨および鉄貨の母銭が
果たす役割の金属学的検討 :桐野文良、大野直志、田口智子、小椋聡子 15 ポリゴンデータ検証による泉屋博古館所蔵の四鳳文鏡の 29 京都大学人文科学研究所蔵青銅如来立像のポリゴンデータ 43 甘粛礼県出土青銅器的内部結構観察及其型芯定位技術 51 紅銅紋飾青銅器鋳?法与嵌?法工芸解析 57 ウラル地域・カザフスタンの青銅器時代冶金関連土器の 65 アジア鋳造技術史学会 第9回 表彰審査結果 :外山潔、高濱秀、大橋修、阿部裕之
|
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年8月2日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介文】 【目次】 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年8月2日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介文】 【目次】 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年8月2日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介文】 【目次】 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年7月21日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【刊行元説明より】 |
…………………………………………………………………………………………………………
【2021年7月21日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容簡介】 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2021年7月9日】 【2021.7.8入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 韓日交渉の考古学―古墳時代―刊行辞 第1部 総 説 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2021年7月6日】 【2021.7.6入荷】【ご注文承り中】
|
|
【目次】 高橋 克壽:ウワナベ古墳調査「限定公開」参加記 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2021年7月4日】 【2021.7.4入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介】 弥生土器をはじめ考古資料の実証的な解析を経て、経済・儀礼 【目次】 第2章 近畿地方弥生土器の変化と年代 第3章 近畿地方弥生土器の地域的様式差の形成 第4章 地域的様式差の展開と構造 第5章 弥生時代の生産/消費システム 第6章 集落からみた弥生地域社会 第7章 唐古・鍵遺跡の環濠と構造 第8章 弥生地域社会総論 第9章 集落と墳墓からみた古墳時代への社会変化 結 語 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2021年7月4日】 【2021.7.4入荷】【ご注文承り中】
|
|
【簡介】
|
……………………………………………………………………………………………………………
【2021年7月2日】 【2021.7.1入荷】【入荷が遅れて申し訳ありません】
|
|
【目次】 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2021年7月2日】 【2021.7.1入荷】【入荷が遅れて申し訳ありません】
|
|
【目 次】 区域互動與本土化:中国早期冶金新観察 第二部分:古代青銅器的鋳造與生産 安陽商代晩期鋳銅遺址的考古新発現及学術意義 第三部分:金属工芸研究 中国古代鋼鉄技術研究的現状與挑戦―陳建立
p.35 内蒙古涼城地域における中国北方青銅器文化金属器の |
……………………………………………………………………………………………………………
【2021年6月30日】 【2021.7.4入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介文】 【目次】 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2021年6月30日】 【2021.7.2入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹 介】 1987年に岐阜県大垣市教育委員会の文化財担当者となられて 【内容目次】 |
……………………………………………………………………………………………………………【2021年6月25日】 【2021.6.24入荷】【ご注文承り中】
|
|
【目次】 東・東南アジアの時代区分論に二〇二〇年を 研究動向 「公儀」と藩をめぐる最近の研究動向について 業績目録】 業績目録(抜粋) 追悼文 少壮考古学徒の羅針盤 たかし よいち先生を偲ぶ 七隈史学会第22回大会研究発表要旨 ……………… 23 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2021年6月16日】 【2021.7.6入荷】【ご注文承り中】
|
|
【目次】 中井均先生 略歴・業績一覧 …………………………………………… 447 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2021年6月14日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【目次】 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2021年6月14日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【目 次】 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2021年6月14日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【目 次】 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2021年6月1日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容紹介】 古代学研究会2017年度拡大例会シンポジウムをもとにした成果報告書。 【目 次】 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2021年6月1日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容紹介】 城郭研究のパイオニアであり、分野を越えて歴史学全般にも 【目次】 ■第1章 権力の動向と城郭の展開 ■第2章 進む城郭の再評価 ■第3章 石垣・瓦・出土遺物 ■第4章 城郭史への研究視点 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2021年6月1日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【目 次】 はじめに-湖と古墳に学ぶ考古学- |
……………………………………………………………………………………………………………
【2021年5月19日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
<紹介> 今号は外部研究者1 名のほか、 顧問、常勤所員3名 <掲截論文> 前田時人 「朝鮮三国時代の会盟について」 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2021年5月19日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容説明】 ①馬文化の渡来に迫る ②日本全国を網羅 ③古墳時代中期から摂関期までの約700年間 ④古代社会を支えた馬の諸相 ⑤馬の一生 【目 次】 カラー口絵(8頁) Ⅰ部 総 論 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2021年5月7日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容簡介】 中近世和鏡の鏡背意匠はどのような精神観念を 【目次】 はじめに |
……………………………………………………………………………………………………………
【2021年5月7日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容簡介】 博物館学の泰斗であり、和鏡の研究でも知られる 【目次】 はじめに (井上洋一) 第1章 特別寄稿 第2章 現代の博物館の諸相 第3章 文化財の保護と活用 第4章 考古学・歴史学 あとがき (金山喜昭) |
……………………………………………………………………………………………………………
【2021年5月7日】 【入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介文】 世界遺産となった百舌鳥・古市古墳群はほとんどが「陵墓」で 【目次】 「陵墓限定公開」四〇周年を迎えて Ⅰ基調講演・報告 大仙古墳は允恭(倭王済)墓である 岸本直文 副葬品からみた大山古墳 世界の墳墓と世界遺産 中久保辰夫 調査手法の進展と「陵墓」情報の充実 新納 泉 近代天皇制と「陵墓」 高木博志 Ⅱ 討論 文化財としての「陵墓」と世界遺産 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2021年5月7日】 【2021.4.30入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容簡介】※本書”はじめに”より抜粋 ここに『山陰歴史考古学論攷』 として鳥取、島根 【目 次】 はじめに |
……………………………………………………………………………………………………………
【2021年4月24日】 【2021.4.22入荷】【ご注文承り中】
|
|
平成26年度に大量の副葬品が出土した島内139号墓で、 【章立目次】 第1章 整理調査経過・体制 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2021年4月24日】 【2021.4.22入荷】【ご注文承り中】
|
|
【作品概要】 【目次など】 第1部 埴輪からみた倭王権 第2章 埴輪生産の変遷――倭王権の関与 第3章 倭の五王の時代における円筒埴輪の規格 第2部 倭鏡からみた倭王権 第5章 前期倭鏡の変化と「政権交替」 第6章 中期倭鏡の研究――讃・珍・済・興の鏡 第7章 古墳時代後期の出土鏡と長期保有 第3部 その他の副葬品からみた倭王権 第9章 甲冑と革盾 第10章 鈴釧の研究 第4部 古墳出土品からみた倭王権と社会 第12章 古墳時代人の思想 第13章 古墳出土品からみた国家形成 あとがき |
……………………………………………………………………………………………………………
【2021年4月15日】 【2021.4.12入荷】【ご注文承り中】
|
|
【目次】 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2021年3月24日】 【2021.3.22入荷】【ご注文承り中】
|
|
【目次】 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2021年3月24日】 【ご注文承り中】
|
|
【内容紹介】 東南アジア考古学の泰斗、菊池誠一(昭和女子大学教授)、坂井隆 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2021年3月24日】 【ご注文承り中】
|
|
【紹介文] 鎌倉時代、九州北部に来襲した元の大軍は、 【目次] 第1章 蒙古襲来とは |
……………………………………………………………………………………………………………
【2021年3月24日】 【ご注文承り中】
|
|
【紹介文】 貿易都市博多周縁の久山町の山中から、貿易陶磁器の優品や 第1章 まぼろしの山林寺院 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2021年3月19日】 【ご注文承り中】
|
|
本書は桜井市内に存在する横穴式石室(一部、横穴式石槨を |
……………………………………………………………………………………………………………
【2021年3月13日】 【2021.3.12入荷】【ご注文承り中】
|
|
【目次】 ●上巻 ●下巻 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2021年3月13日】 【ご注文承り中】
|
|
【内容簡介】 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2021年3月13日】 【ご注文承り中】
|
|
【内容簡介】 <目次> |
……………………………………………………………………………………………………………
【2021年3月5日】 【2021.3.5入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 特集「動物・植物考古学 」刊行にあたって ……… (1)
|
……………………………………………………………………………………………………………
【2021年3月5日】 【2021.3.5入荷】【ご注文承り中】
|
|
【目 次】 縄文文化解体期をめぐる土器資科群の研究3 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2021年3月3日】 【2021.2.20入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2021年1月22日】 【2021.1.21入荷】【ご注文承り中】
|
|
【目次】 はじめに
池田保信・中久保辰夫 …… 1 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2021年1月18日】 【2021.1.18入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 録 シンポジウム 「古代中国の産業と考古学」趣旨説明 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2020年12月30日】 【2020.12.30入荷】【ご注文承り中】
|
|
埋蔵文化財の保護と考古学研究の発展のために |
……………………………………………………………………………………………………………
【2020年12月28日】 【2020.12.28入荷】【ご注文承り中】
|
|
──────────────────────────── 【論 文】8世紀末期における跳和同の鋳造動機について |
……………………………………………………………………………………………………………
【2020年12月28日】 【2020.12.28入荷】【品切れ】
|
|
目 次 夢村土城の最新發掘成果と高句麗土器についての若干の考察 回想文 資料調査や古代武器研究会のことなど………………阪口英毅 443 柳本照男さんのあゆみ 柳本照男さん履歴……………………………………………………457 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2020年12月26日】 【2020.12.19入荷】【ご注文承り中】
|
|
【目次】 巻頭言 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2020年12月26日】 【2020.12.19入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 陣屋の歴史的価値一大阪府下の事例を中心に一 福岡藩関連の陣屋・御殿 筑前国怡土郡西部の陣屋について |
……………………………………………………………………………………………………………
【2020年12月26日】 【2020.12.16入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 古墳時代中期編年の研究史と課題 〔資料集成〕 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2020年12月15日】 【2020.12.15入荷】【ご注文承り中】
|
|
第16回古代武器研究会「弥生時代後半期における金属製武器の 【論文】 弥弥生時代の九州地方における鉄製武器の普及 【総合討議】…………………………………………………… 135 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2020年12月7日】 【2020.12.7入荷】【残部僅少!】
|
|
※残部僅少のため、品切れに際はご容赦ください。 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2020年11月27日】 【2020.11.27入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 1.総説 和鏡鑑賞の手引き 川見典久 003 凡 例 ・本図録は第124回展観「和鏡賞鏡‐図像でたどる千歳のねがい‐」 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2020年11月24日】 【2020.11.27入荷】【ご注文承り中】
|
|
目次 〈新韓日考古学〉序 李 健茂 … 1 第2部 韓半島の青銅器文化の展開と弥生時代のはじまり 第3部 韓半島の鉄器時代・原三国時代と弥生時代の国の形成・ |
……………………………………………………………………………………………………………
【2020年11月22日】 【2020.11.18入荷】【ご注文承り中】
|
|
【目 次】 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2020年11月2日】 【2020.10.30入荷】【ご注文承り中】
|
|
世界史と中国史―グローバル・ヒストリーとアジア史と 【小特集「南北朝時代の九州―九州における観応の擾乱― |
……………………………………………………………………………………………………………【2020年11月2日】 【2020.10.25入荷】【ご注文承り中】
|
|
|
……………………………………………………………………………………………………………
【2020年10月20日】 【2020.10.21入荷】【ご注文承り中】
|
|
●令和2年度秋季特別展●(紹介) |
……………………………………………………………………………………………………………【2020年10月20日】 【2020.10.18入荷】【ご注文承り中】
|
|
【本文目次】 基調講演・研究報告「求菩提山の山岳信仰」 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2020年10月17日】 【2020.10.15入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 ・
松菊里文化の起源再考 …………安 在皓 (1〉 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2020年10月17日】 【2020.10.17入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介文】 古市・百舌鳥古墳群に巨大な前方後円墳がつくられた5世紀、 【目次】 第1章 黒姫山古墳とは 第2章 解明された黒姫山古墳 第3章 最多の古墳出土甲冑 第4章 埴輪列と埴輪 第5章 黒姫山古墳の被葬者像 第6章 黒姫山古墳周辺をめぐって |
……………………………………………………………………………………………………………
【2020年10月17日】 【2020.10.17入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介文】 岡山市の西、足守川流域から総社平野にかけては、古墳時代 【目次】 第1章 超巨大古墳がなぜ岡山に? 第2章 みえてきた陪塚のすがた 第3章 千足古墳の発掘 第4章 造山古墳の発掘 第5章 だれが埋葬されているのか? 第6章 吉備政権を支えた人びと |
……………………………………………………………………………………………………………
【2020年10月17日】 【2020.10.17入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介文】 世紀の新発見、太古の人びとの暮らしの解明……夢やロマンを 【目次】 01 考古学・考古学者とは |
……………………………………………………………………………………………………………
【2020年10月15日】 【2020.10.15入荷】【ご注文承り中】
|
|
----目 次----- 【特集 海辺における集落と墓制の実像】 和歌山県磯間岩陰遺跡にみる交流とその意義 【研 究】 【資料紹介】 【集成】 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2020年10月15日】 【2020.10.14入荷】【ご注文承り中】
|
|
目 次 鋳造遺跡研究と再現製作実験 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2020年10月15日】 【2020.10.14入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容紹介】 『魏志倭人伝』に記された倭の国々。朝鮮半島から海を越え對馬国、 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2020年10月7日】 【2020.10.11入荷】【ご注文承り中】
|
|
≪開催趣旨≫ |
……………………………………………………………………………………………………………
【2020年9月30日】 【2020.9.30入荷】【ご注文承り中】
|
|
【目次】 「南九州から奄美諸島の貿易陶磁」の開催について 【投稿論文】 束アフリカ・ザンジバルにおける海岸採集の東洋磁器 |
……………………………………………………………………………………………………………
【2020年9月27日】 【2020.9.27入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容紹介】 日本列島各地の有力首長墓から出土する三角縁神獣鏡を実証的 【目次】 序 章 三角縁神獣鏡研究の目的と課題 |
------------------------------------------------------------------------
【2020年9月19日】 【2020.9.19入荷】【ご注文承り中】
|
|
【紹介文】 本書は1972年からこれまで実施した5次にわたる釜塚古墳と |
------------------------------------------------------------------------
【2020年9月16日】 【2020.9.16入荷】【品切】
|
|
【研究報告刊行のお知らせ】 ― 目 次 ― 第1部 調査報告篇 第Ⅱ章 位置と環境 第Ⅲ章 石作窯の遺構と遺物 第Ⅳ章 小塩窯の遺構と遺物 第Ⅴ章 自然科学的分析 第Ⅵ章 考察 付表 第2部 研究報告篇 第Ⅰ章 緑釉陶器窯について
第Ⅰ章 古志部瓦窯の窯道具 第4部 研究の総括 研究の総括 |
------------------------------------------------------------------------
【2020年9月1日】 【2020.9.17入荷】【ご注文承り中】
|
|
【内容紹介】 農耕社会の中国中原地域のみならず、牧畜社会の長城地帯を
第Ⅰ部 北方青銅器文化 第1章 北方青銅器文化の変遷と展開 第Ⅱ部 中原青銅器文化 第7章 中原青銅器文化の始まり 第Ⅲ部 中国西南青銅器文化 第12章 川西高原の石棺墓の展開 第Ⅳ部 東北アジア青銅器文化 第15章 遼東の遼寧式銅剣 結語 ― 東アジア青銅器時代の始原と展開 |
------------------------------------------------------------------------
【2020年8月27日】 【2020.9.1入荷】
|
|
【内容紹介】 【目次】 |
------------------------------------------------------------------------
【2020年8月21日】 【2020.8.19入荷】
|
|
観光考古学とは、「遺跡を観光資源として捉え、活用の方策に 【目次】 巻頭言 観光考古学会の発足にあたって
坂詰秀一 3 |
------------------------------------------------------------------------
【2020年8月17日】 【2020.8.19入荷】
|
|
【紹介】 【目次】 【森古代学と終末期古墳】 【森古代学と「魏志倭人伝」】 【森古代学と生産】 【森古代学と地域】 【森古代学と文化史】 【森古代学と天皇陵古墳】 続きを読む |
------------------------------------------------------------------------
【2020年8月17日】 【2020.8.19入荷】
|
|
大きな窓のような目、長く突き出た口、踏んばった両脚に 【目次】 第1章 金生遺跡の発見 |
------------------------------------------------------------------------
【2020年8月6日】 【2020.8.6入荷】【品切】
|
|
目 次 遠部 慎 「特集にあたり」 |
------------------------------------------------------------------------
【2020年7月22日】 【2020.7.24入荷】
|
|
【内容簡介】 |
------------------------------------------------------------------------
【2020年7月9日】 【2020.7.9入荷】
|
|
序 【目次】 序 |
------------------------------------------------------------------------
【2020年7月8日】 【2020.7.12入荷】
|
|
目 次 |
------------------------------------------------------------------------
【2020年7月8日】 【2020.7.2入荷】
|
|
目 次 黒川古文化研究所の歩み 1990-2019 |
------------------------------------------------------------------------
【2020年7月3日】 【2020.7.1入荷】
|
|
目 次 論集刊行によせて……………………………………高橋克壽 |
------------------------------------------------------------------------
【2020年6月30日】 【2020.6.15入荷】
|
|
【目 次】 【基調講演】 【研究発表】 【誌上発表】 【各県の島々と縄文遺跡 資料集成】 【
「思うこと」人はなぜ島を目指すか 】 【各県の動向】 【研究会の記録】 |
------------------------------------------------------------------------
【2020年6月26日】 【近日入荷】
|
|
【内容紹介】 宗像沖ノ島砲台をはじめとする九州北部の砲台・防備衛所と 【目 次】 序文 |
------------------------------------------------------------------------
【2020年6月20日】 【2020.6.20入荷】
|
|
【紹介】 大阪府弥生文化博物館の副館長である著者が、博物館業務と 【目次】 はしがき ―個人的な備忘録をこえて |
------------------------------------------------------------------------
【2020年6月10日】 【2020.6.10入荷】
|
|
【目次】 松林山古墳の埴輪と副葬品と築造時期 |
------------------------------------------------------------------------
【2020年6月9日】 【2020.6.14入荷】
|
|
目 次 窯跡研究第4号の刊行にあたって 炭窯で綴る木炭史……………………………藤原 学〈3) 対談記録 |
------------------------------------------------------------------------
【2020年6月5日】 【2020.6.5入荷】
|
|
【目次】 序 |
------------------------------------------------------------------------
【2020年6月2日】 【2020.6.1入荷】
|
|
【内容紹介】 広域流通財としての玉類を精緻に分析し、その流通・消費 【目 次】 第Ⅰ章 研究史と問題の所在 第Ⅱ章 資料と方法 第Ⅲ章 各器種の流通動態 第Ⅳ章 セット構成からみた玉類の流通形態 第Ⅴ章 地域社会における玉類副葬 第Ⅵ章 玉類流通の具体像と古墳時代開始期の社会変革 終 章 玉からみた古墳時代の開始と社会変革 附 表 弥生時代後期~古墳時代前期の玉類副葬集成 |
------------------------------------------------------------------------
【2020年5月21日】 【2020.5.20入荷】
|
|
【目次】 |
------------------------------------------------------------------------
【2020年4月23日】 【2020.4.23入荷】
|
|
【目次】 長崎の寛文大火層出土陶磁を中心に ……………… 1 【西日本】 【東日本】 |
------------------------------------------------------------------------
【2020年4月22日】 【2020.6.3入荷】
|
|
【内容紹介】 日本列島における人類史の画期的なイベントである縄文時代 【目次】 の詳細な検討から論考する。 序章 |
------------------------------------------------------------------------
【2020年4月22日】 【2020.4.22入荷】
|
|
I. 貝を巡る考古学 島における獣形貝製品の研究 …………山野 ケン陽次郎 1 Ⅱ. 装身具の考古学 九州における縄文時代早期の石製装身具小論 Ⅲ. 南島の考古学 南島爪形文土器の研究 ………………………… 新垣 匠 97 Ⅳ. 中国の考古学 中国華北地域における細石刃石器群の出現と展開 木下尚子先生 略歴・業績目録 …………………………… 245 |
------------------------------------------------------------------------
【2020年4月20日】 【2020.4.18入荷】
|
|
【目次】 ご挨拶 ………………………………………1 |
------------------------------------------------------------------------
【2020年4月16日】 【2020.4.16入荷】
|
|
本書は、2019年5月25日~8月4日にかけて開催された |
------------------------------------------------------------------------
【2020年4月14日】 【2020.4.6入荷】
|
|
|
------------------------------------------------------------------------
【2020年3月19日】 【2020.4.2入荷】
|
|
中世遺跡から多量に出土する陶磁器をどのように見るか、 |
------------------------------------------------------------------------
【2020年3月3日】 【入荷】
|
|
九州から東アジアにかけて、豊富な現地調査と緻密な 第1部 原始~古代 第2部 対馬・壱岐の古墳と山城 第3部 宗像・沖ノ島古代祭祀遺跡 第4部 古代大宰府―大宰府都城の成立と関連社寺― 第5部 学会史・文化財調査史 第6部 研究余滴・追悼記 小田富士雄先生と韓国考古学(鄭澄元) 小田富士雄先生の考古学と私(亀田修一) |
------------------------------------------------------------------------
【2020年3月3日】 【入荷】
|
|
【内容簡介】 朝鮮半島から伝播した新来の文化である須恵器が、 【目 次】 |
------------------------------------------------------------------------
【2020年3月3日】 【入荷】
|
|
◎基調講演 ◎報 告 ◎シンボジウム |
------------------------------------------------------------------------
【2020年3月3日】 【入荷】
|
|
【内容紹介】 ヤマト王権はいかにして成立したか? 考古学の成果から、奈良の
序 章 ヤマト王権とは何か |
------------------------------------------------------------------------
【2020年3月3日】 【入荷】
|
|
【紹介文】 亡くなった人は海の彼方にある他界へと舟にのり旅立つ……。 【目次】 第1章 海からのまなざし |
------------------------------------------------------------------------
【2020年3月3日】 【入荷】
|
|
【紹介文】 映画『男はつらいよ』で有名な東京都葛飾区柴又で、まるで 【目次】 第1章 寅さんが出土した? |
------------------------------------------------------------------------
【2020年3月3日】 【入荷】
|
|
【内容紹介】 岩手県一戸町の台地にある御所野遺跡は、縄文時代中期後半に
●ムラをとりまく自然環境 ●ムラのくらし ●ムラの移り変わり ●祈りとまつり ●見えてきた縄文世界 |
------------------------------------------------------------------------
【2020年3月3日】 【入荷】
|
|
【内容簡介】 【目次】 第1章 装飾馬具生産と初期造仏活動の研究史 第2章 研究の視点 第3章 装飾馬具生産の開始と確立 第4章 装飾馬具生産の展開 第5章 装飾馬具生産の変質と初期造仏活動 終章 結論 参考文献・図出典/索 引 |
------------------------------------------------------------------------
【2020年3月3日】 【入荷】
|
|
馬考古学の研究成果を凝縮した決定版。 最初に日本列島にきた馬はどんな馬だったのか。 【目次】 第2章 東アジアの馬文化 第3章 畿内に定着した馬文化 第4章 開拓される東国の馬産地 第5章 遺跡から出土する馬とその足跡 第6章 馬をとりまく人々の動き |
------------------------------------------------------------------------
【2020年1月14日】 【入荷】
|
|
|
------------------------------------------------------------------------
【2020年1月14日】 【入荷】
|
|
目 次 口頭発表 ポスターセッション
|
------------------------------------------------------------------------
【2020年1月14日】 【入荷】
|
|
目 次 1.西北九州産黒曜石原産地研究の諸問題 〔研究発表要旨] 一本 尚之 「腰岳黒曜石原産地について」……………… 1 2.九州・沖縄各県の調査・研究動向(2019年1月~2019年10月) 3.九州旧石器文化の研究 芝 康次郎・片多 雅樹「腰岳山腹採集石器の黒曜石産地分析」 |
------------------------------------------------------------------------
【2019年12月19日】 【入荷】
|
|
【目次】 講演 誌上報告 特別寄稿 |
------------------------------------------------------------------------
【2019年12月19日】 【入荷】
|
|
目 次 中世土器・陶磁器研究の課題と新概説書の刊行にむけて 〈特集 中世土器・陶磁器研究の課題〉 平安京左京内膳町跡の土師器皿 ………………伊野 近富 5 〈投稿論文〉 |
------------------------------------------------------------------------
【2019年12月19日】 【入荷】
|
|
目 次 柱状高台土器の再検討―山陰地域の視点から― |
------------------------------------------------------------------------
【2019年12月16日】 【入荷】
|
|
今回の研究集会では官衙・集落から出土する遺物のうち大型甕 宮都における大甕………………………………………小田 裕樹 10 Ⅱ 討 議 |
------------------------------------------------------------------------
【2019年12月11日】 【入荷】
|
|
目 次 第15回「古代武器研究会」の開催にあたって 武器多量埋納古墳と政権 高橋 工 (一財)大阪市文化財協会 嶺南地域原三国期鉄剣・環頭刀の地城別展開過程 |
------------------------------------------------------------------------
【2019年12月11日】 【入荷】
|
|
弥生時代後半期における金属製武器の普及と防御施設 【特別講演】 【研究報告】 |
------------------------------------------------------------------------
【2019年12月11日】 【入荷】
|
|
論 説 一般発表 動 向 |
------------------------------------------------------------------------
【2019年12月11日】 【入荷】
|
|
【目次】 第2章 船原古墳とは 第3章 豪華な出土品 第4章 船原古墳の被葬者は 第5章 船原古墳のこれから |
------------------------------------------------------------------------
【2019年12月11日】 【入荷】
|
|
【目次】 第2章 布留のまつり 第3章 物部連氏の台頭 第4章 布留の生産体制 第5章 その後の物部連氏 |
------------------------------------------------------------------------
【2019年12月11日】 【入荷】
|
|
第2章 位置と環境 第3章 調査・研究のあゆみ 第4章 墳丘と埋葬施設 第5章 出土遺物の検討 第6章 考察 第7章 総括 ………………………………………… 134 |
------------------------------------------------------------------------
【2019年11月17日】 【入荷】
|
|
【目次】 巻頭言 |
------------------------------------------------------------------------
【2019年11月16日】 【入荷】
|
|
【目次】 第一章 論文集 一 古代城郭 怡土城に関する諸問題-怡土城に使用された瓦について- 在地を守る城郭と在地を攻める城郭 三 近世城郭 福岡藩内の石切場-福岡城を中心として-植田紘正 ……164 《特別寄稿》 福岡県の中近世城郭研究のあゆみ-私の城郭研究の取り組み- |
--------------------------------------------------------------------------
【2019年11月8日】 【入荷】
|
|
【内容簡介】 【目次】 序文 銅鏡研究と日本考古学 實盛良彦 Ⅰ 中国の鏡 後漢・三国鏡の生産動向 上野祥史 Ⅱ 倭でつくられた鏡 倭における鏡の製作 加藤一郎 Ⅲ 三角縁神獣鏡と関連の鏡 三角縁神獣鏡生産の展開と製作背景 岩本 崇 Ⅳ 銅鏡から歴史を読む 新見東呉尚方鏡試考 朱棒/藤井康隆(訳・解題) 跋文 銅鏡から読み解く二・三・四世紀の東アジア 實盛良彦 |
--------------------------------------------------------------------------
【2019年11月7日】 【入荷】
|
|
(内容) 『歴史・民族・考古学論攷』 第Ⅰ集 (郵政考古紀要第69号) 古稀を言祝ぐ 坂誥 秀一 『歴史・民族・考古学論攷』 第Ⅱ集 (郵政考古紀要第70号) 無形文化遺産としての造船技術 石村 智 『歴史・民族・考古学論攷』 第皿集 (郵政考古紀要第71号) サトイモと纏文文化 新津 健 |
--------------------------------------------------------------------------
【2019年11月6日】
|
|
北陸屈指の大集落、石川県小松市八日市地方遺跡は、弥生時代のイメージ
|
--------------------------------------------------------------------------
【2019年10月31日】 【品切れ】
|
|
目次 公開講演会 研究発表分科会Ⅰ 環境変化と生業からみた社会変動 研究発表分科会Ⅲ ジェンダー考古学の現在 |
--------------------------------------------------------------------------
【2019年10月23日】 【品切れ】
|
|
令和元年度秋季企画展「ヤマト王権とその拠点ー政治拠点と経済 【目次】 ごあいさつ |
--------------------------------------------------------------------------
【2019年10月16日】 【2019.10.23入荷】
|
|
【展覧会内容簡介】 玄界灘に浮かぶ壱岐島は、『魏志倭人伝』に記された「一支国」の 【図録目次】 はじめに……………………………………………………………… 4 |
--------------------------------------------------------------------------
【2019年10月16日】 【品切】
|
|
【内容簡介】 近年、磯間岩陰遺跡や西庄遺跡といった海辺の集落と墓制に 目 次 講演 誌上発表 |
--------------------------------------------------------------------------
【2019年10月16日】 【入荷】
|
|
【小特集 紀州の近世城郭】 和歌山城・田辺城・新宮城の特長と意義……水島 大二(1) |
--------------------------------------------------------------------------
【2019年10月1日】 【入荷】
|
|
https://www.chugoku-shoten.com/mokuji/jmokuji/78915/78915.pdf ご挨拶と開催趣旨 (武末純一) …………………………………………
4 |
--------------------------------------------------------------------------
【2019年9月21日】 【品切れ】
|
|
【目次】 小嶋 篤(九州国立博物館) 「祭式と考古学」 |
--------------------------------------------------------------------------
【2019年9月21日】 【入荷】
|
|
【内容紹介】 第一次世界大戦時のドイツ兵捕虜を収容した鳴門市の板東俘虜
第1章 一〇〇年前の慰霊碑…………………………………… 4 第2章 第一次世界大戦とドイツ兵捕虜……………………… 11 第3章 姿をあらわした収容所………………………………… 27 第4章 文化活動と地元住民との交流………………………… 65 第5章 よみがえる板東俘虜収容所…………………………… 83 参考文献 …………………………………………… 92 |
--------------------------------------------------------------------------
【2019年9月21日】 【入荷】
|
|
【内容紹介】 古墳時代後期、眼下に河内平野が広がる大阪府八尾市の高安山麓 【目次】 第1章 河内平野をのぞむ群集墳………………………………… 4 第2章 歴史のなかの高安千塚古墳群…………………………… 14 第3章 高安千塚古墳群を探る…………………………………… 37 第4章 古墳群に葬られた人びと………………………………… 68 第5章 「やまんねき」の自然のなかで………………………… 87 参考文献 ………………………………………………… 90 |
--------------------------------------------------------------------------
【2019年9月20日】 【入荷】
|
|
【目次】 |
--------------------------------------------------------------------------
【2019年9月17日】 【入荷】
|
|
・埋蔵文化財の保護と考古学研究の発展のために 特集◎愛媛の縄文・弥生時代の石器(前) |
--------------------------------------------------------------------------
【2019年8月11日】 【品切れ】
|
|
【目次】 こあいさつ 大阪府立弥生文化博物館 館長 禰宣田 佳男 2 |
--------------------------------------------------------------------------
【2019年8月11日】 【入荷】
|
|
「古代土師氏考」 舘野 和己
7 |
--------------------------------------------------------------------------
【2019年8月3日】 【品切れ】
|
|
大会開催趣旨 九州前方後円墳研究会では、昨年から「集落と古墳の動態」として、 目 次 西幸子・濱口真衣 井浦一・白木英敏 中島圭・甲斐郁・宮本博喜 宇野愼敏・山口裕平 渕ノ上隆介 林田和人 長直信 甲斐康大・近沢恒典 橋本達也 |
--------------------------------------------------------------------------
【2019年7月19日】 【品切れ】
|
|
目次 Ⅰ
発表要旨 ……………………………… 1 Ⅱ
飛鳥・藤原地域出土飛鳥時代土器実測図集成 ………………………181 |
--------------------------------------------------------------------------
【2019年5月31日】 【入荷】
|
|
|
--------------------------------------------------------------------------
【2019年5月31日】 【品切】
|
|
【目次】 |
--------------------------------------------------------------------------
【2017年10月16日】
|
|
福岡市西部地域(西区・早良区・城南区)の遺跡を網羅的に紹介 |
--------------------------------------------------------------------------
【2017年10月16日】 【品切】
|
|
【本書の概要】 本書は、2011年10月29・30日に福津市および宗像市で開催された 【目 次】 〇はじめに |
--------------------------------------------------------------------------
【2017年9月21日】 【入荷】
|
|
【目 次】 |
--------------------------------------------------------------------------
【2017年9月21日】 【品切】
|
|
【目 次】 報告1
|
--------------------------------------------------------------------------
【2017年6月23日】 【入荷】
|
|
目 次 |
--------------------------------------------------------------------------
【2017年6月23日】 【入荷】
|
|
【目次】 「丹後・岩滝法王寺古墳出土埴輪の再検討」 辻川哲朗
1 |
--------------------------------------------------------------------------
【2017年6月19日】 【入荷】
|
|
目 次 山口 健剛(山鹿市) 橋口 剛士(嘉島町) 今田 治代(氷川町) 神川めぐみ(宇城市) 田中
康雄(玉名市) 【資 料】 |
--------------------------------------------------------------------------
【2017年4月24日】 【入荷】
|
|
本書は千石唯司氏より平成26年・29年に兵庫県立考古博物館が寄贈、 【目次】 序 |
--------------------------------------------------------------------------
【2017年4月5日】 【入荷】
|
|
3世紀中頃から5世紀にかけての日本列島、とりわけ近畿地方を 【目次】 序 章 本書の目的と課題 |
--------------------------------------------------------------------------
【2017年4月5日】 【入荷】
|
|
【内容紹介】 日本城郭史の中世から近世への転換を決定付けた織豊系城郭は、 目 次 巻頭言………………………………………………
村田 修三 3 第1章 総 論 1 織豊系城郭とは何か ………………………… 髙田 徹
10 第2章 織豊権力の城郭政策 1 織田信長権力と城郭政策 第3章 織豊系城郭と地域社会 第4章 織豊系城郭における遺物と遺構 ◆遺構論 ◆遺物論 第5章 織豊系城郭の諸論点 第6章 個別城郭 |
--------------------------------------------------------------------------
【2017年4月5日】 【入荷】
|
|
4~6世紀の朝鮮諸国と倭の関係には謎が多い。両地域の古墳に副葬された 第Ⅰ部 垂飾付耳飾の型式学的検討 …………………………………… 13 |
--------------------------------------------------------------------------
【2016年10月21日】
|
|
三
角縁神獣鏡から倣製鏡まで、弥生・古墳時代の出土鏡を完全網羅。 【目次】 〇序 文 |
--------------------------------------------------------------------------
【2016年12月21日】
|
|
【内容・目次】
■目 次■ 序/目次/例言/開催趣旨/プログラム |
--------------------------------------------------------------------------
【2016年12月21日】
|
|
三角縁神獣鏡を含む青銅鏡1000面以上の三次元計測のデータベースを |
--------------------------------------------------------------------------
【2016年1月10日】
|
|
【目 次】 趙晟元 「4~5世紀代慶南地域出土軟質土器と土師器系土器」…… 9 重藤輝行 「4~5世紀の九州地域の土器と渡来人集落」 …………… 45 李暎澈 「榮山江流域と目本の4~5世紀日常土器・土師器・須恵器 -土師器と軟質日常土器情報交換段階-」 ………… 83 寺井誠 「4~5世紀の近畿地域を中心とした土器と渡来人集落」 ・ 103 朴升圭 「加耶と倭の4~6世紀陶質土器と須恵器」 ……………… 127 田中清美 「須恵器窯と生産集落」 ………………………………… 163 金才喆 「嶺南地方 4~6世紀土器生産工房の變遷」 ………… 187 土田純子 「交叉編年資料としての中國陶磁器」 …………………… 216 村上恭通 「日韓の鉄生産(製鉄)」 ………………………………… 243 金武重 「韓半島 中南部地域4~5世紀 鐵器生産 聚落」 …… 259 亀田修一 「4~5世紀日本列島の鉄器生産集落・韓半島との関わりを中心に」 …………………………………………………… 283 |
--------------------------------------------------------------------------
【2016年1月10日】
|
|
【目次】 【論文】 縄文土器の器形と文様の系譜について ―九州縄文時代早期後半期の壷形土器における可能性― 水ノ江和同 1 九州[王夬]状耳飾の研究 大坪 志子 21 福岡県津屋崎古墳群に用いられた玄武岩石材の供給地 井浦 一 石橋秀巳 森 康 41 宮崎県平野部における地下式横穴墓群の群構造と埋葬原理 ―六野原古墳群・地下式横穴墓群を対象として― 吉村 和昭 61 歴史的地名活用の有効性と問題点 ―唐房と「トウボウ」地名― 高倉 洋彰 89 研究ノート 韓国の土器工人集落(予察) 太田 智 109 報告 南さつま市干河原遺跡出土土器の圧痕調査報告 小畑 弘己・真邉 彩 125 責料紹介 甕棺内部に描かれた抽象絵画 ―小久保・勧貫遭跡出土大型塞棺について― 八木健一郎 133 長承2年書写『蘇悉地羯羅供養法』第一の奥書 ―福岡嫉久留米市田主丸町観音寺経塚関遵資料― 木下 浩良 141 書評 大坪志子著 『縄文玉文化研究―九州ブランドから縄文文化の多様性を探る一』 宮地聡一郎 147 追悼 田中良之さん 武末 純一 151 |
--------------------------------------------------------------------------
【2014年12月26日】
|
|
【目 次】 Ⅱ モノから見た中世の対馬 Ⅲ 中世史料と宗家文庫 |
--------------------------------------------------------------------------
【2014年12月4日】
|
|
【目 次】 口頭発表 吉野ヶ里遺跡出土の弥生時代石器について………………………渡部芳久 新幹線建設に伴う大村市竹松遺跡の調査……………田島陽子・川畑敏則 小児用甕棺にみられるススコゲ痕跡 ………………………………永島聡士 九州南部における甑形土器の受容過程 …………………………松崎大嗣 佐賀県伊万里市腰岳黒曜石原産地における黒曜石露頭および遺跡群の 発見とその意義 ……………… 芝康次郎・及川穣・稲田陽介・角縁進・船井向洋・一本尚之 熊本大学構内における縄文時代後期遺跡の発見とその意義 ………………………………………………… 山野ケン陽次郎・大坪志子 鹿児島県甑島手打貝塚の貝資源利用 …………………………………… 大西智和・別府佳祐・本田汀・野元勇介 重圏文鏡の生産と流通 ………………………………………………中井歩 本陣古墳の調査成果について~朝倉地域における首長系列の再検討~ ……………………………………………………………………… 中島圭 イモガイ装雲珠・辻金具を伴う馬装の性格 …………………………宮代栄一 ポスターセッション ----------------------------------------------------------------------------------- 地球科学的高精度分析に基づく今山系石斧の新たな原産地……田尻義了・ 足立達朗・渡部芳久・石田智子・中野伸彦・小山内康人・田中良之 石斧資料の新たな資料採取法の開発と紹介 …………田尻義了・足立達朗 熊本白川流域における弥生時代の標石についての調査報告 ―新南部遺跡群第7次調査及び幅・津留遺跡の出土例をもとに― ……………………………………………………………馬場正弘・宮本大 |
--------------------------------------------------------------------------
【2014年12月3日】
|
|
【目 次】 開催趣旨 プログラム 事例報告 1 横穴墓からみた東北地方における他地域との交流 …………岩橋 由季 2 装飾古墳と装飾横穴……………………………………………千田 一志 3 須恵器の流通と交易 …………………………………………大久保弥生 4 イワキとヒタチ …………………………………………………稲田 健一 誌上発表 1 「海洋民」について ……………………………………………西川 修一 2 関東地方沿岸部の横穴墓について …………………………柏木 善治 3 湖西窯における須恵器生産 …………………………………鈴木 敏則 4 古墳時代の陸路と海路 …………………………………………田中 裕 5 いわき市内の後期古墳出土の玉類について…………………大賀 克彦 6 陸奥と近江の交流 ……………………………………………菅原 祥夫 7 列島東北部における大型透孔付鉄鏃 ………………………廣谷 和也 8 横穴式石室について …………………………………………鶴見 諒平 9 いわき市出土東海系須恵器 ……………………竹田 裕子・高島 好一 あとがき |
--------------------------------------------------------------------------
【2014年12月3日】
|
|
【目 次】 韓國出土帯金式板甲の諸問題………………金榮珉(蔚山大學校博物館) 朝鮮半島出土の倭系武装にみる日韓交流 ………………………………………………鈴木一有(浜松市教育委員會) 三國時代武装體系の變化と地域性―韓半島東南部地域を中心として― …………………………………………………………李賢珠(鼎冠博物館) 日韓の刀・劍・鉾………………………………………豊島直博(奈良大學) 三國時代装飾大刀の特性と系譜……………禹炳喆(嶺南文化財研究院) 5~6世紀の胡[竹/録]について ―復元の再檢討と日本列島出土胡[竹/録]の系譜― …………………………坂 靖(奈良縣立橿原考古學研究所附屬博物館) 古代韓日札甲の交流―Ω字型要札と附属甲― ……………………………………………………金赫中(園立金海博物館) 日韓の佳甲……………………………………松崎友理(九州歴史資料館) 三國時代漁具の地域性と階屠性……………………金在弘(國民大學校) 日韓の漁具……………………………魚津知克(大手前大學史學研究所) 韓國の三國時代農器具………………………………金度憲(東洋大學校) 古墳・三國時代における外來系農工具の定着過程 …………………………………………………河野正訓(國立東京博物館) 韓日鐵製農工具の比較檢討……………………李東冠(國立晉州博物館) |
--------------------------------------------------------------------------
【2014年2月20日】
|
|
大阪の河内周辺は多くの古墳があり,調査が進められていた. そのうち古市古墳群に属する野中古墳は出土資料が質・量 ともに充実した遺跡である.資料のうち11領の鉄製甲冑は, 1古墳からの出土数としては日本でも傑出しており,襟付短甲 と呼ばれる王権を代表する象徴的な甲冑も含む.1964年の 発掘以来未公開であったが,このたび修復作業が完了し、 初展示・公開される. 【目 次】 第1部 図説「野中古墳と河内の古墳」 「倭の五王」の時代を探る (1)「倭の五王」の時代と考古学 (2)野中古墳の発掘調査 政の要は軍事なり-武器と武具 (1)甲冑 (2)鉄剣・鉄刀 (3)鉄鏃 技術革新と古墳祭祀 (1)鉄製農工具の出現と大開発の時代 (2)土器からみる東アジア交流 (3)墳丘上の儀礼と埴輪・石製品 古市古墳群の形成と内実 (1)3・4世紀の中河内地域 (2)誉田御廟山古墳・墓山古墳とその陪家 (3)東アジア情勢と百舌鳥・古市古墳群 第2部 論考「野中古墳をめぐる諸問題」 |
--------------------------------------------------------------------------
【2014年2月20日】
|
|
【内容紹介】 平成元年9月、旧八日市市と近江八幡市、竜王町にまたがる雪野山 (標高約309m)の山頂から古墳時代前期の前方後円墳が未盗掘の 状態で見つかり、218点もの埋蔵物が次々と発見された。 中でも3面の三角縁神獣鏡(国重要文化財)はヤマト政権との関係を うかがわせる大きな発見として全国の話題を集めた。その全貌をわかり やすく解説した竜王町教育委員会主催の講座を一冊にまとめた。 【目次】 一、近江の古墳時代史と雪野山古墳 大阪大学大学院/福永伸哉 二、雪野山古墳の鏡から見た古墳時代史 大阪市立大学/岸本 直文 三、雪野山古墳と石製品 東海大学/北條 芳隆 四、靫(矢入れ具)から見た雪野山古墳 熊本大学/杉井 健 五、副葬された武器からみた雪野山古墳 岡山大学/松木 武彦 六、農工漁具から見た雪野山古墳 奈良文化財研究所/清野 孝之 七、琵琶湖地域の中の雪野山古墳 滋賀県文化財保護協会/細川 修平 八、古墳時代前期甲冑の技術と系譜 鹿児島大学/橋本 達也 九、雪野山古墳で見つかった中世の城跡について 滋賀県立大学/中井 均 |
--------------------------------------------------------------------------
【2014年2月20日】
|
|
【内 容】 【目 次】 |
--------------------------------------------------------------------------
【2014年1月5日】
|
|
【目次】(執筆者/論文名) 藤島志考 中九州における弥生前期土器の様相 ―熊本平野を中心として― 武末純一 弥生時代の権―青谷上寺地遺跡例を中心に― 井上義也 福岡平野の弥生時代青銅器生産の開始期 ―須玖遺跡群を中心に― 今塩屋毅行 宮崎県下における弥生・古墳時代墳墓と土器 ―出土状況から探る壺形埴輪導入以前の葬送儀礼― 桃﨑祐輔 九州出土子持勾玉研究入門 宇野愼敏 大村市・黄金山古墳の再検討 津曲大祐 横口式土壙墓と地下式横穴墓 ―宮崎内陸部における地下式横穴墓の出現をめぐる諸問題― 下原幸裕 頸基部に突帯を有する須恵器壺・瓶 上田龍児 御笠川流域の古墳時代 ―集落・古墳の動態からみた画期とその背景― 齊藤大輔 皇南大塚南墳副槨出土鉄鉾の系譜 朝岡俊也 横穴系埋葬施設の排水溝―豊前地域― 阿南翔悟 九州出土鋸について 小田富士雄 総説・大宰府都城制の成立 山口 亨 塔が遅れて造られる理由 長 直信 豊後国における官衙関連遺跡の基礎的研究 ―旧大分郡・海部郡を中心に― 比嘉えりか 福岡市那珂遺跡群出土古瓦の検討 是田 敦 島根県の古代の骨蔵器 五十川雄也 大分市羽田遺跡出土の羽釜鋳型を考える ―羽釜鋳型から製品復元への問題点― 小嶋 篤 九州北部の木炭生産―製炭土坑の研究― 中村啓太郎 福岡城の路面遺構 平尾和久 韓国における紡錘車副葬墳墓の時期的変遷とその特徴 ―韓国慶尚道出土例を中心として― 山内亮平 呉越・銭弘俶八万四千塔再考 大津忠彦 松本清張文学作品における「考古学もの」への契機・始動と昇華 甲元眞之 内蒙古東南部出土の帯銘青銅器 小田富士雄・武末純一・桃﨑祐輔 福岡大学考古学研究室の歩み |
--------------------------------------------------------------------------
【2012年12月30日】
|
|
【目次】 第一部 古代人の息づかい 第二部 ものづくりの技と知恵 第三部 いくさと戦争 第四部 人の死とまつり・祈り 第五部 対外交流の証し 第六部 制度と都市計画 第七部 北九名物ここにあり! 第八部 その時、その思い・・ 付 編 郷土の誇り! 市内の遺跡ベストテン |
--------------------------------------------------------------------------
【2012年10月5日】
|
|
聖なる山、神社、寺院、イワクラ、古墳、そして文献…古代吉備研究の 第一人者・薬師寺慎一が、「吉備」の歴史を知る上で欠かせない 約700項目を超すキーワードを、独自の視点で集めて編纂。 ------------------------------------------------------- 本書で取り上げた事項は、考古学関係の遺跡や遺物・歴史の古い神社 ・同じく寺院・古記録・聖なる山・泉・イワクラなどの中で、およそ吉備の 古代史に関心をお持ちの方なら多分興味をしめされるであろうと思える ようなものです。(中略) 「事典」というものの性格を考慮して、できるだけ「中立」を心掛けました。 だが、読み返していると、筆者の悪い癖で、自分独自の観点から説明を 加えた事項もかなりあることに気づきました。そこで、この点について、 出版社の意向をお聞きしたところ、「いや、あなたの考えで書いて下さって 結構です。」との返事でした。故に、そうした点についてはそのままにして おきました。そうした部分は、筆者としては、問題提起のつもりで書いた ものもあるからです。(「まえがき」より)(ともに版元HPより) |
--------------------------------------------------------------------------
【2012年9月27日】
|
|
細分化する研究の全体像を捉えるべく現状を概観・総括し、各地域 ごとの様相をまとめ地域史的な視点から古墳時代を俯瞰する。 【目次】 各地の古墳 Ⅰ 南九州[池畑耕一] Ⅱ 北部九州[下原幸裕] Ⅲ 山陰[岩本崇・角田徳幸] Ⅳ 瀬戸内[古瀬清秀] Ⅴ 南海[清家章] Ⅵ 畿内[坂 靖] Ⅶ 東海[岩原剛] Ⅷ 中部高地[風間栄一] Ⅸ 北陸[小黒智久] Ⅹ 関東[内山敏行] ⅩⅠ 東北[菊地芳朗]) 古墳文化接触地域の墓制 Ⅰ 南島・沖縄[池田榮史] Ⅱ 北東北・北海道[藤沢敦]) 古墳各論 Ⅰ 竪穴系埋葬施設(含棺)[岡林孝作] Ⅱ 横穴系埋葬施設(含棺)[小林孝秀] Ⅲ 墳丘規格・築造法[青木敬] Ⅳ 埴輪[城倉正祥] Ⅴ 葬送儀礼[日高慎]) |
--------------------------------------------------------------------------
【2012年9月27日】
|
|
遺構・遺物の検証から列島における生産・流通の様相を分析しつつ、 祭祀や墓の有様など各論にも言及し、古墳時代の特性を抽出する。 【目次】 生産と流通 Ⅰ 農業[若狭徹] Ⅱ 製塩[岩本正二] Ⅲ 繊維製品[沢田むつ代] Ⅳ 土器[望月精司] Ⅴ 製鉄・鍛冶[野島永] Ⅵ 武器・武具[鈴木一有] Ⅶ 馬具[諫早直人] Ⅷ 鏡[辻田淳一郎] Ⅸ 石製品[徳田誠志] Ⅹ 装身具[高田貫太]) 社会構造 Ⅰ 集落[高久健二] Ⅱ 豪族居館[青柳泰介] Ⅲ 祭祀遺跡[大平茂] Ⅳ 渡来人[亀田修一]) 政治構造 Ⅰ 首長墳[土生田純之] Ⅱ 群集墳[右島和夫] Ⅲ 考古学からみた王権論[菱田哲郎] Ⅳ 古代史からみた王権論[吉村武彦] |
--------------------------------------------------------------------------
【2012年6月28日】
|
|
【柳沢遺跡における重大発見】(刊行元宣伝より抽出) *柳沢遺跡からは銅鐸5点、銅戈8点が出土。 *銅鐸と銅戈が同じ埋納坑から出土するのは、兵庫県桜ヶ丘遺跡に次いで 2例目。 *近畿型Ⅰ式銅戈と九州の中細形C類が同じ埋納坑から出土するのは 全国初。 *埋納坑の約40m北側で周溝を伴う18基の礫床木棺墓を検出。中央の1号 礫床木棺墓は長野県最大級の規模を有し、副葬品の量も県内の同時期 の墓では最多を誇る。 *「シカ絵土器」の発見。西日本における青銅器祭祀との深い関連性が推測 される。 *柳沢遺跡調査指導委員7名による見解の提示。(工楽善通・石川日出志・ 難波洋三・吉田 広・村上 隆・保柳康一・笹澤 浩) |
--------------------------------------------------------------------------
【2012年6月28日】【品切】
|
|
【目次】 1.宗像地域の古墳群と沖ノ島祭祀の変遷変〔花田 勝広〕 2.九州出土の中国鏡と対外交渉―同型鏡群を中心に―〔 辻田淳一郎〕 3.九州出上の馬具と朝鮮半島〔諫早 直人〕 4.古墳時代前期~中期の九州出土朝鮮半島系土器と対外交渉〔中久保辰夫〕 5.九州出土の鉄製農工具と鍛冶関係遺物から見た対外交渉〔李 東冠〕 6.朝鮮半島における「倭系古墳」築造の歴史的背景について〔高田 貫太〕 7.列島における横穴式石室の導入と朝鮮半島〔宮元 香織〕 8.韓半島からみた九州諸勢力との交流〔金 洛中〕 9.日韓集落祭祀から見た変化と画期〔平尾 和久〕 10.九州の集落から見た変化と画期〔吉田 東明〕 11.九州出土甲冑から見た対外交渉―胴丸式小札甲を中心に―〔松崎 友理〕 12.九州出土大刀からみた対外交渉〔斉藤 大輔〕 13,九州出土鉄鏃から見た対外交渉〔秦 憲二〕 14.九州出土木製品から見た対外交渉〔渡部 芳久〕 15.6・7世紀の北部九州出土朝鮮半島系土器と対外交渉〔寺井 誠〕 16.壱岐島・対馬島の諸勢力と対外交渉〔田中 聡一〕 17.筑前西部~中部の諸勢力と対外交渉〔上田 龍児・比嘉えりか〕 I8.筑前東部の諸勢力と対外交渉〔池ノ上 宏〕 19.筑前南部~筑後の諸勢力と対外交渉〔中島 圭〕 20.肥前の諸勢力と対外交渉〔渕ノ上隆介〕 21.肥後の諸勢力と対外交渉〔木村 龍生〕 22.豊前の諸勢力と対外交捗―京都郡・仲津郡を例として―〔山口 裕平〕 23.豊後の諸勢力と対外交渉〔長 直信〕 24.古墳時代の日向における対外交渉〔和田 理啓・甲斐 貴充〕 25.大隅・薩摩の諸勢力と対外交渉〔藤井 大祐〕 |
----------------------------------------------------------------------------
【2011年7月2日】
|
|